曲目はジャズ・スタンダードの揃い踏み──ウォルター・ビショップ・ジュニアの最高傑作
 Album : Walter Bishop Jr. Trio / Speak Low (1961)
Album : Walter Bishop Jr. Trio / Speak Low (1961)
Today’s Tune : On Green Dolphin Street
ジャズ・スタンダードといえば、この曲
みなさんは、スタンダード・ナンバーというと、どんな曲を思い浮かべるだろう──。古今東西、名曲は汲めども汲めども尽きることはない。たとえ天寿を全うしても、ひと一人が聴く曲、演奏する曲には、数に限りがある。だからこそ、音楽を愛好するものは、スタンダードというコトバに、とても蠱惑的な響きを感じるのだろう。とりわけ、ジャズ・ファンはスタンダード・ナンバーと聞くと、すぐに食指が動かされ、胸を高鳴らせて、それを身をもって味わおうとするのである。ちなみに、スタンダード・ナンバーというコトバは和製英語で、ネイティヴはそれを言い表すとき「a standard」あるいは「standards」と云う。
まあ、いまで云うところのカヴァーにあたるのだろうが、先人が発表した曲を、歌ったり演奏したりすることは、ジャズでは慣例となっている。ことに、コード進行に沿って即興演奏で自己の音楽を表現するモダン・ジャズにおいては、周知の曲をリニューアルすることでオリジナリティをアピールすることが有意義とされる。様々なアーティストが独自の想像力と表現力をもってして、たとえ古典的な曲にでも新たな息吹を注ごうとするのは、そういう理由から。いっぽうリスナーも同時に、ジャズ・スタンダードを聴くことによって、得もいわれぬ喜びが引き出されるのである。
ときに、ジャズ・スタンダードというと、単にジャズ・オリジナルの有名曲を意味するように聞こえるが、決してそうではない。ポップス、映画音楽、ミュージカル・ソング、シャンソン、フォーク・ミュージック、クラシックにいたるまで、ジャンルを問わず、とにかくジャズメンに幾度となく採り上げられる曲であれば、そう呼ぶことができる。そんなジャズ・スタンダードの歴史は、古くは19世紀まで遡る。スティーヴン・フォスターの歌曲、スコット・ジョプリンのラグタイムあたりが、そのはじまりだろう。
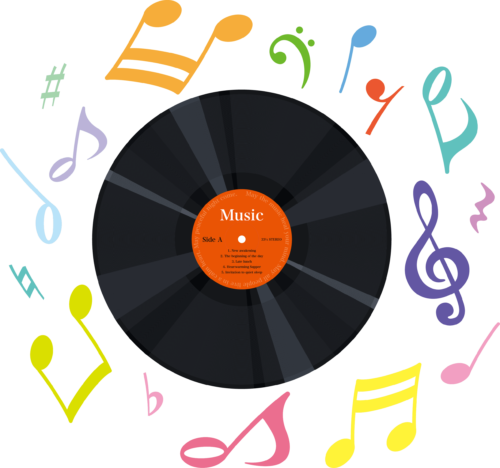
20世紀に入ると、ジェローム・カーン、コール・ポーター、アーヴィング・バーリン、ハロルド・アーレン、ジョージ・ガーシュウィンなどの、いわゆるティン・パン・アレー系、すなわち職業作曲家がわんさか登場したおかげで、名曲がたくさん生まれた。それ以降、とくに1930年代から1940年代までは、スタンダード・ナンバーの宝庫の時代。ぼくの好みの曲も、このころに集中する。ポップスやミュージカル・ソングのヒット曲も然ることながら、映画音楽から数多くの名曲が生まれたことも、忘れるわけにはいかないだろう。なお、1950年代からはプレイヤー自身の曲が、ぐっと増える。
そんな数え切れないほどのジャズ・スタンダードのなかでも、ぼくにとって、もっとも好きな曲のひとつが「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」だ。甘美なメロディとコード進行が印象深い。ポーランド出身でハリウッドで活躍した作曲家、ブロニスラウ・ケイパーが映画『大地は怒る』(1947年)のために書いた曲。スタンダード化のキッカケは、1958年にマイルス・デイヴィスが採り上げたこと。彼はテーマのアタマでペダルポイントを活かしているが、これはその後、常套的手法となっている。とはいっても、そのときのセッションが『1958 マイルス』として世に出るのは、1979年まで待たなければならなかった──。
この曲が入っていれば、未知のものでも手にする
面白いのは、この吹き込みの翌年、マイルスのグループの当時のピアニスト、ビル・エヴァンスと、その後任のウィントン・ケリーが、立て続けにこの曲を採り上げていること。あと、ふたりよりもちょっと遅れて、マイルスとは直接関係ないけれど、デューク・ピアソンも名演を残している。というわけで「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」は、早々にどちらかといえばピアノ・トリオの楽曲というイメージが強くなった。ちなみに、ケイパーの曲では「インヴィテーション」(1950年の日本未公開映画『A Life of Her Own 』の主題曲)も魅力的で、大好き。
この「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」は、もちろん曲自体も好きなのだが、個人的には、ジャズ・ピアニストのセンスやテクニックを推測する目やすというか指標になっている。だから、もしもこの曲を野暮ったくプレイしていたら、そのピアニストはぼくの理想のタイプではないということになるのだ。幸いなことに、これまでに拒否反応を起こすような演奏には、お目にかかったことがない。というわけで、この曲が収録されているアルバムに出会うと、たとえそれがまったく未知のものであっても、ぼくは好奇心をそそられて、ついつい手にしてしまうのだ。
ついでに付言すると、おなじように音楽の評価基準となるような曲がもうひとつある。それは、1970年代のスタンダード・ナンバー。ロバータ・フラックのヒット曲「愛のためいき」(原題「Feel Like Makin’ Love」)がそれ。1960年代からシンガーとして活躍していた、ユージン・マクダニエルズが彼女に提供した曲だ。この曲には、聴いても弾いても、こころを奪われてしまう。つまり、曲想的にも構造的にもたいへん魅惑的で、ホントよくできた曲だと思う。そういうわけで、ポップスやフュージョンのミュージシャンの才幹を推し量るのにも、とても役立つのだ。

閑話休題。ぼくがウォルター・ビショップ・ジュニアの『スピーク・ロウ』(1961年)を手にしたのは、まさに「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」が収録されていたから。もののハズミとは、こういうことを云うのだろう。本作が、多くのジャズ・ファン、ことにピアノ・トリオの愛好家が認める傑作であるとは、つゆほども知らなかった。ビショップについても、まったく聞き及んでいなかった。ぼくのいちばん好きなアルト奏者、ジャッキー・マクリーンの『スウィング・スウァング・スウィンギン』(1959年)や『カプチン・スウィング』(1961年)でピアノを弾いているのは彼だけれど、そのときはまだ、それらの作品に出会っていなかったのだ。
ニューヨーク出身のビショップは、ウディ・ハーマン楽団に楽曲提供していたジャマイカ出身の作曲家を父にもつ。高校を中退して、ハーレムのダンス・バンドでピアノを演奏していたという。確かにそのプレイには、生粋のジャズ・スピリッツが感じられるね。1950年代に入ると、マイルスやチャーリー・パーカーと共演するようになるが、こころざし半ばで、当時のジャズメンが陥りがちな悪癖により、半ば引退状態となる(もったいない!)。1958年に刑務所を出て、社会復帰した。その後、33歳にしてようやく初リーダー作を吹き込んだ。それがこの『スピーク・ロウ』というわけ。
あまりにも傑作過ぎて、大きなプレッシャーを抱えることに──
結論から云うと、このアルバムは噂に違わぬ名盤である。お目当ての「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」も期待以上の出来栄え。というか、全6曲のスタンダーズは、どれも痛快無比。ビショップのピアノには、やや指遣いにおぼつかなさが感じられるけれど、そんなのは大したことない。シンプリシティを貴ぶように、よくスウィングし、よく歌っているのだから。それにも増して、曲に対する解釈が卓越している。どの曲も、他の選択肢を選ぶ余地などないと思わせるような、素晴らしいアレンジが施されているのだ。
ところが、いきなり名作をものしたことが、その後のビショップにとって、裏目に出てしまう。本作で彼に興味をもったぼくは、後続のリーダー作を何枚か入手した。しかしながら、十分ではないが一応は満足できたのは、コティリオン・レーベルの『サマータイム』(1963年)くらい(アレンジはいいのだが、どの曲も小粒)。どうやら彼は、自らのバップ・スタイルにコンプレックスをもっていたようで、その後、ジャズ・ロックやフュージョンのスタイルまで採り入れていく。つまり、当時のジャズ・シーンに流されたわけ。しかしながら、そこにかつての輝きも閃きもなく、彼の存在は、文字通りワンヒットの奇跡となってしまった。
よく二作目の壁は厚いと云うが、ビショップの初リーダー作は、それだけ傑作だったわけ。ホント女神が微笑むとはこのこと。リズムを支えるプレイヤーにも恵まれた。コルトレーンのグループに加入する直前のジミー・ギャリソンによる逸出したベース・ワークと、ランディ・ウェストンとの共演が多いG.T.ホーガン(グランヴィル・セオドア・ホーガン)の手堅いドラミングが、これまたどの曲でも実にパワフルでエキサイティング。この魅力的なコンビネーションが、ビショップのピアノ・プレイを引き立たせているのだ。そういう意味でも本作は、ピアノ・トリオの名盤。

そして、曲目もジャズ・スタンダードの揃い踏み。これも、本作の人気の大きな要因。ヴィンセント・ユーマンスのミュージカル・ナンバー「時に楽しく」は、バド・パウエルも採り上げたことのある有名曲。ゆったりしたドドンパ・リズムが心地いい。ギャリソンのベースが、ソロも含めて印象的。つづく「ブルース・イン・ザ・クローゼット」も、パウエルの名演でおなじみ。ベーシストのオスカー・ペティフォードの代表曲。リフ調のスウィンギーなブルースを、トリオは躍動感いっぱいにプレイ。ピアノとドラムスのバース交換も痛快。そして「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」だが、ソロ・ピアノのルバート演奏、テーマのラテンのリズム、アルコ・ベースなどが特徴的。それにも増して、ビショップの楽しげに歌うアドリブが鮮やか。
アーサー・シュワルツのミュージカル曲「アローン・トゥゲザー」はジャズメンに好まれる曲だが、ここでは中間のキメが新鮮。こういう何気ないところに、ビショップのセンスのよさが感じられる。つづいてマイルスの「マイルストーンズ」では、ビショップが繰り出す精悍で鮮明なフレーズに、気分爽快にさせられる。後半のスリリングな三位一体の展開は、圧巻のひとこと。ラストのクルト・ヴァイル作のミュージカル曲「スピーク・ロウ」は、お約束のラテン・リズムが挿入された軽快なテンポの4ビート。ベース・ソロ、ピアノ&ドラムスの8バースという構成の妙も然ることながら、得も言われぬレイドバック感がいい。これは、まさしく名演。
ということで、本作はスタンダード・ナンバーが耳に馴染みやすく、味わい深く調理された大傑作である。あまりにも傑作過ぎて、皮肉なことに、ビショップは大きなプレッシャーを抱えることになったのだが──。もがき苦しみながらいろいろ演ってみたが、もう二度と持ち直すことはないのだろうか?──そんなふうに思っていたら、思いがけないときに、彼はインタープレイ・レーベルから『ジャスト・イン・タイム』(1988年)という佳作を発表。まあ『スピーク・ロウ』ほどの輝きはないけれど、愛すべきジャズ・スピリッツが、しかと感じられた。その後、日本のヴィーナス・レコードが『スピーク・ロウ・アゲイン』(1993年)というアルバムを制作したけれど、みんな彼の復活を望んでいたのだね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。







コメント