ブルース、ゴスペル、ブギウギ、ストライド奏法──そのピアニズムにノックアウトされる

Album : Ray Bryant / Hot Turkey (1975)
Today’s Tune : Satin Doll
飽くまで聴き手の立場で楽しむピアニスト
弾きたくても、弾けない。マネしたくても、マネできない。趣味ないし余技程度にピアノを弾くぼくにとって、そんな高嶺の花のごときピアニストは、星の数ほど存在するだろう。アタリマエだ。でも、せめて砂粒の数ほどにとどめたいな──。なんて、おバカなことを云っても仕方がないのだけれど、そんなふうに実感させらることが、過去に二度ほどあった。度肝を抜かれることなんて滅多にないから、すぐに思い出せる。それは、リチャード・ティーとレイ・ブライアントのピアノ・プレイを、はじめて聴いたときのこと。
ティーの場合、厳密にははじめて聴いたときではなくて、彼の『ストローキン』(1979年)というレコードに収録されている同名曲のコピー譜を入手して、実際に弾いてみようとしたときのこと──。中学生のぼくに、衝撃が走った。激しく動揺した。こころのなかで「指が届かない!」と叫ぶ。そして、唇を噛む。アップテンポに乗って疾走するファンキーなピアノ。その強靭なリズム感とドライブ感!オクターブ奏法とパラディドル奏法のミックス!仕舞いには「手が忙しすぎるよ──」と、ため息をつきたくなるような心持ちになった。
まあ、どうこう云っても結局、弾けないのは、ぼくの演奏技術が未熟だから。現にあとでぼくの妹が、楽譜を見ながらそれなりに弾いていた。思わずこころのなかで、舌打ち──。すっかり、くじけ折れた。時をおなじくして、ブライアントの演奏に触れた。譜面は見たことがない。今度はゴスペルとブギウギのミックス!右手でメロディ&コード、左手でバス声部を弾いている。特に左手が屈強。コードチェンジに即して繰り返されるシンコペーション。そのベースラインの強烈なビート感覚に、もう立ち直れないくらい叩きのめされた。その影響力は定かではないけれど、彼は中学生のころコントラバスも弾いていたらしい。
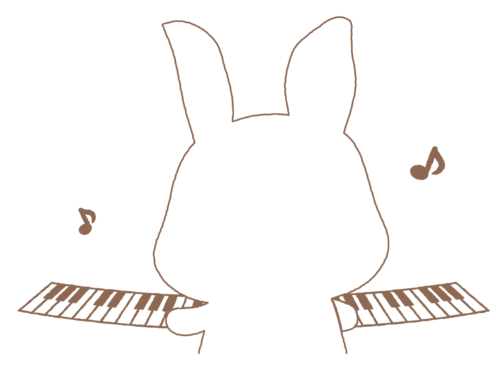
そんなことで、ぼくは、日ならずして諦めの境地に達した。ところが、自分には弾けないという事実が明らかになると、逆に邪念が払われて、飽くまで聴き手の立場でそれを楽しむことができるようになる。しかも、敬意を表することはあっても、思いのほか憧憬の念を抱くことがなかったりする。自分にないものを持っているひとに出会うと、そんな気持ちになることがあるもの。だからその後、二度とふたりの演奏をマネしようなんて思うことはなかったけれど、いまもって両者とも、ぼくの大好きなピアニストでありつづけているのだ。
今回は、そんな大好きなブライアントの、これまた大好きな一枚『ホット・ターキー』をご紹介──。ちょっと待って!『レイ・ブライアント・トリオ』(1957年)じゃないの?「ゴールデン・イアリング」が入っている──。ああ、あれも超のうえに超がつく名盤だ。珠玉の名演がズラリだからね。ぼくも好きだよ。でも、あちらはリリカルでロマンティックなアルバム。敢えてひとりきりになりたいような心理状態のときには、とても重宝する哀愁漂う一枚。ところが、ぼくをノックアウトしたのは、彼のそういう側面ではなくて、ブルース、ゴスペル、ブギウギがブレンドされた、コクのあるプレイのほう。
フランス盤、日本盤、レコード、CD──楽曲構成は様々
ということで、なかば強引に話を先に進める。この『ホット・ターキー』は、1975年10月15日、ニューヨークのナショナル・スタジオで録音されたのだが、フランスのブラック・アンド・ブルーというレーベルからリリースされた。いまだオリジナル盤を目にしたことはない。ぼくがリアルタイムで購入したレコードは、1979年に日本フォノグラムがスタートさせた「“K”コレクション」という名盤発掘シリーズの一枚として発売されたもの。この“K”とは、スイングジャーナル誌(2010年に休刊)の編集長を17年にわたって務めた児山紀芳のこと。
実はこのレコード、たまたま児山さんと一緒に仕事をしたことがあった、ぼくの父の勧めで手にした(買ってもらった)。クラシックの愛好家だった父は、ジャズといえばエリントンとブレイキーの繰り返しで、まったく代わりばえのしないひとだった。当然のごとく、ブライアントのことなど知らなかったはず。間違いなく、児山さんのお墨付きというだけで購入を促したのだろう。まあ結果的に、その中身はぼくを夢中にさせたのだから、タナボタ、モッケの幸い。とにかく前述の『ストローキン』同様、レコードが擦り切れるほど、何度も何度も聴いたもの。
アルバムの構成は変則的で、A面がトリオ、B面がソロ・ピアノとなっている。1993年には徳間ジャパンコミュニケーションズのノーマ・レーベルから、全編トリオの曲でまとめられたレコードも発売された。やっぱり日本人はピアノ・トリオが大好きなのだ。ぼくも好きだけれど、油断していたら完全限定プレス盤だったので、買い損なった。CDではトリオもソロも全曲聴くことができる。ぼくもCDを入手して、ようやくトリオの演奏の全貌を知ることができた。ちなみに、日本フォノグラム盤のみ、A面の1曲めと3曲めが入れ替わっている。ぼくはすっかり、こちらに慣れてしまった。

それでも便宜上、2018年にウルトラ・ヴァイヴのレーベル、ソリッド・レコードから発売されたCDに沿って話をすすめる。曲順は、ブラック・アンド・ブルーのオリジナル盤のA面、B面、それにノーマ盤のB面が後続という体裁。わかりやすいね。ただ、トリオ①→ソロ→トリオ②というかたちになってしまう。気持ちがわるいというひとは、プレイヤーにプログラム機能があれば、お好みで曲順を変更してみてね。ちなみに、1997年にリイシューされたブラック・アンド・ブルーのCD(フランス盤)では、ソロ→トリオ①→トリオ②(一部曲順に変更あり)となっている。いったい、どれがいいのかな?
前向きな気持ちに切り替えよう。トリオのメンバーは──。ベースは歌うコンバスマン、メイジャー・ホリー。1940年代後半から西海岸で活躍しているけれど、個人的には、1960年代から1970年代にかけて吹き込まれた、クインシー・ジョーンズの作品でお世話になった。あとケニー・バレルの名盤『ミッドナイト・ブルー』(1963年)のベースも彼。なんといっても、スラム・スチュアートばりのハミング奏法がキャッチー!いっぽう、バークリー音楽大学で教鞭を執るような、インテリな一面も窺える。
ブライアントならではのソウルフルなピアニズムが満載
いまひとり、ドラムスはパナマ・フランシス。御大は1930年代からプロとして活躍してきた。とてもスウィンギーなプレイヤーでリズム・アンド・ブルースもお得意。ラテンやブギウギで盛り沢山のブライアントのポップなアルバム『グルーヴ・ハウス』(1963年)で、すでに共演済み。実は彼、本名はデヴィッド・アルバート・フランシスという。ところが、トランペッターのロイ・エルドリッジが新人ドラマーだった彼の名前を失念して、フランシスがたまたまパナマ帽をかぶっていたところから“パナマ”と命名。ホント、失礼すぎるよ。
さてさて、役者は揃った──。オープナーの「ホット・ターキー」からトリオは飛ばしまくる。イントロはない。いきなりメロディから──。シンコペーテッドなアップ・テンポ。ブライアントのピアノが、ファンキー&グルーヴィーなフレーズをガンガン繰り出す。終始彼の強靭なアドリブが主役だけれど、フランシスの五目炒飯なドラミングも曲を盛り上げる。1964年に吹き込まれた『コールド・ターキー』のタイトル・ナンバーは、異名同曲。もともと意味深長なタイトルだったけれど、この度ホットに改められた。いいんじゃない。今回コンガは入っていないけれど、演奏はこちらのほうが断然熱いもの。
ベイシー楽団の人気曲「リル・ダーリン」では、8分の6拍子のゆったりしたテンポに乗って、ブライアントのピアノが饒舌にブルースを歌う。フランシスはそれを、リムショット→ヘッドショットと徐々に鼓吹していく。つづくエリントンの「サテン・ドール」は本作のベスト・トラック。ダイナミックに駆け降りたり、ブギウギしたり、ブライアントはどこまでも飛翔する。フランシスのマシンガンキッドなスネアもゴキゲン。そして、お待たせ!ホリーのハミングベース!彼はなんと、あのボブ・ジェームスの『サイン・オブ・ザ・タイムス』(1981年)でも、このワザを披露。キャッチー!

ここで一旦、ソロ・ピアノ。途中からテンポが上がるブルージーなハンディの「セントルイス・ブルース」ブギウギからスウィング・スタイルに移行するストレイホーンの「A列車で行こう」バラード演奏が香気と品格に満ちたエリントンの「ソフィスティケイテッド・レディ」そしてブライアント自身の曲でちょっとモンクを彷彿させるブルース・ナンバー「B&Hブルース」と、いずれの曲も、ブライアントの得意とするゴスペル・タッチのソウルフルなプレイが際立っている。その魅力的なテクニックといったら、1600人以上の聴衆のハートを鷲づかみにした、あのライヴ盤『アローン・アット・モントルー』(1972年)で、すでに証明済み。
そして、あとから発掘されたトリオ演奏へ──。ドラムスのソロがジャンプしまくる、まさにブロードウェイ讃歌として有名な「ブロードウェイ」本作中唯一のスローでリリカルなジェンキンスの「ディス・イズ・オール・アイ・アスク」リラックスした演奏が心地よくて途中ウォーキングベースのソロも出来するブライアントのオリジナル「ブルース・イン・C」と、どれをとってもブライアントらしい演奏だ。すなわち、ブルース、ゴスペル、ブギウギ、さらにストライド奏法といった、ソウルフルなピアニズム。いくら練習しても、ぼくにはこんなに雄弁に弾くことはできない。弾けないから、聴き手として楽しむばかり。それでよし。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント