独特のリズム感覚を活かしたアレンジと進取の気性に富んだピアノ・プレイが特徴のホレス・シルヴァー──その最初期のレコーディング『ホレス・シルヴァー・トリオ&アート・ブレイキー、サブー』
 Album : Horace Silver / Horace Silver Trio And Art Blakey-Sabu (1956)
Album : Horace Silver / Horace Silver Trio And Art Blakey-Sabu (1956)
Today’s Tune : Ecaroh
ブラジルのピアニスト、セルジオ・メンデスとの共通項を備える音楽家
ぼくは、ブラジル生まれのピアニスト、セルジオ・メンデスが大好きで、年端もいかない子どものころから現在に至るまで彼の作品をずっと愛聴しつづけている。セルメンといえば、セルジオ・メンデス&ブラジル’66のバンマスというイメージが強い。そしてバンド名に“ブラジル”が冠されているから、実際に音を聴いたことがないひとは彼のことをブラジル音楽の巨匠と思い込んでいるかもしれない。確かにセルメンには、アントニオ・カルロス・ジョビンやジョアン・ジルベルトといったブラジル音楽を代表する音楽家たちの影響を受けて、ボサノヴァを演っていた時期もある。でもその後、彼はすぐにブラジルから飛び出してしまうのだ。もっと洗練されたグローバルな音楽を演りたかったのだろう。
ときの移ろいとともに、バンド名はブラジル’66からブラジル’77、ブラジル’88と変わっていく。バンド名の変遷は、サウンドの移り変わりを示唆するものでもある。時代の流行や趨勢に敏感なセルメンはバンドに、ロック、ポップス、ソウル、ラテンと幅広く音楽のエッセンスを採り入れていく。今世紀に入ると、ブラック・アイド・ピーズのウィル・アイ・アムをプロデューサーに起用し、ヒップホップまで導入したほどだ。それでもセルメンの作品には、奇を衒うような印象を与えるところはまったくない。むしろ彼はエンターテインメント志向でありながら、いつも音楽のクオリティを高めようとしているのである。
そんなセルメンは1960年代のはじめにはボサノヴァを演っていたけれど、それ以前はジャズ・ピアニストだった。バンマスのイメージが強い彼だが、実はピアノ演奏も非常に上手いのである。と、セルメンのハナシはここまで──。実は彼の音楽を楽しむときとおなじようなスタンスで、ぼくはこのひとのレコードをターンテーブルにのせている。だから思わず、セルメンを引き合いに出してしまったというわけだ。そのひととはだれあろう、ジャズの黄金期を支えた音楽家のひとり、ホレス・シルヴァー(1928年9月2日 – 2014年6月18日)だ。そのサウンドには従前のバップ・スタイルをより上の段階にもっていったような感じがあるから、彼はハード・バップの立役者のひとりと云えるだろう。
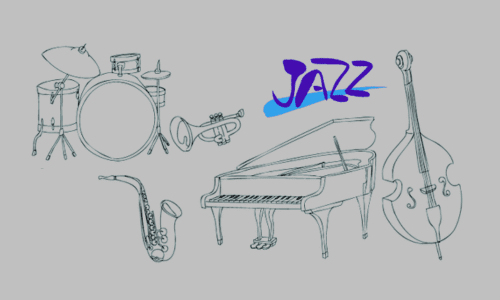
ハード・バップとひと口に云っても、シルヴァー・サウンドにはゴスペル、アフロ・キューバン、ラテン・ミュージックなど、広範囲にわたる音楽ジャンルからの影響が感じられる。そういう音楽性はスタイルの違いこそあれ、セルメンのそれと共通する。次にセルメンと同様に、シルヴァーのピアノ演奏もまた極めて優れている。ことにバッキングが上手い。ソロを執っているミュージシャンに刺激を与えるとともに、トータル・サウンドを盛り上げるようなパターンを直感的に次々に繰り出していく。しかもリズムのセンスが抜群によくて、即興でクリエイティヴなリフを紡ぎ出すこともあれば、ときにはコードでアグレッシヴにコンピングしたりもする。セルメンは伴奏においても決して手を抜かないが、シルヴァーもまた然りである。
さらにシルヴァーは、セルメンと同様にバンマスのイメージが強い。さきほど来ぼくはバンマスを連発しているが、念のために云っておくと、バンマスとはバンドマスターのこと。文字どおりバンドにおいて主導的立場を執るひとを意味するのだが、それに加えて演奏を統括するひとというニュアンスも含まれている。セルメンにしてもシルヴァーにしても、どちらかというと後者に当たる。ふたりには、音楽の方向性を明確にし、それに沿って楽曲をハイスペックなものに仕上げるという点で、卓越した才能のもち主。彼らが制作したアルバムは、リスナーが充分に楽しめる作品として、いつでも高い水準に達している。そういった意味では、シルヴァーもまた稀代のエンターテイナーと云えるかもしれない。
ぼくがシルヴァーのことを知ったのは、父の所持していたコロムビア盤の『ザ・ジャズ・メッセンジャーズ』(1956年)において。クラシック音楽の愛好家だった父だったが、なぜかあの“ナイアガラ・ロール”という豪快なドラミングでおなじみのアート・ブレイキーのことが好きだったようだ。そんなわけでぼくは、アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズのレコードを、ものごころがつくまえから聴くともなしに聴いていたのだろう。しかしぼくがジャズに興味をもちはじめたのは、小学校高学年のころ。ずっと年上の従兄からバド・パウエルやビル・エヴァンスの作品を聴かされたのを機に、積極的にジャズを聴くようになった。そんなさなか、手っ取り早く父のレコード棚からもち出したのが、このレコードだった。
このアルバムの演奏は、1956年の4月6日と5月4日に吹き込まれたものだけれど、当時のザ・ジャズ・メッセンジャーズのバンマスはシルヴァーだった。ブルーノート盤にも『ホレス・シルヴァー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ』(1956年)というのがあるしね。もともと1954年にこのバンドを結成したのはシルヴァーとブレイキーだったわけだが、この『ザ・ジャズ・メッセンジャーズ』がリリースされた1956年にシルヴァーはバンドを離脱する。というかブレイキーと袂を分かつことになった──と云ったほうが正しいのかもしれない。その後、シルヴァーは自己のクインテットを結成。まとめ役を失ったブレイキーのほうは、1958年に作編曲が得意なテナー奏者、べニー・ゴルソンをバンドに迎える。そしてそのときはすでに、ちゃっかりバンド名をアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズとしていた。
ザ・ジャズ・メッセンジャーズの中心人物、袂を分かつ──その後は?
それはともかく『ザ・ジャズ・メッセンジャーズ』が、実質シルヴァーのアルバムであることは、実際に音を聴けば火を見るより明らかだ。前述のように、各々の楽曲はハード・バップのスタイルがとられていながらも、ジャズ以外の音楽のエッセンスが盛り込まれている。それでも全体的には整然として聴こえるようなところが、いかにもシルヴァー・サウンド。そのオーガナイザーぶりは、ハード・バップの発展に寄与したアーティストのなかでも抜きん出ている。さらに、アフロ・キューバンのリズムがスタイリッシュな「ニカの夢」や、複雑で独特の響きをもつコード進行のラテン・ナンバー「エカロー」といった、シルヴァーのオリジナル曲には、彼の作編曲家としての類い稀なるひらめきが感じられるのである。
メンバーもいい。ドナルド・バード(tp)、ハンク・モブレー(ts)、ダグ・ワトキンス(b)と、みなぼくの好みのタイプのミュージシャンばかり。いや、このアルバムを起点に彼らを追いかけるようになったと云ったほうがいいのかも──。ちなみに父の所持品は国内盤だったのだが『ジャズ・メッセンジャーズの黄金時代』というとんでもない邦題が付されていた。国内仕様のジャケットの表と裏のふたつの面には、ブレイキーひとりだけの写真があしらわれていた。ちょっと適当過ぎるようにも思われるが、当時の日本の音楽ファンの間では、ブレイキーは絶大な人気を誇っていたのだろう。なにせクラシックの愛好家である父が聴いていたくらいだから──。そんな変なジャケットとは関係なく、ぼくは本盤をオトナになってから自分で購入し直した。それくらい好きなのである。
考えてみれば、バードは整ったアドリブラインが爽快だし、かたやモブレーは落ち着いたマイルドなソロが魅力的。シルヴァーのようにバンド・サウンドの全体像を考えているようなミュージシャンとは、とても相性がいいと思われる。ぼくもそういうアドヴァンテージに惹かれて、彼らのブルーノート盤を聴き漁るようになった。ブレイキーのことは抜群のテクニックをもったスーパー・ドラマーだと思うけれど、センシティヴなプレイもできるのに推進力が強いせいか、ときおり彼の演奏はめまいがするほど煌びやかで派手に映ることがある。卓越したスキルをもったひとだから、チャンス到来とあらばおもいきり叩きたくなるのも致しかたない。その点、全体にまとまりがなくなることもある。

ブレイキー自身それをわかっていたからだろう、彼のバンドではメンバーにミュージカル・ディレクターの役目を果たすようなプレイヤーが加えられることが慣例となっていた。実際、ときとして音楽監督が不在のとき、ブレイキーはまえに出過ぎることがあった。もし前述のベニー・ゴルソンがいなかったら、歴史的名盤『モーニン』(1958年)は誕生していなかっただろう。ゴルソンのようなオーガナイザーが存在したからこそ、アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズは、キャッチーなメロディとアレンジでファンのこころを鷲づかみにすることができたのである。彼もシルヴァーと同様に間もなくバンドから離脱するけれど、ご存知のようにブレイキーは、テナー奏者のウェイン・ショーターをその後釜に据える。
ショーターの非凡な才能は、バンド・サウンドに均衡を保たせたばかりでなく、従来それが有していたファンキーなムードをモーダルなフィーリングにリフレッシュさせた。それはさておき、かたやシルヴァーは自己のクインテットで、独特のリズム感覚を活かしたアレンジと進取の気性に富んだプレイをもってして、ファビュラス・シルヴァー・サウンドを息つく間もなく繰り広げていく。彼はザ・ジャズ・メッセンジャーズの屋号をブレイキーに譲渡してすぐに、エピック・レコードから『シルヴァーズ・ブルー』(1956年)という佳作をリリースしたが、その翌年の1957年から1980年までの23年間、名門ブルーノート・レコードの看板アーティストとしてリーダー作を発表しつづけた。
ちなみに、ブルーノート盤『ハンク・モブレー & ヒズ・オール・スターズ』(1957年)において、それぞれの活動をスタートさせていたシルヴァーとブレイキーは、奇跡的に再会セッションを果たしている。このアルバムの冒頭には、モブレーが書いた「リユニオン」という曲が収録されている。この曲のタイトルに、多くのファンが深い含蓄を感じたのではないだろうか。いかにしてふたりの共演が実現したのか、ほんとうのところは知る由もない。かわいい後輩のために、気のいい先輩たちがひと肌脱いだというところか。あるいは、プロデューサーのアルフレッド・ライオンによる尽力の賜物かもしれない。いずれにしても、和やかなムードが溢れるなか、モブレーはいつになく寛いだテナーを聴かせている。
さて余談はこれくらいにして、話題を本筋に戻すとしよう。シルヴァーの作品でもっとも人気の高い一枚といえば、すぐに『ソング・フォー・マイ・ファーザー』(1965年)が挙げられる。冒頭のタイトル・ナンバーからいきなりキャッチーなものだから、だれでも即座に引き込まれてしまうのだろう。シルヴァーはコネチカット州ノーウォーク市の出身だけれど、彼の父親はかつてポルトガルの植民地だったカーボヴェルデ諸島のひとつ、マイオ島の生まれ。母親のほうはアイルランド人とアフリカ系のハーフだ。そして、このアルバムのジャケットに写る葉巻をくわえカンカン帽をかぶったオジサンこそ、シルヴァーの父であるジョンそのひと。この作品のオープナーは、シルヴァーがジョンに捧げた曲なのである。
最初期のレコーディングながら特徴的な音楽性が顕著に窺える名盤
このシルヴァーにとってはシグネチュア・チューンとも云うべき、エキゾティックなリズム・パターンとセンチメンタルなメロディ・ラインをもった曲の誕生は、実はジョンの助言がキッカケとなっている。彼はかねてから息子に、ジャズのなかにポルトガルの民謡を採り入れることを勧めていた。はじめは聞き流していたシルヴァーだが、それまでのクインテットを解散して間もない1964年の2月、単身ブラジルに渡った際、ジョンの助言が正しかったことに気づく。彼は現地でショーロ、ノルデスチ、サンバ、それにボサノヴァといった音楽に直接触れ、それらに触発されて新たな創作への意欲を燃やす。名曲「ソング・フォー・マイ・ファーザー」は、ジョンへの感謝のしるし。そしてブラジルへの旅先でシルヴァーが宿泊したのは、そうセルメンことセルジオ・メンデスの自宅だったのである。
実はセルメンとシルヴァーは、数年前に顔を合わせていた。アルト奏者のキャノンボール・アダレイのアルバム『キャノンボールズ・ボサノヴァ』(1963年)のレコーディングに、当時セルメンが率いていたザ・ボサ・リオ・セクステットが参加したときだから1962年のこと。吹き込みはニューヨークで行われたがその際、当時マンハッタンはブロードウェイの52丁目にあった往年の名ジャズ・クラブ、バードランドを訪ねたセルメンは、かねてから憧れていたシルヴァーにはじめて対面した。それが発端となり、今度はシルヴァーのほうがセルメンに会いにいったというわけだ。シルヴァーは、セルメンの家で行われたパーティーでひらめきを得て「ソング・フォー・マイ・ファーザー」を書いた──という伝説もある。
しかし、これはどうやら飽くまで口承によるウワサばなしで、真実ではないらしい。セルメン自身が「ソング・フォー・マイ・ファーザー」はすでに作曲されていたと思うと語っているので──。それと同時に彼はこの曲を長年のフェイヴァリット・ソングとも述べている。さらにセルメンは、シルヴァーのことを自分のメンターであり音楽的なインスピレーションを与えてくれるひとと、敬意を表している。確かにシルヴァーの書く曲は、どれも魅力的だ。ただその曲が有する独特のムードを最大限に高めることができるのは、シルヴァー以外にはいないように思われる。というのも「ソング・フォー・マイ・ファーザー」をはじめとする数々の名曲には、作曲者本人以外の演奏に名演が見当たらないからだ。
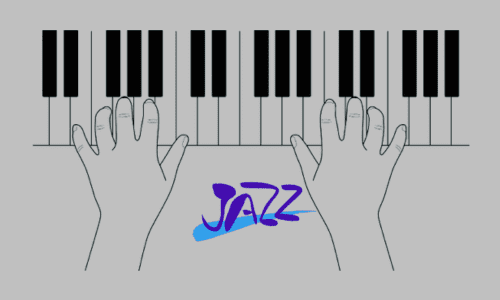
ということで『ソング・フォー・マイ・ファーザー』のことばかり語ってしまったが、それ以外のシルヴァーのアルバムもみなクオリティが高い。ことに1950年代の中ごろから1960年代の後半にかけてクインテットで吹き込まれた作品は、どれを手にしても損することはないだろう。そんな理由から、ここで最後に敢えてトリオ作品をおすすめしておく。この最初期のレコーディングをまとめた『ホレス・シルヴァー・トリオ&アート・ブレイキー、サブー』(1956年)は、すでに特徴的なシルヴァーの音楽性が顕著に窺える名盤だ。本作は、もともとブルーノート5000シリーズとしてリリースされた、2枚の10インチ盤がカップリングされたもので、全16曲のうち12曲が収録されている(CDによってはコンプリート盤もある)。
吹き込みは、1952年10月9日、20日、1953年11月23日で、ベーシストがそれぞれジーン・ラミー、カーリー・ラッセル、パーシー・ヒースと入れ替わる。ドラムスはすべてアート・ブレイキーが担当、1曲のみプエルトリカンのサブー・マルティネスがコンガで参加している。記念すべきシルヴァーの初リーダー・セッションが含まれているが、これは本来ルー・ドナルドソン・クァルテットによる録音となる予定だったもの。主役欠席のため、急遽変更された。シルヴァー=ブレイキーによる、はじめての吹き込みでもある。冒頭のシルヴァーの自作「サファリ」には、パウエル派の殻を破るようなファンキーさ、そしてお得意の引用フレーズと、シルヴァー独特のピアニズムが感じられる。
前述の「エカロー」の原曲は、エキゾティックなテーマ部と明るく澄んだカラーの後半とのコントラストが素晴らしい。そんな楽想の柔らかで軽やかな感じが、ぼくは大好きだ。なお曲名は“HORACE”を逆に綴ったもの。デューク・エリントンの「プレリュード・トゥ・ア・キス 」では、そつないバラード演奏にもの足りなさを感じる向きもあるだろうが、そのさり気なさには好感がもてる。ブレイキーとサブーのデュオ「メッセージ・フロム・ケニア」では、ふたりの精力的なプレイに圧倒されるばかり。ブレイキーはリズムの奥義を逡巡することなく披露している。シルヴァーの自作「ホロスコープ」では、軽快なテンポと小気味いいピアノのアドリブが寛いだ感じを与える。やはりシルヴァーのオリジナル「ヤー」では、アップテンポでのピアノ・プレイにおいて、シルヴァーは真骨頂を発揮している。
さらに2曲のスタンダーズ、バートン・レーンの「ハウ・アバウト・ユー」では颯爽としたドライヴ感、ヴィクター・シャーツィンガーの「アイ・リメンバー・ユー」では意匠の凝らされたアレンジと、シルヴァーならではの音楽が展開される。シルヴァーの人気曲「オパス・デ・ファンク」では、ピアノ・プレイにおけるファンキーな一面がしっかり披露されている。ドラムスのみの「ナッシング・バット・ザ・ソウル 」では、ブレイキーの若き日の名人芸を堪能するばかり。つづくラスト2曲では、独特のリズム感覚と流麗なシングル・トーンが活かされたアドリブにおいて、スタイリッシュなシルヴァーが立ち現れる。オリジナル曲「シルヴァーウェア」ルーブ・ブルームの「デイ・イン・デイ・アウト」と、テンポは上がりサウンド・カラーも明るくなっていき、アルバムは爽やかな余韻を残す。トリオ編成でもシルヴァーは、やはりスタイリスト。いつでもジャズのカッコよさ、楽しさを教えてくれるのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント