いまだに手に取ると、なにかが始まるような気がする、マッコイ・タイナーのファースト・リーダー作

Album : McCoy Tyner Trio / Inception (1962)
Today’s Tune : There Is No Greater Love
新たな鼓動を強く感じさせるピアノ・スタイル
英語の“inception”とは「はじまり」という意味だ。たしかに、なにかが始まった。聴く者を眩惑するような即興演奏。そこにはブルースのなかのモーダルな解釈、ダイナミックなスケールアウト、そして美麗なコードのヴォイシング──どこか奇妙だけれど、とてもクールな響きが感じられた。スウィングしなけりゃ意味がないけれど、スウィングするだけがジャズではない。そんな目からウロコの、意識改革がなされるような、新たな鼓動を強く感じさせるピアノ・スタイル──。いま思い返して見ると、マッコイ・タイナーの登場は、新しいスウィングのはじまりだったように、ぼくには感じられる。
高校生のころだったかな、音を聴いてその心地よさを表現することを、表面的に模倣するばかりだったぼくに、ちゃんと音楽理論を掘り下げなければ──と思わせたのが、マッコイのピアノ・プレイだった。ジャズを演るには、耳で覚えて真似することも大切だと思うけれど、最終的には知識の蓄積と理論の裏付けも必要になるのだ。たとえば、ペンタトニック・スケールをしっかり使えるようになったうえで、それを故意に半音ずらして演奏したり、本来避けるべきである音と承知したうえで、敢えてアヴォイドノートを弾くことによって、独特な響きを生み出したり──。
こういうテクニックは、楽理を知らなければできない。音楽の表現方法は、もちろん自由だ。しかしながら、単なる非論理的な演奏は、メチャクチャになってしまう可能性が高い。そりゃメチャクチャにも、もっけの幸いが訪れるようなことがあるのかもしれないけれど、そこから創造的な音楽が生み出されるようなことは、まったくないだろう。音楽の構造を知り尽くし、逆にそれを崩していくという手法だからこそ、希少な心地よさを生み出すことができる。不協和音程を理解すれば、それが必ずしも不協和感を与えるとは限らない──ということにも気がつくわけだ。
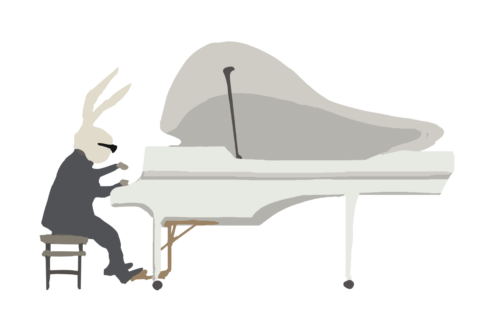
まあとにかく、それまでソニー・クラークやウィントン・ケリーを好んで聴いていたぼくにとって、マッコイの演奏は衝撃的だった。と同時に、にわかにジャズが高尚な音楽のように思えてきて、一時だが、ぼくは「好きなピアニストはマッコイ・タイナー」と、触れまわっていた時期がある。それで、とんでもない赤っ恥をかいたこともある。まったくバカだね。若気の至りとはいえ、いまでもそのことを思い出すと顔から火が出るような思いがする。ただ、このころのぼくは、たしかに彼のことを偶像崇拝していたけれど、ジャズ理論に真剣に取り組んでもいたな。
そんなこともあって、マッコイは、ぼくにとってイワクつきのピアニストになってしまった。実はその後、彼の演奏に対するぼくの関心は、だんだん薄れていった。たぶん、ピアノのテクニックばかりを観ていて、それを必死で追い求めることのみに意識を傾けていたせいか、ぼくは彼の作品に、だんだん魅力を感じなくなっていったのだ。たぶん、純粋に音楽を楽しんでいなかったのだろう。ブルーノートのBNLAシリーズあたりから「ん?」となり、マイルストーン時代ともなると、たしかにピアノ・プレイは相変わらずスゴイのだけれど、音楽作品としては一向に満足のいくものがなかった。
マッコイを聴くなら、インパルス!にかぎる
たとえば、ストリングスが入った『フライ・ウィズ・ザ・ウィンド』(1976年)は、マッコイの1970年代を代表する大作と云われるけれど、ぼくにはどうもシックリこない。彼はこのアルバムで、作編曲にもチカラを入れている。それ自体は決して悪くないのだが、その超絶技巧のピアノ演奏と噛み合っていないように感じられる。どうも、落ち着いて聴いていられない。アフロ・キューバンを採り入れた『ザ・レジェンド・オブ・ジ・アワー』(1981年)も然り。まだやるのか、マッコイ?果たしてそこにあなたのピアノが必要なのか?──と、首を傾げざるを得ない。まあ、トリオやソロのアルバムもリリースされていたけれど、ぼくは徐々に彼から離れていった。
ということで、ここでハッキリ個人的見解を示しておく──。マッコイ・タイナーには、モダン・ジャズがよく似合う。彼の斬新なスタイルは、ジャズの本流に乗っているときにこそ、光り輝くのだ。そういう意味では、スタイルこそまったく違うけれど、ビル・エヴァンスとよく似ている。というのも彼らのプレイには、新しく響くいっぽうで、確たる伝統的なジャズのスピリッツを感じさせるところがあるからだ。革新的なジャズは、ハービー・ハンコックやチック・コリアに任せておけばいい。現にマッコイは、ジョン・コルトレーンのグループに居たけれど、師匠がフリー・ジャズに傾倒すると、まもなく脱退したよね。
では、反発の声があがるかもしれないが、いま一度ここで、キッパリ私感を述べておく。マッコイを聴くなら、インパルス!にかぎる。彼がインパルス!に残したリーダー作は『インセプション』(1962年)『リーチング・フォース』(1963年)『バラードとブルースの夜』(1963年)『トゥデイ・アンド・トゥモロウ』(1964年)『ライヴ・アット・ニューポート』(1964年)『プレイズ・エリントン』(1965年)と、6枚。『ブルース・フォー・コルトレーン/トリビュート・トゥ・コルトレーン』(1988年)というMCA傘下時代のインパルス!盤もあるが、これは除く。話題性ばかりが先行した、ちょっと残念な作品だし──。

やはりマッコイは、純粋にピアニズムを探求していた時代がいい。もし彼もビル・エヴァンスのように、ひたすらピアニスティックな表現を究めることに徹していたら、モダン・ジャズを代表するピアニストとして、その名を轟かせたかもしれない。しかしながらあいにく彼は、ジャズ・ロック、フリー・ジャズ、フュージョンといった、ジャズの複雑多様なものへの変化のなかで、時代の波に翻弄されながら、もがき苦しんでいくことになる。インパルス!の全6作は、コルトレーンのコンボ在籍時の吹き込み。かたや伴奏者としての責務を負い、忠犬のように師匠に寄り添っていた彼が、それらのリーダー作では、その呪縛が解かれたかのように、トラディショナルなジャズ魂を発揮している。
きっとマッコイは、とても真面目なひとだったのだろう。コルトレーンの即興演奏のボルテージがあがればあがるほど、背後でプレイする彼が繰り出す音の味つけは控えめになっていく。その点、彼はそのパワフルなタッチとはウラハラに、とてもデリケートなキャラクターの持ち主であると、ぼくは観ている。ピアノをはじめたのは、13歳のとき。なんだ、ぼくよりも遅いではないか!でもまてよ、それで21歳のときにはコルトレーンの『マイ・フェイヴァリット・シングス』(1961年)の吹き込みを終えていたのだから、彼は相当な努力家だ。実際、自宅にピアノがなかったマッコイ少年は、近所の家にあがり込んで練習に励んでいたという。
新しいスウィングのはじまり、音楽性の覚醒と解放のはじまり
さて、ここからは、まったくのぼくの想像。インパルス!の6作は、どれも素晴らしい出来栄え。どれを購入しても、損はない。なぜか?それは当時、コルトレーンが健在だったからだ。マッコイにとって、コルトレーンは師匠であるとともに、父親のような存在だったのではないだろうか(年齢的には歳の離れたアニキだけれどね)。ファースト・リーダー作『インセプション』(1962年)のマッコイの演奏からは「ねえねえ、父さん、観て観て!」「ぼくはこんなふうにも弾けるんだよ!」というような声が聞こえてくる。しかし、その喜びもつかの間、1967年コルトレーンが不帰の客となり、彼は自らの音楽を育む指標を失うのである。
ぼくは冒頭で、マッコイの登場は新しいスウィングのはじまりと云ったが、それは同時にその音楽性の覚醒と解放のはじまりでもあった。そういう意味で、彼のファースト・リーダー作には、“inception”ということばがよく似合う。作品の完成度からすれば、セカンドの『リーチング・フォース』のほうが出色の出来栄えだ。しかしながら、ぼくは『インセプション』のもつ、まさに「はじまり」にともなう期待と不安、そして興奮が入り混じった感じが好きなのだ。はじめてレコードをターンテーブルに乗せたときの心境、一聴してこころを躍らせたときのことを、いまだに忘れることができない。
ここでマッコイをサポートしているのは、まずコルトレーン・クァルテットの僚友、エルヴィン・ジョーンズ(ds)。ポリメトリックなドラミングを軽々と叩いてしてしまう天才。本作では、彼から終始刺激を与えつづけられるマッコイが、とても気持ちよさそうにグルーヴィーな鮮明で力強いフレーズを繰り出している。そしていまひとりは、やはりコルトレーンの『オーレ!コルトレーン』(1961年)で共演済みのアート・デイヴィス(b)。ジャズだけではなくクラシックのレコーディングにも参加し、かたや大学で臨床心理学の教鞭を執るという変わり種。ソロ・パートもあるが、軽快なウォーキングベースが印象に残る。

オープナーの「インセプション」はマッコイのオリジナル。こみあげるようなイントロ、流れるようなメロディ、目まぐるしいコードチェンジ──と、まさにピアニスティックなナンバー。アップテンポでエルヴィンのドラムスも跳ねまくる。つづくスウィング・バンドのバンマス、アイシャム・ジョーンズの代表曲「ノー・グレイター・ラヴ」は本作の白眉。こんなにも小洒落た演奏、こんなにも可憐な雰囲気──マッコイには珍しい。3曲目の「ブルース・フォー・グウェン」もマッコイの自作。カノニカルなテーマからブルース進行へと展開していくが、歯切れのいいグルーヴに身を委ねるばかり。
アルコベースの響きも効果的なマッコイのオリジナル・バラード「サンセット」は、爽やかさのなかに愁いの気配が漂う美しい曲。最近、新世代のパウエル派、ベニー・グリーンがソロ・ピアノ作品『ソロ』(2023年)で採り上げた。やはりマッコイのオリジナル「エフェンディ」は、ミッドテンポのアルバム中もっともモーダルな曲。コルトレーン・クァルテットのときよりも、演奏に品格があるように聴こえる。ピアノもベースも小気味いいが、ここは手数の多いドラムスに拍手(追従するのにひと苦労)。そして、おなじみのクルト・ヴァイル作「スピーク・ロウ」は、お約束のラテン・リズムが挿入されたアップテンポの4ビート。アルバムは、ハッピーなムードでフェイドアウト──。
ところで、ぼくは最初のほうで「好きなピアニストはマッコイ・タイナー」と触れまわって、とんでもない赤っ恥をかいたことがあると述べたが、それはあるジャズ通のかたに「もう古いよ」と反駁されたときのこと。たしかにそのころのマッコイといえば、前述したような、ちょっと首を傾げざるを得ない時代に突入していた。ジャズ通のかたにとって、彼はすでに終わったひとだったのかもしれない。しかしながら、インパルス!のマッコイはいま聴いても新しい。そして、ぼくはいまだに『インセプション』を手に取ると、これからなにかが始まるような気がしてならないのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント