味わい深いカクテル・ピアノとは?──たとえばレッド・ガーランドの極上の演奏

Album : The Red Garland Trio / A Garland Of Red (1957)
Today’s Tune : A Foggy Day
Who is your favorite jazz pianist?
プロのジャズ・ピアニストに、好きな──あるいは、影響を受けたピアニストは?──と訊くと、たいていビル・エヴァンスという答えが返ってくる。アート・テイタム、バド・パウエル、セロニアス・モンク、オスカー・ピーターソン、ハービー・ハンコック、近年ではブラッド・メルドーなどの名前も挙がる。ワザに長けたひとばかりだね。それはそうだ。関心の対象が研鑽を積むためのものとなるのは、当然のこと。なぜなら、プロの世界はいつの世も戦国時代。みな、自らの演奏技術に磨きをかけ、旧来の慣習を打破するような様式を模索しながら、しのぎを削る日々を送っているのだから──。
ぼくはアマチュアだけれど、かつてジャズ・ピアノを独学しはじめたころ、あるクラブの店主におなじ質問を受け、つい虚勢を張ってこころにもなく、マッコイ・タイナーと答えてしまったことがある。まったく赤面の至りで、いまでもそのことを思い出すと、体内をめぐる血液がぜんぶ上昇してくるような気分になるのだ。バカだねぇ。しかも、ぼくの答えを聞いた店主は、ニヤニヤしながら「もう古いよ」と宣った。ホント、穴があったら入りたいとは、このことだ。まあ、それはともかく、その店主を唸らせるには、いったいなんと答えればよかったのだろう?
それから時は流れ、就職してからはひと前でピアノを弾く機会がぐっと少なくなった。ところが不思議なことに、偶然にも当時の勤務先の上司が大のジャズ好きだった。職場では厳しいひとだったけれど、大して仕事もできないぼくを、(たぶん)ジャズを聴いたり演奏したりするという、ただそれだけの理由で、ずいぶんと可愛がってくれた。たとえば、仕事が終わると中古レコード店巡りに連れていってくれたり、休みの日には自宅のスゴいオーディオ装置でレアなレコードをたくさん聴かせてくれたりした。美人の奥さまの手料理まで振る舞ってもらったっけ──。
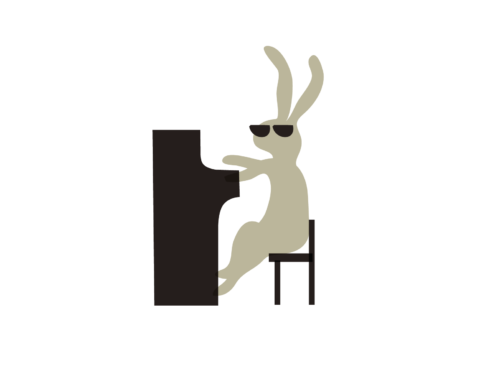
まあ、いまから考えると、そのひとは、ぼくにとってジャズの師匠みたいな存在だった。それまでのぼくはといえば、好きなものばかり聴いていて、かなりの偏食家だった。それに、どこかジャズを研究するような聴き方をしていたと思う。でも、そのひとからことあるごとに、ジャズの歴史や、レコードやアーティストにまつわる興味深いよもやま話を、シクシク聞かされているうちに、ぼくはだんだん、ジャズを系統立てて聴くようになっていった。そして、師匠に倣って(すっかりCDが主流の時代だったが)、アナログ盤に散財したもの。
ちょっと煎じ詰め過ぎているけれど、なにが云いたいのかというと、レコード・ジャケットをすべて透明フィルムで包装するような、ジャズの愛好家が愛してやまないピアニストは誰か?──ということ。はじめはとても意外に思ったのだけれど、あとになってみると、大いに合点がいった。所詮はカクテル・ピアニスト──と、バカにする向きもあるようだが、おそらく、そう云って酷評するひとは、カクテル・ピアノが実際どんなものなのか知らないのだろう。そして、味わい深いカクテル・ピアノがあるということも──。ぼくの師匠がもっとも敬愛した、レッド・ガーランドの極上の演奏のように──。
You can enjoy high quality cocktail piano.
ちなみに、カクテル・ピアノとは、ホテルのラウンジ、レストラン、クラブなどで演奏される、さっぱりと洗練された感じの、洒落たピアノ演奏のこと。楽しい気分や心地いい空気を作り出し、その場を満たすことに主眼が置かれた音楽。端的に云ってしまえば、BGMだ。食事や会話の妨げになってはいけないので、当然のごとくハードなプレイはご法度。だから、そんなムードはあるけれど、そのぶんソフトでライトな響きは、スクェアなジャズ・ファンからすると、だいぶ物足りなく感じるのだろう。そんな理由で、いまでは信じられないだろうけれど、かつてビル・エヴァンスでさえ忌み嫌われたときがあったのだ。
あれこれ語ったが結局、ぼくもガーランドのことが好きになった(師匠に感謝)。あとで知ったのだけれど、実は彼のアルバムは多くのジャズ・ファンに愛聴されている。ぼくが、青二才なだけだったのね。でも、プロのミュージシャンともなると、彼をフェイヴァリット・ピアニストとして挙げるひとはなかなかいない──と思っていたら、それが居たのだ。ジャズ・ピアニストとしては大ベテランの、大野雄二がそのひと。この20年くらいの間、大野さんの談話のなかには、ことあるごとにガーランドの名前が飛び出してくる。特にそのプレイを“引き算”と表現していたのが、印象に残っている。
おそらく“引き算”とは、熱くなって力まかせに弾いたりせず、ゆとりのあるくつろいだプレイをするという意味だろう。大野さんのような演奏に熟達したひとでも、ライヴが終わったあとに、“足し算”をやってしまったと後悔することがある──と聞いて、ちょっと驚いた。というのも、1990年代にぼくは銀座のサテンドール(後にもつ鍋屋に変わっていてショックを受けた)というクラブに通っていたのだけれど、そこに大野雄二トリオがよく出演していた。そして、そのころの大野さんといえば、コルトレーンの「インプレッションズ」を、それこそマッコイ・タイナーばりにガンガン弾いていたりしたのだから──。

確かにその後の大野さんの演奏には、ガーランドを彷彿させるような展開(ブロックコード奏法とか)が垣間見られるようになった。なによりもアドリブが、ファンキーだけれど以前に比べるとシンプルになった。ひとつひとつの音を、丁寧に弾いているように聴こえる。即興演奏の道理、ひいては音楽の真理みたいなものを見極めたのかもしれない。ホント大野さんって、気さくな言動とはウラハラに、音楽に対する鋭敏な感覚が感じられるひと。やはりスゴいジャズメンなのだ。そんな大野さんが敬愛するのだから、レッド・ガーランドもまたスゴいピアニストということになる。
そんなガーランドのプロフィールは、ちょっと変わっている。ウィリアム・マッキンリー・ガーランド・ジュニア──これが、彼の本名。20代の頃、髪の毛を赤く染めていたところから、“レッド”というニックネームがついた。ホント、よかった。彼にはたいへん失礼だけれど、なんだかしかつめらしい本名より、その小気味いいピアノさばきには、やはり粋な感じの愛称のほうが似合うもの。それと、彼はピアニストとしてデビューするまえは、なんとライト級のプロボクサーだった。抜群のリズム感は、リング仕込みか──?さらに、ピアノを弾きはじめたのは、ずいぶん遅くて18歳のとき。それまではクラリネット、サックス、それにトランペットを吹いていたという。
His distinctive style has fully formed already.
では、ガーランドの名盤は──?マイルス・デイヴィスのバンドに在籍していたころ(1955年~1958年)の彼の演奏は、どれもいい。リーダー作も佳作揃いだから、なにを選ぶかは個人の好みによる。ぼくは『ア・ガーランド・オブ・レッド』が好き。「録り溜めのボブ・ウェインストック」「寄せ集めのプレスティッジ」の作品にしては、珍しく全曲同日(1956年8月17日)の吹き込み。まとまりがあるのだ。ちなみに、マイルスのマラソン・セッション4部作は、もともと2回のレコーディングが振り分けられたもの。それが、毎年1枚ずつ4年かけてリリースされたのだ。
アルバム・タイトルが「赤い花輪のガーランド飾り」と、ウイットに富んだ『ア・ガーランド・オブ・レッド』は、名は体を表すというように、中身のほうも軽妙洒脱。ガーランドが33歳にして満を持してリリースしたデビュー作でもある(偶然にもぼくがはじめて購入したガーランドのレコードでもある)。驚くべきは、彼の独特なピアノ・スタイルが、この作品ですでに完成されている──ということ。十八番の右手オクターヴ+左手4音ヴォイシングによるブロックコード奏法も、ちゃんと出てくる。ぼくなんかは、どちらかというとオフビートな左手のコンピングに、ついつい耳がいってしまうのだけれど──。
メンバーもいい。ベースは、マイルス・バンドの僚友、ポール・チェンバース。このひと、ピチカートはもちろんアルコ奏法によるアドリブが有名だけれど、力強い4ビートのベースラインも魅力的。ドラムスは、個人的にはジャッキー・マクリーン(as)のアルバムでずいぶんとお世話になった、アート・テイラー。マイルス・バンドのフィリー・ジョー・ジョーンズに比べると器量は小さいけれど、無駄がなくて安定感のあるドラミングはガーランドにピッタリだ。このトリオのアルバムは8枚あるけれど、ぜんぶ好き。マイルス・バンドの呼称に勝手にあやかると、ファースト・グレート・トリオ!

このトリオの洗練されて巧みなところは、アルバムの冒頭からひしと伝わってくる。ガーシュウィン兄弟の「ア・フォギー・デイ」──この軽やかで爽やかな感じ──もはや、ガーランドのテーマ曲。しっとりバラードで聴かせるロジャース&ハートの「マイ・ロマンス」は、深くこころに染みるという点では至高のヴァージョン。本作の最初の山場は、コール・ポーターの「恋とは何でしょう」──コロコロ転がるようなピアノ、アルコベースとブラシのソロもスマート。インストでは珍しいミュージカル・ナンバー「メイキン・ウーピー」では、ブロックコードが朗々と歌いつづける。ベースのピチカートによるソロも快調。
ジョージ・シアリング・クインテットのテーマ曲として有名な「九月の雨」は、本家よりもテンポが速くて軽妙さが増している。アルコベースもふたたび登場。やはりロジャース&ハートによるバラード「リトル・ガール・ブルー」では、ひたすら澱みがなく美しいピアノに耽溺──。チャーリー・パーカーの「コンステレーション」は、二度目の山場。高速で熱くビバップする点は、このトリオにしては異色。しばし三人の即興合戦をご堪能あれ。ガーランドのオリジナル「ブルー・レッド」では、ベースが主役。延々とソロがつづいたあと、今度はブルージーなピアノが登場。スモーキーな味わいが、余韻を残す。
これは余談だが、もう15年くらいまえのはなし──。前述したぼくのジャズの師匠に久々に再会する機会があった。その懐旧の会食が中盤にさしかかったころ、ぼくは師匠に、やおら「いまはどんなの、聴いてるんですか?」と訊ねた。すると「E.S.T.知ってるか?エスビョルン・スヴェンソン、いいぞ」と返された。もちろん、知っていた。なにせ、ぼくの当時のいちばんのお気に入りは、ラーシュ・ヤンソンだったのだから──。それでも、最後はガーランドのはなしになった。秋の空のように嗜好が変わるジャズの愛好家たちを、いつでも温かく迎えてくれるのは、やはりガーランドおじさん──ちょっと都合がよすぎるね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント