溢れるモダニズムとリリシズム──アートオリエンテッドなピアニスト、ドン・フリードマンの人気盤『サークル・ワルツ』
 Album : Don Friedman Trio / Circle Waltz (1962)
Album : Don Friedman Trio / Circle Waltz (1962)
Today’s Tune : Sea’s Breeze
ドン・フリードマンといえばリヴァーサイド 盤+プレスティッジ盤
まだまだご紹介していない、好きなピアニストがたくさんいるな。自室のレコード棚をなんとはなしに眺めながら、そんなことを思う。ぼくは、レコードもCDも楽器別に分類している。そのなかでアーティストのファミリーネームでアルファベット順に配列。さらにそれを発表年順に並べている。おそらくオーソドックスな整理の仕方だろう。しかしながらぼくの場合、いささか問題がある。どういうわけか、なにを聴こうか迷ったときは、まえのほうから選んでしまうことが多いのだ。実に非効率的な行動様式と云える。なんだろうね、この習癖は。たとえば映画鑑賞においても、シリーズものだったりすると1作目から観たくなる。そういうとき多くの場合、最終作までたどり着かなかったりする。そして忘れたころに、また1作目から──。結局1作目ばかり観ている。
ホント、バカだね。そういえば大学受験のときも、日本史の教科書を何度となくはじめから読んでいた。だから古代についてばかり詳しくなって、現代に近づくにつれて曖昧模糊とした状態のままに終わる。そんなことをやっているから、社会科の点数は非常によろしくない。英語と国語がなかったら、完全に終わっていたな。どうにかならないのかね、この愚かなりしわが習性。そんなグチをこぼしても、如何ともし難い。閑話休題、例によって棚のまえのほうからレコードを漁りはじめると、ピアノのFの一隅にいい塩梅に未紹介のアーティストの作品がちょこなんと収まっていた。このところ、あまり聴いていなかったが、これを機にあらためてじっくり聴き直してみようと思った。ぼくは、おもむろにレコードをターンテーブルにのせる──。
ということで、ぼくが聴きはじめたのは、ドン・フリードマン(1935年5月4日 – 2016年6月30日)の『ア・デイ・イン・ザ・シティ』(1961年)。彼の初リーダー・アルバムだ。やはり1作目から聴いてしまった。タイトルどおりニューヨークの一日の印象を綴った作品で、組曲風の構成という意匠が凝らされたコンセプト・アルバム。サイドを務めるのは、のちにビル・エヴァンス・トリオに参加するチャック・イスラエル(b)と、当時ジョージ・ラッセル(p)のセクステットで活躍していたジョー・ハント(ds)。なおハントのほうもその後、エヴァンスのツアーに参加する。本作はなかなかの力作で、熱烈なフリードマンのファンからはベストワンとも云われている。ところが、一般的な人気はイマイチのようで、日本での発売もほかの作品よりもずっとあとだった。
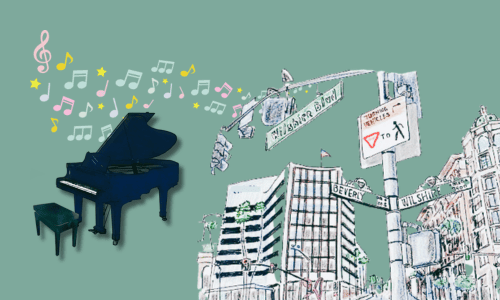
そういうぼくもまた、フリードマンのことを熱心に追いかけるクチではないけれど、なぜかしら、レコード棚には彼のアルバムがいつの間にか増えている。それって、知らず知らずのうちに彼のピアノ演奏に惹かれているということなのだろう。おまえの好きはその程度かと云われれば返す言葉もないのだけれど、どうしてだかわからないが無性に聴きたくなるときがあるのもまた事実。とにもかくにも、リヴァーサイド・レコードの4枚、すなわち『ア・デイ・イン・ザ・シティ』をはじめ『サークル・ワルツ』(1962年)『フラッシュバック』(1963年)『ドリームズ・アンド・エクスプロレイションズ』(1964年)は、ことあるごとにターンテーブルにのる。ぼくは勝手に、プレスティッジ・レコードの『メタモルフォーシス』(1966年)もあわせて、これらを5部作と云っている。
ちなみに、最初の3枚はメンバーは異なるがトリオ編成による吹き込み。後続の2枚はハンガリーのジャズ・ギタリスト、アッティラ・ゾラーが加わったクァルテット作品となっている。実はこのあと、フリードマンのリーダー作はしばらくご無沙汰となる。およそ9年のブランクののち、彼は突然、日本のジャズ・レコード・レーベル、イースト・ウィンドから『ホープ・フォー・トゥモロウ』(1976年)というアルバムをリリースする。ただこの作品において、フリードマンはフュージョン志向とまではいかないが、アコースティック・ピアノ以外にフェンダー・ローズやアープ・ストリング・アンサンブルも弾いている。エレクトリック・ベースまで登場するのだが、それらに必然性が感じられず、ぼくにとっては残念な作品となっている。
やはりぼくの場合、フリードマンの作品といえば、前述の5部作を循環的に聴くことがほとんどなのである。さらにつけ加えるとしたら、クラシック作品の制作で知られる日本のマイナー・レーベル、カメラータ・トウキョウからリリースされた『スコット・ラファロの思い出』(1988年)だろう。早世の天才ベーシスト、スコット・ラファロが参加した1961年のプライヴェイト・レコーディングをCD化したものだ。ラファロとフリードマンは1959年から、ニューヨーク市マンハッタン区のアッパー・イースト・サイドの住居兼リハーサル・ルームにおいて、およそ1年間の同居生活を送った。無二の親友であるふたりのセッションは、たいへん貴重であり、いまもなお瑞々しさを残す。
フリードマンはどんなピアニスト?エヴァンス派?それとも──
ところで、ドン・フリードマンというピアニストを語るとき、必ずといっていいほど、エヴァンス派だとか、エヴァンスの後継者だとか、エヴァンスの好敵手だとか、とにかくビル・エヴァンスが引き合いに出される。確かに前述のチャック・イスラエルにしてもスコット・ラファロにしても、エヴァンスのトリオで活躍したベーシスト。フリードマン自身のピアノ・プレイにも、印象主義音楽のハーモニーを彷彿させるコード・ワーク、叙情的なフレージング、そして繊細で美麗なタッチといった、エヴァンスに通じるニュアンスを垣間見ることができる。特にリヴァーサイド時代の最初のほうの作品では、そんな感触が濃厚なピアニズムが繰り出されている。しかしながら、果たしてフリードマンをエヴァンス派と決めつけていいものだろうか?
ぼくには、フリードマンがエヴァンスに似ているとは思えない。どちらかといえば、初期のクレア・フィッシャーやクロード・ウィリアムソンといったウエストコースト・ジャズのピアニストに近いような気がする。いやいや、その程度のものではないな。むしろレニー・トリスターノやデニー・ザイトリンの流れを汲む、アヴァンギャルドでエクスペリメンタルなジャズを展開するときもあるのだから。なるほどリリカルな魅力を放つという点では、エヴァンスとフリードマンの音楽は相似すると云える。しかしながら、それぞれの本質は異なる。異論を唱える向きもあると思うが、ぼくにとってエヴァンスはピアノ・オタクであり、フリードマンは詩人ハダシなのだ。云ってみれば、エヴァンスはフランツ・リスト、フリードマンはフレデリック・ショパンということになる。
エヴァンスが自己のピアノ演奏の可能性と音楽理論の蓋然性をひたすら掘り下げていくのに対し、フリードマンは広範囲にわたってアートオリエンテッドな音楽を具現化することに挑む。フリードマンの場合、件の5部作をすべて聴くと、それがよくわかる。たとえば彼は、それらのうち後半の作品において、アブストラクトな演奏も披露している。当時のフリードマンは、フリー・ジャズの先駆者であるオーネット・コールマン(as)ともすでに共演を果たしていたから、少なからずコールマンからの影響があったと思われる。そういえばスコット・ラファロも、コールマンのレコーディングに参加していた。いずれにしてもフリードマンは、前衛音楽とまではいかないまでも、実験的かつ芸術的な音楽をクリエイトしようとしていたのである。

くどいようだが、エヴァンスは天才、フリードマンは凡才とまでは云わないが、ごくごく正統的なひと。もちろん、ピアノのテクニックは十二分。作曲についても巧妙と云える。でも、飽くまで本流の系統を受け継ぐ音楽家なのだ。ただし、これはぼくの想像だけれど、彼は謹厳実直で飛耳長目なひとなのだと思う。自己の音楽を芸術の域にまで高めようとするチャレンジ精神と、流行や趨勢に敏感でそれをいち早く導入する柔軟性には、並々ならぬものがある。だからときには、前述の『ホープ・フォー・トゥモロウ』のように、1970年代のトレンドを積極的に採り入れて、ジャズ・ロックとリリカルなジャズをミックスアップしたような奇妙キテレツな作品も作ってしまうのだ。
このちょっとやっかいなアルバムには、プロデューサーとして伊藤八十八(1946年8月8日 – 2014年11月19日)の名前がクレジットされている。国内のアーティストでは、渡辺貞夫(as)、日野皓正(cort)、マリーン(vo)、ザ・プレイヤーズ、ザ・スクェア(ティー・スクェア)などを手がけた音楽プロデューサーだが、海外のアーティストにおいても、ケニー・バロン、ウィル・ブールウェア、ボブ・ジェームス、ハンク・ジョーンズ、ジョー・サンプルといった、ジャズ・シーンに名だたるピアニストたちの素晴らしい作品を世に送り出した。伊藤さんは、ジャズ、フュージョン、ロック、ポップスなど幅広いジャンルの音楽に関わったひとだから、フリードマンに『ホープ・フォー・トゥモロウ』のような異色作を吹き込ませたのも、いまになってみると不思議ではない。
その伊藤さんが27年後、ちょっと失礼な云いかたかもしれないが、フリードマンの作品においてリベンジを図る。伊藤さんは、2002年にヴィレッジ・レコードのサブ・レーベルとしてエイティ・エイツを立ち上げた。そして、このレーベルにおいてフリードマンの作品を立てつづけに制作した。最初のレコーディングが行われたのは、フリードマンが67歳の誕生日を迎えたすぐあとのことだった。特にトリオで吹き込まれた『ワルツ・フォー・デビイ』(2003年)『マイ・フェイヴァリット・シングス』(2004年)『タイムレス』(2004年)『スカボロー・フェア』(2005年)といった最初の4枚は、ぼくの愛聴盤。そこにはもはや、彼をエヴァンス派と疑う余地は少しもない。正統的なピアニストの円熟味を増した、味わいが深いプレイが堪能できるばかりである。
エイティ・エイツの作品でも、フリードマンはエヴァンス所縁のナンバーを採り上げている。ときには曲の構成においてエヴァンス・トリオとおなじようなアプローチも散見される。しかしそんなときもフリードマンのピアノ・プレイには、エヴァンスよりもパワフルなタッチが際立つ。またインプロヴィゼーションにおいて、経過的に急速なパッセージが度々繰り出されるが、このドライヴ感はエヴァンスにはない特色と云える。いずれにしても、フリードマンの実に逞しいピアニズムが堪能できる。途中からグループ名が、ドン・フリードマンVIPトリオとなるが、これはご愛嬌。なおその後、このレーベルからソロ・ピアノによる『ムーン・リヴァー』(2007年)、トリオによる『サークル・ワルツ・21C』(2010年)もリリースされるが、こころ温まる佳作といった出来映えだ。
ピアノ・トリオの名盤の呼び声が高い『サークル・ワルツ』
考えてみればドン・フリードマンは、リーダー・アルバムを50枚以上も吹き込み、しかも傘寿祝いの目前までレコーディングに臨んだ。その晩年において演奏能力に失調をきたしたとしても、それはごく当たりまえのこと。しかしながら、彼の演奏は最後まで比較的壮健だったように思われる。特に美しいハーモニーのセンスは衰え知らずで、そういった意味でフリードマンは生涯、リリシズムに溢れたジャズ・ピアニストとしてトップの座を占めつづけたと云っても過言ではない。彼はロサンゼルスでジャズ・ピアニストとしてのキャリアをスタートさせ、はじめはトラディショナルなジャズ・プレイヤーだった。ところがニューヨークへ移り自らの殻を破るがごとくモダンなスタイリストに変容。それらの経験がほどよくブレンドされて円熟期を迎えた──フリードマンは、そういうピアニストである。
フリードマンはカリフォルニア州サンフランシスコ市の生まれだが、両親は移民で父親はリトアニア、母親はドイツの出身である。4歳からクラシック・ピアノを弾いていたフリードマンは、15歳のときにロサンゼルス市街、サン・フェルナンド・バレーに移住する。ハリウッド・パラディアムで上演されたスタン・ケントン楽団などのビッグ・バンドのコンサートを体験したことから感化され、17歳くらいからジャズ・ピアニストを目指すようになる。また彼は、ハリウッドの麓に位置する2年制大学、ロサンゼルス・シティー・カレッジにおいて作曲も学んでいる。その後1956年から、前述のオーネット・コールマンをはじめ、バディ・デフランコ(cl)、デクスター・ゴードン(ts)、チェット・ベイカー(tp)といった、西海岸の猛者たちと共演。クラーク・テリー(tp)のビッグ・バンドのピアニストを務めたこともある。
そんなフリードマンは1958年、ニューヨーク市に移り住み結局そのまま永住した。ロサンゼルス時代からマイルス・デイヴィス(tp)の、俗に云うファースト・グレイト・クインテットを最高のコンボと崇め、ニューヨーク行きを夢見ていたという。本人の弁によると、音楽的にもっとも影響を受けたのは東海岸のミュージシャンたちからとのこと。たとえば、彼が23歳にして夭逝したブッカー・リトル(tp)のサイドを務めたことは、あまりにも有名だ。また、エリック・ドルフィー、ジミー・ジュフリーといったマルチ・リード奏者との共演から、フリー・インプロヴィゼーションの世界にも足を踏み入れている。その後リヴァーサイド・レコードと契約し、前述のデビュー作『ア・デイ・イン・ザ・シティ』を発表した。

このフリードマン26歳にしてはじめてのリーダー作は、そのポストバップともいうべきサウンドの独創性、特にハーモニー感覚に現代音楽の要素が含まれているという点で、高く評価された。そのいっぽうで、エヴァンスの模倣という批評もあった。ところがそんな評判から却って上手くことが運び、早々にセカンド・アルバム『サークル・ワルツ』が制作された。フリードマンのリーダー作ではもっともエヴァンス色が強く、同時にもっとも人気を集めたアルバムでもある。レコーディングは1962年5月14日、フリードマン27歳のとき。ちなみにこのとき、ラファロが参加したエヴァンスのリヴァーサイド4部作はすでに世に出ていた。もちろんフリードマン自身、エヴァンスを意識したのだろうが、それ以上にエヴァンス風を志向したのはアルバム・プロデューサーのオリン・キープニュースだったと思われる。
サイドにチャック・イスラエル(b)、ピート・ラロカ(ds)を迎えて吹き込まれた本作は、ピアノ・トリオの名盤の呼び声が高い。おそらく多くのリスナーが、オープナーであるリリシズムを湛えたロマンティックなジャズ・ワルツ「サークル・ワルツ」を聴いただけで、そのモダンで瞑想的な美しい世界に引き込まれるからだろう。この曲、確かにいい曲なのだが、ちょっとエヴァンスの「リ・パーソン・アイ・ニュー」を彷彿させるところがある。インタープレイらしきものも出来する。しかし吹き込みは、エヴァンスのほうが少しあと。ひょっとしてラファロを事故で失い落ち込んでいたエヴァンスに、キープニュースがこのフリードマンのオリジナル曲を聴かせて焚きつけたのでは?──と、ぼくはそんな勝手な想像をしたくなる。
だがしかし、ぼくが本作で好きなのは2曲目から3曲目。フリードマンの自作「シーズ・ブリーズ」では、テンポの軽快さ、メロディック・ラインの洗練された感じ、そしてピアノのアドリブの小気味よさが、得も云われぬ爽快感を生んでいる。サイドとのソロ交換も絶妙。ややクラシカルなルバートからテンポが上がっていく「アイ・ヒア・ア・ラプソディ」では、さらにトリオは三位一体のプレイを披露。ディック・ガスパールの曲でもともとスウィング・バンドのナンバーだったが、ここではそれを忘れさせるくらいスリリングな展開を見せる。後半では、フリードマンのピアノもラロカのドラムスも高く飛翔する。ここでレコードを裏返す。デイヴ・ブルーベックの「イン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ」では、フリードマンが唯一無二の解釈によるバラード演奏を聴かせる。知的で現代的なサウンドと想像力に富んだフレージングは、まさに芸術だ。
フリードマンのオリジナル「ラヴズ・パーティング」は、アルバム中もっともリラックスした叙情的なバラード。聴くもののこころを鎮めて瞑想に誘うようなコード進行が素晴らしい。フリードマンの情感に溢れたピアノの歌わせかたも極上。コール・ポーターの「ソー・イン・ラヴ」では、フリードマンの技巧的なソロ・ピアノを堪能できる。その速弾きからは、それこそまえに述べたようにレニー・トリスターノからの影響が感じられる。フリードマンの自作「モーズ・ピヴォティング」は、その名のとおりモーダルな曲だが、フリードマンはエヴァンスに通じるスケールを、より抑揚をつけて押広げていく。後半はジャムセッション風になるが、幽玄な雰囲気はフェードアウトされるまでつづいていく。まさに本盤は、トラディショナルなピアニストが、モダンでエステティックなスタイリストを気取った作品。フリードマンは、決してエヴァンス派ではないのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント