モダン・ジャズ・ピアノのパイオニア、バド・パウエルが残した芸術的作品
 Album : Bud Powell / The Bud Powell Trio (1957)
Album : Bud Powell / The Bud Powell Trio (1957)
Today’s Tune : Indiana
ビバップの先駆者であり、ピアノ・トリオの草分け
ジャズの愛好家の間では、ピアニストを言い表すときに、よく「パウエル派」というコトバが使われることがある。べつにジャズに流派があるわけでもないし、音楽の様式を説明するときに便宜上、系統づけているだけのことと思う。でも「モンク派」とか「ピーターソン派」とは云わない。「トリスターノ派」とか「エヴァンス派」はよく聞くけれど──。いずれにせよ、もっとも多く使われるのは、やはり「パウエル派」だろう。ビバップの先駆者であり、ピアノ・トリオ=ピアノ+ベース+ドラムスというスタイルの草分けでもある、バド・パウエルが度々引き合いに出されるのは、当たりまえといえば当たりまえだ。
ビバップを作ったと言われるアルト奏者、チャーリー・パーカーがそうであるように、パウエルもまた技巧に優れたミュージシャンだ。つまり、コード進行に基づく即興演奏を開拓したひと。アドリブ演奏は、ニューオーリンズ・ジャズのころからあったけれど、どちらかといえば装飾的なものであったり、メロディをフェイクする程度のものだった。主役は飽くまで曲そのもので、プレイヤー自身にスポットが当たるのは、ほんのごく一部のこと。そんな状況のなか、パーカーやパウエルは、サウンドと演奏の幅を広げるような、ロジカルな方法を生み出した。云ってみれば、ジャズを芸術の域に達させたわけだ。
まあ、そんな革新的な音楽を創造するのだから、音楽理論はもとより高度な演奏テクニックが要求される。その点、パーカーにしてもパウエルにしても、まさに芸術的な表現力に富んだ、凄まじい技巧の持ち主。これは余談だが、当時ビリー・エクスタインのビッグ・バンドのメンバーだった、若き日のマイルス・デイヴィスが、横でバリバリ吹きまくっているパーカーの演奏に圧倒された──というエピソードは有名。マイルスはその高速プレイについていくことができず、まったく吹けなくなってしまったという。パーカーは、ぼくの大好きなジャッキー・マクリーンをはじめ、多くのアルト奏者に影響を与えたけれど、そういえば「パーカー派」というのもよく耳にする。

いっぽうパウエルのほうも、ピアノ演奏のテクニックは天才的。それまでのスウィング・ジャズでは、左手のオモテでベース、ウラでコード、右手でメロディという弾きかたが主流だったが、パウエルはといえば、ボトムとリズムはベーシストとドラマーにお任せして、自分は右手でメロディとアドリブに集中。左手のほうではコード・プログレッションの複雑化を図った。6歳からクラシック・ピアノを弾いていただけに、とにかく指はよく動く。あまりにも右手ばかり動かすものだから、あのアート・テイタムが、彼のことを“片手のピアノ奏者”と揶揄した。それを耳にしたパウエルは、あるときステージで左手のみの演奏を披露したという。すごいレジェンド!
とにかもかくにも、パウエルの即興演奏に対する集中力は神業的。彼のことを“ピアノのチャーリー・パーカー”と呼ぶ向きもあるようだが、大いに頷ける。そんな彼のいちばんの人気作といえば『ザ・シーン・チェンジズ』(1959年)だろう。当時3歳だった息子のジョンくんとのツーショットのジャケットが、微笑ましい。このアルバムが多くのひとから支持されるのは、冒頭の「クレオパトラの夢」があまりにもいい曲だから。ブルージーでどこかエキゾティックな響きは、いかにも日本人の琴線に触れそう。この曲も含めてアルバムの収録曲は、すべてパウエルのオリジナル。実はこれが、案外しんどかったりする──。
名曲「クレオパトラの夢」には、ちょっと息苦しさを覚える
ほとんどの曲がマイナー・キー。コード進行も似たり寄ったり。はじめてジャズを聴いたひとにもわかるくらい、ミストーンが散見される。明らかに、指がもつれている。そして、後期のパウエルにつきものの唸り声が、しきりに聞こえてくるのだ。でも、その集中力たるや、ちょっと怖いくらいに持続する。たとえ演奏にミスがあってもお構いなしに、次々に即興でフレーズを繰り出していく様には、鬼気迫るものがある。ただ聴いているほうは、ちょっと息苦しさを覚える。だからぼくの耳はいつも、気がつくとポール・チェンバース(b)とアート・テイラー(ds)のプレイに逃げてしまっている。
バド・パウエルは、まさに破滅型の天才と呼ばれるに相応しい。ピアノ・トリオ延いてはモダン・ジャズにおいて、イノベーターの役割を果たしながら、同時代のジャズメンが陥りがちな悪癖を彼もまた矯めることができなかった。その体たらくといえば、まるで悪魔に魂を売ったかのようだ。なにせ統合失調症を患いながら、ピアノを弾いていたのだから──。そんなわけで、彼の音楽家としての最盛期は、1940年代後半から1950年代の初頭まで。1950年代の半ば以降は、不調期と云える。それでも「クレオパトラの夢」は多くのリスナーを魅了し、その鬼気迫る演奏も独自性と評価されたりするのだから、やはりパウエルは常人ではない。
たぶん「クレオパトラの夢」はテレビCMで何度か使用されたから、それらを機に『ザ・シーン・チェンジズ』を手にしたひとは多いと思う。なかにはパウエルの名前をはじめて知ったひと、あるいはジャズにはじめて触れたひとも、たくさんいるのではないだろうか?かく云うぼくも、10歳以上年上の従兄に強く推されてこのレコードを購入したが、それがパウエル初体験だった。そして、見事に肩透かしを食らった。もし、ぼくとおなじように気落ちしたひとがいたら、それで彼のことを嫌いにならないで欲しい。ぼくはそうは思わないが、並大抵のピアニストと比較したら、不調でもパウエルの演奏のほうが上という向きもあるし、なんといっても最盛期の演奏は神業的だから──。
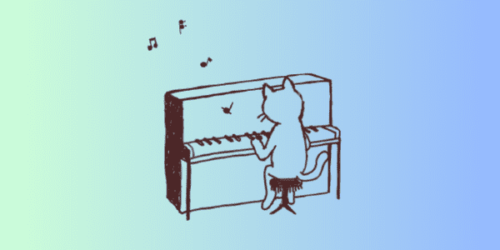
確かに、この破滅型の天才の生き様を俯瞰するという意味では、晩年の演奏を聴くことも有意義だ。やたらに凄味ばかりが際立つダメダメなプレイを聴かなければ、ほんとうにパウエルを理解したことにはならないという、彼の信奉者もいるくらいだ。まあ、それだけ彼が途轍もないジャズ・レジェンドである──ということなのだね。そうはいってもヤワな神経の持ち主であるぼくのように、とんでもない気迫に満ちた演奏を聴きつづけることに苦痛を覚える、感情の細やかなリスナーもいると思う。そんなひとには、ぜひ彼の最高潮のプレイをよく玩味して聴いて、そして楽しんでいただきたいもの。
そこで、おすすめするのが『バド・パウエルの芸術』だ。この邦題、一見思慮に欠けるようにも映るが、いやいや、なかなかアッパレなのである。このアルバムでのパウエルのピアノ・プレイは、不朽の輝きを放っていて、まさに芸術の名に相応しい。本作は、1949年にテディ・レイグが設立したルースト・レコードからリリースされた2枚の10インチ・レコード『バド・パウエル・トリオ』(1951年)と『バド・パウエル・トリオ Volume 2』(1953年)が、1957年に12インチLPとしてまとめられたもの。特に前者は、デラックス・レコードでお蔵入りとなっていた1947年のセッションで、パウエル・トリオの最初期の吹き込みである。ちなみに、これまた芸術的なジャケットは、Volume 2のアートワークがそのまま採用されたものだ。
孤高の音楽家による芸術
レコードのA面には、1947年1月10日に吹き込まれた8曲が収録されている。サイドは、カーリー・ラッセル(b)とマックス・ローチ(ds)。特にローチのブラシワークが、素晴らしい。ここではスローでもアップでも、ひたすらブラシ。特にアップ・テンポの曲では、エッジが効いていてスピード感が増している。オープナーの映画挿入歌「四月の想い出」は、モダン・ジャズの解釈として、その後のお手本となった。パウエルのピアノは、とても流麗。つづくパーカーも影響を受けた「インディアナ」での、彼の早弾きはまさに神業!ぼくは一聴で、完全にやられた。ミュージカル曲「誰かが私を愛している」は、リラックスしたムードのなかでも、ピアノは饒舌に歌う。映画主題歌「アイ・シュッド・ケア」は、眩いばかりに美しいバラードだ。
パウエルのオリジナル「バッズ・バブル」は、アップ・テンポでのドラムスとの交換も然ることながら、とにかくピアノのアドリブが、次々と千姿万態のフレーズを繰り出してくるのが圧巻。セロニアス・モンクの「オフ・マイナー」では、モンクからの影響は否定できないけれど、パウエルのプレイは正統的なアプローチを見せる。ガーシュウィンの映画音楽「首尾よくいけば」では、一糸乱れぬピアノの高速演奏がすこぶるゴキゲン。トリオの息も完璧に合っていて爽快。弾き語りの名手マット・デニスの「エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー」では、きらめくバラード演奏を堪能。この曲を聴くと、パウエルが“片手のピアノ奏者”ではないとわかる。アルペジオもペダルも使うのだ。
B面には、1953年8月に録音された8曲が収録されている。ジョージ・デュヴィヴィエ(b)とアート・テイラー(ds)が、サイドを務めた。出所後のパウエルは、日常生活や社会参加が困難な状態にあり、すでにその演奏はいささか精彩を欠いている。ブルーノート盤『ジ・アメイジング・バド・パウエル Vol.2』(1954年)の編曲も手がけたデュヴィヴィエと、安定感のあるドラミングで定評のあるテイラーの手堅いプレイにずいぶん助けられているように、ぼくには聴こえる。1曲目のガーシュウィンの「エンブレイサブル・ユー」は、含蓄のある表現法でなんとか乗り切った感じ。パウエルのオリジナル「バート・カヴァーズ・バド」は、ピアノは弱めだが、明るい曲想と軽快なグルーヴで、まあまあ聴ける。

ロジャース&ハートの「マイ・ハート・ストゥッド・スティル」では、以前のパウエルように多弁とまではいかないが、比較的淀みなく弾いている。コール・ポーターの映画主題歌「帰ってくれたらうれしいわ」は、超スロー・テンポのアレンジが功を奏して、テーマがメロディアスに響く。ミルト・ジャクソンの「バグス・グルーヴ」は、優美さに欠けるが、曲がマイナー・ブルースのせいかパウエルの演奏は熱っぽく聴こえる。バリトン歌手、ヴォーン・モンローのヒット曲「マイ・ディヴォーション」は、左手がコードを押さえるばかりで、正直に云ってちょっとキツイ。
ヴィクター・ヤングの映画主題曲「星影のステラ」では、ソロ・ピアノを披露。曲がロマンティックなバラードだけに、ケレン味のない演奏に好感がもてる。ラストはディジー・ガレスピーの代表曲「ウッディン・ユー」だが、これはいい。コンパクトにまとまっていながらも、トリオの一体感といい、パウエルの小気味よく歌うアドリブといい、胸がすく。というわけで、B面の吹き込みは、A面の奇跡的な演奏から6年の隔たりがあるが、その間のピアノ・トリオというスタイルの発展と、それに反する精神的、肉体的な退行が如実に表れている。だが、好調なときもそうでないときも、ピアノを弾くことをやめなかった(苦悶を音楽のなかに封じ込めた)パウエルは、破滅型の天才であると同時に、孤高の音楽家だった。そう考えると前述の「パウエル派」というコトバも、軽忽に使えなくなるのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント