レジェンダリー・ベーシスト、スコット・ラファロが参加した、女性ジャズ・ピアニスト、パット・モランの唯一のトリオ作品『ディス・イズ・パット・モラン』を楽しむ
 Album : Pat Moran / This Is Pat Moran (1958)
Album : Pat Moran / This Is Pat Moran (1958)
Today’s Tune : Come Rain Or Come Shine
屈強なキーストロークと豪勢なスウィング感を有するパット・モラン
百花繚乱という、素敵な字面のコトバがあるが、現代におけるわが国の女性ジャズ・ミュージシャンがまさにそんな状況ではないだろうか。種々様々な花のごとき個性的な優れたプレイヤーたちが華やかに、しかも美しく咲き乱れる景色を眺めることができる。もちろんジャズを演るのに性別は関係ない。とはいっても、ひと昔まえの日本のジャズ・シーンでは、シンガーはともかく楽器を操る女性は非常に少なかった。そういった意味では、10代から駐留軍クラブでジャズ・ピアニストとして活動していた秋吉敏子の存在感は圧倒的だ。しかしそれは悲しいかな、ジャズ業界がまだ男性優位だったことを意味するものでもある。
おまけに、漠然とではあるがそれほど遠くない昔、確かにジャズを楽しむ環境にも閉鎖的なところがあった。たとえば1990年代のこと。ぼくは銀座のサテンドールというクラブ(のちにもつ鍋屋に変わった)によく足を運んでいたのだけれど、あるとき、おひとりさまの女性客がアイスクリームの盛り合わせをつまみにカクテルを味わいながら、気持ちよさそうに音楽に合わせて身体を揺らしていた。ほかに居たのは男性客ばかりだったが、みな女性の姿に大層目を丸くしていたもの。本来とりわけ不思議なことでもないはずだが、その場にいたジャズの愛好者のほとんどが、自分でも気づかないうちに英国の紳士クラブにでもいるような気分になっていたのだろう。いまはもっと開放的になっていると、信じるけれど──。
いずれにしてもジャズという音楽は、プレイヤーにとってもリスナーにとっても、もっともっと広く門戸が開かれるべきである。よく耳にする、ジャズはハードルが高い──というのは単なる俗信で、実際はほかの音楽と同様に気軽に楽しむことができるものなのだ。さらに云えば、現代ではジェンダーレスやボーダーレスが謳われる機会が多いけれど、仮に音楽が男性的に響く──という場面があったとしても、女性ミュージシャンはそれに迎合して男性的な演奏をする必要はないし、敢えて女性的な面をアピールする必要もないと、ぼくは思う。それと同時に、ジャズは可能性が広がる音楽であるとも思っている。だから演るのも聴くのも、もっと自由でいいというわけだ。

ということで、今回は女性ジャズ・ピアニストの作品をご紹介──。このパット・モランというピアニスト、知名度のほうはあまり高くない。でも、ピアノの鍵盤のうえに置かれた赤いヒールを履いたおみ足のアップ──という、カヴァーアートはけっこう知られている。ぼくはこのジャケットをはじめて見たとき、とっさにピチカート・ファイヴのアルバムではなく、イタリア式コメディの快作『女性上位時代』(1968年)という映画を連想してしまった。新婚の女性が馬になった亭主に跨がって、ルンルン気分で新居をハイシドウドウするあれだ。ちなみに音楽は、ぼくの大好きなジャズ・ピアニスト、アルマンド・トロヴァヨーリが担当。まあとにかく、女性の可愛らしいけれど勇ましい──といったイメージが、件のジャケットと重なった。
主役はわたしよ!と云わんばかりに、ドラマーとベーシストの男性はアウトフォーカス。被写体のおみ足が、一段と際立っている。ヒールのつま先を点々で指して「これはパット・モランです」となっている。ああ、あとになったが、これは『ディス・イズ・パット・モラン』(1958年)というアルバムのジャケット。この小洒落たカヴァーアートの写真のとおり、本作はピアノ・トリオで吹き込まれた。しかもモランがリーダーとして関わったアルバムはたったの4枚しかなくて、純粋なトリオ作品としては本作のみである。それこそジェンダーレスではないが、弾いたときに鍵盤が下がったまま上がってこなくなったり、ピアノ線が切れたりするのではないかと憂慮されるほどの、モランの強烈なタッチを存分に楽しめる貴重な作品だ。
モランは、その屈強なキーストロークと豪勢なスウィング感から、たまにリスナーに男性プレイヤーと勘違いされることがあるとか──。そのうえパットというファーストネームも男性をイメージさせるから、そんな思い込みがあっても致しかたない。せめて本名のヘレン・マリー・マジェットで活動していたら、すぐに女性とわかったのだろうけれど──。モランは1934年12月10日、オクラホマ州ガーフィールド郡の郡庁所在地、イーニドに生まれた。イーニドは田園風景が美しく歴史的建造物も多いことから、わが国でも人気の観光スポットとしてよく知られている。モランは、そんな自然が豊かで歴史のある都市でのびのびと育った。きっと活発な女の子だったに違いない。彼女のピアノ演奏から、ぼくはそんな想像をしてしまう。
ベヴァリー・ケリー、スコット・ラファロとの出会い
ぼくは、モランがピアノを弾いている姿を、ライヴではもちろんのこと映像においてすら観たことはない。でもどうしても、堂々としていて威厳さえ感じられるような佇まいで、力強く鍵盤を叩いている彼女をイメージしてしまう。スピーカーから、そいう音がするのだ。両親が音楽家だったこともあり8歳からクラシック・ピアノを弾いていた。そこはもっとドルチェで弾きなさい──なんて、先生に注意されていたかもしれない。思わずそんな空想に耽って、ニヤニヤしてしまう。彼女はイーニドの私立大学フィリップス・ユニヴァーシティでピアノを専攻し、さらにその後オハイオ州のシンシナティ音楽院で腕に磨きをかけた。日本を代表するヴィルトゥオーソ、大井和郎もここの出身。
ということで、モランはもともとコンサート・ピアニストを目指していた。ところが、バド・パウエルとジョン・ルイスの演奏に感化されジャズ・ピアニストに転向した。クラシックからビバップという流れは、ちょうど先達のふたりと共通する。彼女はニューヨークのヒッコリー・ハウスおよびバードランド、シカゴのブルーノートなどのジャズ・クラブでライヴ活動をしたが、なんといってもザ・パット・モラン・クァルテットの結成が、そのキャリアにおいてもっとも成果を上げたと云えるかもしれない。クァルテットといっても4つの楽器で重奏する純粋な楽隊ではなく、どちらかというとこのバンドにはモダン・ジャズ・コーラス・グループといった趣きがある。楽曲にはインストゥルメンタルもヴォーカル・ナンバーもある。
メンバーは、パット・モラン(p, vo)、ベヴァリー・ケリー(vo)、ジョン・ドーリング(b, vo)、ジョニー・ホワイテッド(ds, vo)ということで、ピアノ・トリオ+ヴォーカルという編成だが4人とも歌唱を務める。男女各2人による4人のジャズ・コーラスというと、マンハッタン・トランスファーが思い出される。モランのクァルテットは、彼らほどの卓越したハーモニーとヴォーカル技術を持ち合わせてはいないけれど、ひとかたならぬスウィング感のなかにポップなセンスが光る、とても親しみやすい音楽を繰り広げる。モランは、ピアノ・プレイはもちろんのことヴォーカルのセンスもなかなかのもので、実に才媛の誉れが高い。とはいっても肩肘を張るようなところがないので、楽しく聴ける。そこがいい。

このグループはベツレヘム・レコードから『ザ・パット・モラン・クァルテット』(1956年)と『バードランドのパット・モラン・クァルテット』(1957年)という2枚のアルバムをリリースしている。オススメは断然ファースト・アルバムのほう。セカンド作も決して悪くはないが、レギュラー・メンバーのほかに管楽器奏者が参加しており、いささかバンドとしての一体感が欠けるように思われる。特筆すべきは、シンガーのベヴァリー・ケリーについて。彼女は1934年6月18日、オクラホマ州メダイナとウェインとの両郡に位置する都市リットマンに生まれている。もうお気づきだろう、彼女はモランとおなじオクラホマ州の出身で同学年。しかもモランと同様に、シンシナティ音楽院でピアノと声楽を学んでいるのだ。
ケリーとモランは、1954年の初頭、やはりオハイオ州モンゴメリー郡の郡庁所在地デイトンで出会った。この都市のとあるジャズ・クラブに出演していたふたりは、音楽の志向はもとより出自や年齢など、共通するところが多かったからか、すっかり意気投合した。ふたりはコンビを組んでクラブやテレビに出演するようになるが、同年の秋ごろに前述のザ・パット・モラン・クァルテットを結成した。ケリーのヴォーカルは、キュートな歌声とは裏腹にスウィンギーなセンスとコントローラブルなテクニックが際立っている。もちろんチャーミングなのだけれど、どこかクールなフィーリングが伝わってくる。その洗練された歌唱は、いま聴いてもモダンに響く。その魅力はファースト・リーダー作『ベヴァリー・ケリー・シングス』(1958年)で、たっぷり堪能できる。
オーディオ・フィデリティ・レコードからリリースされた、このケリーのアルバムでも、やはりモランのトリオがバックを勤めている。モランはここでもダイナミックなピアノ演奏を繰り広げており、トータル・サウンドをヴィヴィッドなものにしている。その爽快感といったら、一度聴いたらやみつきになること間違いなしだ。ぼくは、躊躇することなく名盤の太鼓判を捺す。また、このレコーディングでは、ピアノのモラン、ドラムスのホワイテッドといったケリーの僚友も参加しているが、ベースがドーリングからレジェンダリー・プレイヤー、スコット・ラファロに替わっている。ビル・エヴァンス・トリオのあのラファロだ。この天才ベーシストが1961年7月6日、自動車事故を起こして25歳という若さで急逝したというのは、あまりにも有名な出来事である。
勇ましいけれど可愛らしくもあり、そしてなによりも楽しい
ラファロといえば、だれもがインタープレイというコトバを思い浮かべるだろう。多くのジャズ・ファンが、エヴァンスのピアノと対等に即興でハイセンスなフレーズを紡ぎ出す彼に、陶然とする。ピアノが流麗にメロディを奏でると、ベースはハイノートでオブリガートする。さらにドラムスも巻き込んで、3台の楽器はときに呼応し、ときに交錯する。その相互作用から生まれた革新的なサウンドは、その後のピアノ・トリオのスタイルに大きな影響を与えた。なかでも、ラファロの斬新なアプローチは、ベースという楽器の概念を再定義するほどのものだった。しかしながら、彼の手腕をそれだけで評価するのはいかがなものだろう。太い音でよくバウンスしながらリズムとハーモニーのボトムをキープするときの存在感もまた、途轍もなく大きいのだ。ぜひ痛快極まりないウォーキング&ランニングも、お楽しみいただきたい。
さて、はなしを戻すが、このケリーのアルバムと同時にリリースされたのが『ディス・イズ・パット・モラン』だ。吹き込みは1957年の12月で、モラン、ラファロ、ホワイテッドというレコーディング・メンバーも同一。まったくけしからんことに、原盤の解説にはベーシストがジョン・ドーリングと記載されている。のちに「パット・モランと共演したオーディオ・フィデリティ盤の出来に私は満足している」というラファロ自身の談話により、彼の参加が明らかになった(ケリーのアルバムのほうにも彼のクレジットはない)。すると、さらに甚だよくないことに、本作は1978年にはじめて日本でリリースされるときに『ザ・レジェンダリー・スコット・ラファロ』というタイトルに変えられてしまった(ジャケットもラファロの写真に変更)。気持ちはわかるが、(4曲のソロ・ピアノもカットされて)ちょっとモランがかわいそう。
そうはいっても、本作ではついついラファロの小気味よいリズムと鮮明なトーンのベースに耳がいってしまうのも事実。まあ、彼のおかげで、モランのほうもそれに負けじと、いつにも増して力強いタッチでスウィングしまくっているのだけれど──。ぼくは、そんなところを大いに楽しんでいる。オープニングのミュージカル・ナンバー「メイキング・フーピー」では、モランによる余裕綽々で徐々に盛り上げていくファンキーなアドリブが素晴らしい。ラファロの強力なソロのあと、彼女のテンションはさらに高まる。デイヴ・ブルーベックの有名曲「イン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ 」では、モランは控えめに弾いておりラファロの速弾きに下駄をあずけた感がある。それが微笑ましい。
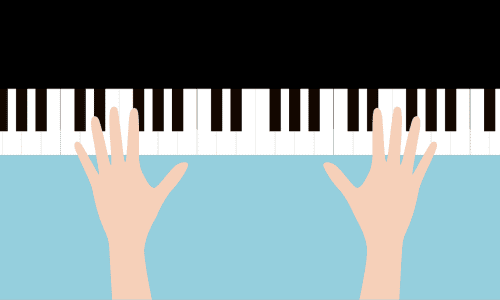
トロンボーン奏者フランク・ロソリーノの「オニリソー」は、テーマからアドリブまでラファロのひとり舞台。モランのソロもあるが、ここでは飽くまで神輿を担ぐばかり。ヴィクター・ヤングの映画主題曲「星影のステラ」とガーシュウィン兄弟の「サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー」はソロ・ピアノだが、どちらの曲も粛々とはじまり途中から熾烈な展開を見せる。モランのピアノにはクラシック音楽のマナーが垣間見られるが、そのテクニックはなかなかのもの。ハロルド・アーレンの名曲「降っても晴れても」では、モランのブロック・コードによるテーマと軽快なアドリブに胸がすく。4バース・チェンジでのホワイテッドのブラシ・ワークも軽妙だ。
ポピュラー・ピアノの教則本でおなじみのデヴィッド・カー・グローヴァーの曲「ブラックアイド・ピース」では、ソウルフルな三位一体の演奏が痛快。ラテン調のテーマ部、ピアノとベースのソロ、ピアノとドラムスの4バースと淀みなく進行する。アイナー・アーロン・スワンによる映画主題歌「ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン」は些か物憂げなソロ・ピアノだが、その高い技量には目を見張るものがある。おなじみのフレデリック・ロウのミュージカル・ナンバー「一晩中踊れたら」は、メトリック・モジュレーションを活かしたアレンジが面白い。ラファロの4ビートのランニングが強靭過ぎて、息を呑む。モランとプロデューサーで作曲家のシドニー・フレイとの共作「フェアウェル」は、ブルージーなソロ・ピアノ。後半のドラマティックな展開が感動を喚ぶ。
ジェローム・カーンによるミュージカル・ナンバー「イエスタデイズ」は、ピアノによるテンポ・ルバートから突然アップテンポになるが、この曲では意外な展開。トリオのグルーヴ感が極めて痛快。モランのピアノは普段より饒舌。ラファロのベースには巧緻を極めた鋭敏さが観られ、ホワイテッドのブラシも軽やかでキャッチーだ。やはりモランとフレイの共作「ブルース」は、タイトルどおりリラックスした雰囲気のブルース。トリオの地に足がついた演奏は、クロージングを飾るのに相応しい。本作では、確かにラファロに耳を傾ける機会が多いけれど、彼の存在感とおなじくらいモランの弾けるような活発さは魅力的。勇ましいけれど可愛らしくもあり、そしてなによりも楽しい。それが、彼女のピアノだ。モランは2018年、オクラホマ・ジャズ・ホール・オブ・フェイムに殿堂入りを果たした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント