ビル・チャーラップがヨーロッパの敏腕ミュージシャンたちと共演した知るひとぞ知る名盤『ギフト』
 Album : Stephen Keogh, Bill Charlap, Louis Stewart, Mark Hodgson / Gift (2000)
Album : Stephen Keogh, Bill Charlap, Louis Stewart, Mark Hodgson / Gift (2000)
Today’s Tune : The Song Is You
些細な所以から手にしたチャーラップの『アロング・ウィズ・ミー』
音楽の愛好者であれば誰でもそうだろうが、はじめて出会ったミュージシャンのプレイが気に入れば、そのひとの演奏をもっと聴きたくなるものだ。ぼくの場合、その音楽がジャズであるとき、そういう傾向が一段と強くなる。ジャズは即興性の高い音楽で、ミュージシャンのコンディションによって演奏のクオリティが変動する。だから、ただひとつのパフォーマンスに触れただけで、それが果たして至高のものなのかどうかを判断するのは極めて困難だ。もちろん、その演奏を一度聴いただけで素晴らしいと感じ、やにわにそれを高く評価することもある。しかしながら、もっと本領が発揮されたプレイが存在するのではないか?自分はそれを体験する機会を逸しているのではないか?そんな希望と不安が入り混じった思いから、そのアーティストを追いかけることになるのである。
それを平たくいえば、ハマると云う。まったく甲斐性のないことだが、所詮ぼくのような音楽オタクはそうやって飽くなき欲求を満たそうとしたり、ときには音の世界に自己のアイデンティティを見出したりしているのだ。まあそれはともかく、ぼくがそんなふうに夢中になったミュージシャンのひとりに、ピアニストのビル・チャーラップ(実際は“シャーラップ”と発音する)が挙げられる。1990年代のはじめから、ほぼリアルタイムで彼を追いかけた。チャーラップとの出会いは、幸いなことに彼の初リーダー・アルバム『アロング・ウィズ・ミー』(1993年)においてだった。なぜぼくが彼に興味をもったのかというと、これがあまりにも取るに足らない理由で申し訳ない気持ちになる。その些細な所以とは、このアルバムの冒頭に「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」が収録されていたということ。
たったそれだけで、未知のアーティストの作品を手にするのか?そう訊かれたら、案外そんなものと答えるしかない。ぼくは、この蠱惑的なまでに甘美なメロディとコード進行の曲が、大好きなのだ。作曲したのは、ポーランド出身でハリウッドで活躍した作曲家、ブロニスラウ・ケイパー。オリジナルは映画『大地は怒る』(1947年)の楽曲だが、1958年にマイルス・デイヴィスが採り上げたのを機に、すっかりジャズ・スタンダードと化した。なぜかビル・エヴァンス、ウィントン・ケリー、デューク・ピアソン、ウォルター・ビショップ・ジュニア、それにチック・コリア──と、ピアニストの吹き込みが目立つ。そんなこともあってこの名曲は、ぼくがジャズ・ピアニストのセンスやテクニックを評価するときの指標にもなっているのである。

ところでこのキアロスキューロ盤は、アンディ・ユーロー(b)、ロン・ヴィンセント(ds)とのトリオ、ショーン・スミス(b)とのデュオ、さらにチャーラップのソロをまとめたもの。収録曲は1991年と1993年に数回にわたって吹き込まれたもので、スタジオ録音のトラックはもとより、なかにはライヴ・レコーディングされた音源もある。そのわりには全体の印象に違和感はない。モダンでジェントルな響きに好感がもてる。その反面、ちょっと疑問に思ったことがある。無粋なことで恐縮だがメンバーの年齢を観てみると、ヴィンセントは最年長で40代だけれど、残りのメンバーはみな20代後半から30そこそこ。ミュージシャンは、比較的若い。それなのに、どこかオッサンくさい。なぜ──?実はそれが、チャーラップに対するぼくの第一印象だった。
ここでチャーラップを単にオッサンくさいピアニストと断定してしまったら、まったく早計である。いくらまだまだ若輩者だったとはいえ、ぼくもそこまで軽率ではない。彼は確たるピアノのテクニックを有しながら、超絶技巧を振りかざしたりはしない。幻想的な世界に浸り楽しみながら、美に耽り陶酔するようなところもない。ピアノ・トリオの芸術性を追求するが故に、テクニカルなパートを押し広げたり、意図的に三位一体の緊張感を作り出そうともしていない。つまりそのピアニズムに、驚天動地の斬新な趣向などはまったくないのだ。チャーラップがプレイするジャズは、ごくごくオーソドックスなモダン・ジャズ。いぶし銀の演奏技術を披露するには、20代の彼にはまだちょっと早すぎるような気がする。もちろん、彼自身もそうしよとはしていないのだけれど──。
決定的に恋に落ちた『オール・スルー・ザ・ナイト』
ビル・チャーラップは、1966年10月15日、ニューヨークに生まれたから、もう57歳になるわけだ。まえにも述べたように、ぼくはリアルタイムで彼の作品に触れてきたので、30年以上も彼のプレイを聴きつづけてきたことになる。結論から云うと、彼の音楽と向き合うときのスタンスは、ほとんど変わっていない。そして、そのピアニストとしての揺るぎない姿勢こそが、ぼくに彼を追いかけさせる要因だった。そう、ぼくのこころを鷲掴みにしたものをひとことでいえば「歌心」ということになる。彼の演奏は、常に歌っている。くわえて採り上げる楽曲を、とても大事にしている。曲のほうも彼に弾いてもらって喜んでいる──そんなふうに、ぼくには聴こえる。そして、彼が曲をかけがえのないもとして扱うものだから、選曲にも卓越した才能が発揮されるのである。
そこでもう一度『アロング・ウィズ・ミー』の収録曲を観てみると、前述の「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」とチャーリー・パーカーのバップ・ナンバー「ドナ・リー」以外は、比較的地味な曲が多いことに気づく。ところが、たとえ世間一般であまり知られていない曲でも、チャーラップの手にかかると名曲の誉れ高きスタンダーズと比べても遜色のない輝きを放つのである。これは、スゴイ才能だ。彼の音楽の本質を見極める能力と、それを実際に全身全霊で音にする表現力は、まさに天才の領域に達している。いかにして彼がそんな音楽性を身につけたのか?──そのヒントが、実は本盤のラストに収録されている「ジャズスピーク」にある。これは曲ではなく、文字どおりチャーラップ本人のおしゃべりによるセルフイントロダクションだ。
チャーラップはこのトークのなかで、自分のルーツを明かしている。母親は1960年代に活躍したポップ・シンガー、サンディ・スチュワート。1963年のスマッシュヒット「虹色の日記」が有名だ。父親はブロードウェイの作曲家、ムース・チャーラップ。ミュージカル『ピーター・パン』(1954年)が、その出世作。ムースはビルが7歳のときに他界。その後、スチュワートは、ビル・ワトラス&ザ・マンハッタン・ワイルドライフ・レフュージのメンバーとして知られるトランペッター、ジョージ・トリフォンと再婚(実際は再々婚)。ちなみに、ムースにはすでに前妻のエリザベスとの間に子どもがふたりいたのだが、ひとりはベーシストのトム・チャーラップだ。なんだか、ややこしいな。

この家族はたいへん仲がよかったのだろう、サンディ・スチュワート(vo)、ビル・チャーラップ(p, arr)、トム・チャーラップ(b)、ジョージ・トリフォン(tp, flh)、それに前述のロン・ヴィンセント(ds)といったメンバーで『サンディ・スチュワート&ファミリー』(1994年)というアルバムを吹き込んでいる。なお実の親子のみの共演作では、ビル・チャーラップ&サンディ・スチュワート名義の『ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ』(2005年)というデュオ・アルバムもある。さらに付言すると、1940年代から現代まで長きにわたり活動し、ストライド・ピアノからフリー・ジャズまで幅広くプレイするピアニスト兼作曲家、ディック・ハイマンはチャーラップの遠縁にあたる。
生まれたときからジャズが溢れた日常を過ごし、3歳からピアノをはじめ、しっかりクラシックのメソッドも学んだチャーラップ。幼少期から恵まれた環境でそれにともなう充実した教育を受けたのだから、彼が並外れた「歌心」を身につけているというのも、大いにうなずけるというもの。しかも、チャーラップ家において両親が彼に与えたのは、まず間違いなく“詰め込み教育”ではなく“ゆとり教育”だったのだろう。彼の繊細な音の織成によって、各々の楽曲が精彩を放つさまを実際に体験すると、そう思わざるを得ない。幸運なことに、ぼくの感性はそのように働いた。かくしてその後、ジョン・ゴードン(as)、マイケル・ムーア(b)、ジェイ・レオンハート(b)、ジーン・バートンシーニ(g)、ショーン・スミス(b)などのアルバムも含めて、ぼくはチャーラップを追いかけることになったのである。
ぼくがチャーラップに対して決定的に恋に落ちたのは、彼の4枚目のアルバム『オール・スルー・ザ・ナイト』において。選曲にリスナーに阿るようなところがまったくないのが、却って好感がもてる。たとえば、個人的にも大好きな曲「ピュア・イマジネーション」が入っている。英国の作曲家レスリー・ブリッカスによるミュージカル映画『夢のチョコレート工場』(1971年)の主題歌だ。こういうあまり脚光を浴びることのない名曲に、しっかり着目してくれるから、チャーラップのことが好きになってしまうのだ。トリオによる軽快で明るく澄んだ色鮮やかな曲がつづくなかで、この曲は唯一ソロでしっとり歌い上げられている。そして本作は、その後現在まで長きにわたりビル・チャーラップ・トリオのサイドメンを務めることになる、ピーター・ワシントン(b)、ケニー・ワシントン(ds)との最初の吹き込みでもあり、非常に重要な一枚と云える。
あまり知られていない良質な作品『ギフト』
日本でビル・チャーラップが広く知られるようになるきっかけを作ったのは、ヴィーナスレコードのプロデューサー原哲夫だ。1995年からチャーラップはフィル・ウッズ・クインテットに参加していたが、わざわざウッズのほうから原さんにチャーラップを強く推してきたという。結果『ス・ワンダフル』(1999年)という名盤が世に送り出された。ところが、トリオはほどなくブルーノートに移籍。第一弾の『星の降る夜』(2000年)は、日本でもリリースされ人気を博した。そんななわけで、原さんは自分のレーベルでこのトリオの作品を制作できなくなってしまったため、ジェイ・レオンハート(b)、ビル・スチュワート(ds)というチャーラップと過去に共演歴のあるふたりをサイドに迎え、よりスウィンギーなニューヨーク・トリオを編成した。ぼくたちは期せずして、二種類のタイプのトリオを楽しむ幸運に恵まれたのである。
その後、チャーラップはすっかり日本でも人気者となった。ぼく自身、そのふたつのトリオによる数々の名盤から、あらためてジャズを聴く楽しみを教わった。特にニューヨーク・トリオのアルバムは音が抜群によく、ぼくはオーディオファイルではないから、とりたてて優れた耳をもってはいないけれど、演奏に臨場感が増したことにとても幸せな気分になったもの。まあそんなことも含めて、多くのリスナーがその後のチャーラップ作品についてはご存知だろうから、いまさらぼくがこれ以上、鼻息を荒くして語る必要もないだろう。ということで、すっかりあとになってしまったが、チャーラップのあまり知られていない良質な作品を一枚だけご紹介しておこう。アイルランドのアッシュブラウン・プロダクションズという未知のレーベルからリリースされた『ギフト』(2000年)というアルバムがそれだ。
このアルバムは、チャーラップのほか、ルイス・スチュワート(g)、マーク・ホジソン(b)、スティーヴン・キーオ(ds)といった4人の名義でリリースされた。制作の発起人は、プロデューサーも努めたキーオと思われる。彼はアイルランド出身でスペインを拠点に活躍するドラマー。母国以外にもロンドンやニューヨークで音楽の教育を受けており、ジャズ・プレイヤーとしてはもとより、ワシントン・ナショナル交響楽団でパーカッショニストとして活躍したこともあるという。いっぽうベーシストのホジソンはイングランドのケンダル出身。もともとエレクトリック・ベースを弾いていたが、18歳のときにコントラバスに転向。ロンドンを拠点に活躍しているが、1998年からの4年間はスペインに移り活動していた。キーオとのつながりは、このときにできた。そして彼は、フュージョンやファンクもこなす実に現代的なプレイヤーである。
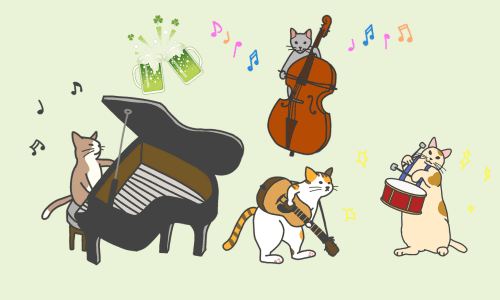
実はチャーラップ、ホジソン、キーオの3人は、本作の吹き込みのあと、ザ・ヨーロピアン・ジャズ・トリオというグループ名で『アートフリー』(2001年)というアルバムをリリースする。リリース先はスペインのアーバン・ビューティ・プロダクションズで、プロデュースはキーオとホジソン。2001年3月ロンドンの名門、ピザ・エクスプレス・ジャズ・クラブにおいてライヴ・レコーディングされた。こちらもなかなかの出来栄えなので、機会があったらぜひ聴いていただきたい。このトリオに、さらに2016年に他界したアイルランドのジャズ・プレイヤー、名手ルイス・スチュワートが加わり、クァルテットで演奏されたのが『ギフト』である。レコーディングはスチュワートの地元であるダブリンで、2000年5月に行われた。
アルバム冒頭のバリトン奏者ジェリー・マリガンの「ライン・フォー・ライオンズ」は、リラックスしたムードで4人のソロ&バースが展開されるビバップ。ポール・ホワイト楽団のレパートリー「星へのきざはし」は、スチュワートとチャーラップとの美しいデュオ。やはりマリガンの曲「カーテンズ」は、チャーラップが何度も吹き込んでいる彼の愛奏曲。演奏はピアノ・トリオのみで、上品なチャーラップのピアノと現代的なキーオのブラシの組み合わせが面白い。アルト奏者チャーリー・パーカーの「ヤードバード組曲」もトリオで演奏される。ここでのチャーラップは歌声が聴こえてしまうくらいスウィングしている。ホジソンの弾けるようなベースもいい。アルト奏者ジジ・グライスの「ブルー・ライツ」は、チャーラップ抜きのギター・トリオで演奏される。とにかくスチュワートのギターが、まるで凄みを利かせるかのようにブルージーだ。
ベーシストのボブ・ハガートの「ホワッツ・ニュー」は、クァルテットでの演奏。スチュワートとチャーラップのソロもいいが、ホジソンのしなやかなベース・ソロがひときわ光る。ジェローム・カーンのミュージカル・ナンバー「イエスタデイズ」では、スチュワートの哀愁を帯びたスウィンギーなギター・プレイのあとに、チャーラップの珍しくトリッキーなピアノ演奏がつづく。やはりカーンの「ザ・ソング・イズ・ユー」は、本作中いちばんの聴きどころ。4人が一体となって、ちょっと緊張感を孕んだ得もいわれぬ爽快感を生み出している。アップテンポのビートに乗ってギターとピアノが流れるような速弾きを展開。ソロ交換もある。と同時に、跳ねるようなブラシと軽快にランニングするベースも気持ちがいい。こういう演奏を、ゴキゲンというのだろう。こんなに上機嫌で、オッサンくさくないチャーラップは、ちょっとレアかも──。本作は現在入手するのがちょっと困難かもしれないが、見かけたらぜひ手にとるべき一枚だ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント