チャーリー・ヘイデンが絶賛しアイリーン・クラールが寵愛したピアニスト、アラン・ブロードベントの知的で趣味のいいアルバム『アウェイ・フロム・ユー』
 Album : Alan Broadbent Trio / Away From You (1989)
Album : Alan Broadbent Trio / Away From You (1989)
Today’s Tune : Sonny’s Step
音楽の聴きかたは“芋づる式”、求める手づるのほとんどはプレイヤー
タワーレコードの有名な企業スローガン“NO MUSIC, NO LIFE.”は、とてもこころに響くコトバ。それに共感するひとは多いと思う。かく云うぼくもまた、音楽のない人生なんて考えられないひと。そうはいっても、タワレコさんが根本の考えかたとして云い添えている、“音楽があることで気持ちや生活が豊かになる”というような高い見識は、ぼくにはまったくない。ぼくの場合は実に単純で、ただ音楽が好きなだけ。とにかく、聴くのも演るのも楽しい。そしてぼくの人生において、音楽を求めることに終わりはない。だから自室には、レコードとCDが溢れ返っている。そろそろまた整理しなければと思いつつも、なかなか手をつけられない。妻のカミナリが落ちるまえになんとかしなければと、まんじりともしないで夜を明かす今日このごろである。
そんな音楽バカのぼくがよく訊かれるのが、いかに自分の音楽ライブラリを充実させるかということ。そもそもぼくは音楽の聴きかたについては偏食家を自認するもので、あまり偉そうなことは云えない。強いて云えば、こころの琴線に触れたものを追いかける──ということに尽きる。ただ、いっときのことだが(20代前半のころ)、もとの職場の上司(ぼくのジャズの師匠)の半ば強引な推しで、名盤の誉れ高きジャズのレコードをやみくもに購入していた時期がある。好むと好まざるとにかかわらず、それらを一所懸命に聴き込んで、なんとか師匠についていこうとしていた。ジャズの愛好家としては、あのころのぼくはまだまだヒヨッコだった。それはそれで、勉強にもなり利益にもなり教訓にもなったのだけれど──。
ただ、そんなことをしていたのは3年ほどの期間で、ぼくの長い気ままな音楽生活においては異例のこと。では、ぼくの本来の音楽の聴きかたはといえば、ひとことで云うと“芋づる式”ということになる。一枚のレコードから、それに関連した作品を次々に手にとるというやりかただ。特にジャズの場合は、求める手づるのほとんどは、その作品に参加したプレイヤー(楽曲の場合もある)。リーダーを気に入れば、またそのアーティストのアルバムを手にとるのは、ごく当たりまえのこと。ところがサイドメンバーのほうまで気に入ってしまうことがあるから、ちょっとやっかいだ。リーダーであろうがサイドであろうが、フェイヴァリット・アーティストの演奏をできるだけ多く聴きたくなるのは、人情の常。自ずと購入するアルバムも多くなるのである。

そうやって新たに手に入れたレコードの参加メンバーのなかに、またまた気になるひとを見つけたりする。そんなときは、いささか慌てながらもこころが踊る。そしてにわかに、子供のころのことが思い出されたりもする。まだものごころがつくまえ、ぼくは幼稚園のそばの畑で芋ほりを体験した。新たなフェイヴァリット・アーティストに出くわしたときの感覚は、そのときに身をもって感じた驚きと喜びに似ている。芋づるをたどっていくと次々に芋が見つかるあの瞬間を、ぼくはいまだに忘れることができない。そんなささやかな幸せがやみつきになり、ぼくは次から次へと手づるを求める。そして知らず識らずのうちに、ぼくの所蔵するレコードやCDは、どんどん増えていく。音楽バカとは、そんなものなのである。
ところで、今回ご紹介するジャズ・ピアニスト、アラン・ブロードベントのことをはじめて知ったときが、まさにそんな感じだった。ブロードベントは1987年からチャーリー・ヘイデン・クァルテット・ウェストのメンバーとして活躍していたが、当時のぼくはまだ彼の演奏を聴いたことがなかった。いまにして思えば、その知的でありながらどこか優しさと温かみが溢れるピアニズムから、一部のツウなジャズ・ファンにはすでに知られた存在だったのかもしれない。ぼくが彼に注目したのは、1990年の桜の花もすっかり散り、うららかな日和がつづくころだったと記憶する。ぼくはそういうことを、音楽と結びつけてよく覚えているのだ。具体的には、アルゼンチンのジャズ・ピアニスト、セルジオ・ミハノヴィッチが作曲した「サムタイム・アゴー」という3拍子の曲において──。
この柔らかで麗しい「サムタイム・アゴー」は、もともとぼくの好きな曲だった。小学生のときに父に買ってもらったセルジオ・メンデス&ブラジル’66の『イエ・メ・レ』(1969年)というアルバムで、はじめて知った。ハーブ・アルパートの奥さま、ラニ・ホールが歌っている。セルメンのレパートリーにしては珍しく(デイヴ・グルーシンのオケが入っていないせいか)アレンジがシンプルな、ライト感覚に溢れたスタイリッシュなボサノヴァとなっている。その後、ビル・エヴァンスの『ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング』(1981年)を聴いて、ぼくはこの曲がさらに好きになった。ほかに女性ジャズ・シンガー、アイリーン・クラールも『クラール・スペース』(1977年)で採り上げている。偶然にもそのバックにおいて、ブロードベントの美しいバラード・プレイが聴ける。
リー・リトナーのアルバムで発見したお気に入りのピアニスト
クラークは46歳という若さでこの世を去った実力派のシンガーとしていまも語られる機会が多いが、当時のぼくは彼女のことをまったく知らなかった。もちろん、彼女の豊かな表現力が発揮された「サムタイム・アゴー」も、まだ聴いてはいない。したがって、ブロードベントが彼女のキャリアにおいて重要なアカンパニストだったと知るのもずっとあとのこと。では、ぼくが聴いたブロードベントがプレイした「サムタイム・アゴー」とはなにかというと、ギタリスト、リー・リトナーのリーダー作『ストールン・モーメンツ』(1990年)のラストに収録されているヴァージョンである。意外に思われる諸兄姉もおられるだろうが、従来フュージョン・シーンで活躍してきたリトナーが、このアルバムではギブソン L-5一本でモダン・ジャズに取り組んでいる。
思い起こせば1980年代の半ばくらいから、多くのフュージョン系のアーティストがジャズのルーツへ戻るような現象が見られるようになった。それ以前からチック・コリア、ハービー・ハンコック、パット・メセニー、ウェザー・リポート、ステップス(のちのステップス・アヘッド)などは、早々に4ビート・ジャズにアプローチしていた。ジャズへの回帰は、もはや類型化していたフュージョンという音楽に閉塞感を覚えた彼らが見出した、ひとつのブレイクスルーだったのかもしれない。その影響を受け、好景気だった日本の企画で、マンハッタン・ジャズ・クインテットやL.A. ジャズ・クインテットといったジャズ・バンドまで登場した。メンバーはフュージョン系のミュージシャンが中心だったが、主流派のモダン・コンボという看板が掲げられていた。
しかしながら正直なところ、ぼくにはそれらのサウンドがフェイクにしか聴こえなかった。プレイヤーたちはみな優れた技量の持ち主ばかりなのだが、モダン・ジャズとしてはどうもしっくりこない。ここでは挙げるのを控えるが、案外そういう作品は多い。ところがリトナーのアルバムには、変な気負いがまったく感じられなかったのである。極めてナチュラルに聴こえたし、いま聴いても楽しめる。まあ、彼としては久しぶりに、少年時代の自分にとってアイドルだった、ウェス・モンゴメリーみたいな演奏をやりたかっただけなのかもしれない。なにせデビューしてから間もない1975年にミシェル・ポルナレフのバックを務め、それからというもの、彼がハード・バップを演るような機会は皆無だったのだから──。

とはいえリトナーは、デイヴ・グルーシンの『ディスカヴァード・アゲイン!』(1976年)などで、ちょっとだけモンゴメリーばりのオクターヴ奏法を披露していたりもする。その点から裏を返せば、彼がこういう作品をものするに至ったのはごく自然な成り行きだったと云える。リトナーはリトナー。なにも変わっていないのだ。それはさておき、アーニー・ワッツ(ts)、ジョン・パティトゥッチ(b)、ハーヴィー・メイソン(ds)といったフュージョン・シーンに名だたるアーティストたちに混じって、このレコーディングに、ブロードベント(p, elp)が参加している。ぼくにとっては、セカンド・ギタリストとして2曲に参加したミッチ・ホルダー(acg)も含めて、ブロードベントだけが未知のミュージシャンだった。
もとはジャズ・ピアニスト兼コンポーザーだが、どちらかというと音楽ジャーナリストとして名高いレナード・フェザーが、このリトナーのアルバムを絶賛している。それに気をよくしたからか、リトナーはつづけて『ウェス・バウンド』(1993年)というアルバムを制作する。云うまでもなく、大先輩であるモンゴメリーへのトリビュート作品だ。そして、このアルバムにもブロードベントは参加している。ただこちらでは4ビートの曲もプレイされているが、トータル的にはモンゴメリーのCTIレーベルにおけるクロスオーヴァー作品のようなサウンドが際立つ。そんななか、ブロードベントのソロには極上のジャズ・オリエンテッドなムードが横溢している。本来この位置にはデイヴ・グルーシンがいるべきところだが、敢えてブロードベントを起用したリトナーの慧眼もなかなかのものである。
ということで、ブロードベントに興味をもったぼくは、すぐさま彼の当時の新譜を手に入れた。それは、ロサンゼルスのトレンド・レコードからリリースされた『アウェイ・フロム・ユー』(1989年)というアルバムで、幸いなことにすでに輸入盤が日本のCDショップで販売されていた。しかもピアノ・トリオという編成が、ぼくにとっては望むところ。そして、そのときはブロードベントのプロフィールについてなにも知らなかったぼくだが、このアルバムを聴くやいなや、その卓越したジャズ・ピアノのテクニックと新鮮なエクスプレッションから、彼にすっかり惚れ込んで夢中になった。これこそ、“芋づる式”から得た幸運である。ぼくはさらに芋のまわりの土を掘り、彼の2枚のリーダー作『エヴリシング・アイ・ラヴ』(1986年)と『アナザー・タイム』(1987年)も入手した。
肩肘の張らない、それでいて安定感のあるセッション
さらにリトナーとのレコーディングのあとにリリースされたブロードベントの『オーヴァー・ザ・フェンス』(1990年)は、ちょっと入手するのに手間取った。ニュージーランドのオード・レコードというマイナー・レーベルからリリースされていたことからか、日本のショップでは見つけることができなかった。結局インターネットを利用して、同レーベルで(トランペット奏者が加わった)クァルテットで吹き込まれた『ファイン・アンド・ダンディ』(1991年)と一緒に個人輸入した。思いがけなく新たなお気に入りができると、必ずといっていいほど面倒なことになるから不思議だ。なおブロードベントがニュージーランド出身のひとであると、ぼくが知ったのはこのときだった。
上記の『エヴリシング・アイ・ラヴ』『アナザー・タイム』『アウェイ・フロム・ユー』『オーヴァー・ザ・フェンス』さらにコンコード・レコードへの移籍後に吹き込まれた『パシフィック・スタンダード・タイム』(1995年)といった、ブロードベントの5枚のリーダー作はすべてピアノ・トリオ作品。そしてそれらのレコーディングは、おしなべて同一のメンバーによるバランス感覚に優れた演奏となっている。その顔ぶれは、アラン・ブロードベント(p)、パトリック・ヴァーン “パター” スミス(b)、フランク・ギブソン・ジュニア(ds)の三人。ちなみにパター・スミスはロサンゼルのベーシストで俳優でもある。映画『007/ダイヤモンドは永遠に』(1971年)の悪役、ミスター・キッドを演じているのは彼。いっぽうギブソンは、ニュージーランドのドラマーだ。
アラン・ブロードベントは、1947年4月23日、ニュージーランド北島北部の都市、オークランドに生まれた。7歳のときから母国でピアノと音楽理論を学び、15歳のときにはすでに地元のジャズ・クラブで演奏していたというから、驚くべき早熟ぶりを示していたわけだ。その後、1966年にダウン・ビート誌より奨学金を得て米国のバークリー音楽院(現在のバークリー音楽大学)に進み、作曲と編曲をトランペッターのハーブ・ポメロイに師事した。その間2年にわたり毎週、音楽院のあるマサチューセッツ州ボストン市からニューヨーク市まで通い、あの鬼才ピアニスト、レニー・トリスターノの個人レッスンを受けたという。1972にはロサンゼルスへ移住しているが、母国へ凱旋した際にもレコーディングを行なっている。
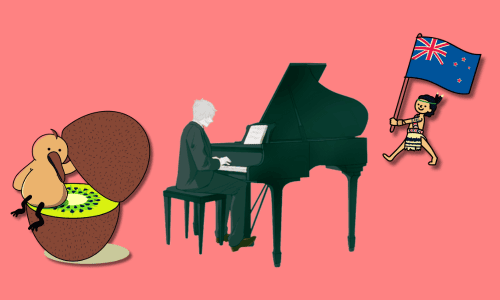
ブロードベントのデビュー・アルバムは、レナード・フェザーのプロデュースによりロサンゼルスのレーベル、グラナイト・ミュージックからリリースされた『パレット』(1979年)である。驚くなかれ、実はこのアルバムはビッグ・バンド作品。しかもそこでプレイされているのはスウィング・ジャズではなく、フュージョンに近いジャズ・ロック。どちらかといえば、コンポーザー、アレンジャー、あるいはミュージカル・ディレクターという、彼のもうひとつの側面の原点が浮き彫りになった作品だ。確かにブロードベントは後年、バーブラ・ストライサンド、ポール・マッカートニー、それにロッド・スチュワートといった、ジャズ以外のアーティストの作品で、アレンジャー&コンダクターとして才能を発揮するが、実はぼくはそちらにはあまり興味がもてなかった。
ブロードベントがもっとも光り輝くのは、やはりピアニストのときである(作曲も素晴らしい)。ソロもデュオも演っているけれど、なんといってもトリオがいい。ぼくは、そう信じてやまない。2000年代に澤野工房が入手困難だったニュージーランドでの吹き込み『ソング・オブ・ホーム』(1985年)と『ファーザー・ダウン・ザ・ロード』(1986年)を復刻。いずれもゴキゲンな佳作だ。キングレコードも負けじと『あなたと夜と音楽と』(2003年)『ラウンド・ミッドナイト』(2004年)といった、いかにも日本人の好みにあわせたロマンティックな作品を制作。ちょっとらしくないけれど、どちらも上品で美しい。これらのトリオ盤は、彼が日本で人気を博すのに大いに貢献したが、個人的にはまえに挙げた5枚のアルバムのほうが好みである。なかでも『アウェイ・フロム・ユー』に愛着を感じる。
まず、渋い選曲がいい。ブロードベントの自作曲が5曲、カヴァー4曲も作曲家ではなくプレイヤーの曲ばかり。そして、気の置けない仲間が集まって、肩肘の張らない、それでいて安定感のあるセッションを展開。演奏は軽やかなスウィング感に彩られていて、聴きごこちは爽快だ。たとえばオープナーの「ソニーズ・ステップ」は、その点で最高峰。ソニー・クラークに捧げたブロードベントのオリジナル。アップテンポのトリオの快活さが際立ったナンバー。こんなに爽やかなハード・バップは、なかなかない。それに反してウェイン・ショーターの「フットプリンツ」はテンポを落としてブルージーに演奏される。そのコントラストがお見事。ブロードベントが僚友チャーリー・ヘイデンに捧げた「ウェイティング・フォー・チャーリー」はモンク風のブルース。妻アリソンに送った耽美的なバラード「アウェイ・フロム・ユー」と、エスプリの効いたエヴァンス風の「ベター・デイズ」は、どちらもブロードベントの自作曲である。
やはり「ソナタ・フォー・スウィーピー」もブロードベントのオリジナル。ビリー・ストレイホーンの楽曲にインスパイアされた、ミディアムテンポのくつろいだムードと小洒落たトリオのプレイが心地いい。クリフォード・ブラウンの「ダフード」は1曲目と同様に爽やかなハード・バップに仕上がっている。ブロードベントのアドリブも小気味よくスウィングする。ギブソンとの8バースも軽妙だ。ジョン・コルトレーンの「ナイーマ」は静謐を湛えるエレガントなバラード。ピアノのアドリブがことのほか流麗。ソニー・ロリンズの「ペントアップ・ハウス」はブロードベントの流れるような即興演奏がもっとも際立ったナンバー。スミスのしなやかで淀みのないソロも快調。得もいわれぬ清々しさが残る。なおこの名トリオは、(編成はトリオではないが)オード盤『トゥゲザー・アゲイン』(2009年)で限定復活する。冒頭で「ソニーズ・ステップ」を再演。またもや、ぼくはジャズを聴く愉悦に浸ってしまう。ああ、なんということだろう、またぞろCDが増えてしまうではないか──。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント