スペイン出身にしてもっとも世界に勇名を馳せたジャズ・ピアニスト、テテ・モントリューの佳作 『トゥーティーズ・テンポ』
 Album : Tete Montoliu Trio / Tootie’s Tempo (1979)
Album : Tete Montoliu Trio / Tootie’s Tempo (1979)
Today’s Tune : Invitation
北欧最高峰のジャズ・レーベル、スティープルチェイス・レコード
最近その機会がめっきり減ったのだが、以前は気の置けない仲間がぼくの自宅に集まって、酒席を囲むことがままあった。考えてみれば、知人からお招きにあずかるようなことも、昨今少なくなった。歳をとると、みなそうなるものなのだろうか。確かに外で一席設けたほうが、お互いに気を遣う必要もないし準備やあと片付けの手間もないから、ラクはラクだ。まあそれはともかく、ぼくの場合、だれかが自宅に遊びに来ることになると、どんな音楽を振る舞えばいいのだろうとややもすると迷ってしまったりする。余計なこころ遣いなのかもしれないが、ぼくの家まで遊びに来るようなひとはたいてい酒好き、音楽好きだから、気を回さざるを得ないのである。やはり、客人には心地いい時間を過ごしてもらいたいからね──。
ところが、そんなことを長年やっていると、目からウロコも落ちるものなのである。リクエストがあるときはそれを優先するけれど、特に要望がない場合はオープナーとして特定のレコードをかけるようになった。それはただ単に過去に評判がよかったものなのだが、たいてい流行にかかわりなく安定した心地よさのあるものだ。それとこれまでの経験からすると、ほどよいインパクトも大事と思われる。ただし、薬も過ぎれば毒になるというけれど、衝撃の強いものは駄目。それとはなしにグルーヴ感がどんどん増していくようなものがいい。さらにつけ加えるならば、世にその名がとどろきわたった名盤は避けたい。音が鳴りはじめた途端、場にいまさら感が漂い、こちらも妙にきまりがわるいからだ。
そこでご登場願うのが、テテ・モントリュー(1933年3月28日 – 1997年8月24日)のピアノ・トリオである。ちょっと、意外だったかな?モントリューのレコードといっても、特にスティープルチェイス・レコードの作品が重宝する。理由は、音質だ。ルディ・ヴァン・ゲルダーのサウンド・エンジニアリングをこよなく愛するひとのなかには、厚みのない平坦な音に聴こえるという向きもあるかもしれない。そう云うぼくも好むと好まざるとにかかわらず、彼がデザインした音空間にすっかり慣れ親しんでしまっている。しかし、それはヴァン・ゲルダーの考案によって作り出された、オリジナリティに富んだフィクションの世界。マイクを楽器に密着するくらい接近させて配置し、拾った音を増幅させているのだ。
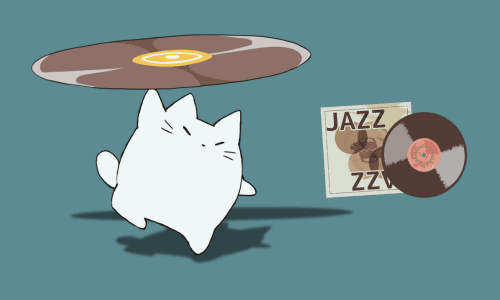
1950年代から1960年代にかけてのモダン・ジャズ・サウンドの代名詞とも云われる、いわゆるRVG録音は各楽器がぶっとい音に聴こえる迫力満点のもの。それはそれで、マジェスティックに響き実に素晴らしい。そんなヴァン・ゲルダーの独特のレコーディング技術によって生み出されたサウンドは、それこそぶっとい音でブルージーでハートフルなプレイを聴かせるテナー奏者、スタンリー・タレンタインをして、自分の生音よりもカッコイイ音と云わしめたほどだ。ところが、スティープルチェイスのサウンドといえば、特別な加工が施された様子はなく、ひたすら良質な臨場感にアプローチするばかりだ。それは云ってみれば、カジュアルにライヴ演奏を楽しむことができる、小規模なジャズ・クラブで聴くような音だ。
デンマークのコペンハーゲンに拠点を構えるスティープルチェイス・レコードは、北欧最高峰のジャズ・レーベル。ジャズの愛好家からは、1970年代のブルーノート・レコードとも観られている。まあ、それは、多くの名盤を世に送り出したこのレーベルの功績を踏まえれば、当然の捉えかたであり称賛するものにほかかならない。スティープルチェイスは、1972年に当時まだコペンハーゲン大学の学生だったニルス・ヴィンダによって設立された。コペンハーゲンにあるジャズ・クラブ、ジャズフース・モンマルトルは、アメリカの有名なジャズ・プレイヤーたちがたくさん訪れたことで有名だが、ヴィンダがそこでライヴ・レコーディングをはじめたことが、スティープルチェイス設立の契機となった。
思えば、1968年にコネチカット州で教職に就き、音楽活動のほうはすっかり休止していた、アルト奏者ジャッキー・マクリーンをふたたび表舞台に担ぎ上げたのも、スティープルチェイスだった。つまり、彼の久々のリーダー作『ライヴ・アット・モンマルトル』(1972年)は、いまやデンマークの老舗レーベルとなったスティープルチェイス・レコードの記念すべき第1作なのである。ある意味で、マクリーンのようにしばらく第一線から退いていたミュージシャンをカムバックさせるという点において、このレーベルは抜群の真価を発揮したとも云える。ケニー・ドリューやデューク・ジョーダンといったかつてのバップ・ピアニストの復活は単純に嬉しいことでもあったし、その作品の完成度の高さは驚嘆すべきものだった。
ところで、1987年からはクラシック音楽のレーベルもスタートさせたスティープルチェイスの作品群は、当初から音のよさには定評があった。その特徴的なサウンドといえば、前述のようにベクトルがリアルなサウンドへ向いており、決してパワフルではないけれど気軽さと寛いだ感じが魅力となっている。簡単に云うと、迫力は薄め、内容は濃いめ──である。こういう音は時代の趨勢でもあったわけで、1970年代のジャズ作品をあらためて聴いてみると、そんな方向性が打ち出されたものがままあることに気づかされる。ただ、確かにヴァン・ゲルダー・サウンドのように大きな圧力はないけれど、RVG録音よりピアノの音は美しく前面に出ているしベースの音程は明確になった。ドラムスはセパレートに響いている。
リスナーを圧倒するがごとき超絶技巧と、気分を高揚させるスウィング感
そんなスティープルチェイスにおけるテテ・モントリューの作品では、その右手から淀みなく紡ぎ出される音符の錦糸が、ごく自然な息遣いをともなった精彩を放っている。本来モントリューのピアニズムには、リスナーを圧倒するがごとき超絶技巧と、あわせて気分を高揚させるようなほどよいスウィング感が共存する。よく云われるのは、彼の演奏がアート・テイタムばりのテクニックと、ウィントン・ケリーのグルーヴ・フィーリングを兼ね備えた、強力なスタイルであるということ。ところが、モントリューが繰り広げるプレイが畏怖さえ感じさせるような凄まじいものであっても、なぜかスティープルチェイス盤で聴くと、溜め息の出るような躍動感を感じながらも得も云われぬ親近感を覚えるものだから、溜飲が下がるのである。
モントリューの代表作といえば、一般的にはスペインのディスコフォンというレーベルに吹き込まれた『リネの想い出』(1972年)がよく挙げられる。エリック・ピーター(b)、ジョー・ナイ(ds)といったサイドメンも、モントリューときわめて相性がいい。選曲のセンスもよく、しっとりとしたバラードから高速のワルツまで、彼の独特のピアニズムが縦横無尽に展開される。構成的にも静と動のコントラストが見事で、モントリューの緩急自在の演奏を堪能することができる。また、ドイツのSABA盤『ピアノ・フォー・ヌリア』(1968年)も、モントリューの妙技が際立つ名盤。旧西ドイツ出身のペーター・トルンク(b)、のちに主要メンバーとなるアルバート “トゥーティー” ヒース(ds)とのコンビネーションも絶妙だ。
上記の2枚がまごうことなき名作であるのに対し、スティープルチェイス盤のほうは、名作というよりも佳作と云ったほうがしっくり来るように思われる。でもぼくは、自宅にだれかが遊びに来ると、前述のような理由からスティープルチェイス盤のほうを、よくターンテーブルにのせるのである。そして音が鳴り出すと、せせこましいぼくの部屋に、たちまち小規模なジャズ・クラブのような空気が漂いはじめる。そんなモントリューのトリオによるスティープルチェイス作品といえば、(さきほど数えてみたら)自室のレコード棚に7枚ほどあったのだけれど、おもてなしの定番は『カタロニアン・ファイア』(1974年)『テテ!』(1975年)『テテ・ア・テテ』(1976年)『トゥーティーズ・テンポ』(1979年)といった4枚に集中する。
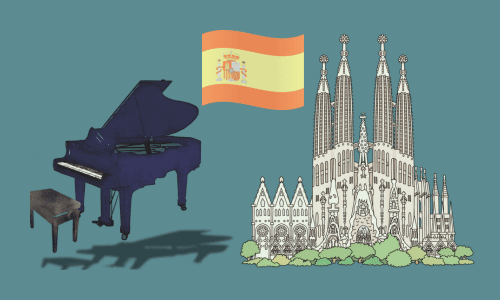
なぜこの4枚かというと、賢明なる読者の諸兄姉ならお気づきだろうが、それはトリオのメンバーが同一で、それがぼくのもっとも好きな組み合わせだから──。その3人をあらためてご紹介すると、テテ・モントリュー(p)、ニールス=ヘニング・エルステッド・ペデルセン(b)、アルバート “トゥーティー” ヒース(ds)となる。なおサイドのふたりはともに、ケニー・ドリューのスティープルチェイス時代の名盤『ダーク・ビューティ』(1974年)のレコーディング・メンバーだった。ペデルセンは、デンマークのシェラン島ロスキレ近郊のオステッド出身で、前述のジャズフース・モンマルトルのハウス・ベーシストを務めた。ベースラインはわりとオーソドックスだが、ソロにおけるメロディアスなフレージングとスムースなフィンガリングが美しい。
かたやヒースは、アメリカ、ペンシルヴェニア州フィラデルフィアの出身で、3兄弟で結成したバンド、ザ・ヒース・ブラザーズのドラマーとしても知られる。愛称の“トゥーティー”は、幼いころトゥッティ・フルッティ・アイスクリームが好きだったことから、お祖父ちゃんに名付けられたのだとか──。ジョン・コルトレーン(ts)の初リーダー作、プレスティッジ盤『コルトレーン』(1957年)のドラムスは、ヒースが叩いている。彼にとっては、初のレコーディングだった。彼のリズム・ワークはいつも勘どころを押さえていて、タイムキーピングも高精度。そんな手堅いドラミングゆえか、地味という向きもある。ぼくはこういう安定感のあるプレイヤーが好きなのだけれど、ヒースの演奏は年を追うごとに、ほどよく自由闊達になっていく。
地に足のついた秀逸を極めるバッキングとともに、まるでわが世の春を謳歌するかのごときプレイも垣間見せるサイドメンを得て、モントリューのピアノによるヴァーチュオシティはより饒舌になる。そんな3人の強みが見事に重なり合ったセッションに、リスナーであるぼくは、ただただ胸がすくばかりだ。あとになったが、リーダーであるモントリューの横顔にも触れておこう。彼はスペイン出身にして世界に勇名を馳せたジャズ・ピアニストとしては、数少ないひとりである。ただしモントリュー本人は、自分自身をスペイン人というよりはカタロニア人であると、きっぱりと述べている。カタロニア(カタルーニャ)はスペイン北東部の地中海岸に位置する、独自の歴史と伝統、そして言語をもつ自治州である。
そういえば、モントリューのオリジナル曲に「カタラン組曲」という、カタロニアに伝わる5つの民謡をつなぎ合わせた複合的ジャズ・ナンバーがあった。まえに挙げた『テテ・ア・テテ』のラストを飾る20分にも及ぶ大作だ。また彼は、カタロニアのシンガーソングライター、ジョアン・マヌエル・セラートの楽曲を採り上げたりもしている。セラートは1969年に、あのポール・モーリアのカヴァーで有名な「エーゲ海の真珠」を歌ってヒットさせたひと。モントリューは、その大半をセラートの楽曲でまとめたソロ・ピアノ集を吹き込んでいる。タイムレス・レコードからリリースされた『カタロニアン・フォークソングス』(1978年)というアルバムがそれである。いずれにしても、モントリューのカタロニアに対する愛着は深い。
スティープルチェイスにおけるもっともカジュアルなモントリュー作品
テテ・モントリューは、生まれながらの視覚障害者だった。父親はオーボエ奏者だったが、母親の勧めで視覚障害教育を行うピアノ教室において、1歳からおよそ10年間クラシック・ピアノのレッスンを受けた。13歳から20歳までは、バルセロナのリセウ高等音楽院において、クラシック音楽やスペイン音楽の教育を受けながらも、インプロヴィゼーションのカリキュラムを履修。ジャズ・ピアノのメソッドとテクニックを学んだ。見えないが故に研ぎ澄まされた感覚をもつモントリュー、この時期に彼はジャズ・プレイヤーとして、晴眼者のそれを遥かに超えるような、繊細な表現力と気迫のこもった演奏技術を身につけた。それからときを置かず、モントリューはバルセロナのパブリック・ハウスを皮切りに、プロ・ミュージシャンとして活動するようになる。
それからモントリューは1950年代の初頭、一時バルセロナに滞在していたテナー奏者、ドン・バイアスと2年間一緒にプレイする。1956年にはヴィブラフォニスト、ライオネル・ハンプトンと共演、スペインの首都マドリードにおいてレコーディングを果たす。アルバム・クレジットにその名は記載されていないが、ライオネル・ハンプトン楽団の『ジャズ・フラメンコ』(1957年)というレコードでピアノを弾いているのは、まぎれもなくモントリューだ。1958年には、ダグ・ワトキンス(b)、アート・テイラー(ds)を従えて、カンヌ・ジャズ・フェスティヴァルにも出演した。モントリューにとっては、記念すべき初リーダー作『テテ・モントリュー・イ・ス・クアルテート – ヴォルーメン1』(1958年)がリリースされた年のことだった。
1960年代のモントリューといえば、スペイン、ファルセス出身のテナー奏者、ペドロ・イトゥラルデや、R&Bとジャズとを往来するアメリカのシンガーソングライター、ドナ・ハイタワーらとともに、マドリードのウィスキー・ジャズ・クラブに頻繁に出演していたという。また1963年、モントリューはドイツの首都ベルリンのジャズ・クラブ、ブルーノートでも演奏を披露している。注目すべきは、1967年の4月の出来事。モントリューは今度はアメリカに渡り、ニューヨークのジャズ・クラブ、ヴィレッジ・ゲイトに出演した。サイドを務めたのは、リチャード・デイヴィス(b)とエルヴィン・ジョーンズ(ds)だった。ふたりとも革新的なプレイヤーだけに、実に興味深い。
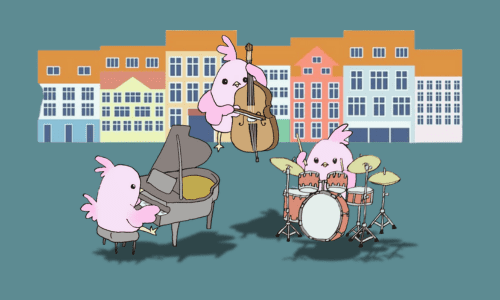
モントリューはニューヨークにおいて10週間のクラブ出演を果たしたが、そのうち上記のトリオによる2回のライヴは、インパルス!レコードによってアルバム・リリースが目論まれ、実況録音されたという。しかしながら、その音源はいまだ日の目を見ないままである。単なるウワサばなしでなければ、埋もれさせておくにはあまりにも惜しい、貴重なライヴ・レコーディングのひとつと云える。それはともかく、いよいよ1970年代──モントリューのスティープルチェイス時代だ。彼は同時期にドイツの名門レーベル、エンヤ・レコードや、オランダに拠点を構えるジャズ・レーベル、タイムレス・レコードにも多くの吹き込みを残しているけれど、ぼくにとって親しみやすいのはなんといってもスティープルチェイス盤だ。
なかでもさきに挙げた4枚のトリオ作品は、ぼくが勝手に思うに、どれも客人をおもてなしするのに相応しい。特にどの盤も、1曲目がいい。ささやかな宴の幕開けに、もってこいなのだ。アルバムの発表順に列挙すると、ブロッサム・ディアリーの「スウィート・ジョージ・フェイム」ジョン・コルトレーンの「ジャイアント・ステップス」ボブ・ハガートの「ホワッツ・ニュー」ブロニスラウ・ケイパーの「インヴィテーション」となる。ほんとうに、いい曲ばかり演ってくれたものだ。実はぼくが最初に手にしたモントリューのレコードは『テテ・ア・テテ』で、冒頭の「ホワッツ・ニュー」を聴いた瞬間に、彼のファンになってしまった。このアルバムと『テテ!』が一般的には人気があるようだが、もっともカジュアルなのは『トゥーティーズ・テンポ』だろう。
本作を愛聴する理由は、単純に「インヴィテーション」がぼくのフェイヴァリット・チューンだから。まったくもともこもないことだが、この曲が収録されていると未知の作品でも、ついつい手にとってしまう。余談だが、トランペット奏者のメイナード・ファーガソンが『プライマル・スクリーム』(1976年)というアルバムで、この曲をクロスオーヴァーな装いでプレイしている。ニヒリスティックな感じがして、失笑を禁じ得ない。ついつい、眉間にシワを寄せた天知茂の顔を思い浮かべてしまう。やはりこの曲は、モダン・ジャズが似合っている。その点、モントリューの演奏は抜群にセンスがいい。サビからはじまるところも、ハートをわしづかみにされる。こういうなにげなくスタイリッシュなスタートの仕方が、いかにもジャズ・クラブでの演奏をイメージさせる。
とにかくこの「インヴィテーション」では、終始モントリューのアドリブが、たたみかけるようにファンタスティックなフレーズを繰り出してくる。それが、なんとも痛快だ。ペデルセンとヒースとによるバッキングの手堅い疾走感も心地よく、思わず身体を揺らしてしまう。ロジャー・ラミレスとジミー・シャーマンの「ラヴァー・マン」は、ドラマティックなソロ・ピアノから風格のあるピアノとベースとのダイアローグへと進行する。モントリューによる、ほどよくブルージーなエスプリの効いた表現が、楽しい。ジョン・コルトレーンの「サム・アザー・ブルース」は、オーソドックスなビバップ。たゆみないスウィング感に、寛ぐばかり。ヒースのバウンスする感じも快適。このあとCDでは、スライド・ハンプトンの「タイム・フォー・ラヴ」が、ボサノヴァ・テイストで演奏される。
後半のトップは、J. J. ジョンソンの「ラメント」だが、モントリューの神業的なピアニズムが全開する。美しいバラード演奏のバックで、ヒースがさりげなく16ビートを打ち出しているのも新鮮。4ビートになってからは、とどまるところを知らないモントリューが繰り出す音符の羅列に、圧倒されるばかりだ。モントリューの「トゥーティーズ・テンポ」では、アップテンポに乗ってトリオは情熱的になり、一体感をより高めている。ラストを飾るジミー・ヴァン・ヒューゼンの「ダーン・ザット・ドリーム」では、ルバートからインテンポまでモントリューの華麗な技巧と表現力が感動を呼ぶ。最後までじっくり、ご堪能あれ。と、あらためて完全無欠のモントリューを感じさせられるが、気軽に悠々と音楽を楽しむことができる1枚でもある。そこがミソだ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント