ブルーノート随一のレイドバックでエンジョイアブルなジャズ

Album : The Three Sounds / Moods (1960)
Today’s Tune : Tammy’s Breeze
♫デアゴスティーニ
年明け早々(2023年1月)に、テレビCMでおなじみのデアゴスティーニさんから『隔週刊 ブルーノート・ベスト・ジャズコレクション』というパートワークが発刊された。パートワークというのは、ひとつのテーマやジャンルに特化した定期刊行物で、毎号そろえていくと最後には百科全書みたいになることから、分冊百科とも呼ばれるもののことだ(念のため──)。名門ブルーノート・レコードに残された名演の数々を、高音質CDで堪能できるというこのパートワーク──雑誌扱いだから、本屋さんで販売されている。仕事柄ぼくは、出版物の情報にはちょっと詳しいのだけれど、これがよく売れていると聞く。
毎号、ひとりのアーティストにフォーカスされ、その半生と活躍の歴史が紐解かれていく──。冊子にはアーティストのバイオグラフィ、コラム、貴重な写真などが満載──。そして、付属のSHM-CDはデアゴスティーニさんのオリジナルのセレクションで、名演奏のなかから選りすぐりの楽曲5~7曲が収録されるという仕様──。しかも、創刊号は特別価格の490円(税込)──というのだから、完売店続出!──と聞いても、その言説は疑いようもない。そして、このシリーズは90号まで刊行される予定とのことなので、ぜんぶ購入したら、きっとブルーノート博士になれるのだろうね。
それにしても、(敢えてそう云うけれど)この目まいがするほど蠱惑的なコレクション──どんなひとが、買い求めるのかしらん?ここからは、まったくぼくの想像──。青春時代、ジャズ喫茶に入りびたっていたのだけれど、レコードはぜんぶ処分しちゃったな──という熟年層のかた?あるいは、吹奏楽部でサックスを吹いているのだけれど、コミックの『BLUE GIANT』を読んでジャズに興味をもった──という純情な高校生?いずれにしても、いまだに古いレコードしかもっていない(買い直せない)貧乏人のぼく(カッコわるー!)とは違って、みんなスマートでインテリジェントなひとたちなのだろうな──。
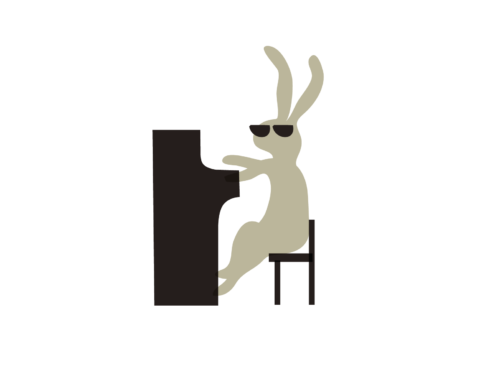
まあ、あまりネタミやソネミをクドクドしたためるのは見っともないので(さらにカッコわるー!)、これくらいにするけれど、正直なところ実はちょっと嬉しい気持ちが込み上げてきた──。というのも、ごくふつうの生活様式やひとの営みにおいて、ジャズばかり聴いているぼくのようなオッサンは、圧倒的なマイノリティと云える。でも、ジャズに関心があるかたが、まだまだいらっしゃると知ったら、思わず笑みがこぼれてしまった──。つまり、むかし流行った『人間まるわかりの動物占い』では、キャラクターが孤高のオオカミのぼくも、ほんとうは一方通行の同族意識を抱いて嬉々とする、ただの寂しがりやなのである(バカだねぇ)。
さあさあ、とるに足らないオトコのたわごとは無視して、大いにブルーノート・サウンドを楽しもう!なんたって──モダン・ジャズの黄金時代といえば、ブルーノート。ハード・バップといえば、やはりブルーノート。いい音といえば、ルディ・ヴァン・ゲルダー。キャッチーなジャケット・デザインといえば、リード・マイルス。社長はライオン、写真はウルフ(ん、動物園か?)──とにもかくにも、ブルーノート・レコードは、どこを切ってもその切り口にジャズのトップランナーの顔が現れる、いわば、ジャズ界の金太郎飴なのであるから──(もう、いい加減にしなさい)。
ぼくにとってのブルーノート・アーティスト・ベスト5
そこでだ──ぼくにとっての、ブルーノート・アーティスト・ベスト5を、ちょっと考えてみた。このレーベル、管楽器のスターが多いという印象が強いのだけれど、自分はピアノを弾くからピアニストに絞り込んだ。比類なき名盤を数多く残したという意味では、ホレス・シルヴァーとハービー・ハンコックは、文句なく入るだろう。レーベルへの貢献度からすると、ソニー・クラークとデューク・ピアソンも、また然り。では残りのひとりはというと、これがちょっと逡巡してしまうのだ──。
ケニー・ドリューとウィントン・ケリーは、とても好きなのだけれど、アルバムが少ない。マッコイ・タイナーは、インパルス!レコードの作品のほうが好み。チック・コリアやセシル・テイラーも、ブルーノートのひとではない。バド・パウエルの場合、芸術的で神がかった彼は、もうここにはいないし──。あと、アルバム単位だったら、ウォルター・デイヴィスJr.、ユタ・ヒップ、ハービー・ニコルズなどの作品も、けっこう好きだなのだけれど──。
こうして改めてブルーノートにおけるピアニストのリーダー作を思い浮かべていくと、案外たくさんあるものだ。それでも、ホーン奏者の作品のほうは、パッとイメージがひらめくのに対して、ピアニストのそれとなると、すぐにチョイスするのはなかなか困難だ。そんなわけで、最後のひとりはやはりホレス・パーランあたりに落ち着くのかな?彼のピアノ・スタイルには、目からウロコが落ちるような気持ちにさせられるし──。それは、コンプレックスを克服して可能にしたというか、制限があったからこそ生み出すことができた、彼ならではの新しい奏法で、ぼくも大好きなのだ。
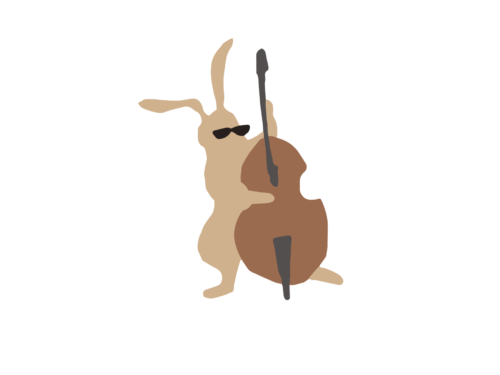
うん?でもちょっと待てよ、ぼくは大事なひとを忘れているぞ!いや、正確には個人ではなくて、グループ──それが、スリー・サウンズだ。というか、もしかすると、ぼくにとってブルーノートといえば、スリー・サウンズと、云えるかもしれない。しかも逆に、ある意味で真剣にモダン・ジャズに取り組んだブルーノートからは、どちらかといえば硬派なレーベルという印象を受けるのだけれど、そのなかにおいてこのグループは、ひときわ異彩を放っているのだから、ホント愉快だ。
このジーン・ハリス(p)、アンディ・シンプキンス(b)、ビル・ダウディ(ds)からなるピアノ・トリオ、スリー・サウンズがプレイするのは、端的に云うと、ブルーノート随一のレイドバックでエンジョイアブルなジャズということになる。たぶん、これほど鷹揚で楽しげにスウィングするジャズを聴かせるアーティストは、ブルーノートにおいて彼らのほかにはいないだろうし、ブルーノート以外の作品でも、すぐには思いつかないな。さらに云えば、このグループには、ヴァーヴ、マーキュリー、ライムライトといったレーベルにも吹き込みがあるのだけれど、どれもブルーノートでの諸作には到底およばない。それらの点を踏まえると、スリー・サウンズは異形でありながら、ブルーノートならではの存在と云えるのである。
ブルーノートきっての愉快な音楽隊
スリー・サウンズの前身である、フォア・サウンズ(当初はテナー奏者がいた)は1956年に結成されたが、早々にピアノ・トリオとして定着し、1958年、ニューヨークのオフビート・クラブに出演中、来店していたアルフレッド・ライオンに見初められた。なんと、その場でブルーノートとの契約が成立。その数日後に、早くもデビュー・アルバム『イントロデューシング・ザ・スリー・サウンズ』が吹き込まれた。ちなみに、このアルバムはブルーノート1500番台シリーズの最後を飾るもので、このトリオをライオンに薦めたのは、ホレス・シルヴァーだったという。さらに付け加えると、びっくりするくらいジャズ・ファンクなアルバム『ジーン・ハリス・オブ・ザ・スリー・サウンズ』(1972年)は、ブルーノート4000番台の最後の作品。なんだか、運命めいたものが感じられる。
ともあれかくあれ、スリー・サウンズはブルーノートきっての愉快な音楽隊。ジャズの楽しいエッセンスをたっぷり詰め込んだ、くつろいだ演奏が魅力的だ。なお、ピア二ストのジーン・ハリスも、それとそっくりそのままの表現が当てはまるプレイヤーで、まったく泥臭さがなくて、決して弾きまくるような演奏もしない。ブロック・コードの使いかたも、レッド・ガーランドのように際立ってはいない。そのぶん、シンプキンス、ダウディとのコンビネーションは、常に均衡が保たれている。ひょっとすると、三人がグループ名をジーン・ハリス・トリオとはせず、スリー・サウンズとしたのは、そんな音楽を志向したからかもしれない。結果的に彼らは、多くのジャズ・ファンからもてはやされることとなった。
ところで、スリー・サウンズのアルバムのなかで、ぼくにとって、特に思い入れがあるのは前述のデビュー作だ。個人的なおはなしで恐縮なのだが、高校時代に生徒会長のNくんと制作したラジオ番組(せいぜい校内放送レベルだけれどね──)で、このレコードに収録されている「テンダリー」をテーマ曲として使っていた。チャチャチャのリズムが心地よくて、番組の気さくな雰囲気に、ピッタリだった。ただ、このアルバムが際立った出来ばえなのかというと、ちょっと違う。ブルーノートに残された彼らの作品群は、佳作揃い。ハズレもない。つまり、あまり大差がないのだ。というわけで、どれを聴くかは──たとえば、好きなスタンダード・ナンバーが入っている──というような理由で選ばれてみては、いかがだろう。

おそらく、もっともポピュラーなのは、やはり(ルー・ドナルドソンとの共演盤を除くと)4枚目の『ムーズ』だろう。人気の理由の半分は、麗しく艶やかな女性のお顔があしらわれたジャケットの恩恵。この婦人、ラジオ番組のDJで、のちにライオン社長の二番目の奥さまになるルース・メイソンというひと。ソニー・クラークの『クール・ストラッティン』(1958年)のジャケットに写っている美脚の主も、彼女。そして残りの半分は、もちろん純粋に音楽的な内容のよさによるもの。特に楽曲が、有名なスタンダード・ナンバーばかりなので、多くのひとにとって、親しみやすいのだと思う。しかも、どの曲もエスプリの効いた味付けがなされているのが、とても楽しい。
すっかりボサノヴァに変身した、コール・ポーター作の「ラヴ・フォー・セール」は、後半ディジー・ガレスピーの「マンテカ」が引用されていたりする。エリントン先生の「昔はよかったね」とベイシー先生の「リル・ダーリン」(作曲はニール・へフティ)は、なぜか超スローでおもいっきりブルージーなのだけれど、決してアーシーではない。むしろ、軽やかささえ感じられる。ブロニスラウ・ケイパーの映画音楽「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」は、数多の演奏が存在するが、これほどリラックスしたムードのヴァージョンはほかにないかも──。そのほか、レッド・ガーランド風の「ルース・ウォーク」ハンドクラップまで飛び出す「アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト」小粋なブルース「サンデュ」と、トリオは実に軽妙洒脱なアンサンブルを披露──。
唯一のオリジナル・ナンバー「タミーズ・ブリーズ」は、ジーンのペンによるものだが、実はぼくはこの曲がいちばん好き。このなんともチルアウトした雰囲気が、たまらないのだ。メジャー・キーとマイナー・キーのローテーションで作り出される曲想は、ちょっと異国情緒を漂わせている。そんな音世界に身を委ねていると、こころは都会の喧騒を離れて、とても穏やかになっていく──そんな気さえするのだ。こういうムードこそ、スリー・サウンズの音楽ならではのもの。それに浸っていると、ぼくにとって、ブルーノートといえば、スリー・サウンズなのだな──と、確信させられる。そして──窮屈な姿勢はちょっとやめて、おもいっきり伸びをして、ついでにこころのほうもリブートしてしまう──そんな情調をもったジャズもある。これを楽しまない手はない!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント