オランダの逸材ロブ・ヴァン・バヴェルの若き日の吹き込み──メインストリームの伝統が受け継がれた極上の味わいをもつ『ロブ・ヴァン・バヴェル・トリオ』
 Album : Rob Van Bavel / Rob Van Bavel Trio (1989)
Album : Rob Van Bavel / Rob Van Bavel Trio (1989)
Today’s Tune : Waltz On B-Street
ふたたび脚光を浴びているピアニスト──最初は澤野工房が発掘
ロブ・ヴァン・バヴェルが、この数年ふたたび脚光を浴びているようだ。そのピアノ・プレイといえば、けっこう躍動感に溢れていながら、まったくといっていいほど外連味がない。むしろタッチはいい意味で軽い。しかも随所にほどよいリリシズムの片鱗をうかがわせるような、上品な美しさがある。なんといっても、小難しさのない鷹揚な演奏に好感がもてる。とにかく気軽に楽しめるところが、ぼくは大好きだ。そんな彼が、2021年に急逝したチック・コリアをトリビュートした『500マイルズ・ハイ〜チック・コリアに捧ぐ』(2022年)や、やはり彼の敬愛するホレス・シルヴァーのソング・ブック『ホレス・シルヴァーに捧ぐ』(2022年)を、立てつづけにリリースして話題になった。なおこの2枚は、おなじトリオにより同日(2021年10月19日)に吹き込まれた。コリアが他界したおよそ8ヶ月後のことである。
さらにヴァン・バヴェルといえば『タイム・フォー・バラッズ〜ザ・マーネ・セッションズ』(2021年)と『タイム・フォー・バラッズ〜ザ・スタジオ・セッションズ』(2022年)といった、2枚のトリオによる極上のバラード集が高く評価された。歌ごころに溢れた彼のピアノ演奏は、多くのリスナーのハートを鷲掴みにしたことだろう。繰り返すが、ヴァン・バヴェルのピアニズムに、面倒な理屈っぽさはまったくない。ジャズははじめて──というかたでも、少しも遠慮はいらない。そんな気やすさが、ぼくにはとても魅力的に感じられる。彼は、センスとテクニックにおいても申し分のない力量をもっているが、まだまだ知るひとぞ知る存在。だからこうして、ちょうど創作意欲を高めている彼にスポットが当てられるのは、ほんとうに嬉しいことである。
ぼくはたったいま、ヴァン・バヴェルがふたたび脚光を浴びていると云ったが、彼が最初に日本で注目されたのは、トリオ編成による初リーダー・アルバム『ジャスト・フォー・ユー』(1988年)が国内で紹介されたとき。日本のリスナーが知る由もないオランダのサークル・プロダクションというマイナー・レーベルからリリースされていたこのレコードが、世界ではじめてCD化されたのは2000年のこと。大阪市浪速区の履物屋であり、ジャズ・レーベルである澤野工房によってリリースされた。そのころの澤野工房といえば、旧ソ連、レニングラード出身のピアニスト、ウラジミール・シャフラノフのトリオ盤『ムーヴィン・ヴォーヴァ!』(2000年)が人気を博していたが、ほとんどの大手CDショップにはすでに澤野工房の特設コーナーが設けられており、ヴァン・バヴェルのアルバムも一緒に陳列されていた。

代表者の澤野由明は、もともと新世界にある履物屋の4代目店主だったが、趣味が高じて日本のジャズ・アルバムをヨーロッパに輸出したり、逆にヨーロッパのジャズ作品を輸入販売したりしていた。結局、澤野さんはCD制作にも乗り出しレーベルとしての澤野工房を立ち上げたわけだが、その影響は日本に止まらず世界中に波及した。なんといっても、知られざるアーティストの発掘におけるその功績は誠に大なるものがる。澤野工房のWebサイトには「聴いて心地よかったらええやんか」という考えかたが、澤野さんの原点とある。そんなシンプルな音楽に対する愛情表現は、高品質な作品を次々にリリースする氏のヴァイタリティにつながるものがある。とにもかくにも、ぼくがヴァン・バヴェルを愛聴するようになるキッカケを作ってくれたのは澤野工房である。
あとになったが、ロブ・ヴァン・バヴェルはオランダのジャズ・ピアニスト、同時にコンポーザーでもありアレンジャーでもある。ビバップやモダン・ジャズはもちろんのこと、フュージョンやクラシックまでこなす。彼は1965年1月16日、オランダ南部のブレダに生まれた。ピアノの教師である父とギターとオルガンの教師である母をもつ。両親は楽器店も経営しており、ヴァン・バヴェルの周囲には、生まれたときから音楽が溢れかえっていた。そんな環境のもと、彼は3歳からクラリネットやハーモニカを吹き、7歳からはピアノのレッスンを受けるようになる。はじめはクラシックのピアニストを目指していたが、中学時代にジャズに開眼。ディキシーランド・ジャズのバンドでも演奏したという。その後、ロッテルダム音楽院で学び、1987年に同院を主席で卒業している。なお息子のセバスチャンもピアニストで、ジャズに現代音楽の要素を採り入れたトリオで活動中。
ヴァン・バヴェルは、新人ジャズ・プレイヤーの登竜門として知られる、セロニアス・モンク国際ジャズ・コンペティションの記念すべき第1回のピアノ・コンペで第2位を獲得している。彼が音楽院を卒業した、1987年のことである。審査はローランド・ハナ、バリー・ハリス、ハンク・ジョーンズ、ロジャー・ケラウェイが務めたという。その顔ぶれのスゴさも然ることながら、彼らからその才能と実力を認められたヴァン・バヴェルも伊達ではない。なんといったって、アルバム・デビューすら果たしていない20代前半のオランダの若者が、400人以上の応募者がいるアメリカのジャズ・コンペで上位に入賞したのだから、これを快挙と云わずしてなんと云おう。ちなみに、このとき第1位を獲得したのは、当時すでにウィントン・マルサリス(tp)のグループで活躍していたマーカス・ロバーツである。
澤野工房の発掘から国内盤がリリースされるまでのおよそ5年間
この賞以外にも同年にヴァン・バヴェルは、オランダのもっとも主要なジャズ賞であるヴェッセル・イルケン賞を受賞。翌年の1988年には、ドイツの有名なジャズ・フェスティヴァル、レーヴァークーゼナー・ジャズターゲにおいて、ヨーロピアン・ヤング・ジャズ・アーティスト賞を獲得。さらに1990年には、オランダのグラミー賞とも云われるエジソン賞を受賞している。ヨーロッパだけでなくジャズの本場であるアメリカにおいても、ひとかどのジャズ・ピアニストとしてのオーソライズを得たヴァン・バヴェルが、なぜ日本では10年以上も放って置かれたのか、ぼくは不思議でならない。当時のわが国のレコード産業においては、まだオランダとの国交が開かれていなかったということか?いずれにしても、前述の澤野工房が『ジャスト・フォー・ユー』をCD化するまで、彼の存在を知る日本のリスナーはほとんどいなかっただろう。
確かにヴァン・バヴェルのプレイには、メインストリームの伝統が受け継がれているのが顕著に見て取れる。残念なことに、一部のジャズ・ファンの間では、そういうオーソドックスな演奏形態には食指が動かされない──という現象がときおり発生する。どうしても驚天動地の斬新な趣向が凝らされたプレイのほうに視線が向いてしまうからだ。もちろん、それはそれで素晴らしい。ただぼくの場合、進取の気性に富んだアーティストも大歓迎だけれど、どちらかというと伝統的で穏健な表現方法で極上の演奏を聴かせてくれるプレイヤーのほうに、こころ惹かれる傾向がある。そして、まさにヴァン・バヴェルは後者のタイプ。それ故か、せっかく澤野さんが彼のことを紹介してくれたのにもかかわらず、その後の国内盤といえばオランダのミューニック・レコードが制作した『オールモスト・ブルー〜トリビュート・トゥ・チェット・ベイカー』(2005年)まで待たなければならない。
輸入盤のほうも、それまでのおよそ5年間では、やはりミューニック盤の『ピアノ・グランド・スラム』(2003年)が、日本のCDショップをちょっとだけ賑わせたくらい。このアルバムは、レニー・トリスターノ、ビル・エヴァンス、ハービー・ハンコック、バド・パウエル、マッコイ・タイナーといったピアノ・レジェンズの楽曲を、ヴァン・バヴェルなりに新しい解釈で演奏したもの。こう云っては失礼にあたるが、おそらくショップのバイヤーさんも多くのジャズ・ファンのかたも、ヴァン・バヴェルの名前よりもまずは彼が採り上げた5人のビッグネームに視線を向けたことだろう。なおこの作品では、ザ・ニュー・ロブ・ヴァン・バヴェル・トリオ名義でリリースされている。メンバーは、クレメンス・ヴァン・デル・フィーン(acb)、ウド・パンネケート(elb)、クリス・ストリック(ds)。さらに当時11歳の息子、セバスチャン・ヴァン・バヴェル(p)も1曲だけ参加している。
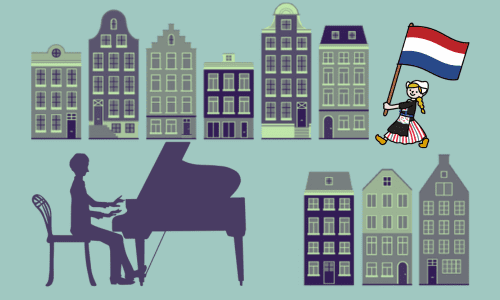
このアルバムはタイトルからもわかるように、クール・ジャズ、ビバップ、モーダル・ジャズなど、モダン・ジャズのスタイルをすべて制覇するというような内容で、ヴァン・バヴェルの飽くなき探求心の結晶とも云える。曲によってはその様式に則って、ボトムがアコースティック・ベースからフレットレスのエレクトリック・ベースギターに替わっている。ヴァン・バヴェル自身も、アコースティック・ピアノのほかにフェンダー・ローズも弾いている。楽曲のアレンジもトリオの演奏も素晴らしいし、ヴァン・バヴェルの高度なピアノ・テクニックも冴えわたっている。ただこのアルバムは、楽曲の扱いかたが巧妙であるという点から、全体的には実験作の印象が強い。そのぶん、前述したような本来ヴァン・バヴェルがもつ大らかな魅力がいささか薄まっている──ということは、どうしても否めないのである。
もちろん、澤野工房の手引きによってヴァン・バヴェルのファンになったぼくが、その後チェット・ベイカー(tp)の最後のピアニストという謳い文句とともに前述のミューニック盤が国内発売されるまでのおよそ5年間、ただ手をこまねいているはずもない。ジャズを愛好するかたであれば、きっとお解りいただけることと思う。はじめて出会ったミュージシャンのプレイが気に入れば、そのひとの演奏をもっと聴きたくなるもの。その期間、わが国のジャズの専門誌においてヴァン・バヴェルについて触れられることは皆無だったけれど、そんな残念な状況を指をくわえて観ているわけにはいかない。ぼくの場合、音楽に対する好奇心と欲求を抑えることは、大人気ないほど困難を極めるのである。リアル店舗でまったく見かけない彼のアルバムを、ぼくは結局インターネットを駆使して探し求めた。
そんなことばかりしているから、ぼくのCD棚は偏ってしまうのだ。どうも浅く広く聴くことが苦手なもので──。まあその件は一時保留としておくが、そんな偏執的な愛情の甲斐あってぼくは何枚かのヴァン・バヴェル作品を入手することができた。比較的簡単に手にはいったのは、オランダのチャレンジ・レコードからリリースされた『ソロ・ピアノ ‘ジャズ・アット・ザ・パインヒル’』(2000年)というアルバム。これはオランダのピアニストたちがソロ・ピアノをスタジオ・ライヴ形式で披露するシリーズの一枚。吹き込みは1999年5月7日で、肩肘を張らずに聴くことができる楽しい演奏となっている。ここでのヴァン・バヴェルはけっこうダイナミックに弾いているのだけれど、それがまったくバタバタした感じのない緊張の解けた素晴らしいプレイなのだ。個人的には、ますます彼のことが好きになった作品である。
小難しさのない鷹揚さがもっとも際立った若き日の一枚
それに反して、肩透かしを食らわされたアルバムもある。自主制作盤の『デイドリームス』(1991年)は、おそらく河合楽器製作所が開発したデジタル・シンセサイザーのデモンストレーションのために作られたアルバムなのだろう。ヴァン・バヴェルのトリオの当時のレギュラー・メンバーであるハンス・ヴァン・オーステルハウト(ds)も参加しているのだが、どちらかといえばKAWAIのシンセサイザーやコンピュータが駆使されたフュージョン作品といった趣がある。確かに彼の作曲や編曲の才能が光るところもあるのだが、どうひいき目に見ても、そのピアニズムにおける本来の能力や特性が引き出されているとは、ぼくには到底思えないのである。そういう点では、ミューニック・レコードからリリースされた『クァランティーン』(2002年)にもおなじことが云える。
このアルバムは、ザ・ピッチ・パイン・プロジェクトというグループ名義で吹き込まれた、バリバリのフュージョン作品。メンバーには、前述の『ピアノ・グランド・スラム』にも参加していたウド・パンネケート(elb)、クリス・ストリック(ds)のふたりに、マルティン・ヴァン・イテルソン(g)、トム・ベーク(sax, bcl)が加わっている。ヴァン・バヴェルは、アコースティック・ピアノのほかにフェンダー・ローズやシンセサイザーも弾いている。みな実力のあるミュージシャンばかりだ。そのサウンドをひとことで表現すると、オランダ版ウェザー・リポート。なかなか聴き応えのあるアルバムなのだが、やはりヴァン・バヴェルにフュージョンは似合わない。なおこのグループはその後、チャレンジ・レコードからセカンド作『アンプレセデンティド・クラリティ』(2008年)をリリース。ランディ・ブレッカー(tp, flh)のゲスト参加が、目玉となっている。
やはりヴァン・バヴェルの魅力が全開するのは、メインストリームの伝統が継承されたモダン・ジャズ作品。結局、個人輸入するしか方法はなかったが、なんとか入手することができたつぎの2枚のアルバムでは、彼を実力派のピアニストと評価するに相応しい、ファンタスティックな演奏を聴くことができた。そのアルバムというのは、ミラサウンド・プロダクションからリリースされたセカンド作『ロブ・ヴァン・バヴェル・トリオ』(1989年)、そして自主制作盤のフォース作『ジ・アザー・サイド』(1991年)である。これらの作品はピアノ・トリオによる吹き込みで、メンバーは前述のファースト作『ジャスト・フォー・ユー』と同様に、ロブ・ヴァン・バヴェル(p)、マーク・ヴァン・ローイ(b)、ハンス・ヴァン・オーステルハウト(ds)の三人。前者にはフェルディナンド・ポヴェル(ts)が、後者にはベン・ヴァン・デン・ドゥンエン(ts, ss)とピーター・グイディ(fl)が、それぞれゲスト参加している。

ぼくとしては、初期のヴァン・バヴェルのアルバムでは、これらのトリオ作品をベスト・スリーに挙げたい。なかでもいちばん好きなのが『ロブ・ヴァン・バヴェル・トリオ』である。理由は、最初にも述べたがヴァン・バヴェルのピアノ・プレイの魅力のひとつである小難しさのない鷹揚さが、もっとも際立っているから。聴いていて、とにかく楽しい。冒頭のアイシャム・ローンズの「ゼア・イズ・ノー・グレーター・ラヴ」からすぐに引き込まれる。ゆったりとしたテンポで徐々に躍動感が増していく様には、ほんとうにワクワクさせられる。ヴァン・バヴェルの自作「ワルツ・オン・Bストリート」はリリカルな三拍子。優しさと気品に富んだ佳曲だ。やはり自作の「イッツ・ア・シャッフル」では文字どおりトリオが豪快にシャッフルする。またまた自作の「シント・マールテン」では陽気なカリプソのリズムが心地いい。
ソニー・ロリンズの名曲「ドキシー」ではトリオがジャムセッション風にファンキーに盛り上がる。さらなる自作曲「プラクティス・アンド・プリーチ」はスローなゴスペルだが、そこはかとなく洗練された雰囲気を漂わせる。ジェローム・カーンの「ノーバディ・エルス・バット・ミー」ではポヴェルのテナーがとにかく爽快。ヴァン・バヴェルのピアノもスウィングしまくる。ロジャース&ハートの「時さえ忘れて」ではピアノの緊張をほぐすような歌いまわしが際立つ。つづくオリジナル「エポキシ」ではピアノの歌いかたが若干ソウルフルになりドラムスとのソロ交換も入る。クルト・ヴァイルの「スピーク・ロウ」はアルバムのハイライト。ヴァン・バヴェルのピアノがどこまでも飛翔する。勢いづいて引用も飛び出す。8バースもある。でも外連味はない。そこがいい。コール・ポーターの「いつもさよならを」では、ポヴェルのバラード演奏がなんとも清々しい。アルバムのラストに爽やかな余韻が残る。
このオランダの逸材にふたたびスポットが当てられているいま、もし彼に興味をもったら、ぜひ初期の吹き込み(上記の3枚のトリオ盤)も聴いていただきたい。特に『ロブ・ヴァン・バヴェル・トリオ』では、彼の終始優美なピアノのタッチはもちろんのこと、極上の味わいをもつオーソドックスなジャズのスタイルを、気軽に楽しむことができる。だから本作を見つけたら、ジャズははじめて──というかたも、遠慮しないで手にとっていただきたいもの──。いろいろと語ってしまったが、いちばん大切なことは、ちょうど前述した澤野さんの「聴いて心地よかったらええやんか」というコトバに集約される。そして、この若き日のヴァン・バヴェルのアルバムは、まさにそういう作品なのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント