1979年のフュージョン・シーンを象徴するような明るく爽やかな印象を与える『モーニング・ダンス』──実はすべてのクリエイティヴな作業にしたたかな戦略性が感じられる名盤だった
 Album : Spyro Gyra / Morning Dance (1979)
Album : Spyro Gyra / Morning Dance (1979)
Today’s Tune : It Doesnt’t Matter
1979年──“朝”をテーマにしたフュージョンの名曲が目立つ
フュージョンにはモダン・ジャズのようにスタンダーズと呼ばれる曲がなかなかない。すぐに思い浮かべることができるのは、ロバータ・フラックの「愛のためいき」くらいだ。1974年に全米1位を記録した曲で、多くのアーティストがカヴァーしている。あとはヴィヴァ・ブラジルの1980年のデビュー作のオープナー「スキンドゥ・レ・レ」が、様々なミュージシャンに採り上げられているかな。自分の知識不足を申しわけなく思ういっぽうで、ジャズ・スタンダーズに比べてフュージョン・スタンダーズは圧倒的に少ないとあらためて認識する。おそらくフュージョンの場合、アーティストたちが演奏と同時に作曲においても鎬を削るようなところがあるから、あまり他人の楽曲は採り上げないのだろう。
と、そんなことを述べているうちに、チック・コリア&リターン・トゥ・フォーエヴァーの『ライト・アズ・ア・フェザー』(1973年)に収録されている「スペイン」や、ボビー・ウーマックの「ブリージン」を思い出してしまった。ちなみに「ブリージン」のほうは、ジョージ・ベンソンの『ブリージン』(1976年)のタイトル・ナンバーとしてあまりにも有名だし、シングル盤としても大ヒットした。しかしながら、ベンソンのヴァージョンは実はカヴァーで、オリジナルはハンガリーのジャズ・ギタリスト、ガボール・ザボの『ハイ・コントラスト』(1971年)に収録されている。このレコーディングのために、セカンド・ギタリストのウーマックが書き下ろした。ザボとベンソンのアルバムは、ともにトミー・リピューマがプロデュースした。偶然ではない。
いずれにしても、フュージョンにおいてスタンダーズと呼ばれるような楽曲は非常に少ない。理由は簡単。その手の作曲を生業とするひとがいないからだ。モダン・ジャズの場合、その発展において、コマーシャルなポップスを量産する作曲(または作詞)の専門家たちが有効な貢献を果たしている。その代表といえば、ブロードウェイ・ミュージカルとつながりの深い、1910年代から次第に台頭しはじめたティン・パン・アレー系の職業作家たちが挙げられる。また、著名なビッグ・バンドがこぞって関心を寄せた、1950年代後半から1960年代の終わりまで流行したブリル・ビルディング・サウンドのクリエイターたちの存在も大きい。つまり昔は、即興演奏に集中するジャズ・ミュージシャンにとって、手っ取り早くレパートリーに加えることができるような楽曲が、わんさか産出されていたのである。

ところがフュージョンの場合、その音楽性から演奏のみならずサウンドメイキングにも趣向が凝らされるので、結局アーティスト自身が作曲を手がけることになる。つまり出来上がった楽曲はプレイヤーの存在証明ともなるものだから、ほかのミュージシャンはよほどのリスペクトがないかぎり、その曲を採り上げることはしないのだ。そういうわけで、フュージョンにおいてスタンダーズと呼ばれるような楽曲は、自ずと少なくなる。しかしながら、これだけは云える。フュージョンには数えきれないほどの名曲の誉れ高きナンバーがある。しかもフュージョン作品は、レコーディングのコンセプトが明確化されている場合が多いから、名曲を収録するアルバムは概ね名盤と称されるのである。
ところで、フュージョンの名曲をここに列挙することは控えるが、1979年のフュージョン作品をあらためて観てみると、面白い現象に気づく。それは日本産のフュージョン・アルバムの収録曲のなかに、“朝”をテーマにした名曲がいくつかあるということ。個人的に真っ先に挙げたいのは、渡辺貞夫の『モーニング・アイランド』のタイトル・ナンバー。渡辺さんはアルトではなくフルートを吹いている。その飾り気のない優しい音色、デイヴ・グルーシンの繊細なアレンジ、ニューヨークのファースト・コールたちによる柔軟なリズム──と、いかにも朝の光に包まれるような爽やかさが魅力的だ。ぼくがこの曲を素晴らしいと思うのは、カリプソの要素が採り入れられている点。南国情緒が漂う明るい曲調に、意表を突かれた。
つづいて気になったのは、増尾好秋の『グッド・モーニング』のやはりタイトル・ナンバー。偶然にもこの曲もカリプソ風だ。ヴィヴィッドなアコースティック・ギターとエモーショナルなエレクトリック・ギターのコントラストが鮮やか。メロウだけれどリフレッシングな心地よさを感じさせる。さざ波が寄せる浜辺から朝陽が昇る水平線を見つめる──そんなイメージが浮かぶ。そしてさらに、いささかこじつけになるが、カシオペアのセカンド・アルバム『スーパー・フライト』には、彼らの代表曲「朝焼け」が収録されている。こちらは文字どおり、朝焼けが照り返す高層ビル群を眺めながら湾岸道路をドライヴするのにピッタリな、軽快なビートが鮮烈なナンバー。まさにジャパニーズ・フュージョンの名曲だ。
「モーニング・ダンス」はスパイロ・ジャイラにとって異色だった?
上記の3曲は、いずれも1979年に発表された。ところがそれらは、マイルス・デイヴィスが『ビッチェズ・ブリュー』(1970年)で演っていたエレクトリック・ジャズや、ジョン・マクラフリン率いるマハヴィシュヌ・オーケストラの『火の鳥』(1973年)のジャズ・ロックとも称されるサウンドとは、まったく趣きが異なるものと感じられる。確かにマイルスやマクラフリンのアグレッシヴなまでに理想の音楽を追求する姿勢は素晴らしいし、そのアンサンブルもインプロヴィゼーションも聴き応えは十二分だ。しかしながらドライヴのBGMにしたら、カーヴでハンドルを余計に切り過ぎそうで、ちょっと怖い。それに反して1979年の3曲は、日常生活に優しい。間違いなくこのころのフュージョンは、大衆が聴きやすい音楽に移行していたのである。
そんな時代に登場すべくして登場したのが、アメリカのフュージョン・グループ、スパイロ・ジャイラである。奇しくもおなじ1979年にリリースされた『モーニング・ダンス』は、日本でも人気を博した。当時のわが国に、彼らに関する情報はまったくもたらされていなかった。それにもかかわらず、その軽薄とも取られかねないサウンドがあっさり受け入れられたのは、日本のリスナーにそのお膳立てがすっかり整っていたからである。特に渡辺貞夫の作品の影響は大きいと、ぼくは思う。やはりカリプソのリズムが特徴的な『カリフォルニア・シャワー』(1978年)のタイトル・ナンバーは、日本のフュージョン・ブームの呼び水となった曲。しかもその燦々と降り注ぐ陽光のような明るい曲調は、それまでのファンクやソウルの要素を含むフュージョンのイメージを覆すものだった。
この『モーニング・ダンス』のタイトル・ナンバーは、それこそ知名度抜群のフュージョンの名曲だが、やはり明るく爽やかな印象を与える。しかもカリプソ風にアレンジされていて、もはや偶然とは思えなくなってくる。ときにソニー・ロリンズが早い時期からジャズにカリプソを採り入れていたけれど、あのモダンなテイストとハッピーなフィーリングとが共存するような雰囲気が、この曲にも漂っている。そういえばスパイロ・ジャイラは、よくライヴでロリンズの『ザ・ウェイ・アイ・フィール』(1976年)の冒頭を飾る「アイランド・レディ」を演奏していたから、幾ばくかの影響を受けているのかもしれない。とにもかくにも、 暑い日に冷たい柑橘系ドリンクでも飲みながら聴きたくなるような、このフレッシュなフュージョン・ミュージックは広く歓迎されたのである。
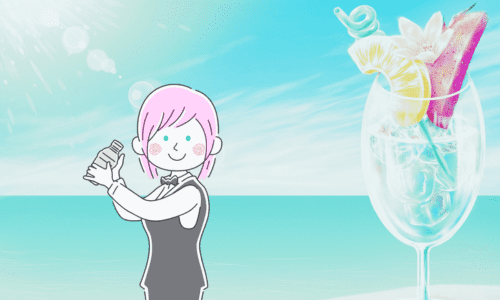
繰り返しになるが、スパイロ・ジャイラの「モーニング・ダンス」は、紛うかたなきフュージョンのマスターピースだ。ところが、あらためてアルバムをひとわたり聴いてみると、意外にもこの曲にしたたかな戦略性が感じられるのである。もともとこのグループの音楽性は、のちのスムース・ジャズのように、聴き心地がいいサウンドに主眼が置かれたものではない。確かにアルバムには「モーニング・ダンス」と同様に軽妙洒脱なナンバーも数曲あるが、曲によってはジャズ・ファンクとも云うべき、グルーヴが強調されたリズム・アンサンブルやハードなアドリブ・プレイも観られる。そんな演奏には、ニューヨークのクラブの閉店後の定番であるジャム・セッションをイメージさせるようなインテンシティが感じられる。実は「モーニング・ダンス」のほうが異色なのである。
よく間違えられるのだけれど、この『モーニング・ダンス』はスパイロ・ジャイラのデビュー作ではなくセカンド・アルバムだ。ファースト・アルバムの『スパイロ・ジャイラ』(1978年)が日本で発売されたのは『モーニング・ダンス』よりあとだったから、勘違いされても致しかたない。それはいいとして、このファースト作を聴いていただければ、このグループのさらなるハードなパフォーマンスに驚かされるだろう。それはまさに、ニューヨーク産のジャズ・ファンクといった風情だ。そんななかに「シェイーカー・ソング」というトロピカル・フルーツのような甘口の曲がある。ビルボード誌のアダルト・コンテンポラリーのシングル・チャートにおいて16位を獲得した。マンハッタン・トランスファーの『エクステンションズ』(1979年)で、早々とカヴァーされるほどの人気曲だ。
全体的には革新性に富んだデビュー作においては、むしろ異なる色彩を帯びていると感じられる「シェイカー・ソング」の大当たりは、その後のスパイロ・ジャイラの方向性を定めたとも云える。次作のトップに据えられた、まるでもぎたての果実のようなフレッシュネスとアーバン・ライフを彩るようなソフィスティケーションがミックスされた「モーニング・ダンス」は、その象徴とも云える曲だ。ニューヨーク州北西部エリー郡の都市、バッファローのインディペンデント・レーベル、クロスアイド・ベア・プロダクションで自主制作されたファースト・アルバムが大きな話題となり、スパイロ・ジャイラはMCAレコード傘下のインフィニティ・レーベルと契約。セカンド作のコンセプトが立てられる際、真っ先に念頭に置かれたのは、なによりも「モーニング・ダンス」の明るいイメージだろう。
スパイロ・ジャイラの結成は、ニューヨーク州南東部に位置するロングアイランドにおいて、当時大学生だったサクソフォニストのジェイ・ベッケンスタインが夏休みになると、ハイスクール時代の友人、キーボーディストのジェレミー・ウォールとともにギグを楽しんでいたことに端を発する。7歳からサックスをはじめたベッケンスタインは、バッファロー市の大学で生物学を学んでいたが音楽にのめり込み、とうとう専攻を音楽に変更する。ウォールのほうも大学卒業後バッファローに移り住み、ベッケンスタインに合流。ふたりは1974年から地元のジャズ・クラブ、ジャック・ダニエルズにおいて、店の休業日である毎週火曜日の夜にジャム・セッションを主催。そして1977年、そこに集まったローカルの腕自慢たちをメンバーとした、スパイロ・ジャイラがついに旗揚げする。
すべてのクリエイティヴな作業に戦略性が感じられる名盤
これは余談だが、バンド名のスパイロ・ジャイラには、耳慣れない響きがあるけれど、もともとアオミドロという意味がある。デビュー作のジャケットにあしらわれたドラゴンのイラスト(のちに異なるアートワークに差し替えられた)を見ると、ポケモンの一匹ドラミドロをイメージしてしまうのは、ぼくだけだろうか──。アオミドロは緑藻、つまり緑色植物の属名であり、それに属する藻類の呼び名でもある。アルバムを自主制作する際に、大学で藻の研究をしていたベッケンスタインが冗談めかして、グループ名にネーミングした。ところが本来の学名は“Spirogyra”と綴られるのだが、ジャック・ダニエルズのオーナーが“Spyro Gyra”とスペルを誤って表記。それがそのままフュージョン・シーンを席巻するバンド名になるとは、実に愉快である。
スパイロ・ジャイラは、40余年にもわたる長期の活動において、何度もメンバーが入れ替わっている。日本ではじめて『モーニング・ダンス』がリリースされたときは、クレジットを見ただけでは誰がレギュラーで誰がゲストなのか、正確にはわからなかった。当時はレコードの投げ込みにプリントされた、メンバーが街頭で談笑するかのようなスナップショットから、想像をたくましくするしか手はなかったのである。もちろんいまでは、その面々が誰なのかハッキリしている。写真にうつっているのは、ジェイ・ベッケンスタイン(sax)、トム・シューマン(key)、チェット・カタロ(g)、ジム・カーツドーファー(b)、イーライ・コニコフ(ds)、ジェラルド・ヴェレス(perc)の6人で、彼らが当時のレギュラー・メンバーである。
ジェレミー・ウォールは、その後もしばらくレコーディングに参加するが、この時点ですでにグループから離脱している。このあとすぐにプロデューサーのクリード・テイラーに手腕を買われ、マルチ・リード奏者、ユセフ・ラティーフの『テンプル・ガーデン』(1979年)や、女性ヴォーカリスト、パティ・オースティンの『ボディ・ランゲージ』(1980年)、さらにはフュージョン系の人気アーティストによるコラボレーション・アルバム『フューズ・ワン』(1980年)といったCTIレーベルの作品で、コンポーザー、アレンジャー、キーボーディストとして活躍する。さらに、バッファロー市に拠点を構えるインディペンデント・レーベル、アムハースト・レコードから『クール・ランニング』(1991年)『ステッピング・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド』(1992年)というリーダー作もリリースするが、正直云ってスパイロ・ジャイラの作品のような魅力は感じられない。
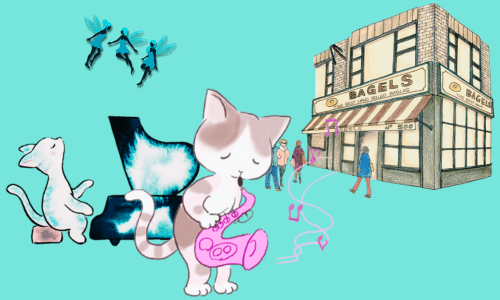
それはさておき、名盤『モーニング・ダンス』は、レギュラー・メンバー以外に、ニューヨークの敏腕ミュージシャンたちによるリズム・サポート、トム・マローンやブレッカー・ブラザーズが参加したホーン・セクション、6人編成のストリングス、ラニ・グローヴス、ディーヴァ・グレイ、ゴードン・グロディーによる定番とも云えるバックグラウンド・ヴォーカルズ──と、とにかくレコーディングに贅が尽くされている。世界各国で個展を開き数々の受賞歴をもつ画家、ジュリー・ヘファナンによる写真のようなイラストがあしらわれたレコード・ジャケットも、グレード感の高い演出である。こうなるともはや、アルバムの企画および制作におけるすべてのクリエイティヴな作業に、したたかな戦略性が感じられてしまう。
オープニングの「モーニング・ダンス」はベッケンスタインの曲。印象的なスティール・ドラムとマリンバはデイヴ・サミュエルズによる。彼はのちに正式メンバーとなる。ジョン・トロペイの弾けるようなようなギター、ルーベンス・バッシーニの軽快なコンガとクラベス、爽やかなベッケンスタインのアルトとウォールのローズと、どこをとっても名曲だ。次の「ジュビリー」はウォールの曲。アーバン・ファンクからクラップハンドが入ったゴスペル調への移行が楽しい。ランディ・ブレッカーの炸裂するエレクトリック・トランペットとウィル・リーのフレキシブルなベースにインパクトあり。3曲目の「ラスル」もウォールの曲。アフロポリリズムに乗ってベッケンスタインのソプラノとストリングスのアンサンブルが交差。ジョン・クラークのホルンも耳に残る。
レギュラー・メンバーによる「ソング・フォー・ローレイン」はベッケンスタインの曲。サンバのリズムが蒼い波が弧を描くように爽快。途中ビバップになるところも気が利いている。なんといってもここで主役を張っているのはトム・シューマンのローズとピアノだろう。つづく「スターバースト」はウォールの曲。アップテンポのフュージョン・ブギー。ウォールのローズ、トロペイのギター、バッシーニのティンバレス、マイケル・ブレッカーのテナーと、ソロがつながれる。スティーヴ・ジョーダンのドラムスも飛翔。途中のパラディドルもキマっている。後半の1曲目「ヘリオポリス」はベッケンスタインの曲。サルサ・ファンクといった感じの都会的なナンバー。ブーバムの奇妙な音色とブラスのシャープな響きが効果的。シューマンのローズ・ソロもソリッドかつファンキーでいい。
レギュラー・メンバーによる「イット・ダズント・マター」はカタロの曲。ギターのナチュラルでちょっとウェットな音色が最高。センチメンタルな曲想も素晴らしい。バックグラウンド・ヴォーカルズも効果的。カタロはこの名曲をリーダー作『ファースト・テイク』(2010年)でも再演した。そしてさらなる名曲「リトル・リンダ」はウォールの曲。アコースティックなラテン・ジャズ。ベッケンスタインのアルト、ウォールのピアノ、サミュエルズのヴァイブと、みなハッピーにバップする。ラストの「エンド・オブ・ロマンティシズム」はゲストのギタリストのリック・ストラウスの曲。まるでプログレのような壮大な構想が感じられる。実はこのインテンシティこそ、スパイロ・ジャイラの原点なのかもしれない。彼らの音楽はその後徐々に、高い音楽性はキープされながらも安定感のあるバンド・サウンドへと変貌していく。それ以前の『モーニング・ダンス』は、何度聴いても新鮮に感じられる。やはり飽きのこない名盤だ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント