ヴィブラフォンのヴァーチュオーソ、マイク・マイニエリのフュージョン史に残る名盤『ラヴ・プレイ』
 Album : Mike Mainieri / Love Play (1977)
Album : Mike Mainieri / Love Play (1977)
Today’s Tune : Easy To Please
ヴィブラフォンに関するいくつかの思い出
ヴィブラフォンというと、サクソフォンと同様に、ジャズのための楽器というイメージが強い。ええ!オーケストラのなかにもいなかったっけ?ちょっと想像してみると、おなじ鍵盤打楽器でもグロッケンシュピールが使用される場面はすぐに思い浮かぶのだけれど、クラシックのコンサートでヴィブラフォンが活躍するシーンを想起するのはなかなか困難だ。まったく不勉強なもので、特殊楽器を好んで採り入れていたショスタコーヴィチの交響曲くらいしか、ぼくは思いつかなかった。まあ、20世紀前半に開発された楽器だから、現代音楽ではけっこう使用されているのかもしれない。いずれにしても、このアルミニウム合金の音板と共鳴管から響いてくる独特な音色は、ジャズによく似合う。
故人であるぼくの父は、基本的にはクラシックのレコード・コレクターでありながら、アート・ブレイキーやデューク・エリントンなどの音楽も愛好するひとだった。とにかく型破りな人間で、ラテン音楽も邦楽も聴く。さすがは昭和一桁世代!サンバと祭囃子をおなじ感覚で楽しむようなところには、いまさらながらだが敬意を表する。その父がライオネル・ハンプトンのエンターテイナーぶりを、ことあるごとに絶賛していた。父は、ぼくがまだ生まれるまえに、ハンプトンの生演奏を来日公演で目の当たりにしたのだそうだ。よく酔っ払うと、エア・ギターならぬエア・ヴァイブをやっていた。その大げさな演奏の身振りが、当時のぼくには恥ずかしかったが、いまではなんとも微笑ましく思える。
きっとぼくには、幼いころからハンプトンの演奏が無意識のうちに刷り込まれていたのだろうが、実は父のエア・ヴァイブしか記憶に残っていない。では、ぼくがはじめてヴィブラフォンという楽器を意識したのはいつかというと、やはり父が所蔵していた『ヴィレッジ・ゲイトのハービー・マン』(1962年)というレコードを聴いたときのこと。当時大人気だったジャズ・フルーティスト、ハービー・マンのアルバムだ。音源は1961年11月17日、ニューヨークの有名なジャズ・クラブ、ヴィレッジ・ゲイトで実況録音されたもの。ジャズとはいっても、ラテンのリズムが採り入れられた、ちょっとエキゾティックでオプティミスティックなサウンドは、いま聴いても独特で新鮮だ。

ウッドベースやパーカッションの乾いた響きも然ることながら、まるで熱帯域を一定のタイミングで吹き抜ける貿易風のような、涼やかで湿った空気を含んだヴィブラフォンの音色に、ぼくはとても魅了された。ここでヴァイブをプレイしているのは、10年くらいまえからそのグルーヴィなサウンドが再評価されている、カナディアン・ソフト・ロック系グループ、ハーグッド・ハーディ&ザ・モンタージュのリーダー、ハーグッド・ハーディそのひと。だいたいヴィブラフォニストというと器用なひとが多いのだが、ハーディもまたヴァイブ演奏のみにとどまらず、ジャズ・ピアニストとして活動したり、日本では劇場公開もされたテレビ映画『赤毛のアン』(1985年)の劇伴を手がけたりもしている。
それはさておき、ハービー・マンの天衣無縫ともいうべきフルート・プレイは、しなやかなリズム感と自由自在なインプロヴィゼーションが魅力的だが、それとハーディのクールなバッキングや時折見せるうねるようなフレージングとは、とても親和性が高いように感じられる。考えてみれば、ぼくがフルートとヴィブラフォンの楽器としての相性のよさに気づいたのは、このレコードにおいてだった。まあこれはアレンジの常套手段になってしまうのだけれど、この属性が異なるふたつの楽器にユニゾンでメロディを歌わせたりすると、それだけで化学反応的に清涼感が生まれるのだ。このアルバムはいまでも好きだけれど、ぼくがハーディを追いかけることはなかった(間もなくゲイリー・マクファーランドのほうにハマったので)。ただずいぶんあとになって、自分の敬愛するマーティン・デニーのグループでマレットを揮っていたのがハーディと知り「やっぱりな」と思ったもの。
強大なインフルエンスをもったヴァイブ作品
フルートとヴィブラフォンのコラボレーションといえば、すぐに思い出されるのは『オパス・デ・ジャズ』(1955年)ではないだろうか。サヴォイ・レコードが誇る、モダン・ジャズの名盤だ。フランク・ウェスのフルートとミルト・ジャクソンのヴァイブが絡むバラード「ユー・リーヴ・ミー・ブレスレス」は、瑞々しい響きと淀みのない演奏が相まって、ジャズにしては稀に見る透明感に富んだ美しい音世界が繰り広げられている。ルディ・ヴァン・ゲルダーによるレコーディングのよさもあるのだけれど──。この曲以外はブルースばかりがプレイされているが、フルート×ヴァイブのコラボがサウンドを軽妙洒脱なものにしている。気軽に楽しめるので、個人的にはいまでもよく聴く一枚となっている。
あとフルート×ヴァイブというと、ぼくの敬愛する日本のジャズ・ミュージシャン、大野雄二の曲「A Joyful Walk 刑事たちの散歩道」が、すぐに思い出される。テレビドラマのサウンドトラック・アルバム『大追跡』(1978年)に収録されている。軽快なジャズ・ワルツを、爽やかなを響きとキャッチーなフレージングで盛り上げているのは、まさにフルートとヴァイブのユニゾンだ(ストリングスのピチカートも軽妙)。ところで、1978年から1979年にかけて、大野サウンドにヴィブラフォンは欠かせない楽器だった。映画の劇伴でいうと『野性の証明』(1978年)『殺人遊戯』(1978年)『黄金の犬』(1979年)『ルパン三世 カリオストロの城』(1979年)などに、顕著に見て取れる。
そんな大野さんのレコーディングでヴィブラフォンを演奏していたのは、たいていティンパニストでもある金山功だった。金山さんは、ジャンルを超越して数多くの音楽作品でマレットを揮ったひと。聖子も明菜も、ひろみもみゆきも、みんなお世話になっている。ナイアガラ関連、渋谷系サウンド、エヴァ・シリーズと、なんでも演っている。まさに日本を代表するヴィブラフォニストだ。近年では、鷺巣詩郎が手がけたエヴァのサントラ盤『Shiro SAGISU Music from “SHIN EVANGELION”』(2021年)に、金山さんのクレジットを発見。傘寿を迎えたのちの吹き込みということになるが、ただただ感服するばかりである。

それはともかく、ヴィブラフォンがふんだんに使用された大野さんの『ルパン三世 オリジナル・サウンドトラック3』(1979年)に「You Are Like Breeze そよ風の誘惑」と「Vicious Glory 悪の栄光」という曲が収録されている。ところがこの2曲がそれぞれ、ヴィブラフォニスト、マイク・マイニエリの曲「イージー・トゥ・プリーズ」と「マジック・カーペット」によく似ている。前者などは『カリオストロの城 オリジナル・サウンドトラック BGM集』(1983年)に、ヴィブラフォンがリードを執るヴァージョンも存在し、マイニエリの楽曲からの強い影響が感じられる。ちなみに、やはりこれら二枚のサントラ盤に収録されている「Mysterious Journey ミステリアス・ジャーニー」は、ギタリスト、アール・クルーの「アコースティック・レディ・パート1」を彷彿させる。
この件が剽窃に該当するか否かを、ぼくはここでとやかく云うつもりはない。ただ云えるのはその事象が、上記のマイニエリの楽曲が収録された『ラヴ・プレイ』(1977年)というアルバムが、当時、強大なインフルエンスをもっていた──という事実を裏付けるものであるということだ。ご承知のとおり、マイニエリはヴィブラフォンの演奏については、ヴァーチュオーソと呼ぶべき存在。1978年9月、ニューヨーク・オールスターズの一員として来日した彼のプレイを実際に目撃したひとにとって、それは過去に味わったことのない驚愕の体験になったのではないだろうか。敏腕ミュージシャンたちのなかにあって、ときに6本のマレットを操ったりして、ひとりでステージをさらってしまったのはマイニエリだった。
1938年7月4日生まれのマイク・マイニエリは、生粋のニューヨーカー。12歳でマレットを手にし、14歳にしてすでにプロのヴィブラフォニストとして活動していたという。そのことを踏まえると、来日公演で彼が披露したパフォーマンスが、観客を圧倒するほど卓越して高度なテクニックであった──というのにも頷ける。とはいっても、彼の演奏の技巧や能力が達人の域に達したのは、比較的早い時期だったと想像される。マイニエリは一時期、これまた超絶技巧のドラマー、バディ・リッチの楽団に在籍していたが、リッチのリーダー作『プレイタイム』(1961年)において、その鮮烈なヴァイブ・プレイを確認することができる。マイニエリが22歳のときの演奏である。
フルコースを味わうような感覚で楽しめるアルバム
ぼくがマイニエリの名前をはじめて知ったのは、ボブ・ジェームスの『ヘッズ』(1977年)において。ボズ・スキャッグスのリリカルなバラードが、ダイナミックでリズミカルな曲にお色直しされた「ウィアー・オール・アローン」でフィーチュアされる、ヴァイブのスリリングなアドリブ・プレイにこころ惹かれた。それから間もなく、深町純の『オン・ザ・ムーヴ』(1978年)で思いがけずマイニエリに再会。深町さんがマイニエリの「アイム・ソーリー」という曲への返歌として作曲したという「ユーアー・ソーリー」と、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ「悲愴」の第二楽章が16ビートのグルーヴィな曲にアレンジされた「ホエン・アイ・ゴット・ユア・ウェイヴ – パテティック -」といった2曲で、ソフィスティケーテッドなヴァイブ・サウンドを堪能した。
そして、すでに国内発売されていた『ラヴ・プレイ』を、ぼくは遅ればせながら手にした。案外、当時ぼくとおなじような経路を辿ったひとは多いのではないだろうか。というのも、このアルバムが日本で発売された当初は、それほど話題にならなかったからだ。そのときのマイニエリといえば、注目の新鋭というような扱いをされていたが、実際はもう40代目前のベテランだったのだから、なんとも皮肉なことだ。彼が一躍有名になるのは、やはり前述のニューヨーク・オールスターズの来日公演以降。それからほどなくして、自己のグループ、ステップス(のちにステップス・アヘッドと改名)を結成したり、そのライヴ・ツアーに参加したギタリスト、渡辺香津美のアルバム『TO CHI KA』(1980年)をプロデュースするなどして、マイニエリはすっかりフュージョン・シーンの寵児となった。
というわけで、この『ラヴ・プレイ』──いまではフュージョン史に残る名盤とされている。その一般的な要因としては、マイニエリの卓越したテクニックが駆使されたヴァイヴ・プレイを確認できる──ということも然ることながら、ニューヨークのスター・プレイヤーたちが勢揃いしている──ということが大きい。ただ、ぼくも彼のアルバムのなかでは本作がいちばん好きなのだけれど、理由はちょっとそれとは異なる。ヴィブラフォニストによる超絶技巧が記録された作品は、けっこう存在する。楽器の特性からか、ワザに焦点を当てられることが多いようだ。聴くほうも、思わず襟を正し背筋を伸ばしてしまうほどである。ところがぼくの場合、スゴイと思いながらも、そういうアルバムをターンテーブルにのせる機会が自ずと少なくなっていく傾向がある。マイニエリの作品にもその類いのものはあるが、その点本作には、それらに反して得もいわれぬ気安さがある。
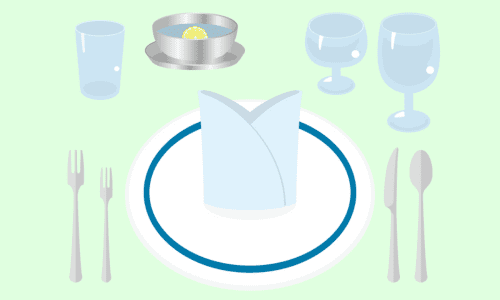
つまり『ラヴ・プレイ』は鑑賞用音楽として、実に優れた作品なのである。もちろんマイニエリの演奏はスゴイ。でもスゴさが目立つのは、どちらかといえばスティーヴ・ガッドの神業的ドラミングのほう。本作におけるマイニエリの素晴らしさといえば、その懐の深い音楽性が際立っているところだ。彼がプロデュースを手がけたシンガーソングライター、ベン・シドランの『グルーヴィなジャズメンとあの帽子』(1979年)と同様に、出来するサウンドは洗練されたエッジの効いたものでありながら、リラックスして聴けるような仕上がりとなっているのだ。本作の楽曲には、難易度の高い演奏技術が目立つ「ラヴ・プレイ」もあれば、かたやコーラス入りのポップな「イージー・トゥ・プリーズ」もある。どんなに豪勢な食事にも、箸休めは必要。その点で本作は、フルコースまるごと楽しんで聴ける一枚だ。
そのほかのメニューは、以下のとおり──。西アフリカのリズムが特徴的な「ハイ・ライフ」では、リータ・ギャロウェイのヴォーカルとマイニエリのマリンバがフィーチュアされる。プログレ風の「マジック・カーペット」では、エキサイティングなシンセヴァイブ(キーボードとお間違いなく)が強烈なインパクトを残す。懐かしいメロトロンによるストリングスとカリンバの音色も心地いい「ラテン・ラヴァー」では、マイニエリのお茶目なヴォーカルが楽しめる。前述の「アイム・ソーリー」では、マイケル・ブレッカーのテナーによる都会のセンチメンタリズムを堪能できる。マイニエリの盟友であるキーボーディスト、ウォーレン・バーンハートの「シルクワーム」では、温もり感いっぱいのミニモーグとリラックスしたアドリブを展開するヴァイヴとのコントラストがとても美しい。ホール&オーツのカヴァー「サラ・スマイル」では、ビターな味わいで鳴きまくるデヴィッド・サンボーンのアルトと、ブルージーなマイニエリのヴァイブに魅惑されるばかりだ。
ということで、ヴィブラフォニストの名作といえば、ぼくにはこの『ラヴ・プレイ』が真っ先に思い浮かぶ。マイニエリにとっても、最高傑作であろう。たしかにそれ以前にも『枯れ葉(インサイト)』(1968年)や『ジャーニー・スルー・アン・エレクトリック・チューブ』(1968年)といった力作もあるけれど、正直いってちょっと小難しい部分もある。ハード・バップなデビュー作『ブルース・オン・ジ・アザー・サイド』(1963年)は、リラックスして聴けるせいか比較的ターンテーブルにのることが多い。しかしながら、それこそオードブルではじまりコーヒーでおわるという、西洋料理のフルコースを味わうような感覚で音楽を楽しめる──という点では『ラヴ・プレイ』の右に出る作品はないと、ぼくは思う。たとえインテリなゲイリー・バートンや、グルーヴィなロイ・エアーズの傑作群でも、ちょっと及ばないのではないだろうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント