無限に広がるイマジネーションが創造するアーティスティックな音世界

Album : Chick Corea / The Mad Hatter (1978)
Today’s Tune : The Mad Hatter Rhapsody
難易度の高い演奏技術が駆使されて生み出された音楽
チック・コリアの突然の訃報を聞いて、驚きと哀しみを禁じ得なかった音楽ファンは、とても多かったと思う。あれから二年──歳月は、まるで何事もなかったかのように過ぎていくものだから、こんなときは、時の神様はなんて無慈悲なのだろうと感じられる。ひとの世ははかない。どんなものでも消滅流転し、永遠不変のものはない。しかしながら、ひとが生きた証しは残る。チックが創造した音楽は、世界に数多存在する音楽を愛するひとたちの胸に、深く刻まれていることだろう。かく云うぼくも、そのひとり。チックの作品を聴いていると、彼がいますぐ近くに居るようにさえ感じられるのである。
ぼくのチックに関する思い出は、中学二年生のころにさかのぼる。東京生まれのぼくは、その近県とはいえ在郷とも云いたくなるようなところに位置する中学校に転校した。いまでは珍しくもなんともないと思うのだけれど、当時、ピアノを弾いたりジャズを聴いたりしているような十三歳は、自然のなかでゆったり暮らしているクラスメイトたちにとって、まったくの闖入者だった。しかも、ぼくのほうも愚かなことに、クラスのみんなにとって自分は必要のない存在──なんて、いまから思うとずいぶん自分勝手な疎外感を抱いてしまった。いずれにしても、ぼくの内向性はこのころに生まれた。
そんなまだ青い果実だったぼくに、声をかけてくれたのは、クラスでいちばんの優等生、Kくんだった。実は、彼は高校生のお兄さんの影響で、ジャズを愛好していた。彼にとって、共通の趣味をもっているおなじ年ごろの子は、ぼくがはじめてだったとのこと。彼とはジャズ以外の話はあまりしなかったけれど、いつも会話が弾んで、そんなときは、なんとなく自分の価値が認められているような気がして、ずいぶんと救われたもの。そんなKくんが敬愛していたピアニストが、ジョー・サンプル、そしてチック・コリアだった。当時、ぼくはこのふたりについては、名前こそ聞いたことはあったが、実際にその演奏に触れたことはなかった。

そのときの自分に、Kくんに付いていこうといういじましさがあったことは否定できないけれど、それよりも未知の音楽への好奇心が激しく掻き立てられて、まもなくぼくは、このふたりのレコードを一枚ずつ購入した。ジョー・サンプルのほうは『虹の楽園』(1978年)というアルバムで、ここでジョーはわりとアーシーに弾きまくっているのだけれど、それに反して彼の書いた曲はどれもメロディアスでロマンティックだったから、とても聴きやすかった。問題はチック・コリアのほう。中学生のお財布にやさしい廉価盤という理由だけで、レジにもっていったのは『ナウ・ヒー・シングス・ナウ・ヒー・ソブス』(1968年)という作品だった。このアルバム──正直云って、初めて聴いたときは、あまり良さがわからなかった。一聴で、チックがすごいピアニストであると、確信させられたのにもかかわらず──。
このアルバムは、ピアノ・トリオの歴史を塗りかえるような革命的な作品と広く受け入れられているが、当時のぼくはまだ、そんなことは知る由もなかった。そしてはじめは、ただただチックの超絶技巧のピアノ演奏に圧倒されるばかりで、純粋にこの作品を楽しむゆとりなど、未熟な自分にはまったくなかったのである。感覚的には、マッコイ・タイナーをもっとシャープにしたような感じ──というか、マッコイよりも音の揃いかたが機械のように正確だな──と、そんな点に驚嘆するばかり。でも、その素晴らしさがわからなかったのは、実はぼくの聴きかたに問題があったから。難易度の高い演奏技術が駆使されて生み出された音楽を、アタマで理解しようとしてはダメなのだ──。
終始表現の自由にこだわり抜いた偉大な音楽家
それでもぼくは、クラスメイトのなかで唯一の自分の理解者がすすめてくれたアーティストの作品だから、わけもわからず『ナウ・ヒー・シングス・ナウ・ヒー・ソブス』を繰り返し聴いていた。そうはいっても、たとえば読書のときにとか、昼寝のときにとかで、あまり真剣には聴いていなかったのだけれど──。ところが、そんないいかげんな聴きかたが、かえって功を奏したのか、ある日、自分がとらわれていたであろう雑念のようなものが、ふと解消された。それまでスリリングな演奏のなかに紛れて見えなかった、映像的とも云える美しい歌ごころを、ぼくの感性はようやくキャッチしたのである。
音楽は、理屈で理解するものではなく、こころに響かせるもの──そんな、あたりまえのことを、ぼくはすっかり忘れていた。そして、音楽家は、芸術家ではあっても、大道芸人ではない。指をどれだけ速く動かせるかを、聴衆に見せつけるために、高度なテクニックを用いているのではない。自分のなかに浮かんだ心象風景や空想世界を、思いのままに音楽として表現するのに必要だからこそ、ミュージシャンはときに難易度の高い演奏に傾倒するのである。そんなことを意識しながら、あらためてチックの音楽に触れてみると、彼は音楽至上主義というよりも、とても透明感に溢れたイマジネーションの独自性が高く優れたひと──と、思われる。
その後早々に、ぼくにとってチック・コリアの存在はぐっと身近になり、それは、次はどんな世界に連れていってくれるのだろう?──と、彼の新譜をこころ待ちにするほどだった。とはいっても、ぼくにとって彼はいつまでも、はじめて聴いたときの印象どおり、すごいピアニストなのである。彼の才能には、たとえ千倍練習したとしても、ぼくなどは及びもつかない。そんなことは、百も承知、二百も合点だ。それでも、ぼくがシンパシーを感じるのは、彼がどんな音楽作品をクリエイトするときでも、自分の想像力を大事にしているという点。無限の想像性がなければ、音楽もまた人生と同様、味気ないものになってしまうものだから──。
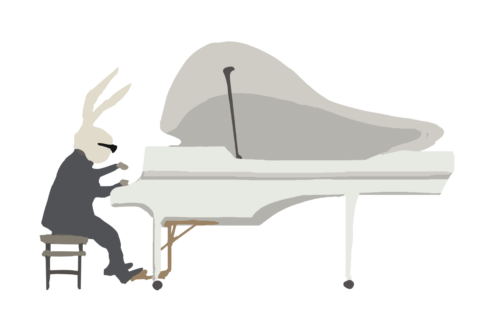
ところで、進取の気性に富んだチックの膨大な数の作品群のなかからベストワンを選ぶのは、極めて困難である。たとえば、ピアノ・トリオによるレコーディングのみに絞り込んでも十二種類のトリオがある(作品の方向性でメンバーを替えている)。このことは、彼のヴァーサティリティに富んだ音楽性をよくあらわしていると思う。多くのピアノ・トリオは、(音楽性を高め合える)相性のいいメンバーでほぼ固定的に、長きにわたり活動するもの。だが、チックの場合は違う。彼は作品を制作する際には必ず、程度の差こそあれ、一定のテーマに基づいて編成や楽曲を選んでいるのだ。そういった意味で、彼は、単なるジャズ・ピアニストではなく、終始表現の自由にこだわり抜いた偉大な音楽家だった。
というわけで、これはまったく個人的な好みになってしまうのだが、トリオ、フリー・ジャズ、フュージョン、クラシック、ソロ・ピアノ、デュオ……と、まあとにかく多彩なチックの作品群のなかでも、ある種のコンセプト・アルバムのようなものに、ぼくは強く惹かれる。特にジャズというひとつのジャンルにとらわれることなく、彼がイメージする心象と空想が自由に表現されて、実にカラフルなサウンドとして出来した三作品はおすすめ。それは──アイルランドに伝わる妖精の物語で構成された『妖精』(1976年)、過去の作品からもすでに影響が感じられていたスペイン音楽にディープに傾倒した『マイ・スパニッシュ・ハート』(1976年)、そして、ぼくのいちばんの愛聴盤、ルイス・キャロルの小説『不思議の国のアリス』や『鏡の国のアリス』にインスパイアされた『マッド・ハッター』(1978年)。
不思議の国のチック・コリア
なかでも『マッド・ハッター』は、チックの奔放な想像力と芸術的な創造性が、渾然一体となって作り出した音楽世界のなかでも、もっとも傑出した作品と、ぼくは評価する。組曲仕立てのアルバム・コンセプトは極めて明解で、ストーリー性のある楽曲構成もとても理解しやすい。おそらく、たとえジャズに興味がないひとでも、その魅力的な世界に抵抗なく入っていけるだろう。さあ、あなたも、少女アリスとともに、白ウサギを追ってウサギ穴に飛び込もう!そして音楽の異世界に迷い込みながら、めくるめく冒険の旅を体験しよう!
オープナーは序曲ともいった風情の「ザ・ウッズ」で、リスナーはこの曲でいきなり現実世界から離脱させられる。ピアノとマリンバがポリメトリックに別々の時間を刻みはじめると、数種のモーグ・シンセサイザー、アープ・オデッセイ、オーバーハイム8ヴォイスなどのシンセサイザーが美しいアンサンブルを奏でる。中盤のクラシカルなピアノの即興演奏は、まるでとれたての果実のように瑞々しく響く。やがてアコースティックとエレクトロニックの、それぞれの異種楽器たちは一気に溶け合う──。ここでの演奏は、オーヴァー・ダブにより、すべてチックひとりによって行われた。この一曲だけとっても、このアルバムを聴く価値があると、ぼくは思う。
つづいて、ピアノと弦楽四重奏による「トウィードル・ディー」は20世紀の新古典主義からの影響が感じられる。チックのピアノもバルトーク・ベラ風に、パーカッシヴに跳ねる。この曲は「ザ・トライアル」へとつながり、ホーン・セクションが加わる。そして、ハーヴィー・メイソン(ds)によるマーチング演奏とジェイミー・ファント(b)のしなやかなフィンガー・ピッキングをバックに、チックの奥さま、ゲイル・モラン(vo)が「タルトを盗んだのはだ〜れ?ハートのキング?」という感じに、反復的に歌い上げるのが、ちょっと奇妙でもありユーモラスでもある。

後年、チック・コリア・アコースティック・バンドの『ラウンド・ミッドナイト』(1991年)でセルフ・カヴァーされた「ハンプティ・ダンプティ」は、いまではチックの代表曲のひとつ。アルバム中、唯一の4ビートでもっともジャジーな曲。とはいってもスウィンギーではない。のちにステップスやマンハッタン・ジャズ・クインテットでコンビを組む、スティーヴ・ガッド(ds)&エディ・ゴメス(b)が、コンテンポラリーでタテ割りな4ビートを刻んでいく。それに乗って、リターン・トゥ・フォーエヴァーの元メンバー、ジョー・ファレルのテナー・サックスとチックのミニモーグが、軽快にアドリブする。
やはりミニモーグとテナーのソロがフィーチュアされる「プレリュード・トゥ・フォーリング・アリス」〜「フォーリング・アリス」は、ふたりのソロに呼応したハーヴィーの素晴らしいドラミングに注目。彼が、神様的なガッドとはまるで違うタイプのドラマーであることが、確認できる。ファントのアルコ・ベースがフィーチュアされた短い「トウィードル・ダム」をはさんで、サンバ風のリズムに乗って、今度はゴメスのベース・ソロが大きな特色となる「ディア・アリス」がスタート。中盤のファレルのフルートと後半のガッドのパラディドル(やはり彼は神様だ!)も快調。
ラストのフルメンバーで演奏される「マッド・ハッター・ラプソディ」(後半はふたたび「フォーリング・アリス」になる)は名曲。ガッドの気持ちのいいハイハット・ワークに乗って、チックのミニモーグとハービー・ハンコックのフェンダー・ローズが大ソロ合戦を展開!特にハービーのアドリブ・ソロは、これまでの彼の即興演奏のなかでもかなりの名演と云える。以上──異世界では時間の経過があまりにも速い(およそ50分)。しかしながら、チック不在の現世にあっても、ぼくたちはいつでも時間と空間を超越して、不思議の国のチックに出会うことができる。それは本作のように、彼の創造した音楽が、想像力と芸術が一心同体となったものだったから──。その入り口まで、ひとりぼっちのぼくを誘ってくれたKくんのように、もし、この拙文が読者の世界を拡大する一助にでもなれば、ぼくはとても嬉しい!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント