ウェイン・ショーター──哀悼の意を表して、その偉大なる足跡をふりかえる

Album : Wayne Shorter / Native Dancer (1975)
Today’s Tune : From The Lonely Afternoons
名サクソフォニストであり名作曲家
またひとり、ジャズの巨匠が天国へ旅立った。名サクソフォニストであり名作曲家でもあるウェイン・ショーター。その非凡な才能は、アメリカではもちろん、わが国でも広く知れわたっている。オルフェウス・チェンバー・オーケストラとの共演による4部構成の組曲と、ダニーロ・ペレス(p)、ジョン・パティトゥッチ(b)、ブライアン・ブレイド(ds)を率いての、ロンドンでのライヴが収録された、まさにドレッドノートを超える3枚組の大作『エマノン』(2018年)が話題となったのが、ついこの間のことのように思い出される。
あまり気にしたことはなかったのだが、ショーターは、グラミー賞において21回もノミネート、そのうち11回は受賞を果たしている。以前からぼくのなかには、艶やかな躍動感に溢れたサックス・プレイと、深い情感と陰影をたたえたそのサウンドから、(敬虔な仏教徒という点も手伝って)どこか神秘的なひとという印象があったのだが、いまさらながら、彼はリアルに傑出したミュージシャンだったのだなと、再認識させられた。2023年3月2日、ロサンゼルスの病院で家族に看取られながら、旅立ったとき、彼は89歳だった。
あらためてその経歴を振り返ってみると、ショーターは実に進取の気性に富んだ音楽家だったということがわかる。それと同時に、その若き日から自らの才能を大いに発揮していたことも、かさねて認識されるのである。そのことは、彼が参加した1959年以降のアート・ブレイキー・アンド・ザ・ジャズ・メッセンジャーズの吹き込みを聴いてみれば、だれの耳にも明らかだろう。確かにこのグループ、ベニー・ゴルソン(ts)が音楽監督を務めていたときも、そのキャッチーなメロディとアレンジで、ファンのこころを鷲づかみにしていた。

しかしながら、ファンキーであるぶん粗野な部分もあった。それがパターン化していたことも、否めないのではなかろうか。とはいっても、ちゃんとバランスのとれたカッコいいジャズ・コンボだったのだけれど──。ところがそのサウンドは、ショーターが加入すると同時に、それまでウリだったアーシーなムードはすっかり抑えられて、むしろかなり洗練された雰囲気に変化した。たとえば、名盤『チュニジアの夜』(1960年)では、ビバップの時代から数多の名演が存在するタイトル・ナンバーが、モーダルな感じにリフレッシュされているのだ。
その要因が、ショーターがミュージカル・ディレクターとして迎えられたことである──というのは、火を見るよりも明らかだ。それに、ときとして音楽監督が不在のとき、ブレイキーはまえに出過ぎることがある。それを抑制させ、バンド・サウンドが均衡を保つようにさせていたのは、誰あろうショーターだ。しかも当時の彼、演奏の面では、まだ力強さが目立ってはいたが、作曲のほうではすでに新鮮さが溢れ出していた。たとえば、(これも名盤だが)『モザイク』(1961年)に収録されている、やはりモーダルな「チルドレン・オブ・ザ・ナイト」は、極上の出来映えだ。
“帝王”が革新的な音楽を創造するとき、必要不可欠な存在
1964年からショーターは、念願のマイルス・デイヴィスのグループに参加。とはいっても、最初バンド・メンバーに志願したショーターはマイルスにフラれ、その後しばらくの間、今度は逆にショーターほうがマイルスの求愛に応えなかった──という有名なエピソードがある。ふたりの立場は、すっかり逆転していたわけ。それはともかく、ハービー・ハンコック(p)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムス(ds)も参加した、ふたりの蜜月バンドは、セカンド・グレート・クインテットと呼ばれ、その後のニュー・メインストリームなジャズを牽引した(個人的にはファーストのほうも好きなのだけれど──)。
マイルスもまた、従来のジャズのマナーにとらわれるようなひとではない。というか、常に現状に甘んじることなく、積極的に新しい音楽をクリエイトしようとしていた。そして、自分の理想のサウンドを実際に形にしてしまうのだから、リスナーの好むと好まざるとにかかわらず、やはり彼は「モダン・ジャズの帝王」の名に相応しいミュージシャンだと、ぼくは思う。特に、革新的な音楽を創造するために、この上ないほど才気煥発なミュージシャンを的確に見出し、自らのグループに取り込んでしまうという、鋭い洞察力と強引とも云える行動力は、まさに驚異的。
このときのマイルスにとって、ショーターは必要不可欠な存在だった。だから、おそらくマイルスはショーターのやることに、あまり口出ししなかったのではないだろうか?ジャズ・メッセンジャーズのときと同様に、ショーターが音楽監督とまではいかないまでも、少なくともヘッドコーチくらいの役割を担っていたことは、吹き込みを聴けば歴然だ。確たる音楽教育に裏打ちされた理論に基づく表現方法を、敢えて解放していくようなショーターの音楽性が、圧倒的な存在感を放っている。それは、マイルスの替わりにフレディ・ハバードが参加した、V.S.O.P.クインテットにおいても同様だ。
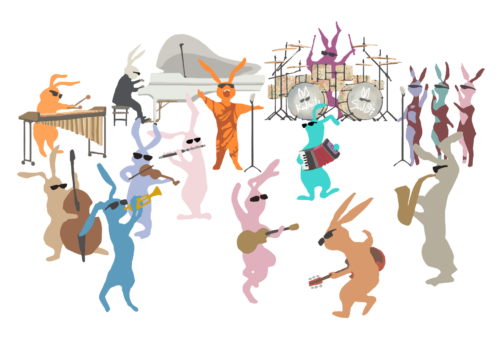
ショーターはマイルスのクインテットで数々の名曲を生み出したけれど、もっとも衝撃的だったのは『ネフェルティティ』(1967年)の一曲目のタイトル・ナンバー。フロントのふたりが淡々と神秘的なメロディを繰り返していくなか、リズム・セクションによるソロともバッキングとも名状しがたいプレイが、徐々にアグレッシヴになっていく様には、意表を突かれたもの。そんなジャズの定石を覆すというか、形式を崩していくような音楽性から、ぼくは勝手にショーターを割り算の音楽家と観ていた。でも、それはちょっと違っていたのだけれど──。
ショーターは、ともするとセオレティカルになりがちな進歩的な音楽を、作法とか規制から解放し、もっと自由なものとして出来させたかったのではないだろうか?そいう彼の理想とする音楽がもっとも具現化したのは、1970年から1986年まで彼が在籍したグループ、ウェザー・リポートにおいてだったと、いまさらながら確信させられる。というのも、そのサウンドが、ときに実験的で難解に響くこともあったけれど、マイルスのクインテットにはなかった、音楽というものの本来の存在意義ともいうべき娯楽性をもっていたからだ。
ショーターが創造した音の楽園
以上、述べてきたグループ活動の合間を縫って、ショーターはリーダー・アルバムのほうも精力的に吹き込んでいる。内容的には、ハード・バップあり、フリー・ジャズあり、ジャズ・ロックありと、いかにも彼らしくひと所に留まることを知らない。ひょっとするとソロ作では、意図的にバンドではできないことに、チャレンジしたのかもしれない。繰り返しになるが、彼はまさに進取の気性に富んだ音楽家の名に相応しいひとだ。そんなことから、その代表作を一枚選ぶとなると、かなり意見がわかれると思われる。
まことに勝手ながら、ぼくは、ウェザー・リポートの活動のみに集中していたショーターが、1974年9月12日、やにわに吹き込んだリーダー・アルバム『ネイティヴ・ダンサー』を、断然推す。なぜなら、ここでクリエイトされたサウンドは、間違いなく彼がやりたかった音世界と映るし、なによりも、これまでの彼のどの作品にもなかった、えもいわれぬ心地よさをもったものだから──。それは、MPBの代表的なシンガーソングライター、ミルトン・ナシメントとのコラボレーションによる、二種類の芳醇なミュージカリティがよくブレンドされた、上質な音楽だ!
ちなみに、MPBとはポルトガル語のムジカ・ポプラール・ブラジレイラの略で、ブラジリアン・ポピュラー・ミュージックという意味。MPBは、1960年代後半に起こったブラジルの温故知新的な芸術運動である、トロピカリズモが発祥とされているけれど、当時はそんな出来事はおろか言葉さえ知る由もなかった。ブラジルといえば、聴いたことがあるのは、サンバとボサノヴァくらいのもの。デイヴ・グルーシンとリー・リトナーが、イヴァン・リンスをはじめ、ジャヴァン、カエターノ・ヴェローゾ、ジョアン・ボスコ、ゴンザギーニャなどを、アメリカや日本に紹介したのは1980年代の中頃。その点、ショーターは早かった。

レコーディングには、ショーターの僚友、ハービー・ハンコック(key)、アメリカのロック系のミュージシャン──ジェイ・グレイドン(g)、デヴィッド・アマロ(g)、デイヴ・マクダニエル(b)、そしてブラジル勢──ヴァグネル・チゾ(key)、ホベルト・シルヴァ(ds)、アイアート・モレイラ(perc)が参加。楽曲は、ショーターが3曲、ミルトンが5曲(作詞はすべてフェルナンド・ブランチによる)、ハンコックが1曲──と、それぞれが持ち寄っている。特にオープナーの「砂の岬」はミルトンが自身のリーダー作『ミナス』(1975年)で歌っているほか、アース・ウィンド・アンド・ファイアや、なんとあのTHE BOOMもカヴァーしている有名曲。
ミルトンの独特な歌声は、まるで楽器のように美しく、ショーターの肉声のようなサックスと相性がとてもいい。上記の「砂の岬」アジムスのカヴァーでも知られる静謐な「タルジ」壮麗な6拍子「魚類の奇蹟」キャッチーなボサロック「孤独な午後」ミステリアスなサンバとロックの融合「リリア」──以上がミルトンの曲。ファンク風でありながらリラックスしたムードをもつ「美女と野獣」ショーター自身によるピアノとソプラノ(オーヴァー・ダブ)が溶け合う小曲「ジアナ」流麗なメロディをもつボサノヴァ風の「アナ・マリア」──以上がショーターのオリジナルで、すべてミルトン抜きの完全なインストゥルメンタル。申し訳ないが、ハンコックの映画音楽「ジョアンナのテーマ」は、リリカルでわるくはないのだが、このアルバムにおいてはちょっと違和感を覚えざるを得ない。なんとなれば、ここは約束の地だから──。
ところがこのアルバム、残念ながら、良質なブラジリアン・フュージョンと、ひとことで片付けられてしまうこともあるようだ。しかしながら、ふたりの音楽性と実際の演奏が、ときには親密に絡み合い、ときにはスリリングにぶつかり合い、創造されるサウンドには、もっと奥深いものを、ぼくは感じる。早々とMPBに注目したショーターの先見の明も妙々たるものだが、このアルバムから感じられるキーワードは「解放感」とか「娯楽性」で、作品全体に本来音楽がもちうるべき心地よさが横溢しているところが、なによりも素晴らしい。それは、まさに音のパライーゾ!
ウェイン・ショーターは、間違いなくジャズの巨匠だったけれど(シリアスなジャズ作品では1964年吹き込みの『ナイト・ドリーマー』が最高!)、音楽に対してもっと広く、こころが開かれていたひとだったと──いま『ネイティヴ・ダンサー』を聴きながら、ぼくは強く思うのである(突然の訃報に接し、こころから哀悼の意を表します)。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント