ピアノのヴィルトゥオーソ、ラムゼイ・ルイスがカリンバ・プロダクションの協力を得てものした最高傑作『サロンゴ』
 Album : Ramsey Lewis / Sălongo (1976)
Album : Ramsey Lewis / Sălongo (1976)
Today’s Tune : Slick
卓越した演奏技能を身につけた根っからのピアノ・プレイヤー
ぼくにとって、ラムゼイ・ルイスはちょっとやっかいなピアニストだ。好きか嫌いかと訊かれれば、好きと答える。しかし、好きなピアニストは?と訊ねられた場合、彼の名前をあげることはない。自分がジャズ・ピアノを弾きはじめたときも、彼から影響を受けることはなかった。それでも、彼のレコードはよく聴いていた。なぜかといえば、ぼくは格調の高い演奏ばかり聴いていると、ときおり膨満感のようなものを覚えるのだが、そういうとき多少荒っぽくても素朴で大衆的な音楽を聴くと、それがずいぶんと解消されるからだ。正直に云って、ぼくはルイスのピアノ演奏にはアーシーで品性に欠けるところがあると思う。それは、ぼくの理想とするジャズ・ピアノからは、マナー、スタイル、そしてテクスチュアにおいて、かなりかけ離れたものなのだ。
ところが、ソニー・クラーク、ウィントン・ケリー、トミー・フラナガン、あるいはレッド・ガーランドの演奏と同様に、ラムゼイ・ルイスのピアノも、ぼくの大好物なのである。つまり、彼のピアノ演奏はぼくにとって、云ってみれば規格外のもの。それにもかかわらず、不思議とちょいちょい聴きたくなってしまうから扱いがやっかいなのである。ただお断りしておくが、ルイスは卓越した演奏技能を身につけたピアニストだ。超絶技巧という点では、オスカー・ピーターソンに比肩するのではないだろうか。極めて強靭なタッチといい、ダイナミックな展開といい、目を見張るものがある。華麗なるピーターソンの愛好者からは、まともに取り合ってもらえないかもしれないが、実はぼくはルイスのほうが断然好きだ。
やっかいといえば、ルイスがとんでもないほどの多作家であるということも、ぼくにとっては迷惑千万である。おなじみのエルディ・ヤング(b)とアイザック “レッド” ホルト(ds)とともにトリオでレコーディングされたデビュー作『ラムゼイ・ルイス・アンド・ヒズ・ジェントルメン・オブ・スウィング』(1956年)から、2022年9月12日にシカゴの自宅で永眠する寸前にソロ・ピアノで吹き込まれた『ザ・ビートルズ・ソングブック』(2022年)まで、面倒だけれど彼のアルバムをちょっと数えてみた。オマー・ハキム(ds)、ヴィクター・ベイリー(b)、グローヴァー・ワシントン・ジュニア(sax)なども参加したフュージョン・グループ、アーバン・ナイツのアルバムも含めると、なんと彼のリーダー作83枚にものぼる。

デビュー作をリリースしたころのルイスは21歳、まだ大学に在学中だった。それからピアノひとすじ66年である。しかもルイスはメンバーにこだわりがあるのか、長いキャリアに対して共演するミュージシャンの選択幅は非常に狭い。特にデビューから22作目の『ハング・オン・ラムゼイ!』(1965年)まで、ゲスト・プレイヤーの参加があったりストリングスが加えられたりすることはあったものの、ラムゼイ・ルイス・トリオのメンバーはまったく不動だった。まあこれだけたくさんのアルバムがリリースされたのだから、きっと当時、彼らの人気はよほど高かったのだろう。徐々にレパートリーの幅は広がっていき、演奏している当人たちにもこころから楽しんでいる様子が窺える。
いかんせん、ぼくの忍耐力は尽きた。このトリオの作品群は一聴、それなりに工夫が施されていて外観は変化しているようにも感じられるが、よく聴くと演奏に新味はないし変わり映えすることもない。そもそもルイスはピアノ演奏に関しては凄腕のひとだから、自分の弾きかたを変える気など毛頭ないのだろう。しかも、ルイスは作曲をしないひと。アレンジくらいはするのだろうが、それにも原曲と少し違う弾きかたをする程度のものにしか感じられない。彼は根っからのピアノ・プレイヤー。だからアートオリエンテッドな音楽を創造することはもちろんのこと、クリエイティヴな音楽性を前面に押し出すこともない。ルイスはいつでも申し分なく実力を振るっているのだが、その魅力が遺憾なく発揮されるのはライヴにおいて。スタジオ録音には不向きなひとなのである。
ルイスにはオーディエンスを上手く乗せて、自分もいっそう勢いづくようなところがある。そんなグルーヴィーな瞬間が記録されたのが、かの有名な『ジ・イン・クラウド』(1965年)。1965年5月13日から15日にかけて、ワシントンD.C.にあったクラブ、ボヘミアン・キャヴァーンズで行われたトリオによるライヴの実況録音だ。とにかくノリノリな客の歓声、女性客の鼻歌、それにプレイヤーの声まで入っていて、いかにライヴが大盛況であったかがよくわかる。シングルカットされミリオンセラーを記録したタイトル・ナンバー「ジ・イン・クラウド」は、もともと1964年、R&Bシンガーのドビー・グレイが歌ってヒットした曲。ルイスは曲を書かないひとだから、手っ取り早く流行っている曲を演ってしまう。結果的に、シングルもアルバムもよく売れたのだが──。
当初クラシックのコンサート・ピアニストを目指していた
ところが逆に、ルイスの音楽はこういうあざとさを抱えているからだろう、日本のジャズ・ファンには正面から向き合ってもらえないのである。とはいっても、くだけた感じのクラブで聴いているような気にさせられるのは、かなり楽しいもの。ぼくにとっては、このあたりも実にやっかいなのだ。まあ、ぼくが『ジ・イン・クラウド』をはじめて聴いたのは、1980年代に入ってからのこと。そのときの感覚では、正直なところ、すでに旬を過ぎたものとして聴こえた。いずれにしても、ルイスは流行りのファンキーでソウルフルなロック・ビートをもってして、大衆を大いに沸かせた。でももっとも騒いでいたのは、案外ジャズ以外の音楽ファンだったのではないだろうか。皮肉なことにルイス自身もこの大ヒットのせいで、しばらくポップ・ジャズ路線から抜け出せなくなってしまう。
そんなジレンマに陥ったルイスだが、卓越したピアノ・テクニックを有するだけに、なんとももったいない。膨大な数のリーダー作をリリースしていながら、いつも彼について真っ先に語られるのは『ジ・イン・クラウド』のことばかりで、ちょっとかわいそう。ああ、しまった!そういうぼくもご多分にもれず、おなじ轍を踏んでしまった。実はルイスのリーダー作のなかには、ほかにも予想外の出来栄えに思わずほくそ笑むようなものがいくつかある。彼の作品群はまさに玉石混淆なので、すべてを入手するのはちょっと憚られるし、あっさり見限ることもできないのである。ルイスは、常にダウン・トゥ・アースなダイナミック・レンジでしかも歯切れのいいピアニズムをキープ。それゆえ、それが上手く活かされたプロジェクトは自ずと完成度が高まるわけだ。
それでは、そんなヴィルトゥオーソと呼びたくなるようなルイスのピアノ演奏の格別な技巧や能力は、いかに涵養されたのだろうか?それは、あらためて彼のプロフィールを観ると得心がいく。ラムゼイ・ルイスは1935年5月27日、アメリカはイリノイ州のシカゴに生まれた。この世を去ることになる87歳まで、生涯ピアニストとして活躍した。ピアノを弾きはじめたのは6歳のとき。教会の聖歌隊のコンダクターだった父親の勧めで、クラシック・ピアノのレッスンを受けるようになった。その後、ルイスはイリノイのウィネットカ村にある名門シカゴ音楽院、シカゴ市のカトリック系の私立総合大学であるデポール大学音楽学部において、ピアノと音楽理論を学んだ。
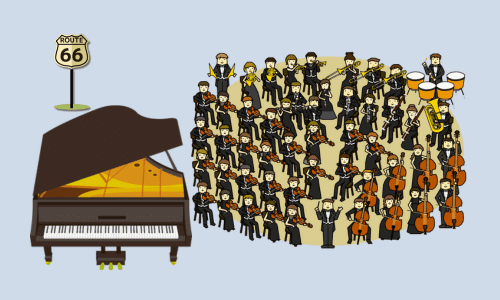
当初コンサート・ピアニストを目指していたルイスは、世界最高のオーケストラのひとつと称される、あのシカゴ交響楽団と共演しピアノ・コンチェルトを演奏したこともあるという。彼の演奏技術が格別に優れているのも当然というわけだ。しかしながら、もし彼がジャズへ転向することなくクラシックをつづけていたとしても、その後プロとして大成したかといえばいささか疑問である。音楽というものは世界共通の言語であるはずだが、実際はそうではない。おかしなことだが、実際クラシックの世界ではアフリカ系アメリカ人の音楽家は非常に少ない。現代社会が多様性を尊重する傾向にあるのにもかかわらず、西洋の芸術音楽、ことに古典の世界は、残念ながらまだまだ閉鎖的なのである。
いくばくか横道に逸れてしまったようなので、はなしを戻そう。結局ルイスはコンサート・ピアニストの道を断念したが、クラシック音楽に対する思慕の念が消えることはなかったのかもしれない。思い起こせば、彼はデビュー・アルバムでジョルジュ・ビゼーの「カルメン」を弾いていた。忘れたころに『レ・フルール』(1983年)というアルバムでフレデリック・ショパンの「前奏曲 ホ短調 作品28の4」も弾いた。こちらはシカゴ・ソウルの立役者、TOM TOM 84ことトーマス・ワシントンがアレンジを施し「エッセンス・オブ・ラヴ」というタイトルのスタイリッシュなナンバーに変換されている。さらにルイスは『タイム・フォー・ラヴ』(1988年)で、英国が誇るフィルハーモニア管弦楽団とも共演。コンダクターはシカゴの名アレンジャー、ジェームス・マックが務めた。
そんなクラシックへの思いを残しつつも、ルイスはジャズの道へ進んだわけだが、きっかけは大学時代のアルバイトだった。彼は学生時代、日なかはデパートのレコード売り場で店員として働き、夜になるとクレフスというバンドのピアニストとしてクラブで日銭を稼いだ。そのバンドにおいて前述のヤングとホルトに出会う。彼らの演奏はシカゴ近辺においてすぐに話題となり、地元のレコード会社であるアーゴ(のちのカデット・レコード)が、このトリオにレコーディングをもちかける。デビュー作の売れ行きは思いのほか好調で、同系列のレーベルにおいて16年の間にルイスのアルバムは計38枚もリリースされた。作品の出来具合のよしあしはともかく、やはりルイスはアーゴ・レコードのドル箱スターだったのだろう。
人気があるゆえに、ルイスのレコードは次々に制作される。作品の数が多ければ、そこに宝玉と石ころが混じり合っていても致しかたない。ただ繰り返しになるが、ルイスはピアノ演奏に徹しつづけた。おそらく彼は、自分がひとえにピアニストであるべきと思っていたのだろう。その点においては、無論あざとさではなく賢明さが感じられる。イングランドの詩人、ジェフリー・チョーサーも云っているではないか。己を知りうる者は賢者なり──と。ピアノひとすじ66年、そのテクニックはまったく衰え知らずだった。そんなルイスのアルバムが宝玉のごとき完成度の高さを誇るとき、必ずと云っていいほど、彼のピアノ演奏を上手く活かしたプロジェクトを推進する、縁の下の力もちがいたのである。
カリンバ・プロダクションの最初期の作品にしてルイスの最高傑作
たとえば1960年代にルイスを支えた人物といえば、シンガーソングライターのテリー・キャリアーや女性ジャズ・シンガーのマリーナ・ショウの作品を手がけた、チェス・レコードのハウス・アレンジャー、リチャード・エヴァンスが挙げられる。ラテン好きのぼくにとって愛聴盤となっている『ラムゼイ・ルイスのラテンで行こう!』(1967年)は、エヴァンスがアレンジを担当。ルイスのソウルフルなピアノを中心としたリズム・セクションと、ボサノヴァ、ブーガルー、アフロ・キューバンなどのフィーリングが活かされたオーケストラが見事にミックスされている。1970年代では、ディスコ・ファンクがお得意なプロデューサー&アレンジャーのバート・ドゥ・コトーの存在も忘れることができない。DJ/クラブ世代に人気の『ラヴ・ノーツ』(1977年)『テキーラ・モッキンバード』(1977年)は、彼が手がけた作品だ。
あともうひとり、45歳という若さでこの世を去った伝説的プロデューサー、アレンジャー、そしてコンポーザーのチャールズ・ステップニーが、ことに抜きん出ていた。彼がルイスの作品で果たした功績は、非常に大きい。ステップニーはやはりシカゴ生まれで、さきに挙げたエヴァンスと同様にチェス・レコードで活躍した。のちにアース・ウインド&ファイアの作品も手がけることになるが、それはもとはといえば、彼がルイスのリーダー作『処女航海』(1968年)にアレンジャー、ソングライターとして参加したことに端を発する。当時のラムゼイ・ルイス・トリオでは、すでにヤングとホルトは脱退しており、クリーヴランド・イートン(b)とモーリス・ホワイト(ds)がサイドを務めていた。云うまでもなく、ホワイトはEW&Fのリーダーである。
ステップニーとホワイトは、1976年にカリンバ・プロダクションを共同設立した。カリンバとはアフリカの楽器で、鉄や竹の棒を親指で弾いて演奏することからサムピアノとも呼ばれる。ホワイトの愛用する楽器として有名だが、弾きかたを教えたのはルイスだ。そんなルイス、ステップニー、ホワイトといった組み合わせが生んだ最大の成果物といえば、コロムビア・レコード時代のルイスのリーダー作『サロンゴ』(1976年)ではないだろうか。ちょうどエモーションズの『恋のチャンス/愛に咲く花』(1976年)とEW&Fの『魂 スピリット』(1976年)とに挟まれてリリースされた、カリンバ・プロダクションの最初期の作品だ。同年5月に心臓発作で急逝したステップニーへの追悼盤でもある。実はぼくは、この『サロンゴ』をルイスの最高傑作と観ている。
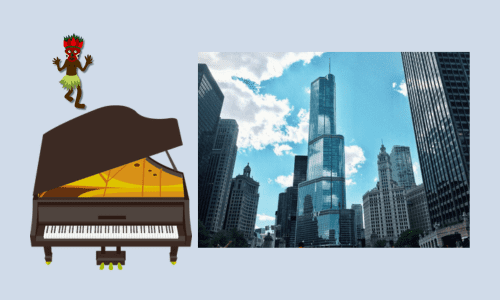
前作『ラムゼイ・ショック!』(1975年)もステップニーが手がけた作品だが、どちらかといえばメロウ・グルーヴなサウンドが目立った。それに比べて初のL.A.録音である『サロンゴ』は、ジャズ/フュージョン色が強くなっている。なおルイスは本作でも、作曲はひとまかせ。オープナーの「スリック」は、まさにジャジーなファンキー・フュージョン。ホワイトとステップニーの共作。短いストライド・ピアノ風のイントロから、いきなりレオン・ンドゥグ・チャンクラーのドラムスによる歯切れのいいリズムへ──。つづいて軽快なベース・ラインをトロンボーンがなぞる。さらにホーンズによるトレモロが活かされたテーマが緊張感を与える。その後トランペット、テナー、そしてルイスのピアノがスリリングなソロを展開。文句なしに名曲だ。なお大野雄二の「大追跡のテーマ」(1978年)のもとネタでもある。
つづく「オーフ・ウードゥ」はダーク・レクロウ・ラヒームの曲。アフロなミディアム・ファンクでルイスはシンセをプレイ。ラヒームのアーシーなフルートもいい。インタールードの「ルバート」はステップニーの曲。ホーンズ&ストリングスのシンフォニック・サウンドがマジェスティックに響く。前半ラストの「サロンゴ」はバイロン・グレゴリーの曲。ディスコティークで盛り上がりそうなナンバー。グレゴリーのギターとラヒームのフルートがフィーチュアされるが、彼らはルイスのアルバムではおなじみのふたり。ルイスもフェンダー・ローズで楽しげにアドリブを繰り広げる。そして、エンディングにふたたびストライド・ピアノが登場する。ここまで聴いただけでも、本作のフュージョン・サウンドには、アフリカとラテンが隠し味となっていることがわかる。
後半、最初の「ブラジリカ」はホワイトとギタリストのマーティン・ヤーブロウの共作。EW&Fのサウンドを彷彿させるブラジリアン・フュージョン。アーニー・ワッツのテナーがフィーチュアされたあと、おもむろに音を鳴らしはじめるルイスのローズが、次第に力を入れて激しく擦るようなプレイになっていくのがカッコイイ。この曲はルイスのお気に入りらしく『アイヴォリー・ピラミッド』(1992年)や『アーバン・ナイツ VI』(2005年)でも採り上げられた。つづく「ニコル」はフィフス・アヴェニュー・バンドのリード・シンガーだったソングライターのジョン・リンドの曲。ローズの音色が美しいリリカルなバラード演奏。オケが入ってからは、ピアノがダイナミックでファンキーな展開を見せる。ピアノひとすじであるルイスの面目躍如たる演奏だ。
ラストの「セヴンス・フォールド」はステップニーの曲。ちょっとミステリアスでアーバンなサウンドは、ルイスのアルバムでは珍しい。洗練された曲想のなかでギター、ローズ、テナーなどがソロをとるが、徐々にジャム・セッション風になっていくのが、幕引きに相応しい。こうしてあらためて本作を聴いてみると、ルイスのピアノの登場シーンがいつもより少ないことに気づかされる。しかしながら、彼はいざ登場すれば自分のピアニズムを躍動的に打ち出してくる。そういう采配を振りながら、ルイスをポップ・ジャズ路線からジャズ・ファンクを核とするフュージョンへと導いた、ホワイトとステップニーの簀の子の下の舞としての手腕はお見事である。こういう傑作があるから、ラムゼイ・ルイスというピアニストは、ほんとうにやっかいなのだ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント