胸が熱くなるワン・アンド・オンリーのコラボレーション

Album : Full Moon / Full Moon Featuring Neil Larsen & Buzz Feiten (1982)
Today’s Tune : The Visitor
フュージョンはジャズの一部ではない──ジャズのないものもある
フュージョンといえば、一般的に(CDショップやラジオ・ステーションなどで)、ジャズをスタイルごとに細分化したときの、分類項目のひとつとして扱われている。確かにそう呼ばれる音楽には、ジャズから派生したものがたくさん存在する。しかしながら、ぼくは、フュージョンは決してジャズの一部ではないと考えている。このブログのカテゴリーで、敢えてジャズとフュージョンをわけているのは、実はそういう観点からなのだ。もとはといえば、このジャンル名は──「フュージョン」=「融合」であり、フュージョン以前の呼称「クロスオーヴァー」=「交差」というところから、様々な要素が混合した新たな形態ということを意味するものだった。
ということは、フュージョンと呼ばれる音楽のなかに、必ずしもジャズの要素が入っていなくてもいいのではないだろうか?ぼくは、単純にそう捉えている。カテゴリーとは飽くまで便宜上、要されるものであって、音楽性をしばるものであってはいけないと、ぼくは思う。よくマイルス・デイヴィスが1960年代後半に演っていたエレクトリック・ジャズが、フュージョンの原点と云われるけれど、正直なところ、ぼくはその見解にあまり賛同することができない。電気楽器が導入されればフュージョンなのかというと、そういうものではないと思う。
逆に──もとトランペッターでビッグ・バンドのアレンジャーとして、1950年代の中頃から1960年代後半まで大活躍した、クインシー・ジョーンズ──彼が1970年代からA&Mレコードでリリースした数々のヒット作は、当時クロスオーヴァー/フュージョンにカテゴライズされていたけれど、徐々に進化するそのサウンドは、1980年代に入るころには、ジャズとはほとんど関係のないものになっていた。それでいい。音楽に垣根は必要ないのだから──。それに、どちらかというとジャンルにとらわれることなく音楽を楽しむものからすると、脱カテゴリー・ミュージックみたいなものは、大歓迎である。

なぜクドクドとこのようなことを述べるのかというと、今回ご紹介するアーティストが、フュージョン・プレイヤーと目されながらも、ジャズとはひと味もふた味も違う音楽性をもった人物だから──。そのひととは、ロックンロールの殿堂入りを果たしたシンガーソングライター、レナード・コーエンをして「ハモンド B-3のもっとも優れた演奏者」と云わしめた、ニール・ラーセンである。ちなみにニールは、2008年から2013年までコーエンのレコーディングやコンサート・ツアーをサポートした──。それでは、当時類型化しはじめていたフュージョン・サウンドとは一線を画す、時代を経ても色褪せることのない個性的な音世界を、気軽に楽しもう!
ということで──フュージョン・ミュージックにカテゴライズされながら、それこそフュージョン全盛期の作品とは趣きを異にする、ニール・ラーセンのグループ名義のアルバム『フル・ムーン』(1982年)について──。ぼくがニールの名前をはじめて知ったのは、彼のファースト・ソロ・アルバム『ジャングル・フィーヴァー』(1978年)が発売されたときのこと。個人的には、このレコード──ロジャー・ニコルスやニック・デカロのヴォーカル作品ですでにその名に馴染んでいた、トミー・リピューマがプロデューサーを務める、新生ホライズン・レコードからのリリースと知って、興味をもった。
同時代のキーボーディストのなかでも、ひときわ異彩を放っている
それまで、A&Mレコードのジャズやファンク部門のサブレーベルだったホライズン・レコードには、はっきり云って、ぼくはまったく関心を寄せていなかった。ところが、当時ワーナー・ブラザースにおいて、スタッフをはじめジョージ・ベンソンやマイケル・フランクスなどの名作を世に送り出したばかりのリピューマのことだから、ホライズンでもきっと何か面白いことをやるだろうと、勝手に推しはかったというわけ──。思い返せば、そのころの自分はとんでもないマセガキだったと思うけれど、それだけ音楽に敏感だったということなのだろう──ぼくの勘はあたった。
新生ホライズンのアーティストといえば、マーク=アーモンド、ドクター・ジョン、デヴィッド・グリスマン、リチャード・エヴァンス、ゴードン・マイケルズ、ブレンダ・ラッセル、ベン・シドラン、シーウィンドなど、どちらかといえばロック系のアーティストが多い。ところが、それらの作品のレコーディング・メンバーのクレジットをチェックしてみると、クロスオーヴァー/フュージョン系の(それも有名な)ミュージシャンたちの名前が大多数を占めていたりする。当然のことながら、出来したサウンドもロックにしては洗練された感じだし、フュージョンにしてはややポップだ。それでいて、主役の音楽性が大きく変わったりすることもないのだから、さすがリピューマだ!
ニール・ラーセンの場合もご多分にもれず、同時代のフュージョン系キーボーディストの作品のなかでも、ひときわ異彩を放っている。たとえば、彼の楽曲には、ジャズ特有の複雑なコード・ワークがほとんど観られない。そこから発生する即興演奏においても、当然のごとく激しくスケール・アウトすることはないし、テンション・ノートでさえあまり使われていない。それでいて、ペンタトニックやブルースの音階を上手く用いて、哀愁の漂うフレーズをよく歌わせているのだ。つまり、彼の音楽のルーツは(聴いてはいただろうが)ジャズではなくて、ロックやリズム・アンド・ブルースなのではないだろうか?
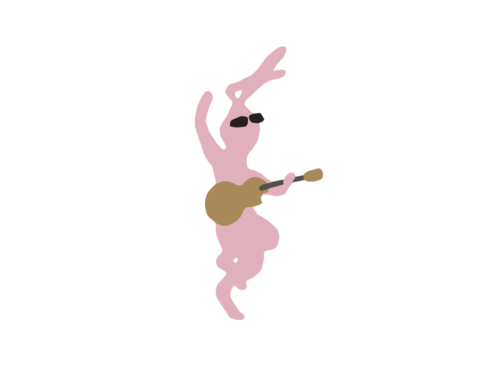
そしてニールの独特なサウンドが生み出されるもうひとつの要因といえば、やはりコーエンが指摘していたように、ハモンド・オルガンとレスリー・スピーカーの使用である。彼はアコースティック・ピアノやフェンダー・ローズも弾くけれど、メインの鍵盤楽器としては、逡巡することなくハモンドを好んで使うのだ。1970年代後半といえば、モーグ・シンセサイザーが急速に発展していた時期ということもあり、ジャズやフュージョンにおいて、ハモンドが楽曲の根幹に据えられることはおろか、隠し味としてさえ使用されることもレアなケースとなっていた。そのことをニールは故意に逆手にとったわけではないだろうが、結果的にはそれが彼の個性となった。
さらに、ニールの楽曲のユニークなサウンドが生成されるとき、なくてはならない重要な構成要素がまだある。彼の僚友、バジー・フェイトンのギターだ。メロディ・ラインをニールのハモンドとユニゾンで演奏したり、アドリブ・パートではレイドバックとラグに溢れたフレーズで鳴きまくったり──とにかく、ニールの無駄を削ぎ落としたような音楽性と相性がとてもいい(バジーはニールの四枚のソロ作に参加)。そしてそのプレイから、バジーもまたロックンロールやリズム・アンド・ブルースのひとと、すぐにわかるのだ。そのことは、ポール・バターフィールド・ブルース・バンドやラスカルズのメンバーだったという、彼の過去の経歴からも明らかだ。
いつかラーセン=フェイトンのようなバンドを作ろう!
1980年、ホライズン・レコードの閉鎖にともない、リピューマはワーナー・ブラザースへ復帰。彼のプロデュースのもと、ニールはバジーとともに『ラーセン=フェイトン・バンド』をリリース。おりしも、クルセイダーズ、リー・リトナー、ジョージ・ベンソン、グローヴァー・ワシントンJr.などの人気フュージョン系のアーティストたちがこぞってヴォーカル・ナンバーをフィーチュアしてAORに急接近していた──ということもあってか、バジーはもちろんニールまで歌唱を披露。シングルカットされた「今夜はきまぐれ」はスマッシュ・ヒットとなった。このあたり──モノクロームのニールとバジーの顔が大写しになったジャケットも含めて、リピューマのプロデュース能力に並々ならぬものが感じられる。
そして、2年後──ラーセン=フェイトン・バンドはセカンド・アルバム『フル・ムーン』をリリース。バンドのメンバーは、前作同様、ニールとバジー、それにアート・ロドリゲス(ds)とレニー・カストロ(perc)の四人。ベーシストは正規のメンバーが不在で、ドゥービー・ブラザーズのウィリー・ウィークスとイエロージャケッツのジミー・ハスリップが、サポーターとして参加。ライヴのほうでは、1990年代後半、スムース・ジャズ系のグループ、アバーヴ・ザ・クラウズのメンバーでプロデュースも務めた、ヴァーノン・ポーターがベースを弾いていたので、あるいは彼が正式なメンバーだったのかもしれない。
本作の楽曲は、ニールのインストゥルメンタル(今回は歌っていない)、バジーのヴォーカル・チューン──それぞれ四曲ずつ計八曲となっている。まずバジーの曲──バウンスするグルーヴが気持ちいい、ちょっとスモーキーな「ファントム・オブ・ザ・フットライツ」チルアウトした雰囲気の「トワイライト・ムーン」ストレートなロックンロール「ブラウン・アイズ」レゲエ風の「スタンディング・イン・ライン」と、曲調がヴァラエティに富んでいる。

ニールのほうは──ヤマハ・エレクトリック・グランドによる和音の八分きざみとドラムスのリムショットの四分きざみが印象的な「シエラ」シンコペーテッドでちょっとクセのある「ヒーローズ・ウェルカム」レニーのパーカッションも活躍するサンバ「リトル・カウボーイ」デヴィッド・サンボーン(as)をゲストに迎えた「訪問者」(1981年にモントルーで行われたライヴではロベン・フォードのギター・ソロが素晴らしかった──2021年発売の『カジノ・ライツ・ツインズ』に収録)と、バジーの曲にも同じことが云えるのだけれど、前作よりも微妙に大衆路線から外れていて、トータルするとバンドのコンセプトがより強化されたように感じられる。
ニールのハモンドとバジーのギターによるコンビネーションのよさは健在なのだけれど、本作では、間違いなくワンランク上のサウンドが目指されている。そのことは(日本盤では混乱を避けるためラーセン=フェイトン・バンドと表記されているが)、バンド名がフル・ムーンに変わったことが、端的に示しているのではないだろうか?フル・ムーンといえば、1972年にアルバムを一枚だけ残して消滅したブルー・アイド・ソウルの隠れた名グループで、ラーセン=フェイトンの原点でもある。バンド名の変更は、売れ線を意識せず、ときには先鋭的になったとしても、自分たちの好きな音楽を演ろう──そんなふたりの意志を象徴するものなのかもしれない。
すっかり長くなってしまったが、そのついでに蛇足ながら個人的なエピソードを──。本作が発売された年──高校生だったぼくは(年齢がバレるね)、シンガーである菊池真美さんの『縞馬に乗ったセクレタリー』(1982年)というレコードを聴いて、すっかりラーセン=フェイトンに魅了された、軽音楽部でギターを弾いていたMくんと、そのころ新宿五丁目にあった東京厚生年金会館にフル・ムーンの来日公演を観にいった(ちなみにMくんの彼女もギターの弾き語りをしていて菊池さんに師事していた)。その帰路、興奮冷めやらぬMくんとぼくは「いつかラーセン=フェイトンのようなバンドを作ろう!」と、夜空に浮かぶ月に向かって誓い合った(実現しなかったけれど──)。青かったねぇ。そんなわけで、このワン・アンド・オンリーのコラボレーションを聴くと、ぼくはいまでも胸が熱くなるのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント