リー・リトナー&デイヴ・グルーシンのブラジル音楽、延いては音の芸術に対する深い愛情が際立った『ブラジル』
 Album : Lee Ritenour & Dave Grusin / Brasil (2024)
Album : Lee Ritenour & Dave Grusin / Brasil (2024)
Today’s Tune : Canto Invierno (Winter Song)
名コラボレーションとハイクオリティのブラジリアン・サウンド
リー・リトナーとデイヴ・グルーシンのコラボレーション・アルバム『ブラジル』(2024年)が、ぼくの手もとにも届いた。この新作のリリースを機に、このブログでも彼らのかつてのコラボ作品『ハーレクイン』(1985年)を採り上げた。そのときも触れたのだれど、国内盤の発売元であるポニーキャニオンの公式ページにある「40年の時を経て、リトナー&グルーシンが名作の続編を完成!」というコピーに、ぼくはなにかすっきりしない感じがした。というのも、ぼくはかねてから『ハーレクイン』が単なるブラジル音楽にちなんだ作品とは、観ていなかったからだ。ここで詳しくは語らないけれど、要はそれだけでは片付けることのできない奇跡的な作品と、ぼくはこの旧作を高く評価しているのである。
まあ、それは置いておいて、リトナーにしてもグルーシンにしても、もはやレジェンダリー・ミュージシャンと呼ぶべき存在であり、2024年でそれぞれ72歳と90歳という高齢者でもある。まずは、ふたりのコラボレーションが健在であることを、素直に喜びたいと思う。しかしながらそういう思いがあるいっぽうで、正直に告白すると今回の新作のリリースについて、ぼくは少年時代のように期待に胸を膨らませるようなことはなかった。現にCDが自宅に届いてもすぐに封を切ることはなく、いまのいままで放置しておいたくらいだ。なぜかというと、リトナーとグルーシンのこの10年の音楽活動を顧みたとき、ふたりにはもはや、往年の獅子奮迅のごとき活躍を見せていたころのヴァイタリティは、さすがになかったからだ。
特にグルーシンは、加齢による演奏能力の衰えを感じさせたり、そのせいか自ら第一線から退くような印象を与える。近年リーダーとしてはもちろんのこと、サイドマンとしても音楽作品からすっかり遠ざかり、たまに地味なドキュメンタリー映画の音楽に携わるくらいのグルーシン。きっと今回の新作においても、彼のプレイはしごく落ち着いたものになるのだろうと、ぼくは予想していたのである。そして実際にレコーディングは、事前にぼくが推し量ったのとほぼおなじ方向に進められていた。全盛期のグルーシンのパフォーマンスに見られる、聴くものの気持ちを高揚させるような躍動感と疾走感が溢れるキーボード・ワークは、すっかりトーンダウンしている。しかしながらそのサウンドから、彼のヒューマン・カインドネスが消えることはなかった。

そもそも今回のプロジェクトでは、企画段階からリトナーとグルーシンのヴィルトゥオーソとしての側面を強調することが目的とはされていないようだ。それが却ってふたりのブラジル音楽、延いては音の芸術に対する深い愛情を際立たせているように、ぼくは思う。ニュー・アルバム『ブラジル』は、リトナーとグルーシンがこれまでに影響を受けたブラジル音楽をリプレイするいっぽうで、現在彼らが注目するブラジリアン・ナンバーを、そのオリジネーターたちをそのままフィーチュアして、ニュー・アレンジで聴かせるという仕様。そういう方向性において『ブラジル』は、ブラジルの音楽にインスパイアされながらもコンテンポラリー・ジャズの可能性が追求された『ハーレクイン』とは、まったく趣きを異にする。
そう考えると、過去にリトナーとグルーシンがここまでブラジルに寄り添った作品はなかったかもしれない。変な云いまわしかもしれないが、本作におけるふたりのブラジリアン・ミュージックに対する斟酌の仕かたが、実に思慮深いのである。気障な云いかたをすれば、この『ブラジル』で彼らが展開しているのは、まさに大人の音楽ということになる。ジャズ、フュージョン、そしてフィルム・スコアにおいて、キーボーディスト、コンポーザー、アレンジャー、プロデューサーとして長いキャリアをもつグルーシン。グルーシンのサポートによりデビューを果たした、フュージョン・ギターの雄であるリトナー。両者のアーリー・ワークスには、すでにブラジル音楽の要素が導入されていたが、それは穏やかに熟成が進んでいき、いま実にまろやかな味わいとなっている。
いっぽう本作では、ぼくの想像の域を遥かに超える収穫もあった。それは今回のリズム・セクションが、ブラジリアン・サウンドをハイクオリティのものにする機能を、抜群に発揮しているということだ。今回のメンバーといえば、リトナーとグルーシン以外はすべてブラジル人。ベーシックなレコーディングは、ブラジル音楽産業の中心となっている南半球最大のメガシティ、サンパウロで行われた。ブラジル勢は、ブルーノ・ミゴット(b)、エドゥ・ヒベイロ(ds)、マルセロ・コスタ(perc)の3人。サンパウロ出身のミゴットは渡辺貞夫のブラジル録音『オウトラ・ヴェス~ふたたび~』(2013年)に参加、その際来日も果たしている。本作でもフィーチュアされている、シコ・ピニェイロの4枚目のリーダー作『シティ・オブ・ドリームス』(2020年)のベースも、彼によるものだ。
ヒベイロはサンパウロの人気ジャズ・ユニット、トリオ・コヘンチのドラマー。本作においては、彼のドラミングが圧巻。ブラジルのリズムとジャズのテクニック&メソッドの融合、そして絶妙なバランス感覚が素晴らしい。なおヒベイロのトリオ作『ニュース』(2022年)には、ミゴットも参加している。カリオカのパーカッショニストでドラマーでもある、コスタはいわゆるブラジルではファーストコール・ミュージシャン。カエターノ・ヴェローゾ、マリア・ベターニア、ガル・コスタなど、多くのアーティストをサポートしてきた。ある意味で、MPB(ムジカ・ポプラール・ブラジレイラ)の陰の立役者と云える。サンバ、フォーク、ロックを超越した女性シンガーソングライター、マリーザ・モンチのグループで来日も果たしている。
(『ハーレクイン』については、下の記事をお読みいただければ幸いです)
リトナーとグルーシンのインスピレーションの源となったブラジル音楽
本作で創出されたサウンドには、独特のフォーマット、グルーヴ、カラー、あるいはそれらの結合から、リスナーの聴覚にある種の美感を与えるものがある。その大きな要因は、上記の本場ブラジルのミュージシャンをリズム・セクションに起用したことと、ぼくは思う。考えてみれば、グルーシンがおよそ12時間のフライトを経てサンパウロに赴き、現地のミュージシャンとレコーディングするというのは、はじめてのことではなかったか。かたやリトナーは、アコースティック・ギターをフィーチュアした『リー・リトナー・イン・リオ』(1979年)において、リオデジャネイロに渡りルイザォン・マイア(b)やパウリーニョ・ブラガ(ds)らと共演しているが、全7曲中2曲のみのことである。
かつての名作『ハーレクイン』のトラックは、すべてカリフォルニア州ハリウッドで吹き込まれた。リズム・セクションは西海岸の敏腕スタジオ・ミュージシャンたちで、ガッチリ固められている。そんな状況を考慮しても、単純に『ブラジル』が『ハーレクイン』の続編と云い切ってしまうことには、やはり釈然としないものがある。コンテンポラリー・ジャズがサウンドの主体となる『ハーレクイン』に対し、明らかに『ブラジル』という作品には、リスナーの心身をリフレッシュするような、太陽と大地、そして潮風が生み出す自然の香りが漂っている。もちろん、リトナーとグルーシンのプレイには、洗練されたジャズのエッセンスが感じられる。それにも増して際立つのは、ブラジル勢が紡ぐ清涼感に溢れるフレーズやリズムなのである。
やはりブラジル音楽は、素晴らしい。リトナーとグルーシンが自らの音楽のインスピレーションの源となったブラジリアン・ミュージックは、ボサノヴァ時代にはじまる。ボサノヴァは、1950年代にリオデジャネイロのコパカバーナやイパネマといった海岸地区で生まれた音楽だけれど、ふたりがその影響を受けたのは、1960年代に入ってからだろう。スタン・ゲッツ(ts)、ズート・シムズ(ts)、クインシー・ジョーンズ(arr)といったアメリカのミュージシャンが、ボサノヴァ作品をリリースしはじめたころだ。ブラジルのピアニスト、セルジオ・メンデスがカーネギー・ホールでのコンサートに出演したのも1962年のこと。ご存知のとおり、リトナーとグルーシンの仲を取りもったのは、だれあろうセルメンである。
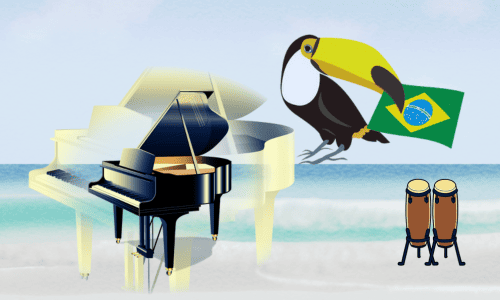
思い起こせば、ぼくもリトナーやグルーシンとほぼおなじタイミングでブラジル音楽を体験してきた。1960年代、ヴァーヴ、CTIといったレーベルからリリースされたアントニオ・カルロス・ジョビンのボサノヴァ作品に、無意識に馴染んでいた。1970年代、ウェイン・ショーター(ts, ss)の『ネイティヴ・ダンサー』(1975年)でフィーチュアされたことから、ミルトン・ナシメントの作品をよく聴くようになった。ぼくにとっては、はじめてのMPB体験だったと思う。1980年代には、クインシー・ジョーンズが手がけたアルバムに収録されていた楽曲からイヴァン・リンスの名を知り、彼のレコードを買い漁った。彼は作曲において特異なコード進行を用いるのだが、ぼくにとっては衝撃的だった。その間、セルメンのアルバムも、継続的に聴いていた。
ということで、ぼくにとってブラジリアン・ミュージックは、ジャズに次ぐ重要な音楽と云える。では、酷暑にへばるばかりの今日このごろ、一服の清涼剤ともなる『ブラジル』を聴いて、爽快な気分を味わおうではないか──。なお、本作のプロデュースとアレンジは、リトナーとグルーシンの共同作業となっている。レコーディングとミキシングにおいては、フィラデルフィア・ソウルの代表的グループ、ザ・スピナーズの『新しき夜明け』(1974年)の濃密なサウンドで知られる、ドン・マレーがエンジニアを務めている。マレー自身もギターを弾くが、彼はリトナーをそのセカンド・アルバム『キャプテン・フィンガーズ』(1977年)から支えている。前述の『リー・リトナー・イン・リオ』も『ハーレクイン』も、彼が手がけた作品である。
それでは、ヴァモス・クルチール・ムジカ!──アルバムの幕開けは、ミルトン・ナシメントの「クラヴォ・イ・カネーラ(クローヴ・アンド・シナモン)」だ。ナシメントとギタリストでありシンガーソングライターでもあるロー・ボルジェスとの、2枚組共演盤『街角クラブ〜クルービ・ダ・エスキーナ』(1972年)からの1曲。ふたりの少年が写った写真がジャケットにあしらわれた、あのレコードだ。ブラジルの民族音楽タンボーリス・ジ・ミナスのリズムが活かされた、ナシメントの代表曲のひとつ。作詞は本作に参加しているセルソ・フォンセカともコラボした、ホナルド バストス。なおクルービ・ダ・エスキーナとは、ブラジル南東部のミナス・ジェライス州、ベロ・オリゾンチ市に集うミュージシャンたちの呼び名である。
ナシメントはこの曲を『ミルトン』(1976年)というアルバムでセルフ・カヴァーしているのだが、こちらではハービー・ハンコックがピアノを弾いている。また、このアルバムにはウェイン・ショーターも参加しており、前述の『ネイティヴ・ダンサー』と関係が深い。ほかにも多くのアーティストにこの曲は採り上げられているけれど、忘れることができないのはジョージ・デューク(key)の『ブラジリアン・ラヴ・アフェア』(1980年)に収録されているヴァージョン。ナシメント本人の歌唱も然ることながら、デュークが操る各種のシンセサイザーがこの曲によく合っている。ちなみにコーラスには、イヴァン・リンスのもとの奥さま、ルシーニャ・リンスも参加している。
新たなレジェンド──ほかのアーティストではなし得ないもの
ところで今回の演奏でこの曲は、ほぼ原曲どおりのアレンジで進行する。リトナーのエレクトリック・ギターがシングル・トーンでシンプルにテーマとサビを提示したあと、ヴォーカルが重なってくる。歌っているのは、そのクリスタル・ヴォイスが話題となったサンパウロの新進女性シンガー、タチアナ・パーハ。抑えめの歌唱が、アンサンブルに溶け込む。グルーシンのアコースティック・ピアノ、リトナーのギター、そしてグレゴア・マレのハーモニカがソロを執る。平明で落ち着いた感じのアドリブに、熟成香が漂う。ヒベイロのドラムスが刻む、サンバのリズムも快調。清澄な空気をつくっているマレは、いまは亡きトゥーツ・シールマンスの後継者と目されるスイス出身のジャズ・ハーモニシストだ。
つづく「フォー・ザ・パームズ」はリトナーの新曲。転調を効かせたテーマ部が、往年のグルーシンの曲を彷彿させる。そのせいか、グルーシンのピアノ・ソロが、程よいスウィング感を醸し出している。彼を敬愛するぼくとしては、嬉しくなる瞬間である。マレの哀愁を帯びたハーモニカも、静謐なオブリガートでサウンドに潤いを与えている。リトナーのアコースティック・ギターによる、ジャジーでありクラシカルでもあるアプローチは極上。ヒベイロはスマートなブラシ・ワークに専念。ミゴットもここではアコースティック・ベースにもち替えている。釈は短めだが、ニュー・ステージのアコースティック・フュージョンを予感させる、清らかで美しいジャズ・ワルツに仕上がっている。
3曲目は、グルーシンのアルバム『ジェントル・サウンド』(1978年)からのナンバー「カタヴェント」である。原曲はミルトン・ナシメントのデビュー・アルバム『トラヴェシーア』(1967年)に収録されているが、一般的にはつづくCTIレコードからリリースされた『コーリッジ』(1969年)のヴァージョンで周知された。かつてのグルーシンは、この曲をスティーヴ・ガッド(ds)を主軸に据えたニューヨークのリズム隊で、かっちりしたサンバとしてプレイしていたが、ここでは鷹揚な律動を際立たせている。それがよりブラジリアン・ミュージック特有の爽快感と清涼感を引き立てている。以前はフェンダー・ローズでよくバウンスしていたグルーシンも、今回はアコースティック・ピアノでゆったりと玉を転がすように鍵盤を動かしている。
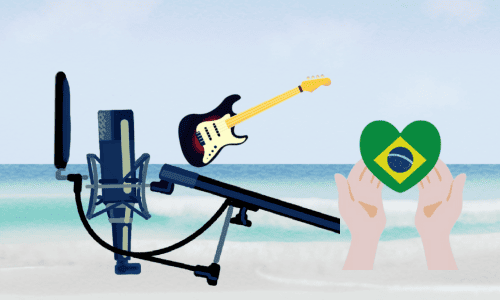
4曲目は、イヴァン・リンスのヴォーカルをフィーチュアした「ヴィトリオーザ」で、オリジナルは彼のソン・リヴレ移籍第1作『イヴァン・リンス』(1986年)に収録されている。リンスの『ハーレクイン』への参加に対する返礼のごとく、グルーシンがプロデュースとアレンジを手がけた。レコーディングもマレーによる。まだ幼かったリンスの息子、クラウディオ・リンスのスキャットも微笑ましかった。今回はリンスとパーハとによるデュエットで、さざ波に揺れる夕陰と頬をなでてくるそよ風が交じり合うような、優しくて爽やかな雰囲気が絶品。グルーシンのピアノによるバッキングも温かい。なおリンスはこの曲を、彼を長年アレンジとキーボードで支えた、ジルソン・ペランゼッタとのコラボ作『クンプリシダージ』(2017年)でも、歌っている。
アルバムの折り返しとなる「メウ・サンバ・トルト」は、セルソ・フォンセカの『ナチュラル』(2003年)からのチョイス。フォンセカは、ギタリストとしても活躍するカリオカのシンガーソングライター。シンプルなミッド・テンポのサンバだが、ブルージーな曲調とフォンセカのカジュアルなヴォーカルが、アーバンなムードを演出。パーハのサポートもこざっぱりとしていて、いい感じ。つづく「ストーン・フラワー」は、アントニオ・カルロス・ジョビンの『ストーン・フラワー』(1970年)からのナンバー。ジョビンの作品のなかでも、エスノフューチャリズム路線の曲だ。ここでバンドは、マラカトゥのリズムに乗って、ハードコアなコンテンポラリー・ジャズを展開。力強く聴き応え抜群だ。かつてリトナーは、この曲を『ツイスト・オブ・ジョビン』(1997年)でも採り上げた。
7曲目の「ボーカ・ヂ・シリ」は、どこまでもリフレッシングで軽快なサンバ。これまでニューヨークのジャズ・シーンで注目されてきた天才ギタリスト&シンガー、シコ・ピニェイロがフィーチュアされている。オリジナルは彼の『ゼアズ・ア・ストーム・インサイド(フロール・ジ・フォーゴ)』(2010年)に収録されている。カエターノ・ヴェローゾを彷彿させる美声と柔らかな語り口が、繊細な波音と心地いい涼風をイメージさせる。グルーシンによるローズも思わず跳ねる、まさに気分爽快な1曲だ。つづくリトナーのオリジナル「リル・ロック・ウェイ」においても、シンコペーションやモジュレーションによって、実に清々しい空気が生み出されている。ファンキーなパートもあるが、飽くまでドライ。リトナーのギター、パーハのスキャット、それにマレのハーモニカも小気味いい。
アルバムのラストを飾る「カント・インヴィエルノ」は、グルーシンの旧作。曲名はスペイン語で「冬の歌」という意味だが、原曲は「エチュード」というタイトルの6拍子のボサノヴァで、リトナーの『キャプテンズ・ジャーニー』(1978年)に収録されていた。その後、リトナー&グルーシンの『トゥー・ワールド』(2000年)でも、再演された。ここではボサノヴァのリズムからスタートするものの、後半ではリハーモナイズしながらタンゴ風に展開するのが新鮮。リトナーのギターの心地いい音色とそれが紡ぎ出す美しい楽句、そしてグルーシンのリリカルなシングル・トーンとリズミカルな両手のコンビネーション──ここにあるグルーヴは、ほかのアーティストではなし得ない、ただひとつのもの。また、新たなレジェンドの誕生でもある。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。










コメント