長年の盟友であるデイヴ・グルーシンとリー・リトナーとによるブラジル出身のイヴァン・リンスをフィーチュアしたコラボレーション・アルバム『ハーレクイン』
 Album : Dave Grusin & Lee Ritenour / Harlequin (1985)
Album : Dave Grusin & Lee Ritenour / Harlequin (1985)
Today’s Tune : Silent Message
レジェンダリー・ミュージシャン──リトナー&グルーシンのこの10年
リー・リトナーにしてもデイヴ・グルーシンにしても、もはやレジェンダリー・ミュージシャンと呼ぶべき存在。月日の経つのは早いもので、キャプテン・フィンガーズという異名をとったリトナーも、すでに古希を迎えている。古希は古稀とも書くんだけれど、70歳まで生きるひとは稀であるという古来の思想に由来する。まあ、人生100年時代とも云われる昨今、音楽家としてはまだまだ活動すべき年齢ということになるのだろうか。それにしたって、グルーシンに至っては日本だったら数え年で卒寿祝いを済ませている年齢だ。コンポーザー、アレンジャー、キーボーディスト、コンダクター、プロデューサー、レコード会社の経営者として、八面六臂の活躍を見せていたころのヴァイタリティはさすがにない。
たとえば、グルーシンにとって音楽性においても人間性においても共通するものをもつ莫逆の友、日本を代表するサクソフォニスト、渡辺貞夫の『アンコール!』(2017年)というライヴ盤をお聴きになったことがあるだろうか。このアルバムの音源は、2016年12月11日、渋谷オーチャードホールにおいて、1980年に行われた伝説の武道館公演の楽曲が36年ぶりに再演されたもの。その伝説のコンサートは『渡辺貞夫ライヴ・アット武道館~ハウズ・エヴリシング』(1980年)という、2枚組のレコードに真空パックされている(CDでは楽曲が一部編集されている)。ニューヨークの敏腕ミュージシャンたちに交じってフェンダー・ローズとヤマハ・エレクトリック・グランドを弾きわけ、東京フィルハーモニー交響楽団を指揮していたのは、だれあろう46歳のグルーシンだった。
そして36年ぶりのコンサートにおいて、デイヴ・グルーシンはゲストに迎えられた。御年82歳であった。ファンにとってはたいへん興味深くもあり単純に嬉しくもあるプロジェクトだったのだが、残念なことにグルーシンのキーボード・ワークに、往年のプレイに見られた聴くものの気持ちを高揚させるような躍動感は、終始現われることはなかった。しかもこのときは、グルーシンはアレンジを手がけておらず、36年まえに彼が書いたスコアをトロンボーン奏者の村田陽一がリアレンジしていた。迫力のあるビッグバンド・サウンドも悪くはないのだが、グルーシンの表現力に富んだオーケストラルなテクスチュアに比べると、いささかもの足りない。グルーシンを敬愛するぼくとしても、一抹の寂しさを覚えざるを得なかった。
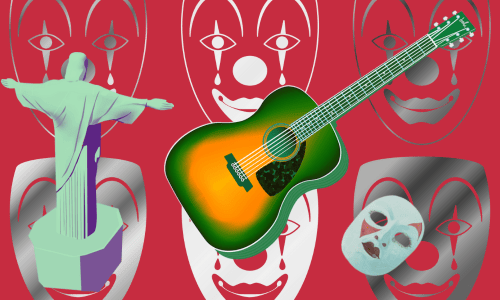
かたやリトナーのほうは、さすがにアルバム・リリースのペースは全盛期に比べるとダウンしているが、ギターをプレイすることへの熱意はまだまだ衰えていないようだ。ギターを弾きはじめてから60周年を迎えた際、彼ははじめてのソロ・ギター・アルバム『ドリームキャッチャー』(2020年)を制作した。それまでバンド、アンサンブル、コラボレーションといったスタイルで演奏してきたリトナーにとって、それは新たなるチャレンジだった。50年以上にも及ぶ輝かしいキャリアにおいて、やり残した試みに彼は意欲を燃やし演奏に対する集中力を高めた。結果、うっとりするほど心地いいギターの音色とそれが紡ぎ出す美しい楽句に、ぼくもわれを忘れて聴き入ってしまったのだが、リトナーはそんな強烈な魅力をもった作品を創出したのである。
そのときのリトナーは68歳だったが、若いころから変わることのない彼の向上心というか成長意欲の高さには、ほんとうに感服させられる。実はこのアルバムを制作する2年ほどまえ、リトナーはカリフォルニア州のマリブにあった自宅兼スタジオを山火事(ウールジー・ファイア)で失っている。およそ100本のギター、40台にも及ぶアンプ、大量の譜面、すなわち彼の築いたキャリアの歴史が一瞬にして灰燼に帰したのである。しかも火災の一週間後、リトナーはそれまで自覚症状のなかった大動脈弁疾患が判明したことから、すぐに手術を受けている。そんな不運にめげることなく、彼はおなじカリフォルニア州のマリナ・デル・レイに新居を構え、その簡易スタジオにおいて、たった7本のギター、そしてパソコンを頼りにアルバムを制作したのだった。
ところで、リトナーにとって新たな出発となった『ドリームキャッチャー』の収録曲のなかに「フォー・ディー・ジー」という洒落たハーモニー感覚が際立つナンバーがある。“ディー・ジー”とは“DG”、つまりデイヴ・グルーシンのイニシャルだ。リトナーはこの曲を、メロディをリハーモナイズしながら楽曲の魅力を最大限に引き出すという、グルーシンの特徴的なマナーをイメージして作曲したのだという。リトナーにとってグルーシンは、生涯のコラボレーター、そしてこころから打ち解け合える親友。今後もその絆が切れることはないだろう。前述のように近年、加齢による演奏能力の衰えを感じさせたり、そのせいか自ら第一線から退くような印象を与えるグルーシンだが、いまでもリトナーは彼をレコーディングに誘う。グルーシンもまた、それに応える。
前述の渡辺貞夫のオーチャードホールでのライヴのおよそ2年前、グルーシンはリトナーのレコーディングに参加している。リトナーの初期の楽曲から新曲まで全曲自身のオリジナル・ナンバーでまとめられた、セルフ・カヴァー・アルバム『ツイスト・オブ・リット』(2015年)の吹き込みである。ここでは残念ながら、往年のリトナーの作品のようにグルーシンのソフィスティケーテッドなアレンジは聴くことができない。アレンジはリトナーとキーボーディストのジョン・ビーズリーが担当している。それでもグルーシンは、プレイヤーとして13曲中7曲に参加している。全盛期の疾走感溢れるパフォーマンスはすっかり影を潜めたが、ピアノやフェンダー・ローズをはじめハモンド・オルガンやミニモーグ、それにクラヴィネットまで弾いている。それらのキーボード類が美味しいところで登場するのは、リトナーの粋な計らいだろう。
リトナー&グルーシンの新作『ブラジル』は『ハーレクイン』の続編?
さて、長々と語ってしまったが、実は間もなく『ブラジル』(2024年)というリトナーとグルーシンのコラボレーション・アルバムがリリースされる。海外盤はCDとLPがキャンディド・レコードから5月31日に、国内CDはポニーキャニオンから6月19日に発売される。日本でも8月3日にLPレコードが発売されるので、オーディオファイルのかたはそちらもどうぞ──。もうおわかりいただけたと思うけれど、リトナーとグルーシンの近年の様子を思うままに述懐したのも、これがいかに奇跡的な出来事であるかを、お伝えしたかったからなのである。リーダーとしてはもちろんのこと、サイドマンとしても音楽作品からすっかり遠ざかり、たまに地味なドキュメンタリー映画の音楽に携わるくらいのグルーシンが、まさかニュー・アルバムを制作するとは、ぼくは夢にも思わなかった。
このアルバムは、リトナーとグルーシンが共同でプロデュースをしたようだが、キッカケを作ったのはやはりリトナーのほうらしい。レコーディングはカリフォルニア州ロサンゼルスと、ブラジルのサンパウロで行われた。リズム・セクションに本場ブラジルのミュージシャンを起用するため、ふたりは遠路はるばる、およそ12時間のフライトを経て、現代においてブラジル音楽産業の中心となっている南半球最大のメガシティに乗り込んだのである。それだけブラジル音楽に寄せる、リトナーとグルーシンの想いは強い。今回のアルバムは、ふたりが注目するブラジリアン・ナンバーを、そのオリジネーターたちをそのままフィーチュアして、ニュー・アレンジで聴かせるという仕様。最高齢であるグルーシンのプレイはリラックスしたものになるだろうが、それでも楽しみである。
その内容にちょっとだけ触れると、 全9曲中4曲がポルトガル語で歌われるヴォーカル・ナンバーとなっている。シンガーを務めるのは、リトナー&グルーシンとの結びつきが強い、MPB(ムジカ・ポプラール・ブラジレイラ)の代表的なシンガーソングライター、イヴァン・リンス、ギタリストとしても活躍するカリオカ、セルソ・フォンセカ、これまでニューヨークのジャズ・シーンで注目されてきた天才ギタリスト&シンガー、シコ・ピニェイロ、そして、そのクリスタル・ヴォイスが話題となったサンパウロの新進女性ヴォーカリスト、タチアナ・パーハの4人。さらにインストゥルメンタリストとしては、いまは亡きトゥーツ・シールマンスの後継者と目されるスイス出身のジャズ・ハーモニシスト、グレゴア・マレが参加している。レコーディング・エンジニアは、リトナーとグルーシンの作品ではお馴染みのドン・マレーだ。
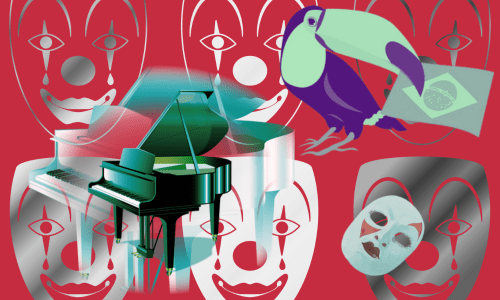
個人的には今回のレパートリーのなかに、グルーシンのアルバム『ジェントル・サウンド』(1978年)に収録されていた、ミルトン・ナシメントの曲「カタヴェント」や、リトナーの『キャプテンズ・ジャーニー』(1978年)及びリトナー&グルーシンの『トゥー・ワールド』(2000年)で演奏された、グルーシンのオリジナル曲「冬の歌」(別名「エチュード」)、さらにはリンスの『イヴァン・リンス』(1986年)でグルーシンがアレンジを手がけた「ヴィトリオーザ」といった懐かしいナンバーが織り交ぜられていることに、こころがくすぐられる。どんなニュー・アレンジ、どんなプレイがなされているのか、ぼくは少年のころのようについ想像をたくましくしてしまう。しかしこれ以上は、実際に音を聴くまえからあれこれ云うのはやめておこう。
それはそうと、この件に関してひとつだけ引っかかることがある。国内盤の発売元であるポニーキャニオンの公式ページには、本作について「40年の時を経て、リトナー&グルーシンが名作の続編を完成!」というコピーが見受けられる。実はぼくはこの云い表わしかたに、なにかすっきりしない感じがするのである。すなわちこの広告文は、本作をブラジリアン・フュージョン・アルバムの傑作としてあまねく知られる『ハーレクイン』(1985年)のシークエル的な作品と謳っているのだが、果たしてほんとうにそうなのだろうか?ブラジル音楽という共通根はもつものの、ブラジリアン・ナンバーではないグルーシンのオリジナル曲がグラミー編曲賞に輝いていることからも『ハーレクイン』が単なるブラジル音楽にちなんだ作品ではないことは明白だ。
そもそもデビュー当時のリトナーにとって、グルーシンはメンターのような存在だった。ショービズの世界に飛び込んだばかりのリトナーは、高い音楽性をもつグルーシンのワーク・パフォーマンスやキャリアを手本としたはず。グルーシンのほうもサウンド・クリエイトについて助言を与えたり指導したり、ときには音楽家としての成長や精神面においてもリトナーをサポートしたであろうことは、容易に想像することができる。なによりも、音がそう云っている!そんなリトナーとグルーシンの仲を取りもったのは、あのセルジオ・メンデスだったという。リトナーはセルジオ・メンデス&ブラジル ’77のサポーターとして、1973年の日本公演やアルバム『ヴィンテージ ’74』(1974年)のレコーディングに参加。そして、セルメン・サウンドのスウィートなオーケストレーションを長年手がけていたのは、云うまでもなくグルーシンだった。
グルーシンはその後ときを移さず、彼の映画音楽の代表作となった『コンドル』(1975年)やダイレクト・ディスク『ディスカヴァード・アゲイン!』(1976年)のレコーディングにおいて、リトナーを起用した。さらにグルーシンは、リトナーの記念すべき初リーダー作『ファースト・コース』(1976年)、それにつづく『キャプテン・フィンガーズ』(1977年)などにおいて、コンポーザー、アレンジャー、キーボーディストとして、18歳年下の若き有能なギタリストをバックアップすることにやぶさかではなかった。そんなふたりのマスター&ディサイプルのような関係は、やがて友情を深めながら対等のものとなっていく。お互いに敬意をもって思いやり、かつストレスなく意見を交わしながら作り上げた、はじめてのコラボレーション・アルバム──『ハーレクイン』は、そんな作品だ。
(『ブラジル』については、下の記事をお読みいただければ幸いです)
リトナー&グルーシンによる目の覚めるような美しいサウンドスケープ
思い起こせば、当時のリトナーはオランダで活躍していたエリック・タッグをフィーチュアリング・ヴォーカリストに迎え、AORにアプローチしたアルバム『RIT』(1981年)『RIT/2』(1982年)『バンデッド・トゥゲザー』(1984年)を立てつづけにリリースしていた。グルーシンのほうも32トラック・デジタル録音によるエレクトロニクス技術を駆使したアルバム『ナイト・ラインズ』(1984年)を制作。これまでになくヴォーカル・ナンバーがフィーチュアされており、彼のまえ向きな姿勢と強い意気込みが感じられる。実はそれにはワケがあって、この作品がリリースされる前年の1983年に、1978年以来アリスタ・レコード傘下にあったグルーシンの自己レーベル、GRPレコードが独立したのである。リトナーも1985年、エレクトラ・レコードとの契約が切れると、すぐにGRPへ移籍した。
このころには、リトナーにしてもグルーシンにしても、アーティストとして十二分に成熟していたわけで、だれの庇護を受けずともハイレヴェルな音楽作品を創出することができるようになっていた。それどころか制約がなくなったことから、これまで以上に自分たちの本当に演りたかった音楽を具現化する好機が到来したのである。当然ふたりは張り切っただろうし、出来上がった作品も悪いはずがない。このときリトナーは、兼ねてからやりたかったことのひとつを叶えている。それは前述の『ブラジル』にも参加した、イヴァン・リンスとの初共演だった。リトナーは『リー・リトナー・イン・リオ』(1979年)のレコーディングでブラジルに赴いた際、はじめてリンスの存在を知り、彼の熱烈なファンになったという。
イヴァン・リンスがブラジル以外で注目されるようになったのは、1980年代に入ってから。いち早く彼の楽曲をリーダー作やプロデュース作品で採り上げたのは、クインシー・ジョーンズだった。当時の彼が関わった作品ではロッド・テンパートンがソングライターとして世間の耳目を集めていたが、ぼくの関心は圧倒的にリンスに向いていた。それでも恥ずかしながら、ぼくは当初彼のことを新進の作曲家と思い込んでいた。ところがすぐあとに、ある音楽雑誌のなかでリトナーが自分の愛聴盤としてリンスの『ノーヴォ・テンポ』(1980年)を紹介したので、ぼくも彼がブラジルのシンガーソングライターであると認識するに至った。そして慌てて輸入盤を入手したぼくは、すっかりリンスに惚れ込んでしまった。特にその楽曲の特異なコード進行には、かなり衝撃を受けたもの。
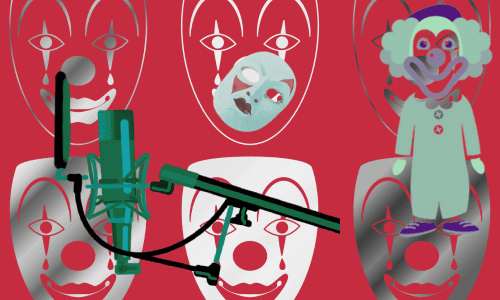
ときにリトナーとグルーシンは、その『ノーヴォ・テンポ』のトップを飾る「アルレキン・デスコニェッシード(名もなき道化役者)」前作『ある夜』(1979年)に収録されている「アンチス・キ・セージャ・タルヂ(今を生きよう)」さらに『デポイス・ドス・テンポライス』(1983年)のタイトル・ナンバー「デポイス・ドス・テンポライス(嵐のあとで)」といった3曲をチョイス。それぞれ「ハーレクイン」「ビフォア・イッツ・トゥー・レイト」「ビヨンド・ザ・ストーム」と英語のタイトルが付されたが、リンスは相棒のヴィトル・マルチンスが書いたポルトガル語の歌詞をそのまま歌っている。原曲よりもセンシティヴなアレンジが施されたどの曲においても、リトナー&グルーシンによるソフィスティケーテッドなオブリガートとリンスのアーシーなヴォーカル・パフォーマンスとのコントラストが絶妙に美しい。
特に「ビヨンド・ザ・ストーム」では、リトナーとグルーシンのソロ・パートも然ることながら、なによりもエンディングのビスにおけるリンスを含めた3人の即興演奏が楽しい。両手のコンビネーションを活かしたピアノのバッキングは、グルーシンのお家芸だ。バックを務めるのは、ロサンゼルスの敏腕ミュージシャンたち。ジミー・ジョンソン(b)、カルロス・ヴェガ(ds)、パウリーニョ・ダ・コスタ(perc)、アレックス・アクーニャ(perc)が主体となるが、曲によってはベースとドラムスが、エイブラハム・ラボリエル(b)、ハーヴィー・メイソン(ds)に入れ替わる。ことにラテン・アメリカの多国籍グループ、カルデラのメンバーだったヴェガによる、イージーゴーイングでダイナミックなドラミングが、トータル・サウンドに爽快感を与えている。彼は1998年4月7日、ジェームス・テイラーのツアー中に自ら命を絶った。その点、ここでのプレイは貴重と云える。
リトナーとグルーシンは書き下ろしの新曲を2曲ずつもち寄った。リトナーの曲は、哀愁が漂うシンコペーションからパワフルな16ビートへ進行する「サン・ユーシドロ」と、ジャズとロックンロールが融合したようなポップ・ナンバー「グリッド・ロック」だ。どちらかといえばヘヴィヒッティングでフルブラストな曲を、アンプを通したアコースティック・ギターでプレイしているのが新鮮。このマナーはこれ以降、リトナーのトレードマークとなる。グルーシンの曲は、グラミー編曲賞に輝いた「アーリー A.M. アティテュード」と、リラックスした2分の3拍子「サイレント・メッセージ」となる。前者では、MIDI アコースティック・ピアノで演奏されるリハーモナイズされたメロディック・ラインが、独特のグルーヴを生んでいる。いかにも、グルーシンらしいリズム感覚だ。後者は、ペダルポイントやモジュレーションを効かせた、新世代のアコースティック・ジャズ。まごうことなき名曲である。
今回はレコーディングに不参加だったグルーシンの実弟、ドン・グルーシンの提供曲「キャッツ・オブ・リオ」は、8分の7拍子のサンバ。ボーダレスな様々なフレーバーが一体となっているところ、シンセサイザーやコンピュータが多用されているところが、いかにも彼の曲らしい。変拍子であろうと小気味よく疾走するグルーシンのアコースティック・ピアノが痛快だ。アルバムを締めくくる「ザ・バード」は、メイソンとキーボーディストのマイク・ラングとの共作。トロピカルな香気を放つような明るく爽やかなナンバー。MIDIピアノとアコギの対話が実に楽しげ。ミュージシャン全員が悠然と音楽に興じている様子が浮かんでくる。ということで『ハーレクイン』では、確かにリンスのインパクトが強いけれど、なによりもリトナー&グルーシンのコンビネーションが生み出す、目の覚めるような美しいサウンドスケープに感動を覚える。そんな名盤を、単なるブラジル音楽にちなんだ作品として片付けてはならない。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。










コメント