映画音楽の巨匠ラロ・シフリンの、いつもとひと味違う鋭いセンスが光る傑作『ブリット』
 Album : Lalo Schifrin / Bullitt (1968)
Album : Lalo Schifrin / Bullitt (1968)
Today’s Tune : Room “26”
映画音楽の巨匠──もとはジャズ・ピアニスト
まだ子どもが生まれるまえのことだったな。妻とふたりで、100戸規模のマンションに住んでいたころ。わが家はそれなりに快適に暮らせる間取りではあったけれど、なにせ部屋数が少なかった。だから、オーディオは一式リビングに設置していた。ぼくの部屋は、レコードとCD、それにピアノでもうイッパイイッパイだったからね。というわけで当然のごとく、ぼくの聴いている音楽は、べつに音楽がなくても生きていける妻にも、そっくりそのまま聴こえてしまうのだった。ちょっと身が縮まる思いもあったが、それでも友人が遊びに来たときなどは、食事をしながら音楽を振る舞うことができたので、ぼくには好都合だった。
家族が増えたのを機に戸建てに引越したのだが、オーディオはすべてぼくの部屋へ追いやられてしまった。ちょっと淋しいけれど、致しかたない。それまで、妻もよく我慢してくれたもの。シエシエ。それはともかく、はなしをマンション時代に戻すと、そういう時はよっぽど機嫌がいいのだろう、ときおり妻がぼくの聴いているものに興味を示すことがあった。特にブラジルのフュージョン・グループ、アジムスはお気に入りだったようで「これ、アジムスだよね」と、よく声をかけられた。そんなある日、彼女が「これ、タモさん?」と、CDのジャケットに描かれたグラサン男のイラストを見て、訊いてきた。
もちろん、タモリさんではない。でも、ちょっと髪の毛の多いタモリさんに見えなくもない。というか、妻のせいでそのCDを手にする度に、タモリさんを思い出してしまうではないか!まったく──。ところで、問題のCDといえば、それは『ラロ・シフリン&フレンズ』(2007年)というアルバム。妻の云うところのタモさんとは、ラロ・シフリンのこと。アルバムは、シフリンの自己レーベル、アレフ・レコードからリリースされた、当時の彼の新譜だ。デニス・バディミール(g)、ブライアン・ブロンバーグ(b)、アレックス・アクーニャ(ds)、ジェームス・ムーディ(ts)、ジェームス・モリソン(tb,tp)といったメンバーに惹かれて、入手した。
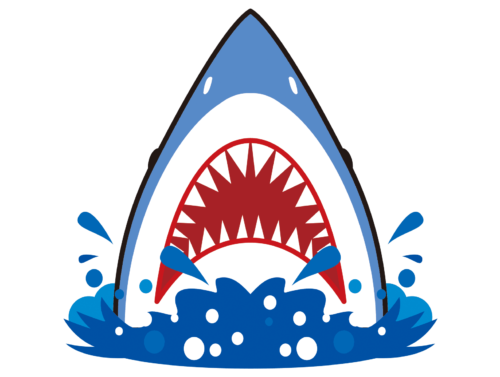
実物は、まったくタモリさんに似ていないシフリンが、かつて1960年代、ディジー・ガレスピー・バンドのアレンジャー兼ピアニストだったことは、よく知られている。ただ、アルゼンチン出身の彼は、もともとクラシックの教育を受けたひとで、その分野でも作曲家、指揮者として活躍した。そんな才能が認められ、ジャズ・ミュージシャンとしてヴァーヴ・レコードに所属していた彼は、まもなくヴァーヴの親会社である映画製作会社MGM(メトロ・ゴールドウィン・メイヤー)で映画の仕事をはじめる。結局、シフリンといえば映画音楽の巨匠というイメージが定着した。
テレビドラマ『スパイ大作戦』(1968年)の、あのあまりにも有名な5拍子のテーマ曲といい、映画『燃えよドラゴン』の、アチョー!というブルース・リーの怪鳥音(実際は“アチョー!”とは叫んでいない)とシンセサイザーが交錯するテーマ曲といい、とにかくド派手な作編曲にただただ圧倒されるばかりだ。以来、サスペンスやアクション作品を中心に、銀幕に躍動感に富んだサウンドをたくさん残してきた。でもそんなシフリンも昔は、ラテン・タッチのデビュー作『ピアノ・エスパニョール』(1959年)をはじめ、ジャズ・ピアニストとしてアルバムを何枚も吹き込んでいたのだ。
ハリウッドで培った商業主義を気兼ねなく全開
さて、タモさんジャケットの(シツコイね)『ラロ・シフリン&フレンズ』だが、シフリンはこの作品で意外なほどオーソドックスなジャズをプレイしている。ヴァーヴ時代の作品には奇を衒うようなところもあったけれど、ここでは彼のオリジナル中心の選曲であるのにもかかわらず、いい意味で力の抜けた溜飲が下がるような演奏をしているのだ。ハリウッドの映画産業における御用達として、俗っぽいサウンドを大量生産していた彼を想像していたので、ちょっと拍子抜けしてしまった。まあ彼の場合、これまでピアノ演奏のほうは、あまり取り沙汰されることがなかったから、このセッションでのハイブリディティに富んだプレイは注目に値するな。
ここで正直に告白すると、シフリンはぼくにとってちょっと苦手な音楽家なのだ。なぜなら、彼が創り出すサウンドは、たいへん高品質でありながら、多くの場合強烈なコマーシャリズムを感じさせるからだ。ちょっと悪い言い方になるけれど、ひとことで云うと節操がない──ということになる。ハモンド・オルガン奏者のジミー・スミスの人気盤『ザ・キャット』(1964年)で、アクの強い豪快なオーケストラ・サウンドを炸裂させているのは、シフリンだ。バロック音楽とジャズ、ロック、R&Bなどをいびつに調和させた『マルキ・ド・サド』(1966年)という変なアルバムも、彼のリーダー作。陽気に錯乱したアンサンブルは、まさに無節操!
たとえ一貫性に欠けようが、ハリウッドで培った商業主義を気兼ねなく全開するところは、好き嫌いが分かれるにしても、間違いなくシフリンのエンターテイナーとしての魅力と云える。現に、彼の大ファン、サントラ盤のコレクターは、たくさんいるのだ。ヴァーヴ時代からその才能を認めていたプロデューサーのクリード・テイラーは、自ら立ち上げたCTIレコードにも彼を引っ張っていく。そして──「シフリンくん、いっちょドギツイのをたのむよ」「ジョーズとかどうっすかね。1億ドル以上稼いでるらしいですぜ。悔しいけど」「イイね、イイね、エゲツなくてもイイから、思いっきりやっちゃって」「んじゃ、流行りのディスコでいってみますか」──と、これはぼくの妄想だけれど、シフリンのCTI第一作『ブラック・ウィドウ』(1976年)は、そんな音がする。

ちなみに、このアルバムに収録されている、モーリス・ストロフ楽団の1956年のヒット曲が軽快なフュージョン・ナンバーにアレンジされた「ムーン・グロウ/ピクニックのテーマ」という曲──テレビ埼玉で放送開始のテーマ音楽として使用されているのは、知る人ぞ知るところ。早朝からシフリンとは、さすがテレ玉!そんな気安いサウンドを作るとは、さすが映画音楽の大家!そして──「シフリンくん、第二弾にはクラシックも入れてよ」「バッハのトッカータなんかどうっすかね。もちろんディスコで」「♪チャラリー。ハナギューだな。イイね、イイね、やっちゃって」「んじゃ、関係ないけどタイトルに“タワーリング”ってつけちゃいましょ。今度は1億1千万ドルだ!」──と、シフリンのCTI第二作『タワーリング・トッカータ』(1977年)は、こうして生まれた──わけはない。
ぼくには、シフリンの音楽を馬鹿にするつもりはまったくないのだが、彼の音楽には、たとえば江戸時代に大名や上級の武士のみが食していた上菓子と相反する、広く庶民から愛された駄菓子のような味わいがある──そんなふうに感じられる。いつもは聴かないが、たまに無性に聴きたくなったりする。折に触れての鑑賞だから、いいのである。なぜなら、彼が繰り広げるスペクタクルなサウンドばかり聴いていたら、ちょっと食傷気味になるからね。とはいっても、例外もある。タモさんのアルバム(まだ云うか!)でもそうだけれど、彼はときおり、いつものド派手な世界とはひと味違う、鋭いセンスが光る瞬間を垣間見せることがある。次に、そんな作品をご紹介しよう。
ド派手な世界とはひと味違う鋭いセンスが光る
それは、1968年に公開された、スティーヴ・マックイーン主演のアクション映画『ブリット』のサウンドトラック・アルバム。映画は、イギリス出身の監督、ピーター・イェーツのハリウッド進出第一作でもある。彼がもとプロのレーシング・ドライヴァーだったせいか、やたらカーチェイスのシーンが目立つ。マックイーンのほうも、プライヴェートでプロのレーサーになるほど、モータースポーツが大好きなおひと。そのせいか本編では、マックイーンが演じるブリット警部補と、彼が運転するフォード・マスタングGT390が、滅茶苦茶クール。でも、ゴメンナサイ、ぼくにとっては、それだけの映画。いやいやそうではない、音楽にはとても惹きつけられたのだった──。
サウンドトラックのオリジナル盤は、当時のワーナー・ブラザース=セヴン・アーツ・レコードがリリース。日本では、東芝音楽工業(現在のユニバーサルミュージック)がディストリビューターとなり、ジャケットは日本独自の仕様に差し替えられた。また、世界で最初のCD化は、日本でのこと。1996年に当時、大阪に拠点を構えていたサウンドトラック・リスナーズ・コミュニケーションズによって実現された。さすが!その際、音源は東芝のLPと同様ものが使用されたが、ジャケットは米国のオリジナル盤のものに戻されている。完全限定盤ということもあり、ファン垂涎のコレクターズ・アイテムとなった。
ところで、このアルバム──サントラ盤とはいいながらも、実は収録曲のすべてが、映画で使用されたフィルムスコアリングによるトラックとは別もの。映画の公開のあと、シフリン自身によって、あらためてレコーディングされた音源なのである。全12曲は、ソース・ミュージックの「ファースト・スノーフォール」のみソニー・バークの曲だが、それ以外はすべてシフリンのペンによるオリジナル曲。レコーディングには、シフリン(key)をはじめ、レイ・ブラウン(b)、ラリー・バンカー(ds)、ハワード・ロバーツ(g)、バド・シャンク(fl)など、名うてのジャズ・ミュージシャンが参加している。

おすすめの曲は、まずはやはり「ブリット(メイン・タイトル)」だろう。いかにもシフリンらしい独特なベース・ラインに乗って、ギターがブルージーなメロディを歌ったあと、ダイナミックなビッグ・バンド・サウンドが展開される。フィルム音源より、テンポはやや速くなっている。つづいて、洗練された雰囲気のジャズボサ「26号室」は、いつものシフリンと違って控えめで、とてもスタイリッシュ。フルートとハモンド・オルガンもキャッチー。大野雄二の「A Day Of The Town」という曲は、これのパクリ(云っちゃった)。あと1曲、ミッド・テンポのボサノヴァ「アフターマス・オブ・ラヴ」は、トロンボーンの甘い音色も然ることながら、ストリングスやフルートのアレンジが素晴らしい。ぼくにとっては、理想型。
まだまだ、テーマ曲のヴァリエーションで、ギター・ソロが熱い「サン・マテオへの道」とか、ピアノとベースがスリリングな展開を見せる「殺し屋マイク」とか、ポリリズムに乗ってフルートがドライヴする「キャシーの歌」とか、ホーンとストリングスがサスペンスフルなアンサンブルを繰り広げる「シフティング・ギア」とか、カッコイイ曲が満載。もちろん、なかにはド派手なシフリン・サウンドが爆発する曲もある。でも、本作はトータル的に観ると、実にバランスがいい。現在、これらのアルバム・ヴァージョンにフィルムで使用されたトラックがプラスされた全31曲のCDが、フィルム・スコア・マンスリーからリリースされている。名曲「26号室」のビッグ・バンド・ヴァージョンも聴ける!興味のあるかたは、ぜひそちらをどうぞ──。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント