洋食屋さんの料理のごとき庶民的な妙味が楽しいアルマンド・トロヴァヨーリの代表作『黄金の七人』
 Album : Armando Trovajoli / Sette Uomini D’Oro (1965)
Album : Armando Trovajoli / Sette Uomini D’Oro (1965)
Today’s Tune : Seven Golden Men
どんな素材でも腕に縒りをかけて調理する、もとジャズ・ピアニスト
音楽と料理はよく似ている。たとえば、厳選された高級食材を、職人が繊細で高度な技術を活かしながら手間暇かけて調理する、食の芸術品ともいうべきものがある。そんな料理には、単純に美味いと感じさせられるだけでなく、まるで人生に豊かな彩りがひとつ添えられたような気分にさえさせられる。そのいっぽうで、比較的安価な食材が使用されていながら、気軽に食べられるような庶民的な妙味溢れる料理もある。決して贅沢な食饌ではないが、やはり、とても美味い。そしてお腹だけでなく、こころまで豊かにしてくれるのだ。ぼくは、学生時代に大学のそばにあった洋食屋さんのコロッケ、カレー、オムライス、スパゲティなどの味を、いまだに忘れることができない。
ぼくは、A級、B級という呼びかたとか、ランキングとか、はたまた星の格付けとかは、あまり好きではない。大事なのは、自分がどう感じるかだ。映画産業においても、A級映画、B級画という呼称が使われている。たとえ多額の製作費が注ぎ込まれていようが、あるいは人気俳優が勢揃いしていようが、もしくは名だたる監督がメガホンをとっていようが、結局、面白くないものは面白くない。ブロックバスター映画には、派手な宣伝につられて鑑賞してみると一気に興醒めするような作品が、案外多かったりする。反感を買うかもしれないが、たとえばジェームズ・キャメロンやローランド・エメリッヒの作品は、興行的に大きな成功を収めているが、ぼくにとっては、こけおどし映画。味に深みがない。
映像作品においてもちゃんと旨味や風味があって、料理がそうであるように、それらが豊かであることがいちばん大切なのだ。そして、音楽もまた然り──。なにも贅を尽くすことが、美味しい音楽を創造することに直結するとはかぎらない。特に音楽の場合は、ミュージシャンの内面にある精神的のはたらきが重要だ。それは、音楽から生まれる雰囲気や味わいを微妙な点まで理解し、どうすれば魅力的でこころに留まりやすい音を出すことができるかを知る──そんな鋭敏な感覚だ。そして、それを具体的に表現する卓越したテクニックを駆使して、どんな素材でも腕に縒りをかけて調理してしまうような音楽家に、ぼくは大いに敬意をはらうのである。イタリアの音楽家、アルマンド・トロヴァヨーリ(1917年9月2日 – 2013年2月28日)も、そのひとりだ。
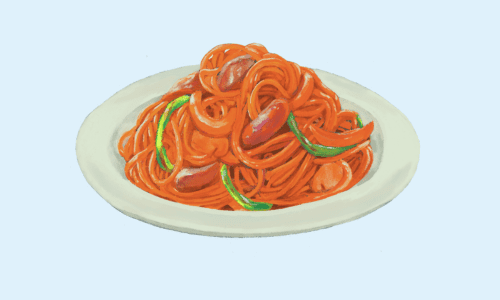
トロヴァヨーリは、イタリアの首都ローマに生まれた。幼いころは、4歳のときにヴァイオリニストの父親からヴァイオリンを学び、6歳からピアノのレッスンも受けるようになる。のちにローマにあるサンタ・チェチーリア音楽院においてピアノと作曲を学んだ。先輩にはやはり映画音楽で名を馳せた、アンジェロ・フランチェスコ・ラヴァニーノがいた。ともに作曲活動に切磋琢磨したという。もっともトロヴァヨーリは音楽院に入学するまえから、高級ナイト・クラブでジャズ・ピアノを弾いていた。彼が17歳のときのことである。家庭の経済状況が厳しいことからはじめたアルバイトだった。そんな思いがけない経験が、のちの彼の音楽性に大きく影響したことは、容易に想像できる。
そう、いまでこそトロヴァヨーリの名前は映画音楽の世界にとどろきわたっているが、もともと彼はジャズ・ピアニストだった。彼は1948年、音楽院を卒業後すぐに演奏活動を開始する。1949年5月にパリで開催された、第1回国際ジャズ・フェスティヴァルにもピアノ・トリオで参加。1950年代にはロマーノ・ムッソリーニと並んで、イタリアを代表するモダン・ジャズのピアニストとして注目を集めた。そのプレイは実にフレキシブルなもので、ときにはウェストコースト・ジャズのようなクールさが、ときにはニューヨークのパップ系ジャズのごときファンキーさが見られるから面白い。彼のフィルム・スコアに独特のモダンなセンスが窺われるのは、ラテンやボサノヴァのリズムが採り入れられたこともあるけれど、その音楽性の根幹をなすのがジャズだからである。
トロヴァヨーリは、RCAイタリアーナに『シャンパン・フォー・ディナー』(1955年)をはじめ、アルマンド・トロヴァヨーリ・イ・ラ・スア・オルケストラ名義でアルバムを数枚吹き込んでいるが、それらはジャズありラテンありポップスありカントリーあり──と、要はなんでもありの、どちらかといえばイージーリスニング系の作品だ。一部にトロヴァヨーリのクール・ジャズ・スタイルの演奏を聴くことができる『マジック・モーメンツ』(1958年)のみ、日本でもリリースされた。トータル的にはストリングスによるアンサンブルの美麗さ、チェンバロや女性のスキャットなどの軽妙洒脱さが際立つが、曲によってはピアノ・トリオによるスウィンギーなナンバーも収録されている。このごった煮感は、のちのトロヴァヨーリ・サウンドにつながる。
モリコーネは高級西洋料理、トロヴァヨーリは飽くまで庶民的洋食
トロヴァヨーリのピアノ・スタイルはオーソドックスだが、メロディアスでタッチが力強く鮮やかな印象を与える。それは、ちょっとテディ・ウィルソンを彷彿させるような、モダンなコードとフレーズを繰り出しながらよくスウィングするプレイである。彼のジャズ・ピアニストとしてのアルバムでは、やはりRCAイタリアーナに吹き込まれたクァルテットによる『トロヴァヨーリ・ジャズ・ピアノ』(1959年)、セクステットによる『ソフトリー』(1959年)といった2枚が、国内で発売されたこともあり、ジャズ・ファンの間ではよく知られている。しかしながら、彼は実は1949年から映画音楽の仕事をしていて、1960年代に入ると次第にジャズから遠ざかり、専らサウンドトラックの作曲と指揮に集中するようになる。その作品の数は、優に200本を超えるという。
そんなトロヴァヨーリ・ミュージックの新奇なアイディアが百花斉放となるのは、やはりジャズ・ピアニストから映画音楽作家に転身してからのこと。そのなんとも云えない味わいは、ぼくにとっては、前述した大学生のころに通った洋食屋さんの料理に似ている。決して贅が尽くされているわけではないけれど、彼の斬新な発想と工夫によって、思わず「ブォーノ!ブォーノ!」と云いたくなるような、ほっぺたが落ちそうになるくらい美味しい音楽がクリエイトされるのだ。しかも彼は、そんな軽やかで、さっぱりとしていて、洒落気があって、如才のない素敵な音楽で、半世紀以上もぼくらを楽しませてくれた。卒寿を迎えてもなお現役として活動した彼に、あらためて「エラ・トゥット・ブォニッシモ!」と云おう。
繰り返しになるが、トロヴァヨーリ・サウンドの魅力といえば、やはり洋食屋さんの料理のごとき庶民的な妙味。気軽に楽しめるところがいい。イタリアの映画音楽の作曲家といえば、だれもが真っ先に思い浮かべるのはエンニオ・モリコーネだろう。それよりもちょっとまえのひとだと、ニーノ・ロータあたりが挙げられるかもしれない。ふたりともアカデミー作曲賞の獲得者。そのうちモリコーネは、実はぼくにとっても、もっとも好きな映画音楽作家のひとり。各々の映画作品の語るべきことが、的確な音楽で表現されるという点で、彼のスコアは他の追随を許さない。平たく云えば、彼は観客に感動を与える達人なのである。そういった意味では、モリコーネ・サウンドは高級イタリアン。

ロータのほうは、子どものころからオラトリオやオペラを作曲し、音楽大学を卒業すると間もなくシンフォニーの作曲に取りかかるという、ばりばりクラシック畑のひと。サウンドトラックでは甘く切ないメロディも奏でるが、それでも厳粛な雰囲気が漂う。彼の音楽もまた、どちらかといえばリストランテの華麗な食卓が似合うのだ。モリコーネは、もともとマカロニ・ウェスタンで名声を高めたひとだが、1980年代のなかごろからそのサウンドに謹厳実直な匂いを感じさせるようになる。まあ結局、彼はそれを機に世界的な知名度を得たわけだから、作品から高級食材の香りが立つのも当たりまえといえば当たりまえ。同様に映像作家だと、ルキノ・ヴィスコンティ、ミケランジェロ・アントニオーニ、フェデリコ・フェリーニあたりは、ぼくにとっては高級イタリアン。食すのに、いちいち襟を正してしまうのである。
とはいってもイタリアの映画は、歴史映画やプロパガンダ映画、あるいは文芸作品ばかりではない。それ以上にネオレアリズモ・ローザとか、イタリア式コメディとか、マカロニ・ウェスタンとか、ジャッロとか、とにかく理屈抜きに楽しめる映画が種々雑多にあるのだ。ぼくが子どものころは、そういう低予算で製作され小規模に公開されるような娯楽映画が、テレビでプライムタイムに堂々と放映されていた。まったくいい時代だった。ときには、トロヴァヨーリと何本かコンビを組んだマルコ・ヴィカリオ監督のお色気たっぷりの作品まで、何事もなかったかのように家族が集うお茶の間に届けられた。そこから聴こえてくる、トロヴァヨーリの音楽といったら、気づいたらいつの間にか口ずさんでいるような、実に庶民的な小粋で洒落たメロディを有していた。つまり、モリコーネは西洋料理だけれど、トロヴァヨーリは飽くまで洋食なのである。
そんなオツな味わいは、低予算からくるものなのか、それともトロヴァヨーリの人柄からくるものなのか、興味は尽きない。本人曰く、飽くまで映像から受けたインスピレーションを音にするのみ──ということだが、確かにユニークな作品群の刺激を受けて彼のアイディアは大きく膨らむのだろうが、たぐいまれなるセンスの持ち主でなければ、あれほど個性的なサウンドを生み出すことはできないだろう。1960年代のトロヴァヨーリ・サウンドのトレードマークといえば、あの「ダバダバ」というスキャットであり、スタイリッシュな口笛であり、弾けるようなパーカッシヴなオルガンであり、きらびやかなチェンバロである。ときにはアニメなどでよく聴く口琴を使ったりして「ボヨーン」と、とぼけた感じを出したりもする。
トロヴァヨーリのシックスティーズ・タッチは渋谷系にも影響した
べつにトロヴァヨーリはふざけているわけではないのだろうが、その楽器の使いかたに些かワッキーな感覚を発揮していることは否定できないだろう。でも、それが独特の趣きというか、唯一無二の味わいとなっているからスゴイ!映像に合わせるという大義名分を掲げて、ちょっと悪ノリして、まるで無邪気なイタズラでもするような──そんな茶目っ気感覚が、ぼくは大好きだ。道徳的に問題がありそうなシーンでも、トロヴァヨーリに「ボヨーン」とやられてしまうと、なにやら妙に明るくほのぼのとした様相を帯びてくるから、マジックというしかない。リズムの面でもジャズの4ビート、マンボやボサノヴァ、ロックの8ビートから斬新な16ビートまで変幻自在。そして、そこにはバロック音楽まで飛び出してくるのだ。
そんなトロヴァヨーリ・サウンドの代表作といえば、やはり『黄金の七人』(1965年)だろう。前述のヴィカリオ監督のヒット作だ。主演は、監督の当時の奥さまロッサナ・ポデスタとフランスの名優フィリップ・ルロワ。スイス銀行から強奪した金の延べ棒をめぐる、謎の美女と、教授と呼ばれる天才的ドロボーとその6人の仲間たちの、騙し合いと駆け引きが描かれたイタリア製クライム・サスペンス──というよりは、痛快泥棒アクション。一部ではモンキー・パンチのコミック『ルパン三世』(1967年から1969年まで連載)のもとネタと云われている。確かに笑いありお色気ありのクライム作品という点で共通する。もしかすると、ぼくの大好きなドナルド・E・ウェストレイクの軽妙な犯罪小説で、天才的ドロボー、ジョン・ドートマンダーを主人公としたシリーズも、ちょっとは影響を受けているのかもしれない。
まあ、それはともかく『黄金の七人』はそんな内容だけに、音楽のほうも痛快無比であり一際キャッチーだ。メインとなるテーマは「黄金の七人」と「ロッサナのテーマ」の2曲。あとはヴァリエーションでカヴァー。なんたって2週間で1本分のサウンドトラックを完成しなければならないほど、イタリア映画のコンポーザーは忙しいのだ。そこは、卓越したアイディアと鋭敏なセンスで乗り切ってしまうのだから、トロヴァヨーリもまた天才的職人である。ちなみに、前述したトロヴァヨーリ・サウンドのトレードマークのほとんどを、このサントラ盤において確認することができる。特に「黄金の七人」では「ダバダバ」スキャット、バロックとジャズがよくブレンドされたアレンジ、いっぽう「ロッサナのテーマ」では、ミュート・トランペット、口笛、オルガンのとろけるようなトーンが際立つ。
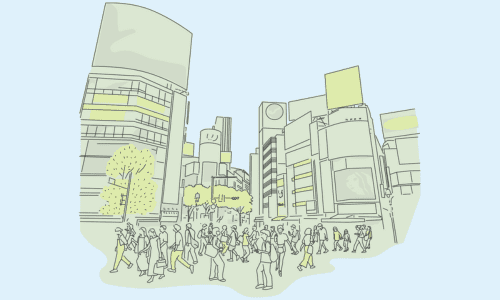
ちなみに、ここで口笛を吹いているのは、イ・カントリーニ・モデルーニというコーラス・グループのリーダー、アレッサンド・アレッサンドローニ。そのスタイリッシュな口笛が、トロヴァヨーリ作品には欠かせないというのも然ることながら、当時のイタリア映画のサウンドトラックに登場する口笛のほとんどが彼によるものであるという事実に、驚嘆させられる。それにしても「ロッサナのテーマ」の曲名には、ジョルジャという謎の女性のキャラクター名ではなく、それを演じる女優ロッサナ・ポデスタの名前が付されているのは、なぜだろう?トロヴァヨーリも彼女の色香にあてられたのだろうか?ポデスタはその後、正統な続編『続・黄金の七人/レインボー作戦』(1966年)や、シリーズとはなんの関係もない『黄金の7人・1+6/エロチカ大作戦』(1971年)にも出演している。
ちなみに、ポデスタもルロワも不在の『新・黄金の七人 7×7』(1968年)は、一応シリーズに含まれるらしい。音楽はすべて、トロヴァヨーリが担当している。特に『続・黄金の七人/レインボー作戦』では「黄金の七人」や「ロッサナのテーマ」が、ゴージャスでエキゾティックなアレンジで帰ってくる。また『黄金の7人・1+6/エロチカ大作戦』では、前述の「ボヨーン」という口琴がフィーチュアされる。『新・黄金の七人 7×7』では、バロックのメロディック・ラインとジャズ・ビート、そしてスピーディなスキャットも健在だ。これらのトロヴァヨーリによるシックスティーズ・タッチは、ピチカート・ファイヴやフリッパーズ・ギターの楽曲に大きなインスピレーションを与えた。
わが国では、ピチカートの小西康陽、カフェ・アプレミディの代表を務める橋本徹らがずいぶん騒いでくれたおかげで、1990年代のなかごろ渋谷を中心にちょっとしたトロヴァヨーリ・ブームが巻き起こり、一般的にもその作品が再評価されるようになった。個人的には、なかなか聴くことができなかったマイナーなアルバムもたくさん復刻されたので、ひとりほくそ笑んでいたもの。なおジャズ・ピアニストで作曲家の大野雄二の曲「THEME FROM LUPIN III ’97」は「黄金の七人」から、おなじく「Cat Walk」は「ロッサナのテーマ」から、それぞれインスパイアされている。トロヴァヨーリの影響力は絶大だ。そんな彼の独特のタッチも、1970年代に入ると変貌を遂げる。ストリングス&ホーンズ、シンセサイザーなどを活かして、清々しいほどに心地いいサウンドを作り出すようになるのだ。ちょっとマイゼル・ブラザーズのスカイ・ハイ・サウンドを彷彿させるのだけれど、それについてはまたの機会に──。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント