人間には知ってはならないことがある──戦慄のミステリー巨編『エンゼル・ハート』
 Album : Trevor Jones / Angel Heart (1987)
Album : Trevor Jones / Angel Heart (1987)
Today’s Tune : Looking For Johnny
セクシーな魅力を放つ新世代の俳優あるいは「猫パンチ」の男
ちょっとやばいレコードがある。ジャケットがやばい。モノクロームの写真に写るステンカラーコートを着た無精髭の男。彼の右手にはすっかり短くなったタバコ。眼を細めて紫煙をくゆらしている。写真の上には、鮮血のごとき真紅の文字による無造作なタイポグラフィが──。なにも知らないひとが見たら、ちょっとデカダンな香りが漂うジャケットから、このLPをブルース・シンガーのレコードと勘違いするかもしれない。本盤のブランド名はアンティルス・ニュー・ディレクションズとなっているが、アイランド・レコードのサブレーベルである。アイランドといえば、レゲエを世界に広めたイングランド出身の音楽プロデューサー、クリス・ブラックウェルが1959年にジャマイカで設立した有名なレコード・レーベルだ。
この伝説的なレーベルでは、フォーク、ロック、プログレ、レゲエと、広範囲にわたる音楽作品が制作、配給された。もともとフォーク作品をメインに制作していたブラックウェルがロック志向に変わるきっかけは、やはりイングランド出身のスティーヴ・ウィンウッドとの出会いだった。ウィンウッドは当時、英国のブルー・アイド・ソウル系のバンド、スペンサー・デイヴィス・グループでオルガンとヴォーカルを担当していた。彼はソロになってからもアイランドで4枚ほどアルバムを吹き込んだが、1987年にヴァージン・レコードへ移籍している。アンティルス・ニュー・ディレクションズが立ち上げられたのは、奇しくもこの年だった。どちらかといえば、ジャズ志向のレーベルのように思われた。
そうはいっても件のレコード、ジャズ作品ではない。そもそもジャケット写真の男は、映画俳優のミッキー・ロークだ。たぶん若い世代のひとが見たら、誰だかわからないだろう。彼は御年71歳にしていまも映画界において現役だが、その貫禄のある体格と威圧感を与えるような容貌からこの写真にたどり着くのは、なかなか困難であろう。なにせ昔から知っているぼくでもびっくりするくらい、凄まじい変貌を遂げているのだから──。写真のロークはまだ34歳だったが、当時の彼はセクシーな魅力を放つ新世代の俳優として、絶大な人気を誇っていた。まあ、騒いでいたのは若い女性が中心だったと思うけれど、ぼくもバリー・レヴィンソン監督の『ダイナー』(1982年)を観たときは、いい俳優が出てきたなと思ったもの。

いやいや、当時のミッキー・ロークの人気といえば、その程度のものではなかったな。日本でもすごかった。女性たちがキャーキャーいっていた。ロークの話題は、ちょっとした社会現象にもなっていた。1988年にはサントリーのウイスキー、リザーブのCMにも出演したくらいだ。あのCM、いくつかのヴァージョンがあったけれど、どれも特別な趣向が凝らされていたわけではない。若々しいロークに年配のバーテンダーがウイスキーを提供するというだけのものだった。それでも多くの女性たちが、杯を傾ける彼の悦に入った表情を見て、うっとりしたものなのである。なおこのときバーテンダーを演じていたのは、ロークの僚友、レナード・テルモ。ロークの主演した『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』(1985年)『バーフライ』(1987年)『死にゆく者への祈り』(1987年)に出演している。
そういえば、マイケル・チミノが監督した『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』において、ローク演ずるニューヨーク市警察の刑事と敵対する、チャイニーズ・マフィア新世代のボスを演じていたのがジョン・ローンだった。ベルナルド・ベルトルッチ監督の『ラストエンペラー』(1987年)で、愛新覚羅溥儀を演じたひとだ。イギリス領時代の香港出身のローンは、そのエキゾティックな容貌とビタースウィートな声色で、やはり多くの女性のハートを鷲づかみにした。奇しくもローンはロークとおなじく1952年生まれ。しかも1988年にサントリーのウイスキー、クラブハウスのCMに出演した。ちょっと出来過ぎだがこんな共通点からか、当時の日本の女性たちの間では、よく「あなたはミッキー派?それともジョン派?」といった具合に盛り上がりを見せていたもの。
そんな人気も下火になってきたころ、ティーンエイジャー時代にボクシングジムに通っていたミッキー・ロークは、1991年にプロ・ボクサーに転身する(俳優業も継続していた)。1992年6月には、ボクシングの試合のため来日。同月23日、両国国技館でダリル・ミラーとの6回戦に臨んだ。豹柄のシースルーのトランクスで登場したロークは、派手なパフォーマンスで会場を大いに沸かせた。まあ、そこまではよかった。初回のゴングが鳴って2分14秒、彼は右フックでKO勝ちを果たす。しかし、このときロークの繰り出した相手への殴打があまりにも弱々しく映り、観るものを唖然とさせた。これがかの有名な「猫パンチ」である。結局この試合、世間から単なるアトラクション、あるいは祝儀目当ての花相撲とまで揶揄されることとなった。
原作小説は“悪魔のバイブル”?映画は終始不安や恐怖を与える
その後ミッキー・ロークは、ボクシングのときに受けた顔面の怪我がもとで、整形手術を受けている。本人も手術は失敗だったとコメントしているが、何度か整形を繰り返したようだ。いずれにしても彼には、時代の寵児から一気に転落したというイメージがつきまとう。考えてみれば、ロークは人気絶頂のころからどこか退廃的な雰囲気を漂わせていたように思われる。演じる役柄からそういう印象を与えるのか、それとも彼自身のキャラクターからそういう役がまわってくるのか、とにかく甘く危険な香りを放っていたのは確かだ。いつの時代もそうだが、破滅に向かう美しい男はモテるのだ。飽くまで美しい男だけれど──。長くなったが、レコードのジャケットに写るロークは、美しい。そして、やばい。
ということでレコードのおはなしに戻るが、このレコードでミッキー・ロークは歌っていない。ほら、俳優でも本格的なリズム・アンド・ブルースのシンガーとしてモータウン・レコードからアルバムをリリースした、ブルース・ウィリスの例もあるからね、念のため──。本盤はロークが主演した映画『エンゼル・ハート』のオリジナル・サウンドトラック・アルバムだ。個人的には、シンプルなデザインだけれど、サントラ盤のアートワークにしてはかなりスタイリッシュなものと受け取られた。映画は予告編しか観ていなかったが、ジャケットが気に入ったので新着したばかりの輸入盤を購入した。実際に聴いてみて、これはやばいと思った。なぜならそこには、原作小説『堕ちる天使』は読んでいたのだが、その世界観がそのまま音楽で表現されていたからだ。
この小説『堕ちる天使』が、またやばい。その凄惨な内容から“悪魔のバイブル”とも呼ばれ、アメリカでは廃刊運動まで起こったという。作者はアメリカの小説家、ウィリアム・ヒョーツバーグ(1941年2月23日 – 2017年4月22日)。ヒョーツバーグはミステリー、SF、ノンフィクションと、作風が多岐にわたる小説家だが、脚本家としても知られている。リドリー・スコット監督、トム・クルーズ主演の映画『レジェンド/光と闇の伝説』(1985年)のシナリオは彼のペンによる。『堕ちる天使』はヒョーツバーグの代表作と云えるが、2015年にJ. マーク・シアースの音楽、ルーシー・サーバーの脚本でオペラ化もされた。なお1981年の日本での出版の際は、ハヤカワ・ミステリ文庫ではなくハヤカワ文庫NV(ノヴェルズ)の一冊としてリリースされた。
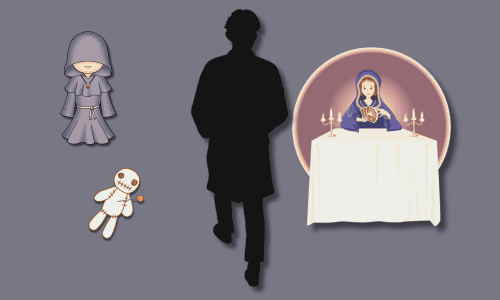
小説の内容をひとことで云うと、オカルティズムに富んだ探偵小説。逆にハードボイルドなホラー小説とも云えるかもしれない。ふり返ればアメリカで出版されたのが1978年のことだから、ジャンル・ミックスの先駆的な作品だったわけだ。物語の舞台はニューヨーク、主人公は私立探偵で、まさにハードボイルドのムードが醸成される。だが次第に悪魔崇拝や黒ミサなどが登場してきて、読者はなにやらおどろおどろしい世界に引きずり込まれていく。本来ロジカルな謎解きがメインとなるミステリー小説と思いきや、この小説は妙に整合性のとれたスーパーナチュラル的解決へと進行する。惨烈を極める殺人、探偵の絶望感は案外淡白に描かれているが、映画のほうではそれらの表現が一気にトップギアに入る。
映画『エンゼル・ハート』(映画のタイトルは掛詞になっている)では、原作とは異なり終始ひとに不安や恐怖を与える雰囲気が漂っている。メガホンをとったのは、イングランド出身の映画監督、アラン・パーカー(1944年2月14日 – 2020年7月31日)。作家でもあり俳優でもあるビリー・ヘイズが自身の実体験を綴った同名の著書を映画化した『ミッドナイト・エクスプレス』(1978年)において、高い評価を得た。思えばこれも、ちょっとやばい映画だった。ぼくは当時この映画をすでに観ていたのだけれど、パーカーのことをやばいけれど実はすごい監督なのではないかと思っていた。そして『エンゼル・ハート』をはじめて鑑賞したとき、ぼくの推測は確信に変わったのである。
パーカー監督がすごいのは、この『エンゼル・ハート』の演出において、少しも臆することなく震え上がらせるような禍々しさと惨たらしさとで、観るひとを煽りつづけているところ。一歩間違えれば、ただ観客を怖がらせるためだけに、現実レベルよりも甚だしい表現をしているようにも捉えられかねない。確かに奇を衒っているようにも感じられるのだが、おそらく敢えてそうしているのだろう、意外にもわざとらしさや不自然さはほとんど感じられない。それどころか、ぼくはまったく訝しむこともないまま、この世にも稀なるスーパーナチュラルなディテクティヴ・ストーリーの世界に、いつの間にか引き込まれてしまっていたのである。その点この映画はある意味で、非日常的な雰囲気に浸ることを楽しむべきものと云える。
物語は1955年のニューヨークからはじまる。ブルックリンに事務所を構える私立探偵ハリー・エンゼル(ミッキー・ローク)は、謎めいたというか誰がどう見ても怪しいルイス・サイファー(ロバート・デニーロ)という男から、ひと探しを依頼される。それは、第二次世界大戦以前に人気を誇ったシンガーで、従軍後に戦争神経症を患ったまま行方不明となったジョニー・フェイヴァリットの生死を確認するというもの。エンゼルはフェイヴァリットの行方を追ってニューヨークからニューオーリンズへ飛ぶ。しかしながら調査の行く先々で、フェイヴァリットの関係者たちが次々に何者かによって殺害されてしまう。しかも血も凍るような凄惨極まる殺されかたで──。やがて事件の背景に、ブードゥー教の秘密の儀式や悪魔崇拝者たちの影が見えてくる。
エレクトロニックベースのスコア、そしてジャズとブルース
物語の舞台は、原作小説では全編ニューヨークとなっているが、それが映画では中盤からニューオーリンズに移される。これはパーカー監督の見事な采配と云える。単純に自然の景色や街並み景観の変遷、それに文化の違いを楽しむことができる。それに、寒そうに襟を立てたステンカラーコートから、背中に汗染みを浮かべた麻ジャケットへ──というロークの出で立ちの変化も、彼のファンとしては楽しいところだろう。それにも増して効果を上げたのは、その土地に息づく音楽である。ニューオーリンズはジャズの発祥地とされる音楽の都として有名だが、間違いなくジャズをはじめブルースやゴスペルなどによって、この一大フィクションは情感溢れるリアルなものへと高められているのである。
音楽を担当したのは、トレヴァー・ジョーンズ。1949年3月23日、南アフリカ共和国のケープタウンに生まれたジョーンズは、イギリスを拠点に活動する作曲家だ。幅広いジャンルの映像作品にスコアを提供しているが、なんと6歳のときから映画音楽の作曲家を目指していたという。18歳のときに奨学金を得て、世界有数の音楽学校のひとつであるロンドンに所在する王立音楽アカデミーに入学。25歳から名門ヨーク大学に通い、映画とメディア音楽の修士号を取得した。また、英国国立映画テレビジョン学校においても3年間、一般的な映画制作と映画および音響の技術を学んでいる。一時期、ロンドンの公共放送局であるBBCで、ラジオやテレビの音楽のレビュアーをしていたこともある。彼が生粋の職人的作曲家であるのは、そんな経歴を観ると得心がいく。
ジョーンズはもともとオーケストラによるシンフォニックなスコアを書いていたが、1980年代に入るとエレクトロニックベースのより劇的なスコアリングを目指すようになる。フェアライトCMIやシンクラヴィアなどのシンセサイザーもいち早く使用しはじめた。シンセサイザーのアルペジオ、コード、リズム、ストラムなどの機能と、ミニマル・ミュージックのパターンが導入されたフレッシュなサウンドは、モーリス・ジャールが当時演っていた映画音楽と共通するところがある。ジョーンズは1990年代にふたたびオーケストラルなスコアを手がけるようになり、ときにはジョルジュ・ドルリューを彷彿させる軽やかな音楽も披露した。彼はこんなメロディアスな曲も書くのかと、ちょっと驚かされたもの。
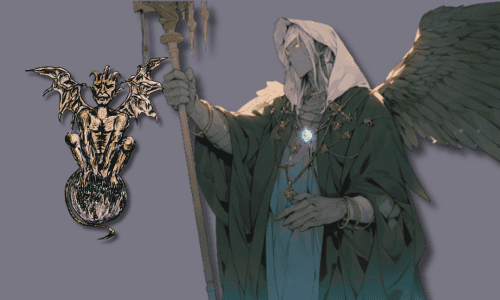
だがしかし、ジョーンズといえばやはり『エンゼル・ハート』をはじめ『ミシシッピー・バーニング』(1988年)『シー・オブ・ラヴ』(1989年)といった1980年代の作品に、ぼくは魅力を感じる。彼は『エンゼル・ハート』では、ブリティッシュ・ジャズのマルチリード・プレイヤー、コートニー・パインをフィーチュアリング・アーティストとして起用。パインは当時アンティルス・ニュー・ディレクションズのアーティストだったから、契約上の都合から本サントラ盤も同レーベルからのリリースとなったのだろう。シンセサイザーをバックにパインのテナーが恐怖、苦痛、驚愕、絶望に対し慟哭するオープニング「ハリー・エンゼル」とエンディング「ジョニー・フェイヴァリット」は、ひとたび聴いたら忘れることができない曲。かなり、やばい。
本作にはジョーンズのスコア以外に、ニューオーリンズのクラブのシーンで演奏されるブルース・ナンバーも収録されている。ピードモント・ブルースのギタリストでありシンガーでもある、ブラウニー・マギーの味わい深い歌声が堪能できる「レイニー・レイニー・デイ」と、女性ジャズ・シンガー、リリアン・ブッテのゴスペル・ライクな歌唱が熱い「ザ・ライト・キー・バット・ザ・ロング・キーホール」の2曲である。なんとマギーは映画のなかで事件の鍵を握るバンドマン、トゥーツ・スウィートを演じているのだが、俳優としてもなかなかのものだ。また、ブッテもトゥーツ・スウィート・バンドのシンガー役として出演している。ブルースのもつアーシーな感じが、映像に俗っぽさというか人間くささを与えているが、音楽通のパーカー監督のこだわりが感じられる。
さらに劇中曲としては、ブルースの女帝ことベッシー・スミスが圧倒的な声量で情感を込めて歌った「ハニーマン・ブルース」(1926年)、グレン・グレイ&ザ・カサ・ロマ・オーケストラによるロマンティックなダンス・ナンバー「ガール・オブ・マイ・ドリームズ」(1938年)、リズム・アンド・ブルースのシンガーでアトランティック・レコードの看板娘だったラヴァーン・ベイカーのハスキー・ヴォイスとパンチの効いた歌いまわしが痛快な「ソウル・オン・ファイア」(1953年)などが収録されている。特に「ガール・オブ・マイ・ドリームズ」は、映画のなかで行方不明の歌手のもち歌という設定となるいっぽう、フィルム・スコア全体のモティーフともなる重要曲である。
ぼくとしては、シンセサイザーは控えめで、ミュートのかかったホーン・セクションやジャジーなキーボードによるハードボイルドなバッキングのなか、パインのテナーが聴くもののこころを惑わすように静かに燃え上がる「アイ・ガット・ディス・シング・アバウト・チキンズ」や「ルッキング・フォー・ジョニー」あたりが好み。ほかにも本作は、シーケンサーによるリズミカルでダイナミックな曲、エスニックなポリリズム、もろクリーピーなナンバー、シンセサイザーのアンサンブルによる壮麗な曲など、ジョーンズの典型的なスコアを多数収録。しかしながら、楽曲に俳優のセリフやSEが重なる箇所も多く、音楽がBGM扱いになるところもある。ぼくはそういう仕様が苦手なのだけれど、このサントラ盤に関してはなぜか許せてしまう。禁忌破りの物語にして掟破りのレコード。ちょっとやばい非日常的な雰囲気を素直に満喫するというのが、本作の妥当な聴きかたなのだろう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント