日本中を震撼させたテレビドラマ『BLACK OUT』と音楽界の異才、蓜島邦明によるサウンドトラック
 Album : 蓜島邦明 / BLACK OUT オリジナル・サウンドトラック (1999)
Album : 蓜島邦明 / BLACK OUT オリジナル・サウンドトラック (1999)
Today’s Tune : B – OUT
「一九九九年、すでに…。」のイントロではじまる空想科学ドラマ
みなさんは、あの「一九九九年、すでに…。」という、いわくありげなイントロダクションからはじまるテレビドラマ『BLACK OUT』をご存知だろうか。1995年10月7日から1996年3月30日まで、テレビ朝日の土曜深夜のドラマ枠で放送された異色作だ。当時の近未来1999年に起こるハイテク犯罪の謎に対し、警視庁科学捜査部の男女ペアの捜査官がその全容の解明に奔走する──という、(そういうコトバがあるかどうかわからないが)SFクライム・サスペンス。一見超常現象とも取れる不可解な事件を、科学によって解決していくというストーリーラインは、東野圭吾の連作ミステリー、“ガリレオ”シリーズを彷彿させる。しかし、このドラマが放映された当時は、天才物理学者、湯川学はまだ創造されていない。
その点で『BLACK OUT』はミステリー・ドラマという観かたもできるが、トリックにまだ一般的ではない科学技術が駆使されていることからサイエンス・フィクションと捉えるほうが妥当だろう。空想科学ドラマというと、すぐに思い浮かぶのは円谷プロダクションとTBSが制作した『怪奇大作戦』(1968年9月15日 – 1969年3月9日)。ものごころがつくまえに、見るともなしに見ていた。ただまだ幼かったぼくにとって、その映像のインパクトはあまりにも強烈だった。壁ぬけ男や白い顔の男が夢に出てきて、ちびりそうになるくらいウナされたこともある。現在欠番となっている第24話「狂鬼人間」を含めた全話をしっかり鑑賞したのは、社会人になってLDを購入したとき。その面白さを、はじめて認識した。
それから5年くらい経ったあと『BLACK OUT』の放映が開始されたとき、ワクワクドキドキしながら『怪奇大作戦』を観はじめたときとおなじように、ぼくは大人げないほどに期待に胸を弾ませたもの。考えてみれば『BLACK OUT』の主人公、警視庁科学捜査部の捜査官、華屋崇一は『怪奇大作戦』のSRI(科学捜査研究所)の所員、牧史郎に似たところがある。冷静沈着な科学の信奉者であると同時に、正義感が強くいかなる犯罪も許さないところ。科学者でありながら、先端科学の暴走を止めようとするところ──などである。そんな共通点からもこのふたつのテレビドラマには、テクノロジーの発展と正しく向き合うための倫理を説くようなニュアンスさえ感じられる。その倫理観に、華屋は苦しむことになるのだが──。
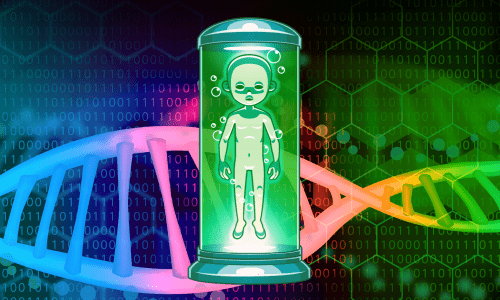
ぼくは、この華屋崇一というキャラクターがとても好きなのだが、それは、彼が科学者だから常に事物を割り切って見つめているのかというと実はそうではなくて、思いのほか曖昧さを残して、その存在理由、目的、意義、価値などを受け入れているから。つまりその点に、人間としての豊かな情緒が感じられるというわけだ。よくオンタイムで専門分野に徹頭徹尾熱中しているひとほど、オフになると実利を求めることも余計なことを考えることもしなくなる──ということがある。そんなところに、邪気のない深い人間味が知覚される。ハイテク時代に、旧ソ連の物理学者が発明しその名が付いた電子楽器テルミンを演奏したり、(捜査用七つ道具を持ち運ぶのに)アンティーク調のボストンバッグを愛用していたりする華屋に、ぼくはシンパシーを抱くのである。
そんな華屋は、その立ち位置も面白い。西北大学理工学部の非常勤教師で、応用物理学を専門としている。実は科学捜査部には嘱託で所属しているのだ。それに対しパートナーの中園祥子は、もと科学警察研究所の所員でFBIのアカデミーに2年間の留学経験がある幹部候補生。正真正銘、科学捜査部唯一の専従捜査官である。このコンビがヴォイスレコーダーを片手に現場検証を行うシーン、特にふたりの夫婦漫才のごときやりとりは、アメリカのSFテレビドラマ『X-ファイル』(1993年 – 2002年)に登場するFBI捜査官モルダーとスカリーのそれを彷彿させるものがあり、なかなか楽しい。華屋と中園を演じた椎名桔平と山本未來(実生活で一度夫婦となった)は、当時ほとんど無名だったけれど、それが却ってフレッシュな魅力を放っていた。
このふたりをメインに、死体フェチであり解剖フェチでもあるエキセントリックな法医学者、沖野真由美(高島礼子)と、内職稼ぎで科学捜査部に協力する17歳の天才ハッカー、小林少年(大地)が、レギュラーとして脇を固める。そんなひとクセもふたクセもある、非公式かつ少数精鋭の特別捜査チームが追いかけるのは、これまたまったく気を抜けない感じを強く抱かせる、先端技術をもってして神の領域に踏み込むことさえ逡巡しない犯罪者たち。近未来のクリミナルたちが妄用する先端テクノロジーといえば、ヒトクローニング、プラズマ兵器、バイオ・コンピュータ・ウイルス、AIホログラフィ、ホメオボックス遺伝子……と、原理的に当時の技術の延長線上にあるものばかり。だから観るものに、戦慄を覚えるようなリアリティを感じさせるのである。
科学万能主義を諷刺するドラマと原作『1999年のゲーム・キッズ』
実は『BLACK OUT』の原案となった小説がある。作家であると同時にゲームクリエイターでもある渡辺浩弐の『1999年のゲーム・キッズ』(1994年アスペクト刊)がそれ。当時アスキーが発行していたゲーム雑誌「ファミコン通信」(現在の「ファミ通」)において連載されていたショートショートSFをまとめたものだ。続編の『1999年のゲーム・キッズII マザー・ハッカー』(1994年)『1999年のゲーム・キッズIII デジタルな神様』(1995年)も発売されたが、それにとどまらず“2000年のゲーム・キッズ”、“2999年のゲーム・キッズ”ほか、計6シリーズが存在する。ただ原案とはいえ実質はアイディア提供なので、小説とテレビドラマのストーリーとに直接のつながりはない。ただ渡辺さんは、のちに『BLACK OUT』のノベライズも手掛けている。
それにしても“ゲーム・キッズ”は、気の利いた小説シリーズである。平易な文章と少ない文字数で読みやすく、それでいて読者を短時間のうちに異世界の深みに引きずり込んでしまうのだから──。内容的には、SFあり、ミステリーあり、ユーモアありと、ヴァラエティに富んでいるが、なんといっても最先端の科学技術にインスパイアされた創造性が異彩を放っている。星新一のハイブロウな感覚と阿刀田高の奇妙な味を、よりプログレッシヴにした感じだ。渡辺さんはこの小説シリーズについて「読者に現実を疑って自分を信じる事を伝えたかった」と述べているが、これは『BLACK OUT』のテーマにもつながるのではないだろうか。なお、このシリーズのいくつかの作品は『世にも奇妙な物語』(1990年より断続的に放映)や『いとしの未来ちゃん』(1997年)といったテレビドラマでも採用された。
おはなしをドラマに戻すが『BLACK OUT』の各エピソードのナンバリングには“Futurity”という単語が付されている。おそらくフューチュアリティとは、未来の出来事という意味だろう。ぼくにとって、もっとも印象に残っているエピソードは、最終話のFuturity 12「BLACK OUT」(前後編)だ。犯罪のない世界を実現するために、ヒトゲノム解析によって犯行予測をするというおはなし。つまり、犯罪を犯す可能性のある人物を特定し四六時中監視するという、ディストピアともいうべき近未来の社会が物語の背景となっている。ここではこの未来像に対して、科学と法律が巨大な管理社会を生み出すというような、悲観的かつ警鐘的な解釈はなされていないが、科学万能主義を諷刺するようなニュアンスは感じられる。
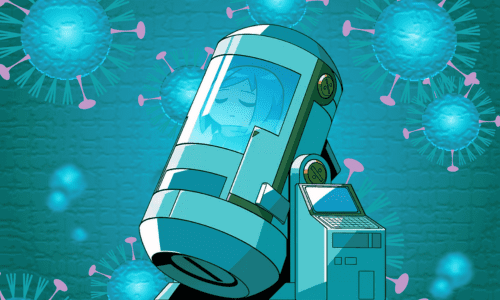
ところで、このエピソードにおいて中園祥子が悲劇に見舞われる。ある日、遺伝子調査によって犯罪者予備軍のひとりとして割り出された男が、核爆発を引き起こす。捜査にあたった中園は爆発に巻き込まれ、被爆し瀕死の状態となる。ところが最先端医療技術をもってしても、彼女の命を救うことは不可能だった。死を覚悟した彼女に、華屋はコールドスリープの処理を施すことを決断する。治療法が確立されるまで、中園の身体を人工冬眠させようというのだ。華屋崇一はやはり科学者であり、科学の進歩を信じ未来に希望を託したというわけだ。そして物語の舞台は、いっきに50年後の2049年にスキップする。果たして華屋と中園の運命やいかに──。ドラマを未見のかたには、ネタばらしになってしまうので、ここで口を噤むことにする。
とはいうものの、ぼくがこのエピソードに惹かれる理由だけは述べておく。最終話に至るまで、華屋崇一と中園祥子との間に恋愛感情を匂わせるような挿話や表現はどこにもない。しかしFuturity 12において、にわかにそれがほのめかされたと、ぼくには感じられた。華屋は中園の蘇生を信じつづけて(おそらく治療法を模索しつづけて)、50年という長い年月を費やす。もちろん華屋にそうさせる動機には、科学はひとの幸福のためにあるべき──という信条を守る彼の科学者としての意地もあるのだろう。それにしても、ひとりの女性の命を救うために人生を捧げるというのは、果たしてそのひとに特別な感情を抱かずしてできることだろうか?この自己犠牲は究極の愛情と、ぼくは思うのである。
人間の感情には、サイエンスやロジックで説明できないところがある。まえにも述べたとおり、華屋崇一という男は科学者だからといって常に事物を割り切って見つめているわけではない。性格にも能力にも曖昧な側面をもち合わせていて、実利にかなわない行動を起こすこともある。だからこそ彼からは、人間としての豊かな情緒が感じられるのだ。科学万能主義に傾倒する近未来の世界が描かれたサイエンス・フィクションの結末において、そんな深いヒューマン・カインドネスが強くアピールされたことに、ぼくはとても感銘を受けたもの。それと同時に、このエピソードのタイトルにもあるブラック・アウトには、記憶を消し去るという意味があることにも気づかされた。果たして記憶が消去されることによって、そのひとに幸福な未来は訪れるのか──そんな余韻を残すラストである。
先端技術と人間性がせめぎ合うような蓜島邦明の音楽
確かに『BLACK OUT』は深夜ドラマ枠の作品ということもあり、低予算の機材による撮影、時間と手間のかからない編集を可能にする、いわゆるビデオドラマではある。フィルムで撮影された映像と比べると、クリア過ぎて光と影に深みはない。それこそアメリカのフォックス放送によって制作されたSFテレビドラマとは、映像のスケール感に天と地ほどの差があることも事実だ。でも観るまえから想像で、この作品を低く見積もるのは軽率というもの。なぜなら、まえに挙げた『世にも奇妙な物語』をはじめ『NIGHT HEAD』(1992年)や『沙粧妙子-最後の事件-』(1995年)といった、ユニークなテレビドラマを演出した落合正幸監督を中心とした、優れたスタッフによる斬新なアイディアと創意に富んだスキルが、作品を観応えのあるものにしているからだ。
そんな卓越した才能と技術をもった制作チームの陣容に、蓜島邦明のクレジットを見出すことができる。唯一無二の作曲家ともいえる蓜島さんは『BLACK OUT』の世界観を、見事に独特な音楽で表現しきっている。彼はテレビドラマ、映画、CM、アニメ、ゲームなど、実に幅広いジャンルにおいて楽曲提供をしているが、どの楽曲もとにかく一風変わっている。変わっているといえば、そのプロフィールもまたほかに類を見ない。1953年1月30日生まれ、埼玉県さいたま市(旧大宮市)出身の蓜島さんは、もとは彫刻家になるつもりだったが、城西大学経済学部を卒業後、叔父が営むパン屋で職人として働く。ところが、元来音楽好きだったことから、当時は珍しかったアナログ・シンセサイザーを入手。一転して劇団の音響を担当しながら、作曲家の道を歩みはじめたのである。
つまり蓜島さんは、音楽を組み立てる楽式、演奏形態やオーケストレーションの方法論などを、すべて独学したのである。音楽に関する専門教育をまったく受けずして、あれだけクリエイティヴな表現力、豊富な知識と技術を体得したというのだから、感服するばかりだ。もともと音楽に対して、豊かな感性をもっていたのだろう。音楽との関わりかたがユニークであれば、その楽曲もみな独創的。一度聴いただけで、記憶に残るものが多い。たとえば『世にも奇妙な物語』のテーマ曲「ガラモン・ソング」の旋律などは、世代を超えて誰もが知るものだろう。ピアノのレッスンを受けるひとなら必ず弾くことになる、ヨハン・ブルグミュラーの「25の練習曲 No.2 アラベスク」のメロディック・ラインをパロディ化したような、あの曲だ。
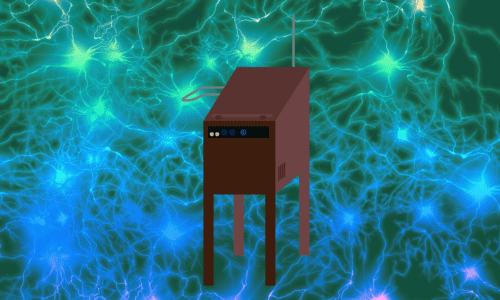
蓜島さんの作品は、シンセサイザーやサンプラー、それにコンピュータが駆使された電子音楽だ。とはいっても、前衛的な現代音楽とはちょっと違っていて、小難しいところがない。シンプルなモティーフとカラフルなタンバー、そして度々ポップなリズムがミックスされていて、実に楽しい。特に音色には細心の工夫と趣向が凝らされており、ときにスージング・トーンだったり、ときにノイジー・トーンだったり、とにかく曲のタイプに合わせて多彩な表情を見せる。いっぽう楽曲は、欧米の芸術音楽や大衆音楽などの方法論で構築されたものもあれば、異国情緒が漂うエスノミュージック風のものもある。たとえば大ブームを巻き起こした超能力を扱ったテレビドラマ『NIGHT HEAD』(1992年)のテーマ曲「ロンゴ ロンゴ」などには、アフリカ音楽のポリリズムが感じられる。
蓜島サウンドではほかにも、テレビアニメ『南海奇皇(ネオランガ)』(1998年 – 1999年)ではインドネシア、やはりテレビアニメ『ガサラキ』(1998年 – 1999年)では日本(謡と囃子)、劇場アニメ『スプリガン』(1998年)ではトルコと、これは飽くまで一例に過ぎないが、様々な国の伝統的な音楽のファクターをしばしば垣間見ることができる。たとえば『BLACK OUT』のなかの1曲「frame」における、リズムやサンプリングされた女性の声にはエスニックな雰囲気が醸し出されている。そのいっぽうで「red chips」ではハードロック、「Cell」ではブリティッシュ・ロック、「S/test」ではニューエイジ、「Opting out」や「OUT CALS」ではテクノ、「Clob~A」ではジャズ、「VPN」ではヘンリー・マンシーニ作曲の「黒い罠 メイン・タイトル」のサンプリングと、ポピュラー・ミュージックの要素も含まれている。
俯瞰的に『BLACK OUT』の音楽を観ると、近未来の空想科学ドラマということもあり、不協和音やノイズ風の音が散りばめられた電子音楽という印象が強い。とはいっても、サウンドに非現実性と相対的に一段とリアルな現実性が意識されているところは、いかにも蓜島さんらしい。云ってみれば、それは音楽のサイバーパンク。音楽の因子がいっぱい詰まった、音のおもちゃ箱でもある。キャッチーに響くサイバー的なテーマ曲「B-OUT」と、テルミンのサンプルとピアノを上手く合わせたアコースティックな「neural」とでは、相反する音楽のように受けとめられるかもしれないが、それらは同一世界に併存するもの。ぼくは、どちらのタイプも好き。そして、この先端技術と人間性がせめぎ合うような蓜島さんの音楽は、まさにテレビドラマ『BLACK OUT』の世界観そのものである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント