名曲「上を向いて歩こう」の名カヴァー「スキヤキ」が収録されたテイスト・オブ・ハニーのサード・アルバム『シーズ・ア・ダンサー』
 Album : A Taste Of Honey / Twice As Sweet (1980)
Album : A Taste Of Honey / Twice As Sweet (1980)
Today’s Tune : Good-Bye Baby
名曲「上を向いて歩こう」──曲はシンプル、アレンジは金城鉄壁
はじめに云っておくと、ぼくはずっと昔から「上を向いて歩こう」という曲を、不朽の名作と思っている。そんなこと、いまさらおまえに云われなくても、誰もがそう思っているよ──という声が聞こえてきそう。まったく、そのとおりだ。この曲、シングル盤は1961年10月に発売されてから、たったの3か月で30万枚も売れたという。1963年にアメリカでもリリースされ、ビルボード誌で3週連続1位を獲得、年間ランキングでも10位にランクインした。でもぼくの場合、この曲を高く評価するとき、実はレコードが大ヒットを記録したことなどは、ほとんど考慮に入れていない。なまいきな口を利くようでおこがましいのだが、音楽として純粋に向き合ったとき、やはりこの曲はよくできているなと、ぼくは感じるのである。
必ずしも売れたらそれがよくできた曲というわけではないが、この「上を向いて歩こう」の場合、よくできた曲だから売れたのだろう。早世が惜しまれるエンターテイナー、坂本九によるエルヴィス・プレスリーやバディ・ホリーから影響を受けた、ちょっとバタくさい独特のヴォーカル・パフォーマンスも然ることながら、ジャズ・ピアニスト、中村八大によるソングライティングのセンスが素晴らしい。中村さんといえば、1950年代に小野満(b)、ジョージ川口(ds)、松本英彦(ts)とともに結成されたビッグ・フォアでの活躍が有名。このクァルテット、後期にはあの渡辺貞夫(as)が加わることもあった。日本のジャズにおけるビッグネームばかりだ。そして、中村さんの洗練された作曲のセンスは、やはりジャズがおおもととなっているのである。
この曲のいい点は、なんといってもメロディとコードがシンプルなところ。全体の曲調はとても単調で明るい感じなのだが、ときおり分数コードが出てきたりマイナーキーになったりして、どことなく愁いを帯びてくる。そんなところには、ボサノヴァのサウダージ感覚に共通する味わいがある。簡単に云うと、ノスタルジックな切なさ。まえに進みながらも、二度と戻ることのできない過去を懐かしみ、胸が締めつけられる──そんな気持ちだ。永六輔による軽妙な歌詞もまた然り。いずれにしてもぼくは、そういうさり気ない感覚が好きなのだ。これは余談だが、ぼくは作曲についてはまったくの独学で、たぶんいちばん影響を受けたのはブラジルのアントニオ・カルロス・ジョビンだろう。フランスのフランシス・レイも好きだけれど、たとえば「ある愛の詩」(1970年)のように終始泣いているような曲は苦手だ。
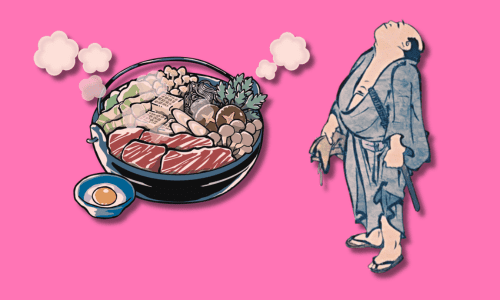
よくシンプル・イズ・ベストというけれど、この「上を向いて歩こう」はその単純な構造と素朴なフィーリングゆえに、どんなシテュエーションにも対応する最良の曲と云える。たとえば、この曲を聴いていると次々と代理コードがアタマに浮かんでくる。既存の曲をアレンジするときには、音楽のお色直しに合わせてコードの置き換えを要することがある。そんなときこの曲は、様々なスタイルを想定することができる。また即興で演奏するときにも、非常にリハーモナイズしやすかったりする。そんな優れた機能性を有するからこの曲は、音楽のジャンル、アーティストの性別、国の内外などを問わず、何度となくカヴァーされてきた。結果的に、エヴァーグリーンな一曲となっている。
名曲「上を向いて歩こう」は、英語圏では一般的に「SUKIYAKI」のタイトルで親しまれている。これは、有名だ。念のために云っておくと、英語詞のどこを探しても“すき焼き”という単語は出てこない。ではなぜ、そんな曲名になってしまったのか?海外での最初のヒットは1962年のことで、英国のパイ・レコードに所属するジャズのトランペッター、ケニー・ボールのインスト・ヴァージョンが全英チャートで10位にランクインした。ボールとしてははじめから曲名に日本語を使うつもりだったのだが、原題の「UE WO MUITE ARUKOU」では長過ぎるということで、たまたま知っていた日本語のひとつ「SUKIYAKI」を選んだ。ほかにも曲名の由来には、僚友のシンガー、ペトゥラ・クラークの勧めとか、パイ・レコードの社長、ルイス・ベンジャミンの日本ですき焼きを食べた思い出とか、諸説ある。
それはともかく、以後「上を向いて歩こう」は様々なアーティストによってカヴァーされることになるのだが、やはりオリジナルを凌駕するのはなかなか至難の業というもの。なにせ原曲は、作曲者の中村八大が自ら手がけたアレンジもまた金城鉄壁なものだからだ。やはりシンプルなのだけれど、無駄な音がないぶんなんとも軽やかで洒落ている。飾り気のないマリンバと穏やかなストリングスによるイントロがちょっとウェスタン風。リズム・セクションによるスウィンギーなリズムと坂本さんのロックンロール調のヴォーカルとのコントラストが鮮やかで、爽やかな空気を作り出している。間奏の口笛も、坂本さんによるものだ。ストリングスとトロンボーンを主体としたホーン・セクションがサウンドに温かみを添えている。フルートとシロフォンのユニゾンも気の利いたアクセントとなっている。
4枚のアルバムを残して消滅したテイスト・オブ・ハニーとは──
この中村八大によるアレンジは、トータル的にぼくの好み。音を鳴らすべきとき、潜めるべきとき、休ませるべきときを的確に判断し、音の無駄遣いをしないやりかただ。結果的に、それまでの流行歌とはひと味もふた味も違う、エレガントでハイセンスな響きが生み出されている。あの時代にしてこの爽やかで洗練されたサウンドは、おそらくジャズを経験した中村さんだからこそクリエイトできたもの。ある意味で、ここまでソツのないアレンジは逆に巧妙な作法とさえ、ぼくには思える。仮にこのソフィスティケーテッドなサウンドをバックに、名優ジーン・ケリーが歌って踊ったとしても、たぶん違和感はないだろう。それはきっと、さながらハリウッド黄金時代の映画作品のワンシーンのような絵面になるに違いない。
ただ数ある「上を向いて歩こう」のカヴァーのなかに、ぼくも声を大にして「これだけは聴いていただきたい」と云いたくなるような傑作がある。正直に云うと、オリジナルよりも好きだったりする。それは1970年代から1980年代前半まで活動したディスコ&ソウル・グループ、テイスト・オブ・ハニーによるカヴァー。1981年のビルボード誌において、ソウル、アダルト・コンテンポラリーの両チャートで全米1位、ポップ・チャートで3位を記録した。日本では東芝EMIからシングル盤が発売されたが、タイトルが「スキヤキ ’81」となっていた。しかもこのグループ、1981年9月21日放送された日本テレビの音楽番組『ザ・トップテン』で、本家の坂本九と共演も果たしている。それ以前にも、1979年に開催された第8回東京音楽祭で金賞を受賞しているから、ご存知のかたも多いと思う。
テイスト・オブ・ハニーは、1971年にロサンゼルスで結成された。当初は南カリフォルニアのクラブや米国の軍事基地で演奏活動を開始。米軍慰問協会(USO)のツアーで、アラスカをはじめ、スペイン、モロッコ、タイ、そして日本を訪れたこともある。次第に知名度が高まり、1976年にキャピトル・レコードと契約。ファースト・シングル「今夜はブギ・ウギ・ウギ」は、1978年のビルボード誌のHot 100で3週間1位を獲得し、200万枚の売り上げを記録した。結局デビューしたばかりのこのグループは、このシングル盤とアルバム『今夜はブギ・ウギ・ウギ』(1978年/原題は『A Taste Of Honey』)とで、2枚のプラチナディスクを手に入れた。さらに1979年には、第20回グラミー賞において最優秀新人賞も受賞している。
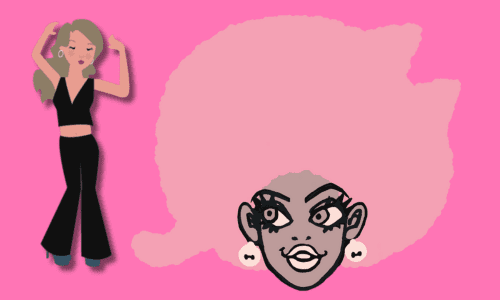
テイスト・オブ・ハニーは、かねてからともにバンド活動をしていたジャニス・マリー・ジョンソン(b, vo)とペリー・キブル(key)が中心となって立ち上げられた。メンバーとしてカーリータ・ドーハン(g,vo)、ドナルド・レイ・ジョンソン(ds)が参加。一時期ではあるが、グレゴリー・ウォーカー(vo)がリードを務めることもあった。グループ名は、ボビー・スコットとリック・マーロウによって書かれた舞台劇の楽曲「蜜の味」にちなんで付けられた。なおオリジナルは、スコットの1960年にリリースされた同名のアルバムに収録されている。ビートルズやハーブ・アルパート&ザ・ティファナ・ブラスのカヴァーでも有名な曲である。とにもかくにも、1976年にドーハンが脱退、ヘイゼル・ペイン(g, vo)がその後釜に座り、グループはひとたび落ち着く。
残念なことに、テイスト・オブ・ハニーは活動期間が短くアルバムも少ない。前述の『今夜はブギ・ウギ・ウギ』をはじめ『ドゥ・イット!! アナザー・テイスト』(1979年/原題は『Another Taste』)『シーズ・ア・ダンサー』(1980年/原題は『Twice As Sweet』)『淑女のためいき』(1982年/原題は『Ladies Of The Eighties』)と、たったの4枚をリリースするのみ(なお2作目の日本盤には「今夜はブギ・ウギ・ウギ」のショート・ヴァージョンが追加収録された)。デビュー作は高く評価されたが、それ以降「SUKIYAKI」以外はヒットに恵まれず、セカンド・アルバム発売後にはキブルとレイ・ジョンソンがグループを離脱する。結果的に女性陣のみが残ったわけだが、考えてみればこのグループは、ファースト・アルバムからマリー・ジョンソンとペインとによる女性ファンク・ユニットという印象を与えていた。
結局テイスト・オブ・ハニーは、フォース・アルバムをリリースして間もなく正式に解散となった。その後、マリー・ジョンソンは、ゲイリー・ゴーツマンとマイク・ピッキリロのプロデュース、ロサンゼルスの名うてのミュージシャンのサポートを得て、キャピトル・レコードから『ワン・テイスト・オブ・ハニー』(1984年)というソロ・アルバムをリリースした。さらに自主制作盤『ハイエイタス・オブ・ザ・ハート』(1999年)も発表。彼女はソングライター、ベーシスト、ヴォーカリストとして才媛ぶりを発揮したが、デビューまえにマイルス・デイヴィスのライヴのオープニングアクトのシンガーを務めたこともある。かたやペインは、国際的な舞台女優に転身。しばらくしてマリー・ジョンソンとペインは、アメリカの公共放送サービスであるPBSテレビが制作した、2004年と2005年の特別番組で再共演した。
さきにグループを脱退したレイ・ジョンソンは、カナダ西部に拠点を構えドラマー、ブルース・シンガーとして活動し、アルバムも数枚吹き込んでいる。いまひとりのキブルも、おなじく1991年にカナダに移り、アルバータ州カルガリー市の音楽シーンに大いに貢献した。地元のバンドをプロデュースしたり、プレイヤーとしてジャムセッションに参加したりしていたが、悲しいことに1999年2月、心不全のため49歳という若さでこの世を去った。まだまだテイスト・オブ・ハニーのメンバーの各々には、知られざる逸話、込み入った事情がありそうだが、いずれにせよリリースされたアルバムが5年間で4枚というのは、その真価が発揮される機会としては充分とは云い難い。当時、日本でもワンヒット・ワンダー的な扱いをされたが、ぼくはひとりで憤慨していたもの。
「上を向いて歩こう」のカヴァー収録──『シーズ・ア・ダンサー』
それくらい、ぼくはテイスト・オブ・ハニーの音楽が好きだったのである。いまでもそれは、まったく変わらない。ぼくがこのグループに関心をもったのは、日本でファースト・アルバムが発売されたときだから、それ以降もほぼリアルタイムでそのサウンドを追いかけたことになる。LP『今夜はブギ・ウギ・ウギ』の国内盤のタスキには「エロチックに絡みあうヘイゼルのギター、ジャニスのベース、そして2人の歌声は甘い蜜のささやき──、全米のディスコを直撃したセクシー旋風、遂に日本上陸!!」と記されていた。まったく上手いことを云うものだが、ぼくが注目したのはそこではない。このアルバムをプロデュースを手がけたのが、フォンス・マイゼルとラリー・マイゼル、すなわちザ・マイゼル・ブラザーズということに惹かれたのである。
つまり、テイスト・オブ・ハニーのデビュー作は、スカイ・ハイ・プロダクションの制作作品なのだ。おりしもぼくは、スカイ・ハイ・サウンドに馴染んでいた。というかそれは、ちょうどジャズとフュージョンを並行して聴きあさりはじめた時期だった。だから、ドナルド・バード(tp)をはじめ、ボビー・ハンフリー(fl)、ジョニー・ハモンド(org)、ゲイリー・バーツ(sax)などの、ジャズとソウルが融合したクロスオーヴァー/フュージョン作品に触れて、マイゼル兄弟の仕事ぶりにも注目していたわけだ。フェンダー・ローズやクラヴィネット、それにシンセサイザーの音色も然ることながら、清涼感と飛翔感に富んだストリングスのアレンジに惹かれた。モータウン・サウンドの立役者、ウェイド・マーカスによるアレンジだ。
当時を振り返ってみると、早くからジャズにソウルの要素を採り入れていたクインシー・ジョーンズやロイ・エアーズなどの作品も、このころからディスコティークを席巻するようなダンサブルな音楽へと、舵を切っていたように思われる。マイゼル兄弟とマーカスは、セカンド・アルバムまでテイスト・オブ・ハニーをサポートしたが、偶然なのか必然なのか、レイ・ジョンソンとキブルの脱退と同時にこのグループから離れることになる。その理由はいまになってみれば、彼らが1980年代に入って音楽シーンから遠ざかったことを視野に入れると、音楽トレンドの変化と因果関係があったように思われる。これも時代の流れか?いずれにしてもサード・アルバムのプロデューサーには、より幅広い音楽性を身につけたフュージョン界のオールラウンダー、ジョージ・デュークが起用された(なお4作目はもとEW&Fのギタリスト、アル・マッケイがプロデュースを務めた)。

この『シーズ・ア・ダンサー』こそ、前述の「上を向いて歩こう」のカヴァーが収録されたアルバムである。レコーディング・メンバーといえば、ジョージ・デューク(key)をはじめ、ローランド・バティスタ(g)、バイロン・ミラー(b)、リッキー・ローソン(ds)、パウリーニョ・ダ・コスタ(perc)といったリズム・セクションに、ザ・シーウィンド・ホーンズが加わっている。デュークのリーダー作『ブラジリアン・ラヴ・アフェア』(1980年)と参加メンバーがかぶり、同じ年にデュークがプロデュースを手がけたシーウィンドの『海鳥』(1980年)とサウンド的に類似するところがある。デュークならではのファンキーなプレイとエッジの効いたサウンドで、過去の2作と比べるとかなりコンテンポラリーなディスコ作品にアップデートされた感じだ。
オープナーの「星空のパーティ」は、フォーオンザフロアとブギーがミックスされた、アップテンポのジャズ・ファンク。ヤマハ・エレクトリック・グランドとラップの絡みもクール。マリー・ジョンソン&ペインとデュークの出会いが生んだ最大の成果と云える。つづく「レスキュー・ミー」は、シンコペーテッドなビートが美味しい、クラシック・ブレイクとしても重宝される曲。シャープなホーン・セクションと浮き立つようなティンバレスも効果的だ。3曲目の「スーパースター・スーパーマン」は、がらっと変わってマイルドな8ビート。ペインがキュートに歌い上げる。「トーキン・アバウト・ユー」は、スラップ・ベースが効いた典型的なディスコ・ビート・ナンバー。アルトのソロも情熱的だ。
後半の1曲目の「シーズ・ア・ダンサー」は、木森俊之とケーシー・ランキンが提供したアップテンポの8ビート。グループとしては新境地と云えるかもしれないが、当時の日本の歌謡曲をイメージさせるのはご愛嬌。つづく「リード・ミー・オン」は、シーウィンドの楽曲を彷彿させる爽やかなフュージョン・ブギー。AOR的なメロウな味わいがいい。3曲目「グッドバイ・ベイビー」は、ミディアム・テンポのまろやかなソウル・バラード。ぼくはこの曲を、クワイエット・ストームの隠れた名曲として高く評価するのだが、実は好きが高じて自分のバンドでカヴァーしたことがある。さらに「セイ・ザット・ユール・ステイ」は、構成の妙味が素晴らしい。ファンキーでスローな16ビートからポップな2/2拍子、そしてテンポがアップして8ビートになるという、盛り上げかたが上手い。
そしてアルバムのラストを飾るのが、お待たせの「スキヤキ(上を向いて歩こう)」である。日系アメリカ人三世によるバンドHIROSHIMAのメンバー、ジューン・クラモトによる琴がサウンドスケープを桜色に染める。デュークのシンプルでフレキシブルなリズム・アレンジが心地いい律動を紡いでいく。ちょっとハスキーなマリー・ジョンソンのヴォーカルは、艶やかさのなかにもときおり愁いを帯びる。ジャズ・ピアニストでフュージョンやラテン・ミュージックもこなすクレア・フィッシャーのアレンジによるストリングスもそつなく美しい。もはや坂本九の顔は、どこにも浮かんでこない。しかしひとがなんと云おうと、ぼくは原曲よりもこのヴァージョンのほうが好きだ。と同時に、こういうオリエンタルな楽曲をサラッと演ってしまうテイスト・オブ・ハニーというグループに、奥深い音楽性すら感じるのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント