ヴォコーダーを多用したハービー・ハンコックのポップなグルーヴ・アルバム『サンライト』
 Album : Herbie Hancock / Sunlight (1978)
Album : Herbie Hancock / Sunlight (1978)
Today’s Tune : Come Running To Me
気がつかぬうちに苦手意識を感じていた優等生のようなアーティスト
ぼくは、優等生が苦手だった。出し抜けに不躾な物言いで、申し訳ない。全国の品行、成績ともに優れた児童、生徒、学生のみなさん、そしてかつて優等生で現在ひとかどの人物として活躍されているかたがた、決して悪気はないので、どうか取るに足らないオッサンのたわ言と聞き流していただきたい。加えて純粋に音楽への興味からこの雑文を読んでくださっているみなさん、だんぜん冒頭から以下二三節ほど読み飛ばすことをお勧めする。なぜならしばらくの間、飽くまで私的な雑記にとどまるばかりで、みなさんにとって得るところはまったくないからである。ということで、ハナシをさきに進める。ぼくがなぜ優等生を苦手と感じるようになったのかといえば、はっきり覚えがある。記憶を辿ると、高校時代まで遡ることになる。
ぼくが優等生が苦手だったのは、もとはといえば自分自身が劣等生だったからだ。高校時代のぼくは日々音楽に興じ、打ち込むのはピアノのレッスンばかり。残りの時間は、好きな本を読んでいるだけ。そんなヤツの学業成績が、良好であるわけがない。まだ小学生や中学生のころは、ピアノが弾ける男の子として尊敬の眼差しを向けられることもあった。だから勉強ができなくても、劣等感を抱くことはほとんどなかった。しかしながら高校生ともなると、健全な生徒であれば大学への進学を最優先事項に位置付けるもの。いくらピアノが上手く弾けても、ぼくのように出来のわるいヤツは単に落ちこぼれと見られるばかり。ぼく自身にも、たとえビル・エヴァンスを聴いて、太宰治を読んで、自分のなかに哲学みたいなものをもったりしても、結局は自分が価値のない人間のように思えるのだった。
そんな現状の自分が他者に比べて劣っていると主観的に感じながら、ぼくはどんどん内向的な高校生になっていった。ただ不思議なことに、成績優秀者がもてはやされるのをねたましく思うようなことはなかった。たぶん当時のぼくの興味や関心は、音楽や文学のなかに自分のアイデンティティを見つけることに向いていたのだろう。ぼくは自分の内面を重視するばかりで、外部のことをあまり気にかけなかったし、他者と積極的に接触するのもあまり好まなかった。いまから思えば、相当やなヤツだったな──。そんなぼくにも、数学の模試で全国2位の成績を収めた経験がある。もちろん、まぐれだ。担任の女性教師にも笑いながらそう云われたが、情けないことに、このあまりにもウソみたいな出来事を自分でも笑ってしまった。

ところがそれから間もなく、学年トップの男の子から声をかけられた。彼の名前は学校内に轟きわたっていたが、彼とぼくとはまったく面識がなかった。実はぼくの優等生に対する偏見が強くなったのは、この出来事がキッカケとなっている。彼はそれまでぼくのことなどつゆほども気にかけなかっただろうし、存在すら知らなかったと思われる。それなのに彼は、初対面のぼくに「ねえ、ぼくたち、友だちにならない?」と提言してきたのだ。そのときのぼくは、きっと鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしていたに違いない。もし彼のなかに同族意識があったのならば、それは大いなる勘違い。そもそも友だちになるのに、いちいち「友だちにならない?」と訊くものなのか?恐るべし、優等生。彼はそれを平然とやってのけたのである。
おそらく優等生はなんでもできるから、自分なら誰とでも友だちになれると信じていたのだろう。自分が下した判断を一抹の疑いもなく正しいと思える、その自信に満ちたところはちょっと羨ましい。それでも人間とは、間違う生きもの。彼は自分の見込み違いに気がつくと、ぼくに二度と近づくことはなかった。それでいい──。ということで閑話休題、ここからは音楽のハナシをしよう。ぼくは常々ハービー・ハンコックという音楽家を、優等生のように感じている。上記の経験がコンプレックスとなっているからか、ぼくは優等生のようなハンコックに対して、自分でも気がつかぬうちに苦手意識をもってしまっていた。まあ、ハンコックほどの偉大な音楽家ともなると、これまでに散々語られただろうから、ここはひとつ彼のことを主観的に述べてみるとしよう。
ハービー・ハンコックというと、オールラウンドなアーティストというイメージが強い。単純にジャズ・ピアニストとは云えないところが、いささかやっかいではある。あれは中学生になったばかりのことだったと記憶するが、ぼくはブルーノート盤『ウォーターメロン・マン』(1962年/原題は『Takin’ Off』)と、コロムビア盤『ヘッド・ハンターズ』(1973年)をほぼ同時期に体験した。それ以前に彼のピアノ演奏は、すでにマイルス・デイヴィスのアルバムで聴いていたのだが、ぼくにとっては強く印象に残るところはなかった。なにせそのころのぼくはといえば、マイルスの『カインド・オブ・ブルー』(1959年)を聴いて、モード・ジャズの響きに魅了され、すっかりビル・エヴァンスのピアノ・プレイに心酔していたのだから。
ぼくは高校の卒業文集に、エヴァンスのピアノ演奏と出会って自分の人生が変わったと書いている。それに対してハンコックのピアノ演奏に巧妙さはあれど、人生を変えるほどの影響力はなかったように思う。それでも世間で大人気のハンコックのアルバムも聴いておかねばと購入したのが、さきの2枚のアルバム。はじめて『ウォーターメロン・マン』を聴いたとき、冒頭のジャジーな8ビートの表題曲にしても、2曲目以降のハード・バップ的な曲、あるいはバップの可能性を押し広げるような曲にしても、中学生のぼくにも率直に受け入れることができた。全6曲、すべてハンコックのオリジナルだ。ただピアノのアドリブはそつなくまとまっているように感じられたので、このひとは作曲やアレンジに長けた音楽家なのだろうと、当時のぼくは勝手に決めつけていた。
「処女航海」のソングライティングと「スライ」のピアノ・プレイ
かたや『ヘッド・ハンターズ』もまた、当時からあまねく音楽ファンに知られるレコードだった。オープナーの「カメレオン」は、一度聴いたら忘れられない名曲。ミニモーグによるベース・ラインは、あまりにも有名。ギタリストがいないので、ハンコックによるクラヴィネットがリズミカルなリフを刻む。ハーヴィー・メイソンのドラムスは歴史に残る名演。ハンコックのフェンダー・ローズによるダブル・クロマティック・アプローチが活かされたアドリブ・ソロ以外は、ジャズらしさは感じられない。これはディスコティークで重宝されるような、ファンク・ナンバーだ。前述の「ウォーターメロン・マン」も、ファンクにお色直しされている。全4曲、(共作を含む)すべてハンコックのオリジナルである。
このアルバムに収録されている「スライ」という曲で、ハンコックはすごいことになる。曲名は、当時サンフランシスコを本拠地として活動していたファンク・グループ、スライ&ザ・ファミリー・ストーンのリーダー、スライ・ストーンにちなんだもの。なお『ヘッド・ハンターズ』も、サンフランシスコでレコーディングされた。これはあとから知ったのだが、ハンコックはスライの音楽に影響されて、自分なりのファンクを追求するようになったという。スタジオに入るまえにもレコーディング・メンバーにより、サンフランシスコ・ベイエリアの何箇所かのクラブでデモンストレーションが行われ、ライヴは大盛況のうちに終わった。そのせいかアルバムでは、よく練られた構成と息の合った演奏が際立つ。
ところで「スライ」という曲だが、テーマ部ではゆったりしたテンポで、泥くささと洗練された雰囲気がほどよくブレンドされた、シンプルなメロディック・ラインが歌われる。ところがアドリブ・パートになると、ちょっとジャズ・ロック風になったあと、いきなり高速になりベニー・モウピンのソプラノがワイルドでアーシーなソロを展開する。問題はそのあとのハンコック。メイソンのドラムスが打ち出す軽快かつ強烈な16ビートを中心にメンバー全員が一丸となって疾走するなか、ハンコックのローズが飛翔する。それもクールかつセオレティカルに。ターゲット・ノートを目指して半音階でアプローチしたり激しくアウトしたりする。そのサウンドからイメージされる心象風景といえば、たとえば火球が高層ビルの谷間を飛び巡るといったものである。
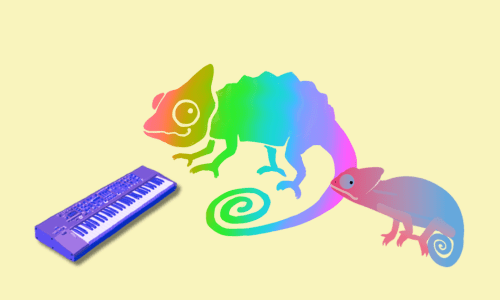
ぼくがハンコックがすごいピアニストであると実感したのは、まさにこの「スライ」においてだった。それと同時に、このときはハンコックがどのような音楽教育を受けたかはまったく知らなかったけれど、直感的に彼のことを芸術系の教育機関でオナーロールをもらうタイプと感じた。実際はちょっと違ったのだけれど、小学生のころからピアノ演奏は抜群に上手く、学業においても飛び級するほど優秀だったという。つまり優等生というわけだ。いずれにしても演奏技術や音楽理論、ことにスケールやコードに関しては、しっかり学び修得したことは間違いない。ぼくは「スライ」におけるハンコックのプレイから、彼が音楽の構造や手法を知り尽くしたひとと確信したのである。
高校生になってからも、ぼくはハンコックの1960年代のブルーノートにおけるポスト・バップ作品と、1970年代のコロムビアにおけるエレクトリック・サウンドが導入されたジャズ・ファンク作品とを、並行して聴いていた。ところが彼のアルバムを聴いているときのぼくは、どうしたものかいつでも居住まいを正してしまう。そして、ハンコックの演奏に集中しているときの自分が、腰を据えて音楽を楽しんでいないことに気がつくのである。ときには逆に、なんとも不届きなことだが、ぼくは珠玉の作品群をBGMとして聴き流してしまうことさえあった。時代の先端を行くような楽曲のなかには大好きなものがたくさんあるのだが、なぜか彼の巧みなキーボード・ワークがエスカレートすればするほど、ぼくの気持ちは冷めてしまうのだった。
それは云うまでもなく、ぼくのなかにある驚異的なピアノのテクニックに対する、まさに劣等複合と呼ぶべき感情が表面化したものにほかならない。なにせ当時のぼくはといえば、劣等感のかたまりへの階段を着実に上りはじめていたのだから──。ただ幸いなことにハンコックの作編曲に関しては、素直に受け入れることができた。むしろニュー・スタンダードとも称されるような新時代の名曲として、たいへん魅力的なものとして感じられた。さきに挙げた2枚のアルバムの幕開けの曲をはじめ「カンタロープ・アイランド」「ワン・フィンガー・スナップ」「スピーク・ライク・ア・チャイルド」「アイ・ハヴ・ア・ドリーム」「テル・ミー・ア・ベッドタイム・ストーリー」「アクチュアル・プルーフ」「バタフライ」と、好きな曲を挙げれば切りがない。
特にブルーノート・レコード第5作『処女航海』(1965年)は、どの曲もパーフェクト。統一的に“海”が基調とされたファンタスティックな楽曲たちは、おそらく意識的にだろうが、コードチェンジなどの従前のジャズの方式が使われておらず、ドラマティックな展開を見せるばかり。それが聴くものにフレッシュな感動を与えるという、実によく練られた作りとなっている。この点は、マイルスにも影響を与えた。全5曲、やはりすべてハンコックのオリジナル。なかでもタイトル・ナンバーの「処女航海」は、稀に見る傑作だ。オープンエンドなコード進行が、とにかく新しい。ハーモニーが着地点を定めずに循環しつづけるところは、それこそ大海原をあてどもなく彷徨する船のごとし。これはもはや、ジャズというカテゴリーに収まり切らない名曲と、ぼくには感じられた。
ヴォコーダーとポップでグルーヴィーな新たなハンコック・サウンド
またアルバムのラストに「ドルフィン・ダンス」というミディアム・スウィングの曲が収録されているが、この曲などはすっかりスタンダード化している。モティーフの展開と転調が上手く使われて書かれているが、これはぼくの好きなやりかたで、個人的には作曲法のお手本となった。ハンコック自身もお気に入りなのか『デディケーション』(1974年)や『ハービー・ハンコック・トリオ WITH ロン・カーター+トニー・ウイリアムス』(1981年)などで、彼はこの曲を再演している(前者はソロ、後者はトリオ)。ぼくとしてはそれらのハンコックの演奏よりも、トリオだったらビル・エヴァンスの『アイ・ウィル・セイ・グッドバイ』(1980年)収録版、コンボだったらグローヴァー・ワシントン・ジュニアの『シークレット・プレイス』(1976年)収録版のほうが好みだ。まあ、作者自身の吹き込みよりも優れたが演奏が存在するからこそ、その曲はスタンダードと呼ばれるのかもしれない。
それはともかく、このアルバムのレコーディング・メンバーは、マイルスの俗に云うセカンド・グレイト・クインテットのそれと重なるわけだが、帝王が不在だからかいつもに比べてぐっとリラックスしたプレイを披露している。ハンコックも普段よりのびのびとピアノを弾いているように、当時のぼくには聴こえたもの。そんなユニークな趣向や着想が際立っているいっぽうで、どこか気安い雰囲気が漂っていたから、このアルバムにおいてはぼくも素直にハンコックの音楽を楽しむことができた。それでもやはり、その後のヘッド・ハンターズによるエレクトリックなファンク路線、ハンコックにしては珍しいピアノ・トリオ、マイルス時代を回顧するようなV.S.O.P.クインテットと、ぼくはなにを聴いてもすごいと感じるばかりで、彼の演奏にのめり込むことはなかった。
とはいえ、ぼくがハンコックのアルバムを聴きつづけたのは、彼の創造する音世界(サウンドやソングライティング)に対しては、食指が動いたからだろう。それから間もなく、ハンコックから離れることを踏みとどまった甲斐あってか、ついに劣等感いっぱいのぼくでももろ手を上げて称賛したくなるような彼のアルバムと遭遇することができた。なぜこれを早く聴かなかったのだろう?ハンコックはダンス・ミュージックへの傾倒の片鱗をのぞかせた『シークレッツ』(1976年)をリリースしたあと、V.S.O.P.クインテットに集中していたが、2年ぶりにエレクトリック作品を発表。それは、それまでのファンク路線が踏襲されながらも、ポップス、ディスコ、ラテン、それにジャズなど、様々な要素が織り交ぜられたフュージョン作『サンライト』(1978年)である。
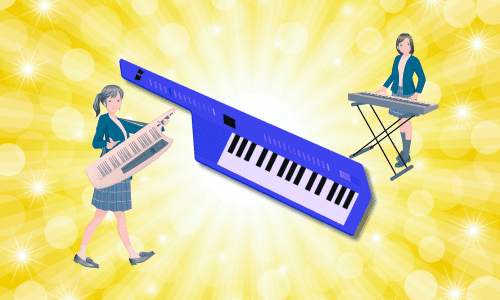
レコード・ジャケットのバックカヴァーにプリントされている写真には、マイクロモーグを弾くハンコックと、計11台のキーボードが写っている。一見仰々しい印象を受けるのだが、実際にシンセサイザーは飽くまでサウンドの色彩を豊かにするツールとしての使用にとどまっている。ハンコックはフェンダー・ローズを主軸に据え、シンセ類については肩肘張らずに使用しており、そのさらっとした味わいに好感がもてる。ただ、ここでは新たな小道具としてドイツのゼンハイザー社製アナログ・ヴォコーダーVSM-201が多用されている。ヴォコーダーとは、その名称がヴォイスとエンコーダーを合わせたものであることからもわかるように、簡単に云えば人声を電子音に変換するシンセ。全5曲、(共作を含む)すべてハンコックのオリジナルだが、最初の3曲で彼自身がこの楽器を使って歌っている。
ポップでジャジーな「アイ・ソート・イット・ワズ・ユー」は、ハンコックにしては珍しくライトトーンの曲。リズムがタイトでダンサブルなところは、ブギー・クラシックとして重宝しそう。ハンコックのローズもファンキーでいいが、彼のペンによるブラス・セクションが効果的。優雅なミディアムテンポのフュージョン・ナンバー「カム・ランニング・トゥ・ミー」は、ホーンズとストリングスが彩りを添える爽快な曲。変化に富んだリズムとコード進行が巧妙で、いかにもハンコックらしい。ローズもほどよく跳ねる、隠れた名曲だ。バウンスするリズムが心地いい「サンライト」は、ベニー・モウピンのソプラノも登場するファンキー・チューン。ある意味で、もっともジャズらしくない曲だ。以上の3曲でハンコックのヴォーカルがフィーチュアされるが、アンサンブルにすっかり溶け込んでおり、どの曲もどちらかといえばインストゥルメンタルのような感覚で聴ける。ことにヴォコーダーをはじめとする電子音に、人間味溢れる温かさが感じられるのが素晴らしい。
展開の妙で聴かせるような「ノー・ミーンズ・イエス」では、ハンコックのローズとそれに呼応するハーヴィー・メイソンのドラムスによって熱いバトルが繰り広げられる。柔軟性に富んだリズム・セクションのみの演奏が、なんとも痛快だ。それに反して、ジャコ・パストリアス(b)とトニー・ウィリアムス(ds)が参加した「グッド・クエスチョン」は、ちょっと壮絶過ぎる。ハンコックもアコースティック・ピアノにもち替えて、どこまでも渾身のインプロヴィゼーションを押し広げていく。これは優等生である彼なりの、熱心なファンへのサービスなのだろう。しかしながらアルバムのポップな流れにおいては、まったく場違いなテイクと思われる。とはいってもそんな矛盾も、本作を1980年代のポップでグルーヴィーなハンコック・サウンドの前哨戦と観れば、許容範囲内ではある。
本作以降ハンコックは、カルロス・サンタナ(g)、レイ・パーカー・ジュニア(g)、ロッド・テンパートン(key)、ビル・ラズウェル(b)といった、ジャズ以外のミュージシャンとのコラボレーションにより、自己のリーダー作にディスコからヒップ・ホップまで大胆に導入していく。このポップ路線には、批判的なひとも多い。ジャズ以外の音楽に溶け込んでいく彼を、体色変化にたとえてカメレオンと揶揄する向きもあった。でもぼくは、そんな彼については肯定派。音楽家はやりたいことをやればいい。きっとハンコックの音楽に対する好奇心は、とどまることを知らないのだろう。7歳からピアノを弾きはじめ、11歳にしてシカゴ交響楽団と共演し、大学で専攻を電気工学から音楽に変更する以前に、すでに独学でジャズ理論をマスターしていたハンコック。やはり、彼は優等生だ。しかしこんなぼくでも、優等生にシンパシーを感じる場合があるのである。ぼくにとって『サンライト』は、そんなアルバムだ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント