クラブ・シーンにおけるキラー・チューン「スキンドゥ・レ・レ」が収録された阿川泰子の『サングロウ 』
 Album : 阿川泰子 / Sunglow (1981)
Album : 阿川泰子 / Sunglow (1981)
Today’s Tune : Skindo-Le-Le
サラリーマンたちのアイドル、阿川泰子はジャズ・シンガーなのか?
どんなものにも、買いにくいというものがある。ここで云う買いにくいとは、値段が高くて手が出ないとか、人気商品であるが故に入手が困難という状況を示唆するものではない。ぼくが云う買いにくいというのは、商品購入に対する気恥ずかしさからくる具合のわるさのこと。書店で高校や中学の男子生徒が、エッチな本を参考書と参考書とでサンドウイッチにしてレジカウンターにもっていくときの、あの心理状態だ。とはいってもいまの時代、そんなヤツはもういないかもしれない。だがぼくらの時代といえば、ティーンエイジャーは過剰なまでに羞恥心というものをもって生きていたように思う。もちろんぼくのクラスにも、少数派だが厚顔無恥なヤツはいた。不思議なことにそういうヤカラにかぎって、みんなの人気者だったりする。
それはともかく、音楽作品においても買いにくいものがある。云うまでもなく、買いにくいという心情は個人的な事情からくるものである。これはぼくが高校生だったころのことだが、とあるレコードを購入する際になんとなく決まりのわるい思いをした経験がある。その場合、商品をレジカウンターにもっていくことも、確かに恥ずかしかった。しかしそれよりも、そのレコードを買ったという事実のほうが、だれに対してというわけでもないのだが、なにか面目が立たないように思えて仕方がなかったのだ。いまから考えると明らかに自意識過剰なのだが、あの時代の思春期の男子といえば、他人の目を意識するあまり極度の緊張状態に陥るほどセンシティヴだった。自分を美化するつもりは毛頭ないのだけれど──。
ところで、そのときぼくが人目をはばかるように手に入れたレコードはなにかというと、日本のジャズ・シンガー(と云われる)、阿川泰子の『サングロウ 』(1981年)である。どうでもいいことかもしれないが、阿川さんにとっては20代最後のレコーディングであり、レコードも三十路を迎えるまえに発売された。当時、阿川さんはすでに人気者だった。アルバムもデビュー作の『ヤスコ・ラヴ・バード』(1978年)から数えると、すでに4枚ほどリリースされていた。それでも当時のぼくは依然として、阿川さんにニューカマーというイメージをもっていた。まあその原因は、ぼくが彼女のことを名前くらいしか知らなかったというだけのこと。しかもぼくのなかでは、阿川さんとジャズとがまったく結びつかなかった。

阿川さんはジャズ・スタンダーズも歌っていたけれど、実質的にはポップ・シンガーとしてデビューしたのではなかったかな。彼女が一般的にジャズ・シンガーという肩書きをつけられるようになったのは、やはり4thアルバムの『ジャーニー』(1980年)がリリースされてからのことだろう。なにせこのレコード、曲目を観るとこれまでになく超有名なジャズ・スタンダーズがズラリ並んでいる。内容はどうあれ、うわべは立派なジャズ作品に見える。おまけにレコードのタスキには「YASUKOの最新作がジャズ・ヴォーカルの歴史を変える!」とまで記されている。確かにこのアルバム、実際に歴史を変えた。なんと本作は発売からおよそ半年で、9万枚のセールスを記録したのだという。日本のジャズ作品としては、異例中の異例だ。
この『ジャーニー』のことは、ぼくも知っていた。当時、レコード店に行けば必ずと云っていいほどどこでも面陳列されていたし、ラジオでもよくプレイされていた。あの頬杖をついてこちらに流し目を送る阿川さんのアップショットがあしらわれたジャケットには、いまにしてみれば実にしたたかなアートディレクションが感じられる。阿川さんはたいへんお綺麗なかただけれど、そこに写る彼女からショウビジネスのオーラのようなものはほとんど発散されていない。どちらかといえば、これから同伴する客を待ちわびている、クラブの美人ホステスさんのように見える。たとえば「食事に連れていってくれたら、遅刻は帳消しにしてあげる」なんて云われそうだ。飽くまで勝手な妄想だけれど──。
そんなジャケットのなかの阿川さんが醸し出す、高嶺の花でありながら身近にいそうな存在感、親しみやすい雰囲気は、さも日々汗をかきながら仕事に邁進する多くの男性たちの疲れた心身を癒しそうではないか。いずれにしても『ジャーニー』が売れたのは、多くのサラリーマンたちから絶大な支持を得たからだという。そんなことから阿川さんは、“ネクタイ族のアイドル”あるいは“オジサマ族のアイドル”という異名をとった。まだ高校生だったぼくは、そんなブームとはまったくの無縁。ショップでこのレコードを見るたびに、前述したように阿川さんを新人のシンガーと勘違いしていたぼくは、ちょっとあべ静江に似ているけれど、スゴい売り込みようだな──なんて、なんとなく思う程度だった。
そうこうしているうちに、ラジオで『ジャーニー』を実際に聴く機会が訪れた。そのときのぼくの感想といえば「ああ、これはジャズ・スタンダーズを歌っているけれど、ジャズのレコードではないのか」というものだ。日本の代表的なアレンジャー、前田憲男が編曲を担当していたり、実力派フュージョン・グループ、ザ・プレイヤーズのメンバーが参加していたり、レコーディングには贅が尽くされていたが、ほとんどジャズが感じられなかった。曲によってはむしろ、イージーリスニングやポップ・ミュージックのように聴こえた。もちろんジャズでなければいけないというわけではないけれど、笠井紀美子の『ジャスト・フレンズ』(1970年)や『バタフライ』(1979年)を愛聴していたぼくには、かなりもの足りなく感じられた。
確かに阿川さんの歌声は、少し鼻にかかった甘い感じで、とてもチャーミングだとは思ったけれど、彼女の演っている音楽自体に、当時のぼくはまったく興味がもてなかったのである。そんなわけで、そのときはいずれぼくが阿川さんのアルバムを手にとる日が来るとは、夢にも思わなかった。ところが、その日は案外早くやってきた。前述のように、ぼくは『ジャーニー』につづく阿川さんの5thアルバム『サングロウ』に、ことのほか食指を動かされたのだ。それは1981年の初夏のこと、ISUZUピアッツァというクルマのテレビCMで、阿川さんの歌声を聴いたとき。というか正確には、阿川さんの歌うメロディック・ラインに、ぼくはハッとさせられたのだった。それは、紛うかたなき既知の曲がカヴァーされたものだった。
憧れのヴィヴァ・ブラジル、そしてもっとも人気を博したアライヴ!
CMで使用されていたのは「シニア・ドリーム」というタイトルの曲で、アルバム『サングロウ』のリリースに先行してシングル盤として発売されていた。実はこの曲、シュガーローフ・レコードという超マイナー・レーベルからリリースされた『ヴィヴァ・ブラジル』(1980年)というレコードに収録されている「シー」という曲がオリジナルだ。原曲のほうも英語で歌われているが、阿川さんのカヴァーとはまったく違う歌詞である。アルバム・タイトルにもなっているヴィヴァ・ブラジルは、ブラジル出身のギタリスト、クラウディオ・アマラルをリーダーとするサンフランシスコのフュージョン・バンド。といっても、彼らのことを詳しく知るようになるのは、ずっとあとのことなのだけれど──。
あとで知ったのだが、この『ヴィヴァ・ブラジル』というレコードは、わずか3000枚しかプレスされなかった超レア盤。まだ日本から出たこともない高校生のぼくが、そんな希少盤を所持するはずもない。ジャケットさえ、見たことがなかった。しかしながらもつべきものは友で、中学時代のクラスメイトのKくんが、このアルバムを録音したカセットテープをぼくに貸してくれたのだ。レコードは彼のお兄さんのもので、海外に出かけたときに入手したとのこと。Kくんは親友というわけでもなかったけれど、云ってみれば聖人君子のようなひとだった。彼もジャズやフュージョンをよく聴いていて、ぼくのような変人にもずいぶんと親切に接してくれた。とにもかくにも、一聴で気に入った『ヴィヴァ・ブラジル』を、ぼくはちゃっかりコピーしてもらった。
ぼくが憧れの『ヴィヴァ・ブラジル』を手に入れたのは1990年代の半ばくらいのことで、そのときはシュガーローフ・レコードからアナログ・レコードのリプレス盤と同時にCDも発売された。2001年には日本盤もようやく発売されたけれど、曲順が大幅に変更されていた。それを見たぼくは、思わずニヤニヤしてしまった。というのも国内盤は、カリフォルニア州バークリー市に拠点を構えるレーベル、セヴン・ブリッジ・レコーディングスのマスターが使用されている。曲順の変更は、本作のクラブ・ジャズ・シーンでの人気を慮った、同レーベルの配慮なのだろう。結果的にオリジナルでは2曲目だった伝説のダンス・クラシックは、アルバムの冒頭にもってこられた。そう、あの「スキンドゥ・レ・レ」だ。
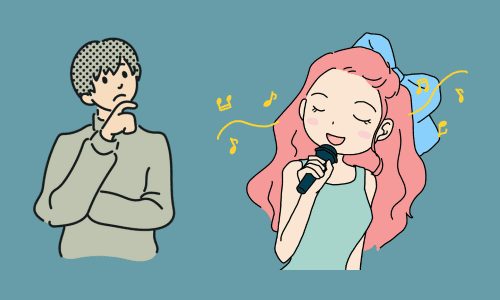
もうお気づきだろう、阿川さんの『サングロウ』には、前述の「シニア・ドリーム」とともに「スキンドゥ・レ・レ」が収録されている。当時はまぼろしのアルバムだった『ヴィヴァ・ブラジル』から2曲も採り上げられるなんて、ぼくにとっては奇跡のような出来事。食指が動かないわけがない。でもね、ジャケットを見たとたん、ぼくは『サングロウ』を購入すべきか否か逡巡した。阿川さんは怒るかもしれないけれど、腰に両手を当てた女史のウェストショットに、高校生には未知の世界であるウォータービジネスのかぐわしき香りを感じてしまったのだ。結局、勇気を出してこのレコードをレジカウンターにもっていったときも、店員のお兄さんに「オマエこれ買うのか?聖子か奈保子でも聴いとけよ」と、云われているような気がしたもの。
もちろん、これはぼくの被害妄想。でも阿川さんは、オジサマたちのアイドル。高校生は、蚊帳の外に置かれているのだ。現にぼくの部屋でこのレコードを見つけた父に「オマエこんなの聴くのか?」と云われた。ここでヴィヴァ・ブラジルについてうんぬんかんぬん説明しても仕方がないので、ぼくは平静を装いながら「まあね」とだけ云った覚えがある。ちょっとまえに『ジャーニー』を容認できなかった手前、あたかも早々に宗旨替えをしたかのような感覚にとらわれ、とにかく決まりがわるかった。堂々と『サングロウ』について語ることができるようになるのは、もうちょっとあとのこと。それは1982年、ヴィヴァ・ブラジルが阿川さんの7thアルバム『ファイン!』(1982年)に参加し、それを機に来日も果たしたときだ。
アルバム『ファイン!』においてヴィヴァ・ブラジルは、全10曲中5曲でソングライティングを担当(すべて新曲!)。5人のメンバーも、クラウディオ・アマラル(g)、ジェイ・ワグナー(key)、エドワード・ソレータ・サルマン(b)、ルーベンス・モウラ・ジュニア(ds, perc)、ケント ミドルトン(perc, fl)と、明らかになった。阿川さんと共演したライヴの模様は、ラジオやテレビでも放送されたが、タイムテーブルにおいて「スキンドゥ・レ・レ」は、ハイライトとなっていた。ヴィヴァ・ブラジルの生演奏は想像以上に素晴らしく、髪をショートにした阿川さんも魅力的に映った。それに乗じたぼくは『ファイン!』を公然と褒めそやし、ヴィヴァ・ブラジルについて高談雄弁したもの。
このころから阿川さんの音楽は、すでにオジサマたちだけのものではなくなっていたけれど、1990年代初頭には、あのアシッド・ジャズを推進したロンドン出身のDJ、ジャイルス・ピーターソンからも寵愛を受けるようになる。かたやヴィヴァ・ブラジルのほうもその少しまえ、のちにスムース・ジャズで人気を博すギタリスト、ジョイス・クーリングの初リーダー作『キャメオ』(1988年)を全面的にサポートし、ふたたび話題となった。このレコードは、サンフランシスコのマイナー・レーベル、ニュークリアス・レコードからリリースされたのだが、案外簡単に入手できた。ちなみにヴィヴァ・ブラジルのキーボードとソングライティングを担当するワグナーは、クーリングの公私にわたるパートナーだ。
さらに付言すると、アマラルとワグナーの共作「スキンドゥ・レ・レ」は、阿川さんがカヴァーしたちょっとあと、サンフランシスコに活動の拠点を置くブラジリアン・ジャズ・グループ、アライヴ!によって採り上げられた。いきおいブラジリアン・ジャズと云ってしまったが、このバンドのメンバーはみなアメリカ人。しかも全員女性で構成されており、特異な存在感を放っている。問題の「スキンドゥ・レ・レ」は、ビル・エヴァンスの敏腕女性マネジャーとして知られる、ヘレン・キーンがプロデュースを手がけた、彼女たちのサード・アルバム『シティ・ライフ』(1982年)に収録されている。ソウル・ジャズ・レコードの創設者ステュアート・ベイカーが監修した『ロンドン・ジャズ・クラシックス』(1993年)にコンパイルされたあたりから、人気に火がついた。
あらゆる音楽シーンでもてはやされる「スキンドゥ・レ・レ」
アライヴ!のヴァージョンは、前述のジャイルス・ピーターソンによるコンピレーション・アルバム『インクレディブル・サウンド・オブ・ジャイルス・ピーターソン』(1999年)にも収録された。つまり「スキンドゥ・レ・レ」はクラブ・シーンにおいて、このころにはすっかり、いわゆるキラー・チューンとなっていたのである。原曲よりアップビートでバウンシーな感じのアライヴ!版は、特に人気を博した。その後「スキンドゥ・レ・レ」という曲は広く知られるようになり、数多のミュージシャンによってカヴァーされるようになる。異色なところでは、声優の宮村優子までもが3枚目のアルバム『不意打ち』(1997年)のなかで、この曲をカヴァーしている。正直云って、EVA弐号機のパイロットそのままの歌声に、戸惑いを禁じ得ない。
もう少しだけ、つけ加えさえてほしい。ぼくにとって「スキンドゥ・レ・レ」のカヴァーで大本命といえば、カリフォルニア州オークランド市出身の女性シンガーソングライター、ローズ・アン・ディマランタ、通称ラッド(rad.)のヴァージョンである。シーラ E.のバンドのキーボーディストとして来日したこともあるので、この小柄なフィリピン系アメリカ人を記憶する向きもあるだろう。アシッド・ジャズ最盛期にドイツのハンブルグ市に拠点を構えるクラブ系レーベル、ソウルサイエティ・レコードからデビューしたときから、ぼくはずっと彼女の大ファンだ。そのソウルフルなヴォーカル・マナーとハイレヴェルなキーボード・ワークには、卓越した才能が光る。作曲や編曲のセンスも素晴らしい。
そんなラッドの「スキンドゥ・レ・レ」は、2001年に発売された彼女の3rdアルバム『ハイアー・プレーン』(1997年)の日本盤にボーナス・トラックとして収録されている(US盤やEU盤では聴けないのでご注意を)。ラッドのヴァージョンは、彼女にしては珍しくソウル色は薄めで、フォー・オン・ザ・フロアで疾走するアーバン・サウンドが魅力となっている。9分近くも洗練されたディスコ・ビートがキープされる踊れるナンバーだ。本作のリリース元が前述のセヴン・ブリッジ・レコーディングスだったり、ラッドがヴィヴァ・ブラジルやアライヴ!と同様に、アメリカ西海岸のベイ・エリア地区で活躍するミュージシャンだったりすることに強い因縁が感じられる。このことは、単なる偶然ではないだろう。
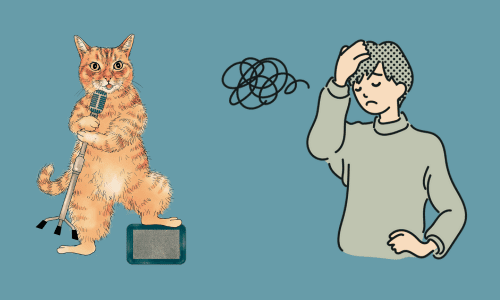
そして「スキンドゥ・レ・レ」が、いまやあらゆる音楽シーンでもてはやされるようになるキッカケを作ったのは、阿川さんであり、1980年代にクラブ・シーンからジャズ・カルチャーが派生していくなかで、そのパイオニア的な1枚となったのが『サングロウ』だったのである。ぼくにとっては、かつて人目をはばかるように手に入れたレコードではあったが、いまでは堂々とおすすめすることができるようになった。では、最後に名盤の誉れ高き『サングロウ』について、簡単にメモしておく。さきに述べたシングル盤としてお披露目された「シニア・ドリーム」と、そのB面のリチャード・ゲイナー作曲、ダイアン・シルヴァーソン作詞の「ソング・オブ・ザ・ウェイヴス」は、キーボーディストの北島直樹がアレンジを担当している。
ヴィヴァ・ブラジルのヴァージョンではスロー・バラード調の「シニア・ドリーム」は、北島さん率いるザ・キャストによって途中からアップテンポのサンバで演奏される。阿川さんのスキャットがかなり甘味だ。かたや「ソング・オブ・ザ・ウェイヴス」は、ピアノと加藤JOEグループのストリングスをバックに、阿川さんのハートウォーミングなバラード歌唱が聴ける。この2曲は、どちらかといえばポップス寄り。残りの7曲は、ラテン・フュージョン・バンド、松岡直也&ウィシングがバックを務めている。アルバム冒頭の「スキンドゥ・レ・レ」では、ハーモニクスで入ってくるストリングス、エッジの効いたホーン・セクション、カルナヴァル風のパーカッション、そしてラテン・タッチでオブリガートするピアノなどが、原曲とくらべても新鮮だ。
ボサノヴァとサンバがクロスする「シネマ」は、アントニオ・カルロス・ジョビンの『テラ・ブラジリス』(1980年)に収録されている「ヴォセ・ヴァイ・ヴェール」に、マイケル・フランクスが英語詞をつけたもの。フランクス自身も『アバンダンド・ガーデン』(1995年)で歌っている。松岡さんによる温もり感たっぷりのストリングスのアレンジがいい。やはりジョビンの「パードン・マイ・イングリッシュ」は、エウミール・デオダートとリンドルフォ・ガヤがアレンジを手がけた異色作『ラヴ・ストリングス・アンド・ジョビン』(1966年)に収録されているオリジナルより編成はかなりシンプルになっている。その反面、サンバ度はかなり増した。松岡さんの采配は見事だ。その点、アルト奏者のリッチー・コールの「アイランド・ブリーズ」が、ストレートなレゲエにアレンジされているのも、実に気が利いている。
ウィリアム・ソルター、ラルフ・マクドナルド、ビル・ウィザースといった名トリオによる「イン・ザ・ネーム・オブ・ラヴ」は、グローヴァー・ワシントン・ジュニア、ロバータ・フラック、それにセルフ・カヴァーと、よくレコーディングされるが、阿川さんのヴァージョンもそれらと同様にスウィートな陰影を湛えている。ただ、ブラスはいささか鳴り過ぎかも──。逆にブラスが効いているのは、ルパート・ホームズの「ディス・サイド・オブ・フォーエヴァー」で、モジュレーションとバウンシーなリズムが効果的に使われたスタイルを、より熱く盛り上げている。EVEによるソウルフルなコーラスもよく合っている。さらにジルベルト・ジルの「ヒア・アンド・ナウ」では、阿川さんのヴォーカルがいつも以上に伸びやかに聴こえる。地味ながらいい選曲だと、ぼくは思う。このチルアウトなナンバーは、ジルのアメリカ録音『ナイチンゲール』(1979年)からの1曲。
というわけで、最初のほうで阿川さんに対してずいぶん失礼なことも云ってしまったが、こころよりお詫び申し上げる。しかしながら、今回あらためて『サングロウ』を聴き直してみて思ったのだが、このときの阿川さんはシンガーとしてはまだまだ発展途上にあった。その後の彼女のアーティストとしての成熟ぶりからすれば、ほんの序のクチなのである。ただハッキリ云えるのは、ぼくにとって阿川さんは、ジャズも歌うけれど、やはりジャズ・シンガーではないということ。のちにセルジオ・メンデスやイヴァン・リンスとともにアルバムを制作したことからも、そう云いたくなる。そんな阿川さんの方向性がはじめて打ち出されたのが、この『サングロウ』だったように思われる。その点でも、本作は重要な1枚だ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








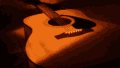
コメント