モダンにスウィング!──そしてよく歌うジャズ・ピアノのお手本

Album : Wynton Kelly / Kelly At Midnite (1960)
Today’s Tune : On Stage
スウィングしなけりゃ意味がない
「スウィングしなけりゃ意味がない」という曲がある。云わずと知れた、デューク・エリントンの超有名ナンバー。この曲が書かれたのは、1932年とのことだから、スウィング時代到来以前に「スウィング」ということばが使われていたことになる。この曲の歌詞を書いたアーヴィング・ミルズは「エリントンこそスウィングの祖」と云ったらしいけれど、そんなエピソードも踏まえると、ジャズを聴かないひとたちにも「スウィング」ということばが耳馴染んだのは、エリントン大先生のおかげと思えてくる。
ところで、この「スウィング」──確かにジャズの場合、上記の曲の歌詞にあるように、これがないとカッコがつかない。では具体的になにをやるのと訊かれると、案外答えに窮する。まあ音楽理論を以ってして説明することは可能なのだけれど、ここでそれを大いに論じることこそ意味がないので、簡単に云うと──たとえば、連続する八分音符を演奏するとき(楽譜どおりには弾かず)、はじめの音符を長めに、次のを短めに……と、繰り返していく──ということになる。
そうやって演奏すると、フレーズ延いては曲のリズムが弾むようになるよね。そんなふうにバウンスすることによって生まれるグルーヴ感が、音楽全体を心地いいものにするのだけれど、それをもっと平たく云うと、曲のノリがよくなる──ということになる。結果的に、スウィングすることが、聴き手の気分を高揚させて、ときには踊り出したくなるようにさえするわけ。これは、大事なこと。いくら指が素早く動いていても、それこそスウィングしていなければ意味がないのだ。
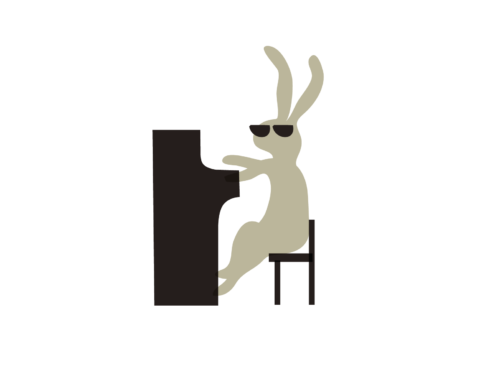
ただし、スウィングすることがすべてではない。イーヴンで演奏したほうが効果的な場合もあるし、あまりレイドバックしすぎると「♪ヨイヨイヨイヨイ」みたいになってしまう(そもそもこれは盆踊りでスウィングではない)。なにごとも程々がいい──実はこれは、音楽においてすごく大切なこと。その昔、大した演奏技術もないぼくは、よくライヴ演奏でついやり過ぎてしまうことがあった──そんなとき、あとになって、抑制することの重要さに気づいたもの。
ということで──スウィングしなれば意味がないけれど、スウィングし過ぎるともっと意味がない。じゃあ、どうやって程よいスウィング感覚を身につければいいの?ぼくの経験で云わせてもらうと、これは身体で覚えるしかない。とはいっても、特別な肉体的トレーニングをするわけではない。やはり、まずは聴くことからはじめる(教則本だけでは無理)──たとえば、ウィントン・ケリーのピアノ・プレイを耳コピーしたり……。
「スウィング」を知り、演奏に活かすためのお手本
ウィントン・ケリーは、もっともスウィングするジャズ・ピアニストのひとり──これは、ジャズを聴くひと、演るひとの間で、広く受容されていること。特筆すべきは、その卓越したリズム感のよさ──スウィングするとひとくちに云っても、彼の演奏をよく聴いてみると、八分音符の連なりがストレートノートに近い感じで、そのレイドバック加減が絶妙なのだ。これは、もはや天性と云うしかない。
そんなウィントンのピアノ・プレイは、その妙々たるスウィング感と、これまたクリーンなタッチも相まって、リスナーに鷹揚な印象を与える。さらに、込み上げてくるようなフレーズが、よく歌っている。ときにそれには、賑々しく乗りまくるような場面もあるのだけれど、それでもちゃんと品格が備わっている。そのあたりは、彼がサイドメンのひとりとしても絶品のプレイをしてきたことと、関係があるのかも……。どんなときでも、決してやり過ぎない──それでいて、その陽気なムードがとても気持ちがいい。
実はぼくの場合、小学生高学年のころ、ずっと年上の従兄からはじめてジャズのレコードを聴かせてもらったのだけれど、そのときに覚えたピアニストといえば、バド・パウエル、マッコイ・タイナー、それにビル・エヴァンスだった。そのせいか、はじめはスウィングすることにはまったく意識が向かず、別のところに衝撃を受けていたわけ。ウィントンやソニー・クラーク、それにトミー・フラナガンなどを聴くようになるのは、もうちょっと後のこと。
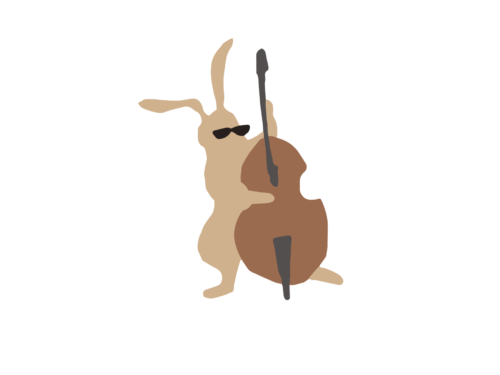
そんなわけでジャズのなかに「スウィング」を見定めるのにも、ジャズ・ピアノのテクニックのひとつを自分のなかに取り入れるのにも、ウィントンの演奏はまさにお手本とも云うべきもの。そんな彼のリーダー・アルバムといえば、作品数こそ少ないけれど、どれも水準を上回るものばかり──だからかもしれないけれど、彼の最高傑作というと、ひとによって意見が分かれるようだ。ぼくは『ケリー・アット・ミッドナイト』が、いちばん好きだ。
よく管楽器の入った『ケリー・ブルー』(1953年)が、ジャズの名盤として採り上げられている場面に遭遇するけれど、ぼくは、すすんで自分を目立たせようとはしないウィントンだからこそ、彼のプレイがよりたくさん聴ける、トリオで吹き込まれた『ケリー・アット・ミッドナイト』を推す。どうでもいいことかもしれないが、本作のオリジナルのタイトルにはスラングの“midnite”が使われているのに、再発売のもののなかには“midnight”に変更されているものがある。なぜだろう?
ちょっと焚きつけてもらいたかったのかも……
それはさておき、ウィントンが1959年から1963年まで、あのマイルス・デイヴィスのクインテットに在籍したことは、あまりにも有名。その後彼は、そのときの朋輩であるポール・チェンバース(b)とジミー・コブ(ds)を、自分のトリオのレギュラー・メンバーとした。ある意味でこのトリオは、前述のようなウィントンの資質が最上のかたちで引き出されたリズム・セクションと云える。しかしながら、本作ではドラムスをフィリー・ジョー・ジョーンズが受けもっている。
フィリーは、ジミーと比べると、かなり手数の多いドラミングをするひと。その革新的なアイディアの数々から、ハード・バップ期の代表的なドラマーと云ってもいいだろう(そういえば彼もいっときマイルスのバンドに居たね)。ただ、そのドラマティックなパフォーマンスゆえに、いささか出しゃばり過ぎと観るひともいるようで、本作でのプレイについてもハイテンションでオーヴァーと批判されることがある。そんな理由からレギュラー・トリオによって吹き込まれた『枯葉』(1961年)のほうを名盤とする向きも多い。
ぼくも『枯葉』は大好きだけれど、聴いていて楽しくなるのは、やっぱり『ケリー・アット・ミッドナイト』のほうなんだよね。個人的なことで恐縮なのだが、ぼくがバンド活動をしていたとき、ドラマーのKくんがフィリーを想起させるようなプレイをしたことがある。彼はあの猪俣猛先生に師事してその後プロになっただけあって、バンドのなかでも飛び抜けて上手かった。あるとき、ヴォーカルものなのにもかかわらず、エンディングのビスのところで、彼がみんなを煽ったため、演奏が延々つづいた──ということがあった。

そんなときぼくは、自分でも信じられないくらいノリノリになってしまったのだが、それ以降、仕掛けられることによろこびを覚えるようになった。ウィントンがわざわざフィリーを連れてきたのも、ちょうどそんな感じで、ちょっと焚きつけてもらいたかったのかも……。なぜなら、本作のオープナー、ウィントンの陽気な雰囲気のオリジナル曲「テンペランス」での彼のプレイが、とてもスウィンギーでハッピーな感じだから──8バース→4バースの箇所なんか、ホント楽しげだ。
つづくシンガーのバブス・ゴンザレスのバラード「ウィアード・ララバイ」では、打って変わって翳りのある哀愁漂う演奏に惹きつけられる(いい曲だな)。そしてレコードではB面に突入するが、最初の曲、ギタリストのルディ・スティーヴンソンの提供した「オン・ステージ」が、最高!これは踊れる!フィリーの変幻自在のドラミングとポールのアルコ・ベースが軽快だし、ウィントンのピアノも次々にご機嫌なフレーズを繰り出してくる(お手本になるな)。
さらに──「スケーティン」はまたもやルディの曲で、ファンキーでありながら軽めな感じで、とてもカジュアル。ラストの「ポット・ラック」はウィントンのオリジナルで、まったく虚飾のない構成だけれど、三人のコンビネーションがバッチリで、スタイリッシュに盛り上がる──。ぼくは、思わず「ウィントンさん、あなたはいつも帽子なんかかぶっていてとてもお洒落だけれど、音楽のほうもそのファッションセンスそのままですね!」なんて云って、拍手を送りたくなる。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント