レコーディングにカジュアルな雰囲気が漂うケニー・ドリューの『ダーク・ビューティ』
 Album : Kenny Drew Trio / Dark Beauty (1974)
Album : Kenny Drew Trio / Dark Beauty (1974)
Today’s Tune : Run Away
ぼくがケニー・ドリューのアルバムを聴かなくなったわけ
自室のレコード棚を見るともなしに見ていたら、思いのほかケニー・ドリュー(1928年8月28日 – 1993年8月4日)のレコードが何枚もあったので、ちょっと決まりがわるい思いがした。というのも、昔は彼のアルバムをよく聴いていたのだけれど、あるときからそれらをターンテーブルにのせる機会がめっきり減ってしまったからだ。ドリューはどちらかといえば、日本でも知名度の高いジャズ・ピアニストだと思うが、実はぼくにとっては簡単に評価することができないひと。理由はぼくのなかで、ドリューのパーソナリティがいまひとつハッキリしないということ。それを必死でわかろうとしたからか、ぼくは過去に彼のレコードやCDをけっこう購入している。そして正直に告白すると、あまり聴いていないアルバムもそれなりにある。実に気恥ずかしい。
べつに責任転嫁をするつもりはないのだが、ぼくがそんな思いをするのも、原因の一端はドリュー自身にもあるのではないだろうか。デビュー作であるブルーノート盤『ニュー・フェイセス – ニュー・サウンズ/イントロデューシング・ケニー・ドリュー・トリオ』(1953年)から、日本のアルファ・ジャズによってリリースされた『ザ・ラスト・レコーディング – ライヴ・アット・ザ・ブルーノート・オーサカ』(1993年)までのおよそ40年間、ドリューのピアノ演奏は明らかに変化している。彼は最後の実況録音の際、まだ64歳だった。云うまでもなく、演奏能力の衰えを感じさせたりするような年齢ではない。それでも1980年代から1990年代までのドリューと、1950年代の彼とではまるで別人のようだ。
ドリューにはトリオ作品が多いが、たとえば『パリ北駅着、印象』(1988年)『欧州紀行』(1989年)『旅の終わりに』(1990年)といった、日本が制作したアルバムがある。どれもニールス=ヘニング・エルステッド・ペデルセン(b)、アルヴィン・クイーン(ds)が、サイドを務めている。3枚あわせてヨーロッパ3部作ということらしいが、これは飽くまで制作サイドによる煽り文句として考えられた呼称。商業的な思惑に乗せられて、無理してすべて揃える必要はない。しかも3部作と云っているわりには『欧州紀行』だけ、ジャケットのイラストがまったく違った印象を与えていて、統一感がない。ちょっとお粗末過ぎる。それでもこの3部作は、けっこう売れたらしい。さらにはこれらを、ドリューの1980年代の代表作に挙げる評論家もいた。
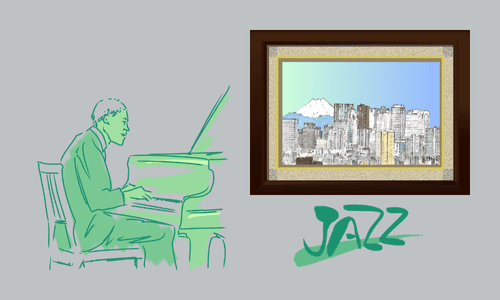
ところでぼくがドリューから離れるきっかけとなったのは、実は1980年代の作品群。特に企画性ばかりが前面に押し出されたいくつかの日本の作品を、ぼくの感性はまったく受けつけなかった。この3部作もまた然り。そもそも『パリ北駅着、印象』のアルバム・タイトル(邦題)やアートワーク(イラスト)をはじめて観たとき、ぼくは実際に音に触れるまえからその内容に危惧の念を抱いていた。昔からジャズのレコードについて、よく看板に偽りなしと云われてきた。さてここで、あらためて『パリ北駅着、印象』を観てみよう。あなたはこの駅に佇むフェドラハットにトレンチコートという出で立ちの女性のイラストを観て、なにを感じるのだろう。ぼくにはそこから、ドリューによるジャズの香り高いプレイを想像することができなかった。
大平美智子というイラストレーターによる『パリ北駅着、印象』のジャケット自体を、ぼくもわるいとは思わない。ただ従来のドリューのブルース感覚に溢れた軽妙なピアノ・プレイに、この水彩画は似つかわしくないのではないだろうか?このアルバムをはじめて手にしたとき、ぼくのなかではそんな疑問が湧くとともに、やにわに不安が募りはじめたのである。繰り返しになるけれど、ジャズ作品では外観が中身を映す鏡となることがままあるからだ。そして実際に音を聴いてみると、やはり外見と実質とはまんまと一致していた。そこには、ぼくが敬愛するソニー・クラークにも通じるドリューのブルース・フィーリングは、あっけなく雲散霧消していた。そしてこのとき前述のように、ぼくは彼のパーソナリティがよくわからなくなってしまったのである。
そうはいっても、これは好みの問題でもある。もしあなたが『パリ北駅着、印象』のジャケットに好感をもったならば、きっとここでドリューが奏でている音楽に惹かれるであろう。アートワークがため息の出るような美しさを湛えていれば、中身の音楽のほうにも美麗でまろやかな味わいがある。明快なメロディック・ラインと端正なアドリブ・ソロ、ソフトなタッチとリリシズムに溢れたエクスプレッションに、得も云われぬ心地よさを覚える向きもあるだろう。本作はその点で、ふだんジャズを聴かないリスナーにも、ジャズが思いのほか聴きやすくてお洒落な音楽と、大いにアピールしたかもしれない。実際1980年代のドリューは、女性ファンから圧倒的な支持を得るようになったとか──。それはそれで意味のあることと、ぼくも思う。
そんなジャズ作品に売れる仕掛けを施したのは、音楽プロデューサーの木全信。木全さんは『ジャズは気楽な旋律』(2014年平凡社刊)という著書も出版しているが、そのなかにも書かれているとおり、彼が目指したのはジャズの大衆化。あのヨーロピアン・ジャズ・トリオを発掘してきて、とっつきやすいジャズを提案したのも木全さんだ。かつて彼はレコード会社において、実績トップを誇る歌謡曲の宣伝マンだっただけに、新奇なマーケティング手法に長けていた。ドリューの作品を女性を中心に大ヒットさせるなどとは、思いも寄らないこと。その奇抜なアイディアには、ただただ感服させられるばかりだ。木全さんはアルファ・ジャズ以前のレーベル、ベイステイト時代にも、ドリュー作品のジャケットに川村みづえによる鮮明な水彩画を使っていた。
デビュー作におけるフレッシュなドリューは一段と魅力的
それはともかく、たとえばイージーリスニング路線とでも云いたくなるような、ムードいっぱいのBGMとして重宝しそうな1980年代のドリューのアルバムではあるが、彼自身のピアノの腕まえが落ちてしまったのかというと決してそうではないと、ぼくは思う。おそらくドリューは日本の制作サイドの要望に応え、熱心なジャズ・ファン以外のリスナーにも即座に好印象を与えるような演奏を、敢えてしていたのだろう。聴くものすべてにリラクゼーションをもたらすようなテクニックを駆使するというのも、生半可な技量でできることではない。ベイステイトやアルファ・ジャズの作品では、木全さんのサジェスチョンに従ったまで。ドリューはプロのピアニストとして、ビジネスライクにレコーディングに臨んだのだと、ぼくは思う。
そうはいっても、当時20代だったぼくは、まだ頑迷固陋だった。そんなドリューを、悪魔に魂を売ったひとと見なし、彼のことを蛇蝎のごとく嫌厭するようになってしまった。おまけになんとも浅はかなことに、1950年代の彼の作品まであまり聴かなくなってしまったのである。ぼくは最初にドリューのパーソナリティがいまひとつハッキリしないと云ったけれど、正直なところ確固たる自己のスタイルを堅持しなかった彼の真意はいまだにわからないままだ。いいほうに解釈すれば、ドリューは淡々と仕事をこなすひと、あるいは日本からの無理な注文に応えるサービス精神が旺盛なひととなる。意地悪な捉えかたをすれば、自己の存在証明は二の次で報酬を得るためならなんでも演るひとと云わざるを得ない。
ぼくも年をとって、かなり寛大な人間になったと思うのだけれど、いまもやはり1980年代のドリューの作品を好きになれない。当時もライヴの際には、彼がもちまえのブルース感覚を発揮するシーンがあっただけに、体裁ばかりをとり繕うようなアルバムがつづいたことは、いまになってみると残念でならない。ライヴ・パフォーマンスを体験すればハッキリわかることだが、あのころも間違いなくドリューのピアノの腕は衰えていなかったし、ブルージーな表現も然ほど変わっていなかったのだから──。さらにお断りしておくが、ドリューの演奏に見られる上品で美しいリリシズムは、1980年代の作品から産声を上げたというわけではない。バリバリのハード・バップをプレイしていたときから、それは淡い光を放っていたのである。

ということで飽くまで個人的にではあるが、この機にドリューのアルバムをちゃんと聴き直してみようと思った次第。ドリューはアメリカ、ニューヨーク市の生まれ。もちろん、デンマークのひとではない。彼は1993年にこの世を去ったとき、コペンハーゲンの地に埋葬されたのだけれど、1964年に活動の拠点を同地に移していた。以来、シェラン島ロスキレ近郊、オステッド出身のベーシスト、ニールス=ヘニング・エルステッド・ペデルセンは、生涯の僚友となった。実はそれ以前にドリューは、ニューヨークを離れている。彼は人種差別が横行する街にうんざりし、1961年にフランス、パリ市に移住していたのだ。それはさておき、ドリューは5歳からピアノのレッスンを受け、マンハッタンの音楽芸術高校(現在のラガーディア高校)で、ピアノと音楽理論を学んだ。
ドリューのレコーディング初体験は、21歳のとき。1950年1月、ニューヨークでのこと。ブルーノート・レコードの10インチ盤『ハワード・マギーズ・オール・スターズ』(1952年)で、彼はピアノを弾くばかりでなく4曲も自作を提供している。このトランペット奏者、ハワード・マギーのアルバムは1990年代に日本でも発売されたから、ご存じのかたも多いと思う。ときはビバップ期にありながらアンサンブルに意匠が凝らされたアレンジは、フレッシュなセンスを感じさせる。また、初々しさのなかにもバド・パウエルを彷彿させる巧妙なアドリブ・プレイは、なかなか聴きごたえがある。その後2年の間にドリューは、バディ・デフランコ(cl)をはじめ、コールマン・ホーキンス(ts)、レスター・ヤング(ts)、チャーリー・パーカー(as)などのバンドに参加した。
1953年にドリューは、カーリー・ラッセル(b)、アート・ブレイキー(ds)とともに、バディ・デフランコ・クァルテットの西海岸へのツアーに参加。その際、彼はそのままカリフォルニア州サンフランシスコ市に滞在し、短期間ではあるが自己のトリオでも活動し、ソニー・クリス(as)、デクスター・ゴードン(ts)、クリフォード・ブラウン(tp)、ジェーン・フィールディング(vo)などのレコーディングをサポートした。この西海岸時代のちょっとまえに、ドリューはおなじトリオでリーダー作を吹き込んでいる。1953年4月16日、ニュージャージー州ハッケンサック市でのことだ。そしてそのアルバムこそ、さきに挙げた彼のデビュー作『ニュー・フェイセス – ニュー・サウンズ/イントロデューシング・ケニー・ドリュー・トリオ』なのである。
ぼくはこのレコードを今回、久々に聴き直してみた。私事で恐縮だが、ジャズ・ピアノを独学していた高校生の自分が懐古された。ぼくがもっとも影響を受けたジャズ・ピアニストはビル・エヴァンスだけれど、当時ジャズ・ピアノの基本的な弾きかたを知るという点でよく聴いていたピアニストといえば、ソニー・クラークを筆頭に、ウィントン・ケリー、トミー・フラナガン、レッド・ガーランドなどが挙げられる。そしてちょうどそのころ、ぼくはこのドリューのデビュー作に出会ったのである。特にジェローム・カーンの「イエスタデイズ」における、美しいルバート演奏とインテンポ後の高速で鍵盤上を疾走する指の動きに魅了された。大好きなクラークよりはサッパリしていて緊張感もやや弱めに感じられたが、ダイナミックな展開に感銘を受けた。
いまにして思えば、やはりアップテンポでプレイされたシグマンド・ロンバーグの「恋人よ我に帰れ」などは、ピアノ・トリオの演奏としては名演中の名演だった。まだまだ天衣無縫ではあるけれど、それ故に生気溌剌たるバッパー然としたドリューのプレイには、胸がすくようなものがある。その輝きはいまも色褪せない。クラークがそうであったように、アメリカでは過小評価に甘んずることとなったドリューだが、ぼくはここでの彼の演奏に、スウィングすることへのひたむきな姿勢をひしと感じた。いまさらではあるが、趣きが奥深くはかりしれず、どこか高尚で優美さを放つ1970年代のドリューもいいけれど、それよりもこのデビュー作におけるフレッシュな彼のほうが一段と魅力的と思われてくるのである。
コペンハーゲンの地ではじめて自由を手に入れたドリュー
デフランコのクァルテットを離脱したあとも、ドリューはロサンゼルスに拠点を置き自己のトリオで活動したが、当時の演奏はノーグラン・レコードからリリースされた『ケニー・ドリュー・アンド・ヒズ・プログレッシヴ・ピアノ』(1956年)で聴くことができる。ノーグランはジャズ界の巨匠である音楽プロデューサー、ノーマン・グランツが1954年に立ち上げたレーベル。その点では、名門ヴァーヴ・レコードの前身とも云える。このドリューのLPはもともと、ノーグラン設立の年に発売された『ザ・モダニティ・オブ・ケニー・ドリュー』と『ジ・アイディエーション・オブ・ケニー・ドリュー』といった2枚の10インチ盤が、カップリングされたものだ。ここにもまた、まだ世間ずれしていないドリューがいる。
このアルバムからも前述のブルーノート盤と同様に、ドリューのみずみずしい感性が伝わってくる。確かにここで観られる演奏のスキルは、彼がひとかどのジャズ・ピアニストとして認められるまでには至っていない。しかしながら本作をあらためて聴き直したいま、ぼくにはドリューのここでのヴィヴィッドなプレイに得も云われぬ爽やかさが感じられた。ユージーン・ライト(b)、 チャールズ “スペックス” ライト(ds)、ローレンス・マラブル(ds)といった、どちらかといえば西海岸寄りのサイドメンを従えた吹き込み故か、デビュー作よりもぐっとリラックスした雰囲気とライトな響きをもった演奏となっている。そしてそのブルースに根ざしたピアノ・スタイルのなかにも、後年全開されたリリシズムの原点がすでに垣間見られるのである。
ニューヨークに戻ってからのドリューは、ジョニー・グリフィン(ts)、バディ・リッチ(ds)、ダイナ・ワシントン(vo)など、様々なスター・プレイヤーと共演を果たしている。あのジョン・コルトレーンの名作『ブルー ・トレイン』(1977年)でピアノを弾いているのも彼だ。このコルトレーンとのセッションのちょうど1年まえにドリューは、おなじサイドメンを従えてリヴァーサイド・レコードでリーダー作を吹き込んでいる。サイドメンとは、ポール・チェンバース(b)とフィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)のふたり。云うまでもなくマイルス・デイヴィスの、いわゆるファースト・グレート・クインテットのメンバーだ。この『ケニー・ドリュー・トリオ』(1956年)は、ジャズ・シーンにドリューの名を轟かせた名盤。本作には、1950年代のピアノ・トリオの本質がある。
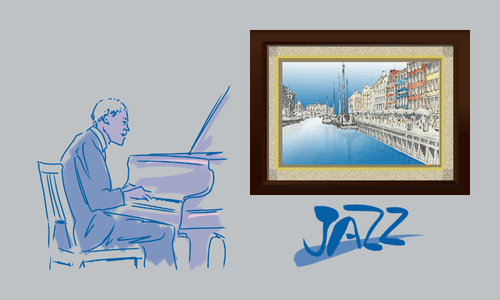
ここでのドリューは、自己のピアノ・プレイの神髄を究めたと云ってもいい。冒頭のデューク・エリントンのアフロ・キューバン「キャラヴァン」ひとつとっても、彼のプレイがこれまでになく熱気に溢れ気魄に満ちたものであるのがわかる。かたやリー・ハーラインの「星に願いを」では、彼のリリカルなエクスプレッションが満開となっている。まあこのサイドメンにあと押しされたら、そうならざるを得ないか。いずれにしても、ぼくのドリューへの関心は、ここからはじまった。つづくベーシストがウィルバー・ウェアに交替した『パル・ジョーイ』(1958年)もいい。リチャード・ロジャース(作曲)とロレンツ・ハート(作詞)とによる、1941年初演のブロードウェイ・ミュージカルのジャズ・ヴァージョン。ここには、よりエレガントでブリリアントなドリューがいる。
それとおなじ1957年に、ドリューはウェアとともに3枚のデュオ作を吹き込んでいる。リヴァーサイド盤の『アイ・ラヴ・ジェローム・カーン』と、リヴァーサイドの某系レーベル、ジャドソンからリリースされた『ア・ハリー・ウォーレン・ショウケース』と『ア・ハロルド・アーレン・ショウケース』である。企画モノという点では前述のアルファ・ジャズ3部作とおなじ方向性をもつが、こちらはより高級なイージーリスニング。健全なお色気ジャケットにも統一感がある。それとは対照的に彼は、ブルーノートに『アンダーカレント』(1961年)という、2管をフロントに据えたバリバリのハード・バップ作品も残している。全曲ドリューのオリジナルだが、どの曲も絶品。作曲に流麗さが際立てば、ブルージーなピアノのタッチにも粒だちのよさが感じられる。
これらの作品からもわかるように、やはりドリューはなんでも演るひと。制作サイドのオファーに見事に応え、その度ごとに自己のプレイを変貌させていくところから、彼がいかに器用なピアニストであるかがよくわかる。それは、1980年代以降のお洒落を気取ったBGM作品においてもまた然り。もはやそういうところを、彼のパーソナリティのひとつと捉えるしかないのかもしれない。そんなドリューにもビジネスライクな感じが薄く、むしろレコーディングにカジュアルな雰囲気が漂う作品がある。彼がコペンハーゲンに移住してからのトリオ作品『ダーク・ビューティ』(1974年)などはまさにそれ。サイドメンは僚友ペデルセン(b)とアルバート “トゥーティー” ヒース(ds)といった、スティープルチェイス・レコードではおなじみのふたり。
A面の冒頭を飾るペア・カーステン・ペーターセンの「ラン・アウェイ」や、B面トップのジミー・ヴァン・ヒューゼンの「イット・クッド・ハップン・トゥ・ユー」では、ヒースの自由闊達なドラミングに誘われて、ドリューのピアノが飛翔しまくる。マイルス・デイヴィスの「オール・ブルース」では、激烈なポリリズムのなかで、3人は情熱的になり一体感をより高めている。ドリューのオリジナル「ブルース・イン」では、彼のピアノの執拗なまでのスウィング感と、終始横溢するブルース・フィーリングが素晴らしい。ソロ交換もいい具合だ。おなじドリューの自作でも「ダーク・ビューティ」では、三位一体のアブストラクトなプレイが幽玄な世界を描き出している。ペデルセンのアルコ・ベースも印象的だ。
ハリー・ウォーレンの「サマー・ナイト」では、ドリューによる流れるような運指が美しい寂寥感を紡ぎ出している。彼ならではのリリシズムに溢れたバラード演奏だ。ヴィクター・ヤングの「ラヴ・レターズ」では、しなやかなペデルセンのベースによるテーマとソロも然ることながら、ドリューによる華麗なバップ・イディオムが眩し過ぎる。トーマス・クラウセンの「シルク・ボッサ」では、洗練されたボサノヴァのリズムに乗って、ドリューが哀愁を帯びたフレーズを展開。さきの「ラン・アウェイ」と同様にデンマーク産のジャズ・ナンバーだが、北欧ジャズの世界にもすっと溶け込んでしまうところが、いかにも彼らしい。どうやらドリューはコペンハーゲンの地で、自己の音楽人生においてはじめて自由を手に入れたようだ。彼のアルバムにしてはめずらしく、そんな音に聴こえる。ぼくのドリューの聴き直しは、さらにつづく──。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント