名曲『ミスティ』の作曲者にして、唯一無二のピアノ・スタイルを確立したエロール・ガーナーの代表作『コンサート・バイ・ザ・シー』
 Album : Erroll Garner / Concert By The Sea (1956)
Album : Erroll Garner / Concert By The Sea (1956)
Today’s Tune : Mambo Carmel
名曲「ミスティ」に関するいくつかの思い出を雑記すると──
数あるジャズ・スタンダーズのなかでも「ミスティ」ほどあまねく知られた曲は、ほかにないのではなかろうか。ぼくはジャズを聴くようになるまえから、この曲に親しんでいた。この美しいバラードが、ジャズ・ミュージシャンによって書かれた曲であるということは、つゆほども知らずにである。というのも、ぼくとこの曲との出会いは、それとはなしに手にとったポピュラー・ピアノ曲集(楽譜)だったからだ。ぼくは小学生高学年のころから、それまで個人レッスンを受けていたクラシック・ピアノと並行して、ポピュラー・ピアノも弾くようになった。師事したピアノの先生は鷹揚なひとで、ぼくにゆったりとした、こせこせしない音楽教育を与えてくれた。その影響で、ぼくは「ミスティ」を弾く機会に恵まれたのである。
ぼくは当時から「ミスティ」が大好きな曲だったのだけれど、実際にその曲を音盤で聴いたのはちょっとあとのことだった。はじめて聴いたのは、中学校に入学したばかりのころ。サラ・ヴォーンの『ヴォーン・アンド・ヴァイオリン』(1958年)というアルバムで、歌詞がついているということもこのときに知った。ずっと年上の従兄弟の所持するレコードを聴かせてもらったのだが、思えばぼくがジャズに興味をもちはじめたのも、ちょうどこのころだった。ヴォーンの驚異的な声量と温もり感いっぱいの歌声も然ることながら、情趣溢れるストリングスの響きにこころ惹かれたもの。アレンジはクインシー・ジョーンズによるものだが、思い起こせばぼくが彼に注目するきっかけとなったのは、このときのオーケストレーションだった。
ぼくには、この「ミスティ」にもうひとつ奇異な思い出がある。さきに述べたように、ぼくは小学生のときにこの曲に出会ったのだけれど、それはちょうどこの曲を練習していたおりに偶然起こった出来事。たまたま家族とテレビの映画番組を観ていたら、そのとき放映されていた映画のなかで「ミスティ」がかかったのだ。それは、クリント・イーストウッドの監督デビュー作『恐怖のメロディ』(1971年)という映画。イーストウッドは主演も務めており、ラジオの売れっ子DJを演じていた。どんな映画かというと、DJがストーカーの女に異常なまでに執着されるという、よくあるサイコスリラー。DJの人気番組に、決まった時間になると必ずおなじ女からリクエストが入るのだけれど、その曲がまさに「ミスティ」だった(映画の原題もまさに『Play Misty for Me』だった)。
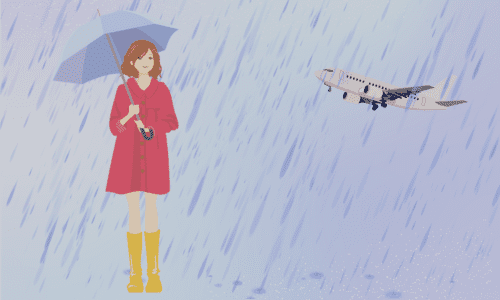
おかげで「ミスティ」を聴くと、ジェシカ・ウォルター演じるストーカー女のナイフを手にして襲いかかってくる姿が、不意にまぶたに浮かぶことがある。まあそれだけ映画では「ミスティ」が効果的に使われていたというわけだ。この映画、ほかにもロバータ・フラックの「愛は面影の中に」(1969年)をはじめ、ちょっと気になる曲がかかったり、サスペンス映画としてもなかなかの佳作なので、未見のかたは一度お試しいただきたい。これは余談だが、ぼくの「ミスティ」にまつわるフラッシュバックについて、ある女性に冗談めかしてはなしたところ、そのひとに「わたしは“冬ソナ”を思い出すな」と返された。あれは「ミスティ」ではないからね!あれはキム・ヒョンソクというひとが書いた(パクった)「夢を越えて」という曲だから。念のため──。
ところで、名曲「ミスティ」の歌詞には、たとえば「I’m too misty and too much in love」というように、実に独特のいいまわしが使われている。恋をするとこころの状態が五里霧中になってしまうということなのだろうか?いずれにしても、拙訳で申しわけないが「わたしは霧のなかにいるように夢うつつ、あまりにも恋したせいで」というようなユニークでロマンティックな歌詞ゆえに、多くのシンガーに採り上げられている。エラ・フィッツジェラルド、クリス・コナー、キャロル・スローンなどの歌唱は有名。前述のサラ・ヴォーンは、何回か吹き込んでいる。作詞をしたのはジョニー・バーク(1908年10月3日 – 1964年2月25日)で、彼は「ヒアズ・ザット・レイニー・デイ」「ライク・サムワン・イン・ラヴ」「ホワッツ・ニュー」と、偶然にもぼくの好きな曲を手がけている。
では作曲したのは誰かといえば、ジャズ・ピアニストのエロール・ガーナー(1921年6月15日 – 1977年1月2日)だ。「ミスティ」の初演は、エマーシー・レコードからリリースされた『コントラスト』(1954年)に収録されている。ワイアット・ルーサー(b)とユージン “ファッツ” ハード(ds)をサイドに据えたピアノ・トリオで演奏された。もともとは、インストゥルメンタルだったのである。なお映画『恐怖のメロディ』で使用されたのも、このヴァージョンである。面白いのは、彼が「ミスティ」のメロディを思いついたのは、飛行機に乗っているときだったというエピソード。サンフランシスコからシカゴへのフライトで、機体が乱気流に突入してしまったとき、窓外に見える霧に包まれた景色からインスピレーションを受けたという。
『エロール・ガーナー・プレイズ・ミスティ 』の音源は寄せ集め
う〜ん、それで「ミスティ」というタイトルになったのか。もともとは恋に落ちたときの女性の心情とは、まったく関係なかったのね。でもちょっと想像してみていただきたい。揺れる航空機の客室でガーナーがひとり、雨露で濡れたガラス窓越しに外を眺めながら旋律を模索している姿を。もしそこでバックに「ミスティ」のトリオ演奏がフェードインしてきたら、それはまるで映画のワンシーンのように、しみじみとした味わい深さと美しさが感じられるのではないだろうか。それくらい「ミスティ」は、美しい旋律と洒落た雰囲気をもった曲なのだ。ガーナーは思いついたメロディを記憶し、シカゴのホテルに到着するやいなやテープを借りて自らのピアノ演奏を録音したという。実は彼、記譜ができなかったのである。
ガーナーは生涯、楽譜を書くことはもちろん読むこともできなかった。ペンシルベニア州ピッツバーグに生まれた彼は、音楽好きの家族に囲まれて育った。兄のリントン・ガーナーもまたジャズ・ピアニストだし、両親もともにピアノを弾いた。ただ父親のピアノ奏法が自己流だったせいか、ガーナーもまたひたすらジャズやクラシックのレコードを聴いて、まったくの独学でピアノの弾きかたを習得した。母親は然るべきピアノ教師を招いたが、ガーナーは正統な音楽教育にまるで関心をもたなかったという。結局彼は、楽譜を読むことを学ばなかったが、そのかわりに驚異的な音感記憶をもつこととなった。さきの飛行機のエピソードのほかにも、ガーナーには、ソ連・ウクライナのピアニスト、エミール・ギレリスの演奏を一度聴いただけで、おなじように弾いたというレジェンドもある。
そんな天才的なピアニストのガーナーであるが、日本でも知名度は高かったように思う。でもそのわりには、人気のほうはいまひとつだったかもしれない。1972年に来日したときも会場には空席が目立ったというし、レコードショップに行ってみても彼のアルバムはあまり置かれていなかった。それでも「ミスティ」が収録されている『エロール・ガーナー・プレイズ・ミスティ』(1962年)は、十中八九どこの店のハコにもちんまりと収まっていた(当時は本作の世評も高かったからね)。ぼくもこのアルバムを、半分は「ミスティ」聴きたさに、半分は選択の余地がなかったので不承々々に購入した。ちょうど大学進学を目前に控えたころで、受験勉強をしながら(大して勉強していなかったけれど)、毎晩のようにこのレコードを聴いていたもの。
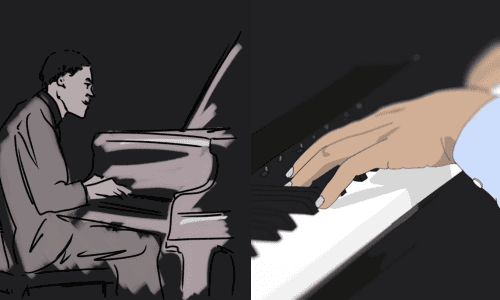
ぼくにとっては、はじめてのガーナーのアルバム。かつて『恐怖のメロディ』で聴いた「ミスティ」を、実際に音盤で聴いたときは感動した。ほかにもポピュラー・ソングやジャズ・スタンダーズを、ガーナーはリラックスした雰囲気の胸のすくような演奏で聴かせてくれる。それではやはり、このアルバムが名盤と呼ぶに相応しいものなのかというと、実のところぼくはいささか疑問を覚えるのである。なぜかというと、ここに収められた演奏が過去にレコーディングされた音源の寄せ集めだからだ。冒頭の「ミスティ」から3曲目までは前述の『コントラスト』のときの1954年7月の演奏。ところが4曲目は、1949年9月に吹き込まれたもの。いきなり音質が、古めかしくなる。最初から一聴で、違和感を覚えた。
このレコード、上記以外にも1946年4月、同年7月、1955年3月の吹き込みが使用されており、実際は計5つのセッションが編集されたコンピレーション・アルバムということになる。吹き込みの時期が違えば、録音の場所もロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴとバラバラ。トリオのサイドメンは入れ替わるし、ソロ・ピアノもある。各々の演奏は素晴らしいのだけれど、アルバムとしてはまとまりがない。おそらく「ミスティ」のヒットにあやかって再編集されたレコードなのだろう。それこそ雨露で濡れたガラス窓越しの、憂いを帯びた女性の玉顔があしらわれたジャケットは、まさに「ミスティ」がイメージされたものであることは、少しの疑問もさしはさむ余地がない。外観はお洒落なのだけれど、残念ながら内実には不満が残る。
その後に入手した『ペントハウス・セレナーデ』(1955年)も、1949年の吹き込みのなかにサイドメンを異にする1945年の演奏が混じっているけれど、まだこちらのほうが違和感なく聴くことができる。ぼくが所持するレコードは、1985年にサヴォイ・ジャズによるリイシュー盤。録音はちょっと古いが、マスタリングは名匠ルディ・ヴァン・ゲルダーによるものだ。ペントハウスでシェリーグラスを手にする女性のジャケット写真と、バラードとミディアム・スウィング中心の選曲とが相まって、おつなアルバムといった風情が感じられる。終始漂う寛いだ雰囲気、聴くものを魅惑するような甘美な旋律、なんとも瑞々しいピアノのタッチなどから、ぼくはガーナーの初期のマスターピースと捉えている。しかも、彼の独特なピアノ・スタイルも、しっかり確認できる。
ガーナーのピアニズムがもっとも自然発生的に成立した作品とは──
ガーナーのピアノ・スタイルといえば、“ビハインド・ザ・ビート”が有名だ。左手が和音で4ビートを刻む、ストライド・ピアノの変形のような独特の奏法だ。ちなみにストライドとは“またぐ”という意味。ストライド奏法は、左手がボトムのルートと上部のコードを行ったり来たりするのだが、その動きがアーチを描くように鍵盤をまたぐところから、そう呼称されるようになった。実際に弾いてみると、左手はかなり忙しい。アップテンポで弾くのは、とても難しい。ガーナーの左手は強靭だが、彼がサウスポーであることと無関係ではあるまい。ときおりアフタービートで入ってくる低音のアクセントも、実にパワフルで印象的だ。あまりにも左手のビート感が強烈過ぎるから、逆に右手のシングル・トーンは若干遅れて聴こえるのである。
この“ビハインド・ザ・ビート”というネーミングは、飽くまでガーナーのピアノ・スタイルを称賛するもの。そこには誰が聴いてもまごうかたなく、彼独自のスタイリッシュな雰囲気とスウィング感が醸し出されているのだ。やはりガーナーがピアノの演奏法を独学で身につけたこと、楽譜の読み書きを学ばなかったことが、結果的にそんな彼の唯一無二のセンスとテクニックを育むことになったと、ぼくは思う。後続のピアニストのなかには、ガーナーの奏法を真似しようとする向きも多々あった。ぼくの敬愛するデイヴ・グルーシンも、アドリブ・パートでよく演っていた。そんな状況には、大いに腑に落ちるところがある。なにせそのピアノ・サウンドには、演るほうも聴くほうもこころが弾むような心地よさがあるのだから。
そんな独自のスタイルで首尾一貫してプレイしつづけたガーナーは、堂々とマンネリズムを押し通したピアニストとも云える。普通だったら、型にはまった表現、あるいは惰性にまかせた演奏と批判を浴びそうだが、彼の場合、まったく普通ではないので許されてしまうのだ。そんなイージーゴーイングで、ハッピーで、エキサイティングで、ダイナミックなピアニズムが、もっとも自然発生的に成立した作品といえば、やはり『コンサート・バイ・ザ・シー』(1956年)だろう。曲目には珠玉のスタンダーズがズラリと並び、演奏には胸のすくような小気味よさがあるという点で、抜きん出ている。サイドのエディ・キャルフーン(b)とデンジル・ベスト(ds)は、それぞれボトムとリズムのキープに徹するばかり。主役は、飽くまでガーナー。それでいい。
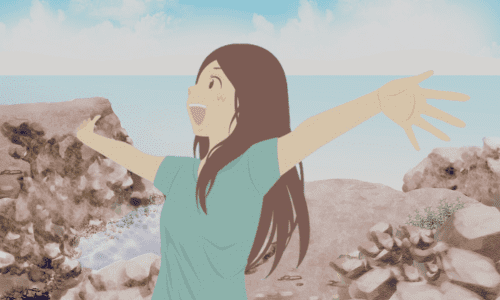
本作は1955年9月19日、カーメル市のサンセット・スクール(現在のサンセット・センター)のホールにおける実況録音。カーメルは、カリフォルニア州モントレー郡のカーメル・バイ・ザ・シーという小さな街。芸術家、詩人、作家などが集まる風光明媚の地として知られる。ジャケットの写真にあるように、断崖から見下ろした波が打ち寄せる海岸線が雄大だ。写真に写る女性のように、思わず手を大きく広げたくなる。なおクルセイダーズのピアニスト、ジョー・サンプルのアルバム『渚にて』(1979年)には「カーメル」「雨のモントレー」という素敵な曲が収録されているが、この街からの影響である。そういえばこのカーメル、クリント・イーストウッドが市長を務めたこともあったな(任期は1986年から1988年まで)。
オープナーは、おなじみの映画の挿入歌「四月の想い出」だが、奇抜なイントロにはじまり華やかなテーマ、饒舌なアドリブと、ガーナーは最初から飛ばしまくる。ジーン・デ・ポールの「ティーチ・ミー・トゥナイト」では、サイドによってくつろいだミディアムテンポがキープされるなか、ピアノだけは力強く歌いつづける。ガーナーのオリジナル・ナンバー「マンボ・カーメル」は、アルバム中もっとも軽やかでテイスティ。テーマ部のピアノの左手が打ち出すクロス・リズムといい、サビの軽快で陰影のある展開といい、ぼくにとってはベストな曲。ジョゼフ・コズマのシャンソン「枯葉」では、ガーナー流バラード・プレイを大いに堪能。絢爛豪華で精力旺盛だ。
前半のラスト、コール・ポーターのミュージカル・ナンバー「イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー」では、ひたすらダイナミックなピアノ・プレイがオーディエンスを盛り上げる。左手の和音による4ビートの刻みも、全開する。後半トップのライオネル・ハンプトンの「レッド・トップ」は、アルバム中もっとも軽妙洒脱な演奏で、思わずパーカー先生の引用も飛び出す。ときおりぶつぶつと念仏のようなものが聴こえるが、これは楽譜が読めないガーナーが音を確認しながら口ずさんでいるのだ。ヴァーノン・デュークのミュージカル曲「パリの四月」において、彼はさきの「枯葉」とはまた違ったリリカルなバラード演奏を聴かせる。つづくガーシュウィン兄弟の「誰も奪えぬこの想い」でも小粋な感じで弾いていて、好感がもてる。
さらに、タイリー・グレンの「ハウ・クッド・ユー・ドゥ・ア・シング・ライク・ザット・トゥ・ミー」にも、洗練された感じが際立つ。ガーナのピアノも悶絶テクニックは控えめで、モダンでスタイリッシュに響く。だが、ロジャース&ハートのミュージカル・ソング「いつかどこかで」では、ここぞとばかりにハッピーな雰囲気で“ビハインド・ザ・ビート”が惜しみなく繰り出される。ガーナーの自作曲「エロールのテーマ」という機知に富んだオマケもついて、アルバムは幕引きとなる。いずれにしても本作では、ガーナーのスケールの大きなピアニズムを素直に楽しむことができる。もしハード・バップのピアニストを聴き飽きたら、ぜひガーナーを聴いていただきたい。ぼくは本作を、そんなふうに聴くことがあるのだけれど、その機会は案外多かったりする。それすなわち、大好きということである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント