北欧の隠れた逸材、ヴィグレイク・ストラースの知るひとぞ知る名盤
 Album : Vigleik Storaas Trio / Bilder (1995)
Album : Vigleik Storaas Trio / Bilder (1995)
Today’s Tune : Slapp Av
北欧を強く意識させられたジャズ・アルバム
ふと、北欧ジャズを聴きはじめたのは、いつだったっけ──なんて、思った。ぼくが北欧を強く意識させられたジャズ・アルバムといえば、ジョン・サーマンのユニットによるECM盤『ノルディック・クァルテット』(1995年)や、ビリー・コブハムの自己レーベル、リズマティクス・レコード第一作『ノルディック』(1996年)だから、1990年代のなかごろということになる。思い起こせばあれは、ぼくが、自分のジャズの師匠と崇める当時の勤め先の上司の呪縛から解放されて間もないころだった。いやいや、これは云いかたがマズかったかな。師匠にはジャズについていろいろと指南していただいたから、ぼくはいまでも感謝の気持ちでいっぱいだ。
なんといっても、ぼくがジャズを系統立てて聴くようになったのは、師匠のおかげだ。それまでのぼくはといえば、好きなものばかり聴いていて、かなりの偏食家だった。それに加えて、バンドをやっていたこともあり、ちょっとジャズを研究するような聴きかたをしていたのだ。でも、師匠と出会い、仕事が終わったあと中古レコード店巡りに連れていってもらううちに、好むと好まざるとにかかわらず、俗に云うジャズの名盤にたくさん触れることができた。さらに師匠の影響で、折しもすっかりCDが主流の時代だったが、ぼくはアナログ盤のよさを再認識した。それで、けっこう散財したな──。しかしながら二年半ののち、ぼくはその勤め先を退職。同時にジャズの聴きかたに、心理的な制約をかけるものがなくなったのである。
指南役を失ったぼくは、免許皆伝となったかどうかは定かではないが、自分自身の勘を頼りにジャズ作品を手にするようになった。もちろん、師匠からしきりに聞かされた、レコードやアーティストにまつわる興味深いよもやまばなしから得た知識も、大いに役立った。そして、黄金時代のモダン・ジャズ作品も相変わらず愛聴していたけれど、未知のアーティストのアルバムにも手を出すようになった。それに、ジャズにかぎらず音楽の愛好家だったら、聴いたことのないものを聴きたくなるのが人情というものだ。そんな流れから、ぼくは北欧ジャズにも手を出しはじめたのである。まあ、それ以前からぼくは、無意識に北欧のピアニストの演奏に触れていたのだけれど──。

たとえば、レッド・ミッチェル・トリオの『ワン・ロング ・ストリング』(1969年)で、ボボ・ステンソンというピアニストを知り、中古屋さんで偶然購入した『サーダナ』(1981年)というレコードで、ラーシュ・ヤンソンのファンになった(ふたりともスウェーデンのひと)。しかしながら、彼らのときに繊細ときに大胆な演奏から、特別に北欧を意識することはなかった。北欧ジャズの斬新なスタイルに興味をもつキッカケとなったのは、やはり最初に挙げたサーマンとコブハムの二枚だろう。ご存知のようにコブハムはどちらかというと、フュージョン系のドラマー。しかも、やたら手数が多くハデハデしい。その彼が、北欧のプレイヤーたちに囲まれてグルーヴ重視の優美なドラミングを展開している。そして、ここでピアノを弾いていたのは、あのブッゲ・ヴェッセルトフトだった。
ヴェッセルトフトといえば、北欧ジャズ・シーンを牽引するノルウェーのキーボーディストでありプロデューサー。オスロのアンダーグラウンドなクラブ・シーンとの結びつきを強め、いわゆるフューチャー・ジャズと呼ばれる新しいジャズのスタイルを提案したひと。彼のアルバムでは、ときにはサンプリングやエフェクト、DJやスクラッチまで採用され、ヒップホップ、テクノ、アンビエントなどのクラブ・ミュージックに迫る、とにかくそれまでのジャズには収まりきらないサウンドが展開されている。ぼくは、ほどなくブッゲの自己のレーベルJazzlandからリリースされた『ニュー・コンセプション・オブ・ジャズ』(1997年)を入手。しばらく、このレーベルにハマることになる。
センシビリティを刺激するかのごとき心象風景を思い起こさせる
いっぽうサーマンといえば、イングランドのリード奏者だが、特にバリトン・サックスを広いレンジで演奏する独自のスタイルが有名。ノルディック・クァルテットは、その名のとおりサーマン以外はノルウェー出身のミュージシャンで構成されている。サーマンは、バリトン以外にもソプラノやバス・クラリネットなどを持ち替えて、スリリングなプレイを展開。ECMではおなじみのギタリスト、テリエ・リピダルが、歪んだトーンで独特な空気を作っている。ジャズ・シンガー、カーリン・クローグのヴォーカルとレシテーションには、ポエティックで幻想的な味わいがある。そして、ヴィグレイク・ストラースのピアノが、このアブストラクトな音楽に、地味ながらもときおり美しい響きで装飾を施している。
サーマンは、ジョン・コルトレーンの影響を受けていると云われるが、たしかに即興演奏において、調性にとらわれることなく縦横無尽に様々な音階を繰り出すようなところがある。とはいっても、コルトレーンのインフルエンスは強大であり、その音楽にインスパイアされたり奏法をコピーしたりするのは、なにも珍しいことではない。ただかりそめにも、サーマンがこのクァルテットで演っている音楽と、コルトレーンを結びつけようとするのには無理があるというもの。ここに出来した音楽には、コルトレーンがクリエイトする激烈さと静謐さが共存する瞑想的世界のようなものはない。ノルディック・クァルテットの音楽は、ミュージック・タペストリーとでもいうべきもので、そのサウンドからはたとえば風景や絵画などがイメージされるのだ。
この作品のジャケット──なんの変哲もない風景写真。船舶が停泊しているところから、どこぞの港湾だろうか(ひょっとしてオスロ・フィヨルドか)?除雪作業の跡と星ひとつ見えない漆黒の夜空が、凍えるような厳しい寒さを伝えてくる。実は、このカヴァ・デザインが音楽のイメージにピッタリだったりする。というのも、ノルディック・クァルテットの演奏からは、こういう風景あるいは様々な情景をナチュラルに想い描くことができるからだ。当然のことながら、リスナーはプレイヤーたちの演奏に集中することもできるが、サウンド全体から自由に空想を巡らせる──という楽しみかたもできるのである。この点は、ヴェッセルトフトの作品にも共通するところで(たとえばオスロ中央駅やカール・ヨハンソン通りあたりがイメージされる)、ひとことで云えばイマジナティヴということになる。
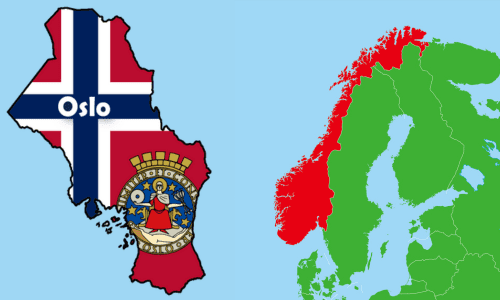
ジャズの聴きかたに、決まりはない。というか音楽の楽しみかたは、ひとそれぞれ。ジャズは基本的に演奏を楽しむ音楽──という通説もある。しかしながら音楽を聴いて、自分のイマジネーションを広げる──というのはいかがだろう?北欧ジャズのなかには、まるで現代アートが醸し出すような独特な雰囲気をもった作品が、しばしば見受けられる。そしてそれらには、たいがい聴き手にセンシビリティを刺激するかのごとき心象風景を思い起こさせる作用がある。この点が北欧ジャズの大きな魅力と、ぼくは考える。もちろんコルトレーンの音楽も大好きだけれど、その作品を聴いているときといえば、どうしても烈火のごとく音を繰り出す彼の立ち姿しか思い浮かばないのである。
たとえ情感豊かな『バラード』(1963年)や、気安さに富んだ『ジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマン』(1963年)であっても、想像力が貧困なぼくには、せいぜいダウンライトの光が優しくカウンターを照らす、落ち着いた雰囲気のバーくらいしかイメージできない。云うまでもなく、それがわるいわけではない。リスナーはただただ、コルトレーンの実は優しい人柄が垣間見えるような、端正な演奏に身を委ねるだけでいい。そして、それとはまた違う心地よさや楽しみかたを見出すことができるのが、北欧ジャズなのである。ご承知のとおり、ジャズはニューオーリンズで生まれた音楽。そもそもアメリカと北欧では、価値観や言語、習慣や行動様式が異なるわけで、ジャズはジャズでも音楽性に相違があるのはあたりまえ。
いかがだろう、北欧ジャズはジャズを外側から見つめて作られた独創的な音楽と捉えるのは──?1990年代のなかごろ、そういう感覚をもってして、ぼくは北欧ジャズを聴く意味や価値を見出したのである。そして当時、ぼくにとっての北欧ジャズ作品の入手先といえば、池袋の西武百貨店内にあったWAVE(2009年閉店)だ。WAVEでは品揃えについては、ほとんど売り場のスタッフに任されていたというが、前述のJazzlandの作品もいち早く揃えられていた。慧眼の士ともいうべきバイヤーによって選び抜かれた数々のレアなCDのなかで、ぼくはある日ノルディック・クァルテットのピアニスト、ヴィグレイク・ストラースと再会した。まえは彼の音楽性がハッキリわからなかったけれど、ぼくは生来記憶力がいいほうで、その名前だけはしっかり脳裏に刻み込まれていた。
三者が筆を自由に動かして、一枚の絵画をドローイングしている
そのアルバムこそが、ヴィグレイク・ストラース・トリオによるデビュー作『ビルデ』(1995年)だった。オスロに拠点を構えるレーベル、カーリング・レッグスからリリースされた一枚。これは余談になるが、カーリング・レッグスというとこんな思い出がある。ぼくがすっかりストラースのファンになっていたころのおはなしだ。WAVEの試聴機において、ストラースの当時の新作『サブソニック』(2002年)と、おなじくカーリング・レッグスから同時にリリースされたカム・シャインのセカンド・アルバム『ドゥ・ドゥ・ザット・ヴードゥー』(2002年)とが、なんと表示とアベコベに装填されていたのだ。二枚とも購入するつもりのぼくにとっては影響はないのだが、一応スタッフのかたにその旨を伝えた(店員さん、あのときのぼくですよ)。
ちなみにカム・シャインとは、ピアノ・トリオをバックに女性シンガー、リーヴェ・マリア・ロッゲンのヴォーカルがフィーチュアされるポップ・ジャズ・グループ。実はロッゲンはJazzlandレーベルのジャズ・ユニット、ウィブティーでも歌っており、個人的にはなにか因縁めいたものを感じる。それはともかく、優れた耳と研ぎ澄まされた感性をもったバイヤーが存在するWAVEのおかげで、ぼくはその後もストラースを追いかけることになる。ヴィグレイク・ストラースは、1963年2月2日、あのエドヴァルド・グリーグが生まれ育ったベルゲンに生まれた。地元のハイスクールで音楽を学び、その後現在のノルウェー科学技術大学に進んだ。在学中は同大学のジャズ・オーケストラのリーダーを、卒業後は音楽学部の助教授を務めている。
リーダー作には、トリオで吹き込んだ『ビルデ』(1995)『アンドレ・ビルデ』(1997年)『サブソニック』(2002年)『ナウ』(2007年)『エピステル #5』(2012年)、ソロ・ピアノ作『エクスカージョン』(1999年)、トロンハイム・ジャズ・オーケストラとの共演盤『トリビュート』(2006年)、セプテットによる『オープン・イアー』(2010年)などがある。ぼくのいちばんのお気に入りは、やはりデビュー作の『ビルデ』だ。ちなみに本作は、ノルウェーのグラミー賞ともいうべきスペルマン賞のジャズ部門において、その年のベスト・アルバムに選ばれている。サイドを務めるのは、ヨハネス・アイク(b)とペール・オッドヴァール・ヨハンセン(ds)。『サブソニック』までは、この組み合わせだ。

全11曲中、セロニアス・モンクの「ラウンド・ミッドナイト」と、ヨハンセンの「ヌーア・アーント」以外は、全曲がストラースのペンによる。なんといってもオープナーの「スラップ・アヴ」がいい。日本語にすると「リラックスしていこう!」という意味になるのかな。タイトルどおり、寛いだ感じのなかにあるほどよい緊張感が素晴らしい。コード・プログレッションとモジュレーションが美しい名曲だ。4ビートではないが、ストラースのピアノがしっかりスウィングしているのにも驚かされる。ベースとドラムスも単なるサイドに終わっていない。まるで三者がそれぞれの筆を自由に動かして、一枚の絵画をドローイングしているようだ。そういう意味では、ビル・エヴァンス・トリオをよりアーティスティックにした感じだ。
このスタイルはほかの曲にも、おなじことが云える。ただ曲想が各々異なる表情を見せるので、飽きがこない。シンプルなメロディと複雑なコード進行のコントラストが鮮やかな「エルネス」エヴァンスのワルツを北欧風に配色し直したような「スコズ・チューン」コルトレーンの高速ナンバーを超スローにお色直ししたかのごとき「バラード・アンプロンチュ」もっともリリカルでデリケートな三拍子「ヌーア・アーント」明るさのなかにグレイッシュトーンが含まれたワルツ「モーネリス」ひたすら静謐で美しい「タンカラール」哀愁を帯びた唯一エモーショナルな「エン・フレムド」複雑で風変わり、それでいて深みのあるモンクの楽曲へのオマージュ、2ピース「モンクズ・ピクチュア」と「モンクズ・ペンシルズ」と、名曲名演揃いだ。
ラストの「ラウンド・ミッドナイト」は、ソロ・ピアノで演奏される。ストラースは、モンクが好きなのだろう。ところがそうかといって彼は、ここでは原曲のようにブルージーに感情を表現しようとはしていない。まるで都会の喧騒を忘れさせられるような、雨の日の人気のないミュージアムで、モンクの肖像画を鑑賞しているような気分になる。ストラースのピアノ・プレイは、単純にそういう気分、あるいは雰囲気を喚起するのみにとどまっている。つまり、ある意味でこの楽曲が最終的に完成するのは、リスナーの思考のなかでなんらかの創造的な作業が行われたとき──ということになる。そう云うと、ますます現代アートみたいだ。だが、これもまた間違いなくジャズであり、ぼくにとっては、北欧ジャズを楽しむ際の水先案内でもあるのだ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント