幻のスーパー・バンド、リマージュのメンバーで吹き込まれたウォーレン・バーンハートのリーダー作『マンハッタン・アップデイト』
 Album : Warren Bernhardt / Manhattan Update (1980)
Album : Warren Bernhardt / Manhattan Update (1980)
Today’s Tune : Manhattan Update
バーンハートのピアノ・プレイにはビル・エヴァンスが生きている
ピアニストのウォーレン・バーンハートが天国へ旅立ってから、早いもので一年以上が経過した。彼が天上の楽士となったのは2022年8月19日のこと。83歳だった(1938年11月13日生まれ)。およそ一週間後にその訃報を知り、ぼくは、音楽を直感的に把握するときのこころの拠りどころをひとつ失ったような、そんな喪失感に見舞われた覚えがある。そのときはまだ自分がブログをはじめるなんて夢にも思っていなかったが、いつか彼について書いてみたいという密かな願望はあった。ところがいざまえへ踏み出してみると、なかなか着手することができないでいる自分に忸怩たる思いが募るばかり。とはいっても実際は、先ほどスティーリー・ダンの『アライヴ・イン・アメリカ』(1995年)を聴いていて、急に思い立ったのだからまったくいい加減なものである。
バーンハートは、このアルバムに収録されている1993年8月から1994年の9月までの全米ツアーにおいて、キーボーディスト兼ミュージカル・ディレクターを務めた。メンバーのなかには、ステップス・アヘッド時代の僚友、ドラマーのピーター・アースキンのクレジットを見出すこともできる。それぞれが、このツアーで重要な役割を担ったことは間違いない。そして、バーンハートの逝去が報じられたとき一様に、彼がこのスティーリー・ダンのライヴや、サイモン&ガーファンクルの再結成ツアーに参加したことが、真っ先に取り上げられた。でもこの件は、長年彼の音楽を追いかけてきたぼくにしてみれば、まったく腑に落ちないことなのである。なぜなら、彼の音楽家としての素晴らしさは、それだけではまるで伝わらないからだ。
確かにバーンハートといえば、熱心なフュージョン・ミュージックの愛好家を除く音楽ファンにとっては、知るひとぞ知る存在なのかもしれない。1978年の夏、モントルー・ジャズ・フェスティヴァルにおいて、アリスタ・オール・スターズによる歴史的なライヴ・パフォーマンスが行われたが、そこで見事なキーボード・ワークを発揮していたのがバーンハートだ。もしもこのときの音源が『ブルー・モントルー』(1978年)『ブルー・モントルー II』(1978年)といった2枚の実況録音盤としてリリースされなかったら、フュージョン・ファンにさえその名前が広く知られることはなかったかもしれない。とはいっても、このライヴの参加メンバーではブレッカー・ブラザーズ、マイク・マイニエリ(vib)、ラリー・コリエル(g)などのほうが、ずっと人気を博したのだが──。
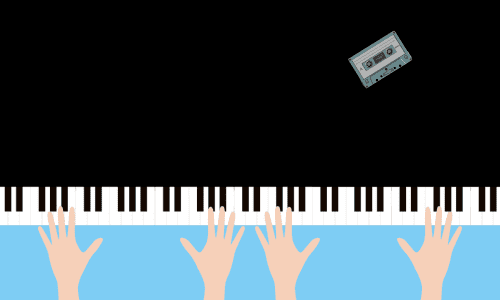
でも、音楽鑑賞に深い造詣があるひと、あるいは音楽を聴取する能力に秀でたリスナーであれば、きっとバーンハートの卓越した演奏能力に気づいただろう。それから10年以上あとのことになるが、ある批評家が『トリオ ’83』(1983年)をはじめとする、DMP(デジタル・ミュージック・プロダクツ)レーベルからリリースされたバーンハートの一連の作品を、ビル・エヴァンスのスタイルを見事なくらい完全に踏襲している──と、評していた。しかもさらに、演奏が上手いのはよくわかるが、いまひとつ凄味に欠ける──みたいなことを、仰っていた。ちょっとがっかりさせられたが、そう云いたくなる気持ちはよくわかる。
バーンハートのピアノ・プレイには、確かに偉大なるビル・エヴァンスが生きている。それをいちばんよく認識しているのは、実はバーンハート本人なのではないだろうか。エヴァンスのほうがバーンハートよりも10歳くらい年長だけれど、ふたりは気の置けない友達のような関係だった。なにせエヴァンスには、バーンハートのアパートに入り浸っては気ままにピアノを弾いていた時期があるのだから──。ときには仲よくフォー・ハンズでピアノのギグを行うこともあったという。これは、けっこう有名なエピソードだ。そんな生活がおよそ2年も続いたのだから、バーンハートが先輩のエヴァンスのピアノ・スタイルに啓発され、なんらかのインスピレーションを得るのはごく自然なことなのである。
エヴァンスが他界したあと、彼のマネージャーを長年務めてきたヘレン・キーンと評論家のハーブ・ウォンのプロデュースで『スペシャル・トリビュート・トゥ・ビル・エヴァンス』(1983年)という2枚組のアルバムがリリースされた。キーンによって選ばれた14人のピアニストが、エヴァンス所縁のナンバーをひとり1曲ずつ演奏したソロ・ピアノ集である。この14人の顔ぶれが錚々たるものなのだが、生前のエヴァンスが敬意を払っていたひと、こころにかけていたひと、そしてプライヴェートで親しくしていたひとが選ばれている。折に触れて彼が名前を口にしたピアニストばかりということだが、意表を突かれるような人選もあり興味深い。そしてそのなかには、バーンハート名前もちゃんとあるのだ。
エヴァンスとは違うバーンハートの独特なピアノ・プレイ
バーンハートはこのトリビュート・アルバムで、エヴァンスの生前にリリースされたアルバムでは聴くことができなかった「ファン・ライド」という曲を演奏している。エヴァンスのオリジナル曲だが、ここでのバーンハートのプレイはタイム感が独特で、エヴァンスのそれとはだいぶ違うように聴こえる。どちらかというと、エロール・ガーナーみたいなグルーヴだ。右手が左手より遅れてスウィングする感じで、エヴァンスのようにバウンスするようなニュアンスはない。しかもどんなに速いパッセージでも、それぞれの音をハッキリ演奏しているのだ。その点、音楽にまったくこせこせしたところのない、得も云われぬ爽快感が生まれている。エヴァンスを見事なくらい完全に踏襲している──なんて、大間違いである。
この曲に関しては現在、エヴァンスのヴァージョンも未発表曲集『ピアノ・プレイヤー』(1998年)などで聴けるので、ぜひ聴き比べていただきたい。ぼくも今回改めて、ふたりのトリオによる二種類の「ファン・ライド」を聴きなおしてみた。エヴァンスのほうは1971年の吹き込みで、サイドはエディ・ゴメス(b)とマーティ・モレル(ds)。オープニングとエンディングでは、エヴァンスのソロ・ピアノも楽しめる。バーンハートのほうは前述の『トリオ ’83』に収録されている1983年の演奏。ドラマーはピーター・アースキンだが、ベーシストはエヴァンスのヴァージョンとおなじくゴメスだ。細かく分析する必要もなく、一聴で各々の「ファン・ライド」が、かなり違った印象を与えることがわかる。
エヴァンスの音符や休符の時間的なずらしかたには、かなりクセがある。その偏りかたには他を寄せつけないような風格があって、それが高潔なイメージを生み出している。内向的であるが故の気高さとでもいうのか、とにかく誰もが簡単に真似できるようなものではない。まあ、それがエヴァンスのエヴァンスたる所以なのである。それに対してバーンハートは、左右の手のタイミングを絶妙にずらしながらも、ビートに強烈なアクセントをつけたりはしない。しかも、すべての音を美しくクリアに鳴らしている。そんな弾き方が音楽に鷹揚なムードを醸し出している。こういうレイドバックな感覚には、エヴァンスにはない心地よさがある。それは、バーンハートがジャズ以外の音楽から持って帰ってきたお土産なのかもしれない。
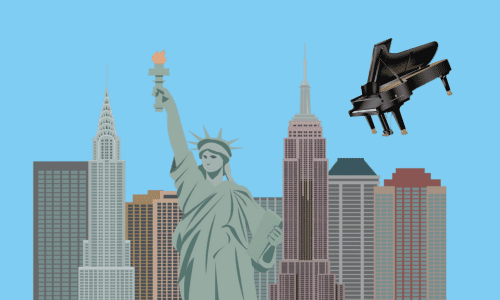
バーンハートはウィスコンシン州ウォーソーに生まれ、5歳からニューヨークで育った。彼のピアニストとしてのキャリアのはじまりは1960年代の前半で、ポール・ウィンター・セクステットでの仕事がもっとも古い。バーンハートは、まだ20代前半だった。このころのウィンター(as, ss)といえば、ニューエイジ・ミュージックに傾倒するまえで、モダン・ジャズを演奏していた。バーンハートは、その後ジェリー・マリガン(bs)、ケニー・バレル(g)などのレコーディングにも参加することになるが、多少ボサノヴァの影響があるにしても基本的にはジャズをプレイしていた。ところが、ゲイリー・マクファーランド(vib)の自己レーベル、スカイでの一連の作品(1968年 – 1971年)では、ピアノに加えてハモンド・オルガンでポップな演奏をしている。マクファーランドを敬愛するぼくは、このときバーンハートの名前をはじめて知った。
このころのマクファーランドといえば、ジャズ・ロックというかクロスオーヴァーのハシリみたいな音楽を演っていたのだが、バーンハートが単なるジャズ・ピアニストに終わらなかったのは、そこでの経験が影響していると思われる。その後も彼は、のちに盟友となるマイク・マイニエリのリーダー作『ジャーニー・スルー・アン・エレクトリック・チューブ』(1968年)への参加を機に、マイニエリとともにジャズ・ロック系の音楽を志向する。それは、今日のフュージョン・ミュージックの基盤のひとつを築いた2枚組の『ホワイト・エレファント』(1972年)であり、このセッション・プロジェクトから派生し自然消滅した幻のスーパー・バンド、リマージュの音楽である。ちなみにリマージュは30有余年のときを経て『2.0』(2009年)『ナウ』(2012年)という2枚のアルバムをリリースした。
バーンハートはアリスタ・レコードからデビュー作『ソロ・ピアノ』(1978年)と、セカンド作『フローティング』(1979年)という2枚のソロ・ピアノ・アルバムをリリースしている。ぼくが最初に入手した彼のレコードといえば、この2枚。ちなみにこのふたつの作品の間に、前述のモントルー・ジャズ・フェスティヴァルにおけるマイニエリとのデュオが収録された『フリー・スマイル』(1978年)が発売されている。ぼくは『フローティング』のなかの「ティモシー」という曲が大好きなのだが、バーンハートが自分の長男のティムに捧げた作品ということで、彼の優しい人柄が伝わってくるようなハートウォーミングなナンバーとなっている。この曲を聴いただけでも、彼が単なるジャズ・ピアニストではないことがわかる。そして、このおおらかさもまた、エヴァンスにはないものである。
バーンハートが専らフュージョンに傾倒した貴重なリーダー作
アルバム『フローティング』のレコーディングは、名匠フランク・ライコによるものだ。エヴァンスやマイルス・デイヴィスの作品も手がけたひとだが、彼の起用はバーンハートによると、クラシック・ピアノの巨匠ウラディミール・ホロヴィッツのアルバムのエンジニアを長年務めたから──とのこと。確かにこの作品では、ジャズやポップスの要素とともに豊潤なクラシックのエッセンスが溢れ出している。しかも、そのピアノのテクニックが並々ならぬものであることも明白である。ところが意外なことに、彼は正式に音楽の教育を受けたことがないという。然るべき音楽学校で学ぶことはなかったという意味だろう。大学では化学と物理学を学んだというバーンハートにとって、音楽との関わりは、幼少期に著名なクラシックのピアニストだった父親に師事したことがはじまりだった。
バーンハートのピアノの特徴としては、瑞々しいタッチ、美しいハーモニー、流麗なメロディ・センスなどが挙げられるが、ときおりコード・ワークやインプロヴィゼーションに不協和音程が含まれたりすることがある。彼の音楽メソッドが自然と身についたものだからこそ、そんな悠然とした展開を見せることがあるのだろう。その結果、演奏に開放的で鷹揚な印象が与えられているのである。その音楽性の幅広さは、後年、彼が自己レーベル、ビッグ・ガイ・サウンズにて発表した3枚のソロ・ピアノ作品『トータリー・アット・ホーム Volume I』(1997年)『同 Volume II』(1997年)『同 Volume III』(1998年)において、パーフェクトなまでに証明される。Vol. Iではエヴァンスの愛奏曲を多数含むジャズ・スタンダーズを、Vol. IIではショパン、ラヴェル、ラフマニノフのクラシック曲を、Vol. IIIでは自作曲を、彼はそれぞれ見事に弾きこなした。
そんなファンタスティックなピアニズムをもつバーンハートではあるが、その仕事ぶりは実にヴァ―サティリティに富んでいる。しかもどんなジャンルの音楽に臨んだときでも、彼の演奏にはそれを楽しんでいるような風情が感じられる。バックを務めた作品には、ロックやフュージョンなどポップな音楽が多い。それに反してリーダー作のほうは、前述のDMPレーベルにおいて8枚ほど吹き込まれているが、どちらかといえばジャズ寄りな作品ばかりだったりする。フュージョン色が強いのは、ステップス・アヘッドで共演済みのチャック・ローブ(g)をプロデューサーに迎えた『ファミリー・アルバム』(1993年)くらいのもの。そんな相反するような活動は、音楽に対する彼の飽くなき欲求の表れかもしれない。その点、アリスタ時代の専らフュージョンに傾倒したリーダー作『マンハッタン・アップデイト』(1980年)は、貴重な一枚と云える。
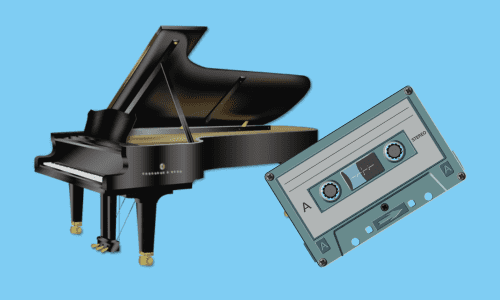
このアルバムがいかに重要な作品であるかは、レコーディング・メンバーを観ただけでもわかる。ベーシックなリズム・セクションは、ウォーレン・バーンハート(key)、マイク・マイニエリ(vib)、デヴィッド・スピノザ(g)、トニー・レヴィン(b)、スティーヴ・ガッド(ds)からなる。この5人の名前を見てピンときたら、あなたはなかなかのフュージョン通。実は彼らこそ前述の、ウッドストックでたった2年間だけ活動した幻のスーパー・バンド、リマージュのメンバーなのだ。それにアディショナル・ミュージシャンとして、パット・レビロ(key)、アンソニー・ジャクソン(b)、エロール“クラッシャー”ベネット(perc)が加わり、音景に彩りを添えている。結果、セッション風のレコーディングでありながら、トータル・サウンドの完成度は非常に高い。
マイニエリの書き下ろし「サラズ・タッチ」は、のちに作者本人のリーダー作、ライヴ盤、ステップス(ステップス・アヘッドの前身)のアルバムなど、ことあるごとに収録される名曲。バーンハートのピアノ、マイニエリのヴァイブ、スピノザのアコースティック・ギターが美しい音色を紡ぎ、ジェントルでデリケートな世界を作り出す。バーンハートとガッドの共作「マンハッタン・アップデイト」は、ガッドの神業的ドラミングのオンパレード。そのサンバを基調とした変幻自在のリズム・パターンに乗って、バーンハートのピアノとミニモーグが小気味よくインプロヴァイズする。スピノザの自作「ハング・グライディン」は、前半では静謐で透明感のある空気が醸し出され、後半ではファンキーでドラマティックな展開を見せる。音の洪水のなかを突き抜けるようなスピノザのギターが爽快。
バーンハートのオリジナル曲「プレイズ」は、コピーライト表示に1975年という記述があること、2008年のバンド・リユニオンの際にもプレイされたことから、ひょっとするとオリジナル・リマージュのレパートリーなのかもしれない。ナイーヴでソフィスティケーテッドなテーマからゴスペル調、さらにロックンロール風に展開されるところが楽しい。バーンハートとマイニエリのプレイは、いつもよりブルージー。ガッド、レヴィン、それにスピノザも跳ねる、楽しいセッションとなっている。バーンハートの自作「ニュー・ムーン」は、ミステリアスなテーマ、軽快なサンバ調のサビ、転調、そしてラグタイム風のエンディングと、構成の妙味が際立つ力作。ガッドの切れ味のいいドラミングと、なんといってもバーンハートのフェイズを深くかけたフェンダー・ローズが、ひたすら心地いい。
この「プレイズ」と「ニュー・ムーン」は、DMPレーベルの『ハンズ・オン』(1987年)で再演されている。「プレイズ」に至っては、前述の『フリー・スマイル』『トータリー・アット・ホーム Volume III』さらにマイニエリ、渡辺香津美(g)との共演作『ロータス・ナイト』(2011年)と、何度も取り上げられており、バーンハートの愛奏曲と云える。とにもかくにも本作では、思う存分にフュージョンをプレイするバーンハートを、気軽に楽しむことができる。ぜひ、多くのひとに彼のワイドレンジな音楽性と確たるピアニズムを知っていただきたい。最後に、彼が優れた音楽家であることを証明する出来事を、ひとつ挙げておこう。ビル・エヴァンスは1979年に南米へ旅行した際、バーンハートのソロ・ピアノをカセット・テープで、飽きることなく聴きつづけていたという。かの批評家が指摘するように、バーンハートが単なるエヴァンスのコピーだったら、そんなエピソードはありえないだろう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント