中庸を得たピアノ・スタイルが触発されて驚異的なプレイに──

Album : Tommy Flanagan / Overseas (1958)
Today’s Tune : Relaxin’ At Camarillo
本国では歌伴のピアニストないし名脇役
アリストテレスの倫理学に「中庸」という概念がある。平たく云うと、充足していないのではお話にならないし、そうかといって行き過ぎるのもダメ──ということだと思う。つまり、過不足がなく調和がとれている様を美徳とするわけだ。そんな偏りがなくて、どんな状況においても常にバランスのいい演奏をするジャズ・ピアニストが居る。その代表格が、トミー・フラナガンだ。
確かに、トミーのピアノの表現様式は、不偏不倚であるぶんインパクトに欠けるとも云える。しかしながら、その演奏のテクニックは、同時代の人気ジャズ・ピアニストたちのそれと比較してみても、かなり高水準であると、アマチュアのぼくでも一聴してわかるのだ。それに、度が過ぎない上質なプレイをする手腕を、恒常的にいつも発揮できるというのは、なによりも驚異的なことではないだろうか?
そんなタイプのピアニストだからか、トミーはサイドメンとして、それこそいぶし銀のプレイで膨大なレコーディングに参加してきた。ただ、1963年から1978年にかけて断続的ではあるが、20世紀を代表する歌姫のひとりであるエラ・フィッツジェラルドの伴奏者を務めたこともあり、アメリカでは単に歌伴のピアニストと観るむきが多いようだ。それに反してわが国では、彼のことをアカンパニストとしてだけではなくリーダーとしても高く評価する傾向があるのだから、まったく愉快だ。
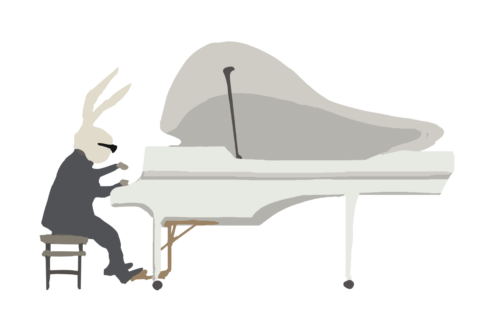
そもそも、どこか温もりのある美しいフレーズを、淡々と紡ぎ出していくようなトミーの演奏は、いかにも日本人好みと思われる。フレージングとアーティキュレーションもごく自然だ。それに、スウィング感にしてもブルース・フィーリングにしてもほどよく洗練された感じだし、コードワークにいたってはとてもエレガントな響きを奏でる──。つまり彼は、全体的に均整のとれたジャズ・ピアニストであり、その聴きやすさがかえってアメリカでは、リーダーとしての彼の評価を下げているのかも──。
本国では、上記のように歌伴のピアニストであり、インストゥルメンタルにおいても名脇役のトミーということになっていたので、そのリーダー・アルバムといったら、1970年代に入るまでたった三枚を数えるのみだった。また、生粋のハード・バッパーの快進撃が、70年代のなかごろからはじまる──というのも、ごく稀なケース。そして、ザ・スーパー・ジャズ・トリオやザ・マスター・トリオのリーダーとして、彼を表舞台に立たせたのは、日本のレコード会社だった(あとドイツも──)。
名盤の陰にトミー・フラナガンあり
それにしても、トミー・フラナガンのようなミュージシャンが、(主に日本の企画で)1990年代後半まで溌剌とした演奏を聴かせてくれるような状況を顧みると、ある意味で日本のジャズ・ファンはアメリカのリスナー以上にジャズが大好きなのでは?──と思えて、なんとなく嬉しくなってしまう。しかも、ジャズのスタイルがモード、ポスト・バップ、エレクトリック、新伝承派と、時代とともに移り変わっていくなか、トミーには流れに逆らうようにしっかりハード・バップを演らせてしまうのだから──。
そんな現象が起こるのも、わが国のリスナーが、1950年代にトミーが吹き込んだリーダー作や彼がサイドメンとして参加したアルバムを正当に評価し、こよなく愛しつづけているからなのだろう。それを裏付けるように、日本のファンの間では彼のことを「名盤請負人」と呼んだり「名盤の陰にトミフラあり」なんて、云われたりするのである。おもしろいね──いやいや、言い得て妙だな──。確かに、日本での人気盤において、彼のクレジットが発見される確率は高い(飽くまで感覚的にだが──)。
では、その名盤にはどんな作品があるかというと、誰もがすぐに思い浮かべるのは、ソニー・ロリンズの『サキソフォン・コロッサス』(1956年)と、ジョン・コルトレーンの『ジャイアント・ステップス』(1959年)ではないだろうか。どちらもテナー・サックスがリードをとるワン・ホーン・ジャズ作品であるが、趣きはまったく違う。前者は軽妙洒脱で優雅さと上品さに富んだ、イースト・コースト・ジャズとしては希有なタイプの作品。トミーもそれに合わせて、気品のあるバッキングとデリケートな粒立ちのいいアドリブ・ソロを聴かせる。

かたや後者は、モーダル・ジャズ直前の、コード進行に基づく即興演奏の限界が極められた作品。強烈な緊張感のなかでも、ミュージシャンたちが均衡を保った演奏を展開しているのが、素晴らしい。高速なテンポと目まぐるしく変化するコード進行(10回転調する)において、各プレイヤーのアドリブが繰り出される、タイトル・ナンバーは超難曲。そういったテンションの高い状況においても、決してバランスを崩さないトミーは、高度なピアノ・テクニックの持ち主と思われる。
以上の例から観ても、トミーがいかなる場面においても安定感のある上質な演奏をするジャズ・ピアニストであることがわかる。ホント、ちょっと妬ましくなるくらい、上手いんだよね──。そして、共演者の能力や特性を的確に理解して、それにもっとも相応しい演奏をする──そんな彼だから、いつになく驚異的なプレイが観られるとすれば、それは共演した誰かに触発されたときということになる。もちろん、他を押しのけて自分ばかりが目立つような演奏は、決してしないのだけれど──。
綺羅星のごとく存在する名演のなかでも最高峰
ときに、トミーの演奏がほかの才人の優れたプレイに接触することによって起こる化学変化が、顕著に現れた作品といえば、やはり『オーヴァーシーズ』ではないだろうか?実は本作は彼の初リーダー・アルバムで、なんと27歳のときに吹き込まれたもの!ぼくはこの点に、名状しがたいほど甚だしい驚きを覚えるのだ。というのも、ここでの彼の演奏には、まるで円熟期を迎えた大ベテランのみが持ちうるような、まさに地に足の着いた安定感が観られるからだ。
本作は1957年、モダン・ジャズという分野ではトロンボーン演奏の第一人者とも云うべき、J・J・ジョンソンのクインテットのヨーロッパ・ツアー中、スウェーデンにおいて、そのリズム・セクション──トミー・フラナガン(p)、ウィルバー・リトル(b)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)により吹き込まれた。この音源は当初、ストックホルムのメトロノームというレーベルから、三枚のEPレコード(各三曲収録の45回転7インチ・シングル盤)としてリリースされたのだが、翌年アメリカの名門プレスティッジ・レコードからLP盤として発売された。
これは余談だが、プレスティッジ盤のジャケットのデザインが、なんとも洒落ている。アルバム・タイトル“Overseas”が本来の表記ではなく、“Sea”が“C”(いっぱい並べられて複数形を意味している)となっている。こういう茶目っ気たっぷりのはからいは、ある種の遊びごころが含まれた音楽であるジャズには、とてもよく似合うのだ。後年メトロノームのEP盤に倣ったトミーの写真があしらわれたジャケットのLPやCDも発売されたけれど、ぼくは断然プレスティッジ盤のほうが好きだ。このジャケットを眺めているだけで、もはや条件反射的に、その内容の素晴らしさを想像して胸をときめかせてしまうのである。

ところで、肝心の内容のほう──前述のように、ここでトミーを触発した張本人といえば、ドラムスのエルヴィン・ジョーンズだ。彼は終始ブラシを使って多様なリズムを軽々と叩き出しているが、そのキャッチーで精力的なプレイは、あたかも本来中庸を得たスタイルのピアニストであるトミーに、刺激を与えてその感情に火をつけようとしているかのごとくである。それに対してトミーは、相変わらずクリアーで流麗な音の羅列をキープしながらも、いつもよりグルーヴィーに鮮明で力強いフレーズを繰り出したりもする。それは、まるで水中の魚がときおり川面に跳ね上がるような感じだ。
さらに云うと、(一応ソロもあるけれど)ボトムをキープすることに徹しているウィルバーのベースでさえ、ちょっとその時代を超越するようなグルーヴのなかにしっかり溶け込んでいるのだから、その揺るぎないトリオの一体感は驚異的と云うしかない。その点を勘案すると、果たせるかな、本作は綺羅星のごとく存在するトミーの名演のなかでも最高峰──ということになる。その証拠に、日本のアルファ・ミュージックが、本作の再演をベースにした好盤『シー・チェンジズ』(1996年)を製作している(66歳のトミーも絶好調!)。やはり彼は、日本のジャズ・ファンにすこぶる愛されているのだ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント