ソニー・クラークが不調を一時的に克服して見せた信じがたいほどハイテンションなパフォーマンスに溜飲が下がるタイム盤『ソニー・クラーク・トリオ』
 Album : Sonny Clark Trio / Sonny Clark Trio (1960)
Album : Sonny Clark Trio / Sonny Clark Trio (1960)
Today’s Tune : Sonia
正式にリリースされたピアノ・トリオ作品はたったの2枚しかない
もっともよく聴いたという点で、ぼくにとって最上位のジャズ・ピアニストといえば、ソニー・クラークにほかならない。いちばん好きなピアニストというわけではないけれど、いまも昔もぼくは彼のレコードをよく聴く。彼のアルバムでもっともよく聴いたのは、ブルーノート・レコードからリリースされた『ソニー・クラーク・トリオ』(1958年)であることは、まず間違いない。ついでに云っておくと、色違いのジャケットの『ソニー・クラーク・トリオ Vo. 2』(1985年)『ソニー・クラーク・トリオ Vo. 3』(1985年)というレコードがあるのだが、この2枚はもともとシングル盤用に録音された演奏を中心に、別テイクや未収録曲がまとめられたもので、日本の東芝EMI(現EMIミュージック・ジャパン)によって発売された。
クラークのピアノ・トリオ作品というと、正式にリリースされたアルバムは実はたったの2枚しかない。ザナドゥ・レコードから発売されたアルバムで、ベーシストのシモン・ブレーム、ドラマーのボビー・ホワイトをサイドメンに迎えたトリオでの演奏を聴くことができる『メモリアル・アルバム』(1976年)というレコードがあるけれど、これをクラークのトリオ作に数えるのはちょっと辛い。このアルバム、さもすべての音源がトリオの演奏を収めたものであるかのように、ジャケットにブレームとホワイトの名前が堂々と表記されている。しかし実際は、トリオでの演奏は7曲中2曲のみで、残りの5曲はクラークのソロ・ピアノによるものだ。しかもそのパフォーマンスは、余興の域を出ていない。
そもそもこの音源は、クラリネット奏者のバディ・デフランコのバンドでヨーロッパ・ツアーの真っ最中だったクラークが、ノルウェー、オスロのとあるクラブで開かれたパーティに招かれた際、それこそ座興で披露した演奏が録音されたものなのだ。つまりそれはレコーディングを前提としたパフォーマンスではないわけで、彼に必要以上の気合が入っていないのも当然のこと。ただ観かたを変えれば、1954年1月15日に録音されたこのライヴ演奏は、クラークの最初期のものであると同時に、ある意味で胡散臭いほどチルアウトしたものでもある。そういった意味では貴重な記録と云えるのかもしれないが、いっとき入手困難なレコードともてはやされた本盤を、実のところぼくは決して血眼になって探すような類いのものではないと思っている。
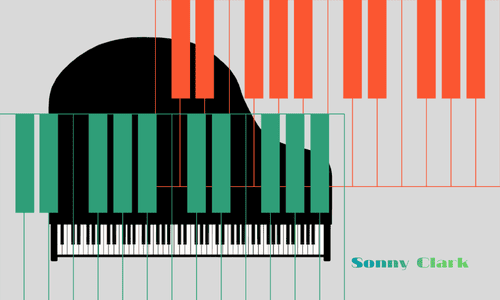
ということで繰り返しになるが、クラーク自身のあずかり知らぬところで制作されたアルバムを除くと、彼のピアノ・トリオ作品はやはり2枚しかないのである。ブルーノート・レコードに、アート・ファーマー(tp)、カーティス・フラー(tb)、ハンク・モブレー(ts)、ウィルバー・ウェア(b)、ルイス・ヘイズ(ds)といった、当時のブルーノート・オールスターズとも云うべき豪華なメンバーとともに初リーダー作『ダイアル・S・フォー・ソニー』(1957年)を吹き込んで以来、同レーベルのハウス・ピアニストとして幾多のセッションに参加したクラークだけに、トリオ作が2枚とは極めて少ないと思われる。まあ彼のプロの音楽家としての活動期間はおよそ12年だから、それもまた致しかたないか──。
クラークは周知のとおり、1963年1月13日、薬物の過剰摂取により31歳という若さでこの世を去った。そもそも生前にリリースされたリーダー作は実のところ6枚しかないわけで、その3分の1を占めるトリオ作は、ハード・バップを象徴するピアニストのディスコグラフィとして考えると、むしろ割合が大きいと云えるのかもしれない。なお『ダイアル・S・フォー・ソニー』の吹き込みは、1957年7月21日にニュージャージー州ハッケンサックにおいて行われた。云うまでもなく、レコーディング・エンジニアを務めたのはルディ・ヴァン・ゲルダーだが、録音当日は奇しくもクラークの26歳の誕生日だった。自分の誕生日に初リーダー作を吹き込むというのは、どんな気持ちになるのだろうか──。
しかもこのレコーディング、ハンク・モブレーのリーダー作『ハンク・モブレー』(1957年)において、クラークがブルーノート作品に初登場してから1か月余りあとの出来事。この異例の早さから、プロデューサーであるアルフレッド・ライオンが、クラークに対して大きな期待を抱いていたことがわかる。くだんのモブレーのアルバムでは、彼のリーダー作のなかでは比較的地味なメンバーによるセッションとなっているが、クラークはポール・チェンバース(b)、アート・テイラー(ds)らとともに、素晴らしいコンピングを披露。アドリブ・パートにおいても、自然体で臨んでいる。1951年から西海岸を拠点に構え演奏活動をつづけてきた彼は、このときニューヨークに移ってからまだ2か月余りだったが、なかなかどうして堂々としたものである。
ときに、さきに挙げたブルーノート盤『ソニー・クラーク・トリオ』と並ぶクラークの正式なトリオ盤とうと、彼のファンならご承知のことだろうが、タイム・レコードからリリースされた『ソニー・クラーク・トリオ』(1960年)である。ブルーノート盤とタイム盤とは同名のタイトルが掲げられているが、むろんまったくの別モノだ。タイムはエマーシー・レコードを立ち上げたことで知られる音楽プロデューサー、ボブ・シャッドによって1959年に設立された。そのカタログにはジャズ作品のほかにカクテル・ポップ系のアルバムやシングル盤も多数含んでおり、1960年代の半ばごろまで西海岸の人気レーベルとして存在感を示していた。ことにジャズ作品はわが国でも、何度となくリイシューされるほど高い人気を得ている。
このレーベルにおいてクラークは、自己のリーダー作をリリースするほか、トロンボニストのベニー・グリーンのアルバム『ベニー・グリーン』(1960年)のレコーディングにも参加している。このアルバムでは「クール・ストラッティン」「ソニーズ・クリブ」「ブルー・マイナー」といった、クラークのオリジナル・ナンバーのなかでも特に人気の高い3曲を聴くことができる。ちなみに、アメリカのオリジナル盤のジャケットには「クール・ストラッティン」を「イッツ・タイム」「ソニーズ・クリブ」を「ソニーズ・クリップ」「ブルー・マイナー」を「クール・ストラッティン」というふうに、誤った表記がなされている。それに反して日本盤では、当初からこの誤記が修正されており、あらためてクラークのわが国での人気を窺い知ることができる。
こころが和むウェストコースト時代のクラークによる鷹揚なプレイ
このセッションのメンバーを列記すると、ベニー・グリーン(tb)、ジミー・フォレスト(ts)、ソニー・クラーク(p)、ジョージ・タッカー(b)、アルフレッド・ドリアース(ds)となるが、ちょうどドラムスをドリアースからポール・ガスマンに入れ替えたメンバーで吹き込まれたグリーンのリーダー作で、ニューヨークの超マイナー・レーベル、エンリカからリリースされた『スウィング・ザ・ブルース』(1960年)というレコードがある。このアルバムのレコーディングは1959年の1月に行われたのだが、タイム盤の『ソニー・クラーク・トリオ』は1960年3月、そして『ベニー・グリーン』は1960年9月の吹き込みとなっている。これらの3枚をあわせて楽しむと、1959年から1960年までのクラークの変遷を確認することができるのだ。
思えばクラークはブルーノートからデビューして以来、ビバップ・スタイルを承継しながらファンキーな味わいを感じさせるプレイで、数多くのハード・バップ作品を盛り上げてきた。にもかかわらず彼は、キャバレー・カードの支給を受けることができなかった。このカードは、1940年から1967年までニューヨークのナイト・クラブで働くために必要とされた許可証。クラークにカードが与えられなかったのは、彼が薬物の常習者だったからだ。ビバップの父と謳われたチャーリー・パーカー、アルト奏者のジャッキー・マクリーン、ピアニストのセロニアス・モンク、シンガーではビリー・ホリデイやフランク・シナトラなども、おなじ理由からカードを取得することができなかった。
すでに薬物依存症だったクラークは、いつの間にかスタジオ・レコーディングに参加することができなくなるほど、意志や行動を自分でコントロールすることができなくなっていた。彼がそんな状況をなんとかやり過ごしながら奇跡的にプレイしていたのが、ちょうど1960年前後のことである。実はクラークの安定期は、わが国のジャズ喫茶を賑わせ、日本からの注文が殺到したことからアルフレッド・ライオンを驚かせ、結局のところニューヨーク・タイムス紙をして不朽のハード・バップ・クラシックと云わしめた『クール・ストラッティン』(1958年)のリリース、あるいはブルーノート作品の研究におけるオーソリティ、マイケル・カスクーナによって発掘された『マイ・コンセプション』(1979年)のレコーディング(1959年3月)あたりまでだった。
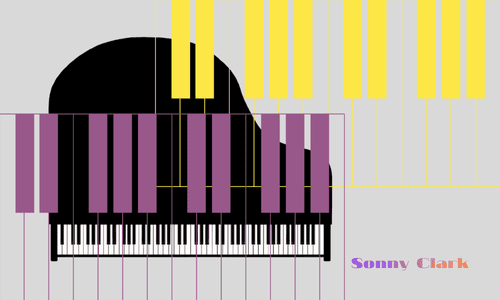
クラークがブルーノートに復帰するのは、1961年10月26日に吹き込まれたジャッキー・マクリーンのリーダー作『ア・フィックル・ソーナンス』(1962年)。リーダー作については1961年11月13日に録音された『リーピン・アンド・ローピン』(1962年)まで待たなければならなかった。このアルバムを聴いた限りでは、クラークが完全復活を遂げたようにしか思えない。それくらいそのプレイは、ファンキーでダイナミックに響く。その後、クラークは1962年にもブルーノートのいくつかのセッションに参加したが心臓病で入院、1963年1月に一時的に退院するも、前述のように薬物の過剰摂取で心臓発作を起こし帰らぬひととなった。結局『リーピン・アンド・ローピン』が、彼の存命中に発表された最後のリーダー作となった。
クラークは1931年7月21日、アメリカ、ペンシルヴェニア州のハーミニーという小さな町に生まれた。彼は生まれてから2週間後に鉱山労働者の父親を亡くしている。ピアノを弾きはじめたのは4歳のときで、超絶技巧のブギウギ・ピアニスト、ピート・ジョンソンから強く影響を受けたという。6歳のときにはラジオにも出演し、12歳のときにピッツバーグに移住。ハイスクール時代には地元のバンドで、ピアノのほかにヴィブラフォンも演奏した。クラークは正式な音楽教育を受けておらず、実戦でジャズ・ピアノのテクニックを身につけた。後世に残る数々の名演において、息つく間もなく繰り出されるブルージーでメロディアスなインプロヴィゼーションや、屈託なく放たれるファンキーなフィーリングは、彼が感覚的に習得したものなのだろう。
1951年、クラークは母親が亡くなったことを機に、カリフォルニア州ロサンゼルス群パサデナ市に移住する。プロのミュージシャンとして活動を開始した彼は、トランペッターのアート・ファーマー、テナー奏者のデクスター・ゴードン、おなじくテナー奏者のワーデル・グレイらと共演。さらにクラークは1953年から、サンフランシスコ市に移りベーシストのオスカー・ペティフォードとトリオを組んでプレイするようになるが、年末にはバディ・デフランコ・クァルテットのピアニストとして、ケニー・ドリューの後釜に座る。彼はデフランコのグループに1956年まで在籍したが、前述したザナドゥ盤『メモリアル・アルバム』の音源はその時代の記録。評論家のレナード・フェザーが企画した「ジャズ・クラブ USA」と題されたヨーロッパ・ツアーに参加したときのものだ。
なおバディ・デフランコ・クァルテットのヨーロッパ・ツアーの模様は、ビリー・ホリデイのライヴ音源とともに『ライヴ・イン・ケルン 1954』(2014年)というCDに収録されているので、興味のあるかたは手にとってみてはいかがだろう。その後クラークは、ふたたびロサンゼルスに戻り一時的ではあるが、ベーシストのハワード・ラムゼイが率いるライトハウス・オールスターズのメンバーとなる。このアンサンブルはその名のとおり、ライトハウス・カフェのハウス・バンド。ライトハウスはカリフォルニア州ハーモサ・ビーチ、ピア・アヴェニューの老舗ナイトクラブだ。クラークは過去にこのクラブの慣例となっていたジャム・セッションにおいて、偶然にもアルト奏者のアート・ペッパーと共演することがあった。
偶然というのは、当初その晩のピアニストを務めるのはハンプトン・ホーズだったのだが、彼がよんどころない事情で来られなくなったため、急遽クラークがステージに上がったから。1953年3月30日のことだが、このときまったくの無名だったクラークは、その力強く溌剌としたプレイでバンド・メンバーとオーディエンスのハートをつかんだ。ペッパーのほうもその夜は絶好調で、全11曲のうちピアノ・トリオで演奏された「テンダリー」以外は、切れ目なくノリに乗ってプレイしつづけた。このときの模様は、なにかと有名なジャズ・マニア、ボブ・アンドリュースによって録音され、その音源は1974年に彼のプライヴェート・レーベルから『ストレイト・アヘッド・ジャズ』というタイトルで、2枚に分けてこっそりリリースされた。
ところがどっこいこのアルバムは、妙中俊哉が主宰するインタープレイ・レコードから2枚組CDの『アート・ペッパー・ウィズ・ソニー・クラーク・トリオ』(1987年)として正式に発売されて以来、様々な仕様で何度となくリイシューされてきた。音質はお世辞にも良好とは云えないけれど、演奏の妙味から不思議とその点に煩わされることはなく、本作は長いあいだぼくの愛聴盤となっている。しかも好きが高じて、ぼくはすでにインタープレイ盤を所持していたが、1992年に日本のジャズ専門のディストリビューター、NORMAによってニュー・マスタリングが施され、オリジナルに準じて2枚のアナログ・レコードとして発売されたヴァンテージ盤のほうも購入してしまった。それだけクラークの瑞々しいタッチと、伸びやかなフィーリングが魅力的なのである。
クラークが気焔万丈となるのはおなじトリオ作でもタイム盤のほう
クラークにはアフリカ系アメリカ人特有の感性で、シャープかつエレガントなハーモニーを響かせながら、流れるようにキャッチーなフレーズを連綿と繰り出していくようなイメージがある。そういうクールネスからクラークといえば、1957年以降のブルーノート作品に人気が集中する。しかしながら、西海岸ならではのリラックスしたアンサンブルと抑制の効いたエクスパンションに身を委ねながら、鷹揚なプレイを展開する彼もまたぼくは好きだ。メロディアスでセンシティヴな楽句を繰り出すペッパーとの相性もいい。なおこのときのセッションでは、ベーシストをハリー・ババシン、ドラムスをボビー・ホワイトが務めている。Vol. 2で聴かれるチェロはババシン(ベースはハワード・ラムゼイが代行)、コンガはクラブのオーナー、ジョン・レヴィーンによるものだ。
ということで、クラークのウェストコースト時代の鷹揚なプレイにこころが和む『アート・ペッパー・ウィズ・ソニー・クラーク・トリオ』彼の絶頂期とも云える機知に富んだ叙情味さえ溢れる安定したエクスプレッションに、爽快な気分にさせられるブルーノート盤『ソニー・クラーク・トリオ』そして、薬物依存から精神と身体にきたした不調を一時的に克服した彼が見せる、信じがたいほどハイテンションなパフォーマンスに溜飲が下がるタイム盤『ソニー・クラーク・トリオ』を、聴き比べてみるのもまた一興である。それは、長年クラークのレコードを聴きつづけてきたぼくにとって、いまではちょっとした楽しみになっているほど。それぞれのピアノのタッチは違ったもののように聴こえるけれど、やはりクラークはクラークで、とにかくイケているのだな──。
ぼくは冒頭で、彼のアルバムでもっともよく聴いたのはブルーノート盤『ソニー・クラーク・トリオ』と云ったけれど、それには個人的な理由がある。実はぼくは、中学生のころからジャズ・ピアノを自分でも弾いてみたいと思い、教則本を手に入れて練習しはじめた。もともとクラシック・ピアノの個人レッスンを受けていたし、小学校高学年のころにはそれと並行してポピュラー・ピアノも弾いていた。だからコードやスケールについての知識はそれなりに身につけていた。ところがジャズを演奏するための体系的な手順や方法を理解した上でいざ実演に臨むと、ぼくの演奏は意気消沈するほどまったくジャズっぽくないのだ。これではいけないと考えひらめいたのが、ホンモノの演奏を真似することだった。
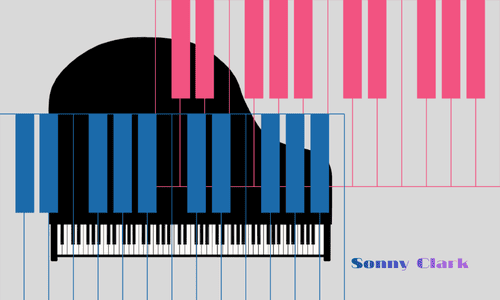
そこでぼくが真っ先に手にとったレコードが、ブルーノート盤『ソニー・クラーク・トリオ』だった。正直なところクラークのピアノのテクニックには、当時の自分が知るほかのピアニストのそれと比較したとき、格別なスゴさは見受けられなかった。しかしながら、その淀みなく連なる簡潔なフレーズとそれが醸し出すブルージーでどこか凛とした雰囲気とに、彼のセンスのよさが感じられた。平たく云えば入門者のぼくには、クラークのプレイがとてもカッコよく思えたのである。耳をそばだてて彼が奏でる音に意識を集中させると、即興演奏のなかにおなじような楽句が何度も出来することに気づかされる。そのなかから気に入ったフレーズを楽譜に転記し、あとはそれを弾けるようにひたすら練習するのみ。これが意外と楽しいのだ。
さらに云うと、ぼくはマスターしたクラークの楽節をいくつもストックしておいて、いざ実戦に臨んだときそれを引用していた。そんな自分の演奏について音楽仲間に「いまのちょっとソニー・クラークっぽくない?」などとツッコまれたときのぼくといえば「そうかな?」としらばっくれていたもの。いずれにしても、ぼくがジャズ・ピアノのお手本にしたというか、ずいぶんコピーさせてもらったのは、クラークのレコードだった。その最たるものといえば、間違いなくブルーノート盤『ソニー・クラーク・トリオ』だ。ちなみに、このアルバムでぼくがいちばん好きな演奏は、リチャード・ロジャースとロレンツ・ハートによる「時さえ忘れて」であり、ふんだんに盗ませていただいたのはディジー・ガレスピーの「トゥー・ベース・ヒット」である。
さて、このブルーノート盤については以前このブログでも採り上げたことがあるので、今回は最後にタイム盤『ソニー・クラーク・トリオ』のほうに対するぼく思いの丈を述べておこう。ブルーノート盤のほうが全曲スタンダード・ナンバーで構成されているのに対し、タイム盤のほうはすべてクラークのオリジナル・ナンバーでまとめられている。どちらも稀なケースと云えるが、クラークによるトリオ演奏のふたつの異なる味わいを楽しむことができるのは、実にありがたい。前者のポール・チェンバース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)に対する、後者のジョージ・デュヴィヴィエ(b)、マックス・ローチ(ds)というサイドメンの違いもまた妙趣を生んでいる。ぼくは両盤ともに好きだけれど、前述のようにクラークが気焔万丈となるのは後者である。
収録曲のうち「マイナー・ミーティング」と「ニカ」(「ロイヤル・フラッシュ」と同名曲)は、米国ブルーノートでは未発売だったがのちに東芝EMIによって発掘された『ソニー・クラーク・クインテット』(1976年)や、前述の『マイ・コンセプション』でも採り上げられた曲。また「ブルース・ブルー」「ジャンカ」「マイ・コンセプション」「ソニア」は『マイ・コンセプション』でもプレイされている。聴き比べするのも一興かと──。なお「ソニーズ・クリップ」は、セカンド・アルバム『ソニーズ・クリブ』(1958年)の表題曲とは別の曲である。オープニングを飾る「マイナー・ミーティング」では、アップテンポに乗ってクラークがクールなフレーズを矢継ぎ早に繰り出す。粋のいいローチとの4バースもいい塩梅だ。
つづく「ニカ」では、軽い足どりのリズムに誘われて、クラークが気持ちよさげにスウィングしまくる。次第に俊敏な指遣いでファンキーなフィーリングを醸成していくところが、なんとも心地いい。デュヴィヴィエのソロもソツなくスマートだ。ややテンポを上げた「ソニーズ・クリップ」は、クラークのキャッチーな楽句が満載で、その機敏な歌わせかたもお見事。ローチとのソロ交換も溌剌としている。ラテンから4ビートに移行する「ブルース・マンボ」では、ローチの推進力のあるドラミングと、それに感化されたかのように饒舌になるクラークの当意即妙のプレイが痛快だ。B面最初の「ブルース・ブルー」は、オーソドックスな12小節のブルースだが、クラークとデュヴィヴィエとのエスプリの効いたダイアローグに、こころがくすぐられる。
快活で洗練された「ジャンカ」では、ピアノ、ベース、ブラシがアンサンブルにしてもソロ交換にしても、とにかく軽妙洒脱。モダン・ジャズならではのウマ味のある1曲だ。つづく「マイ・コンセプション」では、唯一クラークの素朴で淡麗なソロ・ピアノが披露される。機知と叙情味に富んだバラード・プレイに、こころが和む。ラストを飾る「ソニア」では、クラークが軽快なテンポに乗ってビバップ然としたフロウを間断なく展開する。すごく歌っている。しかもそれには、バド・パウエルの気迫とは対照的な整合性が際立つ。そしてその集中力たるや、とても薬物依存症のピアニストのものとは思えない。快調なピアノ演奏とトリオによるソロ交換とが相まって、爽やかな余韻を残す。やはりクラークのピアノは、カッコいい。何度も聴きたくなる。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント