ジャズ界の三賢者による、ピアノ・トリオ屈指の名盤『ウィ・スリー』
 Album : Roy Haynes / We Three (1959)
Album : Roy Haynes / We Three (1959)
Today’s Tune : Reflection
ピアノ・トリオ屈指の名盤に関して、取り違えて認識していたある事実
ぼくは、生来勉強嫌いな人間だった。生まれてこのかた真面目に勉学に励んだ覚えがない。実はこの歳になって、そのことをようやく後悔していたりするのだけれど、学問や知識から養われるであろう品位みたいなものを、いまから高めたいというような欲求は毛頭ない。単純に知見を得ることの楽しさを、いまさらながら見出しただけなのである。そんなわけで、たとえば読書にしても、近年は未知の分野の書物を手にとる機会が増えた。あと、ぼくは文系の人間だけれど、娘の勉強を見ながら、数学や理科の問題を解くことの楽しさを再認識した。
なんでもっと早く、そういう気持ちにならなかったのだろう。答えは簡単。いまのいままで果実として、いや、ひととして十分に熟していない状態だったから。そうはいっても、現在ちゃんと分別のあるオトナになっているのかというと、かなり自信がない。とにもかくにも、さまざまな能力を身につけるために勉強は欠かせない。ほんとうは、そういうスキルは子どものころから少しずつ身につけておく必要がある。そうしないとぼくみたいに、取り返しのつかないことになってしまうのだよ──って、だれに向かって云っているのだろう?それにしても、子どものころのぼくといえば、ほんとうにバカだったな。
小学生のころのぼくは、将来は音楽家になるからバカでもいい──そんなふうに思っていた。ピアノを弾くことができるというのを盾にして、ぜんぜん勉強をしなかった。高校生になっても、大学受験に失敗したらプロのミュージシャンになろうと、まったく分をわきまえず安易に考えていた。繰り返すが、ほんとうにバカだった。まあ結局どうにかこうにか、ごく普通の社会人になることができたのだが、その経緯は、またの機会にどこかでおはなしさせていただく。ときに、まともに勉強もせず、感性と想像力だけで生きてきたぼくは、そうであるが故にある思い違いをしていた。それも、けっこう長い期間──。
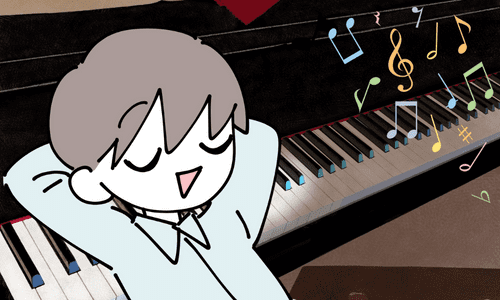
ぼくは長い間バカだったが、それに反して昔から記憶力はいいほうだった。いまでも旧友たちと昔話に花を咲かせるときなど、みんなから「おまえは、ほんとうによくおぼえているな」と、よく感心される。だが、博覧にあらずしてバカで強記というのには、いささか問題がある。いったん誤ったデータがインプットされると、それはずっと修正されないまま、価値のない知識として記憶されるのである。たとえば、ピアノ・トリオ屈指の名盤『ウィ・スリー』(1959年)に関して、ぼくはある事実を長期にわたり取り違えて認識していた。さあ、ここまでで慧眼な諸兄姉であれば、ぼくがどんな思い違いをしたかは、想像に難くないだろう。
どうぞ、冷笑を浮かべていただきたい。あれは、ピアニストのフィニアス・ニューボーン・ジュニアの訃報が伝えられたときだから、1989年のこと。ぼくがどうにかこうにか、ごく普通の社会人になったばかりのころだ。ある日、ぼくのジャズの師匠でもある勤め先の上司から「フィニアスの名盤といったら、なんだろうね?」と、もったいをつける口調で訊かれた。ぼくはおそるおそる「『ア・ワールド・オブ・ピアノ!』もいいんですけれど、個人的には『ウィ・スリー』がいちばん好きですね」と答えた(『ア・ワールド・オブ・ピアノ!』は1962年にコンテンポラリーからリリースされた傑作)。すると師匠は、メガネの奥から鋭い眼光を放ちながら「う〜ん、あれは、一応ロイ・ヘインズのアルバムだからねぇ」と云って、腕組みをした──。
揃いも揃ったジャズ界の三賢者──リーダーはロイ・ヘインズ
ぼくは、愛想笑いを浮かべながら「そうですよね」と口にし平静を装ったが、こころのなかでは「えっ、そうなの?」と完全に冷静さを失っていた。大学生のころから親しんできた『ウィ・スリー』は、ほんとうにニューボーンのリーダー作ではないのか?納得がいかなかったので、帰宅するやいなやレコードを確認した。ジャケットの表をよく観ると、小さな文字で“with”と記されているのを発見。つまり“WE THREE”というタイトルの下に記されたクレジットは、“ROY HAYNES with PHINEAS NEWBORN PAUL CHAMBERS”となっている(ついでにニューボーンの名に“JR.”がついていないのにもはじめて気づいた)。本盤は正真正銘、ロイ・ヘインズのリーダー作だ。これは、不勉強なぼくの上滑りな知識がまねいた、ほんとうのおはなし。
なにせ感性と想像力だけで生きてきた人間だから、ぼくの意識は音楽のほうだけに向いていたのだろう。それに言い訳になるけれど、ジャケット写真に写る三人──真ん中にいるのは、ほかでもないグラサンのニューボーン。ぼくはこれにすっかり騙された。おまけに、ポール・チェンバースがその長身でそれなりに目立つぶん、リーダーのヘインズはいちばん地味にうつる。まさか、ヘインズが主役とは──。まあ、いいジャケットだとは思う。三人が、東方の三賢者然としているではないか。ひょっとすると、ほんとうにクリスマス・キャロルの「我らはきたりぬ(We Three Kings of Orient Are)」を捩ったのかもしれない。
アメリカ文学における短編の名手、オー・ヘンリーの作品『賢者の贈り物』は、あまりにも有名だ。クリスマス・プレゼントをめぐって、ある夫婦に行き違いがおこるが、結局この行き違いがもっとも賢明な行為だった──というストーリーもよく知られている。しかしながら、この小説が、キリストの誕生を祝うため、東方より三賢者が贈り物をもってやってきた──という、新約聖書のなかのエピソードが下敷きになっているというのは、日本人にはあまり知られていないのではないだろうか。その贈り物は、黄金、乳香、没薬だが、各々がイエスが王であり、神であり、さらに人間として死すべきものであることを示唆すると云われている(ほかにも諸説あり)。

ちなみに、三賢者の名前は福音書には記述がなく、のちにカトリック教会が名付けた。メルキオール、バルタザール、カスパールという呼称は、あのテレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』(1995年 – 1996年)に登場する三台のスーパーコンピューターのネーミングで、広く知られるようになった──と、お勉強の時間はこれくらいにして、本筋に戻る。名盤『ウィ・スリー』の三賢者を改めて記すと、ロイ・ヘインズ(ds)、フィニアス・ニューボーン・ジュニア(p)、ポール・チェンバース(b)となる。ここでの賢者の贈り物は、もちろん、和声、旋律、律動である。この三人は、ある意味でジャズという音楽の道理に通じていて、それとともに卓越した演奏技術も備えている。まさに賢者の名に相応しい。というか、よくこれだけのひとが揃ったものだ。
リーダーのロイ・ヘインズは、なにかとモダン・ジャズにおいて重要なレコーディングに顔を出す──という印象がある。たとえば、バド・パウエルの『ジ・アメイジング・バド・パウエル Vol.1』(1955年)、マッコイ・タイナーの『リーチング・フォース』(1963年)、チック・コリアの『ナウ・ヒー・シングス・ナウ・ヒー・ソブス』(1968年)などで、彼のプレイが聴ける。決して自分を目立たせようとはせず、バックにまわり堅実にリズムをキープして、共演者を乗せるのがとても上手い。そのドラミングは、いつも軽快で小気味いい。しかもタイコの音が、最高に綺麗。たぶんチューニングのせいなのだろう。シンバルも含めてドラムスのセッティングでは、ぼくはこのひとのがいちばん好きだ。
ヘインズはドラマーにしてはずいぶんリーダー作を制作しているけれど、複数のサックスを同時に演奏する特殊技能(?)で有名な、あのローランド・カークと共演した『アウト・オブ・ジ・アフタヌーン』(1962年)が、一般的には傑作と云われる。ぼくはどちらかといえば、ヘインズ、エディ・デ・ハース(b)、リチャード・ワイアンズ(p)といったトリオで演奏された『ジャスト・アス』(1960年)のほうが好みだ。云ってみれば、第二の『ウィ・スリー』といった風情がある。デ・ハースにしてもワイアンズにしても、ヘインズのプレイに気分よくさせられたのか、実に趣味のいいフレーズを繰り出している。ヘインズのドラミングも軽やか、そして音がいい。ちなみに、ぼくはこのアルバムを、まさに『ウィ・スリー』がヘインズのリーダー作と認識して間もなく入手した(今度はリーダーを間違わなかった)。
トリオがもち寄った贈り物は、もっとも賢明なものだった
二人めのポール・チェンバースは、ハード・バップ請負人といった貫禄のあるベーシスト。マイルス・デイヴィスのファースト・グレート・クインテットのボトムを支えた。ドラムスのフィリー・ジョー・ジョーンズとの蜜月は、至上の美しさを放つ。マイルス以外の作品でも、彼はなにかと名盤に登場する。アドリブ・ソロにしても4ビートのベースラインにしてもメロディアスで、彼のプレイに耳を傾けていると、そのフレーズを一緒に口ずさみたくなるほどだ。また、ちょっとレイドバックした絶妙なタイム感覚が素晴らしい。ビートに得もいわれぬリラクゼーションが生み出されるのだ。そのスタイルは、時流に乗ることもなく、生涯モダン・ジャズのメインストリームを極めるものだった。リーダー作では、ピチカートにしてもアルコにしても、とにかくベースがよく聴こえる『ベース・オン・トップ』(1957年)が本命。
三人めのフィニアス・ニューボーン・ジュニアは、云ってみれば、ピアニスティックなピアニスト。超人的なテクニシャン。驚異的なインプロヴァイザー。ダイナミズムとアジリティを兼ね備えた、オールラウンド・プレイヤー。左右の手がともによく動くが、2オクターヴほど離したユニゾン・プレイは独特。とにかくピアノという楽器を自由自在に操るその演奏技術は、ハード・バップ期のピアニストのなかでは最高峰ではないだろうか。ジャズ界きっての超絶技巧といえば、すぐにオスカー・ピーターソンが思い出されるが、正直に云うと、彼の無遠慮にハッピーな雰囲気と、軽業師的なパフォーマンスが、ぼくはかなり苦手。音楽的な成熟度では、ニューボーンのほうが優れていると思う。
残念なことに、ニューボーンは精神的な問題を発症し度々入退院を余儀なくされ、そのキャリアは間欠的。ピアニズムのトップランナーでありながらメジャーになれなかったのは、それが原因。リーダー・アルバムでは、やはり前述の『ア・ワールド・オブ・ピアノ!』が代表作になるのだろう。彼のミラクルなテクニックを、たっぷり味わうことができるのだから──。ただ、ぼくはここでの演奏に、確かに天才という形容が物足りなく感じられるほどの衝撃を覚えたのだが、こころに深く刻まれるような強い感動を受けることはなかった。その点で、ぼくの評価は『ウィ・スリー』のほうが上だ。実はここでのニューボーンは、もち得るテクニックを全開してはいない。ところが、そのこせつかないプレイが、却って作品の品格を高めているのである。

オープナーのセンチメンタルな曲想が素晴らしい「リフレクション」は、レイ・ブライアントの曲。トリオが絡み合うキャッチーなイントロは、本ヴァージョンのオリジナル。アート・ブレイキーの『ホリデイ・フォー・スキンズ Vol.2』に収録されている、ブライアント自身の演奏もいいけれど、ぼくはニューボーンの小ワザを効かせた流れるようなプレイのほうに軍配をあげる。ヘインズのソロも、ブレイキーのそれよりハイセンス。ニューボーンの自作曲「シュガー・レイ」では、おおらかで深みのあるブルース・プレイをひたすら堪能すべし。チェンバースとヘインズのソロもなかなか。トニー・ベネットの歌唱で知られる「ソリテア」は、リリカルなチェンバースのソロも素晴らしいが、なんといってもニューボーンのエモーショナルなバラード・プレイが感動的だ。
レイジーなブルース「アフター・アワーズ」は、アースキン・ホーキンス楽団のピアニスト、エイヴリー・パリッシュの曲。数多のミュージシャンによるブルージーな演奏が存在するが、ここではニューボーンの余裕綽々な、ファンキーなフィーリングが最高。カナカナカナというヒグラシの鳴き声のような単音連打は、一度はやってみたい小ワザのひとつ。キレのいいリズムが活かされた「スニーキン・アラウンド」は、またもやブライアントの曲で『レイ・ブライアント・プレイズ』(1960年)において本人の演奏が聴ける。ここではブライアント・トリオに比べて、より鷹揚な演奏になっており、4バースにしてもとても上品。クロージングの「アワ・デライト」は、タッド・ダメロンの代表曲。本盤唯一の明るく快適なアップテンポ・ナンバー。三人の演奏は、まるで高く澄み渡った秋空のように爽快だ。
結局、ヘインズはリーダーでありながら、ひたすらバックに回っている。彼のカラーが特別に強く出るような場面はほとんどない。ただ、ひたすら小気味いいドラミングを継続することによって、爽やかで心地いいサウンドをクリエイトしていく──案外、彼にとってはそんなマナーこそが、自分の世界を創造することに直結するのかも──。ぼくは、本作を長い間ニューボーンのリーダー作と勘違いしていたけれど、ここにある彼の名演は、リーダーでないが故に気負うことなく楽に構えることができたから実現されたものと、いまさらながらに確信する。それは、チェンバースのスタンスについてもおなじことが云える。いずれにしても、彼らはジャズ界の三賢者であり、彼らがここにもち寄った贈り物が、もっとも賢明なものだったことは間違いない。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント