追悼ロイ・エアーズ──クエンティン・タランティーノが惚れ込んだブラックスプロイテーション作品『コフィー』のサウンドトラック盤
 Album : Roy Ayers Ubiquity / Roy Ayers / Coffy (1973)
Album : Roy Ayers Ubiquity / Roy Ayers / Coffy (1973)
Today’s Tune : Coffy Is The Color
ソウル・ミュージックへの傾倒とタスク満載の日々
ロイ・エアーズがこの世を去ったことは、彼の代表作『エヴリバディ・ラヴズ・ザ・サンシャイン』(1976年)をご紹介したときにすでにお伝えした。コンポーザー、アレンジャー、プロデューサー、そしてヴィブラフォニストとして数多くのレコーディングに携わり、長いあいだ音楽ファンを楽しませてくれたエアーズであるが、長い闘病生活の末、2025年3月4日にニューヨーク市で亡くなった。以下は重複するが、あらためて記しておく。彼の死は現地時間5日(日本時間では6日)に、オフィシャル・フェイスブック・ページにて明らかにされた。84歳だった。エアーズは1962からポスト・バップのヴィブラフォニストとしてそのキャリアをスタートさせたが、やがてサウンド・クリエイトにおいて、ジャズを根幹としながらも積極的にソウル・ミュージックの要素を採り入れるようになっていく。
エアーズはプロデュース気質で、新たなフィールドに足を踏み入れることを臆することなく、常に流行の最先端を行く音楽家だった。彼は1966年からジャズ・フルーティスト、ハービー・マンのグループに加入するが、のちに発揮されるプロデュースやアレンジの優れた能力は、マンの門下に学んだ経験の賜物だろう。1970年にマンと袂を分かつとエアーズはときを移さず自身のバンド、ロイ・エアーズ・ユビキティを結成する。彼が一般的にレジェンダリーなジャズ・ファンクのパイオニアとして語られるひとつの契機となったのは、1978年まで継続的にリリースされたこのバンドの13枚におよぶ作品群である。むろん彼は、ひとつの分野に収まりきらない広い視野と柔軟な思考を兼ね備えた音楽性をもつミュージシャン。その後のソロ活動でも、さらなる進化を遂げる。
その点、エアーズはミュージック・シーンにおいて、たいへん稀有な存在だった。ぼくは中学生のころから彼のアルバムを聴きはじめたのだけれど、いつの間にか自室のレコード棚にはその作品がズラリと並んでいた。エアーズがクリエイトする音楽は、スタイリッシュでソフィスティケーテッドなサウンドとコージーでダイナミックなグルーヴとをあわせもつたいへん親しみやすいものだから、いまも多くのリスナーから支持されつづけている。また彼はクラブ・シーンにおいて、もっとも再評価された音楽家のひとり。ジャズ、フュージョン、ファンク、ブギー、メロウ・グルーヴ、ディスコといった様々な側面をもつエアーズの作品は、レア・グルーヴの音盤やサンプリング・ソースとして、いまも重宝されている。これほど世代を超えて愛されるミュージシャンは、ほかにいないかもしれない。
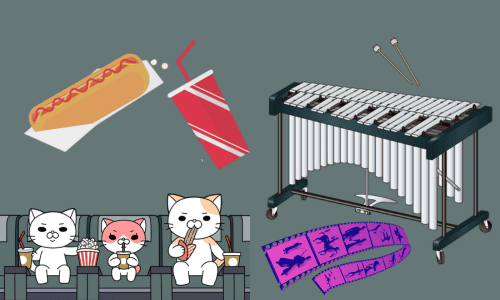
エアーズは、プレイヤーとしては参加せずプロデュースとソングライティングのみを手がけたアルバム『スターブーティ』(1978年)をもってしてユビキティを解散するが、その後もソロ・アーティストとして1990年代の半ばまでコンスタントにリーダー作をリリースしていく。そのいっぽうで彼は、1976年にザ・クルセイダーズを脱退したトロンボニスト、ウェイン・ヘンダーソンとともに、2枚のコラボレーション・アルバム『ステップ・イン・トゥ・アワ・ライフ』(1978年)『プライム・タイム』(1980年)を制作。特にストリングスのアレンジが冴えるレイドバックなサウンドには、従来のエアーズ作品とはひと味違う心地よさがある。これらのアルバムも、DJ/クラブ世代から圧倒的な支持を得ている。
おなじころ、エアーズはナイジェリア出身のミュージシャン、フェラ・クティとともに、妙々たるコラボレーション・ワークに取り組んでいる。アフロビートのゴッドファーザーと観られているクティは、サクソフォーン、トランペット、ギター、キーボード、ドラムスなどを演奏するマルチ・インストゥルメンタリストであり、ヴォーカリストでもある。ふたりは1979年にナイジェリアの主要都市をまわる6週間のツアーを敢行したが、その最終プロセスとしてジョイント・アルバム『ミュージック・オブ・メニー・カラーズ』(1980年)をリリース。A面にクティ、B面にエアーズといった具合に各々の楽曲が1トラックずつ収録されているが、ふたりが相互に客演するというスタイルがとられている。個人的には、このグルーヴ感が病みつきになった。
さらにエアーズは1977年、オハイオ州シンシナティ出身のソウル・グループ、ランプをデビューさせている。グループ名の“Ramp”は、“Roy Ayers Music Production”の頭文字をとったアクロニム。エアーズは自身のメロウ・チューン「エヴリバディ・ラヴズ・ザ・サンシャイン」を、このグループにカヴァーさせている。1980年代に入ると彼は、ニューヨーク市マンハッタン区の南北に走るリヴァーサイド・ドライヴに、自己レーベル、ウノ・メロディック・レコードを設立。5人組のコーラス・グループ、エイティーズ・レディーズ、女性ソウル・シンガー、シルヴィア・ストリプリン、サクソフォニストのフスト・アルマリオらの作品を制作し、卓越したトータル・サウンドをスーパーヴァイズするプロデュース能力を披露した。
思えばエアーズは、その長いキャリアにおいてタスク満載の日々を極めたのは、1980年代だったかもしれない。リーダー・アルバムのレコーディングや自己レーベルの運営の合間を縫って、いちプレイヤーとしての仕事も精力的にこなしていた。たとえばパンク・ファンクのイノヴェーター、ベーシストでシンガーソングライターのリック・ジェームスのアルバム『スローイン・ダウン』(1982年)にエアーズのクレジットを見出すことができる。アルバムのトップを飾るディスコティークを沸かせたヒット・ナンバー「ダンス・ウィズ・ミー」の後半、いきなりエアーズによるヴィブラフォンの熱いソロが登場する。なおそれとは逆に、エアーズは自身のリーダー作『ダブル・トラブル』(2005年)で、ジェームスのヴォーカルをフィーチュアした。
またエアーズは意外なところで、48歳で急逝したソウルシンガー、そして女優でもあるホイットニー・ヒューストンのセカンド・アルバム『ホイットニーII〜すてきなSomebody』(1987年)に参加していたりする。伝説的な音楽プロデューサー、ジョン “ジェリービーン” ベニテスが手がけたアップテンポ・ナンバー「愛がすべてを」という曲の後半で、エアーズによるヴィブラフォンのアドリブがヒューストンのヴォーカルに絡んでくる。ベニテス自身がプログラミングしたデジタル・ドラムマシンやシンセサイザーのサウンドが激烈で、うっかり聴き逃してしまいそうだが、ポール・ジャクソン・ジュニアのギターやパウリーニョ・ダ・コスタのパーカッションと同様に、間違いなくエアーズの生演奏である。
(『エヴリバディ・ラヴズ・ザ・サンシャイン』については、下の記事をお読みいただければ幸いです)
アシッド・ジャズ、ネオ・ソウルにおけるブームの再燃
プロデュース気質のエアーズが、珍しくプロデュースされる側にまわったアルバムもある。エアーズにとってはコロンビア・レコード移籍第1作にあたる『イン・ザ・ダーク』(1984年)がそれ。プロデューサーとして迎えられたのは、アコースティック、エレクトリックともに超絶テクニックをもつベーシスト、スタンリー・クラーク。ところがクラークはここでベースを弾いてはいない。彼がここで使用しているのは、1980年代前半にポップ・ミュージックやジャズ・ファンクなどで絶大な人気を博したドラムマシン、リンドラムである。これもまた時代の趨勢で、ここではヤマハが開発したFM音源搭載のデジタル・シンセサイザー、DX7やオーストラリア産のサンプラー&シーケンサー機能を有するフェアライトCMIなども多用されている。エアーズにとっては、新しいアプローチとなった。
1990年代もエアーズの創作意欲はとどまることを知らず、リーダー作も継続的にリリースしサイドマンとしても多くの作品に参加した。かねてから彼は、アシッド・ジャズのムーヴメントにおいて最大級のインフルエンサーと崇め奉られていたが、1990年代の終盤には“ネオ・ソウルのゴッドファーザー”という異名をとったほど。このころエアーズは、ポップ・カルチャーを通じて多様性を促進する国際的な非営利団体、レッド・ホット・オーガニゼーションの企画にも参加している。そのコンピレーション・アルバム『レッド・ホット・アンド・クール〜ストールン・モーメンツ』(1994年)は、タイム誌によって“アルバム・オブ・ザ・イヤー”に選ばれたが、日本でも発売されたのでご記憶のかたも多いだろう。
もともとこのアルバムは、アフリカ系アメリカ人コミュニティにおけるエイズ流行に対する支援金集めを目的としたもの。とはいえ、単なる企画ものに終わらない高品質を誇る。なおエアーズは本作で、ペンシルヴェニア州フィラデルフィア出身のヒップホップ・グループ、ザ・ラップと共演を果たした。2000年代に入ってもクラブ・シーンでのエアーズの人気は高まるいっぽうで、イギリスのBBE(ベアリー・ブレイキング・イーヴン)レコードとドイツのラプスター・レコードとが提携して1976年から1981年までのお蔵入りとなっていたエアーズのレコーディングを発掘した。その『ヴァージン・ユビキティ』(2003年)『ヴァージン・ユビキティ II』(2005年)『ヴァージン・ユビキティ・リミックスド』(2006年)といった3枚は日本でも大きな話題となった。
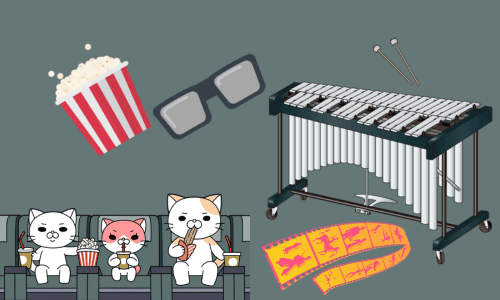
これらの2枚の未発表音源集と音源を名うてのクラブ・ミュージック・アーティストがリミックスした企画盤(2枚組)は、日本のインディペンデント・レーベル、ウルトラ・ヴァイヴが国内発売をしたことから、わが国ではちょっとしたエアーズ・ブームの再燃があった。各トラックのクオリティは意外にも高く、既発のアルバムでは聴けないようなタイプのピースもあり、この掘り起こしは非常に意義深いものと思われる。その後のエアーズといえば、リーダー作のレコーディングはぐっと少なくなるが、ハウス・ミュージックに進出したり、様々なコラボ企画やイヴェントに参加したり、相変わらず目まぐるしい毎日を送った。そして、彼のライヴ活動は2023年までつづいた。なおエアーズは2011年に、ニューヨーク市の人種平等会議から特別功労賞を授与されている。
ということで駆け足でエアーズの足跡をたどってきたが、彼のことを余すところなく語るのはやはり無理である。まだまだお伝えしたいことはあるのだが、それについては断腸の思いでまたの機会とさせていただく。ここからは、本題の映画のハナシである。実はエアーズは、俳優のピーター・フォンダが監督したSF映画『アイダホ・トランスファー』(1973年)に俳優として出演している。映画は人類の未来を託された若者たちが、転送マシンによって56年後の未来世界へ赴き探索するという、一種のタイムトラベルものだが、エアーズはエルギンという役を演じている。これは単なる豆知識というか、まったくの余談である。ここで話題の中心となるのは、彼が手がけた映画音楽について──。
1997年(日本では1998年)に公開された『ジャッキー・ブラウン』という映画がある。エルモア・レナードの小説『ラム・パンチ』を原案としたクライム・サスペンスだ。監督と脚本を務めたのは、俳優で映画プロデューサーでもあるクエンティン・タランティーノ。1990年代から2000年代にかけて、各シークエンスが絡み合うようなプロットと、臆することなく表現されたクライム&ヴァイオレンスとを特徴とする作品で、一大ブームを巻き起こした。かねてより彼は長編映画を10作撮った時点で、映画監督を引退すると公言してるいけれど、すでにその作品は2019年公開の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』で9作を数える。さて今後はどうなることやら──。
タランティーノが20代のころカリフォルニア州のマンハッタン・ビーチのレンタルビデオ店で働いていたことはよく知られているけれど、そのときに培った映画の知識が彼の監督作品にはしっかり活かされている。つまりタランティーノの作風には、自身の映画趣味が随所に見受けられるのである。パロディ、オマージュ、引用などの宝庫だ。音楽にしても『レザボア・ドッグス』(1992年)『パルプ・フィクション』(1994年)では、1960年代から1980年代までの既製のポップス、ロックンロール、R&B、サーフ・ミュージックなどがふんだんに使用されている。この2作ではカリン・ラクトマンという女性ミュージック・スーパーヴァイザーが、タランティーノの右腕としてそれらしい音づけをした。
くだんの『ジャッキー・ブラウン』の音楽も、すべて既製の曲で構成されている。映画のスタッフクレジットにはミュージック・コーディネーターとしてアン・カーリン、ジョン・カトーフシッチの名前があるが、本作の使用曲についてタランティーノは、脚本を執筆する段階でそのほとんどが決定していたと述べている。相変わらず1970年代のソウル・ミュージックを中心に選曲されているが、面白いのはこの映画で使用されている楽曲の一部に、既存のサウンドトラック盤から流用されたものがあること。たとえばボビー・ウーマックの「110番街交差点」は1972年公開の同名映画の主題歌だし、ランディ・クロフォードの「ストリート・ライフ」は数あるヴァージョンのなかからわざわざ映画『シャーキーズ・マシーン』(1981年)のサントラ盤の音源が使用されている。
タランティーノのお眼鏡に適ったフィルム・スコア
タランティーノ作品では既存のサントラ盤の収録曲が二次利用されるのは、この『ジャッキー・ブラウン』がはじめてだったが、その後も彼は『キル・ビル』2部作(2003年/2004年)『イングロリアス・バスターズ』(2009年)『ジャンゴ 繋がれざる者』(2012年)と作品を重ねるごとに、サントラ音源の使用度を高めていく。そのマナーはもはやタランティーノの十八番とも云うべきもので、ときには邦画、カルト映画、エクスプロイテーション・フィルムといったマニアックなセレクションが際立つこともあり、彼のビデオショップの店員時代の経験が大いに活かされていることがわかる。そしてロイ・エアーズが手がけたサウンドトラック・アルバムもまた、タランティーノのお眼鏡に適った1枚だったのである。
映画『ジャッキー・ブラウン』の劇伴には、エアーズによるフィルム・スコアが何曲か使用されている。もとの音源は、ジャック・ヒル監督による1973年公開のブラックスプロイテーション作品『コフィー』のサウンドトラック盤である。具体的にはこのアルバムから「アラゴン」「エスケイプ」「エキゾティック・ダンス」「ヴィットローニのテーマ:キング・イズ・デッド」といった4曲が『ジャッキー・ブラウン』でそのまま使用されている。ちなみにブラックスプロイテーションとはアフリカ系アメリカ人向けのストーリーをもつ、興行成績を上げるためだけの低予算量産型のキワドい映画のこと。ロサンゼルスを舞台に麻薬中毒にさせられた11歳の妹の敵討ちのため、女性看護師のコフィーが犯罪組織に独りで立ち向かうというクライム・スリラーだ。
タランティーノの映画『コフィー』への強い愛着のほどは、想像に容易い。なにせ『ジャッキー・ブラウン』の主人公、客室乗務員でウラの顔は麻薬取引の売上金の運び屋というジャッキーを演じているパム・グリアは、24年まえに『コフィー』のメイン・キャラクター、コフィーを演じたそのひとなのだから。実は『パルプ・フィクション』のときにタランティーノは、当初あの全身ピアスの女、ジョディ役をグリアにキャスティングしようと考えていた。しかし身長の問題で断念し、結局ロザンナ・アークエットに配役した。しかしながら、どうしても自身の映画へグリアを出演させることを諦め切れず、彼は『ジャッキー・ブラウン』のシナリオを執筆する運びとなったのである。そしてグリアが主役の映画なら、音楽はエアーズ以外にあり得ないということなのだろう。
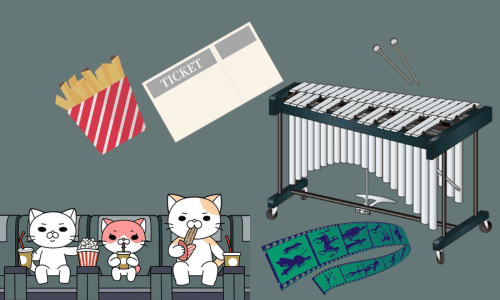
ところが『ジャッキー・ブラウン』のサントラ盤(正確にはコンピレーション・アルバム)に、エアーズのスコアは1曲も収録されていない。それ故か1998年のことだが、日本では本作が公開された直後に『コフィー』のサントラ盤が世界ではじめてCD化された。当時のCD帯にはしっかり「ジャッキー・ブラウン挿入曲収録」という記載がある。その点、タランティーノさまさまなのだが、実は日本ではそれ以前にこのレアなアルバムにスポットライトが当てられていた。ジャズ・ファンクのアナログ・レコードを積極的にリイシューしていた渋谷に拠点を構えるレキシントンが、1995年にヒップホップ・フリークに向けて『コフィー』のサントラ盤をLPで復刻。ぼくも、これを入手した。いきおい日本未公開だった映画のほうも、1997年に本邦初上陸となった。
このアルバム、映画『コフィー』のサントラ盤としてはもちろんのこと、タランティーノ作品『ジャッキー・ブラウン』の劇伴として、そしてエアーズのリーダー・アルバムとしても機能する、アーモンドグリコではないけれど1粒で2度おいしい、いや3度おいしい作品だ。本盤はエアーズにとって、ロイ・エアーズ・ユビキティのアルバム『レッド・ブラック&グリーン』(1973年)と『ヴァーゴ・レッド』(1973年)とのあいだの作品で、まさに脂が乗っている時期の吹き込みだからワルいはずがない。レコーディング・メンバーも、ロイ・エアーズ(vib, vo)、ハリー・ウィテカー(key)、リチャード・デイヴィス(b)、ビリー・ニコラス(g)、ボブ・ローズ(g)、デニス・デイヴィス(ds)、ウィリアム・キング(perc)、セシル・ブリッジウォーター(tp, flh)、ジョン・ファディス(tp, flh)、ガーネット・ブラウン(tb)、ウェイン・アンドレ(tb)など、実に豪華だ。
上記のうちウィテカー、ニコラス、デイヴィスは、ロイ・エアーズ・ユビキティのメンバー。特にキーボーディストのウィテカーは、ホーンズ&ストリングスのアレンジも手がけるキーパーソン。あとヴォーカリストとして、メンフィス出身の女性ジャズ・シンガー、ディー・ディー・ブリッジウォーターと、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、ウェイン・ガーフィールドが参加している。もちろん、エアーズ自身も歌っている。ちなみにディー・ディーとトランペッターのセシルとは、このときは夫婦だった(結婚生活は1971年から1975年まで)。オープニングの「コフィ・イズ・ザ・カラー」では、ディー・ディー、ガーフィールド、エアーズが、3人揃ってファンキーなヴォーカルを聴かせる。
このオープニング・ナンバーはユニークなコード進行の4小節をひたすら繰り返すシンプルな曲だが、その疾走感のあるグルーヴは絶品。簡素な入りかたのブラス・セクションも、シャープで効果的だ。後半はエアーズのヴィブラフォンによる音の奔流にのまれるのみである。つづく「プリシラのテーマ」では、前半は寛いだボサノヴァのリズムに乗ってフルートが爽やかにソフィスティケートされたメロディック・ラインを綴る。後半はスピーディーなラテン・ビートとともにヴィブラフォンのアドリブが飛翔する。ミッドテンポのジャズ・ファンク「キング・ジョージ」では、しなやかなベースのリフがつづくなかエアーズによるスポークン・ワードが胡乱な空気を漂わせる。アフロビートとファンキーなブラス・アンサンブルがキャッチーな「アラゴン」では、ピアノ、ローズ、オルガンと、ウィテカーの独擅場だ。
アジムスの楽曲を彷彿させる「コフィ・サウナ」では、エアーズのスキャットがピースフルな雰囲気に拍車をかける。ラロ・シフリンのスコアを思わせる「キングス・ラスト・ライド」では、リズムがロックンロールからラテンへ移行するなかニコラスがワウギターを唸らせる。レコードにおいてはA面のラストを飾る「コフィ・ベイビー」では、ディー・ディーの温もりのあるソウルフルなヴォーカルを堪能。ハートウォーミングなR&Bテイストが堪えられない。オプティミスティックでグルーヴィーな「ブローリング・ブローズ」では、エアーズのヴィブラフォンとウィテカーのローズが美味しくシンクロする。ブラス・アンサンブルがサスペンスフルなフレーズを奏でる「エスケイプ」では、キングによるボンゴの連打がスピード感を煽る。バラードからラテンに移行する「シャイニング・シンボル」では、前半のガーフィールドのクルーナーなヴォーカルと後半のエアーズの軽妙なヴァイブとのコントラストが鮮やかだ。
ゴスペル調の「エキゾティック・ダンス」では、ニコラスのギターとウィテカーのオルガンとがブルージーなソロを繋いでいく。ゆったりした4ビートの「メイキング・ラヴ」では、ソフトなホーンズの重奏も然ることながらウィテカーによるハープシコードのアドリブがエレガントだ。そのハープシコードのクラシカルなソロ演奏「ヴィットローニのテーマ:キング・イズ・デッド」では、ほのかにシネマ・イタリアーノの香りが漂う。ミステリアスな「エンド・オブ・シュガーマン」では、バンドによるフリー・インプロヴィゼーションが全開される。以上14曲、サウンドトラックということで各楽曲は短尺であるが、レア・グルーヴ・クラシックとしての魅力も満載。そこにあるのはエアーズ・サウンド以外のなにものでもないし、クオリティもすこぶる高い。ぜひご賞味あれ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント