サントラ盤というよりはボサノヴァ生誕40周年を記念するコンピレーションといった趣きの『ワンダーランド駅で』
 Album : Claudio Ragazzi / Next Stop Wonderland (1998)
Album : Claudio Ragazzi / Next Stop Wonderland (1998)
Today’s Tune : The Finale
映画を映画館で観る素晴らしさ──名画座、ミニシアターへの思い
むかしむかし、ぼくは、映画少年だった。小学校高学年のころ、隔週土曜日、4時限授業を終えて下校すると、池袋の文芸坐(現在の新文芸坐)に通っていた。この映画館はいわゆる名画座で、旧作映画を主体に上映していた。たいてい2本ないし3本立てで、入場料金は当時300円とダントツで格安だった。そう、ぼくはべつに旧い映画を観たかったのではなくて、映画鑑賞を楽しむのに小学生のお財布にとても優しかったから、この映画館の常連となったのである。しかも、文芸坐はちゃんと関連性のある映画を同時上映してくれたので、ぼくの柔い感性は、いつもシックリ満たされていた。
おかげで、その世代ではないけれど、ハリウッド黄金時代の作品やアメリカン・ニューシネマ、それにフィルム・ノワールの古典的名作からヌーヴェルヴァーグまで、とにかくたくさんの映画を観ることができた。なかには意味もわからず、雰囲気だけしか味わうことができない作品も多々あった。なにせ、小学生だから──。でも、そのころのぼくは、読書についてもそうだったけれど、ちょっと背伸びをしたくなるような時期だったのだ。年齢と不相応な態度や言動をとる子どもはべつに珍しくもないと思うけれど、それとおなじように、ぼくの感受性はいささかマセていた。それでも、早くから映画を観ることの素晴らしさを知ることができたのは、幸運だったと思う。
その後、中学、高校、大学と、ぼくの名画座通いは止まることを知らず、文芸坐のみならず、飯田橋佳作座(1988年閉館)、ギンレイホール(2022年閉館)といった神楽坂の2館にも、ずいぶんとお世話になったもの。ところが1980年代の後半あたりから、レンタルビデオ、ケーブルテレビ、DVDなどの普及の煽りを受けて、どんどん名画座は減少していった。まあ、そのレンタルビデオでさえ、動画配信サービス、さらにサブスクが一般家庭に浸透するいまとなっては、衰退傾向にあるのだから、これも時代の流れなのだろう。それでも、名作を劇場で──と、現在も頑張っている名画座もある。ありがたいことである。
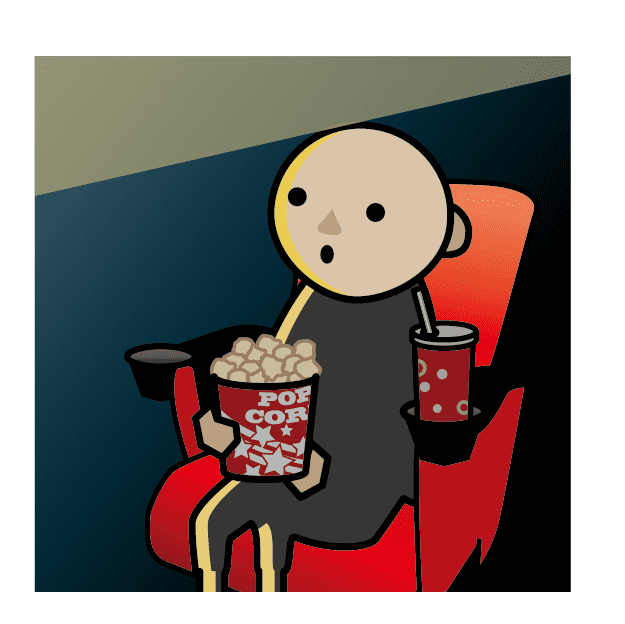
もちろん、家庭で好きな時間に気軽に映画を楽しむことができるというのは、とても便利でいい。しかしながら、劇場に足を運ぶ場合と比較すると、楽しさがなにかひとつ減ったような気分になる──というのが、ぼくの本音である。劇場では生活音に邪魔されず作品に集中できるというのは云わずもがなだが、それよりも映画を観たこと自体が思い出に残る──ということに、得もいわれぬ情趣を感じるのである。名画座でもそれに近い感覚を覚えるのだが、それにもましてミニシアターでの映画鑑賞は、作品と映画館の結びつきが強いことから、忘れがたい体験となることが多い。
たとえば、『ニュー・シネマ・パラダイス』(1988年)『デリカテッセン』(1991年)といえば、シネスイッチ銀座がすぐに思い出される。『ベルリン・天使の詩』(1987年)『恋人までの距離』(1995年)といえば、シャンテシネ(現在のTOHOシネマズシャンテ)なのである。いつ誰と観にいって、帰りにどこで食事をして、どんな話をしたかまで記憶していたりする。これぞまさしく、映画館で映画を観る醍醐味だ。ただ今世紀に入ると、大手シネコンが単館系作品の上映を設けるようになったせいで、老舗のミニシアターも苦境に立たされているという。
インディペンデントならではのアイディアと表現方法が駆使された作品
社会人になってから子どもが生まれるまでのぼくにとって、銀座はホームグラウンドみたいな場所だった。それで前述の映画館のほかにもう一館、忘れられないミニシアターがある。いまはなき銀座テアトルビル(現在はコナミクリエイティブセンター銀座がある)の5階にあった銀座テアトル西友だ。1946年に開業した当時はテアトル銀座、1955年から1981年まではテアトル東京という名称で親しまれたが、建物の全面的な改築が行われ1987年の竣工とともに銀座テアトル西友としてリニューアル・オープン。いやいや、歴史が香るな──。しかしながら、2000年に銀座テアトルシネマと改称、しばらく営業は継続されたが、惜しくも2013年ついに閉館となった。
ところで、銀座テアトル西友といえば、ぼくにとっては『ワンダーランド駅で』(1998年)一択だ。日本で公開されたのは1999年で、ちょうどクリスマスの日に観た。ぼくはわりと記憶力がいいほうなのだけれど、もしそうでなかったとしても、この日を忘れるわけにはいかない個人的な事情がある。実はその日は、結婚するまえの妻とはじめて迎えたクリスマスで、この映画はふたりで鑑賞した。もちろん、ここで惚気話をひけらかすつもりはない。先ほどからこの映画のサントラ盤をなんとなしにプレイしていたら、にわかに当時のことが思い出されたのだ。そして自然と、ミニシアター、名画座と、過去の記憶をさかのぼってしまったというわけ。これもまた、いとおかし──である。
ときに、この『ワンダーランド駅で』だが、どんな映画かというと、キャッチコピーにもあるように「なかなか二人は出逢えない」という、ちょっとユーモラスなラヴ・ストーリー。いまでいうと「あざと連ドラ」(オッサンもたまにはそういうのを観る)をお洒落にした感じか──?ボストンを舞台に、恋や人生の意味を探す、いささか不器用で堅物なひと組の男女が、ともすれば二人の間に恋が生まれそうなシチュエーションにありながら、すんでのところで出逢えない──というシーンが繰り返される。観客はそんな二人を俯瞰しながら、やきもきさせられる。映画の終盤で二人が降り立ったワンダーランド駅は、地下鉄ブルーラインの終着駅。いよいよ、恋のはじまりを予感させられる──。
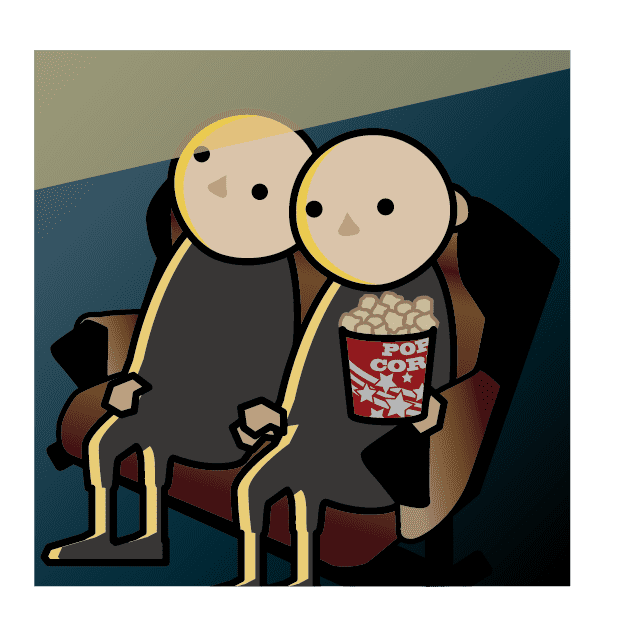
監督、脚本、編集を務めたのは、ヒッチハイカーの男を主人公とした冒険コメディ『ザ・ダリエン・ギャップ』(1996年)でデビューした、ブラッド・アンダーソン。この日本未公開作は、サンダンス映画祭の審査員大賞にノミネートされたほか、サンタ・バーバラ映画祭で最優秀監督賞、フロリダ映画祭で最優秀ナレーティヴ賞を受賞している。これを機にアンダーソンは、1997年にアメリカのエンターテインメント業界誌ヴァラエティによって「注目のインディペンデント界新人映画監督10人」のひとりに選ばれた。2作目にあたる『ワンダーランド駅で』は、受賞には至らなかったが、やはりサンダンス映画祭で観客の人気を集めた。そして、フランスのドーヴィル映画祭では、見事グランプリと観客賞を受賞している。
ご承知のとおり、サンダンス映画祭といえば、数あるインディペンデント映画のなかから、度々ヒット作の鉱脈が掘り当てられることで有名。そんなわけで、上映会場は、配給会社の買い付け担当者、弁護士、エージェント、マネージャーなどで溢れかえる。しかも、映画祭が開催されるユタ州のスキーリゾート地、パークシティのホテルでは、ロビーにおいて連日連夜、朝方まで有望な作品の買い付けの会合が開かれるという。インディペンデントならではのアイディアと表現方法が駆使された『ワンダーランド駅で』は、結局ミラマックス・フィルムズが配給した。スゴイ名作というわけではないが、面白い映画を観た──というささやかな幸福感に満たされるような佳作──そんな本作は、やはりミニシアターがよく似合う。
では、映画についてはこれくらいにして、ここからは音楽のおはなし。アンダーソン監督の意向で、この映画では全編をとおして、バックにボサノヴァが流された。楽曲は、最新録音から往年の名演まで、広範囲にわたる。結果、現代的なユーモアとペーソスに富んだダイアローグとランドスケープが、ボサノヴァのサウダージ感覚によって、その軽妙洒脱な味わいにより深みを増した。いまぼくが聴いているサントラ盤──実はジャケットには「Music From The Miramax Motion Picture」と記載されていて、サウンドトラックというコトバはどこにも見当たらない。そう、ボサノヴァ誕生の年は、ジョビン&モライスによる名曲「想いあふれて」が吹き込まれた1958年。それから、ちょうど40年──。本作は、ボサノヴァ生誕40周年を記念するコンピレーションとして楽しむべきものなのである。
コンテンポラリーな新録音と黄金時代の名演とのスペシャルな出会い
オリジナル・スコアを手がけたのは、アルゼンチンはブエノスアイレス出身でボストン在住のコンポーザー兼ギタリスト、クラウディオ・ラガッシ。映像作品の仕事もするが、自己のクインテットでアルゼンチン・タンゴのアルバムを数枚リリースしている。また、現代タンゴの巨匠、作曲家でピアニストのパブロ・シーグレルのグループのギタリストとしても活躍し、すでに何度か来日を果たしている。2016年には東京JAZZにおいて、ヴァイオリニストの寺井尚子とシーグレルによるTHE JAZZ TANGO PROJECTで、素晴らしいギター・プレイを披露したので「ああ、あのひとか」と思われる向きもあるのではないだろうか。本作には、ラガッシが映画のために書いた4曲が収録されている。
まず「キス」ではピアノ、ギター、フルート、それにストリングスが、洒落っ気を交えてたゆたうように歌う。そして、リズミカルな「クロスド・パス」では、ラガッシのブルージーなエレクトリック・ギターのソロも然ることながら、あのアート・リンゼイのリラックスしたスキャットが聴ける。さらに、ゆったりした「セラピスト」と軽快な「フィナーレ」では、リンゼイとともに、べべウ・ジルベルトも即興で柔らかな歌声を披露。リンゼイといえば、これまでにノー・ウェイヴ、ノイズ・パンク、フェイク・ジャズなど、様々なスタイルの音楽を展開してきたが、どちらかといえば前衛的なイメージが強い。とはいえ、ニューヨーク・アンダーグラウンドの象徴のような彼も、実は3歳から17歳までブラジルで過ごしており、ここではそのルーツに回帰し、いい具合にサウダージしている。
いっぽうのベベウ・ジルベルトは、あのジョアンとミウシャの娘という、云ってみればボサノヴァ界のサラブレッド。本作で彼女はさらに、シンガーソングライター、ギタリスト、パーカッショニストのヴィニシウス・カントゥアリアとのデュオ(NY在住コンビ)で、マルコス・ヴァーリの「バトゥーカ」と、ジョビン、メンドンサ、モライスの「ワン・ノート・サンバ〜イパネマの娘」を歌っている。この新録の2曲をシンプルなサンバにアレンジしたカントゥアリアは、過去にリンゼイともコラボしており、その点で本作には、ニューヨーク=ブラジルのVIPが集結した感がある。新録はあと1曲、ジャズ・ギタリストのジョシュ・ゼインツと、“ブラジルのジャコ・パストリアス”の異名をとるベーシスト、セルジオ・ブランドンによる「スイターズ」が収録されている。ヴァイブ、フルート、トロンボーンの音色が爽やかなインスト・ボッサだ。

つづいて、既存の名曲──。ジョルジ・ベンの代表曲「マシュ・ケ・ナダ」は、作編曲家でありキーボーディストでもあるルイス・エサが率いるタンバ・トリオのセカンド・アルバム『アヴァンソ』(1963年)から。当時、NIKEのCMで使用され、日本でも人気を博した。クールな「ステイ」は、アストラッド・ジルベルトの『ビーチ・サンバ』(1967年)から。洗練されたサウンドは、ドン・セベスキーのアレンジ。ジョビンの「トリスチ」は、エリス・レジーナのジョビンとの共演盤『ばらに降る雨』(1974年)から。ただし、この曲にジョビンは不参加で、レジーナの抑揚に富んだチャーミングな歌声を楽しむのみ。当時ロンドンのクラブで御用達だった「クリケッツ・シング・フォー・アナ・マリア」は、マルコス・ヴァーリのアメリカ・デビュー盤『ブラジリアンス!』(1967年)から。キャッチーなアレンジは、エウミール・デオダートによる。
ジョビンの「コルコバード」は、USAのボサノヴァ・ブームに火をつけた名盤『ゲッツ/ジルベルト』(1964年)から。アストラッドの英語歌唱、ジョアン・ジルベルトのポルトガル語歌唱、そしてスタン・ゲッツの瀟洒なテナーが、じっくり味わえる。オルガン・プレイが小気味いいサンバ「バイーア」は、ワルター・ワンダレイの『ボサ・ノヴァの追想』(1980年)から。瑞々しいサウンドと心地いいグルーヴは、いつも変わらない。ふたたびエリス・レジーナが情感たっぷりに歌う「ブラジルの水彩画」は、1986年にリリースされた同名タイトルのトゥーツ・シールマンスとのコラボ作から(この曲にシールマンスは不参加)。途中のパーカッシヴなスキャットが、とても楽しい。
作者自身による独特なピアノ演奏が切なくも美しい「デサフィナード」は、アントニオ・カルロス・ジョビンの『イパネマの娘』(1963年)から。透明感と包容力を兼ね備えたオーケストレーションは、もちろんクラウス・オガーマンによる。そして、ジャジーな「鷲鳥のサンバ」は、巨匠コールマン・ホーキンスの『デサフィナード』(1962年)から。ホーキンスのテナーが悠然とブロウし粋なフレーズを繰り出していく──。以上、いかがなものだろう?このコンピレーションとしてのクオリティの高さは、コンテンポラリーな新録音と黄金時代の名演とのスペシャルな出会いによるものではないだろうか。また、そこにはボサノヴァと映画との素晴らしい出会いもある。そして、ひとと映画との出会いも──。こういう出来事もまた、ぼくにとってはサウダージな感覚のものなのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント