愛の予感のジュブナイル──名作映画『時をかける少女』のオリジナル・サウンドトラック盤 を聴いて1983年へタイムリープ!
 Album : 松任谷正隆 / 時をかける少女 オリジナル・サウンドトラック (1983)
Album : 松任谷正隆 / 時をかける少女 オリジナル・サウンドトラック (1983)
Today’s Tune : いつかどこかで…
原田知世──いまはリアルなオーガニック系、昔はごくふつうの女の子?
ヒンシュクを買うかもしれないが、ぼくのようにヘルス・リテラシーの低い人間にとって、オーガニックをちらつかせているひとは、ちょっと苦手な存在だ。環境や健康について一席ぶたれたりすると、自分のライフスタイルについて深く考えたりすることもなく、ただなんとなく毎日を過ごしているようなぼくは、すぐに拒否反応を起こしてしまう。特にそのひとが女性だったとき、ちょっと近寄りがたいものを覚えることが多い。そういう場合そのひとは、自身の身体をちゃんとケアしながら生活しているだけあって、たいてい美人で綺麗な女性だったりする。それだけに、ぼくは自分とはかけ離れた人物と思い込んでしまうのだろうな。だから、せっかく気遣いをいただいても、なんだか高所からものを云われているような気がしてしまうのである。
ひたすら無農薬野菜を食べて、常にオーガニックコットンを使用した服を着る──そんな生活、ぼくには到底無理である。ぼくにとってナチュラルとは無意識であることで、ナチュラルを強く意識するのは逆にアンナチュラルなこと。ぼくにとって常にオーガニックであることを意識して生活を送るのは、却ってカラダに悪そうだ。これは飽くまで勝手なイメージだけれど、女優の石田ゆり子や長谷川京子には、オーガニックがちらつく。なんか恋愛よりも、自分磨きのほうに興味がありそうに見える。おふたりともすごく見目麗しいけれどそんな印象から、ぼくにとってはいささか扱いにくいアクトレスとなっている(ごめんなさい)。そしてまたひとり、ぼくはここ20年くらい、女優でシンガーの原田知世にもおなじような感触を得ている。
ぼくはいま、ここ20年くらいと云ったけれど、昔の原田知世には少しもオーガニックがちらついていなかった。未加工の野菜や果実を好んだかもしれないが、ファストフードだって美味しそうに食べそうな感じだった。あたりまえのことだが、14歳にして芸能界入りを果たしたころの原田さんは、面差しにまだまだあどけなさを残す、どこにでもいそうなごくふつうの女の子だった。ぼくが通っていた高校にも、後輩に原田さんによく似た女の子がいたな。ただそれは容姿が似ているというだけで、彼女には申し訳ないが、その雰囲気に原田さんが発する神気のようなものはなかった。当時の原田知世は、どこの学校でもクラスにひとりはいそうというアクチュアリティと、実はどこにも存在しないというヴァーチュアリティを同時に抱えた希少な女優だったのである。
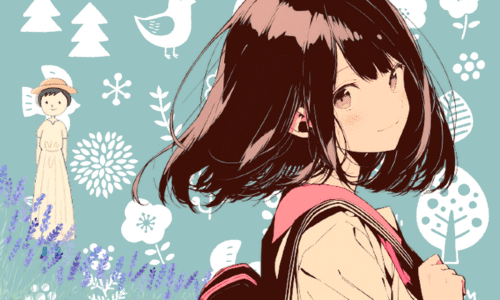
いまではすっかりリアルなオーガニック系のひとになってしまったけれど、ティーンエイジャーの原田知世は間違いなく神聖で清廉な光輝を放っていた。その独特のキャラクターは、音楽や映像の世界に入り込んだとき、蠱惑的なまでに増幅される。いまはもちろん当時も、ぼくは原田さんの熱烈なファンというわけではなかったけれど、同世代のひととしてとてもチャーミングに感じられたもの。原田さんは、デビュー直後からテレビドラマで可愛らしいヒロインを演じていたが、確固たる存在感を放ったのはなんといっても、1983年のスクリーン・デビュー作『時をかける少女』だろう。実はつい先日、ぼくは定額制動画配信サービスを利用して、久々にこの映画を鑑賞した。そしてあらためて、そのことを確信したのである。
映画『時をかける少女』は、1983年7月16日に公開された角川映画。夏休みのロードショー作品として、大学受験のため女優業を休止していた薬師丸ひろ子の復帰第1作『探偵物語』と二本立てで上映された。ぼくの記憶では、ボブヘアの女子大生という華麗なる変身を遂げた薬師丸さんと、このころ演技力が高く評価されていた人気俳優の松田優作との共演ということで、どちらかといえば『探偵物語』が大きな話題になっていたように思われる。一般的には飽くまで薬師丸さんの主演作がメインディッシュで、公開まえの『時をかける少女』といえば、そのサイドメニューのような扱いかたをされていた。思えば、ぼくがロードショーに足を運んだのは、薬師丸さんのファンだった友人に誘われてのことだった。
当時の原田知世といえば、薬師丸ひろ子の妹分という印象が強く、まだまだ存在感が薄かったと記憶する。原田さんの芸能界デビューのキッカケは、映画『伊賀忍法帖』(1982年)のヒロインを一般公募した“角川映画大型新人女優コンテスト”において、特別賞に選ばれたこと。しかし、この映画に原田さんは出演していない。グランプリに輝き当時の人気若手俳優、真田広之の相手役を手に入れたのは渡辺典子だった。なお、薬師丸ひろ子、渡辺典子、原田知世は、のちに“角川三人娘”と呼ばれるようになる。彼女たちは、1980年代の角川映画の看板女優として、一躍トップアイドルとなる。そのいっぽうで、必ず主演映画の主題歌を歌い、レコードをリリースし、さらにはテレビの歌謡番組にも出演することもあった。
ところで、原田さんは角川のコンテストのすぐあとに、フジテレビ系ドラマ『セーラー服と機関銃』(1982年)において、女優デビューを果たしている。同時に主題歌「悲しいくらいほんとの話」を歌い、歌手としてもデビューしている。さらに、その後続番組『ねらわれた学園』(1982年)でも主演女優を務める。主題歌「ときめきのアクシデント」も歌った。ふたつの主題歌はともに、作詞を来生えつこ、作曲を来生たかお、編曲を星勝といったトリオが手がけている。お気づきのことと思うが、これらのドラマは薬師丸ひろ子の主演映画のテレビドラマ版と云える。また主題歌を担当したトリオも、薬師丸さんの1981年の大ヒット曲「セーラー服と機関銃」のライターたちである。このとおり、原田さんは当初、薬師丸さんの妹分のような売り出しかたをされたのである。
大林宣彦──文化功労者だが昔は必ずなにかやらかしてくれる映画監督
結局のところ、プロデューサーである角川春樹の慧眼だけが、当初から原田さんの魅力を見抜いていたということになる。なぜなら、原田さんが圧倒的なカリスマ性を発揮したのは、星泉のときでもなく楠本和美のときでもなく、やはり芳山和子のときだからである。いや待てよ、上記の原田さんのテレビドラマ出演は、演技に関してまったくの素人だった彼女のために角川さんが用意した、ある種のウォーミングアップだったのかもしれない。だがその結果、期待したほど脚光を浴びることのなかった原田さんを憐れむ気持ちから、角川さんはついにポケットマネーを投じて、彼女のキャラクターを主軸に据えた映画を制作する。一時は原田さんを引退させようとも考えた角川さんは、その記念となるような作品を彼女にプレゼントしたかったのだという。
そもそも件のコンテストのときから原田さんに目をかけていた角川さん、その親心のような愛情の深さが、結果的にどこにでもいそうなごくふつうの女の子の魅力を最大限に引出したとも云える。公開まえはほとんど期待を寄せられることもなかった映画『時をかける少女』は、いざフタを開けてみると同時上映の『探偵物語』より、はるかに多くの映画ファンから支持されることとなった。原作は筒井康隆の同名のジュブナイルSF小説。メガホンをとったのは、2019年度の文化功労者に選ばれた大林宣彦(1938年1月9日 – 2020年4月10日)である。大林監督といえば広島県尾道市の出身であることが有名だが、この映画のロケの多くは尾道市で行われている。そのため『時をかける少女』は、あとに『転校生』(1982年)『さびしんぼう』(1985年)といった大林作品とあわせて“尾道三部作”と呼ばれるようになる。
正直なところ、ぼくはにとって『時をかける少女』に至るまでの大林作品には、あまり惹かれるところがなかった。映像的に面白いことをやっているのはよくわかるのだけれど、たとえば音楽でいうところの、タイム感、リズム感、あるいはグルーヴ感のようなものが、ぼくの感性とまったく合わないのである。カルト的な人気を誇る『HOUSE ハウス』(1977年)をはじめ『瞳の中の訪問者』(1977年)『金田一耕助の冒険』(1979年)『ねらわれた学園』(1981年)といった作品は、まったく受けつけなかった。自主製作映画の先駆者でありCMディレクターの経験もある大林さんを、当時は映像の魔術師、映画界の革命児と観る向きもあったが、ぼくにはちょっと独善的過ぎると感じられた。あちらが笑わそうとしているところで、こちらはぜんぜん笑えなかったりするのだ。
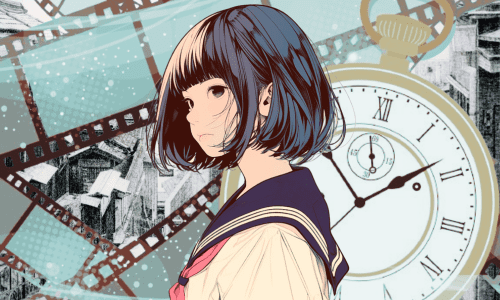
大林監督は、失礼とは思うけれど、ぼくにとっては必ずなにかやらかしてくれるひと。その作品は、なぜかぼくが愛着を抱く著書が原作となっている場合がままあるのだが、それらに対する監督のマナーが甚だ不条理な対応と思われるのだ。たとえば『瞳の中の訪問者』は、手塚治虫の漫画「春一番」が映像化されたものだが、ブラック・ジャックにしてもピノコにしても、はたまたヒョウタンツギにしても扱いが酷い。ふざけているのかと憤りを覚えるようなシーンもある。アニメだったら許されるのかもしれないが、これは実写映画。漫画は漫画、映画は映画。手塚さんは深刻で粛然としたストーリーのなかにときおりコメディリリーフを差し挟むが、それが成立するのは漫画の世界においてのみである。
また、角川映画でもある『金田一耕助の冒険』は、云うわずと知れた横溝正史の短編小説「瞳の中の女」が下敷きにされている。原作小説では事件が完全に解決しないまま物語が幕を閉じるのだが、映画ではその真相を解明し結末を示すというのが基本的なプロットとされている。その点、なかなか面白いアイディアと、ぼくも映画が公開されるまでは思ったもの。しかしながら結局、この映画は単なるパロディ映画だった。しかも横溝さんの小説とはなんの関係もない当時のCMの作り替えや流行語が嫌というほど盛り込まれていて、いま観るとなんのことやらさっぱりわからない。パロディがパロディにならないから、ただの悪ふざけにしか思えない。せっかくテレビドラマにおいて金田一役で人気を博した古谷一行が主演を務めているのに、なんとももったいない。
さらに言及すれば、やはり角川映画の『ねらわれた学園』は、眉村卓のジュブナイルSF小説が原作。眉村さんの小説は、ぼくも中学時代に何冊か読んだが、その著作は当時、学校の図書館にたくさん所蔵されていて、生徒たちがわれさきにと貸し出しを希望するほどの人気アイテムだった。眉村さんがときのひととなったのは、NHK総合テレビジョンで放送された『少年ドラマシリーズ』(1972年1月1日 – 1983年10月11日)からの影響が大きいと思う。この小中学生向けのテレビドラマシリーズでは『まぼろしのペンフレンド』(1974年4月15日 – 5月1日)『なぞの転校生』(1975年11月17日 – 12月3日)『ねらわれた学園』と『地獄の才能』とがミックスされた『未来からの挑戦』(1977年1月10日 – 2月11日)など、眉村作品がいくつか採り上げられたが、みんなワクワクドキドキしながら観ていたもの。
そんなその時代を小中学生として生きたひとにとっては、青春のモニュメントともいうべき眉村さんのSF小説を、大林監督は見事にぶち壊してくれた。写真のコマ撮り、合成カットといった大林作品ならではの撮影および編集上のテクニックにおいては、従来以上にやりたい放題。百歩譲ってそれらを斬新な映像手法と捉えたとしても、原作小説に親しんでいたぼくにとって、大林版『ねらわれた学園』はコマーシャリズムが見え見えの単なるアイドル映画でしかなかった。ただ、松任谷由実の作詞、作曲、そして歌唱による「守ってあげたい」が流れるオープニングのタイトル・シークェンスだけは、素晴らしい。ここは、すごく好きなのだ。この流れに沿って本編のほうも制作されていれば、ひょっとするとこの映画、名作として世に残ったかもしれない。
松任谷正隆──楽曲のよさを際立たせることに徹する名引き立て役
そんななか、もういいかげん大林作品を観る意味や価値を見出すことについて、匙を投げそうになっていたとき、ぼくの監督への評価が一気にコペルニクス的転回を見せることになる。それは、前述の“尾道三部作”のひとつである『転校生』を観たときのこと。それは文字どおり、やんちゃでクラスの人気者的な中学生の男の子と、突然彼のまえに現れた成績優秀な転校生の女の子との身体が入れ替わってしまうという、コミカルだけれどちょっぴり胸がしめつけられるような切なさを残す青春映画。この映画で監督は、お得意の才気の奔出ともいうべき映像テクニックをほとんど使っておらず、自身の出身地である尾道市を舞台にひたすら自らの郷愁を込めることに集中している。その文学的ともいうべき情趣溢れる映像世界は、ロベルト・シューマンの「トロイメライ」とともに、ぼくのこころにも深く刻まれた。
大林監督が映画作家としてひとつの頂点を築いた『転校生』につづく作品が、監督にとって3本目の角川映画『時をかける少女』である。そう、三度目の正直というが、映画は期待以上の出来映えとなった。原田知世演じる主人公がラベンダーの香りを嗅ぐとタイムリープする(タイムトラヴェルとテレポーテーションを同時に行う)というSFものだが、SFのエッセンスは極力抑えられている。本作では、思春期の男女の“時の壁”による成就することのない恋模様に焦点が合わせられている。形而上学的体験により、少女の恋愛感情が理想と現実のはざまで迷子になるといところには、純文学の香りすら漂う。さらに、ふたたび尾道市でロケが行われているが、海浜部での撮影は敢えて避けられたようだ。そのせいか尾道でありながら、明るいイメージの尾道にはない幻想的な翳りが生み出されている。結果的にこの映画は、得も云われぬ静謐さと詩情を湛えることとなった。
このありそうでない架空の地方都市の町並みに加え、コンサヴァティヴな学生服、原田さんの素足に履く下駄、高柳良一の羽織るインヴァネスといった、古典的なアイテムが作品に散りばめられているが、そういった意匠が非日常的な空気を作り出している(残念ながら原田さんのブルマー姿だけは時代性を感じさせる)。さらに学生たちは、古めかしいほど丁寧な言葉遣いと棒読みのような喋りかたをしたりもする。作家の林真理子がプロデューサーの角川さんに「当時、あんな女子高生はいなかった」と苦言を呈したそうだが、なにを観ているのだろう。どこにもない町、どこにもいない若者たちが描かれていることこそが、作品の普遍性に繋がっているのである。それに、もともと古めかしいものは、時代が変わっても古くならなかったりする。映画『時をかける少女』がときを経ても色褪せることを知らないのは、そんな理由からではないだろうか。

実は『時をかける少女』はこの映画化以前に、前述のNHK『少年ドラマシリーズ』の第1作『タイム・トラベラー』(1972年1月1日 – 1972年2月5日)として、映像化されている(オリジナルの続編もある)。ぼくもリアルタイムで楽しんだが、大林監督による映画版のほうがはるかに傑出している。そもそも比べること自体、ナンセンスと云えるのかも──。なにしろ、あちらはSF、こちらはラヴ・ストーリーなのだから。大林監督も映画の後半で、またぞろ独自の特殊効果テクニックを発揮するが、それ以外は実に抑制の効いた演出をキープしている。原田さんの演技も、ストイックなまでに華やかさはなく控え目だ。原作にはない11年後の切ないエピソードも気が利いている。映画『時をかける少女』は、いたずらにアイドル映画と化した『ねらわれた学園』とは真逆の、極めて文学性の高い作品なのである。
そして、この映画をさらなる高みに登らせたのは、音楽である。スコアを手がけたのは、日本を代表するアレンジャー、松任谷正隆。云うまでもなく、シンガーソングライター、松任谷由実の公私にわたるパートナー。もちろん、松任谷さんはキーボーディスト、コンポーザー、音楽プロデューサーとしても腕を振るっているのだが、もっともその本領が発揮されているのは編曲において──と、ぼくは感じる。だから敢えてアレンジャーと記した。ぼくが松任谷さんから受ける印象といえば、名引き立て役のひとことに尽きる。編曲においては自分の存在証明は二の次で、常に楽曲のよさを際立たせることに徹している。キーボード・ワークにしても、バッキングの神髄を究めるような風情がある。
松任谷さんの作品といえば、ティン・パン・アレーの『キャラメル・ママ』(1975年)と『TIN PAN ALLEY 2』(1977年)、それに唯一のリーダー作『夜の旅人』(1977年)が、長い間ぼくの愛聴盤となっている。特に「HONG KONG NIGHT SIGHT」はぼくにとって、作編曲、演奏、そして歌唱(!)において、松任谷さんの作品のなかでもっとも好きな曲となっている。ただ松任谷さんは自分がまえに出ることを好まないひとなので、そのサウンドをさらに楽しむにはアレンジャーやバック・ミュージシャンとして参加したアルバムを入手するしかない。個人的好みでは、やはりユーミンさんの『14番目の月』(1976年)や『昨晩お会いしましょう』(1981年)あたりをおすすめする。映像作品はあまり手がけていないが、このサントラ盤『時をかける少女』がベストである。
大林監督は作品のイメージを伝えるために松任谷さんに、アメリカのSF恋愛映画『ある日どこかで』(1980年)を観ることを勧めたとのこと。参考となったジョン・バリーの音楽の影響からか、松任谷さんのスコアはストリングスのアンサンブルを前面に出したクラシカルなサウンドでまとめられている。なおサントラ盤では、楽曲に俳優のセリフやSEが重なる箇所がある。映画全体のシノプシスやムードを伝えるオーヴァーチュア風の「星くずとわたし」モティーフ・ディベロップメントがミシェル・ルグラン風のメイン・タイトル「時の子守唄」ミステリアスな「ラベンダーの謎」弦による重奏がさらに謎めいたムードを醸し出す「9:87」ヴァイオリンのソロからロマンティックに展開されていく「ふれあい」オーボエのソロから麗しいストリングスへとハートウォーミングに進行する「タイム・トラベラー」と、まるでオペラのような構成となっている。
後半はさらに、重厚で禍々しい雰囲気から感傷的なテーマへと移行する「歪んだ時間」平田穂生の作詞、大林宣彦の作曲による、原田さんと高柳さんとのデュエット「愛のためいき」後半のタイムリープのシーンで使用された、楽曲中もっともドラマティックでゴージャスにオケが鳴る「走りくる夢」静かで安らかなシークェンスからさらっと温もりのあるメイン・テーマへとつながる「いつかどこかで…」と、松任谷さんのスコアは一糸乱れず穏やかで上品に映像をバックアップする。もちろん、原田さんが歌った大ヒット曲「時をかける少女」も収録されている。映画のエンドロールでは、実験室で倒れていた原田さんが起き上がり、NGを含めた名場面を巡りながら、この曲を歌っていく。この唯一アイドル映画のような演出には、芳山和子が原田知世に戻るというニュアンスが感じられる。大林監督の愛のこもった粋な計らいである。未見のかたは、ぜひご確認あれ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント