5拍子のグルーヴ感が際立つ不滅のテーマ曲をはじめ、ラロ・シフリンの鋭いセンスが光る楽曲が収録された『スパイ大作戦 Vol. 1(Music From Mission: Impossible)』
 Album : Lalo Schifrin / Music From Mission: Impossible (1967)
Album : Lalo Schifrin / Music From Mission: Impossible (1967)
Today’s Tune : Mission: Impossible
ポピュラー・ミュージックにおいて5拍子の繁栄に寄与した曲
5拍子の曲というと、多くのひとがすぐに思い浮かべるのは、デイヴ・ブルーベック・クァルテットの「テイク・ファイヴ」ではないだろうか。同グループの最大のヒット曲だけれど、アルバム『タイム・アウト』(1959年)の3曲目に収録されている。アルバム・リリースからおよそ1年と5か月後(1961年)にはシングルカットされ、ポップ・チャートを賑わせてミリオン・セラーを記録した。日本ではもともとジャズ喫茶の定番曲だったが、1987年に武田薬品(現アリナミン製薬)の栄養ドリンク剤、アリナミンV-DRINKのテレビCMで使用され、ジャズを聴かないひとたちにも周知されるようになった。作曲したのはバンド・メンバーのアルト奏者、ポール・デスモンドだけれど、ブルーベックが起案するところもあったのではないだろうか。
ブルーベックは甚だクラシック音楽の影響を受けたジャズ・ピアニストで、この『タイム・アウト』をあらためて聴いてみるとかなりクラシカルな音楽に感じられる。たとえばぼくの大好きなモーリス・ラヴェルが、バレエ音楽「ダフニスとクロエ」の第2組曲の終盤でメイン・リズムを5拍子としている。つまりブルーベックはジャズに、そういった芸術音楽における舞曲のスタイルをもち込んでいるように思われるのだ。その点ではむしろ『タイム・アウト』の冒頭を飾る「トルコ風ブルー・ロンド」のほうが、その趣向が顕著に現れている。このブルーベックのオリジナルは8分の9拍子で演奏されるのだけれど、伝統的なトルコ民謡のリズムを西洋音楽的な解釈で打ち出している。こういうマナーは、もはやジャズではない。
そういえばテナー奏者のジョシュア・レッドマンが、リーダー作『ビヨンド』(2000年)のなかで真っ向から拍子というものに取り組んでいる。やはり5拍子の「ア・ライフ」という曲が収録されているのだけれど、これがなんとも軽やかで美しい曲なのだ。クァルテットの各々が互いに触発されながら、シンプルなメロディック・ラインとそれにインスパイアされたインプロヴィゼーションを展開していく。ノスタルジックなバラード風のナンバーだが、この心地よさの一端は明らかに5拍子のグルーヴ感が担っていると思われる。なおこのアルバムでは、6拍子、9拍子、10拍子、13拍子といった複合拍子や変拍子の曲が満載だ。革新性を求めて作られた音楽ではあるがわりと自然に聴けるので、興味のあるかたはどうぞ──。
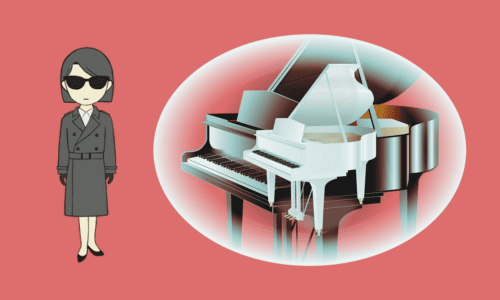
さて、西洋音楽においてスラブ地域の民族音楽から引用されて発展した5拍子は、どこか異国の情緒や雰囲気を醸し出すところがあるが、いまではごく身近な変拍子のひとつとなっているのではないだろうか。そして、ポピュラー・ミュージックにおいてその独特のビート感覚の繁栄に寄与した曲といえば、なんといっても「スパイ大作戦のテーマ」だろう。いまや「ミッション:インポッシブルのテーマ」という呼びかたのほうが、しっくりくるかもしれない。トム・クルーズ演じるCIAの極秘諜報部隊であるIMF(Impossible Mission Force=不可能作戦部隊)のエージェント、イーサン・ハントを主人公としたスパイ・アクション映画のシリーズは、日本でも非常に人気が高い。
この映画シリーズは2025年公開予定の『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』で8作を数える。このシリーズ、4作目までは監督がすべて異なり、順を追って記載すると、ブライアン・デ・パルマ、ジョン・ウー、J. J. エイブラムス、ブラッド・バードとなる。5作目からはクリストファー・マッカリーが継続的にメガホンをとっている。フィルム・スコアのほうも、ダニー・エルフマン、ハンス・ジマー、マイケル・ジアッチーノ(第3作、第4作を担当)、ジョー・クレイマー、ローン・バルフ(第6作以降継続)と、何度か入れ替わっている。不動の地位を確保するのは、シリーズのプロデュースも手がけるトム・クルーズと、あの5拍子のテーマ曲ということになるのだろうね──。
ここでシリーズ全作品の音楽について触れることはできないので、記念すべき第1作『ミッション:インポッシブル』(1996年)のサウンドトラックについてのみ述べておく。この映画はCBSのテレビシリーズ『スパイ大作戦』(1966年 – 1973年)をベースにしているわけだが、もともとテレビ版がたいへんな人気番組だったため、映画版のスコアはオリジナルをオマージュせざるを得なかった。まずテーマ曲だが、アイルランドのロック・バンド、U2のドラマーのラリー・マレン・ジュニア、ベーシストのアダム・クレイトンがリメイクしている。原曲をサンプリングしたブレイクビーツのスタイルがとられているが、5拍子なのは最初だけですぐにポリメトリック的に単純拍子に移行する。映画ではエンドクレジットで使用された。
全体の音楽を手がけたダニー・エルフマンは、ドラマティックでロマンティックなスコアを書くひとだけれど、彼の音楽は映像とのマッチングがすこぶるいい。そのせいか現在に至るまで数多くの映画作品に、エキサイティングなスコアを提供してきた。ティム・バートン、サム・ライミといった監督とコンビを組むことが多いが、まるでハリウッドの娯楽大作を一手に引き受けているような印象を与える。過去にニュー・ウェイヴ系のバンドで活動していたこともある変り種で、それ故かエルフマンのサウンド・デザインにはいつもユニークな意匠が凝らされていて感心させられる。なお本作の楽曲のアレンジは、エルフマンのバンドでギターを弾いていたスティーヴ・バーテックと、フィルム・オーケストレーターとして有名なマーク・マッケンジーが担当している。
エルフマンのスコアでも「ミッション:インポッシブルのテーマ」は堂々と演奏される。オープニングクレジットで使用されたエルフマンのヴァージョンは1分強と尺は短いが、しっかり原曲どおり5拍子がキープされながら、よりオーケストラルなアレンジが施されたダイナミックなピースとなっている。ほかにも「トラブル」という曲の後半で、このテーマ曲がパラフレーズされたりする。なおテーマ曲以外では、テレビシリーズでお決まりのように毎回流れる「筋書きはこうだ!」という曲があるのだが、エルフマンのスコアでは「インポッシィブル・ミッション」で一部抜粋されている。ちょっとわかりにくいかもしれないが、スネアドラムやパーカッションの動きに注目していただきたい。
鑑賞用音楽としての機能性という点ではテレビ版のほうが数段上
ちなみに、記念すべき映画シリーズ第1作『ミッション:インポッシブル』のサウンドトラック・アルバムは2種類存在する。発売は2枚とも映画が公開された1996年で、日本でも両作ともに国内仕様のCDがリリースされた。1枚は『ミッション:インポッシブル オリジナル・サウンドトラック』で、タイトルはそうなっているが実際はサントラ盤というよりもコンピレーション・アルバムと云える(ややこしい!)。前述のU2のふたりが録り下ろしたテーマ曲や、ビョーク、パルプ、キャスト、マッシヴ・アタックなどの映画未使用曲、エルフマンのスコアの一部が収録されている。映画にインスパイアされて作られたオリジナル曲を中心とした、一種のイメージ・アルバムだ。こちらはU2が立ち上げたマザー・レコードからリリースされた。
もう1枚の『ミッション:インポッシブル オリジナル・スコア・ヴァージョン』は、エルフマンのフィルム・スコアのみで構成されている。本盤は英国のクラシック音楽のレーベル、ポイント・ミュージックからリリースされた。エルフマンにしては飾り気のないスコアだが、躍動的な律動と緊張感を拡大するような管弦楽法はお見事。その壮観な音景はスリリングな映像を的確に盛り上げるものだが、その作法はすでに職人芸の域に達している。ただこのアルバムは、飽くまでフィルムスコアリングに徹せられたトラックをまとめたものだから、独立した音楽作品として楽しむにはいささか辛いものがある。そのサウンドはスタイリッシュでスピーディなのだが、ホットなジャズが軸に据えられたテレビシリーズの音楽のもつ人間くさい魅力には、ちょっと敵わない。
その点、映像作品としての魅力について映画版とテレビ版とを比較したときにも、おなじことが云えるかもしれない。映画ではオープニングクレジットの5拍子のテーマ曲や(導火線にマッチで火を点ける)映像の演出において、テレビシリーズのものが踏襲されているけれど、実質的に両作はまったくのベツモノと捉えるべきなのかもしれない。まあこれは時代性なのだろうが、テレビドラマの見どころが知略縦横、臨機応変の心理戦だったのに対し、映画のそれはどちらかといえばハイテクが駆使されたアクティヴな肉弾戦。いっぽう映画でも自動的に消滅する指令テープの引用はあるけれど、それを聴くミッションのリーダー、ジム・フェルプスのキャラクターはまったく異なるものになっているし──。
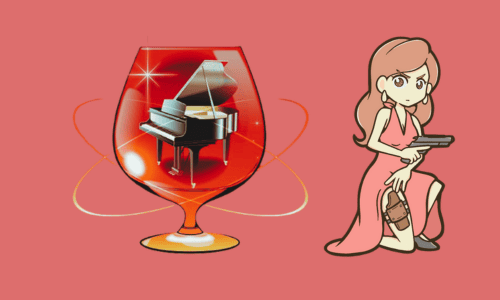
いずれにしても、鑑賞用音楽としての機能性という点では、テレビシリーズのサントラ盤(実質はレコード用の音源)のほうが数段上を行く。というか、個人的にずっと愛着がある。なんといってもテレビシリーズ『スパイ大作戦』は、ぼくにとっては幼少期にあたるが、当時の日本でもお茶の間を賑わす人気番組だったのだから──。アメリカよりおよそ半年遅れだったが、フジテレビ系列で日本語吹替版が断続的に放映されていた。子どものぼくは、両親が熱心に観ている『スパイ大作戦』を、その横で観るともなしに観ていただけだから、エピソードごとの記憶は曖昧である。しかしながら「おはよう、フェルプスくん──」(最初は“ブリッグスくん”だった)ではじまり「なお、このテープは自動的に消滅する。健闘を祈る」で終わる、テープレコーダーから流れる指令の文言はハッキリ覚えている。
そしてそれ以上に、5拍子が生み出す独特のグルーヴ・フィーリングとゾクゾクするようなサウンドスケープをもつ「スパイ大作戦のテーマ」は、幼いぼくにも強烈なインパクトを与えたのである。たぶん父親が購入したものだろうが、わが家にはしっかりサウンドトラックのLP盤があった。ぼくの記憶ではそのLP、ジャケットが赤を基調としIMFのメンバーのポートレートがあしらわれたものだったから、おそらくテレビ放映の開始とともに当時の日本ビクターが発売した国内仕様のレコードと思われる。ぼくは、これをよく聴いていた(というか聴かされていた)。ところがぼくは引っ越しの際、このLPをポール・モーリアのレコードなどと一緒に、つい気前よく近所に住んでいた同級生の女の子に進呈してしまったのだった(もともと自分のものでもないのにね)。
ちょっと後悔していたら、折よく当時のビクター音楽産業が、既発のLPと同一の音源を今度はオリジナル・ジャケット仕様で完全限定復刻してくれた。これはホント、ありがたかった。この『スパイ大作戦 Vol. 1(Music From Mission: Impossible)』は、もともと1967年にドット・レコードがリリースしたもの。オリジナルのジャケットは、地色が赤いのは既発の国内盤とおなじだが、例の導火線に火を点けようとするマッチ棒を摘んだ手が写っているものだ。さらに嬉しいことに本盤の発売からときを移さず、1969年にパラマウント・レコードからリリースされていた続編の『スパイ大作戦 Vol. 2(More Mission: Impossible)』のほうも復刻された。こちらは、本邦初発売だった。
ちなみに上記の2枚のサウンドトラック・アルバムは、前述の映画版第1作『ミッション:インポッシブル』が公開された1996年にMCAレコードから1枚のCDにカップリングされ、装いも新たに『ミッション・インポッシブル(スパイ大作戦)』としてリイシューされた。実は1994年にジャケットは異なるが内容は同一のコンパイルCDがすでにリリースされていたのだが、映画化のタイミングにあわせて、その話題にあやかりながらもオリジナルはこちらと云わんばかりに新装盤が発売されたのである。なお本盤にコンパイラーとしてクレジットされているテリー・ワクスムートは、1960年代から1980年代初頭までのロックやジャズ/フュージョンの名作の復刻で知られるレーベル、ウーンデッド・バード・レコードの設立者だ。
とにもかくにも本CDは、疾走感に富んだ5拍子のテーマ曲からビッグバンド・スタイルを中心としたジャジーな劇伴の数々まで、テレビシリーズ『スパイ大作戦』のスリリングなサウンドを一気に楽しめる仕様なので、音盤を所持していない往年のファンのかたにはもちろんのこと、未体験のかたにもぜひ気軽に手にとっていただきたい1枚である。そんなわけで、例によって長々と語ってしまったが、ここからはぼくにとってもっとも愛着のある『スパイ大作戦 Vol. 1(Music From Mission: Impossible)』についてお伝えしていこうと思う。すっかりあとになったが、5拍子の名曲として燦然と輝く「スパイ大作戦のテーマ」を作曲したのは、だれあろうアルゼンチン出身の作編曲家、ラロ・シフリンである。
ラロ・シフリンという音楽家と『スパイ大作戦』の音楽
1932年6月21日生まれのラロ・シフリンは、ヴァイオリニストの父親の影響で幼いころから音楽に親しんでいたが6歳から6年間、あのピアニストで指揮者のダニエル・バレンボイムのお父さんにピアノの指導を受けていたという。地元のブエノスアイレス大学では社会学と法律を学んでいたが、20歳のときにパリ国立高等音楽院に留学して確固たる音楽教育を受ける。クラシックの音楽理論をみっちり身につけるかたわら、シフリンは当時からジャズにも強い関心を寄せていた。1957年にラロ・シフリン・アンド・ヒズ・オーケストラ名義のイージーリスニング作『スペクトラム』が吹き込まれているが、ジャズ・ピアニストとしてのリーダー・アルバムは、ラテン・タッチの『ピアノ・エスパニョール』(1959年)がデビュー作となる。
またシフリンは、1960年代にディジー・ガレスピー・バンドのアレンジャー兼ピアニストを務めたことはよく知られているが、それを契機にニューヨークへ移住した。その後、彼はヴァーヴ・レコードにおいてリーダー作を吹き込んだり、同レーベルの所属アーティストの作品のアレンジを手がけたりするのだが、まもなくヴァーヴの親会社である映画製作会社MGM(メトロ・ゴールドウィン・メイヤー)で映画やテレビドラマの仕事をするようになる。たとえばMGMが製作したテレビシリーズ『0011ナポレオン・ソロ』(1964年 – 1968年)といえばジェリー・ゴールドスミスが作曲したテーマ曲が有名だけれど、劇伴においてはシフリンがスコアを提供したこともある。なんにせよ結局のところ、シフリンといえば映画音楽の巨匠というイメージが定着した。
そんなシフリンのファンは国内外問わずたくさんいると思われるが、実はぼくにとって彼はちょっと苦手な音楽家だったりする。なぜならシフリンがクリエイトするサウンドはたいへん高品質でありながら、多くの場合強烈なコマーシャリズムを感じさせるからだ。云いかたはわるいが、ひとことで云うと節操がないのである。たとえばハモンド・オルガン奏者、ジミー・スミスの人気盤『ザ・キャット』(1964年)では、アクの強い豪快なオーケストラ・サウンドを炸裂させている。また自己のリーダー作『マルキ・ド・サド』(1966年)では、バロック音楽にジャズ、ロック、リズム・アンド・ブルースなどをいびつに調和させたりしている。その陽気に錯乱したアンサンブルは、まさに無節操と云える。
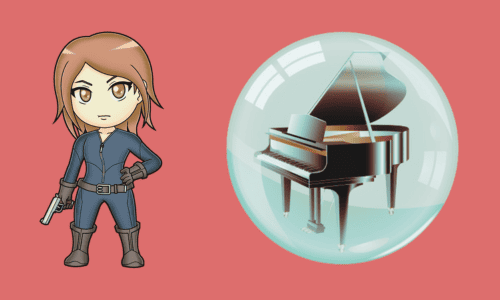
CTIレコードからリリースされた『ブラック・ウィドウ』(1976年)『タワーリング・トッカータ』(1977年)やタブー・レコードで吹き込まれた『ノー・ワン・ホーム』(1979年)といったフュージョン作品においても、シフリンはあからさまにディスコ・サウンドを採り入れたりしてド派手なマナーを全開。もちまえのあざとさを、遺憾なく発揮している。個人的にはCTI作品だったらボブ・ジェームスのアルバムのほうが断然聴き応えがあると思うし、映像作品だったらデイヴ・グルーシンのスコアのほうが味わい深く感じる。ただ、たとえ一貫性に欠けようが逡巡せずにハリウッドで培った商業主義をフルスロットルにするところは、好むと好まざるとに関わらず、稀代のエンターテイナー、ラロ・シフリンの最大の魅力と云えるのかもしれない。
とはいえ『スパイ大作戦 Vol. 1(Music From Mission: Impossible)』は、シフリンが手がけた作品のなかでも鑑賞用音楽として実にバランスのいいアルバムと、ぼくは思う。本作では、いつものようにケバケバしいシフリン・サウンドが爆発することもあるけれど、そんな独特の世界とはひと味違う彼の鋭いセンスが光る瞬間が垣間見えることも多々あるのだ。そういう点で本作は数多のシフリン作品において、スティーヴ・マックイーン主演のアクション映画『ブリット』(1968年)のサウンドトラック・アルバムに次いで、ぼくの愛聴盤となっている。では、各曲(曲名は1979年に限定発売されたビクター盤に則る)について観ていこう。なお全11曲中1曲のみ、マーベル作品で知られる作曲家ジャック・アーボントとプロデューサーのブルース・ゲラーとの共作である。
オープナーはもちろん「スパイ大作戦のテーマ」である。ピアノの低音部が5拍子の鼓動を響かせる緊張感のあるイントロ、フルートによるエキゾティックなテーマ、エレクトリック・ハープシコードによるブルース進行のアドリブ・ソロ、そしてストリングスを絡めたダイナミックなビッグバンド・サウンドと、どこをとっても文句のつけようがない。つづく「ジムは行動中」は、中南米のリズムからジャズ・ロックへ移行するキャッチーなナンバー。アルト・フルートとミュート・トランペットによるエスプリの効いたテーマ部とブラス・セクションによる華美なコーラス部とのコントラストが鮮やかだ。マイク・メルヴォインによるファンキーなピアノ・ソロも、なかなかのもの。逆に「チャーム作戦」では、ゆったりしたボサノヴァのリズムに乗って、シフリン自身が印象的なピアノ演奏を披露。流麗なストリングスのアレンジも見事だ。
ボンゴの連打がスリリングなムードを高める「狙撃者に気をつけろ」では、ストリングスによるヒンドゥスターニー調のメロディ、シタールとハープシコードとの絡みがいかにもな感じだ。つづく「ローリン・ハンド」では、スウィートなソロ・ピアノから煌びやかなオーケストラによるジャズ・ワルツへと展開。ストリングスが眩いばかりの動きを見せるが、乱脈を極めることもなく心地好く響く。前述の「筋書きはこうだ!」では、マーチングバンド風の演奏のなかでエレクトリック・ハープシコードがロック・ビートを刻んでいるのがユニークだ。B面1曲目の「でっかいウィリー」は、もっともダンサブルなナンバー。シンコペーテッドな8ビートのリズムに乗って、ビッグバンドが軽快に揺れ動く。
アーボントとゲラーによる「シナモン(レディは愛されるためにつくられた)」は、ドリーミーな三拍子。トロンボーン、ウッドウィンズ、ストリングスが甘美なイメージを描いていく。バド・シャンクのアルトも極甘口。クールな4ビート「バーニーは任務完了」では、シフリン、シャンクに加えて、ステュ・ウィリアムソンがミュート・トランペットでソロをとる。メランコリックなムードの「危険」では、異国情緒漂うメロディック・ラインとルンバ調のリズムがヘンリー・マンシーニの楽曲を彷彿させる。ラストの「スパイ大作戦/作戦完了」では、ファンキーなジャズ・ロックが全開。当時のポップカルチャーを大胆にサウンドに反映させるところは、いかにもシフリンらしい。テーマ曲のモティーフも、顔を覗かせる。いずれにせよ本盤は、シフリンならではのエンターテインメントに富んだ、しかもグッドバランスなアルバムである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント