横倉裕の名曲「サマー・ウィズアウト・ユー」を収録したL. A. トランジットのアルバム『ジ・ノヴォ』とは──
 Album : L. A. Transit / De Novo (1986)
Album : L. A. Transit / De Novo (1986)
Today’s Tune : Summer Without You
どうしても忘れられない曲「サマー・ウィズアウト・ユー」
先日、自宅で夕食の支度をしていたら、何年もご無沙汰していた親友のNくんから、突然の電話をもらった。彼曰く、ボブ・ジェームスの『オブセッション』(1986年)というアルバムを聴いていたら、にわかに学生時代にぼくと過ごした楽しい時間が思い出されたとのこと。まったく嬉しいことを云ってくれる。ぼくはこれでも記憶力がいいほうだから、ああ、あのときにはこんなことがあったね──と、すぐさまハナシに花を咲かせる。長いあいだ連絡をとっていなくても、まるで昨日会っていたかのように淀みなく会話はすすんだ。親友とは、そういうものだ。積もるハナシは尽きないのだが、ぼくのほうが火を使っていたものだから、早々に通話を終了した。年末にささやかな忘年会を開くことを約束して──。
ところでNくんと過ごした1986年といえば、彼が挙げたジェームスのアルバムに収録されている叙情的な「レイン」が思い出されるのだが、それ以外にもどうしても忘れられない曲がある。それは「サマー・ウィズアウト・ユー」という曲。スローなボサノヴァのリズム、美しいコード進行、ノスタルジックなメロディック・ライン、そしてなんとも感傷的な歌詞が、ぼくたちのこころを揺さぶったのだ。夏を想い、二度と戻らないひとの瞳の輝きを思い出し、ふたりが分かち合った時間をどうしても追想してしまう──そんなサウダージ感覚が横溢するハートブレイク・ソング。知るひとぞ知る、奇跡的な名曲である。もしも、この曲をご存知ならば、きっとあなたは音楽を深く愛するかたなのだろう。ぼくは、そう信じる。
では、あなたはこの曲をどこで聴いたのだろう?ひょっとして、藤田朋子のファースト・アルバム『ザ・ウーマン・イン・ミー』(1989年)だろうか?藤田さんは女優が本業なのだろうけれど、玉川大学文学部外国語学科を卒業しており英語に堪能。そしてポール・マッカートニーのファンだったこともあり、自らがヴォーカルを務めるバンドを組みライヴ活動を積極的に行った。そんな彼女がロサンゼルスで現地のミュージシャンたちとレコーディングしたのが、このアルバムだ。彼女は全曲英語で歌っているが、自分が敬愛するビートルズの「アイ・ウィル」もしっかりカヴァーしている。ときにこのアルバムに、件の「サマー・ウィズアウト・ユー」が収録されている。

このヴァージョンの心地いいリズムのドラム&パーカッションは、プログラミングによるもの。しかしながら、当時、西海岸の人気フュージョン・グループ、ウィッシュフル・シンキングのメンバーだったジェリー・ワッツ(b)と、リオからロスに移りブラジリアンはもとよりフュージョンにも欠かすことのできないオスカー・カストロ・ネヴィス(g)とが、かたやボトムを支え、かたやリズムとハーモニーに彩りを添えている。バックグラウンド・ヴォーカリストのひとりに、ケイト・マーコウィッツのクレジットがある。ぼくは以前から彼女のことを、ドン・グルーシン(key)のアルバムや“セルメン”ことセルジオ・メンデス(key)のコンサートなどで知っていたが、そのどこか可憐で透きとおるような声が大好きだった。
そしてここで、マーコウィッツとともに独特なソフト・タッチの歌声を披露しているのは、あの横倉裕だ。敢えて“あの”とつけたが、それにはワケがある。横倉さんは際立って個性的なサウンドを創造し、誰にも代役を務めることができない、世界にただひとりの音楽家。そのアイデンティティの明確さ、キャリアの長さは相当なものだ。それにもかかわらず、彼はいまもって知るひとぞ知る存在。それでもぼくにとっては、絶対に目を離すことのできない人物。おそらく、その唯一無二の音楽にこころを奪われたかたならば、ぼくとおなじように感じるのではないだろうか。そんな思いからぼくは、甚だ恐縮だが敬意を払う意味も込めて、横倉さんに“あの”とつけさせていただいた。
云い忘れたが、藤田さんのヴァージョンで横倉さんは、バックグラウンド・ヴォーカルのほか、キーボードとプログラミングも担当している。アルバム・プロデュースも、彼が手がけている。ついでに云うと藤田さんのセカンド・アルバム『カラーズ・オブ・ラヴ』(1990)でも、横倉さんは2曲のサウンド・プロデュースとアレンジを受けもっている。20歳でプロデビュー、大学を中退し単身渡米、そして現在も活動の拠点をロサンゼルスに構える横倉さんが、日本のアーティストの作品を手がけるのは珍しい。藤田さんのアルバムのほかに彼が直接関わった作品といえば、同時期に制作された河合奈保子の『コーリング・ユー…呼びよせられて…』(1989年)くらいしか思いつかない。なおこの作品においては2曲で、一聴で横倉さんのそれとわかるアレンジとキーボードワークが全開している。
ブラジル ’66をオマージュするL. A. トランジット
それはさておき「サマー・ウィズアウト・ユー」についてだが、藤田さんのヴァージョンが世に出てから10余年ののち、新たなカヴァーが生まれる。しかも、西太平洋に浮かぶ東南アジアの国で──。それは、フィリピンのシンガー、チャド・ボルハのセカンド・アルバム『ショウ・ミー・ザ・ウェイ』(2000年)に収録されている。おなじくフィリピン生まれの歌姫、クー・レデスマとデュエットしている。ちなみに彼女は、1982年に日本で「夏物語(One Day Soon)」というシングル盤をリリースしたこともある。松任谷由実の楽曲「夕涼み」をカヴァー(というかほぼ同時リリース)、英語詞で歌ったものだ。いっぽうメインのボルハはAOR系のシンガーで、ソフトな声質がちょっと横倉さんに似ている。ボルハのほうがやや躍然としているが、それが爽やかさを生んでいる。
この『ショウ・ミー・ザ・ウェイ』は、ワーナーミュージック・フィリピンからのリリースということで、発売当時も日本のマーケットではほとんど見かけなかったが、音楽ツウの間では大きな話題となった。全面的に横倉さんがプロデュースとアレンジを手がけていたり、当時人気だった女性シンガー、ケヴィン・レトーがゲスト参加していることもあり、まさに横倉裕の音世界が繰り広げられている。ぼくとしても多くのかたに聴いていただきたいので、本盤がたとえばいま流行りのシティ・ポップとして再評価され、国内でもリリースされることを祈るばかりだ。なおボルハは本作をリリースしたあと闘病生活を送ることになるが、カムバック後にふたたび横倉さんのプロデュースで『イカウ・ラン・サ・ハバン・ブハイ』(2013年)をリリースした。こちらも素晴らしい。
横道に逸れるのはこれくらいにして、1986年にぼくとNくんがともにこころを奪われ、30年以上経ったいまでも愛聴しつづける「サマー・ウィズアウト・ユー」について核心に迫ろう。すっかりあとになってしまったが、この魅力的な曲を書いたのは横倉裕、歌詞をつけたのはラニ・ホールだ。ホールはハーブ・アルパートの奥さま。アルパートはトランペッターであると同時にA&Mレコードの創始者でもある。A&Mのドル箱スターといえば、すぐに思い出されるのはセルジオ・メンデス&ブラジル ’66。ブラジル ’66のリード・ヴォーカリストを務めたのは、ホール。1970年にホールと入れ替わりでグループに加入したのは、グラシーニャ・レポラーセ。そしてレポラーセはセルメンの奥さまだ。セルメンは横倉さんの渡米のきっかけを作ったひと。そして横倉さんは、のちにセルメンのツアー・メンバーとなるのである。
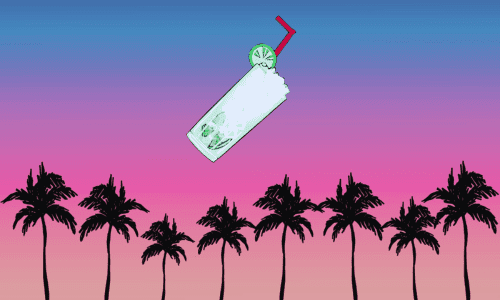
いかがだろう、この素敵なつながり──。ぼくにとっては、名前を見ただけで胸を高鳴らせてしまうアーティストばかりなのだが──。見てのとおり、これはセルメンを中心として築かれた関係だが、このファミリー的な結びつきから生まれたアルバムがある。L. A. トランジットの『ジ・ノヴォ』(1986年)が、まさにそれだ。日本コロムビアのジャズ専門のサブレーベル、インターフェイスからリリースされた。世界初の実用型デジタル録音機を開発した同社ならではの、PCMデジタル・レコーディングが採用されている。そう、本作は日本で制作されたアルバムである。グループ名というかプロジェクト名のL. A. トランジットは、ロサンゼルスの名うてのミュージシャンたちによるリゾート感覚が溢れる音楽──というセールスポイントをアピールした命名と思われる。
思い起こせば、1980年代に日本で制作された海外アーティストのフュージョン系の作品には、グループ名にやたらと“L. A.”が冠されていた。おそらく一流のミュージシャンによる爽やかな音楽──というデザインコンセプトからの着想だろう。本作においてもレコードのタスキにある「シティ・リゾートへ誘う」というセールスコピーが目にとまるが、いまさら気することもないだろう。本作の実態は、セルジオ・メンデス&ブラジル ’66に対するオマージュ作品。つまり、ブラジル産のアーシーな楽曲をポップなボサロックにアレンジするいっぽうで、逆に英米のポップ・チューンをボサノヴァ風にカヴァーするという、音楽に対して実に懐の深いセルメン・サウンドをリスペクトするものなのである。しかも、アーバンな感覚で──。
そして、名曲「サマー・ウィズアウト・ユー」の初出は本作において。このアルバムのために、横倉さんが書き下ろした(歌唱も横倉さん自身による)。彼は本作でキーボードとヴォーカル、それにすべての曲のアレンジを担当している。彼がフルに関わった作品としては、ファースト・リーダー作『ラヴ・ライト』(1978年)以来だから、8年のブランクがあったことになる。横倉さんはコマーシャリズムとはまったく無縁なミュージシャンであり、とにかく音楽に対して誠実で、自己のアイデンティティを堅持し、ときにはストイックなまでに孤高を持する。彼の玄米菜食主義がそれと関係あるのかどうかは定かでないけれど、その音楽に対するスタンスが甚だしく首尾一貫しているのは、サウンドからまざまざと感じられる。高い理想を現実に変えるのに、時間がかかるのは致しかたない。
(『ラヴ・ライト』については、下の記事をお読みいただければ幸いです)
世界にただひとつの横倉裕によるミュージック・タペストリー
本作で横倉さんを起用したのは、プロデューサーの小島大八とブラジリアン・フュージョン・バンド、スピック&スパン(当時は一時的にスピックスを名乗っていた)のリーダー、吉田和雄だ。まだ日本では広く知られていない横倉さんだったが、その音楽性を高く評価したふたりのセンスのよさに、ひとりの横倉裕ファンとしてここにあらためて、ふたりに敬意と感謝の意を表する。さらに、ここまでセルメン所縁のミュージシャンを集結させたことについても、ただただ天晴れと発するしかない。まず3人のシンガーは、ニュー・ブラジル ’77やブラジル ’88の作品、その後のソロ名義のアルバムでも長年レギュラーだったキャロル・ロジャース、セルメンの1984年のジャパン・ツアーでヒット曲「愛をもう一度」を熱唱したケイト・マーコウィッツ、そしてグラシーニャ・レポラーセと、みなセルメンの寵愛を受けた歴代の歌姫たちである。
リズム・セクションは、オスカー・カストロ・ネヴィス(acg)、ポール・ジャクソン Jr.(elg)、エイブラハム・ラボリエル(b)、ジョゼ・マリノ(b)、アレックス・アクーニャ(ds)、吉田和雄(ds)、パウリーニョ・ダ・コスタ(perc)、トム・スコット(as, ss)、そして横倉裕(key, vo)。そのうちカストロ・ネヴィスとスコットはセルメンの作品では、サポート・メンバーとしておなじみ。またマリノは、本作のあとに横倉さんのプロデュースにより『イーリャ・ドス・フラージス』(1989年)というアルバムをリリースしたブラジリアン・フュージョン・グループ、ヴェラスのリーダー。そのほかは説明する必要もない、フュージョン・シーンにその名がとどろきわたる、西海岸の敏腕ミュージシャンたち。とはいっても、決して複雑でテクニカルなプレイはしておらず、太陽と風が香るような楽しいセッションを展開している。
特筆すべきは、本作ではその時代を映し出す電子楽器が使用されているということ。FMアルゴリズムを使用したデジタル・キーボード、音源内蔵のミュージック・シーケンサー、それに六角形のパッドを使用したエレクトロニック・ドラムなどがそれだ。本来それらは、いまとなっては旧時代的なサウンドとして響くのだろうが、ここで繰り広げられている音楽の普遍性の高さから、まったく違和感なく聴こえる。それはひとえに、横倉さんの高度なミュージカリティを明示するものである。ぜひとも、爽やかなブラジリアン・テイスト、肩肘張らずに聴けるフュージョン・ミュージック、新たに都会的な装いが凝らされたセルメン・サウンド、そして世界にただひとつの横倉裕によるミュージック・タペストリーと、多角的な魅力をもった本作をお楽しみいただきたい。

楽曲について、セルメンとの関わりも含めてメモしておこう。オープニングの「マシュ・ケ・ナーダ」は云うまでもなくジョルジ・ベンの名曲。ブラジル ’66のファースト作『マシュ・ケ・ナーダ』(1966年)のトップを飾った。横倉さんのアレンジにより、シンコペーションとビートの効いたアーバン・フュージョンに様変わりした。ロジャースのソウルフルなヴォーカルとスコットのパッショネイトなアルトがグルーヴィー。つづく「波」はアントニオ・カルロス・ジョビンの人気曲。ブラジル ’66のセカンド作『分岐点〜コンスタント・レイン』(1967年)に収録。リラックスした16ビートのボサノヴァにアレンジ。短いながらシンセパッドの音色も印象的だ。
3曲目の「ザズエイラ」はふたたびベンの曲。セルメンがプロデュースしたグループ、ボサリオのセカンド作『アレグリア!』(1970年)に収録。このグループのシンガーだったレポラーセが本作でもリードをとる。思いのほかストレートなサンバで演奏されている。横倉さんのサイドヴォーカル、カストロ・ネヴィスのアコギにも、洗練されていながらもちょっとアーシーな味わいが感じられる。4曲目の「ハウ・インセンシティヴ」はふたたびジョビンの曲。ブラジル ’66結成以前のジャズボサ作品『クワイエット・ナイツ』(1967年)に収録。横倉さんによる繊細で優美なイントロがファンタスティック。マーコウィッツのセンチメンタルな歌唱も艶やかだ。次にレコードではSideーAのラストとなる、横倉さんのオリジナル曲が登場する──。
この「ムイト・マイス」では、独特なバランス感覚を有するサンバのリズム、意匠が凝らされたコード進行、テンション・ノートが多用された絶妙なハーモニーと、横倉サウンドが最大出力となる。レポラーセのヴォーカルもどこか神秘的。この曲は前述のヴェラスによってカヴァーされているが、そちらのリード・ヴォーカルはケヴィン・レトー。レトーもまた、セルメン・ファミリーのひとりだ。つづいてSide-B──1曲目の「おいしい水」はみたびジョビンの曲。前述のブラジル ’66のヒット作『マシュ・ケ・ナーダ』に収録。ここではファンキーなフュージョン・ブギーにアレンジされている。スコットのソプラノもソウルフル。つづく「プリティ・ワールド」はアントニオ・アドルフォの曲。原曲よりもブラジル ’66の5作目『クリスタル・イリュージョンズ』(1969年)のヴァージョンのほうが有名。横倉さんのアレンジは、師匠であるデイヴ・グルーシンのそれを上手く発展させた感じだ。
3曲目の「エニシング・キャン・ハプン」はプロデューサーの小島さんによる書き下ろし。転調を効果的に使った洒落た曲。マーコウィッツの突き抜けるようなファルセットに思わず恋してしまう。ジャクソン Jr.のジャジーなギター・ソロも手堅い。このあといよいよ「サマー・ウィズアウト・ユー」が登場。すでに言及済みなので、ひとつだけ付言する。この曲、一般的に「この星の上で」が原曲と観られている。若き日の横倉さんを中心とするグループ、NOVOの1973年のシングル盤だ。確かにその痕跡が認められるが、相当な改変がなされている。キーがDからFにチェンジされる感動的なサビは、ここだけのものである。そして、ラストの「トリステーザ」はアロルド・ロボの曲。ブラジル ’66の3作目『ルック・アラウンド〜恋のおもかげ』(1967年)に収録。カーニヴァルよろしく全員のコーラスで、アルバムはハッピーに締めくくられる。本作のあと、横倉さんは1988年にグルーシンが率いるGRPレコードと契約。YUTAKA名義で活躍することになるが、それについてはまたの機会に──。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。










コメント