ビル・エヴァンスが惚れ込んだ特定のピアニストの系譜に属さないジョアン・ブラッキーンの初リーダー作『ネフェルティティ』
 Album : Joanne Brackeen / Snooze (1975)
Album : Joanne Brackeen / Snooze (1975)
Today’s Tune : Nefertiti
ボブ・ジェームスのセミフォーマルなアコースティック・コンサート
ジャズ/フュージョンの雄、ボブ・ジェームスの昔のアルバムに『ニューヨーク・ライヴ』(1981年)というのがある。アルバム・タイトル(原題は『All Around The Town』)どおり、1979年の暮にニューヨーク市の3つの会場で行われたコンサートの模様が実況録音され、その音源のうちベスト・プレイが2枚組LPに纏められたものである。これがなかなか気の利いたアルバムで、その生演奏の臨場感も然ることながら、ジェームスの多彩な音楽性を一気に楽しむことができる仕様となっている。ここに収められた3つのコンサートは、敢えて会場によって楽団のフォーメーションや音楽のスタイルを異にするという、いかにも懐の深い練達の士であるジェームスらしい趣向が凝らされたものだった。
その3つのコンサートの内訳は、12月18日、19日にボトム・ラインで行われた6人のレギュラー・メンバーによるコンボ・スタイルでのライヴ、12月21日にタウン・ホールで行われた3台のピアノ、2台のドラムス、それに1本のベースといった特殊な編成でのセミフォーマルなアコースティック・コンサート、そして12月22日にカーネギー・ホールで行われた6名のリズム・セクションに8名のホーン・セクションが加えられたリトル・ビッグバンドでのライヴとなっている。もちろんこの手の込んだ企画は、フュージョン・キーボーディストとしての熱いプレイ、ジャズ・ピアニストとしての面目躍如たる演奏、そしてアレンジャーとしての才気煥発ぶりが発揮されたキャッチーなサウンドといった、ジェームスの魅力を多面的にアピールするものである。
そのいっぽうで、このプロジェクトにはもうひとつの目論見があった。ジェームスは1973年からコロムビア・レコードでプロデューサーとして仕事をしていたが、1977年にその傘下で自己レーベル、タッパン・ジー・レコードを立ち上げた。レーベル第1弾は、ギタリストのスティーヴ・カーンの初リーダー作『タイトロープ』(1977年)で、ジェームス自身も間もなく『ヘッズ』(1977年)を発表した。ところで、くだんの『ニューヨーク・ライヴ』のジャケットのバック・カヴァーには、上記の3つのコンサートに参加した全ミュージシャンの名前が大きめに、ファミリーネームのアルファベット順で記載されている。そのなかには、当時タッパン・ジーに所属していたアーティストのクレジットも見出すことができる。
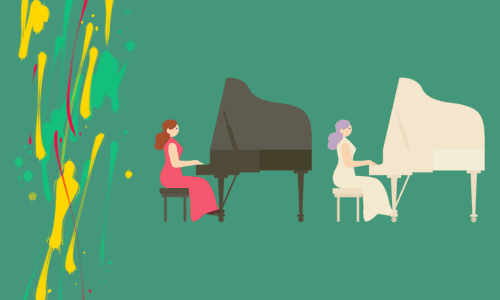
具体的には、マーク・コルビー(ts)、ウィルバート・ロングマイアー(g)、リチャード・ティー(p)、そしてジョアン・ブラッキーン(p)が、タッパン・ジーと専属契約をするアーティストだった。3つのコンサートが開催されるまえに、すでにコルビーの『サーパンタイン・ファイアー(太陽の戦士)』(1978年)と『ワン・グッド・ターン』(1979年)、ロングマイアーの『サニー・サイド・アップ』(1978年)と『シャンペン』(1979年)、ティーの『ストローキン』(1979年)、ブラッキーンの『キード・イン』(1979年)と、各々のリーダー作がこのレーベルからリリースされていた。つまりライヴ・プロジェクトは、タッパン・ジーの所属アーティストとその作品をアピールする、マーケティング戦略の一環でもあったわけだ。
この『ニューヨーク・ライヴ』において、ぼくがもっともこころ惹かれたのは、タウン・ホールにおけるちょっとフォーマルな“アコースティックの夕べ”の模様。タッパン・ジー・レーベルのタイプの異なる3人の傑出したピアニストの重奏や即興演奏のクロストークは、まさに夢の競演と呼ぶに相応しい貴重なパフォーマンスである。ボブ・ジェームスのオーソドックスなポスト・バップ・スタイル(センター)、リチャード・ティーのファンキーなゴスペル・タッチ(右チャンネル)、ジョアン・ブラッキーンのアヴァンギャルドなフリーフォーム(左チャンネル)といった、3つの要素が打ち出すハイブリディティに富んだサウンドは、当時ジャズ・ピアノを学びはじめたぼくにまったく新しいモダン・ジャズの醍醐味を味わわせてくれた。
3台のピアノが置かれたすぐ後ろで、バックを務める3人のミュージシャンもまた素晴らしい。ウッドベースをぶっとい音で鳴らし、鮮やかなフィンガー・ピッキングでつぎつぎとしなやかなフレーズを繰り出しているのは、エディ・ゴメス。彼はビル・エヴァンス・トリオに加入したことで名を馳せたけれど、4ビート以外の音楽でも正確無比なボトムをキープするひと。そのゴメスの後方にセットされた、ツイン・ドラムのプレイヤーがスゴい。ひとりは1970年代の前半にハービー・ハンコックのグループで活躍した、フレキシブルなドラマー、ビリー・ハート。そしてもうひとりは、もとスタッフのメンバーでフュージョン随一の技巧派ドラマー、スティーヴ・ガッド。このふたりもまた、まったく違うタイプのミュージシャンだ。
ここではハートのスティックによるスウィンギーで重量感のあるドラミングと、ガッドのブラシによるタイトで軽快なリズムが際立つプレイとが、見事に絡み合う。ひとつのグルーヴにおいて、ふたりのコントラストがなんとも鮮やかだ。ただ残念なことに『ニューヨーク・ライヴ』は2枚組LPという体裁をとりながらも、このタウン・ホールでの演奏をたったの2曲しか収録していない。すなわちセレクションは、ゆったりしたテンポでバンドがスウィングするエドガー・サンプソンの「サヴォイでストンプ」と、アップテンポでエキサイティングなプレイが展開されるボブ・ジェームスのオリジナル曲「ゴールデン・アップル」のみとなっている。なお後者をこのアルバムのハイライトと、ぼくは観ている。
この「ゴールデン・アップル」はジェームスのCTIレコードにおける2作目『夢のマルディ・グラ』(1975年)に収録されていた曲で、原曲はCTIが得意とするオーケストラルなフュージョン・ナンバーだった。しかしながらそんな大編成の演奏と比較しても、この15分にもおよぶタウン・ホールでのアコースティックな演奏のほうが、圧倒的な迫力を誇る。ところが不届き至極なことに『ニューヨーク・ライヴ』がCD化されるにあたり、収録時間の関係から「ゴールデン・アップル」は編集され5分ほど短縮された。なんともはや、テーマのあと先行するブラッキーンの迸るようなアグレッシヴなインプロヴィゼーションが、まるまるカットされているのである。もっとも白熱するところなのだけれど──。
ジョアン・ブラッキーンって、どんなピアニスト?
実はぼくはこの『ニューヨーク・ライヴ』を聴くまで、ブラッキーンのことをまったく知らなかった。あとで知ったのだが、ブラッキーンは1970年にアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズのメンバーとして来日し、わが国でもすでに新進気鋭の女性ジャズ・ピアニストとして注目を集めていた。当時のぼくはそんなこととはつゆ知らず、とにもかくにもタッパン・ジーからすでにリリースされていた彼女のリーダー作、前述の『キード・イン』と『ダイナスティ』(1980年)を、慌てて購入した覚えがある。というのも、メガネをかけたさながら第一線で活躍するデキる女性といった風貌に、いささか前衛的なピアノ・スタイルといった、ブラッキーンの鮮烈なイメージにぼくは大きな衝撃を受けたからである。
ちなみに『キード・イン』は、エディ・ゴメス(b)、ジャック・ディジョネット(ds)を従えてのピアノ・トリオ作品。これは、ものスゴい傑作。全7曲がブラッキーンのオリジナルだけれど、彼女にしては珍しくメロディアスな側面が際立つ。サイドも含めてインプロヴィゼーションのクオリティがすこぶる高く、1970年代のピアノ・トリオの神髄を究めるような演奏が繰り広げられている。かたや『ダイナスティ』は、ゴメス、ディジョネットの強力なバックアップにあわせて彼女の師匠であるジョー・ヘンダーソン(ts)が参加したクァルテット作品。4人はやや複雑なブラッキーンの4つのオリジナル・ナンバーを、胸のすくようなテクニックをもってしてセンセーショナルな逸品に仕上げている。
そんなマスターピースでありながら『キード・イン』も『ダイナスティ』も、いまだCD化に至っていない。しかもほかのタッパン・ジー作品のほとんどが、すでにリイシューされているのにもかかわらずである。なぜだろう?なお、ロンドンに拠点を構えるチェリー・レッド・レコードから『ヴェリー・ベスト・オブ・タッパン・ジー・レコード』(2018年)というCD2枚組のコンピレーション・アルバムがリリースされているが、ここに唯一『キード・イン』の冒頭を飾るワルツ「レット・ミー・ノウ」が収録されている。ほんの一端に過ぎないが、ぜひ美しいピアニズムと力強いインタープレイに触れていただきたい。しかもこのコンピ、やはり未CD化のアレン・ハリス・バンドの名盤『オーシャンズ・ビトウィーン・アス』(1978年)の表題曲も収録したおトクなアルバムなので──。

ぼくとしては『キード・イン』と『ダイナスティ』の単体でのCD化をことに切望するのだけれど、それを勝手に期待しながら待つついでに、ずけずけと無理難題を云ってみたい。前述の3つのコンサートをそれぞれ単体でCD化、当然のごとく全曲コンプリートするというのは、いかが思われるだろうか。エンジニアのジョー・ジョーゲンセンは、コンサートの全日においてテープを回したということだし──。ことにタウン・ホールでの演奏は「ゴールデン・アップル」の編集の件もあるから、なんとしても実現してほしい。ちなみに当日にプレイされたアルバム未収録曲には、ブラッキーンの「息子」と「ハイチ B」ビリー・ストレイホーンの「A列車で行こう」ビリー・ジョエルの「ニューヨークの想い」デューク・エリントンの「スイングしなけりゃ意味ないね」などがある。
ところで、ジョアン・ブラッキーンって、どんなピアニスト?彼女は1938年7月26日、カリフォルニア州ヴェンチュラ市にジョアン・グローガンとして生まれた(結婚してブラッキーン姓となった)。現在86歳ということになるが、思っていたよりもお年なのでちょっと驚いた。確かにブラッキーンのリーダー作は20枚を超える程度で、決して多いとは云えない。リード・ミュージシャンとしてのはじめての吹き込みは1975年の3月のことで当時彼女は36歳だったから、ずいぶんと遅いスタートを切ったことになる。しかもそのリーダー作も、2000年代に入るとぷっつり途絶えてしまう。まあブラッキーンはそれ以降、マサチューセッツ州ボストン市のバークリー音楽大学やニューヨーク市のニュースクール大学で教鞭を執り、後進の育成に尽力したのだけれど──。
実はブラッキーンはなんと12歳のときからプロのピアニストとして活動しており、1950年代にはデクスター・ゴードンをはじめ、チャールズ・ブラッキーン、テディ・エドワーズ、ハロルド・ランド、チャールス・ロイドらと共演している(なぜかテナー奏者ばかりだ)。ちなみにチャールズ・ブラッキーンは、彼女のもと旦那さま。ふたりは1965年に結婚しており、それを機にニューヨークへ移住している。ふたりの間には、4人の子どもがいる。ちょうどそのあとブラッキーンは、はじめてレコーディングを経験。ヴィブラフォニストのフレディ・マッコイのサード・アルバム『ファンク・ドロップス』(1966年)において、彼女はザ・ビートルズやザ・ジャズ・クルセイダーズのジャズ・ロック・ヴァージョンを堂々とプレイしている。
1970年代に入るとブラッキーンは、ジョー・ヘンダーソンやスタン・ゲッツ(ts)のグループの重要メンバーとなる。また彼女はジャズ・ハーモニシストの巨人、トゥーツ・シールマンスがチョイス・レコードに残した名盤『酒とバラの日々』(1974年)に参加。セシル・マクビー(b)、フレディ・ウェイツ(ds)とともに見事なサポートを見せた。実を云うとそれ以前にブラッキーンは、チョイス・レーベルのオーナーであるジェリー・マクドナルドと、当時マンハッタン区グリニッジ・ヴィレッジにあったジャズ・クラブ、ブラッドリーズで出会っていた。マクドナルドに気に入られた彼女は、すぐにシールマンスのレコーディングで起用され、その翌年いよいよリード・ミュージシャンとしてデビューを果たすことになるのである。
ブラッキーンは9歳からピアノを弾きはじめたのだけれど、少女時代の彼女のアイドルは膨大なカクテル・ピアノ作品を残したフランキー・カールだったという。意外に思われる向きもあるだろうが、偶然カールのオーケストラに親しんだぼくからすると、なんとなく腑に落ちるのである。というのも、カールはそれこそ魅惑のストリングスをバックに流麗なピアノ・プレイを繰り広げるのだけれど、その演奏は、ゆるみがなく精度が高い。“鍵盤の魔法使い”の異名をとるだけあって、彼のピアニズムがもつダイナミックかつエレガントなフィーリングは、絶品と云える。ブラッキーンは11歳のときに、8曲のカールのソロ演奏をコピーし、それを6か月で完璧に弾けるようになったという。まさしく、天才少女だ。
革新的な表現は、不思議と聴き心地がすこぶるいい
その後のブラッキーンといえば、14歳のときにはじめてジャズと邂逅。特にビバップのイノヴェーターであるアルト奏者、チャーリー・パーカーの即興演奏に魅了された。16歳のときにヴェンチュラからロサンゼルスに移住し、ハイスクールの後輩だったボビー・ハッチャーソン(vib)やハービー・ルイス(b)らと、セッションを楽しんだ。また、エルモ・ホープ、ポール・ブレイといった先輩格のジャズ・ピアニストとも交流があったという。のちのブラッキーンのアヴァンギャルドな一面は、もしかすると1960年代のフリー・ジャズ・ムーヴメントの一翼を担ったブレイからの影響によるものかもしれない。そんな彼女の音楽的才能に目をつけたのが、ロサンゼルス音楽院(現カリフォルニア芸術大学)だった。
この音楽学校は、ブラッキーンに全額奨学金を給付することを申し出たという。ところが彼女は授業に出席して1週間も経たないうちに、クラスワークよりもフィールドワーク、つまり実際にステージに立つことのほうが有益であると、あっさり判断してしまった。ブラッキーンは実質3日間で、同音楽院を退学している。そんな軸のあるところもまた、いかにも天才肌の音楽家といった印象を与える彼女らしい。結局、実際の演奏体験を通じて培われたその強烈な独自性と創造性から、ブラッキーンはなんらのピアニストの系譜にも属さないプレイヤーとなったのである。そんな稀有な逸材に、強い関心を寄せるミュージシャンがいた。誰あろう、自身も旧来の慣習を打ち破るようなモダン・ジャズのスタイルを確立したピアニスト、ビル・エヴァンスだ。
エヴァンスがブラッキーンの才能に着目したのは、1978年ごろとのこと。彼女が脱退直前だったスタン・ゲッツ・クァルテットによる、コペンハーゲンの名門クラブでの熱演が記録された『ライヴ・アット・モンマルトル』(1977年)がリリースされたあとの出来事だ。1978年といえば、ブラッキーンの6枚目のリーダー作『トリンケッツ・アンド・シングス』(1978年)が発表されるいっぽうで、前年にエヴァンスのトリオを辞したばかりのエディ・ゴメスとの共演作『プリズム』(1979年)のレコーディングが行われた年でもある。もしかするとエヴァンスはゴメスをとおして、ブラッキーンの存在を知ったのかもしれない。いずれにしても彼は当時の自分のマネージャー、ヘレン・キーンに、是が非でもブラッキーンをプロデュースするよう指示したという。
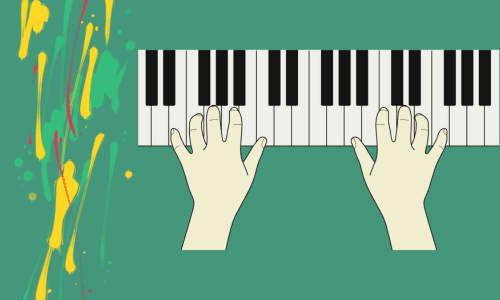
キーン女史はエヴァンスが他界したあと在りし日の彼のコトバに従い、ブラッキーン、ゴメス、ディジョネットといった至高のトリオによる『スペシャル・アイデンティティ』(1982年)、そしてその10年後の再会セッション『ホエア・レジェンズ・ドウェル』(1992年)のプロデューサーを務めた。また彼女は、評論家のハーブ・ウォンとともに『スペシャル・トリビュート・トゥ・ビル・エヴァンス』(1983年)という2枚組のアルバムを制作した。これはキーンによって選ばれた14人のピアニストが、エヴァンス所縁のナンバーをひとり1曲ずつ演奏するという、ユニークなソロ・ピアノ集。その人選といえば、エヴァンスが生前、敬意を払っていたひと、こころにかけていたひと、そしてプライヴェートで親しくしていたひとが対象となっている。
その14人は、折に触れてエヴァンスが名前を口にしたピアニストばかりということだが、その意表を突かれるような錚々たる顔ぶれに驚かされる。そしてそのなかには、しっかりブラッキーンの名前もある。彼女はここでエヴァンスがキーンに捧げた自作曲「ソング・フォー・ヘレン」において、偉大なる先達の音楽に対する彼女なりの解釈を打ち出してみせた。エヴァンスの内省的な音楽世界がもつ美しさを、アブストラクトかつストレートフォワードなプレイで、外界へと揮発させている。抽象性と具象性がせめぎ合うような、絶妙なバランスで高度なパフォーマンスが発揮されながら、驚くほど聴きやすいサウンド・タペストリーが織りなされるようなところが、ブラッキーンのプレイの最大の魅力と云える。
そんなブラッキーンのリーダー作のなかでぼくが好きなのは、前述のタッパン・ジー・レーベルの2作、キーンが手がけた2作、さらに挙げればウォルター・シュモッカー(b)、ビリー・ハート(ds)をサイドに迎えたトリオ作『イズ・イット・リアリー・トゥルー』(1991年)なのだが、どれもなかなか入手が困難なようだ。まあ彼女のアルバムにむなしく空を切るようなものや噴飯ものの作品は皆無だから、どれを聴いてもご満足いただけるとぼくは思う。ということで最後に、比較的入手しやすい彼女の初リーダー作『ネフェルティティ』(1975年)をお薦めしておく。さきにも触れたジェリー・マクドナルドのプロデュースによる、チョイス・レーベルからのリリース作品である。
レコーディングは、1975年3月ニューヨーク州ロングアイランドにあるマクドナルドの自宅スタジオで行われた。メンバーはブラッキーンの複雑なコンセプトから敏腕プレイヤーに限定されるが、サイドにはプログレッシヴでヴァーサタイルなベーシスト、セシル・マクビーとオールラウンドなドラマー、ビリー・ハートが起用されている。トリオはアルバム冒頭からフルスロットルでプレイ。曲はウェイン・ショーターの「ネフェルティティ」だが、最初と最後の三つ巴のフリーフォームな展開、インテンポでのブラッキーンのダイナミックなソロ、ハートのブラシからスティックへのもち替え、マクビーの雄弁にはじけるベースと、どこをとっても痛快だ。つづくマイルス・デイヴィスの「サークルズ」では、ゆったりとしたテンポで芸術的なインタープレイが展開される。そこで描き出される濃淡と明暗の世界は、原曲を遥かに超えた。
ブラッキーンのオリジナル「C-スリ」では、アップテンポでのブラッキーンのイノヴェイティヴなブルース・プレイが心地いい。マクビーとハートもソロ・パートでは思うままに振るまう。トリオによるフリー演奏「ズールー」は、アヴァンギャルドではあるが案外聴きやすい。トリオのアグレッシヴなプレイも然ることながら、ブラッキーンの緻密で重厚なコード・ヴォイシングが素晴らしい。ブラッキーンの自作曲「シクセイト」では、ポリメトリックなリズムとモーダルなインプロヴィゼーションが迫力満点だ。バートン・レーンの「オールド・デヴィル・ムーン」では、比較的オーソドックスな4ビートでの演奏が展開されるが、ブラッキーンの10本の指は相変わらず疾走しまくる。ブラッキーンの「スヌーズ」は、シンプルな6拍子だが、一瞬変拍子と思ってしまうほど即興演奏が熾烈を極める。
さて、アナログ盤では以上7曲で終わりだが、CDにはボーナス・トラックとしてもう1曲収録されている。ロレンツ・ハート作詞、リチャード・ロジャース作曲という名コンビによるミュージカル・ナンバー「時さえ忘れて」だが、この曲の追加はなかなか気の利いた計らいと感じられた。なにせ前曲の「スヌーズ」におけるちょっと前衛的な押しの強い演奏には、アタマがくらくらして目のまえが暗くなるような感じさえするくらいだから、あたかも一服の清涼剤のようなこのモダンでスウィンギーなパフォーマンスの追加は、非常にありがたい。そして確かにブラッキーンには、既成のジャズの概念や形式を打ち破り、革新的な表現をするようなところがあるけれど、トータル・サウンドは不思議と聴き心地がすこぶるいい。本作もまた、そんな高揚感と爽快感に溢れた1枚である。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント