追悼 鈴木央紹──大野雄二プロデュースによるデビュー作『パッセージ・オブ・デイ』を味わいながら、鈴木さんの在りし日の姿を思い浮かべ、偲び、悼む
 Album : 鈴木央紹 / Passage Of Day (2009)
Album : 鈴木央紹 / Passage Of Day (2009)
Today’s Tune : Proof Of The Man
鈴木央紹の横顔①──音楽に触れてから1990年代までの活動
サクソフォニストの鈴木央紹が、天国に旅立った。突然の訃報に驚くばかりである。それは2024年12月28日のことだったが、2025年1月5日に公式サイト、SNSにおいて親族が発表したことから明らかになった。長い間、重い病気と闘ってきたという。辛そうな素振りも見せずに最後の最後まで演奏の場に身を置いた鈴木さん、いまとなっては安らかな眠りにつくことを祈るのみである。それにしても52歳での逝去とは、あまりにも早すぎる。ああ、もうその確固たるテクニックに裏打ちされた演奏能力とセンシティヴィティに富んだ表現力に触れることはできないのか──そう思うと、日本のジャズ・シーンにとっては大きな損失とも感じられるし、いちファンとしても残念でならない。
それにもまして、ときおりシャイな表情を浮かべる、鈴木さんのちょっと少年っぽさを残す端正な面差しを思い浮かべると、胸が張り裂けるような気持ちになる。さらには、鈴木さんが長年バンドメンバーの一員として活躍したYuji Ohno & Lupintic Five、そしてYuji Ohno & Lupintic Sixのリーダー、ピアニストの大野雄二の追悼のコトバに泣かされた。それは2015年1月8日に付された、大野さんの公式サイトでのコメントだけれど、以下にそのまま引用させていただく。まず「Lupintic Sixのメンバー鈴木央紹が旅立ちました。20年に渡り、バンドメンバーとして、そして、サックスプレイヤーとして、僕の音楽をステージでもスタジオでも常に支えてくれました。打ち上げでのメニューの注文も全て彼に任せていました」と、感謝の意が表されている。
そのあとに大野さんはつぎのようなコトバを添えている。鈴木さんに向けて「ばかやろう。すぐに生き返ってこい。すぐに」と結んでいるのである。ファンのひとにはよくわかると思うのだけれど、こういう云いまわしがまさに大野節なのだ。大野さんの場合、その音楽性と同様に会話においてもウィットに富んだ表現をすることがままある。ジャズを地でいくようなサッパリした性格の大野さんには、謹みの気持ちを表したり堅苦しく姿勢を正したりする姿は似合わない。そんな大野さんの自分にとって気の置けない音楽仲間だった鈴木さんへのストレートな思いが込められたコトバに、ぼくは年甲斐もなく思わず泣きそうになってしまった。それだけ大野さんの鈴木さんへの愛情が伝わってきた──。ぼくもあらためて、ここに哀悼の意を表させていただく。

鈴木さんを偲びつつ簡単ではあるが、ここにその横顔を振り返っておく。鈴木央紹は1972年11月22日、大阪市に生まれた。サックス奏者である父親の影響を受けて、4歳からピアノをはじめる。10歳になるとサックスを手にし、ジャズを独学した。16歳のときにはすでに大阪を中心にクラブなどで演奏活動を開始していたとのこと。17歳のときには、リットーミュージックが主催するAXIAミュージック・オーディションにおいて、AXIA賞インストゥルメンタル部門のグランプリに輝いた。大阪音楽大学音楽学部器楽学科においてサックスを専攻する。同大学在学中は、サクソフォニストで指揮者としても活躍する前田昌宏に師事した。ということで当時の鈴木さんは、クラシックとジャズとの二足の草鞋を履いていたのである。
鈴木さんはのちに(2019年4月から末年まで)、大阪音楽大学ジャズ・サクソフォーン特任准教授を務めることになる。演奏活動だけではなく、かつての学び舎において音楽教育のためにも尽力したのである。それはさておき大学卒業後、鈴木さんは国内のみならず韓国でも演奏活動を開始。そのプレイは同地のジャズフェスで好評となり、公共放送局の番組でも採り上げられた。いっぽう同じころ、やはり大阪出身のギタリスト、箕作元総(キサクモトフサ)の幻の名盤『陽のあたる裏通り – Song For Unknown Great People』(1999年)に、鈴木さんのクレジットを見出すことができる。ジャンルを問わず100枚を超える音楽作品のレコーディングに参加した鈴木さんではあるけれど、このアルバムが最初期の吹き込みであろう。
そのあと鈴木さんは、韓国出身の女性シンガーで1998年から日本でも活動していたウンサンのデビュー・アルバム『イントロデューシング・ウンサン(Love Letters)』(2003年)のレコーディングに参加。ベニー・グリーン(p)、ロニー・プラキシコ(b)、ロドニー・グリーン(ds)、コンラッド・ハーウィグ(tb)といった、ニューヨークの敏腕ジャズ・プレイヤーたちと互角に渡り合うような堂々たる演奏を披露。実はぼくはこのアルバムで、鈴木さんの名前をはじめて知った。このアルバムはジャズ・ヴォーカル作品としては、出色の出来である。ウンサンのヴォーカルは、艶やかだけれど軽やかでもある。ベニー・グリーンのピアノは、相変わらずセンシティヴなタッチと美麗なコード・ワークを見せる。
そのモダン・ジャズの伝統的なスタイルと革新的なインタープリテーションが交錯する音景のなかに、鈴木さんのサックスが見事に溶け込んでいる。韓国人としてははじめてニューヨーク、マンハッタンの伝説的ジャズ・クラブ、ブルーノートで歌ったシンガーでもあるウンサンの歌いっぷりも素晴らしいが、ぼくは鈴木さんのアーバンなムードが横溢するバラード・プレイにシビレた。本作は日本盤と韓国盤との2種類が存在するけれど、見かけたらぜひ手にとっていただきたい。なお鈴木さんは、ウンサンの8枚目のアルバム『誘惑(Temptation)』(2015年)にも参加。こちらは韓国を代表するギタリスト、ジャック・リーがプロデュースを手がけたコンテンポラリー・ジャズ作品だ。
鈴木央紹の横顔②──2000年代から大野雄二のバンドに加入するまで
この『誘惑(Temptation)』は、リー・リトナー(g)、ネイザン・イースト(b)、日野皓正(tp)らが参加したことや、ロック、ラテン、リズム・アンド・ブルースなどの名曲が採り上げられていることから、ポップ・ミュージックのリスナーからスムース・ジャズの愛好家まで広く受け入れられた。ウンサンのヴォーカルも、いつもよりクールな表現とソウルフルな歌いまわしが際立っている。鈴木さんはこのアルバムでは1曲のみの参加。ウンサンの自作曲「ユー・ハート・ミー」において、彼女自身のブルージーなヴォーカリゼーションと韓国のミュージシャンたちが奏でる軽快なスカのリズムとがつくる、熱い空気と異国の味わいのなかで、鈴木さんのソプラノがジェントルなフレーズを綴っている。
ハナシをもとに戻すが、2000年代の鈴木さんといえば、2002年の夏、日野皓正のグループでヤマハ・ジャズ・フェスティヴァル・イン・浜松に出演。翌年も大阪の門真市民文化会館ルミエールホールでの日野さんのライヴ(守口・門真ジャズ・フェスティヴァル)に参加している。2004年にはシンガーソングライターの坂井泉水を中心としたユニット、ZARD初の全国ライヴ・ツアーに参加。以来鈴木さんはZARDのレコーディングやライヴには欠かせないミュージシャンとなる。2007年に坂井さんが逝去したあとは、追悼ライヴにも参加していた。いっぽう自己のリーダー・クァルテットでも活動していた鈴木さんだが、2005年11月の大阪梅田の老舗ジャズ・クラブ、ミスターケリーズ(2023年閉店)におけるライヴでは、ニューヨークの名ドラマー、ルイス・ナッシュをゲストに迎えた。
2006年1月、鈴木さんは活動拠点を東京に移す。このころの音盤だと、ジャズ・ピアニストの秋田慎治の初リーダー・アルバム『モーメンツ・イン・ライフ』(2006年)において、鈴木さんのテナーを聴くことができる。このアルバムはいかにもプログレッシヴなジャズ作品で、4ビートのみならず8ビート、16ビートなど多彩なスタイルのジャズが展開されている。曲によってはニューエイジ・ミュージックのような芸術的インスピレーションとリラクゼーションを与えるような演奏もあるが、鈴木さんが参加した2トラックではどちらかといえばストレート・アヘッドなジャズが繰り広げられている。ここでのテナーによる怒涛のブロウは、胸がすくほど爽快だ。アグレッシヴなプレイでありながら少しも乱脈を極めることがないところは、いかにも鈴木さんらしい。
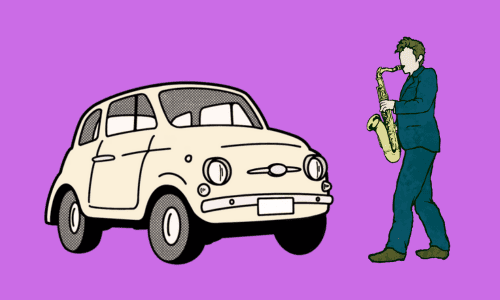
さて、この2006年こそ、鈴木さんがYuji Ohno & Lupintic Fiveに加入した年である。というかこのグループが結成されたのが、まさにこのときだった。リーダーの大野さんはもともとジャズ・ピアニストだったけれど、1971年あたりから徐々にプレイヤーとしての仕事を減らしていく。その後、もちまえの作曲、編曲の才能を活かしてテレビCM、テレビ番組や映画の音楽、ポップ・ミュージックにおいて、サウンド・クリエイターとして大いに腕を振るったことは周知のこと。ときおり銀座や六本木のクラブでジャズ・スタンダーズを弾いてはいたものの、本格的にジャズ・プレイヤーとして復帰するのは2000年代に入ってからだった。そのキッカケとなったのが、1999年にスタートした“LUPIN THE THIRD「JAZZ」”と銘打たれたジャズ・アルバムのシリーズだった。
いささか余談になるが、おなじ1999年に大野さんは“LUPIN THE THIRD「JAZZ」”シリーズとは別に、自身の往年のバンド、You & Explosion Bandをプロジェクト名に冠した『Isn’t It Lupintic?』というフュージョン系のアルバムを吹き込んでいる。このアルバムのタイトル・ナンバー「Isn’t It Lupintic?」は、リチャード・ロジャースとロレンツ・ハートとのコンビによるミュージカル映画の名曲「Isn’t It Romantic?」を捩ったもの。大野さん十八番のダジャレだ。この“Lupintic”は云うまでもなく大野さんが手がけたアニメ『ルパン三世』に引っ掛けた造語。よほどお気に入りだったのだろう、“Lupintic”はバンド名に付されただけでなくレーベル名にまで使用されたのである。
あだしごとはさておき、“LUPIN THE THIRD「JAZZ」”シリーズは、ほとんどがレッド・ガーランドへのリスペクトを感じさせる大野雄二トリオが主幹をなす作品だった。このシリーズで大野さんが自己の音楽性のルーツを辿っていったとき、次に行き着いたのはホレス・シルヴァーが統率していたころのザ・ジャズ・メッセンジャーズだったのではないだろうか。もちろんそれはハード・バップのスタイルをそのまま再現するのではなく、大野さんに影響を与えたあらゆる音楽の要素を盛り込んだ、新しい感覚のジャズ・コンボを提案するものだった。現にYuji Ohno & Lupintic Fiveの演奏には4ビートのみならず、ジャズ・ロックやフュージョンが盛んに飛び出してくる。その点、現代のジャズ・シーンにおいて、稀有なバンドと云える。
Yuji Ohno & Lupintic Fiveのメンバーは、大野雄二(p, elp)、和泉聡志(g)、俵山昌之(b)、江藤良人(ds)、松島啓之(tp)、そして鈴木央紹(ss, ts)の6人。2010年4月にはベーシストが井上陽介に交替している。このバンドはおよそ10年間、ニュー・アルバムをリリースする度に全国ツアーを行い、多くの聴衆にジャズの楽しさ、奥深さを伝えていくが、2015年末にいったん解散する。大野さんはトリオでの活動も休止してしばし充電期間に入る。しかし2016年3月には、和泉さん、松島さん、鈴木さんの3人に、往年のYou & Explosion Bandのメンバー、ミッチー長岡(b)、市原康(ds)、さらに若きハモンド・オルガン奏者、宮川純を加え、ニュー・バンドを結成。それがYuji Ohno & Lupintic Sixだった。
結局、鈴木さんはおよそ18年と半年の間、このバンドで演奏しつづけた。2022年3月に大野さんが体調不良により入院し、しばらく療養に専念することになり、バンドは活動休止状態となった。しかしながら、2024年5月30日(大野さんの誕生日)に活動を再開。大野さんのオンステージはないものの、バンドはLupintic Six with Fujikochans Produced by YUJI OHNOとして、港区赤坂のビルボードライヴ東京において2セットの公演を果たした。バンドは同年の10月14日、恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催されたEBISU JAM 2024にも出演したが、鈴木さんの参加はこれが最後となった。その後12月25日、東京の小岩にあるジャズ・ハウス・コチにて、鈴木さんは僚友の松島さんらとセッションを行なったが、その3日後に帰らぬひととなった。
鈴木央紹の魅力的なプレイが様々な形でアピールされたデビュー作
時計の針を戻すが、Yuji Ohno & Lupintic Fiveが結成されたとき、鈴木さんはそれまで大野さんとはまったく面識がなかった。当時の大野さんはとある談話のなかで、鈴木さんについて「今のうちから知っておくと、将来得をするサックス奏者」と名状している。前述のウンサンのアルバムでその演奏にすでに触れていたぼくも、まったく同感だったもの。それはともかく鈴木さんは、ある日インペグ(ミュージシャン・コーディネーター)の間宮えまりからデモテープを注文され、ひとまず彼女にテープを渡した。ちなみに間宮さんは、2024年12月11日に亡くなった大作曲家、間宮芳生のいちばん上のご息女である。そしてしばらくすると、鈴木さんは出し抜けに大野さんのレコーディングに呼ばれたのだという。
つまり鈴木さんは、オーディションも顔合わせもないまま、いきなり大野さんのニュー・バンドのレコーディングに臨んだのである。おまけに当日、ミュージック・ビデオの撮影まであったという。のちに大野さんは、鈴木さんをバンド・メンバーに選んだ理由について「プレイも上手いとは思ったけど、イケメン重視で選んだ」と語っている。これは一聴、冗談めかしているようにも聞こえるけれど、思いのほか真情が吐露されたものだったりするのではないだろうか。鈴木さんは実際、容姿端麗。演奏中は素っ気なく映るかもしれないが、ふとしたときに甘く優しい一面を見せるようなひとだ。そんな鈴木さんにいちばん惚れ込んでいたのは、おそらく大野さんだろう。なにせ記念すべき大野さんが主宰するルパンティック・レーベルの第1弾が、鈴木さんのソロ・デビュー作だったのだから──。
鈴木さんは、5枚のリーダー作を残した。それ以外では、井上陽介(b)、江藤良人(ds)といったYuji Ohno & Lupintic Fiveの当時のリズム隊を背に、鈴木さんのテナーと多田誠司のアルトがフロントを務めるという変則2管編成ユニット、God Hands QUARTETの『GH4』(2013年)という、スゴいアルバムもある。鈴木さんのアルバムにしては珍しく、ハイクオリティなアレンジが施されたインプロヴィゼーションとインタープレイとを主眼とした骨太のジャズ作品なので、機会があればぜひ聴いていただきたい。とはいえ、もっともサクソフォニスト、鈴木央紹の魅力的なプレイが様々な形でアピールされているのは、やはり大野さんがプロデュースを手がけたデビュー作『パッセージ・オブ・デイ』(2009年)であると、ぼくは思う。

では最後にこのアルバムをあらためて味わいながら、鈴木さんの在りし日の姿を思い浮かべ、偲び、悼みたいと思う。レコーディングは主役の鈴木央紹(ss, ts)を軸に、大まかに大野雄二(elp)、渡辺直樹(elb)、川瀬正人(perc)、近藤和彦(bs)、数原晋(tp)、中川英二郎(tb)らが参加した、大野さんを中心としたゴージャスなセッションと、石井彰(p)、安ヵ川大樹(acb)がサイドメンを務めたアコースティックなパフォーマンスに分けられる。江藤良人(ds)は、すべてのテイクをサポート。さらに金子雄太(org)、馬場孝喜(g)が、ふたつのスタイルを往来する。このレコーディング・メンバーからして、本作が鈴木さんの多彩な音楽性を披露するショーケース的作品であることが、容易に想像できる。
アルバムは唯一のジャズ・スタンダーズ「ラヴ・フォー・セール」で幕を開ける。云わずと知れたコール・ポーター作曲の、1930年のミュージカル・ナンバー。その独特のコード進行故か、多くのジャズメンが採り上げている。名演といえば、鈴木さんも影響を受けたというキャノンボール・アダレイの『サムシン・エルス』(1958年)がすぐに思い出される。しかしここではラテン・ファンク風のアレンジが意表を突く。鈴木さんのテナーも、いつもより闊達だ。途中から4ビートにモジュレートするところもゴキゲン。ホーンのバッキングがリッチ、トロンボーンのソロは痛快、ハモンドも軽妙、ドラムスは気炎を揚げる。まさに鈴木×大野の真骨頂が発揮された、鷹揚なジャズがここにある。
2曲目の「ストレンジ・アイラッシュ」は、鈴木さんが前述の韓国での活動期に書いた曲。シックで落ち着いた雰囲気のボサノヴァ。アンエクスペクテッドなコード進行が心地いい。ソプラノの清涼感に溢れた音色に、こころを奪われる。ギターとピアノのソロも流麗で、独特の空気感を生み出している。3曲目の「マイ・シェリー・アモール」は、シンガーソングライター、スティーヴィー・ワンダーによる1969年のヒット曲。やはりリズム・アンド・ブルースと4ビートが交錯する。テナー、ギター、ハモンドと、行雲流水のごとく展開されるソロが爽やかだ。後半の鮮やかな転調と、オーバーダブによるソプラノとテナーとの掛け合いが、気が利いている。なおこの曲は、NTV系「NNNストレイトニュース お天気」のテーマ・ソングとなった。
4曲目の「人間の証明のテーマ」は、大野さんによる1977年の映画主題曲。表現法においては、難曲である。なにせテーマが“まぶたの母”だから、一歩誤るとド演歌になりかねない。鈴木さんはもちまえセンスのよさで、ブルージーな美しいララバイに仕上げた。テナーのスモーキーかつパッショネイトなエクスプレッションが、実に素晴らしい。その一意専心のプレイが感動を呼ぶ。広がりのあるピアノ演奏も、こころに残る。5曲目の「ターン・イット・アップ」は、大野さんの書き下ろし。ブラスが煌びやかなファンキー・チューン。ギターとハモンドもワイルドな躍動感を放つ。それにもましてテナーのブルース・フィーリングが横溢するエキサイティングなプレイが、なんとも凛々しい。
6曲目の「素晴らしき恋人たち」は、1963年にバート・バカラックが作曲した異色のジャズ・ワルツ。ここではテナーがエレガントでクールなセンシビリティとサウンドを発揮。イントロのベース・ソロの乾いた感じ、ハモンドのシンプルでモダンな歌いまわしが都会的なイメージを強調する。7曲目の「ゲット・アヘッド」は、鈴木さんによる4ビート・ナンバー。軽快なテンポに乗って、テナーが圧倒的なテクニックと多彩な表現力を流露する。ギターとピアノのソロも、ストレート・アヘッドに展開。8バースにおけるドラムスもパワフルだ。ラストの「パッセージ・オブ・デイ」は、ライヴのクロージングでお馴染みの鈴木さんのオリジナル。ゆったりしたゴスペル調のロック・ビートのなか、テナーをはじめピアノ、ベース、ギターもカーテンコールに応える。ぼくは思わず拍手喝采しながら「ありがとう、鈴木さん──」と、ひとり呟くのであった。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント