人間性が伝わってくるような、温もりが感じられる、ゲイリー・マクファーランドの素晴らしき音世界
 Album : Gary McFarland・Peter Smith / Butterscotch Rum (1971)
Album : Gary McFarland・Peter Smith / Butterscotch Rum (1971)
Today’s Tune : All My Better Days
音楽にヒューメインな響きを有する──そこが好き
ぼくのもっと敬愛する音楽家は、デイヴ・グルーシンだ。これまでに、何度も云ってきた。コンポーザー、アレンジャー、キーボーディスト、そしてプロデューサーと、どの側面、どのプロフィールを採り上げてみても、ぼくは常に愛好心がくすぐられ、あわせて彼のことを尊敬の眼差しで見つめてしまうのである。それだけではない。ほんとうに好きになるというのは、まさに恋愛感情と一緒で、もっと直感的なこころの作用。そもそも、ひとの理性や感情にうったえる音楽というものについて、好きになる理由を説いたとしても、それはあとづけされたものに過ぎないのではないだろうか?
強いて云えば、ぼくはグルーシンの音楽がもつ風愛が好き──ということになる。つまり、彼の創り出す音世界に触れたときに感じる質感に、得も云われぬ心地よさを覚えるわけだ。しかもそれは、ただ気持ちいいだけではなく、まるで彼の人間性が伝わってくるような、温もりさえ感じさせるのだ。彼の代表作『ワン・オブ・ア・カインド』(1978年)のバック・カヴァーに掲載された推薦文のなかで、あのクインシー・ジョーンズが「このオトコのこころは大きく開いている──」と云っている。まさに、その音楽性を表現するのに実に巧妙で的確なことばだと、ぼくは思う。
ところで、これは飽くまでぼくの受けた印象だが、音楽にヒューメインな響きを有するという点で、グルーシンと共通するアーティストがいる。コンポーザー、アレンジャー、ヴィブラフォニスト、そしてヴォーカリストでもあるゲイリー・マクファーランドがそのひと。彼は非常に短い期間(およそ11年間)に、ビッグ・バンド、ジャズ・コンボ、ボサノヴァ、ジャズ・ロック、ソフト・ロックなど、様々なスタイルの音楽作品を世に送り出している。なかにはシリアスな大作もあるし、大胆なまでにポップな感覚やラウンジ・テイストを取り入れた作品もある。
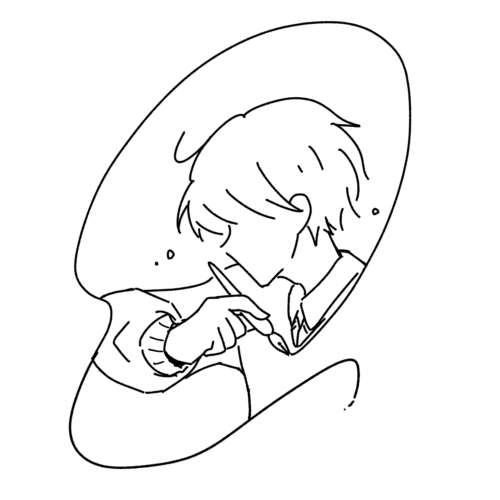
それでも、時にシャープであり時にソフトでもある、マクファーランドが生み出すとてもクールなサウンドからは、一貫して彼の温かな人柄が伝わってくるのだ。その音楽に素朴な面と洗練された面が共存しているところも、グルーシンに非常に似ている。実際に音楽だけではなく、マクファーランド本人も人間として豊かな情緒に溢れたひとだったのだろう。「ただ一緒にいるだけでも楽しくなってくる」「だれからも好かれ、自然にミュージシャンが集まってきてしまう」と、過ぎ去った日々を回顧するのは、日本を代表するアルト奏者の渡辺貞夫。渡辺さんも参加したマクファーランドのリーダー作『ジ・イン・サウンド』(1965年)の、日本盤ライナーノーツでのこと。
思い返せば、ぼくがマクファーランドの音楽に興味をもつキッカケは、渡辺さんのレコードだった。ジャズ作品としては異例の大ヒットとなった『カリフォルニア・シャワー』(1978年)がそれ。このアルバムのなかにマクファーランドが作曲した「デザート・ライド」という曲が収録されている。白熱するセッションをちょっとクールダウンするような、軽やかなラテン調の曲。どこかエキゾティックで、まるで夕暮れに吹く少しだけ涼やかな乾いた風をイメージさせる。とにかくアルバムのなかでは、ひときわ異彩を放っていた──。それから間もなく、ぼくはマクファーランドの音楽にすっかり惚れ込むことになる。
サウンドからは伊達好みの気風さえ感じられる──そこも好き
そういえば、渡辺さんとグルーシンのコラボレーションは有名。上記の「デザート・ライド」の緊張をほぐすような、それでいてリズミカルで爽快なフェンダー・ローズの演奏は、グルーシンによるもの。音楽の世界においても、あらゆるものが因と縁とによって存在しているのかも──おっと、これは少々こじつけ。しかしながら、自分の敬愛するひとやものは、意外なところで相互に関係しあっていたりするもの。それを発見したとき、勝手気ままなぼくは、ちょっと嬉しくなるね。気ままといえば、マクファーランドもたいへん気ままなひとだったようだ。
ロサンゼルス出身のマクファーランドが音楽をはじめたのは、兵役に就いていたときというから、かなり遅いほう。トランペット、トロンボーン、ピアノなどを手にしたが、ぜんぶ中途半端でやめてしまう。除隊後も四つの大学を転々とした。いやいや、ホント気ままだね。そんな彼も観念したのか、サン・ホセの短大に通っているとき、フルート奏者のサンチャゴ・ゴンザレスに謗りと激励を受けながら、ヴィブラフォンの奏法と作曲法を学んだ。バークリー音楽院では、ジョン・ルイス(p)、ハーブ・ポメロイ(tp)に師事し、アレンジャーを目指す。また同校では、のちによきパートナーとなるガボール・ザボ(g)とも出会っている。
デビュー作はヴァーヴ・レコードからリリースされた『努力しないで出世する方法』(1961年)。人気ブロードウェイ・ミュージカルのジャズ・ヴァージョン。ポメロイも参加した、軽妙洒脱なビッグ・バンド作品だ。このアルバムを皮切りに、マクファーランドの快進撃はつづく。ヴァーヴとインパルス!を中心に、立てつづけに吹き込みを残している。なかでも、ジョン・ルイスの『エッセンス』(1962年)、ビル・エヴァンスをソロイストとして起用した『ゲイリー・マクファーランド・オーケストラ』(1963年)、スティーヴ・キューンとのコラボレーション作『10月組曲』(1967年)では、各々のピアニストの個性をうまく引き出しつつ、瀟洒なオーケストラ作品に仕上げていて、彼のセンスのよさが窺える。
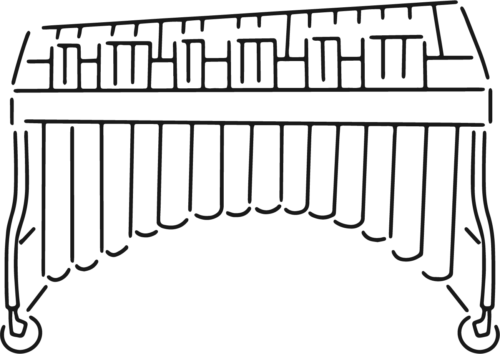
オーケストラといえば、ヴァーヴから『13』(1966年)というアルバムがリリースされているが、これは『Eye of the Devil』というイギリスのホラー映画(日本未公開)のサントラ盤。このアルバムを聴くと、マクファーランドのオーケストラのスコアリングには、実に巧みな表現方法を有することがわかる。おどろおどろしさを出しつつも、クールで美しい。その垢抜けた美的感覚は、まさにグルーシンのそれに共通する。特に「“13”のテーマ」は人気曲で、セルフ・カヴァーが『ソフト・サンバ・ストリングス』(1966年)に収録されているほか、ジミー・スミス(org)&ウェス・モンゴメリー(g)、オルガニストのビリー・ラーキン、それにリー・リトナー(g)も採り上げている。
以上の作品からもわかるように、マクファーランドといえば作編曲家としてのインパクトが強い。では、ヴァイブ奏者としてはどうだったのかというと、これが案外高い技術と技能を有するひとだった。でも、決してマレットで激しく音板を叩きまくったりはしない。ぼくには、まるで無頓着を装いながら、実は巧みで余裕のあるプレイを心がけているように思えてしまう。それが、彼の美学とでもいうように、サウンドからは伊達好みの気風さえ感じられるのだ。こんなにお洒落なミュージシャンは、なかなかいない。あの天才、マイク・マイニエリ(vib)をして強い影響を受けたと云わしめるほど。そんな上手い演奏は、めずらしくスモール・コンボで吹き込んだ『ポイント・オブ・ディパーチャー』(1963年)で確認できる。
コマーシャリズムのいじましさとは無縁──ここがスゴイ
いっぽう、ジャジーなアルバムも然ることながら、マクファーランドといえば、渋谷系サウンドにも影響を与えた、個性的なラウンジ・ミュージック作品を忘れるわけにはいかない。そのはじまりは『ソフト・サンバ』(1964年)というアルバム。ビートルズの曲や映画音楽が積極的に採り上げられているが、まったく原曲とは違ったアレンジがなされている。マクファーランド自身によるスキャット、口笛、そしてヴァイブが織りなすセンシティヴなサウンド・タペストリーは、唯一無二のもの。その爽やかで寛いだ雰囲気に、リスナーはただただ身を委ねるのみ。
まもなくマクファーランドは、ガボール・ザボとのコラボーレーション作『シンパティコ』(1966年)や全曲オリジナルの『スコーピオ・アンド・アザー・サインズ』(1968年)などで、ジャズやラテンだけでなくポップス、ロック、R&Bに至るまで、あらゆるジャンルの音楽の要素を採り入れるようになっていく。そのファンキーでヒップなサウンドは、もはやジャズという枠には収まり切らないものだった。そんな折、ついに彼はザボ、カル・ジェイダー(vib)とともにスカイ・レーベルを立ち上げる。第一弾の『ダズ・ザ・サン・リアリー・シャイン・オン・ザ・ムーン?』(1968年)で、彼はすでに4ビートに別れを告げていた。なんといってもチャック・レイニーがベースを弾いているくらいだから──。
スカイ・レーベルでのマクファーランドの作品のクレジットを観ると、レイニーをはじめ、ウォーレン・バーンハート(key)、グラディ・テイト(ds)、エリック・ゲイル(g)、ジョー・ファレル(sax)、ランディ・ブレッカー(tp)、ヒューバート・ロウズ(fl)、アイアート・モレイラ(perc)など、のちのフュージョン・シーンで活躍することになるアーティストの名前が散見されて、思わずニヤニヤしてしまう。たとえば、社会的メッセージ性の高い異色作『アメリカ・ザ・ビューティフル』(1968年)などは、リズムやグルーヴはジャズ・ロックやR&Bのものだけれど、俯瞰するとクロスオーヴァー/フュージョンの傑作とも受け取ることができる。

では、それがぼくにとってのモスト・フェイヴァリット・アルバムかというと、実はそうではない。マクファーランドの作品はぜんぶ好きだけれど、とりわけ好きなのは、詩人でイラストレーターのピーター・スミスと共演した『バタースコッチ・ラム』(1971年)。マクファーランドの最後のリーダー作だ。異色といえば、こちらのほうが異色。いや、異形と云ったほうがいいのかもしれない。作曲とアレンジは、すべてマクファーランドによる。作詞は全曲、スミスが担当。ヴォーカルはふたりで仲よくリードを分け合っている。これまでになかった点といえば、インストゥルメンタルが一曲もないこと。そして、ヴィブラフォンの演奏がないことだ。
それでも本作は、強くマクファーランドを感じさせる。ソフト・ロックのシンガーを彷彿させるメランコリックなヴォーカルは、とても上手いとは云えないけれどワルくはない。サウンド的には、ときにロックンロール風であったり、フォーキーであったりするのだけれど、どこか都会的でソフィスティケーテッドな響きがある。参加ミュージシャンを観ると、常連のキーボーディストであるバーンハートをはじめ、サム・ブラウン(g)、トニー・レヴィン(b)、ジョージ・ヤング(reeds)、ロニー・キューバー(reeds)など、その後マイク・マイニエリが率いるフュージョンの先駆的グループ、ホワイト・エレファントのメンバーの名が連なる。思わず「やっぱり」と呟きそうになる。
ではなぜ、ぼくが本作をマクファーランドの作品のなかで、もっとも愛聴するのかというと、冒頭で述べたように、音楽がもつ風愛が好きだから。しかも、その音楽にはヒューメインな響きがある。つまり、マクファーランドの人間性が伝わってくるような、温もりが感じられるというわけだ。とりわけ「オール・マイ・ベター・デイズ」と「ダンス・ウィズ・ミー」は大好きなのだが、いかがだろう、ぼくにはそこにデイヴ・グルーシンの影が見えるのだけれど──。マクファーランドは38歳にして夭折の音楽家となったが、もしも彼がもっと長く生きていたら、間違いなくフュージョン・シーンは大きく変わっていただろう。たとえば、コマーシャリズムのいじましさとは無縁の音楽として──。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント