単なるBGMには終わらないオーセンティックなフュージョン・ミュージックが展開されたアール・クルーのデビュー作『アール・クルー』
 Album : Earl Klugh / Earl Klugh (1976)
Album : Earl Klugh / Earl Klugh (1976)
Today’s Tune : Wind And The Sea
チェット・アトキンスからの影響とアコギへのこだわり
アール・クルーがアルバム・デビューを果たしたのは1976年のことで、いまから考えると当時のフュージョン・シーンにおいて、かなり特異な存在感を放っていたと思う。ギターといえばフュージョンという音楽ジャンルでは花形楽器だが、彼が弾いていたのはエレクトリック・ギターではなくナイロン弦のギター。1990年代にフュージョンから派生したスムース・ジャズが主流になると、アコースティック・ギターをメイン楽器とするアーティストも珍しくなくなったけれど、クロスオーヴァーがよりコマーシャルなサウンドへと移行したフュージョンがもてはやされていた時代では、ガットを指先ではじいて鳴らしていたのはクルーくらいのものだった。フュージョンといえば、ギブソンやアイバニーズのエレクトリック・ギターだったのだ。
当時のフュージョン系スター・ギタリストといえば、リー・リトナー、ラリー・カールトン、アル・ディ・メオラあたりだろうか。リトナーもカールトンもアコースティック・ギターを手にするが、どちらかといえばサブ楽器として使用している印象が強い。ディ・メオラは、エレクトリックとアコースティックとの両方のギターを駆使して個性的な音楽を生み出していたけれど、アコースティック・ギターを使用するのは、自己のサウンドに地中海地方のフォーク・ミュージックやフラメンコ音楽を採り入れるときだった。アコースティック・ギター1本で、だれもが親しめるようなポップ・インストゥルメンタル風のフュージョンをプレイしていたのは、やはりクルーしかいない。その点、彼の音楽はスムース・ジャズの原点と云える。
そんなクルーにも短期間ではあるが、エレクトリック・ギターを弾いた時期がある。いまでは信じられないけれど、彼はあのリターン・トゥ・フォーエヴァーに在籍していたことがある。云うまでもなく、ジャズ・ピアニスト、キーボーディストのチック・コリアが率いたバンドだ。1960年代の後半からマイルス・デイヴィスのバンドに参加したコリアが、このモダン・ジャズの帝王のもとでエレクトリック・ジャズの洗礼を受けたことは、あまりにも有名。彼はその影響から、斬新なリズムとビートにイタリア系であるが故の自己の音楽的ルーツを重ね合わせ、新しいサウンドを開拓した。コリアのエレクトリック・ジャズに対する考えや構想が具現化されたバンドが、リターン・トゥ・フォーエヴァーだったのである。
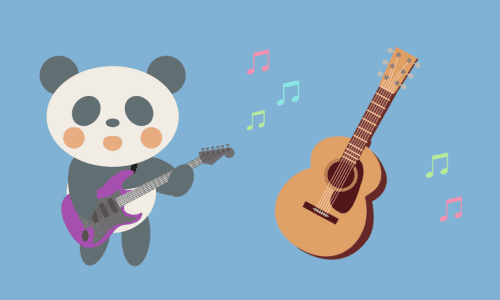
このバンドはスタート時においてラテン音楽のカラーが強かったが、メンバー・チェンジを繰り返すとともに、ロック色が濃厚になっていく。特にビル・コナーズ(g)とレニー・ホワイト(ds)の加入は、バンド・サウンドに大きな変化をもたらした。かいつまんで云うと、それはエレクトリック・ジャズからフュージョンへの進化ということになる。バンドのサード・アルバム『第7銀河の讃歌』(1973年)はまさにロック色の強いフュージョン作品だが、そのレコーディングから1年足らずで音楽性の相違を理由にコナーズが脱退する。そしてその後釜に座ったのが、ほかでもないクルーだったのである。彼はコリアの意向に沿いエレクトリック・ギターを手にするが、なぜか2か月でバンドを脱退している。
脱退の理由は一般的には、クルーが当時病気になった家族を案じたことからと伝えられている。しかしそれはどうだろう?ぼくには、彼が結局アコースティック・ギターへのこだわりを捨てることをできなかったことが、いちばんの要因と思われるのだけれど──。いずれにしても、クルーが参加したリターン・トゥ・フォーエヴァーの発表音源はない。実際にコリア、ホワイト、そしてスタンリー・クラーク(b)らとともに、ロック・ビートに乗ってエレクトリック・ギターを弾ずるクルーの姿を観られなかったのは、ちょっと残念な気もする。なお彼の後任には、前述のアル・ディ・メオラが就いた。バンドは1974年から1976年までの黄金期を迎える。5作目の『ノー・ミステリー』(1975年)においては、グラミー賞も獲得した。
いっぽうクルーは、それ以降アコースティック・ギターのみに集中する。しかもフィンガーピッキングに執着しつづける。サムピックを使用せずに指の爪で弦を弾く彼の演奏スタイルは、ミスター・ギターの異名をとるカントリー・ミュージシャン、チェット・アトキンスのそれを彷彿させる。低音域を親指でミュートしながら、人差し指、中指、薬指でメロディとコードを奏でるという弾きかたは、まさに“チェット・アトキンス奏法”そのもの。実際創出されるサウンドはアトキンスのものとはかなり異なるが、その点クルーは、アトキンスのメソッドを研究した上で独自のスタイルを築いたと云える。彼自身、もっとも強い影響を受けたギタリストとしてアトキンスの名前を挙げている。クルーにとって、アトキンスは少年時代のアイドルだったのだ。
クルーは1953年9月16日、アメリカのミシガン州デトロイト市に生まれた。6歳のときからピアノのレッスンを受けていたが、10歳のときにクラシック・ギターの演奏に転向する。彼は13歳のとき、NBCのテレビ番組『ペリー・コモ・ショー』(1953年 – 1967年)で観た、チェット・アトキンスのギター演奏に魅了された。ずっとあとのことになるが、クルーは自己の4枚目のリーダー作『瞳のマジック』(1978年)のレコーディングにおいて、ダニー・オキーフのカヴァー・ナンバー「グッド・タイム・チャーリー」1曲のみだが、憧れのアトキンスと共演を果たす。その後、今度はクルーのほうがアトキンスのフュージョン・アルバム『アーバン・オアシス』(1985年)において、ゲスト・プレイヤーとして招かれた。
それはともかく、クルーは16歳という若さで早々とレコーディングを経験している。マルチ・リード奏者で作曲家でもあるユセフ・ラティーフがアトランティック・レコードに残した大作『スウィート 16』(1970年)のクレジットに、クルーの名前を見つけることができる。ラティーフはジャズ・プレイヤーだが、ジャズの枠を超えたユニークな作品を発表しつづけたアーティスト。このアルバムもまた然り。ファンキーなジャズ・ロックから前衛的なシンフォニック・ナンバーまで、ジャズというコトバでは云い尽くせない音楽が展開されている。その合間になぜかクルーのソロ・ギターによる「ミッシェル」が収録されている。あまりにも有名なザ・ビートルズのカヴァーだが、15歳の演奏とは思えない味わい深さがある。
脂が乗ってきた時期にあったグルーシンによる好サポート
その後クルーは、ギタリストでシンガーでもあるジョージ・ベンソンのCTIレコード時代のクロスオーヴァー・アルバム『ホワイト・ラビット』(1972年)と『ボディ・トーク』(1973年)とに、立てつづけに参加。前者ではミシェル・ルグランの「おもいでの夏」において、ベンソンを美しいアルペジオやストロークでサポートしている。後者では全面的にリズム・ギターを任されている。さらにクルーは、ブラジル出身のジャズ・シンガー、フローラ・プリンの『ストーリーズ・トゥ・テル』(1974年)にも参加し、音楽シーンにおける知名度を上げた。また彼は、自らの出身地でもあるデトロイトで結成されたソウル・コーラス・グループ、ザ・ドラマティックスのヒット・アルバム『ドラマV』(1975年)もサポートした。
以上のように16歳から22歳までの間に、クルーはプロ・ミュージシャンとして実に濃密な時間を過ごしたと云える。そして彼は1976年の1月から2月まで、カリフォルニア州バーバンク市のケンダン・レコーダーズ・スタジオにおいて、いよいよ初リーダー作の制作に打ち込むことになる。当時のクルーは、貴重な経験を経てきただけに、22歳にしてすでにひとかどの作曲家、演奏家として成長を遂げていた。この稀に見る逸材にいち早く目をつけたのは、コンポーザー、アレンジャー、キーボーディストとして多忙を極めていたデイヴ・グルーシンだった。彼はモダン・ジャズをプレイしていたころからの僚友、ドラマーのラリー・ローゼンとともに、ちょうど新しいプロダクションを立ち上げるところだった。
このレコーディングにおいてクルーは、楽曲のアレンジメントを全面的にグルーシンに委ねている。リズム録りが終わったあと、カリフォルニア州ロサンゼルス市のレコード・プラント・スタジオにおいて、オーケストラ・パートのオーヴァー・ダビングが行われた。6名のホーンズと14名のストリングスで構成されたバッキング・オーケストラの吹き込みでは、グルーシンがタクトを振った。さらにミキシングにはレコード・プラントに加えて、おなじくロサンゼルスにある1970年代に独自の音響設計で人気を博したウェストレイク・オーディオが使用された。エンジニアはレコード・プラントのヌシ的存在、名手フィル・シアーが務めている。そんな贅の限りを尽くしたのは、ユナイテッド・アーティスツ・レコードのA&Rエグゼクティヴ、ジョージ・バトラーだ。
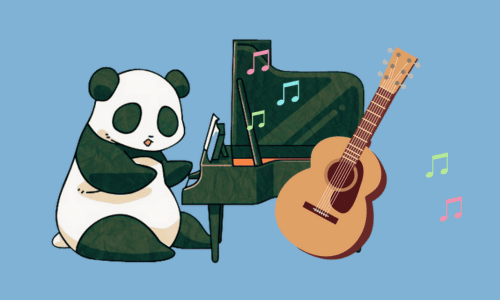
さて、ここからは少々わき道に逸れるが、グルーシンのハナシをさせていただく。グルーシンとローゼンは、クルーをアルバム・デビューさせる以前に、カリブ海のセント・トーマス島出身のシンガーソングライター、ジョン・ルシアンの作品をプロデュースしていた。基本的にソウル・ミュージックでありながらブラジルをはじめとする中南米の音楽の風味が香るサウンドと、ジェントルなバス・ヴォイスによる滋味豊かな歌唱が、なんともユニークな音楽を創出している。ルシアンの『ラシーダ』(1973年)『マインズ・アイ』(1974年)『ソング・フォー・マイ・レディー』(1975年)といった3枚のアルバムでは、グルーシンならではのサウンド・テクスチュアとグルーヴ・フィーリングが、より音楽のクオリティを高めている。
ルシアンのアルバムを制作するにあたってグルーシンとローゼンは、すでにデュオ・クリエイティクス(グルーシンのペンによる同名曲あり)という名称のプロダクションを立ち上げていた。ふたりは新たな飛躍へ向けて、あらためて原盤制作会社、グルーシン/ローゼン・プロダクションを発足させる。このオリジナル・レコードを供給するささやかなプロダクションは、のちにアリスタ・レコード傘下でGRPレーベルをスタートさせ、さらに独立してGRPレコードを創設した。それはともかく、グルーシン/ローゼン・プロダクションはその草創期に、ノエル・ポインター(vln)、パティ・オースティン(vo)、それに横倉裕(key)といった大器を発掘している。そんな才能に溢れた新人アーティストのなかで、先陣を切ったのがクルーだった。
グルーシンは1960年代後半から映画やテレビシリーズに楽曲を提供していたが、クルーをアルバム・デビューさせる直前に彼の代表作である映画『コンドル』(1975年)の音楽を手がけている。グルーシンはこの作品でフィルム・スコアに本格的なフュージョン・ミュージックを採り入れて、かつてない成果を上げた。キャピトル・レコードからリリースされたサウンドトラック・アルバムは、レコーディングにリー・リトナー(g)、ヒュー・マクラッケン(g)、チャック・レイニー(b)、ハーヴィー・メイソン(ds)、ラルフ・マクドナルド(perc)、トム・スコット(ts)といった、フュージョンの人気プレイヤーが参加していることから、日本でも発売当初から音楽ファンの間で大きな話題となった。
またおなじころグルーシンは、テレビシリーズ『刑事バレッタ』(1975年 – 1978年)のテーマ曲を担当。当初はインストゥルメンタルだったが、あとのシーズンでは女性シンガーソングライターのモーガン・エイムズによって歌詞がつけられた。ヴォーカルはアメリカを代表するエンターテイナーのひとり、サミー・デイヴィス・ジュニアが務めた。この「バレッタのテーマ(キープ・ユア・アイ・オン・ザ・スパロウ)」はアメリカでは人気曲で、R&Bシンガーのメリー・クレイトンやディスコファンク・バンドのリズム・ヘリテッジ、それにラテン・ロック・バンドのエル・チカーノなども採り上げている。グルーシンは『ディスカヴァード・アゲイン!』(1976年)でセルフカヴァーし、クルーにも『フィンガー・ペインティング』(1977年)で演奏させている。
とにもかくにもこのころのグルーシンといえば、その長いキャリアにおいてちょうどサウンド・クリエイトに脂が乗ってきた時期にあった。そんなときに始動したグルーシン/ローゼン・プロダクションの作品に空振りなどあろうはずがない。さきに挙げたクルーを含むフレッシュなアーティストたちの魅力的なアルバムも然ることながら、デビュー時からグルーシンがサポートしていたギタリスト、リー・リトナーの(シンフォニック・ジャズ・スウィートを含む)スケールの大きな作品『キャプテンズ・ジャーニー』(1978年)、その独特の音楽性がまるごと詰め込まれたグルーシンのリーダー作『ジェントル・サウンド』(1978年)といったフュージョン・シーンにおけるマスターピースまで制作されている。
グルーシンとクルーとのレアな化学反応から生まれた作品
なおグルーシンが手がけた映画音楽のサウンドトラック・アルバム『ボビー・デアフィールド』(1977年)『出逢い』(1979年)『黄昏』(1982年)などは、レーベルこそGRPではないが3枚ともグルーシン/ローゼン・プロダクションの作品だ。いずれにしてもこのプロダクションによって制作されたアルバムは、グルーシンのフレキシブルでヒューメインな音楽性が色濃く反映されたクオリティの高い作品ばかりである。クルーのデビュー作『アール・クルー』(1976年)をはじめ、それにつづく『リヴィング・インサイド・ユア・ラヴ』(1976年)と『フィンガー・ペインティング』(1977年)といった3枚のアルバムは、グルーシンとローゼンがプロデュースしたものであり、グルーシンがアレンジと指揮を務めている。
これらの3枚は、ユナイテッド・アーティスツ・レコード傘下にあったブルーノート・レコードからリリースされた。ところでクルーの楽曲といえば、わが国ではこれまでにテレビ・ワイドショーのテーマ曲、ラジオ番組のオープニングないしエンディングのテーマ曲、ラジオの交通情報のBGM、そしてなんといってもテレビやラジオの天気予報のBGMとして、無節操なまでにたくさん使用されてきた。それは当時のクルーのパフォーマンスがフュージョンというよりも、どちらかといえばソフトでポップなインストゥルメンタルという印象を与えたからだろう。柔らかな感触のアコースティック・ギターが奏でる、優しいメロディック・ラインは、耳あたりのいい音楽として多くの日本人に歓迎されたのである。
グルーシン/ローゼン・プロダクションと袂を分かったあとのクルーは、ブッカー T. ジョーンズ、デヴィッド・マシューズ、クレア・フィッシャーといったアレンジャーの協力を得て、つぎつぎにヒット作を生み出していく。クルーの演奏は相変わらず淀みなく美しい。しかしながらトータル・サウンドは、次第にミドル・オブ・ザ・ロード(MOR)的な様相を呈するようになっていく。クルーのインプロヴァイザーとしての魅力が堅実に引き出されていたのは、ボブ・ジェームスとのコラボ作品くらいで、それ以外の作品では即興演奏がほんの序の口で終わることが多く、何よりも聴き心地のよさが重視されていた。それにくらべてグルーシンが手がけた3作品では、単なるBGMには終わらないオーセンティックなフュージョン・ミュージックが展開されていた。
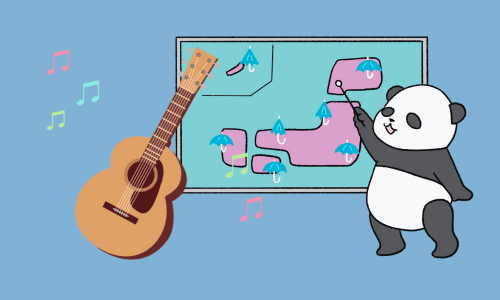
グルーシンは、1967年からセルジオ・メンデスのオーケストレーションをずっと担当しいたが、1973年からはそれと並行してクインシー・ジョーンズの片腕としても働いていた。つまりグルーシンは、ブラジリアン・ミュージックとソウル・ミュージックから同時に影響を受けており、クルーの作品を手がけたときにはすでに、彼の音楽性はヴァーサティリティに富んだものとして結実していたのである。そんな3作品のうちもっとも完成度が高いのは『フィンガー・ペインティング』であり、個人的にいちばん好きなのは『リヴィング・インサイド・ユア・ラヴ』だけれど、ソング・セレクションとアレンジにすこぶる意匠が凝らされたのはなんといっても『アール・クルー』だろう。
前述のとおり、本作は全編にわたってカリフォルニアで吹き込まれたので、クルーをサポートするリズム・セクションは西海岸のミュージシャンで固められている。内訳はデイヴ・グルーシン(key)、リー・リトナー(g)、チャールズ・ミークス(b)、ルイス・ジョンソン(b)、ハーヴィー・メイソン(ds)、ラウジール・デ・オリヴェイラ(perc)となっている。オープニングの「ラス・マノス・デ・フュエゴ」はグルーシンのオリジナル。ミステリアスなテーマ部からサスペンス映画の楽曲を彷彿させる後半部へと進行する。終始ジョンソンのベースがファンキーなビートを刻むなか、クルーはスパニッシュなムードとジャジーなフレージングでスリリングな演奏を繰り広げる。
一転して「フィラデルフィアより愛をこめて」は、ブライトでリズミカルなポップ・ナンバー。クルーの故郷でもあるデトロイト出身のヴォーカル・グループ、ザ・スピナーズのヒット曲だ。はじけるようなメイソンのドラムス、ヴィヴィッドなメロディとブルージーなアドリブを奏でるクルーのギターが、爽やかな空気をつくっていく。つづくカリプソ風の「アンジェリーナ」は、いかにもクルーらしいオリジナルのメロウ・ナンバー。彼のスウィートでセンシティヴなギター・サウンドが絶品だ。グルーシン、ジョンソン、メイソンの共作「スリッピン・イン・ザ・バック・ドア」は、ブラス・サウンドが活かされたジャズ・ファンク。のちにリトナーやグルーシンもカヴァーしている。クルーは首尾一貫ソウルフルなフレーズを力強く紡いでいく。
クルーの自作「ヴォネッタ」では、アップテンポのサンバのなかで名インプロヴァイザーとしてのクルーが飛翔する。グルーシンによるローズのバッキングも軽妙。シンガーソングライター、ニール・セダカの大ヒット「雨に微笑みを」では、クルーの小気味いいギターも然ることながら、バウンスするドラムス、しなやかなギター・エフェクト、大胆な展開を見せるストリングスなどが際立つ。グルーシンによるアレンジの勝利だ。クルーが敬愛するビル・エヴァンスの「ワルツ・フォー・デビイ」では、前半は彼のソロ・ギターがフィーチュアされる。美しいコード・ヴォイシングやお得意の高速アルペジオが堪能できる。後半はグルーシンによる鍵盤類とストリングスが加わる。グルーシンのリハーモナイズが至高を極める。ミニモーグの音色も印象的だ。
ラストの「風と海」もクルーのオリジナル。もともとシンプルなモティーフが、グルーシンのクリエイティヴな味つけによって、色鮮やかな曲に仕上げられている。クロスするオフビートなリズム、サンバホイッスル風のローズ、ユニゾンするフルートとローズ、ミュート・トランペットとギター、ポルタメントの効いたストリングス、後半のホーン・セクションによるオブリガート、そして繰り返されるモジュレーションと、まるでグルーシン・サウンドの宝石箱のようだ。この煌めくアンサンブルに、クルーはただ溶け込んでいくしかなかった。その点にまったくイヤミは感じられず、むしろスッキリとしたあと味が残される。それはグルーシンのマジックでもあり、クルーの22歳にしてもち得たオーラでもある。本作は、そんなレアな化学反応から生まれた。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント