ロマンティックでスタイリッシュな恋愛映画『恋におちて』──数々のニューヨークの観光名所で流れるデイヴ・グルーシンの情熱的で甘美な音楽
 Album : Dave Grusin / Falling In Love (2014)
Album : Dave Grusin / Falling In Love (2014)
Today’s Tune : Catch The Train
不倫は文化?──日本の「不倫モノ」がオマージュしたアメリカ映画
そのむかし「不倫は文化」というフレーズが、世間に広く用いられた。1996年のことだ。翌年には「失楽園する」という云いかたも、もてはやされた。こちらは1997年の流行語大賞に選ばれるほど、ブームを巻き起こした。また、ユーキャン新語・流行語大賞といえば、2016年に「ゲス不倫」がトップテンにランクインした。これらは飽くまで一部の例に過ぎずない。いまでも毎朝のように、テレビのワイドショーを見るともなしに見ていると、やたらと業界を問わず著名人の不倫騒動が報じられていて、うんざりした気持ちになる。慌ただしく身支度を整えているときでもあり、余計に陳腐な話題に思えてしまう。当事者にとってみれば、深刻な問題なのだろうけれど──。
それにしても、いつごろから日本人は、こんなに不倫の話題が好きになったのだろう。確か「金妻ブーム」あたりから、不倫の話題がトレンディな扱いをされるようになったのではなかったかな。「不倫」というコトバが頻繁に使われるようになったのも、このブームがキッカケだったように思われる。それ以前は、かの三島由紀夫先生のベストセラー小説からの影響で「よろめき」というコトバが、よく使われていた。いまではすっかり死語になっていて、若いひとたちは笑ってしまうだろうけれど、1970年代までは平然と「よろめき夫人」とか「よろめきドラマ」とか云われていたのだ。とにもかくにも、TBSによって放送された『金曜日の妻たちへ』のシリーズ(1983年 – 1985年)が、テレビドラマに「不倫モノ」というジャンルを確立したことは間違いない。
個人的な見解では「不倫は文化」は、浅はかな了見と思われる。確かに社会組織ごとに不貞行為の定義に差異はあるだろうけれど、それを文化の違いと云って片付けてしまったらそれまでだ。なぜなら不倫を罪悪と強く感じるのは、集団や社会の秩序よりも、ひととして従うべき道義的な規範を破ってしまうという点にあるのだから。それゆえ文学作品や映像作品の題材としてよく「不倫」が採り上げられ、しばしば名作との誉れ高き作品が生まれるのだと、ぼくは思う。しかもそれらは、ただ不倫の是非を問うものではなく、不倫という状況に置かれた人間の心理がどのように働くか、それとの結びつきから具体的にどのような行動を起こすかを、言語や映像で芸術的に表現しているのである。
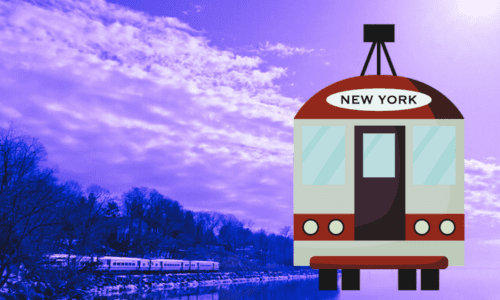
なんでこんなハナシをしたのかというと、1984年公開のパラマウント映画『恋におちて』のなかのあるシーンが、強く印象に残っているから。物語の後半のほうで、主人公の男が妻に問い詰められて、通勤列車で出会った女性との恋について告白する。なんの過ちもおかしてはいないと申し開きをする夫に、妻はいきなり平手打ちをする。パシッという乾いた音を、ぼくはいまでも忘れることができない。男は女性と深い関係に至ることはなかったのに、なぜビンタを食らったのか。実は妻にとっては、夫と女性の間になにもなかったことのほうが、却ってショックだった。つまり妻は、夫とその女性の恋が本物であることを悟ってしまったのである。
ひとは、たとえ踏み行うべき道からはずれることを思いとどまっても、こころで不倫してしまうことがある。映画『恋におちて』では、そんな互いに家庭をもつ男女のプラトニックな不倫が、きめ細かく描かれている。ロバート・デ・ニーロとメリル・ストリープといった名優コンビが演じる、40そこそこ、30代なかばの大人の男女が、まるで10代の少年少女のようなまじりけのない恋ごころを寄せ合うのに、思わず口もとが緩む。不倫ではあるけれど、ふたりのあまりにもピュアな恋愛模様に、観客もついつい温かい気持ちで見守ってしまう。しかもそのロケーションといえば、グランド・セントラル駅、リゾーリ・ブックストア、サックス・フィフス・アヴェニュー、トランプ・タワーといった、ニューヨークの観光名所のオンパレード。とてもロマンティックに映るのだ。
この映画『恋におちて』は、前述のTBSドラマのシリーズのうち『金曜日の妻たちへIII 恋におちて』(1985年)においてオマージュされている。このドラマでは映画の内容に対してリスペクトするだけではなく、映画本編の映像がそのまま挿入されることもあった。また、ニューヨーク郊外のウェストチェスター郡へと通じるメトロノース鉄道のハドソン・ラインは、映画において重要な舞台となっているが、ドラマではその通勤電車のシーンが新幹線で再現されたりしている。なお、ドラマの主題歌、シンガーソングライターの小林明子が歌った「恋におちて -Fall in love-」(1985年)は、ミリオンセラーを記録した。日本で映画『恋におちて』が公開されたのは1985年3月で、ドラマ放送の開始が同年8月のことだから、ほぼリアルタイムでのオマージュということになる。
映画のオープニングで流れるのはグルーシンの既存の曲だった
そういう意味では、映画『恋におちて』は、わが国の「不倫モノ」というドラマ・ジャンルを後押しする形となった。映画がモダンでロマンティックでスタイリッシュなつくりだったから、余計に「不倫」が時代の趨勢のごとく扱われたのかもしれない。そう考えると、10年後に「不倫は文化」というフレーズが飛び出してくるのも、不思議なことではない。それだけ、この映画の影響によって多くのひとがこころを動かされ、恋愛の形に対する考えを変容させられたのである。さらに付言すると、この作品に対する不倫恋愛映画の傑作というような云いかたは、あまりにも薄っぺらな表現と思われるし、そのなんとも味気ない響きは当を得ていない。なんといっても監督のウール・グロスバードは、純愛の心情を実に丁寧に描写しているのだから──。
道徳的には決して許される恋ではないが、よこしまな気持ちは少しもない、ただひたむきな愛──そんな傷つきやすくもあり、それに反して優美にさえ映る、切ないまでに深い思いの恋の行方に、繊細な甘美で洗練された音楽が立体感を与える。スコアはデイヴ・グルーシンのペンによる。彼はハリウッドの伝統を汲みながら、いくぶんそこから逸脱するような多様性と革新性をもった作曲家だ。楽曲のテクスチュアにシンプルな面とソフィスティケーテッドな面が共存しているところが、グルーシンの音楽の特徴とも云える。しかも、そのサウンドからは一貫して彼の優しさに溢れたパーソナリティが伝わってくるものだから、いつもただただ惚れ惚れするばかり。ぼくのもっとも敬愛する音楽家だ。
実はぼくは、映画『恋におちて』をはじめて観たとき、いきなり冒頭から意表を突かれた。学生時代に美術系の大学に通う女の子と一緒に、飯田橋佳作座(1988年閉館)において『刑事ジョン・ブック 目撃者』(1985年)との併映で鑑賞したときのことである。鈍感なぼくは、当時はどうしてふたつの作品が二本立て興行されるのか釈然としなかったが、いまになってみると、どちらも許されぬ恋を扱った作品だったと得心がいく。それはともかく、もともと『刑事ジョン・ブック 目撃者』のほうがお目当てだったぼくは、大して期待していなかった『恋におちて』のオープニングで流れた楽曲に、新鮮な驚きを覚えた。それが既存のグルーシンの曲「マウンテン・ダンス」だったからだ。

ご承知のことと思うが、デイヴ・グルーシンは映画音楽の作曲家であるとともに、コンテンポラリー・ジャズのピアニストでもある。サウンドトラック・アルバムと並行して数多くのリーダー・アルバムをレコーディングしている。彼が1978年に発表した『ジェントル・サウンド』(原題は『...One Of A Kind』)は、ぼくにとって音楽のバイブルともいうべき作品。特にアレンジの手法やスコアの書きかたについて、このアルバムから多くを学んだ。それに次いで、それこそレコードが擦り切れるくらい聴いたのが『マウンテン・ダンス』(1980年)。この作品に収録されている楽曲において、ぼくはグルーシンの特徴的なピアノ奏法、主にフィンガリングとヴォイシングを徹底的に研究した。いわばピアノの教科書である。
もうおわかりだろう、映画『恋におちて』のタイトル・シーンで流れるのは、アルバム『マウンテン・ダンス』のタイトル・ナンバーそのものなのである。グルーシンの曲に「スリー・カウボーイズ・ソング」という3パートからなる組曲がある。彼の故郷であるコロラドに伝わる古き好き時代のアメリカン・ミュージックが、コンテンポラリー・ジャズにアダプトされた曲だ。ちょっとノスタルジックな曲調からは、グルーシンの音楽が有するヒューマンな部分の原点を察知することができる。のちに彼のトレードマークともなる「マウンテン・ダンス」も、その系列に連なる曲。メジャーのペンタトニック・スケールを効果的に使ったメロディック・ラインは、フォーキーでクラシカル。こういうジャズっぽくない曲を堂々と書いてしまうところもまた、グルーシンらしい。
コロラド州といえば、13,000年以上まえからアメリカ先住民が住んでいた地域。その南北にはロッキー山脈が突き抜けていて、州全体の平均標高も全米でもっとも高い山岳地帯だ。そんなコロラドのイメージが直線的に伝わってくる「マウンテン・ダンス」を、まさか恋愛映画の導入部で耳にするとは夢にも思わなかった。ところが意外にも、ハドソン川に沿って軽快に走るメトロノース鉄道の銀の勇姿と、この曲のベースやドラムスによる小気味好く繰り返される律動、そしてアコースティック・ピアノによる流麗で格調高い旋律とが、ほどよくシンクロしていた。一緒に映画を鑑賞した女の子も、この曲をいたくお気に召していたもの。なお、グルーシンが音楽を担当した映画で、既存の曲が使用されたのはこれ一度きり。その理由は後述する──。
サウンドトラックCDには未使用の楽曲「メイン・タイトル」も収録
確かに「マウンテン・ダンス」も強く印象に残るのだが、ぼくとしてはメトロノース鉄道の車内やグランド・セントラル駅のシーンをはじめ様々な場面で流れる所謂“ラヴ・テーマ”のほうが気になった。こちらはグルーシンによって映画のために書き下ろされた楽曲だ。彼のフィルム・スコアは、エンニオ・モリコーネやジョルジュ・ドルリューなどからの影響が顕著に感じられるが、このテーマ曲はまるでヨーロッパの映画音楽のように叙情的で哀愁を漂わせている。ここまで胸が締めつけられるような情熱的で甘美な曲は、グルーシンのフィルモグラフィにおいては珍しい。映画全体の音楽は、このスウィートなテーマの変奏で成り立っている。観客の意識に内的主題を深く刻み込んでいくという、グルーシンのおなじみの手法だ。
ところが映画『恋におちて』の音楽は、楽曲のほとんどがフィルムスコアリングによる短めのトラックばかりだったせいか、公開当時はサウンドトラック盤として日の目を見ることはなかった。本作がアカデミー賞に輝くロバート・デ・ニーロ、メリル・ストリープという、ハリウッドの2大スターの共演作品であること、GRPレコードのアーティストとして大活躍し、グラミー賞を受賞した直後のグルーシンが音楽を手がけていることからすると、ちょっと意外でもある。音源が商品化されなかったことからか、まもなく前述のグルーシンのCDアルバムの帯には“マウンテン・ダンス〜映画「恋におちて」テーマ・ソング”と表記されるようになる。また時を移さず、前述の“ラヴ・テーマ”のカヴァーも登場した。
カヴァーを吹き込んだのは、カナディアン・ソフト・ロック系グループ、ハーグッド・ハーディ&ザ・モンタージュのリーダーとして知られる、ピアニスト兼ヴィブラフォニストのハーグッド・ハーディである。彼のオーケストラによるアルバム『ミスティック・モーニング』(1985年)に収録されている「フォーリング・イン・ラヴ」がそれだ。このアルバムは、当時JVCが新しい音楽の提案というコンセプトではじめた“クラッシー・ミュージック”というシリーズの1枚。簡単に云うとハイセンスなイージーリスニング。ハーディのアレンジも決して悪くはないが、いささかイージー過ぎるきらいがある。特にコード・プログレッションが簡略化されていて、グルーシンならではの繊細なフィーリングが死んでしまっている。
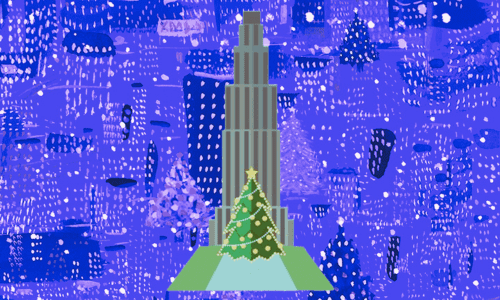
そんなフラストレーションを抱えさせられたまま、30年という膨大な時間が経過する。ぼくなどは、1987年のテレビ放映の際に受像機の音声出力から、その魅力的な劇伴音楽の数々をカセットテープに録音して聴いていたもの。気に入ったスコアは、採譜してピアノで弾いてみたりもした。ところが、そうやって長い年月を経たのち、映画『恋におちて』のファン、ぼくのようなグルーシンのリスペクターの熱い思いは、はからずも成就されることになる。2014年、メディア化されていないサウンドトラックの掘り起こしで定評のあるクリッツァーランド・レーベルが、パラマウント・ピクチャーズでずっと眠りつづけていたマスターテープの音源をついにCD化したのである。
クリッツァーランドはこれまでにも、グルーシンの映画音楽におけるデビュー作『ディヴォース・アメリカン・スタイル』(1967年)をはじめ『天国から来たチャンピオン』(1978年)『月を追いかけて』(1984年)『白く渇いた季節』(1989年)『狼たちの街』(1996年)など、彼のフィルム・ミュージックの貴重な音源をCDとしてリリースしている。おなじころ、フィルム・スコア・マンスリー、ヴァレーズ・サラバンドといったレーベルも、グルーシンのサウンドトラックの発掘に力を注いだ。それは、ハリウッドの映画音楽の枠からはみ出すような、独特な洗練されたセンスをもったグルーシンのスコアが、存在意義のあるものと認められたからだろう。往古来今、グルーシン・サウンドは重宝され高く評価されると、ぼくは信じてやまない。
このCD化により映画『恋におちて』の音楽は、立体的に楽しむことができるようになった。核となる“ラヴ・テーマ”は「シート・テイクン?」「キャッチ・ザ・トレイン」「オールモスト・トゥー・レイト」「トゥゲザー・アット・ラスト」などの楽曲でリアルなものになり、より豊かな深い味わいを感じさせる。さらに、新たな発見もあった。実はグルーシンは、映画の冒頭シーンのためにオリジナルの楽曲を書き下ろしていた。CDには「メイン・タイトル」として収録されている(その他の未使用曲も収録)。ちょうど『喝采の陰で』(1982年)の「メイン・タイトル・テーマ」や『トッツィー』(1982年)の「ある俳優の生活」と似た雰囲気の曲だ。軽妙でウィットに富んだ曲なのだが、ややエキサイトメントが高め。既存の「マウンテン・ダンス」に差し替えられることによって、確かに映像に品格が備わった。そもそも、映像と音楽にそんな品位があれば、題材が「不倫」であるか否かは、もはやどうでもいいことなのである。
記事の更新は、今年はこれが最後。1年間お付き合いいただき、ありがとうございました。2023年も残り数時間、また2024年にお会いしましょう。みなさんに素晴らしい1年が訪れますように──。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント