デイヴ・グルーシンの2000年代唯一のサントラ盤『ディナー・ウィズ・フレンズ』
 Album : Dave Grusin / Dinner With Friends (2001)
Album : Dave Grusin / Dinner With Friends (2001)
Today’s Tune : I Did An Experiment
アカデミー作曲賞を受賞する1988年以前のグルーシンの作品
デイヴ・グルーシン(1934年6月26日 -)のフィルモグラフィをあらためて見つめ直してみると、バド・ヨーキン監督のコメディ映画『ディヴォース・アメリカン・スタイル』(1967年)を皮切りに、2000年代まで銀幕にたくさんの印象的なスコアが残されてきたわけだが、その作品数が圧倒的に多いのは1970年代である。次点は1980年代で、つづいて1960年代が多い。1990年代からは減少の一途をたどり、2000年代に彼が手がけた作品はたったの3本となっている。なおその後は、当時のウェールズ公(チャールズ3世)による環境問題への取り組みが扱われたドキュメンタリー映画『ハーモニー』(2010年)と、5人のティーンエイジャーの冒険が描かれたチャールズ・ミンスキー監督の青春映画『スケーティング・トゥ・ニューヨーク』(2013年)の、2本のみとなっている。
現在グルーシンは90歳という高齢であるが、先ごろ盟友のギタリスト、リー・リトナーとの共同作業で吹き込んだ『ブラジル』(2024年)というアルバムをリリースしたばかり。グルーシンの作品としては、久々に音楽家としての健在ぶりが発揮された力作である。ぼくも本作を聴いて、彼が生み出すグルーヴは、ほかのアーティストではなし得ない、ただひとつのものであると再認識した。そうはいっても、この10年の彼の音楽活動を顧みると、さすがに往時の勢いはない。加齢による演奏能力の衰えを感じさせたり、それ故か自ら第一線から退くような印象を与えるが、これは致しかたない。ぼくはその点を好意的に受けとめていて、グルーシンはいま、自分がほんとうにやりたいことに集中していると解釈する。
そんなわけで今回は、徐々にその作品数が減っていく(あるいは意識的に減らされていく)1990年代から2000年代にかけての、グルーシンのフィルム・スコアを振り返ってみる。そのまえに、まずは1980年代に立ち返る。彼がアカデミー作曲賞を受賞したのは、1988年のこと。ロバート・レッドフォード監督のニューメキシコを舞台にしたファンタジックな社会派映画『ミラグロ/奇跡の地』のスコアが、これまでになく高く評価されたのである。実はそれ以外にも、オリジナル・スコアのノミネートは6回を数える。内訳は『天国から来たチャンピオン』(1978年)『チャンプ』(1979年)『黄昏』(1981年)『恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ』(1989年)『ハバナ』(1990年)『ザ・ファーム 法律事務所』(1993年)となる。
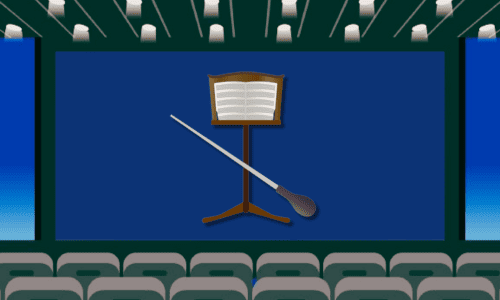
グルーシンの20余年わたる映画音楽の仕事ぶりのなかでも、この『ミラグロ/奇跡の地』は殊に異彩を放つものだった。スコアのモティーフとなっているのは、スペイン文化の強い土地であるニューメキシコ固有のリズムやメロディで、それまでのグルーシンのキャリアにおいて、こういうアプローチははじめてだった。せんずるところこの作品では、アコースティック・ギターやアコーディオンが効果的にフィーチュアされたチェンバー・オーケストラによって、ノルテーニョとヨーロッパの芸術音楽、そしてコンテンポラリー・ジャズがブレンドされた、実にユニークな音楽が繰り広げられているのだ。しかも、その異色のサウンドからは、ちゃんとグルーシンのヒューマン・カインドネスが伝わってくるのだから、素晴らしい。
いずれにしても、当時コンテンポラリー・ジャズの人気アーティストとして活躍していたグルーシンはこの作品において、映画音楽作家としても確固たる地位を築いたと云える。野暮なことを云うようだが、音楽家にとっても賞や栄誉の影響力は大きい。グラミー賞を10回も受賞しているグルーシンだが、映画音楽作家として評価される場合、やはりアカデミー賞のウィナーであることのほうが圧倒的に影響してくる。なにせアカデミーは、世界でもっとも権威のある映画賞。あらゆる意味で、映画の世界に携わる人間にとって、オスカーは無視できない存在なのだ。実際、これを機にグルーシンは映画業界において、これまで以上に注目の的となった。実はそれを裏付けるように、1990年代以降のグルーシンのスコアには、微妙な変化が見られるのである。
いまさら云う必要もないのかもしれないが、グルーシンの音楽家としてのキャリアは、ジャズ・ピアニストからスタートする。彼はエピック・レコードに、ピアノ・トリオ作『サブウェイズ・アー・フォー・スリーピング』(1962年)と、トリオにストリングスを加えたカクテル・ミュージック風の『ピアノ・ストリングス・アンド・ムーンライト』(1962年)を、立てつづけに吹き込んでいる。またコロムビア・レコードから、クインテットによるハード・バップ作『カレイドスコープ』(1965年)をリリースしている。その後1960年代の後半まで、西海岸のギタリスト、ハワード・ロバーツのグループのメンバーだったこともあるが、早々にジャズ・プレイヤーとしての活動に終止符を打ち、アレンジャーとして勇名を馳せるようになった。
ちなみに、1977年にヴァーサタイル・レコードから『ドント・タッチ』というアルバムがリリースされている。グルーシンのスウィンギーなトリオ演奏を聴くことができるのだが、実はこのアルバムは著作権者に無断で発売されたものだ。すなわちいわゆるブートレグで、有名なスタンダーズの扱いにおいても架空の曲名や作曲者名に変更されていて、本盤の製造販売には明らかに恣意的なものが感じられる。ただその音源は、1960年代にエピック・レコードにおいて吹き込まれたデモテープが持ち出されたものだから、一部ピッチがフラットする箇所があるものの比較的音質はいい。しかもグルーシンのプレイが、正規のエピック盤よりも力強く鮮やかに聴こえるから、まったく厄介だ。皮肉なことに本作は、彼が優れたジャズ・ピアニストであることを証明するものとなったのである。
作品数的には減少の一途をたどる1990年代のグルーシンの作品
とにもかくにもデイヴ・グルーシンは、本格的なジャズ・ピアニストとしてデビューするやいなや、(ピアノも弾くけれど)アレンジャーに転身する。彼が1963年から1966年まで、テレビの音楽番組『アンディ・ウィリアムス・ショー』において、ミュージカル・ディレクターを務めたことは、あまりにも有名だ。さらにグルーシンは、1967年からセルジオ・メンデスのオーケストレーションをずっと担当し、1973年からはそれと並行して、クインシー・ジョーンズの片腕としても働くようになる。かたやブラジリアン・ミュージック、かたやソウル・ミュージックと、彼がいかにヴァーサティリティに富んだ音楽性をもったアーティストであるかが、その仕事ぶりからよくわかる。映画音楽においても、オスカー獲得以前のグルーシンのスコアは、実に多種多様である。
1960年代、1970年代、そして1980年代と、グルーシンのサントラ盤をあらためて順番に聴いていくと、あまり時代性は重要視されておらず、飽くまで映画作品の性質に寄り添うような形がとられているのがわかる。基本的には、弦楽器や管楽器によって、そこはかとなくヨーロッパの香りが漂う哀愁を帯びた旋律と、現代的な美しい和声が奏でられることが多い。その点では、エンニオ・モリコーネやジョルジュ・ドルリューからの影響が感じられる。しかし作品に合わせて、様々なジャンルの音楽の要素が盛り込まれるのもまた、グルーシンのスコアの特徴のひとつである。もっとも驚かされたのは、フランスの俳優、クリスチャン・マルカンが監督した『キャンディ』(1968年)。サイケデリック・ロックのなかにグルーシンらしいフレーズを発見するのは、もはやマニアックな楽しみだ。
そんなわけで、云いかたはよくないが、アカデミー作曲賞を受賞するまでのグルーシンは、オールラウンダーというか全天候型作曲家というか、なんでも屋さんだった。ただ注目すべきは、彼がどんなタイプのスコアでも本来自分が得意とする音楽のようにこなしてしまうところ。しかもどんな要求にも、高品質なサウンドで応えるのだから、自ずと作曲のオファーも増えるというわけである。いっぽう、1970年代から1980年代にかけてのグルーシンの純粋な音楽作品といえば『ディスカヴァード・アゲイン!』(1976年)にはじまり『マイグレーション』(1989年)に至るまで、すべてのアルバムがコンテンポラリー・ジャズ作品。クロスオーヴァー/フュージョンのムーヴメントに乗り、絶大な人気を博した。ところが映画音楽では、ジャズが本格的に活かされる機会があまりなかった。

ただ、例外もある。シドニー・ポラック監督は、グルーシンの『シネマジック』(1987年)というアルバムのライナーノーツを執筆するくらい、その音楽性を熟知している。だからポラック監督がグルーシンを起用した9本の作品のフィルム・スコアでは、グルーシンのオリジナルのコンテンポラリー・ジャズ作品と同様に、彼ならではのハイセンスなサウンドの醍醐味を味わうことができる。おそらくオスカーの獲得を機に、グルーシンの本来の音楽性に対して、映画業界の要人たちも理解を深めたのだろう。1990年代から2000年代にかけて、グルーシンのフィルム・スコアは、ポラック作品の先例にならうかのような、コンテンポラリー・ジャズが活かされたものが主流となる。それは、独特の映画音楽として完熟したものでもあり、アクチュアルなグルーシン・サウンドでもある。
1990年代のグルーシンが手がけた映画音楽は10本ほどあるが、俳優のクリストファー・リーヴが監督した『フォーエヴァー・ライフ/旅立ちの朝』(1997年)では、どちらかといえばハートウォーミングなクラシカル・チューンが際立つ。しかしながら、それ以外の作品ではなにかしらの形で、ジャズの要素が盛り込まれている。なかにはマーク・ライデル監督の『フォー・ザ・ボーイズ』(1991年)のように、ストレートにモダン・ジャズが扱われた作品もあるし、俳優のフォレスト・ウィテカーが監督した『微笑みをもう一度』(1998年)のように、AKAIのウィンド・シンセサイザー、EWIがフィーチュアされたアダルト・コンテンポラリー風の曲が印象に残る作品もある。ジャズはジャズでも多岐にわたるのが、またグルーシンらしい。
特筆すべきは、当時のグルーシンが、自身のリーダー・アルバムや彼がプロデュースを手がけた作品において、4ビート・ジャズへの回帰をサジェストしていたということ。それまでのフュージョン・ブームに対する閉塞感を打開する手立てだったのだろう。グルーシンにとってジャズをプレイすることは昔取った杵柄だから、彼は現行のスタイルにいにしえのジャズをなんの違和感もなく採り入れ、しかも新しい感覚が冴えわたるようなパフォーマンスを披露した。ジョージ・ガーシュウィン、デューク・エリントン、ヘンリー・マンシーニ、レナード・バーンスタインへのトリビュート作品や、GRPオールスター・ビッグ・バンドでの活動は、それを証明するもの。これらのことから1990年代のグルーシンは、ほんとうにやりたいことのみに集中していたと捉えられる。
2000年代に入ると、グルーシンの作品はぐっと減る。とはいっても活動の内容は、濃密というか従前に増して充実している。とりわけリー・リトナーとのコラボレーションが生んだ『トゥー・ワールド』(2000年)『アンパロ〜トゥー・ワールド Vol.2』(2007年)といった2枚のクラシック・アルバムは、グルーシンの長いキャリアにおける作品群のなかでも、出色の出来栄えと云える。ジャズ・ピアニストがクラシック音楽を演奏するのは、べつだん珍しいことではない。ただ、グルーシンほどのひとが、単に既存の芸術音楽をなぞるだけに終始するはずもない。トランスクリプション、アダプテーション、そしてアレンジメントと、クラシックの名曲をグルーシン流に料理しているし、オリジナル曲も書き下ろしているのだ。
グルーシンのヒューマニティさえ顕著に伝わってくるサントラ盤
念のためにお断りしておくが、上記の2枚は、CTIレーベルの十八番だったクラシック音楽のパラフレーズ・ナンバー集ではなく、飽くまでトラディショナルな作曲法や演奏法を基調として制作されたクラシカル・ミュージック作品。時間と技能をたっぷり費やして丹念に作られた力作なのである。また、グルーシンはその合間を縫って『NOW PLAYING:映画テーマ集:ソロ・ピアノ』(2004年)をリリースする。彼にとっては、唯一のソロ・ピアノ作品である。いずれにしても2000年代のグルーシンには、やり残した試みに意欲を燃やすような風情があった。自ずと映画音楽の仕事も減り、ノーマン・ジュイソン監督の『ディナー・ウィズ・フレンズ』(2001年)、マーク・ライデル監督の『ザ・ゲーム』(2007年)、ジェイ・ローチ監督の『リカウント』(2008年)と、手がけた作品は3本のみ。
この3本のうち、サウンドトラック盤がリリースされたのは『ディナー・ウィズ・フレンズ』だけである。映画はHBOが製作したテレビ用の作品だが、プライムタイム・エミー賞の音楽部門にノミネートされた。しかもぼくの知るかぎり、いまのところ商品化されたグルーシンのフィルム・スコアとしては、もっとも新しい作品の音源となっている。内容的にもほとんどがコンテンポラリー・ジャズにアプローチしたトラックばかりで、どこを切ってもグルーシン・サウンドが現れるようなサントラ盤。彼の音楽に関心を寄せるひとだったら、必ずや深く魅了されるであろうアルバムだ。なお本作は、1980年代のダンス・ミュージック・シーンを牽引した音楽プロデューサー、ジョン “ジェリービーン” ベニテスのレーベル、ジェリービーン・レコーディングスからリリースされた。
全25曲中、ラストに収録されている「ドント・ドリーム・イッツ・オーヴァー」は既存の曲で、オーストラリアのロック・バンド、クラウデッド・ハウスの1986年のヒットソング。グルーシンとは、なんの関係もない。しかし残りのトラックはすべて、グルーシンが手がけたものだ。映画では、デニス・クエイド(ゲイブ)、アンディ・マクダウェル(カレン)、グレッグ・キニア(トム)、トニ・コレット(ベス)らの出演により、4人の友情、2組の夫婦愛、そして1組の離婚を題材に、人間のこころの機微が描かれる。グルーシンとは『ジャスティス』(1979年)でコンビを組んだジュイソン監督の演出が、辛辣でありながらもほんのり温かな余韻を残す。そしてグルーシンによるスタイリッシュでハートウォーミングな音楽が、作品をより味わい深くしている。
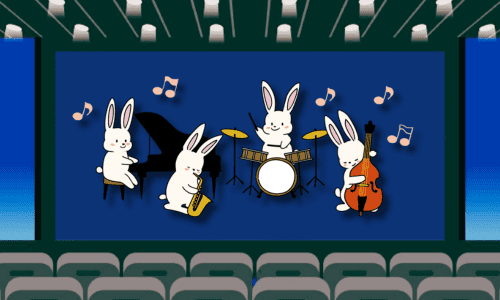
では、曲順に沿ってそのサウンドについて述べていこう。オープニングの「イフ・オンリー・ヒード・トークド・トゥ・ミー」は作品全体のテーマ曲。クラリネットによるメロディとストリングス(シンセサイザー)のバッキングによる叙情的な導入部から、ピアノ・トリオによるリラックスした演奏へ移行する。つづく「アイ・ディド・アン・エクスペリメント」はその長めのヴァージョン。シンセサイザーが加えられている。3曲目の「トム・ゴーズ・トゥ・ザ・デン」は、テナーによるスウィートなバラード。つづく「ゲイブ・アンド・トム・セイ・グッドバイ」はそのロング・ヴァージョン。甘くやるせない都会的なムードが絶品だ。ジミー・マクヒュー作曲、ドロシー・フィールズ作詞の「恋の気分で」では俳優のデニス・クエイドが雰囲気モノのヴォーカルを披露。グルーシンのバッキングは極上、テナーのソロもムード満点だ。
6曲目の「ベス・ドライヴス・ホーム」は不安感を描写する三拍子のキュー。ソプラノ・サックスがソロを執る。後半のピアノのフィルインはいかにもグルーシンらしい。つづく「ビーチ・ペインティング」「ザ・スケア」「イッツ・ゼア・ジョブ」は同一曲のヴァリエーション。メロディはやはりソプラノが吹いている。ここで耳に留めるべきは、アフロビート風のリズム・ワーク。こういうグルーヴは、グルーシンのもちまえのパーソナリティとセンスとの産物である。10曲目の「アイム・ハッピー・フォー・ユー」はギターとヴァイブのユニゾンによるメロディとピアノ・ソロがチルアウトな、カクテル・ジャズ。オープニング・クレジットの曲「ディナー・ウィズ・フレンズ」はトリオ+シンセによるバロック・ジャズ。グルーシンのスウィンギーなソロが秀逸だ。
12曲目「アイ・ノウ・ホエア・アイ・スタンド」から「アイ・クリング・トゥ・ハート」「ドント・ユー・エヴァー・ミス・ミー?」「ゲイブ・アンド・ベス・トーク」「ベス・ブレイクス・ダウン」「トム・ゲッツ・ヒズ・シーツ」「トム・チェックス・オン・キッズ」「トム・リーヴス・ゲイブズ・ハウス」「アイ・ドント・ライク・エニワン」「バック・アット・ザ・ヴィニャード」「エヴリ・カレン・ニーズ・ア・ベス」と、計11曲のピアノとストリングスを中心としたリリカルな心理描写のキューがつづく。これはグルーシンのおなじみのパターンなのだが、ライトモティーフを装飾あるいは展開することによって、登場人物の感情や状況の変化を明瞭に示唆するものである。ぜひ組曲風に楽しんでいただきたい。
23曲目の「ディド・ユー・ゲット・トゥ・ローマ」と、つづく「トゥー・マッチ・ヴァニラ?」はソース・ミュージック。マンドリンとアコーディオンをフィーチュアした、3拍子のカンツォネッタ風の曲。ちょっと『ミラグロ/奇跡の地』の音楽を彷彿させる、云ってみればグルーシン流アトモスフェーラ・イタリアーナだ。以上、お気づきかもしれないが、本サントラ盤のトラックは映画で使用された曲順には配列されておらず、いくつかのヴァリエーションがある楽曲はひとまとめに揃えて収録されている。どの曲も短めなので、この仕様はありがたい。鑑賞する際に、ある種のミュージカル・スウィートを聴くような感覚で楽しむことができるからだ。そしてなによりも、本来劇伴として終わりそうな音源を良質なアルバムとしてリリースしてくれた、プロデューサーのベニテスに感謝したい。
前述の『NOW PLAYING:映画テーマ集:ソロ・ピアノ』には、15曲中『ハバナ』(1990年)と『ザ・ファーム 法律事務所』(1993年)から2曲ずつ『狼たちの街』(1996年)と『ランダム・ハーツ』(1999年)から1曲づつ、計6曲の1990年代のフィルム・ミュージックが収録されている。この選曲は全体の40パーセントを占めているわけだが、作品数的には減少の一途をたどった1990年代も、実はグルーシン本人にとっては、けっこう納得のいく仕事が多い期間だったのかもしれない。しかも、本来のグルーシン・サウンドがもつ、ジャズのエッセンスが強く感じられる曲ばかりだ。そしてまた『ディナー・ウィズ・フレンズ』の楽曲の数々も、それらに連なる名曲ばかり。本作は、グルーシンのヒューマニティさえ顕著に伝わってくる、ファンタスティックなサントラ盤である。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント