チック・コリアが描き出すファンタジックかつロマンティックで、あたかもコンセプチュアル・アートのような音世界の嚆矢となったアルバム『妖精』
 Album : Chick Corea / The Leprechaun (1976)
Album : Chick Corea / The Leprechaun (1976)
Today’s Tune : Lenore
そのピアノ・プレイは正確無比かつ変幻自在
チック・コリアのアルバムを聴いていていつも感心するのは、どんなスタイルの作品であっても、常にそのクオリティが一定の水準に達しているということだ。しかもそのレベルが、ほかのアーティストのそれよりも非常に高いのである。そしてさらに、コリアの音楽作品に触れたときは必ずと云っていいほど、なにがしかの発見がある。だから彼のアルバムをターテーブルに乗せた日といえば、ぼくは身もこころも満ち足りた状態になるのだ。たとえそこに、いささか自分の嗜好とのズレがあったとしても、コリアのアルバムを聴き終わったあとには、この上ない充足感に満たされるものだから、まったく敬服するばかりだ。むろん彼はピアニストとしてもトップクラスのひとだけれど、個人的にはその圧倒的なクリエイティヴィティに強く惹かれる。
思えばぼくがコリアの音楽を聴きはじめてから半世紀近くも経つが、いまもそれは楽しみ尽くすことがないものとなっている。ぼくがコリアのアルバムを手にとるキッカケは、中学2年生のときにクラスメイトのKくんが強力にプッシュしてくれたこと。彼はクラスでいちばんの優等生だったけれど、ちょっとほかの生徒たちよりも大人びていた。Kくんは高校生のお兄さんの影響でジャズを愛好していた。彼にとって共通の趣味をもっているおなじ年ごろの子どもといえば、ぼくがはじめてだったとのこと。あのころの中学生のあいだでは、ゴダイゴ、サザンオールスターズ、それにオフコースなどの曲が流行っていた。稀に見る洋楽好きでも愛聴している音楽といえば、アバ、クイーン、それにザ・ビートルズと、ロックが中心だった。
ジャズやフュージョンを聴いている中学生は、間違いなく少数派だった。そんなわけで、転校生だったこともあってクラスでちょっと浮いた存在だったぼくは、Kくんとふたりでよく音楽の話題で盛り上がっていた。彼とはジャズ以外のハナシはあまりしなかったけれど、会話に興じているときのぼくといえば、なんとなく自分の価値が認められているような気がして、内向的な人間としてはずいぶんと救われたものである。そんなKくんが敬愛していたピアニストが、ジョー・サンプル、そしてチック・コリアだった。それまでぼくは、このふたりについては名前こそ知っていたが、実際にその演奏に触れたことは一度もなかった。Kくんについていこうといういじましさと、未知の音楽への好奇心から、ぼくは慌ててこのふたりのレコードを1枚ずつ購入した。

ジョー・サンプルは云うまでもなく、テキサス州ヒューストン生まれのフュージョン・グループ、ザ・クルセイダーズのキーボーディスト。ぼくが最初に手に入れたのは彼の個人名義のリーダー作で、ABCレコードからリリースされた『虹の楽園』(1978年)というアルバム。この作品でサンプルはわりとアーシーに弾きまくっているのだけれど、それに対して彼の書いた曲ははどれもメロディアスかつロマンティックなものばかりで、このレコードはまだビギナーだったぼくにもとても聴きやすいものだった。問題はチック・コリアのほう。中学生のお財布にやさしい廉価盤という理由だけで、ぼくがレジカウンターにもっていったのは、ソリッド・ステート・レコードからリリースされた『ナウ・ヒー・シングス・ナウ・ヒー・ソブス』(1968年)というアルバムだった。
このアルバム、ピアノ・トリオの歴史を塗りかえるような革命的な作品として、広く受け入れられている。ベーシストをミロスラフ・ヴィトウス、ドラマーをロイ・ヘインズが務めた伝説的なレコーディング。はじめて聴いたときは正直云って、あまりその良さがわからなかった。ただ、一聴でコリアがスゴいピアニストであるということだけは、ぼくにもハッキリとわかった。それでもコリアの超絶技巧のピアノ・プレイには圧倒されるばかりで、それを純粋に楽しむゆとりなど、未熟なぼくにはまったくなかったのである。いまでは、のちにブルーノート・レコードからリリースされた『サークリング・イン』(1975年)で日の目を見たアウトテイクスも含めてこのときの演奏には、ぼくもすっかり慣れ親しんでいるのだけれど──。
中学時代にはじめて聴いたサンプルとコリアのピアノ・プレイについて、各々の本来の音楽性や活動状況からすれば、比較する必要はないと思われる。それでも個人的にはふたりの演奏を同時に聴いたものだから、ぼくは自然とふたつのスタイルを並べて違いを見つけるようなことをしてしまった。いまでも敢えてその共通点を挙げることに、価値や重要性はまったくないと思われるのだが、当時のぼくの感想を素直に云っておくと、それはサンプルにしてもコリアにしてもとにかくよく指を動かすピアニストというものだった。サンプルの第一印象は、ときにファンキーときにリリカルなピアニスト。ただフィンガリングは躍動的でタッチも力強いのだけれど、あまり秩序立てて弾くプレイヤーではないと思われた。嫌いではないが概して云えば、彼はぼくの好みのタイプのピアニストではない。
それでもサンプルのときにリリカル、ときにダイナミックな演奏は、聴いていて胸がすくほど気持ちがいい。その点ではコリアにもおなじことが云えるのだが、彼の場合はそのタッチがもっと繊細で力強く、感情表現の幅が非常に広いと感じられた。なによりもそのプレイで驚かされたのは、コリアの紡ぎ出す一音一音がきわめて正確で、高速のパッセージにおいてもまったく濁るようなことはなく、煌びやかで透明感が際立っているということ。当時のぼくの感覚では、マッコイ・タイナーをもっとシャープにしたような感じというか、粒立ちのよさという点ではタイナーよりも秀でているように思われた。とにかくコリアの奏でる音の揃いかたは、ぼくにはまるで機械のように正確と感じられたのである。
しかもコリアはリズム感も抜群によく、右手が忙しく動いているのにもかかわらず、左手のコンピングにおいても、絶妙なタイミングでパーカッシヴな捻りやアクセントがつけられているのだ。さらにそれには、不協和音も織り交ぜられた独自のハーモニーが含まれていて、コリアのピアノ・プレイといえば、もはや正確無比かつ変幻自在と云うしかない。まあ当時のぼくは、そんな点にただただ驚嘆するばかりで、コリアという音楽家のほんとうの素晴らしさを理解していなかったと思う。そもそもぼくの聴きかたに問題があった。難易度の高い演奏技術が駆使されて創造される音楽というものは、実はアタマで理解しようとしてはダメなのだ。音楽は理屈で理解するものではなく、こころに響かせるもの。そんな当たりまえのことに、そのころのぼくは少しも気付いていなかったのである。
音楽においてもっとも重要視しているのは創造性
それでもぼくは、クラスメイトのなかで唯一の自分の理解者がすすめてくれたアーティストのレコードだから、わけもわからず『ナウ・ヒー・シングス・ナウ・ヒー・ソブス』を繰り返し聴いていた。そしてあるとき、自分がとらわれていたであろう雑念のようなものが、ふと解消された。すなわち、それまでスリリングな演奏のなかに紛れて見えなかった、コリアの映像的とも云える美しい歌ごころを、ぼくの感性はようやくキャッチしたのだった。そもそも彼は、指をどれだけ速く動かせるかを聴衆に見せつけるために、高度なテクニックを用いているのではないのだ。自分のなかに浮かんだ心象風景や空想世界を、思いのままに音楽として表現するのに必要だからこそ、コリアはときに難易度の高い演奏に傾倒するのである。
そんなことを意識しながらあらためてコリアの音楽に触れてみると、彼は音楽至上主義というよりもしごく透明感に溢れたイマジネーションの独自性が高いミュージシャンと思われる。以降、ぼくにとってコリアの存在はぐっと身近になり、次はどんな音楽の旅に連れていってくれるのだろうと、彼の新譜をこころ待ちにするほどになった。とはいっても、ぼくにとって彼はいつまでも、はじめて聴いたときの印象どおり、クリアなアーティキュレーション、鋭敏なリズム感、そして豊かなクリエイティヴィティに富んだフレージングと、とにかくスゴいテクニックをもったピアニストなのである。ぼくもピアノを弾くけれど、たとえコリアの千倍練習したとしても、彼には及びもつかないだろう。そんなことは、百も承知、二百も合点なのである。
それでもぼくがコリアの音楽にシンパシーを感じるのは、彼がどんな音楽作品をクリエイトするときでも、自分の想像力を大事にしているという点。コリアの音楽を聴いていると、どんな場合でも彼が自己の知識を基に新しいイメージを生み出しているように感じられるのだ。たとえ直接見聞きしていない事象や経験したことのない未来、あるいは現実には存在しないものであっても、コリアはそれをアタマのなかで思い描き音楽という形で具現化することができるのだと、ぼくは思う。しかも彼の場合、その創造性はジャンルを超えた多様性、絶え間ない革新への意欲、そしてスパニッシュな感性に特徴づけられている。ジャズであろうがフュージョンであろうが、コリアは常に新しい音楽的探求をしつづけた。そんな彼がミュージック・シーンに与えた影響は大きい。
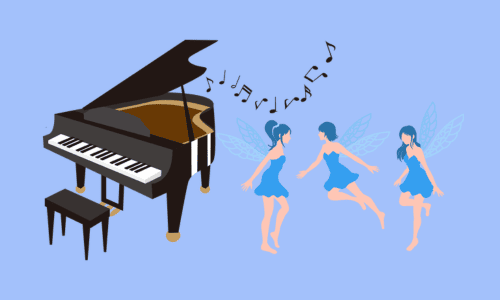
ぼくは冒頭でコリアの音楽について、どんなスタイルの作品であっても、常にそのクオリティが一定の水準に達していると云ったけれど、その判断に至った根拠はまさにそこにあるのだ。多様性という点では、たとえば『ナウ・ヒー・シングス・ナウ・ヒー・ソブス』におけるピアノ・トリオでのアグレッシヴで幾何学的な演奏から、彼の初期のグループ作品『リターン・トゥ・フォーエヴァー』(1972年)におけるフェンダー・ローズをメインに据えたエレクトリック・ジャズへのアプローチ、さらにデジタル時代のフュージョン・グループ作『ザ・チック・コリア・エレクトリック・バンド』(1986年)における多種多様のシンセサイザーが駆使されたサウンドまで、使用する楽器や編成だけに着目しても多岐にわたっていることがわかる。
音楽のスタイルの面でもコリアは、ジャズの帝王ことトランペッターのマイルス・デイヴィスのバンドでの実験的な活動を経て、ベーシストのデイヴ・ホランド、ドラマーのバリー・アルトシュルらと組んだグループ、サークルで大胆なフリー・ジャズを展開しているし、その後自身のバンド、リターン・トゥ・フォーエヴァーを結成し、フュージョンという新しい音楽ジャンルの確立において中心的役割を果たした。音楽ジャンルで考えてみても、コリアはジャズを基盤としながらも、クラシック、ラテン、スパニッシュなど世界中の音楽文化を融合させて、独自のサウンドを生み出した。いずれにしてもその多様性は、コリアが卓越した演奏技術を身につけていながら、音楽においてもっとも重要視していたのは創造性であると、ぼくは確信する。
さらにもうひとことつけ加えると、次々に音楽的探求と多様性に富んだ作品を発表してきたコリアだが、それらにはスタイルやジャンルは違えども確たる一貫性がある。一部には否定的な意見もあるようだけれど、ぼくはそう確信している。引き合いに出して申し訳ないが、コリアとは何度も共演しているピアニストのハービー・ハンコックと比較すると、ますますそう固く信じて疑わなくなってしまうのだ。ハンコックもまたコリアと同様に、多様性に富んだミュージシャンだ。だがオーソドックスなジャズ作品からエレックトリック・ジャズをはじめとするポップ・アルバムまで、ハンコックの手がけた音楽作品の全体を俯瞰してみると、それらは明らかに一貫性に欠けるている。なかには事前に情報を知らされずに聴かされたら、だれが演奏しているのかわからないような楽曲もあるのだ。
そんなわけで、音楽的探求と多様性に富んだ、しかもクオリティの高いコリアの膨大な数の作品群のなかからベストワンを選ぶのは、きわめて困難と云える。ピアノ・トリオによるレコーディングのみに絞り込んでも、彼は作品の方向性によってサイドメンを選ぶのだろう、12種類のトリオが存在する。このこともまた、コリアのコンセプトに応じて柔軟に対応する、飽くまで創造性重視の音楽性をよくあらわしていると、ぼくは思う。多くのジャズ・ピアニストの場合、音楽性を高め合える相性のいいサイドメンとともに、長きにわたり活動するもの。しかしながらコリアの場合は違う。彼はアルバムを制作する際には程度の差こそあれ、必ず一定のテーマに基づいて編成や楽曲を選んでいるのだ。そういう意味で、コリアは単なるジャズ・ピアニストではなく、終始表現の自由にこだわり抜いた偉大な音楽家だった。
さて、長々とコリアの音楽性について自身の思いの丈を述べてきたが、ここからはその珠玉の作品群のなかから、ぼくにとって特に思い入れのあるアルバムをご紹介したいと思う。トリオ、フリー・ジャズ、フュージョン、クラシック、ソロ・ピアノ、デュオと、まあとにかく多彩を極めるコリアの夥しい数の作品のなかでも、ある種のコンセプト・アルバムのようなものに、ぼくは強く惹かれる。特にジャズというひとつのジャンルにとらわれることなく、彼がイメージする心象、あるいは空想する世界が自由に表現され、実にカラフルなサウンドが創出された3作品をお薦めする。それらはどれもファンタジーに満ちたロマンティックなアルバムだが、すべて1970年代後半の作品。幻想的な音世界が描き出されているという点では、リターン・トゥ・フォーエヴァーの『浪漫の騎士』(1976年)以降の作品とも共通する。
アイルランドに伝わる妖精の物語で構成された作品
ときにその3作品とは、アイルランドに伝わる妖精の物語で構成された『妖精』(1976年)、過去の作品からもすでに影響が感じられていたスペインの音楽にディープに傾倒した『マイ・スパニッシュ・ハート』(1976年)、ルイス・キャロルの小説『不思議の国のアリス』や『鏡の国のアリス』にインスパイアされた『マッド・ハッター』(1978年)。以上のアルバムでは、ファンタジックかつドラマティックな展開や、ジャズ/フュージョンのなかにクラシックが盛り込まれた不思議な音世界が特徴となっている。3作はすべてポリドール・レコードからリリースされたが、なかでも『妖精』と『マッド・ハッター』は、特にファンタジーの色彩が強い作品。そのどこか異国情緒が漂う魔法がかったようなサウンドには、何度聴いてもワクワクさせられる。
3作のうち制作順ではまんなかに位置する『マイ・スパニッシュ・ハート』は、ほかの2作と比較すると異世界風というわけではないが、壮大な音楽絵巻という印象を与えるところは共通する。アコースティック・ピアノ、フェンダー・ローズ、そして当時の最先端だった各種のシンセサイザーが巧みに使いわけられ、ジャズ、ラテン、クラシックの境界線が越えられているというのも同様。コリアの音楽的ルーツであるスペイン音楽への憧憬が、全面的に独自の解釈で表現されているという点では、彼のディスコグラフィにおいて重要な作品と云える。コリアはポリドールにおいてひきつづき『シークレット・エージェント』(1978年)『フレンズ』(1978年)といったアルバムを制作するが、ファンタジー色は薄まったものの彼の想像力豊かな世界観はそのまま引き継がれている。この2作もまた、個人的に好きな作品だ。
ということで今回は、コリアが描き出すファンタジックかつロマンティックで、あたかもコンセプチュアル・アートのような音世界の嚆矢となったアルバム『妖精』についてお伝えする。レコーディングは、レコードのジャケット等にその記載はないが、おそらく1975年にニューヨークのレコード・プラント・スタジオで行われたのだろう。当時のコリアといえば、リターン・トゥ・フォーエヴァーのアルバムを吹き込む際に、毎回このスタジオを利用していたからね──。エンジニアはコリアの作品を多く手がけているバーニー・カーシュが務めている。またコリアの作品において、彼の妻(1972年に結婚)でもとマハヴィシュヌ・オーケストラのメンバーだった、ゲイル・モランのヴォーカルがフィーチュアされるのも、本作がはじめてだった。
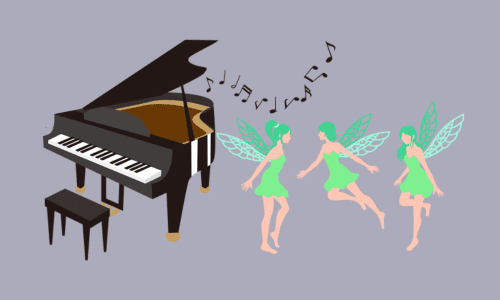
モランはその後『マイ・スパニッシュ・ハート』『マッド・ハッター』『シークレット・エージェント』さらに『タップ・ステップ』(1980年)『タッチストーン』(1982年)と、コリアのアルバムでは常連となる。さらに彼女はリターン・トゥ・フォーエヴァーのメンバーとなり、アルバムでは『ミュージックマジック』(1977年)『ザ・コンプリート・コンサート』(1978年)の吹き込みに参加している。そのいっぽうで、ワーナー・ブラザース・レコードからリリースされたモランのリーダー作『妖精の舞』(1979年)では、コリアがプロデューサーを務めている。コリアはもちろんのこと、リターン・トゥ・フォーエヴァーのベーシスト、スタンリー・クラークも参加しているので、興味のあるかたは手にとってみてはいかがだろう。
ところでレコーディング・メンバーは、チック・コリア(key, perc)、エディ・ゴメス(b)、アンソニー・ジャクソン(b)、スティーヴ・ガッド(ds)、ジョー・ファレル(ss, fl, ehr)、ダニー・カーン(tp)、ボブ・ミリカン(tp)、ジョン・ガッチェル(tp)、ビル・ワトラス(tb)、ウェイン・アンドレ(tb)。さらにクラシカルなストリング・クァルテット(vln ×2, Vla ×1, Vc ×1)が加わる。なお云うまでもないが、ゴメスはアコースティック・ベース、ジャクソンはエレクトリック・ベース・ギターを弾いている。すべてのドラムスをガッドが担っているが、相変わらず精緻なリニア・ドラミング、歌うようなタム回し、そしてタイトかつグルーヴィーなタイム感を披露している。彼のキャリアにおいて、代表的なパフォーマンスのひとつと云ってもいいだろう。
いっぽうコリアが本作で使用している楽器は、アコースティック・ピアノ、フェンダー・ローズ・エレクトリック・ピアノ、ヤマハ・エレクトリック・オルガン、ホーナー・クラヴィネット、アープ・オデッセイ、マイクロモーグ、モーグ・モデル 15 モジュラー・シンセサイザー。またこのレコーディングには、パーカッショニストは参加しておらず、ボンゴ、ベル、ウッドブロック、ベルツリー、タムタムなどは、コリア自身が演奏している。アルバム・タイトルの原題となっているレプラコーンは、ケルト神話に由来する老人の姿をした靴職人の小妖精。虹のたもとに金貨の入った壺を隠していて、捕まえた者に富をもたらすと云われている。ある意味で、コリアの創造力と音楽的な遊びごころを体現したキャラクターと云ってもいいだろう。
収録曲は1曲を除いて、すべてコリアが作編曲したもの。アルバムはエキゾティックなムードが漂う「インプス・ウェルカム」からスタート。オーヴァー・ダブによるコリアの独奏。マイクロモーグのソロがリスナーをファンタジーの世界へ誘う。つづく「レノア」は、軽快なフュージョン・ナンバー。ガッドのファンキーかつタイトなドラミングに乗って、コリアがアコースティック・ピアノとモーグとでエナジェティックなアドリブを展開する。内省的な雰囲気の「夢想」では、コリアのリリカルなソロ・ピアノが静謐を湛えた美しい世界を描き出す。モランの透明感に溢れたコーラスも素晴らしい。そのモランが作詞作曲を手がけた「世界を見つめて」は、アコースティックなポップ・ナンバー。ストリング・カルテットの力強い演奏も印象的だ。
モランのヴォーカル・パートは柔らかで優しい感じだが、後半のインストゥルメンタル・パートではゴスペル・タッチかつプログレッシヴ・ロック風な展開になる。歌詞の意味はよくわからないけれど、個人的にはコリアのことを歌っているようにも思われる。ファンキーなグルーヴが炸裂する「夜の精」は、アルバム中もっともアグレッシヴなナンバー。コリアのシンセ、ファレルのソプラノのソロも然ることながら、ジャクソンとガッドとによる精力的かつ歯切れのいいリズム・キープが素晴らしい。ジャクソンのゴースト・ノートを効果的に採り入れたライン、ガッドのダイナミックな変幻自在のドラミングに胸がすく。ネヴィル・ポーターが作詞した「ソフト・アンド・ジェントル」は、歌詞もそうだが詩情豊かなナンバー。
ネヴィルはリターン・トゥ・フォーエヴァーの楽曲の歌詞で、おなじみのひと。ストリング・クァルテットが加わったパフォーマンスは、クラシカルでリリカルな雰囲気を溢れさせながら、やがて重厚感を増すようになる。モランのヴォーカルも滑らかな感じで歌い出し、次第にエモーショナルになっていく。ゴメスによるベースの音色も印象的な、アコースティックな1曲だ。いかにも妖精たちがコミカルに踊っているようなイメージの「ピクシランド・ラグ」では、コリアがラグタイム調の軽やかなソロを披露。短尺ながら、彼の遊びごころが横溢する楽しいナンバーだ。ラストの「妖精の夢」は、2部構成の大作。幻想的なテーマ、複雑なアンサンブル、各ミュージシャンの熱いソロと、実に聴き応えのある1曲。この越境するクリエイティヴィティこそ、まさにコリアの世界そのもの。ぜひ聴いていただきたい。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント