マイルス・デイヴィス・グループの僚友とともに吹き込まれた、絶頂期にあったウィントン・ケリーの傑作『枯葉』
 Album : Wynton Kelly / Wynton Kelly! (1961)
Album : Wynton Kelly / Wynton Kelly! (1961)
Today’s Tune : Gone With The Wind
極めてスタンダードな名曲「枯葉」が世界的に広まるまで
ようやく暑さが和らいで、季節の変わり目を実感する今日このごろである。ことに朝晩の空気には、かなり秋の気配が深まってきている。例年感じることだけれど、秋は加速度的に季節の息吹を強めてくるから、ぼくの場合、いろいろな面でちょっと対応に苦慮したりする。それに反して感覚のほうは、それこそ明るく冴えた秋空のように研ぎ澄まされてくるから、どちらかというとありがたい時節と云っていい。ところで、ジャズを愛好するものにとって秋といえば、すぐに思い浮かべるのは極めてスタンダードな「枯葉」という曲だろう。実にありきたりな発想で申し訳ないのだけれど、それだけこの曲の存在感が強いというのもまた事実。そして「枯葉」といえば、ウィントン・ケリーのアルバム『枯葉』(1961年)だろう。
思わず断定的に云ってしまったが、飽くまでぼくの独断と偏見での発言。もしもビル・エヴァンスのアルバム『ポートレイト・イン・ジャズ』(1960年)の邦題が『枯葉』だったら、そちらを挙げていたかもしれない。キャノンボール・アダレイのアルバム『サムシン・エルス』(1958年)においても、また然りである。まったくもって、いい加減なものである。逆にキース・ジャレットのいわゆるスタンダーズ・トリオの『枯葉/キース・ジャレット・スタンダーズ・スティル・ライヴ』(1986年)や、マッコイ・タイナーのソロ・ピアノ作『枯葉』(1989年)には、日本ではタイトルに“枯葉”が付されているけれど、ぼくとしてはそれらをもち出すことはないだろう。いずれにしても「枯葉」は、多くのジャズ・ミュージシャンに採り上げられた、秋をイメージさせる名曲だ。
そんなジャズ・スタンダーズ史上に燦然と輝く「枯葉」であるが、もとはハンガリー出身でのちにフランスに帰化した作曲家、ジョゼフ・コズマが1945年にローラン・プティ・バレエ団のステージ『ランデヴー』のために書いた曲だった。コズマは1930年代初頭から1970年まで銀幕に数多くのスコアを提供したフランス映画音楽の大家。彼はマルセル・カルネの監督作品『夜の門』(1946年)の音楽を手がけたが、この作品が『ランデヴー』をモティーフとした映画だったため、既存の曲が使用される運びとなった。脚本を担当したジャック・プレヴェールが新たに歌詞をつけたコズマの曲を、出演者のひとりで当時まだ新人のシンガーだったイヴ・モンタンが劇中で歌った。その際、この曲に「レ・フェイユ・モルトゥ」というタイトルが付された。
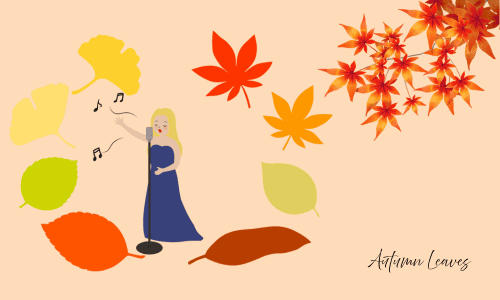
曲名の「レ・フェイユ・モルトゥ」とは、フランス語で表記すると「Les Feuilles Mortes」となり、直訳すると「枯死した葉っぱ」すなわち「枯葉」のことである。あいにく映画もモンタンの歌もヒットしなかったようだが、のちに当時の人気シャンソン歌手、ジュリエット・グレコが歌ったことで「枯葉」は、広く知られるようになった。この曲がアメリカにもち込まれたのは1949年のことで、キャピトル・レコードの創設者のひとりで作詞家のジョニー・マーサーが英語詞を書いた。このひとは外国の曲やイントゥルメンタルに歌詞をつけるのが得意で、おそらく当時フランスで流行っていたこのシャンソンを自国でも売り出そうとしたのだろう。ときを移さず英語詞の「枯葉」は、ビング・クロスビーによってアクセル・ストーダール楽団をバックに歌われた。
しかしながら、1950年にブランズウィック・レコードからリリースされたクロスビーのシングル盤は、それほどヒットしなかったようだ。アメリカで「枯葉」が広く知られるようになったのは、イージー・リスニング系のピアニスト、ロジャー・ウィリアムズによって演奏されてから。1955年にカップ・レコードから発売されたシングル盤は、ビルボード誌のヒットチャートで4週連続第1位を獲得した。その後この演奏は、アルバム『ロジャー・ウィリアムズ』(1956年)にも収録された。グレン・オッサー楽団をバックに、左手でメロディをキープしながら右手で素早く駆け下るという、ウィリアムズの(舞い散る枯葉をイメージした?)独特のピアノ・プレイは、すこぶる煌びやか。とはいってもぼくにとっては、けばけばしく感じられる苦手なパフォーマンスなのだけれど──。
なおオリジナルの「枯葉」にはメロディに入るまえに、テンポ・ルバートで歌われる導入部があった。ところがマーサーは、それを全面的に削除してしまった。当然、その部分の英語詞は存在しない。確かにポピュラー・ソングの序奏としては、いささか長過ぎる。そんな理由からか、バート・ハワードが作詞作曲した有名なジャズ・スタンダーズの1曲「フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン」もまた、いわゆるヴァースの部分が省略されることが多い。シャンソンの愛好者にしてみれば不届き千万なことなのかもしれないけれど、おそらくいまは、ジャズ・ファンのほとんどのひとが「枯葉」のヴァースを知らないという状況にあると思われる。まあこの曲を何度も歌っているモンタンも、その部分を前説的にセリフに変えていることもあるが──。
とにもかくにもこの「枯葉」は、ピアニストを中心に多くのジャズ・ミュージシャンによって採り上げられている。この曲が、メロディック・ラインとコード・プログレッションにおいて極めてシンプルなのにもかかわらず、たとえば紅葉、黄葉といった秋の美しくも儚い印象をストレートに与えるからだろう。また「枯葉」にはそのシンプルさ故に、ミュージシャンが型にとらわれず思うままに演奏することができるというメリットがある。一例を挙げると、サラ・ヴォーンがパブロ・レコードに吹き込んだ、それこそ『枯葉』(1982年)という有名なアルバムがあるが、ここで彼女は「枯葉」を歌詞を排除した即興のスキャットで歌っている。縦横無尽に駆け抜ける歌唱は、もはや秋もへったくれもないけれど非常に痛快で、ぼくは好きだ。
名盤名演といえば、さきに挙げた『サムシン・エルス』だろう。キャノンボール・アダレイ名義のアルバムだけれど、実質的なリーダーはマイルス・デイヴィス。1950年代のはじめ薬物中毒だったデイヴィスを支えたのは、ブルーノート・レコードのプロデューサー、アルフレッド・ライオン。彼はそれから数年後、すっかり立ち直りハード・バップのトップ・アーティストとなったデイヴィスのリーダー作を制作しようと思った。ところが当時、デイヴィスがコロムビア・レコードの専属アーティストだったため、アダレイをリーダーに据えてアルバムをリリース。それが『サムシン・エルス』である。すでに「枯葉」は他のジャズ・プレイヤーが採り上げていたけれど、この曲のジャズ・ヴァージョンはここからはじまったと云ってもいいのではないだろうか。
ジャズ・スタンダーズの仲間入りを果たした「枯葉」の名演
そのくらい『サムシン・エルス』の「枯葉」は名演だし、アルバム自体も不朽の名盤。一般的にアーマッド・ジャマルからの影響と云われるアフロ・キューバン調のリズムが印象的なイントロから、いささかレイジーだけれどすこぶるクールな世界に引き込まれる。それにつづくデイヴィスのハーマン・ミュートが、鋭くも透明感のあるトーンで静謐を湛えたフレージングを展開。それにつられてか、アダレイのアルトは得意のファンキーさは抑えられてエレガントに響くし、アート・ブレイキーのドラムスも極めてセンシティヴなサポートに終始する。ハンク・ジョーンズのピアノは、相変わらず歌ごころに溢れたフレーズを淀みなく繰り出している。ただ秋を感じるというよりも、どちらかというと厳粛な気持ちにさせられると云ったほうがいい。
違った意味でやはり名盤名演なのが、ビル・エヴァンスの『ポートレイト・イン・ジャズ』である。卓越した表現力とそれが生み出す気品のある雰囲気とが際立つのが『サムシン・エルス』での「枯葉」なら、構造的、論理的、美学的に秀逸な音楽が奏でられているのが『ポートレイト・イン・ジャズ』のなかの「枯葉」だ。まず躍動感溢れるイントロからして、飛び抜けている。ユニークなコード・プログレッションとリズミカルなフレーズとが、聴き手をソフィスティケーテッドな音世界へといざなう。つづくモーダルな解釈と雄弁なメロディのフロウも見事。天才ベーシスト、スコット・ラファロとのインタープレイのあと、アップテンポに乗って疾走するエヴァンスのピアノが知的かつ情熱的。とにかくスタイリッシュなフレーズが矢継ぎ早に放たれる。
エヴァンスの「枯葉」は、ジャズ・シーンにおいてことのほか異彩を放っている。注目すべきは、演奏の技巧においてビバップ・スタイルから大きく飛躍していることも然ることながら、楽曲を再構成する際の感覚や表現方法が優れていること。あまりこういう云いかたはされないけれど、つまるところ彼は、アレンジャーとしての資質に恵まれたピアニストだったと、ぼくは思うのだ。もし彼が単に優れたジャズ・ピアニストだったら、ビバップ・スタイルのままモーダルなジャズをプレイしていたかもしれない。コール・アンド・レスポンスを主眼とする、ベースとドラムスをピアノと対等のポジションに置いたトリオ・スタイルにしても、エヴァンスのアレンジャーとしての視点から創出されたものと考えてもいいのではないだろうか。
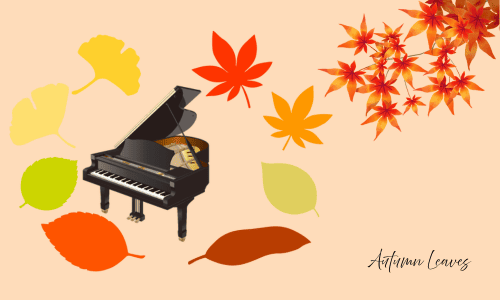
そんなエヴァンスの「枯葉」をカッコいいととるか、ちょっと小難しいととるかはひとそれぞれだろうけれど、トリオの演奏はエスプリの効いたものであるが故に、知的好奇心が高まる季節とも云われる秋に聴くのに相応しいようにも思われる。そういう無理な理由づけなしに秋らしさが感じられるという点で、お薦めしたいのはデイヴ・グルーシンの「枯葉」だ。エピック・レコードからリリースされた『ピアノ・ストリングス・アンド・ムーンライト』(1962年)に収録されている。ベースにミルト・ヒントン、ドラムスにオシー・ジョンソンを据えたトリオにストリングスが加わる。イントロから摩天楼の群れが広がるニューヨークの風景をイメージさせられる。小気味よくバウンスするグルーシンのピアノと流麗な弦のアンサンブルが、都会の秋に溶け込むようだ。
まあグルーシンはぼくのもっとも敬愛する音楽家だから、私情を挟んでいないと云えばウソになるのだけれど、この『ピアノ・ストリングス・アンド・ムーンライト』はチャーミングなアルバムなので、カクテル・ピアノ作品と決めつけたりせずに、ぜひ聴いていただきたい。ストリングスのアレンジと指揮もグルーシンが手がけているので、彼のファンには親しみやすい1枚と云えよう。ということで、名曲「枯葉」について長々と語ってきたが、ハナシをもとに戻そう。ぼくは冒頭で「枯葉」といえば、ウィントン・ケリーのアルバム『枯葉』とキッパリと云い切ったけれど、それはウソ偽りのない気持ちからの発言で、ぼくにとってもっとも聴き込んだという点では間違いなくケリーの「枯葉」がトップなのである。
ケリーは1971年4月12日てんかん発作を起こし、惜しくも39歳という若さでこの世を去ったが、それ故そのリーダー作は非常に少ないし、トリオで吹き込まれたアルバムは数えるほどしかない。この『枯葉』は、彼のトリオ作品としては3枚目に当たる。このアルバムの原題は『Wynton Kelly!』という。オリジナル盤のリリースからときを移さず、日本ビクターによって国内盤が発売されたが、そのときからこのかた、わが国において本作は『枯葉』というタイトルで親しまれている。実は過去にリヴァーサイド・レコードから『Wynton Kelly』(1958年)というタイトルのアルバムがリリースされている。感嘆符があるかないかの違いはあるものの、ちょっとややこしい。それで『枯葉』という邦題が案出されたのかどうかは定かでないが、この呼称が定着した。
なおエクスクラメーション・マークなしのほうは、1962年にリヴァーサイドの傍系レーベル、ジャズランドによってリイシューされ『ウィスパー・ノット』と改題されたが、以来日本のファンのあいだではそれが通り名となっている。ちなみにこの『ウィスパー・ノット』は、A面をギター入りのクァルテット、B面をドラムレスのトリオという変則的な編成で吹き込まれた。サイドを務めたベーシストのポール・チェンバース、ドラマーのフィリー・ジョー・ジョーンズは、当時マイルス・デイヴィスのグループに属していたけれど、ケリーもまたこの吹き込みのあと同グループのメンバーとして活躍したのは周知のこと。ここではそのトリオに、ブルージーでスムースなギター・プレイでお馴染みのケニー・バレルが加わっている。
ついでに云うとこの『ウィスパー・ノット』は、プロデュースを手がけたオリン・キープニュースの証言によると、もともとは全編にわたってクァルテットでレコーディングされるはずだったとのこと。ところがドラマーのジョーンズが定刻になってもスタジオにやって来ないものだから、それならばとドラムレスのトリオによって、バラードやゆったりしたテンポのナンバーからレコーディングが開始された。奇しくもケリーは、オールド・スタイルのピアノ・トリオでプレイする運びとなったのである。結果的に同日の吹き込みでありながら、2種類の異なる編成のセッションが収録されたアルバムが出来上がった。古い文句だけれど、ぼくにとっては“1粒で2度おいしい”一挙了得な音盤として重宝している。
地に足のついたトリオ・プレイをこころ置きなく味わう
このレコードの個人的な楽しみかたは、躍動感溢れるクァルテットのセッションが収録されたA面と、鷹揚で上品さを感じさせるドラムレスのトリオによるギグが収められたB面とを、そのときの気分によって順番を変えて聴くというもの。ぼくはどちらかというと、瀬踏みするような感覚でB面からプレイすることが多い。あたかも気の合う仲間による鼎談のごとき、適度なスウィング感で伸びやかなムードを醸成するドラムレス・トリオのプレイには、ぼくのこころを和ますものがある。ほどよく気持ちの準備が整ったところで、レコードをひっくり返してセットする。A面では遅刻してきたジョーンズによる颯爽としたリズム・サポート、ピアノとの貫禄のある8バース、精力に満ちたソロが加わり、クァルテットの演奏がヒートアップする。
どちらかというと、ぼくはこの『ウィスパー・ノット』では、B面のドラムレス・トリオによる吹き込みに魅力を感じる。ここでのピアノ・プレイではケリーのジャズ・スピリッツがありのままに表出しているというか、どの曲もその持ちまえの悠然とした歌ごころで素直に表現されているように感じられるからだ。このアルバムとくだんの『枯葉』と、あと一般的なトリオで吹き込まれた『ケリー・アット・ミッドナイト』(1960年)とが、ぼくにとってはケリーのベスト3となっている。ブルーノート・レコードからリリースされた彼のデビュー作に当たる『ピアノ・インタープリテーションズ・バイ・ウィントン・ケリー』(1953年)もまたトリオによるレコーディングだったけれど、鮮やかなタッチを見せながらもその個性はまだ序の口だ。
ケリーのリーダー作で一般的にもっとも人気が高いのは、リヴァーサイド・レコードからリリースされた『ケリー・ブルー』(1959年)だろう。セクステットでの2曲とトリオでの4曲といった、ふたつのセッションが交ぜ合わされて収録されている。押しなべて彼ならではのブルージーでスウィンギーなピアノ・プレイが、遺憾なく発揮されている。ぼくの大好きなブロニスラウ・ケイパーの「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」も演っている。そのグルーヴ感といったらゴキゲンのひとことに尽きる。個人的なことで恐縮だけれど、高校時代にジャズ・ピアノを独学していたぼくは、この曲のケリーのアドリブ・ソロをコピーしたことがある。スウィングするとはこういうことなのかと、大いに得心がいった1曲だった。

ただアルバムとしては、さきに挙げた3枚のほうが好きだ。なぜかというと『ケリー・ブルー』がいくら名盤とはいえ、上記のように編成の異なるセッションがミックスされているという点は、だれがなんと云おうとぼくにとってはマイナスポイントになるからだ。しかもホーン・セクションのアレンジからは、テナー奏者のベニー・ゴルソンの匂いがムンムンしてくる。ゴルソンのアレンジはキャッチーだけれど、正直云ってほかでやってもらいたい。ケリー・ブルーというアイルランドのケリー州原産のテリア犬種にちなんだ美味しいカクテルがあるけれど、異なる酒類とチャンポンするのは性に合わない。違う種類の音楽を交互に聴かされるのもまた、ぼくにとってはいささか厭わしいことなのである。
そういうわけで、ぼくとしては『ケリー・ブルー』よりも、ヴィージェイ・レコードからリリースされた『ケリー・アット・ミッドナイト』と『枯葉』のほうを断固推す。この2枚を比較したとき、多くのジャズ・ファンが『枯葉』をより高く評価するようだけれど、ぼくにとっては双方の出来はおっつかっつ。よく云われるのは『ケリー・アット・ミッドナイト』でのフィリー・ジョー・ジョーンズのドラミングがオーヴァーアクティングぎみということ。確かに彼のパフォーマンスは、饒舌というか手数が多い。いささか出過ぎる嫌いがあるのかもしれないが、そんなことはなんのその。ハイテンションなジョーンズに焚きつけられて、陽気にスウィングしまくるケリーのプレイに身を任せていると、こちらまで興が乗るというもの。
なかでもギタリストのルディ・スティーヴンソンが提供した「オン・ステージ」が、途方もなくリズミカルかつダンサブルで最高だ。ジョーンズの変幻自在のドラミングが、なんともドラマティック。ポール・チェンバースのアルコ・ベースは得も云われぬ軽快さを見せるし、ケリーのピアノも次々にゴキゲンなフレーズを繰り出してくる。そういえば、ここでのピアノ・ソロにおける数々の楽句を、高校時代のぼくはそのまま拝借して自分の即興演奏に活用していたな。まさしく彼のピアノ・プレイは、ぼくにとってモダン・ジャズのお手本だったのだ。そういう点では『枯葉』と同日のセッションの未発表音源集『サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム』(1977年)に収録された、タイトル・ナンバーもまた然りである。
いっぽう『枯葉』のほうは、ベーシストがポール・チェンバース、ドラマーがジミー・コブといった、レギュラー・メンバーによるレコーディングということで、地に足のついたトリオ・プレイをこころ置きなく味わうことができる。チェンバースとコブとが打ち出すリズムが、ケリーの天賦の才を自然な形で浮かび上がらせていると云ってもいい。そんなあるがままのスウィング感は、いまも瑞々しく響いてくる。そのクリーンなタッチは、まさに抜けるような秋の青空にフィットする。そういったことを踏まえると、ケリーのアルバムのなかでは『枯葉』こそが、だれにも推奨することができる逸品ということになる。なお吹き込みは、1961年7月20日、21日、ニューヨークのベル・サウンド・スタジオにて行われた。また、3曲(レコードのA-1, A-2, B-2)で、ベーシストがサム・ジョーンズに交替する。
オープニングを飾るハロルド・アーレンの「降っても晴れても」は、軽やかなミッドテンポで明るいタッチのナンバーとして演奏される。ピアノの跳ね返るようなスウィング感が痛快。オリジナルのイントロとエンディングもまた鮮やかだ。ケリーのオリジナル「メイク・ザ・マン・ラヴ・ミー」は、ほのかな愁いを含んだバラード。ケリーのリリカルでハートウォーミングな表現に、こころが癒される。つづいていよいよ「枯葉」である。2拍子風にテーマがスタートするところがモダン。さり気ない3小節目のリハーモナイズも効いている。4ビートになってからは、ピアノのしなやかなスウィング感を堪能するのみ。ベースのソロも軽妙だ。リチャード・ロジャースの「飾りの付いた四輪馬車」は、スウィンギーでも深みのある色調が際立った前曲に対して、こちらはブライト・トーン。秋空のように爽やかだ。
後半の1曲目ケリーの自作曲「ジョーズ・アヴェニュー」は、ほどよいドライヴ感のあるブルース。ファンキーなプレイでも、アクの抜けた清々しさが感じられるところがケリーらしい。やはり彼のオリジナル「サッシー」もまた、ライトなブルース・フィーリングが光るナンバー。こみ上げてくるようなケリーのプレイに、気持ちが浮き立つ。ダニー・スモールの「ラヴ・アイヴ・ファウンド・ユー」は、アルバム中もっとも叙情的なバラード。ここでケリーは、美しく繊細なタッチを披露している。アリー・リューベルの「風と共に去りぬ」は、アップテンポに乗ってピアノが小気味いいフレーズを次々に綴っていく。そのレイドバック加減が絶妙のスウィング感が、なんとも心地いい。ドラムスとの4バースも爽快。昔から赤道付近の国で生まれたピアニストはリズム感がいいと云われるけれど、その点でジャマイカ生まれのケリーは最高峰である。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント