不死鳥のごとき復活を遂げたアル・ヘイグ──低迷期前の『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』もしっかり味わおう!
 Album : Al Haig / Jazz Will-O-The-Wisp (1957)
Album : Al Haig / Jazz Will-O-The-Wisp (1957)
Today’s Tune : Autumn In New York
秋といえばアル・ヘイグの「ニューヨークの秋」
にわかに秋めいてきた今日このごろ、みなさんはいかがお過ごしだろう。ぼくは、胃腸の調子がかんばしくなく、おまけに腰痛に悩まされている。季節の変わり目には、必ずといっていいほど年齢を感じさせられる。寒暖差や気圧変動で自律神経が乱れ、体調不良が現れやすくなるけれど、時季によらずそいうシーンがジワジワと増えてきているというのもまた事実。それすなわち、老いるということ。せめて、こころのほうだけでも安寧を──と、やさしい音楽に今日もまた身を委ねるのである。大好きな太宰治の小説ではないが、詩人が「秋について」という注文を受けて、よし来た!とマイノートを調べて「トンボ、スキトオル」と書いてあるのを見つけるように、ぼくも記憶の抽斗をひらく。
すると「ニューヨークの秋、アル・ヘイグ」と記録されている。いうまでもなく「ニューヨークの秋」は超有名なジャズ・スタンダード。カウント・ベイシー楽団のレパートリーとして有名な「パリの四月」と双璧をなす、作曲家であり詩人でもあるヴァーノン・デュークの名曲だ。この曲は、作詞、作曲ともにデュークのペンによる。ちなみに「パリの四月」のほうは「もう何も言うことはない」でもデュークとコンビを組んだ、イップ・ハーバーグが詩をつけた。ところで「ニューヨークの秋」のほうだが、都会の秋の魅力をセンチメンタルに描いた美しい曲。この曲を聴くとぼくは、プラタナスの葉が舞い散るセントラル・パークのベンチにひとり腰掛けているような気分になる(実際に行ったことはないけれど)。
ニューヨークの秋は、どうしてこんなにもひとのこころを奪うのだろう──と、はじまるこの曲、ニューヨークがいかに素敵な街か、そこで生きていくことがいかにひとに希望を与えるかが、せつせつと謳われている。いわばニューヨークのご当地ソングだが、フランク・シナトラやメル・トーメ、女性だとジョー・スタッフォードの味わい深い歌唱が有名だ。インストゥルメンタルにおいても、その感傷的で温もり感に溢れた曲想からか、それとも単純にニューヨークの美景の数々がイメージされるからか、数多のプレイヤーが採り上げており、しかも粒揃いである。しかしながらぼくにとっては、アル・ヘイグの情感豊かなピアノ演奏が、もっとも印象に残っている。ここまでしみじみとした感じには、なかなか出会えない。

ヘイグの「ニューヨークの秋」は『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』(1957年)というアルバムの冒頭に収録されている。このアルバム・タイトルにある「will-o’-the-wisp」とは、鬼火のこと。このタイトルに、まずはシビれた。巨匠ルイ・マル監督のフランス映画『鬼火』(1963年)を想起させられる。原作はフランスの作家ピエール・ドリュ・ラ・ロシェルの『ゆらめく炎』(1931年)で、この小説の英題が『ウィル・オー・ザ・ウィスプ』だ。ドリュ・ラ・ロシェルの小説とヘイグのレコードとは直接関係がないけれど、危ういが故に美しい──そんなイメージが重なる。なにせヘイグのピアノ演奏からは、なにやら青白い光のようなものが放たれているようにも感じられる。つまり、彼が紡ぎ出すフレーズにはひとのこころを惑わすような妖しい美しさがあるのだ。
実はこの素敵なタイトルは、このレコーディングが世に出てから数年後に付されたもの。1954年3月13日ニューヨークにおいて、アル・ヘイグ・トリオは、フランスのジャズ・ピアニスト、アンリ・ルノーのプロデュースで8曲をレコーディング。この吹き込みは、すぐにフランスのスウィング・レーベルやアメリカのピリオド・レコードによって、10インチ盤として商品化された。アルバムのタイトルは『アル・ヘイグ・トリオ』(1954年)という。ところで同日、ルノーが帰ったあと、エソテリック・レコードのオーナー兼エンジニアのジェリー・ニューマンによって、さらに13曲が吹き込まれた。そのうち8曲が収録された10インチ盤がエソテリックから発売された。
「ホーリーランド」はアル・ヘイグのヴァージョン一択
ところがこのエソテリック盤、タイトルがやはり『アル・ヘイグ・トリオ』(1954年)。なんとも、ややこしい。その3年後、エソテリックはカウンターポイントと社名変更し13曲入りの12インチ盤を発売。その際、アルバム・タイトルもジャケットも一新された。それこそが『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』なのである。1954年3月13日にヘイグのトリオによって行われた、いわゆるマラソン・セッションは、こうしてピリオドの『アル・ヘイグ・トリオ』と、カウンターポイントの『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』の2枚に落ち着いた。しかしこの件の行方は、まだ予断を許さない。1991年にスペインのフレッシュ・サウンド・レコードがやらかしてくれたのだ!
いやいや、フレッシュ・サウンドに罪はないのだよ。むしろワールドワイドに希少盤をリイシューしてくれるこのレコード会社には、感謝の気持ちでいっぱい。ぼくが、そそっかしいだけ。というのは、フレッシュ・サウンドが12インチ盤の『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』を、わざわざエソテリックの10インチ盤のジャケットで復刻したのだ。さあ、ここまでで慧眼な諸兄姉であれば、ぼくがどんな失態を演じたかは想像に難くないだろう。はい、カウンターポイント盤を所有しているのにもかかわらず、はじめて目にするフロント・カヴァから異なる作品と早合点し、あえなく重複購入!ちゃんと曲目を確認すればわかりそうなものだけれど、そのときのぼくは完全に舞い上がっていたのだね。
当時、アル・ヘイグは、それだけマイブームだったというわけだ。実はヘイグのアルバムを聴きはじめたのはかなり遅いほうで、社会人になってからのこと。当時の勤め先の上司がたまたまジャズ・マニアだったのだが、ある日「えっ、ヘイグを知らないの?それはダメでしょ」と、英国のスポットライト盤『インヴィテーション』(1974年)を貸してくれた。冒頭の「ホーリーランド」を聴いた瞬間、ぼくはやにわにヘイグのピアノ・プレイのとりことなった。この曲はヘイグのオリジナルではなく、生涯モダン・ジャズのメインストリームからブレなかったピアニスト、シダー・ウォルトンの曲。ルバートで12小節、インテンポで12小節、それが交互に演奏されるという珍しい形式のマイナーブルース。とにかくメロディが美しく、一度聴いたらなかなか脳裏から離れない名曲だ。
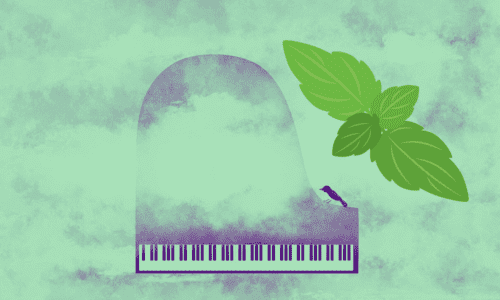
ちなみに本家のほうには『ブーマーズの夜 第1集』(1973年)をはじめ代表作の『ザ・トリオ 1』(1986年)など、いくつかの吹き込みがある。それらのウォルトンのナチュラルで華麗な演奏もいいけれど、ぼくは高貴なまでに優雅なヘイグの演奏のほうが断然好きだ。というか、ウォルトンにはたいへん申し訳ないのだが名曲「ホーリーランド」は、ヘイグのヴァージョン一択と思われる。次曲のブロニスラウ・ケイパーの「インヴィテーション」は及第点だが、それにつづくJ・J・ジョンソンの「エニグマ」が、ほかの吹き込みを選ぶ余地がまったくなくなるような、ビューティフルなバラード演奏──。これを聴いて、ぼくは完全にヘイグに夢中になった。そして、彼のアルバムをもっと聴きたいという欲求が、ぼくのなかにあとからあとから湧いてくるようになったのである。
ぼくは自分でもすかさず『インヴィテーション』を入手。おなじころ、ニュージャージー州ニューアークのデル・モラル・レコードからリリースされた『トゥデイ!』(1964年)が、おりよくフレッシュサウンドによって復刻された。ディスクユニオンさんがディストリビューターとなり、DIWレコードからも国内盤が発売された。センターラベルにミントの葉が描かれていることから、コレクターからは「ミントのアル・ヘイグ」と呼ばれ、入手困難な幻の名盤と謳われていた。ジャズ喫茶MEGのマスターであり評論家でもある寺島靖国をして「『ミントのアル・ヘイグ』を手に入れるのは吉永小百合のハートを射止めるよりむずかしく思われた」と云わしめたほど(まったく上手いことを云うものだ)。
そんな『トゥデイ!』──なんとブートレグまで出まわったそうだが、ぼくはそんな騒動の渦中に巻き込まれることもなく、ジャケットの紙材が良質のDIWレコードのほうを購入した。名盤というよりはトータリティの高いアルバムといった第一印象から、一聴して好感を覚えた。まず収録曲では、当時としては真新しいカヴァーだったのであろうが、ぼくにとっては甚だ馴染み深い2ピースに目が向いた。そのひとつは、フランス出身のシンガー、ギタリスト、ソングライター、そして俳優でもあるサッシャ・ディステルの曲「ザ・グッド・ライフ」──フランスとイタリアが合作したオムニバス映画『新・七つの大罪』(1962年)のなかの一曲だ。
アル・ヘイグの鬼火のごとき演奏は噛めば噛むほど味が出る
そしてもうひとつは、ベルギー出身のハーモニシスト、ギタリスト、そして口笛奏者として有名なトゥーツ・シールマンスの曲「ブルーゼット」──彼のリーダー作『ザ・ウィスラー・アンド・ヒズ・ギター』(1964年)をはじめ、クインシー・ジョーンズの『メロー・マッドネス』(1975年)ほか、様々なアルバムで聴ける名曲である。これらのボサノヴァのリズムが活かされたポップな曲と、思わずため息が出るような、正統派バップ・スタイルの力強い演奏が展開される、ミルト・ジャクソンの「バグス・グルーヴ」やデューク・エリントンの「サテン・ドール」などとが相まって、このアルバムは飽きのこない実に楽しい作品となっている──というように、ぼくには思えた。
しかしながら、あとでDIW盤のライナーノーツを読んで、ぼくはショックを受ける。前述の寺島さんが執筆したものだ。氏のヘイグ愛が溢れんばかりに才筆がふるわれているなかで、ぼくが親近感を覚えた2曲について「平凡な流行歌」「硬質のヘイグに不釣合いなボサ風リズム」「これらの演奏が好きになれない──」というようなコメントがあったのである。しかも寺島さんは、1954年3月13日のマラソン・セッションをヘイグのベスト・プレイと観ており、特に『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』を最高傑作と仰っている。さらには、このアルバムをしっかり聴いてほしいという熱いメッセージまで送られているのだ。これは、ぜったい聴くしかないだろうと、ぼくはすぐにこのカウンターポイント盤を購入した。
そんな経緯から、ぼくはやっとこさ『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』にたどり着いたのだが、正直に云ってはじめはこの作品のよさがあまりよくわからなかった。そのときのぼくは、まだまだアマちゃんだったのだろう。ヘイグはプライヴェートのゴタゴタ(三番目の奥さまに関するあの事件)でいっとき引退状態にあったが、くだんの『インヴィテーション』で不死鳥のごとき復活を遂げた。ぼくは相変わらず、このアルバムも含めてその後にリリースされたイースト・ウィンド、インタープレイ、プログレッシヴなどの復帰後の力作ばかりを聴いていたのだ(ああ、寺島さんがコワいよ──)。ただそれらは『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』での演奏とはまるで別モノと、ハッキリ思えたのも確かだ。
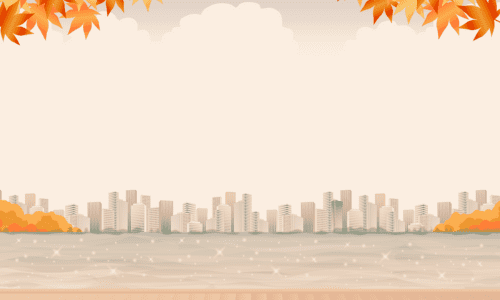
ふと気がつくと、いつの間にか寺島さんと同様にぼくにとっても、このアルバムがヘイグの作品ではベストワンになっていた。まるでそれは、長い年月を経て樽のなかで高級ワインが熟成するような感じか──。いやいや、それとはちょっと違うな。ぼくはこのレコードをずっと寝かせておいたわけではなく、しばしばターンテーブルにのせていた。しかも過ぎゆくときのなかで、知らないうちにその機会は次第に増えていく。それとともに、それがどんどん好きになっていく。つまり『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』は、噛めば噛むほど味が出るスルメイカのような作品だったのである(なんだか色気がないな)。音はあまりよくないし、どの曲も短め、ビル・クロウ(b)とリ-・エイブラムス(ds)はサイドに徹するばかりだが、そのぶんピアノ演奏の鬼火ぶりが引き立っている。
とはいっても「ロイヤル・ガーデン・ブルース」や「神の子は皆踊る」などの高速の曲では、トリオは三位一体となり心地いいバウンス感を打ち出していたりする。三人は「イズント・イット・ロマンティック」「誰も奪えぬこの想い」「風と共に去りぬ」「オン・ジ・アラモ」といったやや速めのテンポの曲では、快調なスウィング感を見せる。特にヘイグのピアノのスピード感に溢れたフレージングが素晴らしい。そんなキレのいい疾走感は「ドント・ブレイム・ミー」「パリの四月」「マイ・オールド・フレーム」といった3曲のソロ・ピアノにも現れている。逆にスローテンポのほうが、その端正で流麗なラインが明瞭になっているようにも思える。トレモロがきらめき、駆け下りたり駆け上がったりするリフが映え、感情豊かなピアニズムが発揮されるのは「バーモントの月」「イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー」「ボディ・アンド・ソウル」などのバラードにおいても同様だ。
そして、そのバラード・プレイの最高峰といえば「ニューヨークの秋」である。ヘイグは私生活ではラヴェルやラフマニノフを愛聴し、マルタ・アルゲリッチやロベール・カサドシュといったクラシックのピアニストがお気に入りだったそうだ。彼の感情表現の豊かさは、そのあたりにルーツがあるのかもしれない。そのいっぽうでヘイグは「パウエル派」と云われることもあるが、バド・パウエルのピアノよりもヘイグのそれのほうが軽やかで小気味いいように思われる。それにとどまらず、ヘイグの演奏表現からは、まろやかな風味とさわやかな香気さえ感じられるのである。と同時に妖しい美しさもあるから、かなりヤバい。とはいえ、ヘイグの「ニューヨークの秋」は耽美的でもあるけれど、どこかやさしい。だからぼくのような不甲斐ない人間は、安心して身を委ねることができる。敢えて云えば、それはメランコリックな気分がリフレッシュされるような美しさ──ということになるのかな。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント